友人Nの原稿
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
対極からの視界
ひざに何かモノが当たった。
その感触で目覚めたわたしは、ボンヤリとしたまま足元に目をやった。モノではなく人間だった。おそらく寝床を間違えたのだろう。別におどろきはなかった。
(昨夜、警察の護送車で病院に運ばれ、診察を受け、注射を打たれ、それから・・・)
そうだ、入院して初めての朝だ。ベッドの「足元の人」を眺めながら、ここが保護室でないことに少し安心した。
わたしが居るのは詰所横の「安静室」だ。ベッドが六つだから六人部屋ということか。だが、わたしと「足元の人」、それに、ベッドに縛り付けられて点滴を打たれているおじいさんが一人、部屋にはこの三人しかいない。あとから聞いた話では、救急用の部屋なのであえて空けてあるとのことだった。
廊下を歩く患者のほとんどが、この部屋を一瞥して通り過ぎていった。なんとも形容しがたい目でこちらを見ていた。
部屋の外へ出ようと思えば出来た。扉がないからだ。だが、食事も薬も看護師が運んできてくれる。結局、その部屋から診察とトイレ以外で足を踏み出したのは、入院から二、三日目のことだった。
部屋を出ようとすると「足元の人」がついてきた。追い返す理由も気力もない。半ば以心伝心というやつで、児童の登校のように手をつないで食堂を横切り、喫煙室へ入った。そこではSさんという人が他の患者達に自己紹介をしていた。Sさんも新入りの患者のようだ。
「足元の人」もおじいさんも話すことが出来ない。診察や看護師との事務的な会話以外、もう長いこと人と話していなかった。そろそろ人と話したい。
わたしはSさんが話しかけてくれるのをじっと待った。Sさんは「健康」な人から順に挨拶しているようだ。だが、どうもわたしに順番が回ってくる気配がない。ついにいたたまれなくなり、わたしは自分から話しかけた。
「(隣の「足元の人」を指しながら)なんでこの人、わたしから離れへんのですかね?」
この瞬間、患者達の目色が急変した。わたしには会話は無理だと思っていたのだろう。Sさんもビクッと振り向き、一呼吸おいたあと笑顔で答えた。
「自分のことを分かってくれてると思っとるからでしょう」
それ以後、Sさんはじめ「普通」の患者達と話すようになった。また、ボンヤリとした感覚も日を追うごとに消えていった。
ある日、Sさんと談笑しているとき、ふとわたし達に向かう視線を感じた。看護師だった。あの瞬間までのSさん達と同じ眼だった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
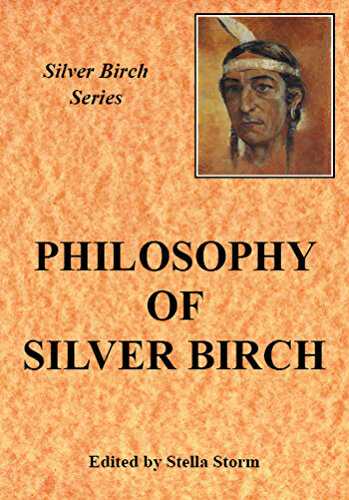
- スピリチュアル・ライフ
- 合う波長が変わります
- (2024-11-27 18:00:07)
-
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- 80万アクセスだけど、ボチボチ。
- (2024-11-15 08:20:37)
-
-
-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…
- 季節の変わり目に寄せて ~体と心を…
- (2024-11-27 21:00:10)
-
© Rakuten Group, Inc.



