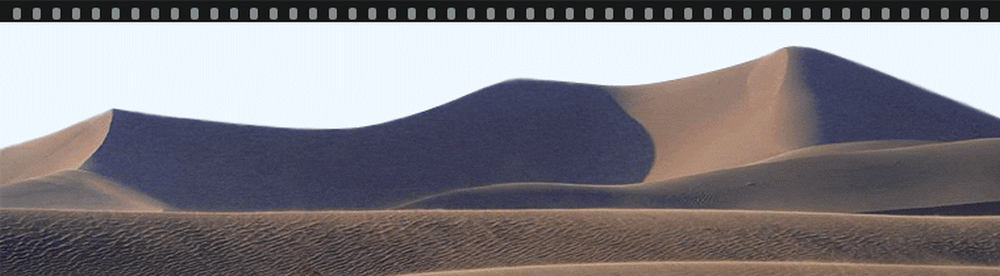****************
……にしても。
俺は溜息をつきながら、『たこ焼き』を食べている周一郎を見やった。
にしても、だ。一体、たこ焼き食って、様になる男がどこにいるんだ、どこに! ああここか、ここにいたよな、うん!
「…ふ…ん…」
ベンチに座った周一郎は、発泡スチロールのトレイに載った『たこ焼き』を、面白そうに突ついている。生まれの良さか、それとも躾か、食べ方もいやになる程上品で、そのくせ全く嫌味なく本人と『たこ焼き』の両方に似合っているものだから、否応無く人目を引いて、さっきから側で歩速を落とす女が後を絶たない。露骨なのになると、立ち止まってしきりに秋波らしいものを送ってきてはいるが、当の周一郎は、経済学の最新論がトレイに載っているのだとでも言いたげに『たこ焼き』に熱中していて、気づかないのか気づかぬふりをしているのか、とにかく一度も顔を上げなかった。
おかげで俺は、振られた女の呪いの視線をまともに浴びることになって、さっきからどうにも居心地が悪い。今しも、妙に目の光にきつい、化粧っ気の全くない女にじろりと睨みつけられた。
俺じゃない。周一郎がそちらに気を向けないのは、絶対俺のせいじゃない!
胸の中で必死に弁解し、嘆願の目を向けようとしたが、あまりにも険しい顔をされたせいで正視することもできず、慌てて知らぬふりをする。相手は睨みつけるだけ睨みつけると気が済んだのか、ふん、とばかりに波打つ黒髪を翻し、足早に去って行った。
「…ふうう」
「?」
「いや、なんでもない。気にせず食ってろ」
「はい」
にっこり笑う周一郎、またもや足を止める女。エンドレスかよ。ひょっとして今日は一日中、隣に座りたいのを無粋に邪魔している気の利かない男として恨まれ続けるのか? だからと言って、サングラスをかけさせて端正な顔を隠そうとしても、余計に目立つかも知れないし。
「…やれやれ」
「では、次のプログラムです! どうぞ!」
ルトに焼きそばの残りをさらわれた俺は、響いた音にステージの方へ目をやった。屋外ステージでは、ちょうど演者が上がったところで、ギター1本持った男がマイクを掴んでいる。
「えー、今日はどうも。上尾旅人です。名前の通り旅から旅で、今年も留年となりましたぁ」
わあっ、と笑い声が上がった。知らない人間じゃない。学園祭だけではなく、喫茶店やカフェでミニ・コンサートをやっていて、なかなかの評判になっている男だ。
「とりあえず、自己紹介がわりに一曲。タイトルは『青の光景』です」
ギターの音色が澄んで響く。
「照る日射し
吹き抜ける7月の風
君は少女になって笑う
彫りつけた影の重さを
軽く道に投げ捨てて
タホ河の川面をゆく
スペインの旅情の色
諦めと天空への憧れが合う街で………」
甘い切なげな声だった。少し強くなってきた雪の中、茶色の髪を肩辺りまで垂らした上尾の顔には深い翳りが浮かんでいた。
「許されぬ愛ならば
この身を削っても貫く
いつの日か結ばれる日
想っては胸に広がる苦さ
思い返せばいつも君は
影の中で笑った
その背に金の羽根が
宗教画のように光る
旅立てば不死の祈り
誰のことばだと訊いた
名も知れぬ詩人の後を
追うように君は発っていく
優しい日々の温もりも
涙色の想いも振り捨てて
祈りさえ届かぬ闇
金の羽根輝かせて
残されたぼくの心を
閉じ込めて君は行くのか…」
ふうん。
こいつの歌を聴くのは初めてだったが、悪くないじゃないか。何よりも声と歌詞が合っている。どこか掠れ気味のハスキーボイス、けれども高音の辛さを感じさせない。
「…どうもでしたー」
拍手が湧き起こった。旅人さーん、と嬌声が上がる。いやあ、俺も一度でいいから、あんな風に呼ばれて見たいもんだが、女の子に呼ばれて楽しいことに繋がった記憶がない。
「えーと、これ、僕の初めての失恋の歌です」
MCにいやーんと女の子が騒いだ。可哀想、と声が続く。
「あははっ」
上尾は照れ臭そうに笑って、一転、生真面目な表情になった。
「ちょっとスペインに行ってたことがありまして……その時に惚れた女性がいるんですよね」
いやーん、と再び女の子が騒ぐ。惚れてもいやーん、振られてもいやーん、だったら、どうせえっちゅうんじゃ、全く。
「不思議な人で、こう、2つの面が共存してるんですよね。激しいところと脆いところ、冷たいところと優しいところが。で、柄にもなく焦って告白したんですが、見事振られてしまいまして……えーと、タイトルの『青の光景』には、その辺りの意味合いがあるんです」
意味がわからないのだろう、観衆がざわめいた。
「スペインの青っていうのは独特の意味があるんです。俗に、スペインの色っていうのは『黒』なんですが、それへと移り変わる前段階に『青』があるんですよね。で、この『青』っていうのは『黒』が死を示すのと同様、1つの意味がある。天上の青、そう呼ばれます」
上尾は熱っぽく語り続けた。
「死へと続く、けれどもっと違った、救いを求める色と言うのか、それが『青』なんですよね。で、その…僕の惚れた女性っていうのが、ちょうど、その『青』と『黒』の境に立っているような女性でして、彼女の周りが夜なのに、羽の輝きでその黒い色が青に見えてしまうって言うか、そう言う感じの女性で……まあ、何を言ってるのか、よくわからなくなってきましたが、そう言うイメージで作りました。えっと、それじゃ、次の曲、『心を傷つけて』…」
「…ごちそうさまでした」
「あ、うん」
周一郎の声が突然聞こえて、我に返った。視線を巡らせると、なぜか沈んだ表情の周一郎を見つける。
「どうした?」
「いえ…」
問いかけに、周一郎は曖昧に笑って見せた。
「…スペインにはあまりいい思い出がないので」
「いい思い出がないって…行ったことあるのか?」
「ずっと昔ですけど。9歳…ぐらいかな」
「へええ」…? 9歳でスペイン旅行ね。俺はその時何をしていただろう? 有難い義務教育を受けながら、施設と学校の間を往復していただけのような気がする。
……やめよう、自分から進んで落ち込むこたない。
「…ん?」
溜息混じりに前方へ目を向け直した俺は、目の前の地面に白いカードが落ちているのを見つけた。さっきまではなかったはずだ。訝しく思いながら拾い上げる。
表面に、たどたどしい感じの紺色の女文字で、次のように書かれている。
『わたしが死んだら
ギターと一緒に
埋めてください、砂の下に
オレンジの木々と薄荷の間に
風見の中に』
「?」
カードをひっくり返す。かなり古いものなのだろう、あちこち黄ばんでいる。隅の方に小さく、表と同じような女文字で年号と名前が書かれている。
「……年、ローラ・レオニ」
その右端に、赤黒い、妙なシミがある。
「…血…?」
「何ですか?」
興味を惹かれたように、周一郎が声をかけてきた。
「いや……これ、さっきの子かな、落としてったんだろ、ほら」
「…」
手を伸ばしてカードを受け取った周一郎が瞬間、体を強張らせる。
「? 何かあるのか?」
「…いえ」
僅かな沈黙の後、ポツリと応じた。それでも、周一郎の眼はカードから離れない。
「詩、か?」
話の接ぎ穂を失って、俺もカードを覗き込む。
「…ガルシア・ロルカの『覚え書』」
「ふうん?」
「…に、似ています」
「遺書みたいだな」
今度はあからさまにぎくりとした周一郎は、やがてゆっくりと振り向いた。
「そうですね」
淡く笑ったその目が深く、妙に頼りなげで、それ以上詮索するのはやめにした。なおもカードを見つめている周一郎の頭を軽く叩く。
「まあいいや。宮田から寄れって言われてるんだ、行こうぜ」
「どこへ?」
いつもは子ども扱いされるとむっとした顔になるはずの周一郎は、素直に俺を見上げた。
「美少年フォトコンテスト。ったく、あいつの趣味は年々ひどくなる」
くすりと笑って、周一郎はカードをポケットにしまい込みながら立ち上がった。
****************