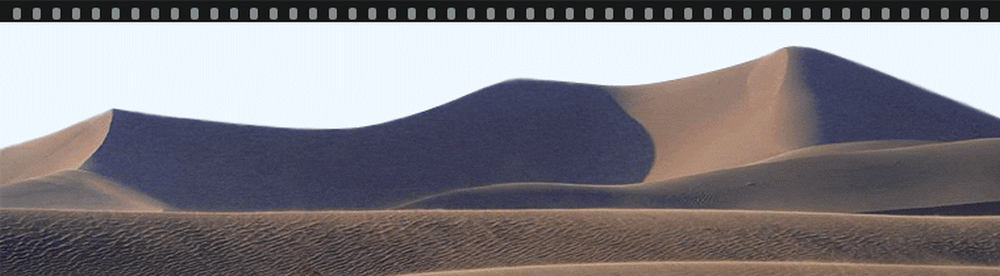****************
(人が必死に探していたのに、心配するなとは)
高野もさすがにムッとして周一郎の側に立つと、少年はついと河の方を指差した。
「高野」
「はい」
「もし、ぼくがここに落ちたら、大悟はどうすると思う?」
「もちろん、お助けになりますよ」
「今は、ね」
少年は高野を振り返って皮肉っぽく笑った。真意を図りかねていると、
「ぼくは、今の計画のパートナーだからね」
「…」
そこで高野は、ようやく、この10歳にも満たぬ少年が何を言っているのか理解した。大悟は、今の計画に周一郎が必要だから助けるのであって、周一郎個人の価値で助けるのではない、言い換えれば、もし計画に周一郎が必要でなければ、いつでも見殺しにできる、そう言うことなのだと。
「そんな、まさか」
「まさかと言うの? ぼくはできるよ。おかしいね、高野」
幼い顔にかけたサングラスの後ろの瞳が、ひたりと高野を見据える。
「ぼくがローラにならないと断言できるってわけ?」
(ああ)
高野は思い起こした。大悟が、ローラ・レオニに彼女の好きなガルシア・ロルカの本を贈り、片言の日本語を教えていたことを。パブロ・レオニと意に染まぬ結婚をしたローラにとって、大悟は例えようもなく魅力的な存在であり、義理とは言え、その息子の周一郎は大切な人の子どもだった。
だが、大悟の好意も、結局はパブロを落とす為の餌であり、RETA(ロッホ・エタ)に襲撃される計画でローラが死ぬとわかっても、大悟は何一つ手出しをしなかった。
「………」
「答えられないだろう。お前は『いい人間』だね、ぼくらと違ってさ」
言い放った周一郎はなおも川面を見つめ続けた、その目に深く重い影を宿して。
そんな時からか。
胸の中で呟く。
そんな時から、自分は1人だと思っていたのか。
どんなに哀しかったろう。自分が他の誰にも必要じゃないと思い続けて、ようやく、能力(ちから)を認めてくれた相手は、いつでも自分を見殺しに出来るのだと思い知らされるってのは。
いつの間にか、目の前に開けたタホ河は、緩やかな流れをゆったりと広げていた。
日本とは川は川でもサイズが違う。広さが違う。
だからこそ、こんな広い景色の中で、ああそうか、どんなに頑張ってもどんなに有能であっても、やっぱり自分は誰にも要らないんだなと必死に飲み込もうとしている9歳の子どもと言うのは、ただただ痛々しくて、辛くて。
それでもな、周一郎。
もう、そこには立っていない少年の姿に呼びかける。
それでも、俺は、お前が生きててくれた方が嬉しいんだからな。馬鹿なことを考えるなよ。自分で自分を諦めちまうなよ。何の役にも立てん俺だって、スペイン語どころ英語もろくに出来んし、電柱にぶつかるし自分の足に蹴躓くしバイトは馘になるし、テストは白紙だし女には振られっぱなしだし、オタオタするしか能のない俺だが、お前の八つ当たりの場所ぐらいにはなってやれるんだから。
「一体…どこへ…」
滲むように高野の声が響いた。
「どこへ行かれたんでしょう」
「暢子!」「っ」
答える術なく黙り込んだ俺は、次の瞬間響き渡った声にぎょっとして振り返った。
日本語だ。
「観光客、のようですね」
「ああ、そうだな」
「待ってくれ、暢子!」
植え込みの向こう、木立の端に一組の男女が言い争っている。
「あれ? あいつ…」
肩に触れるぐらいの茶髪の男は、離れようとする女の手首を掴み、激しい勢いで怒鳴る。
「馬鹿なことはやめるんだ!」
「何が馬鹿なこと?!」
負けず劣らず激しい語調で叫び返し、振り返った女が男を睨み付ける。
「あなたとのことはもう終わったのよ! 私に指図なんかしないで!」
「見てられないんだ」
苦しげな声で男が唸った。
「君だってわかってるはずだ。そんなことをして、君に何が残る?」
「わからないわ! わかりたくもない!」
女は怒りと憎悪を込めた目で男を凝視している。
「後に何が残ろうと構わないわ! 破滅だと言うなら、それでも喜んで受け入れるわ。あなたにはわからないでしょうけど」
「…君は取り憑かれているんだ」
男は疲れたように重く応じた。
「この国の影に毒されて、自分を見失っているんだよ」
「構わない、と言ったでしょう」
女は手首を掴んだ男の手を、汚らわしいもののように振り払い、皮肉な笑みに唇を歪める。
「自分なんていらないのよ。私は、ただ…」
目鼻立ちのはっきりした異国的な顔立ちに細めた瞳、表情のそこここで凶暴な光がちろちろと炎の舌を吐く。にっこり笑った唇が、酔うように甘く一言紡いだ。
「滅びたいの」
「君は…」
「でも、1人ではごめんだわ。『彼』を巻き込んで、もろともに堕ちて行きたいの。あなたが居たいと言うならば拒まないけど、その代わり、最後まで私の堕ちていくのを見届けてちょうだいね。一瞬でも目を逸らせたら…」
冷たい光がとってかわり、女は笑みを引っ込めた。
「絶対に許さない」
「暢子…」
男は哀れなほど肩を落とした。のろのろと首を振りながら、
「君はまるで魔物(ドゥエンデ)だよ」
「魔物(ドゥエンデ)?」
は、と嘲るように嗤って、女は肩をそびやかせた。
「そうだ。とても人とは思えない」
「違うわ」
男のことばを途中できっぱり遮る。
「人だからこそ、魔物(ドゥエンデ)にもなれるのよ。人でない魔物(ドゥエンデ)なんて…」
白い歯を見せて妖しく笑う。
「御伽噺にもなりゃしない」
「……」
「いい? これが最後よ。私の邪魔をしないで」
一言もない男に言い捨て、くるりと身を翻らせて女は足早に立ちさった。残された男は重い溜息を吐いて、立ち竦んでいる。
「…行こう」
「はい」
俺は高野を促してその場を離れた。ただでさえ、面倒ごとに飛び込んじまってるのに、この上、他人の痴話喧嘩に巻き込まれる気は毛頭なかった。
「ご存知の方ですか?」
十分遠ざかってから、高野が問い掛けてくる。
「ご存知って言うほどご存知でもないんだが……大学の奴だよ。名前は確か……上尾、とか言ったはずだ」
「それは…奇遇なことで」
「奇遇ね…」
奇遇、奇遇か。奇遇なら、俺はひじょーに嬉しいのだが、この妙なもやもや感をどう説明すればいいのだろう。何となく、嫌な予感がする。背後霊どころか、守護霊もおいでおいでをしだした気がする。二度ある事は三度あるという奴の、いよいよ三度め、と言った感じだ。
それに、あの女、どこかで見たような気がする。それも、そんなに昔のことじゃない、割と最近だ。紅い唇が笑う、その後ろにあったイメージ、炎と燃えた瞳の色、どことない異国的な顔立ち……。
(どこでだ? どこで見ている?)
別にわからなくてもどうと言うことはないに違いない。知り合いと言っても、学園祭で一方的に見掛けただけの男の痴話喧嘩。首を突っ込む必要もないのだ。だが、何かが引っ掛かる。何か、ひどく重要なこと。
「うー」
呻いて俺は頭を掻きむしった。高野がぎょっとしたように、珍動物でも見るように俺を見る。
「どうなさったんですか」
「いや……脳味噌のマーボードーフを何とかピラフにできないかと…」
「は?」
高野はきょとんとした。
「つまり……その……いやーな予感がするんだ」
「いやーな予感、ですか」
「そう、そのいやーな予感……」
ズドッ!! ビシッ!
「ひっ」
突然耳の側を何かが通り抜けていき、目の前の木の幹に食い込んだ。
「 Señor!!」「ぐわっ」
ほとんど同時に、甲高い、よく通る声が後頭部を殴りつけた。続いて、思い切りよく叩きつけられた両手が、俺を前へつんのめらせる。もちろん、素直な俺が倒れないはずがない。
ドウッ! ドウッ、ドウッ!!
「な、何だ何だ!」
「銃声です」
「んなこた、俺でもわかる!」
地に伏せながら、冷静な高野の声に噛み付く。
「要はどーしていきなり撃たれてんのかってことで…んぎゃ!」
「¡Cuidado con la cabeza!」
きびきびした男の声とともに、俺は頭を地面に押し付けられた。高くもない鼻を思い切りぶつけ、目から火花が出る。
「¡Perdóname! Hasta pronto.」
この野郎、と喚こうとした次の瞬間、男は銃声の途切れた間を狙って立ち上がり、言うやいなやで駆け出して姿を消した。それを追うように、見る見る銃声も遠ざかっていく。
辺りが再び元の静けさに戻ると、高野は感極まったように、地面で果てている俺に頷いた。
「なるほど。滝様の予感とはよく当たるものですね」
「あ、あのな…そこに感心するか、今?」
俺は再びその場で果てた。
****************