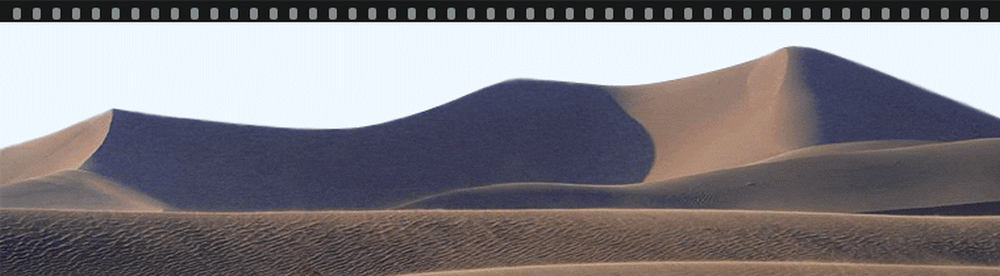****************
唐突に『ランティエ』の声が響いて、俺は我に返った。
「『ヒラルダの塔』と言うのは当たってたみたいですよ。残念ながら、すぐには行けそうにないが」
「え?」
道に迷ったのかエンジントラブルか。だが、お由宇はちらっとバックミラーに瞳を動かして、少し目を細めた。
「はあん」
納得したように呟き、セミロングの髪に軽く触れる。
「ちょっと見えなくなったと思ってたら、懐かしい友人の登場、と言うわけね」
「友人?」
「そ。ご丁寧にパッシングライトして、位置を知らせてくれてるわ」
くい、と立てた親指で後ろを示す。振り返る俺の目に、いつの間に現れたのか、黒い大型の外車が、すぐ後ろに迫って来ていた。チカッとライトを点滅させる。続いて数回瞬くライトに、お由宇に目を戻した。
「知り合いか?」
「私とあなたと共通の、ね」
「俺はスペインに知り合いなんていないぞ」
「あら…」
お由宇はひょいと肩を竦めて見せた。
「居るじゃない、RETA(ロッホ・エタ)が」
「RETA(ロッホ・エタ)ぁ?!」
ちょっと待ってくれ、RETA(ロッホ・エタ)ってのは、暢子を狙ってんじゃなかったのか?
「何言ってるの」
お由宇は呆れた。
「さっき言ったでしょ、RETA(ロッホ・エタ)が本当に狙ってるのは『青の光景』だって」
「わかってるって。だから、周一郎を連れてる暢子を…」
言いかけて、顔から血の気が引いた。
「わかったようね」
お由宇が笑みを含んで応じる。
「事実はどうであれ、『情報』では『青の光景』を持っているのは『あなた』でしょ?」
お…おわっ…。
「それを突いただけで、私達までずっと尾行して来てくれた輩が、獲物を目の前にして周一郎君に拘ると思う? 心配しなくても、復讐心に燃えた暢子は周一郎君を葬るのに躊躇しないでしょうし、そっちの始末は彼女に任せて獲物を取り戻そうとするのが『常道』でしょ?」
んな『常道』があってたまるか! 俺は『大物』じゃない、ただの一般大学生だ!
「弁解が通じる相手じゃないしね」
お由宇は俺の気持ちを見抜いたように呟いた。
「それよりも、どうしてこんなに早く、私達の位置が掴めたのかしら。そう、足取りをすぐに追えるようなのんびりした移動はしていなかったはず……志郎!」
「わっ、はっ、はいっ」
いきなり呼ばれて硬直した。
「ちょっとその辺り、コートの裾とかポケットとか衿とか探してみて。1㎝四方、もっと小さいかも知れないけど、黒いプレートみたいなもの、ない?」
「プレート?」
「そうか!」
はっとしたように高野が頷き、俺の体を撫で回し始めた。
「そう言えば、あの時、一人の女性とすれ違いましたね」
「こっ、こらっ、やめろっ! 気色悪いっ! 自分でやるっ、自分でっ!!」
高野の手を振り払い、コートのポケットの中を探った俺は、くしゃくしゃのハンカチと映画の半券、スーパーのレシートなんかと一緒に、丸い小さなボタンのような物を掴み出した。何せ、ポケットなんて、物を放り込むだけで中身を探るなんてことも滅多にしない。煙草も吸わない俺にとって、特にコートのポケットなぞ、移動式簡易ゴミ箱ぐらいの役割しかない。
「?」
「ありました、佐野様」
「なんだ?」
「TEー33型。電波発信器よ。追われるのもわかるわね」
お由宇は受け取った黒ボタンを指の間から滑り落として、ぐっと踵で踏みつけた。微かな音がして、表面のくすんだ黒の金属が凹む。
「今更遅い気もするけど」
「だけど、いつ?」
「まあ、相手があなただから…」
どーいう意味だ。
「チャンスは山ほどあったでしょうね。誰か綺麗な人に見惚れている間にでも入れられたんじゃない?」
「綺麗な人?」
脳裏に、初めてスペインへ来た時のことが思い浮かんだ。エレベーターから降りる時、すれ違った女性、広いつばの下で笑った朱色の唇……。
(あの時か?)
「とにかく…」
『ランティエ』が後続の車との距離を目測しながら言った。
「撒きます!」
「ひえいっ!」
ぐんっ、と車が振り回されて、俺達が乗った車は横滑りしながら向きを変え、そのまま速度を落とすことなく、角を曲がって突っ走った。俗に言う四輪ドリフトと言うやつか、複雑に入り組んだ街路に入っても、ほとんどスピードを落とさず走り続ける。狭い路、すれすれの幅、壁を掠めて走り抜けるが、敵もさる者、多少は離されてもしっかりついてくる。
「仕方ありませんね」
『ランティエ』は小さく溜息をついて、やや広い路を選んでスピードを上げた。前方に小広場、さすがに深夜のこと、人影が少ないのをいいことに、そこへ突っ込んで行く。
「ちょっと派手ですが」
「ひえええいっ!!」
ぎゅいんっと嫌な音がして、ふいにかかった急ブレーキに車の後ろが大きく回った。ハンドルを回す『ランティエ』は平然として、ブレーキをかけるや否や、アクセルを踏み込む。次の瞬間、俺達の車は180度方向転換、尾けて来た車と正面に向き合っていた。広いとはいえ、車が2台、並んで走り抜けられる幅なぞさらさらない。身を竦める俺に『ランティエ』の叱責が飛ぶ。
「右へ寄って!」
「っ」
とっさに高野に引っ張られ、体が浮いた俺は高野と上尾を下敷きにせんばかりに右へ突っ込んだ。ふわっと車体が傾く。ギャギャギャギャッと鼓膜を痛めつける音が響いて、車は片輪走行で追手とすれ違った。慌てた相手がハンドルを切り損ねてスピンしながら流れて行く。やがて背後でグワッシャッ、とお決まりの衝撃音、数秒後に紅蓮の焔が夜を焼いた。
「ま…この程度ですかね」
ことばもない上尾と俺に、『ランティエ』はあっさり言い放って、バックミラーの中からにやりと笑った。
****************