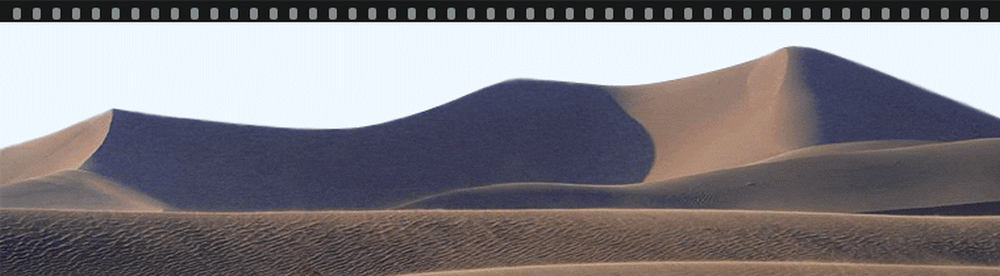****************
「…」
「今度だって、断ろうと思えば断れたんだ。それをいつものお節介で、俺が勝手に飛び込んできたんだからな。お前が責任感じる必要ないんだからな」
10年も前の恨みを背負い込んで、痛めつけられて、傷ついて、それで十分なんだからな。これ以上、お前が負い目を持つこた、ないんだ。
「………」
「聞いてんのか?」
「…でも」
「でももへったくれも何もない! お前はそれでいいんだ!」
俺は続けた。
「いいか? よく聞けよ、お前はそれでいいんだから。お前がお前だってことを負い目に思うこたないんだから。お前はお前であって、お前でないってことはありえなくって、つまりお前はお前でないはずがなくって…」
ええい、くそ!
「だから、影があろーがなかろーが……え? 影?」
ぎょっとした。
「おい、周一郎」
「…はい?」
足元にチラチラするものを凝視する。どこか滲んだような甘酸っぱい声が応じたが、それよりも今。
「この部屋、窓ってなかったよな?」
「はい」
「で、窓がないってことは光が入らないはずで、光がなきゃ、影は出来んよな?」
「………はい」
「で……この下に動いてる奴、何だと思う?」
それはもう、尋ねるまでもなかった。
ついさっきまでは幻のように蠢いていた『それ』は、いまははっきりとした形を取りつつあった。
「光だ!」
慌てて天井辺りを振り仰ぐ。
「どこからか、光が入ってくるようになってる!」
波打つような壁、僅かに曲面になっている天井を区切る曲線の群れ、おそらくはそれらに巧妙に隠された明かり取りがあるのだ。
「滝さん!」
「っ」
周一郎の低い叫び声に、指差す方を見つめてぎょっとした。
十字架の斜め右上あたり、ぼうっとした光条が重なり合って白い光の塊を作っている。それは、月の移動に伴って次第に強くなる光に、見る見る、淡い、けれどもそれとはっきりわかる形を作った。二本の光条が交差してぴんと伸びた白い羽根を思わせる。いくつもの細い光条が重なり合ってふっくらとした体を作り、光り輝く存在になる。
「天使だ…」
「滝さん、あそこにも…」
「う…」
天使の群れはぼんやりと、けれど次第に辺りに増えていった。それぞれの光条が波打つ壁で跳ね返って、部屋をほの明るく照らす。光条に照らされなかった部分は床にのたうち、黒々とした人の塊を思わせる形に凍てついていく。
「おい……こんなことが出来るのかよ……」
思わず呟いた。
十字架を囲み、部屋の四方に浮かぶ天使の白い光の群れ、呼応するようにモザイクの床に固まる影は時に伸び上がり、時に蹲り、救いを求める人々の姿に似て天井を振り仰ぐ。茫然として、ただその光景に魅入られている俺たちの目の前で、光と影は、ゆっくりと互いの位置を変えていった。光の群れが次第に降りて行く。影がじわじわと伸び上がる。天と地、二つの世界を象徴していた場面が、青白い光に照らされた部屋の中、天は地に手を差し伸べ、地は天を求めるように混じり合っていく。
「…『青の光景』…」
天上の青、地上の黒、光と影、生と死が互いを求めて絡みつく。それは果てることない求愛の想いに似て、ただひたすらに抱きしめ合うだけの苛立たしさ………そこには尽きることない昇華への願いがある。
ふっ、と唐突に、ある一筋の光が部屋の隅の床に落ちた。周一郎が無意識めいた動きで近寄って、覗き込み、手で埃を払う。低い呟きが漏れた。
「…我を求めよ……我は全てを受け入れ、全てを与える。我はいつも汝の側にいる……滝さん」
「うん?」
「そのモザイク、赤っぽい石、動きませんか?」
「これか?」
俺は近づいて触った。ごとっと重い感触があって数センチ石が沈む。
「その周りの石で、どこか、その上にずれ込みませんか?」
「周り…な……うん、これが動くぜ」
左隣の黄色の石が、じりじりと赤っぽい石の上に重なった。
「次はその周り」
「周り、と」
同じことを数回繰り返すと、ふいに、石を動かした下に、5センチ四方ぐらいの穴があった。中に何かが入っている。
「フィルム…かな。それに写真…」
『スペインにて』。裏にそう書かれた写真をひっくり返す。側に来ていた周一郎がびくっと体を震わせた。頬に煌めいて雫が零れ落ちる。小さな呟きが掠れて響く。
「大悟…」
それは、他ならぬ周一郎の、カメラに向かってあどけなく笑いかける子どもの頃の写真だった。
****************