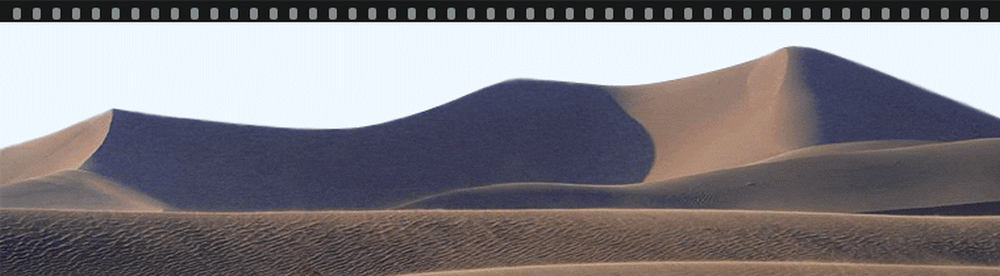なのに、いつもご訪問ありがとうございます。
短い作品・童話・SS・BL新ネタ・猫たちの時間シリーズはメルマガ展開し、『ラズーン』はこちらで10000ごとの展開、あと動かせていないのは『闇シリーズ』と『これは〜』シリーズ。面倒臭がりの私には、発表を仕事化する必要があるようで、2シリーズのどちらかは『猫』の後にでもメルマガ展開してやれば進むかもしれません。
お話の続きも滞っていて、申し訳ないと思いつつ、手持ちしている文章をとりあえず吐き出してしまえば進むのかもと思い、書き溜めてあったエッセイ・小文もアップしようと思います。
よろしかったら、ひとつまみどうぞ。
****************
私には『物書きの神』が憑いている。
この神は実に『いい』性格をされている。
例えば、9歳の私に向かって、優しげに、とても素晴らしいことを教えるように、こう囁かれた。
「なあなあ、たくさん本読んだけど、どうや、何か、今ひとつ、いう感じがせえへんか? もっとこう、ぴったりくるもんが欲しい、と思わへんか?」
この時、神さまは、私の読書量の少なさや読書範囲の狭さについては指摘されない。そんなことを教えてしまったら、未熟な私が自ら文章を書くことなんて始めないだろうと見抜かれていたからだ。
「ほら、好きなん読んでも、落ち着かへんやろ。この辺りでこう、と思うところにヤマがない。そらそうや、あんたと、この本か書かはったお人とは違うし、仕方ない。そやけど、自分の心にぴったりきたい、こら、人情やと思う。あんたもそう思てるやろ。そやから、な、どうや、一つ、好きなもん、書いてみいひんか? いや、なに、別にどんなもんでもええ、どんなもんでもええんや。それはそれなりに、まあ、なっていくさかいに」
そこでにんまり笑われた神さまの、意味ありげなことばに気がつけばよかったのだが、私は、それもそうか、と書き始めてしまった。
始めた時に調子が良ければ、いつの間にか抜き差しならないところへ追い込まれるのが世の常で、この神さま、なかなかしたたかな方だった。
まず、原稿用紙に書かなくてもいい、と言う。レポート用紙や残り紙を適当にホッチキスで止めて、鉛筆でずらずら書いていけ。形にこだわらなくていい。手元の本を見て、それが読みやすい形と思えば、そのように書けばいい。起承転結も構わない。欲しいものを欲しい形で書き出してごらん。
神さまの指示は私にぴったりだった。
私は長文も短文も詩も、ことばを山盛り、好きなように紙に飾った。うまく盛れないと手持ちの本でレシピを探し、似たような盛り方を参考にした。学校で習っていない漢字も、書くリズムや空間の線のバランスに魅かれて盛り付けた。何度も盛り付けていくうちに、好きな材料とテーマがあるのに気がついて、それに拘って書き込んで、とうとう始めと終わりのある作品が仕上がった。
「ようやった、ようやった。その歳でその才能、いや、大したもんや。わしの目も狂うてなかった、いうことやな。どうや、どう思う、物を書くのは。楽しないか、面白ないか。この話はお前だけのもんや、どこも、お前にぴったり、来るやろ」
神さまは手放しで褒めてくれたが、私は納得できなかった。本当に欲しいものに今一つ及ばない部分を知っていた。そこを満たすためには、ことばも感覚も未熟だった。それを埋めたいと感じていた。神さまの指示を待たず、私は作品を書き上げ続けた。一度に一作では物足りず、三作四作、並行して書いた。飽きる気配はなかったが、神さまは手を替え品を替え、私をそこから離れさせるまいとされた。
学校で作文を褒めさせた。辛く苦しい出来事を日記や作品を書くことで乗り越えられると感じさせた。友人を読者に仕立て上げ、なおかつ、熱狂的に支持させて、私にとって作品を書いていくことは、人々の役に立ち喜ばせ豊かにさせるものであると思わせた。
十二分に機を熟して、神さまはこう囁かれた。
「随分と腕が上がったやないか。わしも鼻が高いで。そやそや、今な、こう言う『公募』をやってるで。漫画の原作募集中、や。どうや、力試し、運試し、一つやってみたら。なあに、あかんで元々や。プロ、アマ、問わず、とあるやろ。ここで賞もろたら、大したもんやけど、もらわいでも落ち込むことあらへん。お前はプロちゃうしな。宝くじよりましなもん、と思て、どないや」
この挑発に私は乗った。結果、二度目のトライで佳作を取り、東京の出版社で受賞式となった。19歳。初めての一人での上京。聳える出版社の建物。幾枚もの名刺。閃くフラッシュ。見知らぬ大人達との会食。どれも舞い上がるには十分なものだった。そして、もちろん、神さまは、私の受けた賞が『佳作』であって『大賞』でないことは指摘しなかった。私にとって人生を変えるような晴れ舞台でも、出版社側にとっては毎年一回行われる出来事の一つでしかない、とは言わなかった。ましてや、作家志望の新人予備軍など、星の数以上いて、その中で一回の受賞から煌めく作家になる者など、銀河系のもう一つの生命種と遭遇するようなことだとは教えなかった。
私は一人前のつもりでプレッシャーを感じて書けなくなった。神さまにお伺いを立てようとしたが、忙しいと断られた。出版社にそれまで書き溜めたものを送って見たが、反応は鈍かった。そこでようやく、自分が、井の中の蛙どころか、井の中の微生物だと思い知った。書くのをやめようと思った。私程度の力は世の中に捨てるほどある。今回の受賞は、これまで書き続けてきたご褒美だったのだ、と。
****************