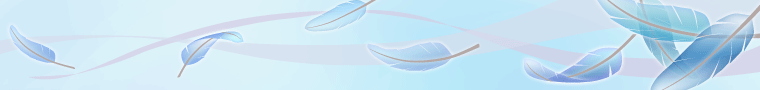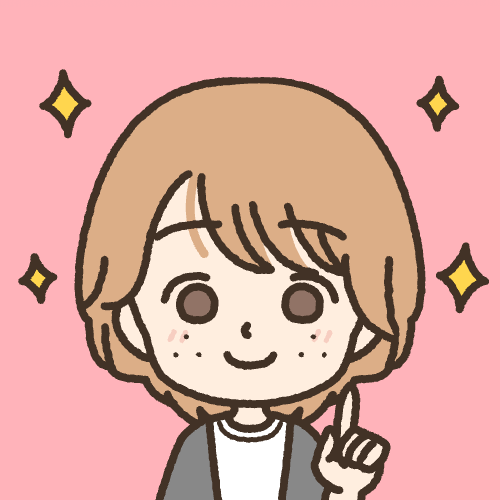フリーページ
全て
| 家計管理:家計ダイエットな日々
| 本 か行
| 映画 か行
| 映画 た行
| 映画 ら行
| 映画 さ行
| 映画 あ行
| 本 さ行
| 映画 は行
| 本 な行
| 本 あ行
| 本 た行
| 本 は行
| 本 ま行
| 本 ら行
| 本 や行
| 本 わ行
| 映画 わ行
| 映画 な行
| 映画 ま行
| 映画 や行
| 楽天ROOM
| ダイエット
テーマ: 読書(8214)
カテゴリ: 本 は行
今日の読書は、2020年度、126冊目
❤他人を信じるとは
1.その人間との関係の中で、自分がどんな価値を主張しても、理解され、受け入れてもらえること
2.相手が自分を利用したり、打ち明けた情報を自分の不利になるように用いたりしないと思うこと
❤重要なのは自分自身を知ることだー自らの嗜好や優先傾向を知り、それを考慮すれば、生まれてくる関係が公平で適正なものか、または違うのかといった感覚も決定づけられる
❤クライアントが陥りやすい5つの罠
1.最初の不信感
2.安堵
3.支援の代わりに、注目や安心感、妥当性の確認を求めること
4.憤慨したり防衛的になったりすること
5.ステレオタイプ化、非現実的な期待、(対人)知覚の転移
❤支援者が陥りやすい6つの罠
1.時期尚早に知恵を与えること:実態を探る時間をとるべき
2.防衛的な態度にさらに圧力をかけて対応すること:間違った問題に取り組んでいないか?公平な支援関係を築けているか?考える
3.問題を受け入れ、相手が依存してくることに過剰反応する
4.支援と安心感を与えること
5.支援者の役割を果たしたがらないこと:クライアントが本当に言わんとしていることに耳を傾け、問題への先入観を捨てること
6.ステレオタイプ化、事前の期待、逆転移、投影
・あなたを助けられる自信はありません。あなたはもっと積極的に、自分で解決策を見つけるべきだと思うからです
・あなたがすべきことを告げるのは違和感があります。私はあなたの立場にないからです。だから、私ならどうするかということしか話せないし、それが間違いなく妥当だとも思えません
❤支援者が知らない5つのこと
1.クライアントは情報や助言、あるいは尋ねられた質問を理解出来るだろうか
2.クライアントは支援者の提案に従うだけの知識やスキルを備えているだろうか
3.クライアントの本当のモチベーションは何か
4.クライアントの置かれた状況はどんなものか
5クライアントは経験に基づいて、期待や固定概念、恐怖心と言ったものをどう決定するだろうか
❤クライアントが知らない5つのこと
1.支援者には助けを与えるだけの知識やスキル、モチベーションがあるか 2.この人に助けを求めれば、どんな結果がえられるか
3.何かを売りつけたり不適切に強制したりするために、状況を利用しようとしない支援者なら、本当に信じられるのか
4.クライアントとして、私は提案されたことを実行できるだろうか
5.支援を受け入れると金銭面や感情面、または社会的な面でどれだけの代価を払うことになるだろうか
❤役割を選択する
役割1.専門家の役割ー情報やサービスを提供する
❤専門家の役割が本当に助けになる条件
1.クライアントが問題を正しく診断しているかどうか
2.クライアントがこの問題を支援者ときちんと話しているかどうか
3.支援者には情報やサービスを提供する能力があると、クライアントが的確に評価しているかどうか
4.支援者にそうした情報を集めさせることや、支援者が勧める改革を実行するという結果を、クライアントが考慮するかどうか
5.客観的に情報を研究して、それをクライアントが利用できるようにする外的現実があるかどうか
❤役割2.医師の役割ー診断と処方
・医師としての役割が成功する要点
1.クライアントが正解な情報を明かす気があるかどうか
2.クライアントが診断や処方を受け入れ、信じるかどうか
3.診断のプロセスによる結果が正解に理解されて、受け入れられるかどうか
4.勧めた変化をクライアントが実行に移せるかどうか
5.クライアントが依存心を強めた結果が、最終的な解決策の助けとなるのか、妨げとなるのか
❤役割3.プロセス・コンサルタントの役割
・クライアントはどんな助けがひつかを知らない場合が多い。
・どのような助けを求めているかクライアント自身が知るためのガイダンスが必要。
・何をどのように改善するかを見極めるには、支援が必要。
・自分が置かれた状況で何が最終的に効果をあげるかがわかるのは、クライアントだけだ
・自分自身で問題を見抜いて対応策を考えないかぎり、クライアントが解決方法を実行に移す可能性は低い
・支援の最終的な機能は、診断するためのスキルをクライアントに伝え、建設的な介入を行うこと
❤どんな支援の状況にも実行すること
1.状況に内在する無知を取り除くこと
2.初期段階における立場上の格差を縮めること
3.認識された問題にとって、さらにどんな役割をとるのが最適かを見極めること
❤ 重要なのは本当に必要なものを双方が理解するためのコミュニケーションのプロセス
❤問いかけを選択する
1.純粋な問いかけークライアントの話だけに集中するもの:クライアントには洗いざらい打ち明けてもらわねばならない。「続けて」「それについてもう少し話して下さい」「それからどうなったのですか」
2.診断的な問いかけー感情や、原因分析、行動の代替案を引き出すもの
・感情と反応
▶️それについてどのように感じましたか
▶️それに対してあなたは何か反応しましたか
▶️それに対するあなたの感情的な反応はどんなものでしたか
・原因と動機
▶️あなたがさこの問題を抱えているのは、なぜだと思いますか。どうして今なのでしょう
▶️なぜ、そんなことをしたのですか
▶️なぜ、あなたはそんなふうに反応したのだと思いますか。
・実行に移した行動、または検討中の行動
▶️どうやってここまで来たのですか
▶️それに対してあなたは何をしましたか
▶️今までのところ、あなたは何をしようとしましたか
▶️次は何をするつもりですか
▶️そのとき彼女は何をしましたか
・体系的な質問
▶️君が検討している服に、同僚たちはどんな反応をするだろうか
▶️もし、あなたがもっと強引になれば、同じグループのほかの人たちはどう反応するでしょうか
▶️さて、あなたができる事が一つありますよ。それによって、グループ内のほかの人たちとうまくいくと思いますか
▶️そういうことをすれば、どんな感じがしますか
3.対決的な問いかけー現状について支援者自身の見解をもたらすもの
▶️そのせいであなたは腹を立てましたか
▶️その件について彼に立ち向いましたか
▶️次のようなことはできませんか
▶️あなたは(彼が)不安だからそんなことをしたのだと思いませんか
4.プロセス指向型の問いかけークライアントに支援者との即座の相互関係に専念させるもの
▶️今の私たちの間にどんな事が起きていると思いますか
▶️これまでのところ、私たちの会話の流れをどう思いますか
▶️あなたの問題への対処について満足していますか
▶️私たちはうまくいっているでしょうか
▶️私の質問はあなたの助けになっていますか
❤意思を疎通させながら、次のタイプの質問に答える
1.クライアントと自分とのコミュニケーション・プロセスについて、私はどう感じているだろうか。無理なくリラックスしているだろうか。クライアントが悩んでいる話を私はわかっているのか
2.どれくらい時間があるだろうか。これは緊急の状態で、充分な情報を得ていなくても必要とされるものを推測すべきではないのか
3.クライアントと私の関係はどんなものだろうか
4.現時点で、クライアントが何に目を向けることが最も役立つと、私の診断力は告げているだろうか。信頼できる方法で充分に話してくれたから、診断的な問いかけもいくらか入れて、クライアントに焦点を当てるべきだろうか。対決的な質問をすべきだろうか。行動に対して説明や提案をすべきときだろうか
❤控えめな質問が支援関係における問題をはらんだダイナミクスが改善できるプロセス
1.クライアントに主導権を握らせ続け、自分のために問題を能動的に解決する立場を取り戻せるようにする事
2.ある程度まで自分のジレンマを自力で解決出来るという自信を与える事
3.クライアントと支援者が協力できるように、なるべく多くのデータを明らかにすること
❤成果をあげるチームワークの作り方
1.私はどんな人間になればいいのか。このグループでの私の役割は何かー多様な人生の状況において、誰もがさまざまなものになる能力がある
2.このグループで、私はどれくらいのコントロール、あるいは影響を及ぼすことになるかー人間としてある程度の影響を及ぼしたいというわれわれの願いに焦点を当てている
3.このグループで、私は自分の目標、あるいは要求を果たすことができるか。ーグループにそもそも自分が入った理由
4.このグループで、人々はどれくらい親しくなるだろうかーグループのメンバーがどれくらい個人的に、また感情的に関わるか
❤初期段階でのパフォーマンスを、グループが見直すことが重要な理由
1.パフォーマンスそのものを分析し、何がうまくいき、何を向上させる必要があるかを知るため
2.さらに役割を検証し、交渉できるようにするため
❤成果をあげるチームとは、自分の役割を心得て、その役割を果たすことが快いと感じるメンバーがいるのが特徴。チームをダメにするのは、始めから各自の役割が不明瞭だったり、見解の一致した役割からメンバーが逸脱したりすること。休んだり、求められたことをやらなかったり、不要な提案をしたり、無用な行動をとったりして、他人の領域を侵入する人がいる場合は、支援が過剰の状態になる
❤フィードバックとは、現在の進行状況が目標に向かっているか、外れているかということを示して、人がゴールに、到達できるよう助けるための情報である
❤部下はマイナスになるかもしれないことを上司に言う方法を学ぶべきだし、上司は不都合な真実を告げても、部下を不当に扱うことにはならない方法を学ぶべきだ。同様に、そうした方法をとるには前向きなフィードバックを与えたり、受け入れたりする能力が求められる
❤フィードバックは、求められたものでない場合は有益と言えない。フィードバックは、具体的で明確なものであるべきだ
❤仕事がもっと楽になるように、私ができる事は何かありましたかなど、フィードバックの求めにイニシアチブを与える。
❤フィードバックは評価的なものより、説明的なもののほうが機能する
❤フィードバックが最良の状態で働くのは、強要されるのではなく、自ら求めたもので、具体的かつ明確であり、共通の目標に適合していて、評価的なものというよりは説明的なものである場合
❤リーダーシップに関連する支援
1.各メンバーやいくつものグループが組織の任務を実行する上で、相互依存するチームワークのための環境を作り出すこと
2.組織のリーダーシップは、任務を達成する上で部下が支援を受けねばならない場合があることを伝える
3.リーダーを支援する
❤クライアントが自発的に支援を求めるまで、誰も変えられない
❤理想的な上司とは、部下に必要な目標を明確に心得ており、その目標を部下が達成するために手を貸す準備が出来ている人。部下が自分の所にきて、手を貸していただけませんかと言ったとき、上司は控えめな質問をして、プロセスコンサルタントにならねばならない
❤リーダーは、実践するうちに出てくるズレを把握するため、質問をして従業員との間に支援関係を確立し、信頼を築かねばならない
❤人は変化を気にかけないが、他人に自分を変えられたくないということは、自明の理の一つである
❤支援者はまず、新たな行動の妨げになっているのは何か、以前の行動をやめられないのはなぜか、クライアントが最初に踏み出せる一歩は何かといったことを尋ねて、人間関係の均衡を保たねばならない。学ぶべきことにクライアントの注意を引きつけるため、支援者は心理的に安心できる雰囲気を作り、望ましい行動の手本を提供する必要がある
❤組織を向上させる最善の方法は、相互に支援し合う環境を作り、組織のほかの者との関わりの中で自身の支援のスキルを明らかにすること。仕事を成功させるために、支援を受けるべきクライアントとして部下をみなす。リーダーシップを低気圧する一つの方法は、目標設定のプロセスと、そうした目標を達成するために部下を支援すること
❤支援関係における7つの原則
原則1:与える側も受け入れる側も用意が出来ているとき、効果的な支援が生じる
コツ1:支援を申し出たり、与えたり、受け入れたりする前に、自分の感情と意図をよく調べること
コツ2:支援したいとか、支援されたいとかいう自分の欲求が良くわかるようになること
コツ3:支援しようという努力が快く受け入れられなくても、腹を立てないこと
原則2:支援関係が公平なものだと見なされたとき、効果的な支援が生まれる
コツ4:支援を求める人は気まずい思いをしているという事を思い出そう。だからクライアントの本当の望みは何か、どうすれば最高の支援ができるかを必ず尋ねること
コツ5:あなたがクライアントなら、何が役立ち、何が役立たないかというフィードバックを支援者に与える機会を探そう
原則3:支援者が適切な支援の役割を果たしているとき、支援は効果的に行われる
コツ6:まず調べてから、どんな支援の形が具体的に必要とされているかを推測すること
コツ7:支援する状況が続く中で、あなたの演じている役割がまだ役に立つものかどうか、定期的に調べること
コツ8:あなたがクライアントなら、もはや助けられないと感じたとき、恐れることなく支援者にフィードバックを与えよう
原則4:あなたの行動のすべてが人間関係の将来を決定づける介入である
コツ9:支援者としての役割の中では、人間関係に与えそうな衝撃によって、自分の言動をすべて評価すること
コツ10:あなたがクライアントなら、やはり自分のあらゆる行動がメッセージを伝えていることを自覚するべきだ。
コツ11:フィードバックを与えるときは、現実の姿の記述にとどめるようにし、判断は最小限に抑えること
コツ12:不適切な励ましは最小限にすること
コツ13:不適切な修正は最小限にすること
原則5:効果的な支援は純粋な問いかけとともに始まる
コツ14:純粋な問いかけからつねに始めるべきである
コツ15:求められた支援がどれほどお馴染みのものに聞こえても、これまで一度も聞いたことがない、まったく新しい要求だとして考えよう
原則6:問題を抱えている当事者はクライアントである
コツ16:関係を築くまでは、クライアントの話の内容に関心を示しすぎないよう注意すること
コツ17:あなたがすべて知っていると思う問題とどれほど似ているようでも、それは他人の問題であって、あなたのものではなきことを絶えず思い出そう。
原則7:すべての答えを得ることはできない
コツ18:支援の対象となる問題を分かち合うこと
❤プロセス・コンサルテーション10の原則
1.絶えず人の役に立とうと心がける
2.今の自分が直面する現実からけっして遊離しないようにする
3.自分の無知を実感する
4.あなたがどんなことを行っても、それは介入、もしくはゆさぶりになる
5.問題を自分の問題として当事者意識を持って受け止め、解決も自分なりの解決として編み出していくのは、あくまでクライアントだ。
6.流れに沿って進む
7.タイミングがすごく大事
8.介入で対立が生じたときには、積極的に解決の機会を捉えよ
9.何もかもがデータだと心得よ。誤謬はいつも起こるし、誤謬は、学習の重要な源泉だ
10.どうしていいか判らなくてなったら、問題を話合おう

人を助けるとはどういうことか第2版 本当の「協力関係」をつくる7つの原則 [ エドガー・H.シャイン ]
❤他人を信じるとは
1.その人間との関係の中で、自分がどんな価値を主張しても、理解され、受け入れてもらえること
2.相手が自分を利用したり、打ち明けた情報を自分の不利になるように用いたりしないと思うこと
❤重要なのは自分自身を知ることだー自らの嗜好や優先傾向を知り、それを考慮すれば、生まれてくる関係が公平で適正なものか、または違うのかといった感覚も決定づけられる
❤クライアントが陥りやすい5つの罠
1.最初の不信感
2.安堵
3.支援の代わりに、注目や安心感、妥当性の確認を求めること
4.憤慨したり防衛的になったりすること
5.ステレオタイプ化、非現実的な期待、(対人)知覚の転移
❤支援者が陥りやすい6つの罠
1.時期尚早に知恵を与えること:実態を探る時間をとるべき
2.防衛的な態度にさらに圧力をかけて対応すること:間違った問題に取り組んでいないか?公平な支援関係を築けているか?考える
3.問題を受け入れ、相手が依存してくることに過剰反応する
4.支援と安心感を与えること
5.支援者の役割を果たしたがらないこと:クライアントが本当に言わんとしていることに耳を傾け、問題への先入観を捨てること
6.ステレオタイプ化、事前の期待、逆転移、投影
・あなたを助けられる自信はありません。あなたはもっと積極的に、自分で解決策を見つけるべきだと思うからです
・あなたがすべきことを告げるのは違和感があります。私はあなたの立場にないからです。だから、私ならどうするかということしか話せないし、それが間違いなく妥当だとも思えません
❤支援者が知らない5つのこと
1.クライアントは情報や助言、あるいは尋ねられた質問を理解出来るだろうか
2.クライアントは支援者の提案に従うだけの知識やスキルを備えているだろうか
3.クライアントの本当のモチベーションは何か
4.クライアントの置かれた状況はどんなものか
5クライアントは経験に基づいて、期待や固定概念、恐怖心と言ったものをどう決定するだろうか
❤クライアントが知らない5つのこと
1.支援者には助けを与えるだけの知識やスキル、モチベーションがあるか 2.この人に助けを求めれば、どんな結果がえられるか
3.何かを売りつけたり不適切に強制したりするために、状況を利用しようとしない支援者なら、本当に信じられるのか
4.クライアントとして、私は提案されたことを実行できるだろうか
5.支援を受け入れると金銭面や感情面、または社会的な面でどれだけの代価を払うことになるだろうか
❤役割を選択する
役割1.専門家の役割ー情報やサービスを提供する
❤専門家の役割が本当に助けになる条件
1.クライアントが問題を正しく診断しているかどうか
2.クライアントがこの問題を支援者ときちんと話しているかどうか
3.支援者には情報やサービスを提供する能力があると、クライアントが的確に評価しているかどうか
4.支援者にそうした情報を集めさせることや、支援者が勧める改革を実行するという結果を、クライアントが考慮するかどうか
5.客観的に情報を研究して、それをクライアントが利用できるようにする外的現実があるかどうか
❤役割2.医師の役割ー診断と処方
・医師としての役割が成功する要点
1.クライアントが正解な情報を明かす気があるかどうか
2.クライアントが診断や処方を受け入れ、信じるかどうか
3.診断のプロセスによる結果が正解に理解されて、受け入れられるかどうか
4.勧めた変化をクライアントが実行に移せるかどうか
5.クライアントが依存心を強めた結果が、最終的な解決策の助けとなるのか、妨げとなるのか
❤役割3.プロセス・コンサルタントの役割
・クライアントはどんな助けがひつかを知らない場合が多い。
・どのような助けを求めているかクライアント自身が知るためのガイダンスが必要。
・何をどのように改善するかを見極めるには、支援が必要。
・自分が置かれた状況で何が最終的に効果をあげるかがわかるのは、クライアントだけだ
・自分自身で問題を見抜いて対応策を考えないかぎり、クライアントが解決方法を実行に移す可能性は低い
・支援の最終的な機能は、診断するためのスキルをクライアントに伝え、建設的な介入を行うこと
❤どんな支援の状況にも実行すること
1.状況に内在する無知を取り除くこと
2.初期段階における立場上の格差を縮めること
3.認識された問題にとって、さらにどんな役割をとるのが最適かを見極めること
❤ 重要なのは本当に必要なものを双方が理解するためのコミュニケーションのプロセス
❤問いかけを選択する
1.純粋な問いかけークライアントの話だけに集中するもの:クライアントには洗いざらい打ち明けてもらわねばならない。「続けて」「それについてもう少し話して下さい」「それからどうなったのですか」
2.診断的な問いかけー感情や、原因分析、行動の代替案を引き出すもの
・感情と反応
▶️それについてどのように感じましたか
▶️それに対してあなたは何か反応しましたか
▶️それに対するあなたの感情的な反応はどんなものでしたか
・原因と動機
▶️あなたがさこの問題を抱えているのは、なぜだと思いますか。どうして今なのでしょう
▶️なぜ、そんなことをしたのですか
▶️なぜ、あなたはそんなふうに反応したのだと思いますか。
・実行に移した行動、または検討中の行動
▶️どうやってここまで来たのですか
▶️それに対してあなたは何をしましたか
▶️今までのところ、あなたは何をしようとしましたか
▶️次は何をするつもりですか
▶️そのとき彼女は何をしましたか
・体系的な質問
▶️君が検討している服に、同僚たちはどんな反応をするだろうか
▶️もし、あなたがもっと強引になれば、同じグループのほかの人たちはどう反応するでしょうか
▶️さて、あなたができる事が一つありますよ。それによって、グループ内のほかの人たちとうまくいくと思いますか
▶️そういうことをすれば、どんな感じがしますか
3.対決的な問いかけー現状について支援者自身の見解をもたらすもの
▶️そのせいであなたは腹を立てましたか
▶️その件について彼に立ち向いましたか
▶️次のようなことはできませんか
▶️あなたは(彼が)不安だからそんなことをしたのだと思いませんか
4.プロセス指向型の問いかけークライアントに支援者との即座の相互関係に専念させるもの
▶️今の私たちの間にどんな事が起きていると思いますか
▶️これまでのところ、私たちの会話の流れをどう思いますか
▶️あなたの問題への対処について満足していますか
▶️私たちはうまくいっているでしょうか
▶️私の質問はあなたの助けになっていますか
❤意思を疎通させながら、次のタイプの質問に答える
1.クライアントと自分とのコミュニケーション・プロセスについて、私はどう感じているだろうか。無理なくリラックスしているだろうか。クライアントが悩んでいる話を私はわかっているのか
2.どれくらい時間があるだろうか。これは緊急の状態で、充分な情報を得ていなくても必要とされるものを推測すべきではないのか
3.クライアントと私の関係はどんなものだろうか
4.現時点で、クライアントが何に目を向けることが最も役立つと、私の診断力は告げているだろうか。信頼できる方法で充分に話してくれたから、診断的な問いかけもいくらか入れて、クライアントに焦点を当てるべきだろうか。対決的な質問をすべきだろうか。行動に対して説明や提案をすべきときだろうか
❤控えめな質問が支援関係における問題をはらんだダイナミクスが改善できるプロセス
1.クライアントに主導権を握らせ続け、自分のために問題を能動的に解決する立場を取り戻せるようにする事
2.ある程度まで自分のジレンマを自力で解決出来るという自信を与える事
3.クライアントと支援者が協力できるように、なるべく多くのデータを明らかにすること
❤成果をあげるチームワークの作り方
1.私はどんな人間になればいいのか。このグループでの私の役割は何かー多様な人生の状況において、誰もがさまざまなものになる能力がある
2.このグループで、私はどれくらいのコントロール、あるいは影響を及ぼすことになるかー人間としてある程度の影響を及ぼしたいというわれわれの願いに焦点を当てている
3.このグループで、私は自分の目標、あるいは要求を果たすことができるか。ーグループにそもそも自分が入った理由
4.このグループで、人々はどれくらい親しくなるだろうかーグループのメンバーがどれくらい個人的に、また感情的に関わるか
❤初期段階でのパフォーマンスを、グループが見直すことが重要な理由
1.パフォーマンスそのものを分析し、何がうまくいき、何を向上させる必要があるかを知るため
2.さらに役割を検証し、交渉できるようにするため
❤成果をあげるチームとは、自分の役割を心得て、その役割を果たすことが快いと感じるメンバーがいるのが特徴。チームをダメにするのは、始めから各自の役割が不明瞭だったり、見解の一致した役割からメンバーが逸脱したりすること。休んだり、求められたことをやらなかったり、不要な提案をしたり、無用な行動をとったりして、他人の領域を侵入する人がいる場合は、支援が過剰の状態になる
❤フィードバックとは、現在の進行状況が目標に向かっているか、外れているかということを示して、人がゴールに、到達できるよう助けるための情報である
❤部下はマイナスになるかもしれないことを上司に言う方法を学ぶべきだし、上司は不都合な真実を告げても、部下を不当に扱うことにはならない方法を学ぶべきだ。同様に、そうした方法をとるには前向きなフィードバックを与えたり、受け入れたりする能力が求められる
❤フィードバックは、求められたものでない場合は有益と言えない。フィードバックは、具体的で明確なものであるべきだ
❤仕事がもっと楽になるように、私ができる事は何かありましたかなど、フィードバックの求めにイニシアチブを与える。
❤フィードバックは評価的なものより、説明的なもののほうが機能する
❤フィードバックが最良の状態で働くのは、強要されるのではなく、自ら求めたもので、具体的かつ明確であり、共通の目標に適合していて、評価的なものというよりは説明的なものである場合
❤リーダーシップに関連する支援
1.各メンバーやいくつものグループが組織の任務を実行する上で、相互依存するチームワークのための環境を作り出すこと
2.組織のリーダーシップは、任務を達成する上で部下が支援を受けねばならない場合があることを伝える
3.リーダーを支援する
❤クライアントが自発的に支援を求めるまで、誰も変えられない
❤理想的な上司とは、部下に必要な目標を明確に心得ており、その目標を部下が達成するために手を貸す準備が出来ている人。部下が自分の所にきて、手を貸していただけませんかと言ったとき、上司は控えめな質問をして、プロセスコンサルタントにならねばならない
❤リーダーは、実践するうちに出てくるズレを把握するため、質問をして従業員との間に支援関係を確立し、信頼を築かねばならない
❤人は変化を気にかけないが、他人に自分を変えられたくないということは、自明の理の一つである
❤支援者はまず、新たな行動の妨げになっているのは何か、以前の行動をやめられないのはなぜか、クライアントが最初に踏み出せる一歩は何かといったことを尋ねて、人間関係の均衡を保たねばならない。学ぶべきことにクライアントの注意を引きつけるため、支援者は心理的に安心できる雰囲気を作り、望ましい行動の手本を提供する必要がある
❤組織を向上させる最善の方法は、相互に支援し合う環境を作り、組織のほかの者との関わりの中で自身の支援のスキルを明らかにすること。仕事を成功させるために、支援を受けるべきクライアントとして部下をみなす。リーダーシップを低気圧する一つの方法は、目標設定のプロセスと、そうした目標を達成するために部下を支援すること
❤支援関係における7つの原則
原則1:与える側も受け入れる側も用意が出来ているとき、効果的な支援が生じる
コツ1:支援を申し出たり、与えたり、受け入れたりする前に、自分の感情と意図をよく調べること
コツ2:支援したいとか、支援されたいとかいう自分の欲求が良くわかるようになること
コツ3:支援しようという努力が快く受け入れられなくても、腹を立てないこと
原則2:支援関係が公平なものだと見なされたとき、効果的な支援が生まれる
コツ4:支援を求める人は気まずい思いをしているという事を思い出そう。だからクライアントの本当の望みは何か、どうすれば最高の支援ができるかを必ず尋ねること
コツ5:あなたがクライアントなら、何が役立ち、何が役立たないかというフィードバックを支援者に与える機会を探そう
原則3:支援者が適切な支援の役割を果たしているとき、支援は効果的に行われる
コツ6:まず調べてから、どんな支援の形が具体的に必要とされているかを推測すること
コツ7:支援する状況が続く中で、あなたの演じている役割がまだ役に立つものかどうか、定期的に調べること
コツ8:あなたがクライアントなら、もはや助けられないと感じたとき、恐れることなく支援者にフィードバックを与えよう
原則4:あなたの行動のすべてが人間関係の将来を決定づける介入である
コツ9:支援者としての役割の中では、人間関係に与えそうな衝撃によって、自分の言動をすべて評価すること
コツ10:あなたがクライアントなら、やはり自分のあらゆる行動がメッセージを伝えていることを自覚するべきだ。
コツ11:フィードバックを与えるときは、現実の姿の記述にとどめるようにし、判断は最小限に抑えること
コツ12:不適切な励ましは最小限にすること
コツ13:不適切な修正は最小限にすること
原則5:効果的な支援は純粋な問いかけとともに始まる
コツ14:純粋な問いかけからつねに始めるべきである
コツ15:求められた支援がどれほどお馴染みのものに聞こえても、これまで一度も聞いたことがない、まったく新しい要求だとして考えよう
原則6:問題を抱えている当事者はクライアントである
コツ16:関係を築くまでは、クライアントの話の内容に関心を示しすぎないよう注意すること
コツ17:あなたがすべて知っていると思う問題とどれほど似ているようでも、それは他人の問題であって、あなたのものではなきことを絶えず思い出そう。
原則7:すべての答えを得ることはできない
コツ18:支援の対象となる問題を分かち合うこと
❤プロセス・コンサルテーション10の原則
1.絶えず人の役に立とうと心がける
2.今の自分が直面する現実からけっして遊離しないようにする
3.自分の無知を実感する
4.あなたがどんなことを行っても、それは介入、もしくはゆさぶりになる
5.問題を自分の問題として当事者意識を持って受け止め、解決も自分なりの解決として編み出していくのは、あくまでクライアントだ。
6.流れに沿って進む
7.タイミングがすごく大事
8.介入で対立が生じたときには、積極的に解決の機会を捉えよ
9.何もかもがデータだと心得よ。誤謬はいつも起こるし、誤謬は、学習の重要な源泉だ
10.どうしていいか判らなくてなったら、問題を話合おう

人を助けるとはどういうことか第2版 本当の「協力関係」をつくる7つの原則 [ エドガー・H.シャイン ]
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[本 は行] カテゴリの最新記事
-
バカでも稼げる「米国株」高配当投資 2024年04月18日
-
ヘアロスしないためにやりたい12のこと 2024年04月02日
-
ほったらかし投資術 2024年03月23日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
© Rakuten Group, Inc.