砂漠の果て(第9部「断崖」)
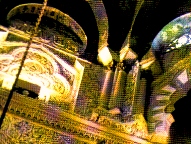
アルブラートは、ベッドに寝たまま、自分をじっと見つめるアイシャを眺めていた。アイシャは、3年前に別れた時よりも、ずっと大人びていた。彼は、彼女が17歳ほどに見えた。
「アイシャ......もう15歳だったよね......今でも歌を歌ってる?」
アイシャは懐かしいアルブラートの問いかけに、嬉しそうに微笑んだ。
「ずっと歌ってたの。シリアの病院で賛美歌を覚えて―入院している人たちに、歌って聞かせたりしてたのよ」
「......シリアにいたの?シリアのどこに?」
「クネイトラよ。ムラートと別れてから......ヨルダン川沿いに歩いて逃げたの......それから、国連軍の人たちに偶然助けられて―クネイトラの病院にしばらくいたの」
アルブラートは、自分が捕虜収容所にいたことは、今は言いたくなかった。だが、アイシャが同じシリアに、しかも自分のいたガリラヤ湖と近い所にいたことに驚いた。彼女の声は、12歳の時よりも落ち着いた響きだったが、可憐で初々しく、澄んでいるところは、昔と同じだった。
彼はしばらく黙って、彼女の温かな頬にじっと手をやり、また、白く細い手を優しく握りしめた。自分たち二人だけが、あのキャンプの生き残りなのではないかと思うと、アイシャが生きていたことで、神はまだ自分を見捨ててはいないと深く感じた。
「アルブラート。彼女を、ムカールが連れてきたんです。この娘さんのおかげで、あなたの手術も無事済みました」
医師の言葉に、彼はそばの椅子に座るムカールの方を見た。ムカールは、やや疲れたような顔で、彼を見つめていた。彼は、青年が、アイシャを、体に無理をして連れて来たのだとすぐに分かった。
「良かったな、アルラート。無事にアイシャと会えて......アイシャもカイロに一緒に行く準備をして来たんだ。もうずっと離すんじゃないぞ」
ムカールはくたびれたような口調だった。医師は、医療用鞄を持つと、自分の部屋に一緒に来るようにと、彼に言った。ムカールは少年に微笑んで見せると、ヨシュアの部屋を出て行ったが、アルブラートは彼の目に不安な翳りを見て取った。
医師は、青年をソファーに座らせると、左手首のやや上に注射をした。ムカールは黙っていたが、急に医師を見上げた。
「先生―先生は、3日以内に死ぬと......私が死ぬと言われました―それは......カイロに着く前に......死ぬ可能性があると......そういうことでしょうか」
「いいえ、私の言葉が足りなかったのはお詫びします......今、あなたに抗生物質を注射しました。これはかなりの量のペニシリンです。この注射を、船中でも、朝晩2回します―それで、壊疽の進行を食い止めておきますので、カイロまでは大丈夫です」
医師はチョッキを脱いで、椅子にかけると、彼の真向かいに座った。
「ペニシリンを投与し、抗熱剤を服用しないままでいると、命にかかわるのです。左腕の切断手術は、今すぐの方がもちろんいいわけですが―カイロの私の病院に行かないと、完全な設備がここにはないわけですからね。ですから―手術は辛いでしょうが......終わるまで辛抱なさって下さい」
ムカールは、蒼ざめながら、両手を組み合わせ、医師を真っ直ぐに見つめていたが、視線を落とすと、低い声を震わせた。
「本当は......本当は......怖ろしいんです......手術のことではなく......いつかは死ぬんじゃないかと......それも......近いうちに......
なぜかそんな予感がして......」
医師は、青年のこんなに怯える様子に驚いた。
「なぜそんなことをお考えになるんですか......?」
「小さい頃から何回も壊疽を起こして......何回も高熱で倒れて......
そのたびに、お医者から言われてきました......20歳までもたないだろうと......」
ザキリスは、何かを言いかけようとして、言い淀んだ。彼は青年の、漆黒に光る緩やかなウェーブのかかった髪や、大理石のように白いつややかな肌や、人を魅了してやまない、深い叡智を秘めた美しい黒曜石のような目を見るにつけ、ある奇妙な想念が浮かんできた。
この青年はアポロン* 以上の卓越した存在だ......
彼はまさしくリーインカーネーションと言ってもいいのではないか......
まさにパルミュラ王国の女王ゼノビア* の化身のようだ......
彼がレバノンに来る前はトルコの孤児院にいたというが......
その前は一体どこに......
彼はどういった生まれなんだろうか......
だが医師は、それ以上の賛嘆や疑念を持つまいとした。目の前にいるのは、病魔に冒され、死の恐怖に慄く一人の若者だった。
「あなたが死を怖れるのは......そのように言われてきたからでしょう―でも、もう25歳になっておられるんですし......今度手術を受ければ、ずっと元気でいられますよ。とりあえず今日はもう、調理場のお仕事は休んで下さい」
ムカールが、仕事をやらないと、支配人に手首を鞭で打たれることを打ち明けると、ザキリスは酷いことをすると言って、驚いた。
「では私が、あなたの主治医として、支配人に直接話しておきます。今日は熱で無理ができないと―今日休んだくらいで、その支配人には、私たちの密航の計画は感づかれやしませんから」
* アポロン(Apollon): ギリシャ神話の神。美しく、男性的な神であり、音楽・医術・弓術・予言・光明の神とし、太陽と同一視される。
* ゼノビア: シリア中部の古代都市パルミュラ王国の女王。地中海とペルシア湾を結ぶ隊商路の中継地として繁栄するが、ローマに滅ぼされる。

医師は、ムカールを自分の部屋のベッドに寝かせ、昼食を取りに1階のサロンに降りて行った。サロンでは、今朝の騒ぎで、演奏用のホールにはカーテンが下りていた。ホールの脇で、従業員に指図している男を見て、医師はそのそばに歩いて行った。
「失礼ですが―あなたがこのホテルの支配人でおられますか」
ザイードは、急に声をかけられて、医師の方をジロジロ見た。
「そうですが。お客様は何の御用で?」
「今朝、治安部隊がこのサロンで、演奏しようとしていた少年の足を狙撃しましたね―私は、その子の怪我を緊急に手術した者です」
支配人は、それを聞いても、素知らぬ顔で、近頃は物騒で困ると愚痴をこぼした。ザキリスは、この男が粗暴で無教養な人間だと一目で分かった。
「あなたはご存知のはずです。あなたが、あの無実の少年をパレスチナ人だと通告したのでしょう―なぜそんなことをするんです?あなたのために、あの子は一生右足が不自由になりました」
「お客様のお話は、私にはとんと合点がいきませんが......あの少年がパレスチナ人だなどと、治安部隊は何か誤解をしたんでしょう」
「それに、ムカールという調理師がいますね......私は彼も診察しました。壊疽がひどくなっていましてね......今朝はひどい熱を出したんです。今日は仕事を休ませないと、もはや命にかかわるんです。でも、あなたは......彼が仕事をしないと、あの左手首を鞭で打つそうですね」
ザイードは一瞬うろたえたが、傲慢な態度で青年をなじった。
「ああ、あれは仕事をすぐにすっぽかす役立たずでして......罰を与えなければ、どうにも言うことを聞かない強情者でしてね」
「いや、あなたは間違っている。私はあの青年と話をして、非常に聡明で立派な理性の持ち主だということが分かりましたよ。それにこのホテルでは、あの青年の料理の腕前は超一流です。その大事な腕を、あなたは鞭で打つなどと......何と卑劣な......道理を弁えない振舞いをするんです?」
医師の毅然とした口調に、ザイードは怪訝そうな顔をしていた。彼は何と言ったら良いのか分からず、混乱したらしく、投げやりな返答をした。
「お医者様のお客様が、あれを休ませたいと言われるんでしたら、どうとでも―ご自由になすったらいいでしょう。私もあれには手を焼いてますんで......」
ザキリスは、窓際に座り、昼食を取った。彼は内心、今の支配人との会話に呆れ返っていた。何とも筋の通らない、あれほど愚劣な者がこのホテルを取り仕切り、罪のない若者たちを窮地に追いやっているのかと思うと、権力の愚かさに憤りを感じた。
この小さなホテルはまるで世界の縮図だな......
愚か者が戦争を起こし、無実の若い命が蝕まれていくんだから......
彼は、食器を片付けに来たファハドにチップを渡すと、アルブラートとムカールに軽い昼食を出すように頼んだ。
「ああそうだ―あのアイシャにも何かお願いしますよ。昼食は私も一緒に運びますから。アルブラートは、今日はあのまま、あそこに寝ていた方がいいでしょう」
ファハドはびっくりして、お客に食事を運ばせるなんてできないと断ったが、ザキリスは笑って、何も気兼ねは要らないと言った。
「私は必要とあらば、何でもする人間ですからね。医師になる前は、それこそ何でもやりましたよ。商店の使い走りから郵便局の事務員―先の大戦でも一兵卒として出征しました。それにアルブラートに話がありますしね」
アルブラートは、医師が昼食を運んで来たのに驚いたが、ようやく上半身を起こすと、何とかベッドの上で食事を始めた。医師は、部屋の中央にある小さな四角形の木製のテーブルに、アイシャの食事を置くと、彼女をそこに座らせ、昼食を勧めた。
「アイシャはあなたによく雰囲気が似ていますね。妹さんですか」 「いえ......難民キャンプで小さい時から一緒に育ったんです」
「そうですか......あの娘さんは実に優秀な看護婦ですよ。それで、アルブラート......あなたの術後の経過ですが―ギブスは1ヶ月で取れます。ですが......撃たれた膝の骨を一部、切除したので、スムーズに歩いたり、走ったりは、もうできないんです......大変残念なことですが......」
アルブラートはそれを聞いても、あまり驚かなかった。彼は食事の手を止めると、しばらく考えていた。
「いいんです......あれだけひどく撃たれたんだから、そうなっても仕方ありません......きっとそうじゃないかと思っていました。でも―撃たれたのが腕や手じゃなくて良かった......最善を尽くして下さって......先生に本当に感謝しています」
医師は、まだ18歳の少年が、礼儀正しく、慎み深いのに深い感銘を受けた。平素は無口なおとなしい性質のようだが、内省的で、考え深い傾向は、逆に、芸術に対する感受性の豊かさの表れだと思い、アルブラートを好ましく感じた。
そのアルブラートに、青年の手術の話をするのはためらわれたが、今言っておかないと、後で受けるショックはより大きいだろうと判断した。
「ところで、ムカールのことですが......彼の左腕はもう壊疽にすっかり覆われていて......破傷風の合併症を今後、引き起こす可能性も大きいのです。それで、カイロの私の病院に着いたら、すぐにでも左肩からの切断手術をする必要があるんです......そうしないと、命にかかわりますのでね」
この医師の話を聞いた途端、アルブラートはまるで大事にしていた宝石が砕け散るような衝撃に見舞われた。その感覚は、ベト・シェアンの収容所で、母がエルサレムに連れ去られたと聞いた時のショックに近かった。
彼は不吉な予感がし、医師に質問をするのを怖れているかのようだった。
「その手術をすれば......死んだりは―しませんか......」
「大丈夫です―助かるための手術なんですから」
アルブラートは、「破傷風」と聞いて、きっとムカールがアイシャを連れて来る途中に、雨の中で転倒したのではないかと感づいた。彼は、昨年の秋に、この街に来たことが悔やまれた。
この街に来たのは本当は、音楽院に入りたかったためだった......
でもムカールはパレスチナ人の俺と出会ったために......
難民の俺をかばったために、支配人から義手を鞭で打たれて......
治安局から名前を剥奪されて......
俺はパレスチナ人だから治安部隊に撃たれた―でもそのためにムカールは......
雨が降るのに危険を冒して―アイシャを連れに行って......
とうとう腕を切断しなけりゃいけないほど、壊疽が進行したんだ......
ムカールが片腕になるのは......結局は俺のせいなんだ......

彼はこの時、生まれて初めて、自分がパレスチナ人であることを厭わしく感じた。母を殺したことを告白した時、自分の苦悩すべてを引き受けてくれたのはムカールただ一人だった。ムカールは自分を両腕で抱きしめてくれ、苦しみを共有してくれた唯一の人だった。
その青年が片腕になる―このことは、彼には、母の最期の息の根を止めたという、自分の怖ろしい行為に対する「罰」のように思えてならなかった。
やっぱり罰が下されたんだ......
罰がこれで済むわけがない......きっともっと怖ろしい罰が......
俺を待ち受けているに違いないんだ......
アルブラートの顔色が悪くなり、不安の面持ちに変わっていくのを見た医師は、彼が青年の死を怖れているのだと察した。
「今お話しするのは、申し訳ないと思いましたが―でも明後日カイロに着いたら、すぐにでも手術が必要ですので......その時いきなりお話するよりはと思ったのです。ムカールも承知しています。何の心配も要りません」
だが彼は目をつぶり、激しく頭を振った。彼は両手で頭を押さえ、体を震わせていた。今にも息が詰まりそうな圧迫感を覚えた。
ムカールがもし死んだら―?あの秘密を知る彼がいなくなったら......!アイシャにも、ザキリスにもあの秘密をとても打ち明けられない......!
その恐怖が彼を押し潰そうとしていた。
アイシャは、アルブラートの異様な雰囲気を敏感に感じ取って、食事を止めると、彼のそばにひざまずいた。彼がアイシャを見ると、その背後に母が昔と変わらぬ姿で立っているような気がした。アイシャは、彼が涙を流しているのに気づいて、頬の涙をそっと拭うと、彼の肩を抱きしめた。
医師は、少年の苦しみが、単に青年の死への恐怖によるものだと思った。ムカールの手術の話が必要だったとは言え、あまりに不用意だったのではないかと、罪悪感に駆られた。
「あの青年は―あなたにとって......とても大事な友人なんですね」
アルブラートは、息をつきながら、ようやく答えた。
「この街に来た時......誰も僕を泊めてくれなかった......でも彼は、僕がパレスチナ人でもいいんだと言って泊めてくれた......彼は、僕に演奏の仕事をさせてくれた最初の人だった......それに彼は僕の母に―驚くほど似ている......だから僕は彼を失いたくないんです......」
「彼があなたのお母さんに......?そんなに似ているんですか」
彼は我に返ったように、ハッとして医師を見た。アイシャも驚いたように、体を起こし、アルブラートの方に視線をやろうとした。
「それは不思議な偶然ですね―でもそれでは、あなたのお母さんは亡くなられたんですか......?」
アルブラートは医師から目を反らすと、黙ってかすかにうなずいた。ザキリスはしばらく無言で少年を見つめていたが、静かな口調で言った。
「だからあなたは、私にあんなに一生懸命、彼の診察をお願いしたんですね......あなたが彼の手術を心配される気持ちはよく分かります。でも―手術は必ず成功しますから......落ち着いて、お食事を取って、出航まで休んでいて下さい」
ムカールは、医師の部屋でしばらく眠っていたが、急に目が覚めた。ベッドのそばには、アデルが心配そうに付き添っていた。もう午後の3時過ぎだった。彼は、仕事の時間だと思ったが、医師から、今日は仕事を休むようにと言われたことを思い出した。
彼は、ソファーテーブルに昼食が置かれていることに驚いた。アデルが、医師がここに食事を運んで来てくれたと説明したが、ムカールはとんでもないと言った。彼は、自分の部屋で食べると言って、アデルに食事を2階まで運んでもらい、自分も階下に降りて行った。
「あんな最上級のお客の部屋で寝かせてもらって、あんな立派な部屋で食事をするなんてもったいないよ。でもああいう所で寝るなんて、生まれて初めてだったな......まるで王子様か何かみたいだな」
「でもあなたにはぴったりよ。ムカールがあのベッドで寝ているのを見ていたら、本当に王子様そのものだったわ......恐いくらいに」
ムカールはこれを聞いて笑った。手術のことは忘れていなかったが、本来の陽気な性質がまた戻って来たらしく、もうあまり先のことを深く考えようとはしなかった。
彼はアデルと椅子を並べて食事をしていたが、アデルの黒髪を愛おしそうに撫ぜると、彼女の肩を抱き寄せ、髪に優しく口づけした。
「お前も冗談が好きだな。俺が王子様に見えるのか」
「そうよ。あなたは自分の魅力に全然気づいてないのね―私はあなたといると気後れしてしまうほどよ......私は美人でも何でもないのに、あなたは誰が見ても立派で、最高に美しいんだもの......」
「ふーん、そうかな。でも俺はアデルが最高にきれいに見えるよ。それじゃ、俺が片腕になっても、アデルは俺を愛してくれるのか」
「もちろんそうよ......あなたがどんなであっても―でもひどいわ......そんなことを平気で言うなんて......」
アデルは涙ぐんでいた。ムカールは彼女に詫びて、慰めたが、自分でも下らないことを言ったと思った。
「片腕になっても」だなんて......
自己卑下もいいとこだな......アデルは俺を愛しているのに......
彼は食事を済ませると、医師から渡された抗熱剤を飲んだ。改めて自分の部屋を見渡すと、目覚まし時計が机の上に置かれたままだった。彼はそれを自分の鞄に入れると、今度はアルブラートの鞄を見た。昨夜、アルブラートと見たモハメダウィの日記帳が一番上に置かれてあった。
ムカールは両方の鞄を閉じると、後はアルブラートの楽器だけだと思った。彼はアデルに、アルブラートの鞄とカーヌーンを持たせ、自分の鞄を右手で持つと、ヨシュアの部屋に荷物を置きに行った。
アルブラートはムカールの手術に対する動揺がやや治まっていた。いつもと変わらない青年を見ると、自分の不安を彼に見せてはならないと思った。ムカールは、ファハドを呼んで、彼に、ホールに倒れたままのウードを持って来させた。
アデルには、夜の9時までいつも通りに仕事をし、10時になったら支度を済ませた鞄を持って、ヨシュアの部屋に来るように言った。その後、ムカールは、医師に言われた通り、自分の部屋のベッドで休んでいた。夕食を済ませると、皆がヨシュアの部屋に集まった。
時計を見ると、もう夜の10時だった。ヨシュアは約束通り、普段使っていない裏口の鍵を渡した。医師は、ファハドの手を借りて、裏口で待っていた知人の車に、先にアルブラートを後部座席に寝かせ、アイシャをそのそばに
座らせると、一足先に、二人を港まで送り、予約してあった船室に案内した。
医師が戻って来ると、今度はムカールとアデルが車に乗る番だった。ヨシュアはムカールと別れるのが辛いと言って、涙を目に浮かべながら彼を見つめていた。ムカールは、深い感情を目にたたえて、老人を見つめていたが、急にヨシュアを抱きしめると、コートのポケットにくしゃくしゃに突っ込んであった手紙を渡した。
「向こうに着いたら、時々ヨシュアの親戚の名前で手紙を送るから......写真も送るよ。じゃあ......さようなら、ヨシュア」

ヨシュアは、裏口の鍵を閉めると、しばらくそこに佇んでいた。青年の遠ざかって行く足音と、車の走り出す音を聞き届けると、自分の部屋に戻った。
ヨシュアは、力なく椅子に腰掛けると、彼から手渡された手紙を読んで見た。きちんと折り畳まずに、しわくちゃになった手紙を渡すところが、いかにもムカールの無造作な性質が表れていると思ったが、ヨシュアには、それさえも愛すべき彼の癖だった。
その物ぐさな性質とは裏腹に、手紙は丁寧な立派な字で書かれてあった。
親愛なるヨシュア
―今までいろいろとありがとうございました。
あなたは私にとって父でもあり、優しいお祖父様でもありました。
前のご主人が亡くなってから、8年間、私の病気のことで、いつも気苦労をおかけしてばかりでした。
そのことを、今、とても申し訳なく思っています。
私のような孤児を愛して下さったご恩は一生忘れません。
神のご加護がありますように心よりお祈りしています。
ムハバイール・アル・モハメダウィ
ヨシュアは、黒いインクで書かれたその手紙のしわを、静かに伸ばすと、もう一度、文面を読み返した。読むうちに、自然と涙が溢れ、止まらなくなった。「神のご加護がありますように」―insha Allah―と最後に書かれてあるのを見て、その言葉をムカール自身に祈りたい気持ちだった。
自分の部屋を見渡すと、9歳の時から16年もの間、可愛がってきたムカールの姿が浮かんできた。彼は幼い時から、神を信じようとしなかった。それが最後に「神」と彼が書いたことに、救われるような心地がした。
「インシャ・アッラー」か......
あの子は片腕になることで、神にすがりたい気持ちが湧いたのかな......
あの子はわしの宝石だった......
もう二度とあんな美しい子はこの世に現われないだろう......
「孤児」だなんて......あの子はきっと気高い身分の生まれだろうさ― モハメダウィのご主人も何か―感づいてなすったに違いない......
だから、あんな新聞の切抜きを大事に取ってなさったんだな......
でも、わしにはあの子は......
このホテルで調理師だった孤独な孤児のムカールのままでいい......
アルブラートは、丸い船窓のそばのベッドに横たわっていた。ベッドのそばには小さな文机と、電話が備え付けてあった。その隣にもうひとつのベッドがあった。全体に、質素な清潔な部屋だった。
アイシャは、ベッド脇の椅子に座り、アルブラートの手を握りしめ、片時も彼から離れなかった。彼は、アイシャの、成長した美しい面立ちをじっと見つめていたが、不意に、なぜ看護婦の見習いになったのかと尋ねた。
「クネイトラで、アントワーヌというフランス人の神父様に出会って、近くの教会で賛美歌を覚えて、入院している患者さんに歌って聞かせていたの。でも、シリアへのイスラエルの爆撃がひどくなって......それで、ベイルートの病院に避難したのよ。神父様は、私の身の回りを世話するジュヌヴィエーブを連れてきてくれたの。でもその後、神父様は二度と戻って来なかったわ......」
アイシャは、その後、ベイルートの空襲も激しくなったので、14歳の夏に、サイダの病院に逃れ、ジュヌヴィエーヴから看護婦の仕事を教わったと言った。彼女の口調は、12歳の時とは異なり、しっかりしていた。アルブラートは、彼女が、自分より一足先に、サイダの街に移り住んだことを知った。アイシャは、今度は、なぜサイダに来たのかと彼に尋ねた。
「俺は昔......先生に、アイシャの父さんに、将来音楽院に進学したらどうかって勧められたんだ。それで、サイダには、音楽院に入学に来たんだけど......その前は、ザハレの農園で、英語とフランス語の家庭教師をしたんだ。その謝礼に、カーヌーンを譲ってもらって......フランス語は、ガリラヤ湖畔の病院で、フランス人の先生に教わったんだ。あの病院には、16から17歳の7月までいたっけ......」
彼の頭の中を、15歳から18歳までの3年間の出来事が、走馬灯のように駆け巡った。
「アイシャ......キャンプが占領された時......俺がアイシャの手を離してしまってごめんよ......でも、あれは......赤十字の人たちがイスラエル軍に銃殺されて、ショックで気を失ったからなんだ......あの後......
俺は......イスラエルの捕虜収容所に半年間捕らえられていたんだ......そこで、ひどい熱病と肺炎になって......シリアの解放軍に救出されたんだ......」
アイシャは彼の頬に、自分の頬を押し当てて、声を立てずに泣いていた。アルブラートは、体を起こし、彼女をしっかり抱き寄せると、その柔らかな白い額に接吻し、自分でも涙を流した。
「でも......不思議だね......こうやってもう一度逢えて......俺は、アイシャのことは忘れたことはなかったよ......夢の中に何度もアイシャが出てきた......でもまさか生きているなんて思わなかった......」
アルブラートは、彼女の体の温かみを感じながら、静かに呟いた。
「ねえ......アイシャ......いつか結婚しよう」
アイシャは真っ赤になったが、強くうなずいた。
「でも今はまだ早いもの......16になったらいいわ。父さんが昔言ってたの......16になったら自由だよって―好きな人と一緒におなりって......
私の小さな時からの夢だったの―ムラートと......ムラートと結婚したいって......」
アルブラートは、それなら、来年の6月18日にアイシャが16になるまで待つと約束した。その日が来たら、白いドレスとヴェールをつけて、ささやかな式を挙げようと言った。
船がわずかに揺れたかと思うと、ゆっくりと出航し始めた。1960年7月29日午後11時だった。ムカールが船室の戸をノックして、入って来た。彼は、アルブラートに、窓からの夜景がきれいだと言った。
「アルラート。ほら、あそこが街の灯りで光っているだろう。あれは、春に一緒に行った海の城だよ。お前、あそこでカーヌーンを弾いたな―あの曲をまたいつか弾いてくれよ。この国とも、もう永久にさよならだな」
アルブラートは、彼がそばに来ると、アイシャの美しささえも、かき消されてしまうのではないかと思った。アイシャは野に咲く可憐な白い花だったが、青年は玉座であり、荘厳な大輪の薔薇そのものだった。
ムカールは彼をじっと見ると、真面目な表情で言った。
「お前―俺の手術の話、聞いたんだろう。お前の顔に全部書いてあるよ。アルラートは隠し事が出来ないんだな。でも何も心配いらないんだ」

ある日の午後、アルブラートは、自分のアパートの部屋にいた。1961年1月末だった。カイロの冬は暖かかった。雨がよく降り、そんな日は仕事場までが多少不便だった。彼の職場は、アパートから歩いて20分のレストランだった。
彼は、黒いジーンズに、黒い半袖シャツを着ていた。2部屋しかないアパートの一室の窓際に、中古のソファーを置き、その上に彼は寝転んでいた。手にした新しいラジオから、「エジプト・シリアアラブ連合瓦解の恐れか」というニュースが聞こえて来た。
「ここカイロにおいても、近頃活動の盛んになって来たパレスチナ・ゲリラグループのメンバーの取り締まりを強化する動きが強まっている」―彼はアナウンサーの緊迫した声を聴いて、ラジオのスイッチを切り替えた。すると、今流行しているウンム・クルスンムの歌声が流れてきた。
アラブ連合といえば―俺をあの収容所から救出してくれた人たちじゃないか......
あれは確かパレスチナ人解放のための連合だったのに......
結局は挫折するんだな......
おまけにカイロでもゲリラ活動だなんて......
またパレスチナ人は周囲から憎まれて厄介者扱いされるだけだ......
パレスチナという国は二度と存在できないんじゃないのか......
彼はあれこれ考えながら、ぼんやりとラジオの流行歌を聴いていた。このラジオは、彼が1月の19の誕生日に、ムカールが贈ってくれたものだった。だが急に、背後から、アイシャが彼を目隠しし、ラジオのスイッチを切った。
アルブラートが驚いて見上げると、アイシャは笑ってラジオを取り上げた。彼女は裾に華やかな刺繍のある、黒いワンピースを着ていた。
「子供っぽいことするなよ、アイシャ」
「だってもう仕事に行く時間じゃない。ラジオを聴いていたら、ムラートはいつも寝てしまうもの」
もう午後の2時だった。アルブラートは4時からレストランで演奏の仕事をする前に、ムカールと街を散歩するのを楽しみにしていた。その日は雨が珍しく上がっていた。ムカールは同じアパートのすぐ上の階に、アデルと住んでいた。
昨年の8月、カイロに着いた後、アルブラートは彼と共に、オペラ座近くのザキリスの病院に入院した。9月にはギブスが取れ、1ヶ月ほど、病院でリハビリを続け、ようやく杖なしで歩けるようになった。ゆっくり歩けば大丈夫だったが、早足で歩くと膝が突っ張るように疼いて、ひどく足を引きずった。
ムカールの手術は成功したが、その後も微熱が続いたために、ようやく容態が安定したのは、ちょうどアルブラートが歩けるようになった10月の初旬だった。そこで、ふたりは10月の中旬に、揃って退院した。
医師は、経済的に困っている若い人からは医療費は受け取らない主義だと言った。ザキリスは、二人のために、オペラ座近くの英国風アパートを借りた。また、アルブラートのために、近くの高級レストランに演奏の仕事を見つけてやった。レストランの主人はアルブラートをすぐに気に入って、月収1000ポンドで契約した。
ちょうどムカールの手術が終わって1ヶ月ほどした頃、アデルが彼に子供ができたことを告げた。彼は驚き喜んだが、退院した後、どうして暮らしていけばいいかと悩んだ。彼は医師に仕事のことを相談すると、ザキリスはそのことは前から考えていたと言った。
「あなたは語学が堪能でしょう。私の所で、書類や書簡を英語やフランス語に翻訳してもらえませんか。月収は1500ポンドお支払いします」
ムカールは喜んでその仕事を引き受けた。彼は最初、書類の整理を面倒に思ったが、慣れて来ると、仕事も早くなった。医師宛の個人的な手紙はアラビア語に訳し、外国客宛の書簡は英語やフランス語に翻訳した。
彼は英語は苦手な方だったが、アルブラートに少しずつ教えてもらいながら覚えた。医学的な用語の多い書類も、医師にその都度訊いて、別のノートにまとめながら専門用語を覚えるよう努めた。1ヶ月も経つと、医師が驚くほどに完璧な翻訳が出来るようになった。
ザキリスは、それでも、彼の術後の体力を考えて、午前の2時間と、午後の4時からの2時間だけ仕事を与えた。アデルの出産は3月頃になる予定だった。ムカールは医師のこの上ない親切に感謝しながら、子供の誕生を楽しみにしていた。
ある日、医師宛の書簡を読んでいると、こんな手紙があった。
親愛なるドクター
―先日はアテネまで来て頂き、大変感謝しております。
おかげさまで私の病気も快方に向かっております。
あなたさまは私の息子のアレクサンドルのことをご存知でしょう。 私はあの子のことを、もう20年もの間探して参りました。
あなたは先日のお手紙で、アレクサンドルではないかと思われる人に 出会ったと書かれておられました。
何の確証もございませんが、私にそれほど似ている人であれば、 ぜひその方がお元気なうちに、一目お会いしたく存じます。
1960年12月10日 オルガ・エレーナ・バシリエフスキー
その手紙はフランス語で書かれてあった。彼が読んでいると、急に開け放った窓から風が吹き込み、手紙は床に落ちた。ムカールはかがんで、その手紙を拾うと、もう一度読み直した。「人探し」をしている女性の手紙だと思ったが、その名前に何となく見覚えがあった。
オルガ・エレーナ......
確か亡命の前の晩にモハメダウィの日記帳に貼り付けてあった女性と
同じ名じゃないか―でも名字は違う......単なる偶然かも知れないな―
こういう名前はロシア系やアルメニア系に多いんだし......
彼はそれ以上深く考えずに、私書用のファイルに入れておいた。
彼は、午前中の仕事が終わると、10分ほど離れた自宅に戻り、午後の2時過ぎにアルブラートを散歩に誘いに、階下に降りて行った。
二人は最初は、高級ブティック街や官公庁街の辺りまで歩いて、ナイル川をよく眺めていたが、年が明けると、東側の旧市街に行くようになった。アルブラートは、20分ほど歩くと、足が痛むために、アル・アズハル大学構内の階段上で腰を降ろし、遠くにそびえるモスクと丘の上の城塞を眺めやった。
ムカールは、あのモスクはムハンマド・アリ・モスクだと言った。
「あれはイスタンブールのモスクを真似して造ったんだ。でもこうやって眺めると本当にきれいだな。あのミナレット(尖塔)のバランスがすごくいいよ。イスタンブール以上かも知れないな」
以前から歴史が好きな彼は、博学であり、アルブラートが知らない間に色々な本を読んでいた。アルブラートは、音楽以外の、歴史や美術関係の知識は、ほとんど彼から教わっているようなものだった。
彼はしばらく黙って、遠方のモスクを眺めていたが、急にアルブラートを振り向くと、やっぱりナイル川の方に散歩に行った方がいいかと訊いた。
「お前はここに来るのに疲れるんだろう。ナイル川ならそんなに歩かなくても済むから―こんな旧市街に来たいなんて言い出して、悪かったよ」
アルブラートは、別にどこに行ってもいいと答えたが、ムカールは、旧市街に来ると人目が気になって嫌だと言い出した。
「気のせいかな―俺が歩いていると、人が振り向いて俺を見るんだよ。なぜかな。片腕だと珍しいのかな―あまり見られると嫌になるな」
ムカールは、手術後は、今までさんざん苦しんで来た義手の腕がなくなって、かえってさっぱりしたなどと言っていた。だが、服はいつも長袖のシャツを身につけていた。
アルブラートは、どういったものかと戸惑っていたが、口ごもりながらこう言った。
「その......旧市街に来ると、かえってムカールは目立つんだよ。ここら辺は街並みも古いし......ムカールは色白で、あんまり立派だから......
人並み以上の容貌だから......だからじゃないかな」

ムカールは彼をじっと見ていたが、右腕を、座り込んだ右膝に当てて、大学構内の方に目を反らして、しばらく考えていた。
「ふーん、お前までそう言うのか。でも人間の外見なんて、大して重要じゃないよ。俺のことを、こんなで羨ましいとか言う奴は―昔からいたな。でも俺はこんな容貌のせいで、レバノンじゃひどい目に遭ったからな」
「ひどい目って......どうして?どんな目に?」
「最初は俺が16歳の時だ。客の中にイタリア人がいた。そいつはマフィアの金持ちだった。その頃はホテルが経営が苦しかったんだ。それでそいつが前の主人に、俺を売れと持ちかけたんだ。代わりに5000万ピアストル払うと言ったんだ―あの時は、主人がそいつを怒鳴りつけて、追い出したから良かったけどな」
アルブラートは、彼が人身売買の対象にされたことにショックを受けた。ムカールは淡々と話を続けた。
「俺が17歳の時に、モハメダウィが心労で亡くなったんだ。その後、あのホテルの支配人にあのザイードがなったんだ......今度はアメリカの成金とかサウジアラビアの大富豪とかが泊まりに来ると、何かと俺に目をつけて、俺を1000万ドルで売らないかと、ザイードに持ちかけるようになったんだ。あの支配人は最低の奴だから、俺にお客の言いなりになれと命令したんだ。何度も怪しげなホテルに連れて行かれそうになったな......でも、俺は客を殴り飛ばして自分のホテルに帰ったよ」
「あのホテルに戻って......支配人はなんて言ったんだ」
「『せっかくの金づるがお前のせいで逃げた』 と怒鳴って、俺を殴ったり、鞭で手首を打ったりした。でも俺は身を売るなんて、死ぬほど嫌だったから―むしろ鞭で打たれた方がましだったな......そういうことから、あのザイードとはしょっちゅう喧嘩ばかりするようになったんだ......俺は身を売るくらいなら死んだ方がいいと何度も思ったな......あのホテルを逃げ出そうと何回も思ったんだ」
「なんで......なぜ逃げださなかったんだ―そんな目に遭っていて―」
ムカールは彼を再び見つめると、溜息をついた。
「......ヨシュアがいたからかな......俺を9歳の時から、前の主人と一緒に可愛がってくれて......17歳で前の主人が亡くなってからは、俺の体をいつも心配してくれて......とにかく、俺は、人の容貌に目をつけて......金の対象にする奴がいることを知ってから、自分のことを誉められてもあまりいい気分はしないんだ。人間に大事なのは外見じゃないからな」
アルブラートは彼の話を聞いて、何とも答えようがなかった。確かに人間は外見で判断できないが、人は美しいものを愛する心を持ち、また神に愛でられるほど美しい人もごく稀に存在する―そう思った。だが周囲から賛嘆されるほどの美貌も、当の本人には苦痛のもととなる―そういう場合もあるのだと気がついた。
母さんだってそうだったじゃないか......
母さんはあまりに美しかったから......司令官の愛人にされて......
結局は陵辱を受けていたんだ......
ムカールは弄ばれる前に相手を殴って逃げることができた......
でも......母さんはそんなことはできなかったんだ......
アルブラートが黙りこくっていると、ムカールは笑って彼の肩を叩いた。
「お前が俺のことを誉めたのは、ありがたく思っているよ。アルラートがさっき言ったことは、純粋な好意からだって分かっているから、気にするなよ。誰でもそれなりの魅力があるって言いたかったんだろう。それを言うなら、アルラートの魅力には、俺は負けているな」
急に彼から誉められたアルブラートは、驚いて彼を見つめた。
「まさかそんな―冗談だろう。だって俺は浅黒くって―いいところなんて何もないよ」
「そんなに自分を卑下するなよ。お前は本当にきれいないい目をしてるよ。アイシャがお前を見ることができたらきっと驚くさ―6月に結婚するんなら、その前に一度あの娘をドクターに診せたらどうだ。もしかしたら目が見えるようになるかも知れないじゃないか」
アルブラートは、ムカールからこう言われるまで、なぜそのことを考えなかったのだろうとふと気がついた。彼はアイシャが目が見えるようになったら、どんなに素晴らしいかと思い、わくわくしながら立ち上がった。腕時計を見ると、もう午後の3時だった。二人はオペラ座の方へ戻り始めた。
「そうだ......本当に―なんで気がつかなかったんだろう......
明日にでも、先生にお願いしてみるよ」
「いや、俺が今日ドクターに話しておくよ。これから仕事なんだから」
翌日の朝9時に、アルブラートはアイシャを連れて、医師のもとを訪れた。ザキリスは、彼女の目を診察すると、こう言った。
「生まれつき見えないと言われて来たそうですが―そういう人はごく稀です。今診たところでは、アイシャは違います。1歳の頃に熱病を患った痕跡がありますが、そのためでしょう―角膜を移植してみましょう。きっとそれで見えるようになると思いますよ」

アイシャの目の手術は、2月の中旬に行なわれることになった。彼女はアパートに帰ると、手術が怖いと言ったが、アルブラートはアイシャを励まし、絶対に手術は成功するからと言い聞かせた。
「アイシャは生まれてからずっと暗闇の中だったんじゃないか。それが今度は何でも見えるようになるんだ―素晴らしいじゃないか」
アイシャは不安そうに彼に抱きついた。彼はソファーに座ると、彼女の艶やかな黒髪を何度も撫ぜて、その細い体を愛おしそうに抱きしめた。彼が寝転ぶと、彼女の長い髪が、彼の頬にさらりとかかった。
「でも......本当にそうね。今まで手の感触でしか、ムラートを知ることがなかったんだもの......今度から、本当にムラートを見ることができるようになったら......私、最高に幸せよ」
ザキリスは、昨年の夏にムカールの手術をし、退院してからも、週に1度は彼の診察を続けていた。術後、半年ほどは特に問題もなく、手術は成功したかに見えた。だが、年が明けた2月の初めに、いつものように診察をすると、予見もしなかった症状が現われていることを発見した。
それは敗血症だった。ザキリスは、青年の血液検査により、白血球の異常な増加を見い出した。彼は、これにより、青年の命があと半年も持たないのではないかと危惧した。
彼は度重なる壊疽で......
免疫力が著しく低下している......
このままでは肺や胃に壊疽が広がるのも時間の問題だ......
それで敗血症のショック症状を起こしたら―あらゆる手立てを尽くしても ―患者の4人に一人は死亡することは疑いない......
医師は、このことをムカール本人にいきなり告げるのはとてもできないと悩んだ。普段は明るく、仕事熱心であり、3月に子供の誕生を待ち望んでいる彼には告知できないと思った。かと言って、出産を控えた妻であるアデルに話すこともできなかった。
青年が、一度だけ、亡命の前夜に、「死が間近に迫っている」と恐怖の念を露わにしたことを考えると、このことを誰に告げたものかと苦しんだ。彼は、青年の一番の友人であるアルブラートに話すしかないと思った。だが、人一倍感じやすいあの若者には、何と話したら良いのかと思い悩んだ。
アイシャの目の手術が2週間後に迫ったある日だった。アルブラートはいつものように、朝の9時から自宅近くのレストランに仕事に出かけた。レストランのオーナーはエジプト人だったが、パレスチナ人には寛容で、親切な人だった。アルブラートのウードやカーヌーンの旋法は、常にその場の雰囲気や、彼の頭の中に蓄積されている数限りないイメージや霊感で、微妙に変化した。
アルブラートは、昔育って来たキャンプの遺跡のイメージや、アイシャの歌声に霊感を受けて演奏することが多かったが、カイロに来てからは、ムカールの美しさを曲に託すことが多かった。彼は、ムカールのことを考えると、宝石の散りばめられた玉座や、広々とした神殿や、一緒に眺めた地中海や、彼の黒曜石のような目の輝きが頭に浮かんだ。
ムカールがその美しさのために......
屈辱を受けそうになったとしても......
彼はまさに美のために生まれて来たんだ......
どんな芸術でも表現できないほどの美を持って―
あの大理石のような―生きた彫刻のような美を音楽に再現して―
そして昇華する......それが俺の仕事なんだ......

アルブラートの音楽は、青年の存在によって、ますます完成度を高めていったが、アイシャの賛美歌をアパートで聴くようになってからは、さらに従来のアラブ音楽にはない、新鮮な旋律が織り込まれた。彼女のラテン語の歌声は、彼に中世ヨーロッパの息吹を吹き込んだ。
彼の演奏は、常にドラマティックであり、悲劇的な哀愁と繊細と力強さのタペストリーだった。レストランのオーナーは感極まって、こんなに感動的で完璧な演奏は聴いたことがないと言った。
「君の演奏は実に詩的で―もう言葉では表現できないほどだ。中世ヨーロッパだったら、ミンストレル* に召抱えられるほどの腕前じゃないかね」
アルブラートはそれを聴いて、内心、自分はもう王侯貴族に仕えているようなものだと思った。その王侯貴族とは、ムカールに他ならなかった。
彼は、少し考えていたが、自分の婚約者にアイシャという娘がいることを話した。彼女の歌声を一度聴いてもらいたい、そして彼女と一緒に舞台に立ってみたいと話した。オーナーは、その話を快く承諾した。
12時に仕事が終わると、外は雨がまた降っていた。雨が降ると、すぐにカイロの街は歩道が水浸しになってしまった。アルブラートは傘を差していたが、勢いよく流れる泥水に足を取られ、怪我をした右足が重くなり、ほんの10分歩いただけでくたくたになった。
歩道の右側を見ると、ちょうど喫茶店があった。彼は助かったと思い、店の扉を開けた。店内は薄暗かった。彼が足を引きずりながら、空いている席に座ると、いきなり銃口が向けられた。
アルブラートはギョッとしたが、よく見ると、その銃を突きつけているのは、まだ12歳ほどの少年だった。店の奥から、男の声がした。
「ジャハール、大事なお客だ。銃を引っ込めな」
23歳ほどの青年が、コーヒーを入れ、彼のテーブルに置くとこう言った。
「ここはパレスチナ人だけの店だ。あんたもパレスチナ人だな」
アルブラートがうなずくと、相手は笑って、同胞に会えて嬉しいと言った。彼は、イブン*・ムハンマッド・アル・ザクルと名乗り、ここのオーナー兼リーダーだと切り出した。
「俺たちは皆難民キャンプで育ったんだ。親兄弟はみんなイスラエルの奴らに殺された。俺たちはカイロ大学で学んでグループを作ったんだ。『聖戦の獅子』だ」
「何......何が『聖戦の獅子』なんだ。何をするんだ」
「何って、決まっているじゃないか。ゲリラ活動をするんだ。エジプト・シリア連合だってダメになったじゃないか。もう周辺のアラブ諸国は当てにならない。俺たちでイスラエルを叩きのめして、俺たちだけの国を造るんだ。そう思って俺たちは結集したんだ」
* ミンストレル:minstrel 王侯貴族の宮廷に上がって演奏する楽師
* イブン:Ibn アラビア語で「息子」の意。
●Back to the Top of Part 9
© Rakuten Group, Inc.






