砂漠の果て(第14部「碑文」)

ムカールはこの2日ほどで、すっかり窶れ果てていた。頬は落ち窪み、髪はくしゃくしゃに額に乱れかかっていた。目の周りには、隈ができ、その黒い瞳は死が間近に迫った人特有の、ギラギラした光を放っていた。
だが、その目に恐怖の淵から這い上がりたい、救いを求めようとする表情を見て取った医師は、彼の変わり果てた面立ちに、思わず涙ぐんだ。
「私はあなたに申し上げる言葉がありません......私は、あなただけは何としてでも助けたかったのです......あのご夫人が捜し求めておられたご子息は、あなただったのですから......カイロに亡命する晩、あなたに私はお約束しましたね―『あなたを絶対に死なせません』と―私は罰を受けても当然です」
ムカールは、やがて訪れる死の瞬間には、再びあの父王の亡霊が自分を連れ去ろうとするのだろうと思い、慄いていたが、悄然としているザキリスを見て、大きな哀しみが胸に迫ってきた。
この人ともやがて別れなければならない......
この人は俺たちの命の恩人なんだ......俺たちを亡命させて―アルラートと俺を手術してくれて......アイシャの目を治してくれて......アザゼルを誕生させてくれて......母さんに俺を会わせてくれたんじゃないか......
「......先生が罰を受けることなど......あり得ません......私は先生にどんなに感謝していることか......せめて......私の死後は......アデルと娘を......どうか......」
だんだん息遣いの荒くなってきたムカールを制止するように、医師は彼の右手を握ると、首を振り、しばらく休むように言った。
「無力な私がこんなことを申し上げるのも......おこがましい限りですが......死は怖ろしいものではありません......どうぞ神の御許に抱かれることをお信じになって下さい」
神......神は本当に存在するのだろうか......俺を苦しめてばかりいる神......そんなものはいやしない......
「......私には......何も信仰など......ありません......」
「それでも......あなたがこの世に生まれ、存在し―今まで生きて来られたのは神のご意志ではないでしょうか......あなたの心に神は必ずおられるはずです......どうぞ天の楽園に導かれることをお考え下さい―アデルと娘さんのことは何のご心配もいりません」
ムカールは、ほんの10分ほどの医師との会話が息苦しくてたまらなくなったが、消え入るような声で、すがるようにザキリスに請い願った。
「......先生......最後のお願いです......どうかアルブラートを......アルブラートの心を救ってやって下さい......」
「......大丈夫ですよ―あなたの大切な人たちを、私は力を尽くしてお守りします......さあ少しお休みになって下さい」
ザキリスは、青年が再び眠りについた様子を見守りながら、アルブラートのことを考えた。ムカールが死の瀬戸際まで、あの少年を心配していることに心を痛め、また、二人の間には、いかに重苦しい告白と受容の時間が流れたことかと考えると、アルブラートの苦しみを今度は自分が共に背負うことは、荷が重過ぎると感じた。
午後になり、再びムカールが目覚めると、そばにアルブラートが腰掛け、彼をじっと見つめていた。少年は、ムカールの灰色に蒼ざめた顔色を見て、医師の言ったとおり、青年に死が近づいていることを真に悟った。ムカールは彼の不安と悲哀に満ちた、怯えるような瞳を食い入るように見入り、アルブラートはもうすべてを知っているのだと思った。
「......アルラート......仕事はしないのか」
「指が動かなくなってしまったんだ......もうだめだよ」
「......指が―動かない......?」
ムカールは右手をアルブラートの方へと震えながら伸ばした。アルブラートは自分の右手で、彼の手をそっと握った。青年の手は白く、長年の調理場の仕事で荒れていた。だがその手は温かく、包み込むように大きな手だった。
「......なんだ......動くじゃないか......お前―演奏家だろ......
仕事しなきゃな......」
「それがだめなんだ......楽器を弾こうとすると―指がこわばって......」
アルブラートは、三年前の春頃にも、同じような症状に陥ったことを思い出した。あれは母の死後、救出されたガリラヤ湖の病院で、楽器が弾けなくなったのだった。
「アルラート......必ずお前の指は治るから......お前は将来は......
ヴァイオリンやピアノまで一流になるからな......心配するなよ......それより―今夜は―ここに泊まっていってくれないかな......」
「俺が病院に......?構わないけれど―なぜ......?」
ムカールは再び息を切らしながら、苦しげに言った。
「......夜になったら......ゲオルギオス2世の......死霊が現われるんだ......それで......恐ろしい力で......俺をどこかに......どこかに連れていこうとするんだ......お前がいてくれたら......きっと......そいつは逃げ出すから......」
アルブラートは、ムカールが熱に浮かされて夢でも見たのだろうと思ったが、医師に頼んで、その晩は簡易ベッドを用意してもらった。ムカールはそれから点滴を受けたまま、昏々と眠り続けていた。アルブラートはいつ青年の息が途絶えるかと心配でたまらず、病人を見守り続けたが、夜の12時を回ると疲れ切ってしまい、ベッドに横になり、うとうとし始めた。

だが、彼が寝入って間もなく、そばに誰かがいる気配で目が覚めた。真っ暗な病室の中で、ムカールのベッドのそばに、王冠を戴いた人物が静かに立っていた。その男性の周りは白く輝く光に包まれていた。アルブラートはどこからともなく響く低い声を耳にした。
「......お前はまだこの世に未練があるのか......アレクサンドル......さあ......私と一緒に長い旅に出かけるんだ......」
アルブラートはぞっとしたが、亡霊が青年を抱きかかえようとしているのを見て、思わず叫んだ。
「ムカールを連れて行くな!その人はアレクサンドルじゃない!」
亡霊は、青い目を見開いて、少年を見た。
「......ムカール......?これは私の息子のはずだが......野蛮なアラブ人め......怨霊に成り果てた私をみくびらぬことだ......まあいい......明日こそは必ず息子を連れて行くぞ」
亡霊の放つ光は、部屋中に大きく広がったが、そのうち霞のように消えてしまった。アルブラートはその間中、恐怖で体が動かなかったが、ギリシャ王の姿が消えると、息詰まるような空気が急に静かになるのを感じた。
怨霊だって......?なぜギリシャ王がそんなものに......?正式に息子を王室に迎え入れられなかったことに恨みがあるのか......?それとも―モハメダウィが真実を察しながら、ムカールを王室に返さず、アラブ人として育てたことが恨めしいのか......?アラブ人のどこが野蛮なんだ......一体どこが悪いんだ......
俺が悪事を犯して......ムカールに頼り切っていたことを王は憎んでいるのかもしれない......神聖な息子が穢れると......それなら俺は―ギリシャ王の怨霊に八つ裂きにされるな......それでも―もう構わない......
翌朝、アデルが看護婦に付き添われて、アザゼルと共に病室を訪れた。アイシャも一緒だった。やや遅れて、遠慮がちに、オルガ・エレーナも見舞いに訪れた。ムカールは、大公妃を見ると、辛そうに目を反らした。自分が別人のように窶れた姿を、母に見せたくなかった。
オルガは、ほんの数日前は大理石のように美しかった青年が、頬がこけ、痩せ細り、死を待つばかりの様相を見せていることに衝撃を受けた。彼女は泣くまいとしていたが、目に溢れた涙は知らぬ間に彼女の頬を伝って流れ落ちた。
「......あなたは私を母と確信なさっておられると......そうアルブラートからお聞きしました......私は、あなたをアレクサンドルとお呼びしてもよろしいでしょうか......」
ムカールの声は絶え入るようで、今にも消え入りそうだった。
「......構いません......先日は......申し訳ないことをしました......」
「こんな時になって―アレクサンドル......あなたをそうお呼びできるなんて......こんな時に......」
大公妃は、おずおずと何かに怯えているような、哀しげな表情のアデルを振り返り、彼女の手を取った。アデルは恐ろしいものを見るように、ムカールの顔を覗き込んだ。彼の窪んだ、青黒い目の淵や、元気だった時とは打って変わった目の濁った光に、彼女は震えながら後ずさりした。
「......アレクサンドル......あなたにもしものことがあった後は......奥様とお嬢様を、エレヴァンの私の別荘にお迎えしたいのです―奥様には、先ほど、ご承知いただきました......あなた方ご一家に、アルメニアの国籍をお贈りしたいのです」
「......そうですか......でも......ギリシャではなく......なぜアルメニアに......」
「ギリシャは現在、王政反対派が常にクーデターを起こし、政情が非常に不安定ですし......私は故ギリシャ王の正式の妻ではなかったからです......かと言って、現在アルメニア大公とは幸福な結婚生活ではありません......あの方は冷たい方で―私はエレヴァンの郊外に―独りで住んでいるのです」
「......わかりました......お母様にすべてをお任せします......」
じゃあ俺は―アルメニアに葬られるんだな......でも......あの王の亡霊は......俺をギリシャの墓地に引きずり込もうとしている......俺は死んでも......落ち着く場所がないな......
彼は、アデルを呼んだ。アデルは頬を濡らしながら彼のそばに跪くと、痩せ衰えた彼の手や頬を震えながらさすった。ムカールはいつものように、彼女の髪を撫ぜようとしたが、手を動かす力さえ萎えていた。
アルブラートは、部屋の外に出ると、医師に、昨夜ギリシャ王の亡霊が現われたことを話した。ザキリスは驚き、不思議がったが、長年行方不明になっていた息子をオルガ・エレーナが探し出したことで、故ギリシャ王が霊界から姿を見せることもあるのかもしれないと思った。
「先生......ギリシャ王は―『明日こそは息子を連れて行く』と言っていました......それが本当なら......今夜ムカールは危ないのではないでしょうか......」
ザキリスは、最後まで最善を尽くすと約束した。だが、その晩10時頃、ムカールの吐血が突然始まった。
青年は全身を震わせながら、苦しげに大量の血を吐いた。たちまちシーツが赤く染まった。その発作の激しさに、そばにいた人々は慄き、思わず顔を覆った。室内に広がる血の臭いに、アデルは卒倒しそうだった。医師は、看護婦に、皆を別室に連れて行くよう指示した。
「早く......!早くたらいとシーツを用意しなさい―アルブラート、早くこの部屋を出なさい!」
ムカールの背をさすりながら、ザキリスは少年に叫ぶように言った。だがアルブラートは、凍りついたように、病人の血にまみれた口元を見つめて動かなかった。アイシャがいきなり、彼の腕を引っ張ったために、二人とも床に転んでしまった。
「馬鹿ね......!ムラート......立ち上がってよ!」
彼女は乱暴に少年を引っ張り起こすと、アデルたちとは別室に彼を連れて行った。そこは誰も使っていない病室だった。アルブラートはそこのベッドに座り込むと、顔を覆い、震える声で呟いた。
「......母さんが苦しんで......死にかけてる......早く楽にしてやらないと......」

向かいの椅子に腰掛けたアイシャは彼が混乱していると思い、その肩を揺さぶった。
「どうしたの......?あそこに寝ているのは―ムカールよ......!」
「......早く銃を持ってくるんだ......早く撃ってしまわないと......」
「ムラート......!何を言ってるの......一体何があったの......?」
アルブラートは真っ青な顔を上げると、アイシャを大きな黒い眼でじっと見た。そのこわばった表情は、アイシャの知っているアルブラートではなかった。彼女は何か恐ろしいものを感じ、彼から手を離した。
「母さんがあそこで死んでいる......口から血を流して......俺が撃ったから......銃で......俺が殺したから......」
アイシャはぞっとし、震える唇を噛み締めた。今の彼は混乱しているのではなく、まったくの正気であり、真実を話しているのだと気がついた。彼女は、彼の母マルカートについては何も尋ねまいとしてきたが、もう黙ってはいられなかった。
「......ムラート......マルカートは......病死じゃ......ないの?今......あなたが言った通りなの......?あなたが―お母さんを......銃で......撃ち殺したの......?」
「三年前の1月に......イスラエル軍の命令で......母さんを銃殺したんだ......遺体はナザレの雪原に埋めた......だから―誰にも分からない......でも......アイシャには―もう分かってしまったな......」
アイシャは、難民キャンプで育った約十年間、アルブラートがどんなに母親を大切にし、深く愛していたかをよく理解していた。その彼が、母を自ら手にかけたという事実を知り、気が遠くなりそうだった。
キャンプの占領後、互いに行方不明になり、昨年の夏、再会できた後も、アルブラートには何か深い心の傷があり、彼が「捕虜収容所で地獄を見た」となぜ語ったのかが、今こそ彼女には明瞭となったのだった。
彼の苦悩が、今度は彼女の苦悩となり、アイシャの魂の奥深くに重い鎖となって食い込んできた。彼女は震えながらも、真っ直ぐに彼を見つめた。
「......嘘じゃないのね......そういう話は......クネイトラで聞いたことがあるもの......でも―あなたが苦しいのなら―私も一緒に苦しむから......ムラートには何の罪もないもの......独りで悩まないで......」
「......いや......アイシャに話すのなら―その時は―もう終わりだと決めていたんだ......アイシャ......もう―別れよう......」
アイシャは椅子から飛び降りるように、彼の足元に跪くと、その膝に身を投げ、泣き出した。だがすぐに彼を見上げ、その胸を抱きしめた。
「......だめよ!私......別れたくない......!私はムラートのそばに一生いるわ......あなたがたとえどんなに悪人でも......それでも―あなたとずっと一緒にいるわ......!ムラートを愛しているから......愛しているから......!」
アルブラートはアイシャを強く抱きしめると、彼女の長い豊かな黒髪に顔を埋めた。彼は、母に似たムカールが吐血で苦しんでいる姿と、三年前、銃殺した後の母の冷たい遺体とが交錯し、正気を失っていた自分に気がついた。彼も涙声になり、アイシャの髪に幾度となく接吻しながら呟いた。
「......俺もアイシャを愛している......愛しているアイシャを穢したくない......だから別れるしかないと思ったんだ......でも俺だってアイシャと別れて生きていけない......アイシャ......ごめんよ......苦しめて―」
「穢れている―あなたが罪で穢れているというの......?ムラートは穢れてなんかいない......!あなたは何の罪も犯していない......!イスラエル軍は悪魔よ......!今でもパレスチナ人は捕らえられたら―男の子には銃を持たせて家族を殺せと命令する―女の人は......さんざん陵辱されて―殺されるのよ......だから私......私は......」
アイシャはもうすぐ16になる少女とも見えなかった。その眼にイスラエルへの憎悪が満ち、声もやや低くなり、口の利き方も毅然とし、すっかり大人の女性になったかのように見えた。アイシャが何かをアルブラートに告げようとしている時、二人を探していた看護婦が、ムカールの発作が治まったことを知らせに来た。
「モハメダウィ様は、意識はおありですが、今のひどい発作で、もうお話はできません。視力も落ちておいでです―病室にお早くお戻り下さい」
二人がムカールの部屋に戻ると、既にアデルとオルガがベッドの側にいた。ついさっきの激しい吐血が嘘のように、シーツは真新しいものと交換され、病人の手や口元の血もきれいに拭い取られていた。だがムカールはもう点滴を受けておらず、酸素マスクもつけていなかった。
アルブラートは側に寄り、彼の名を呼んだ。ムカールは声のする方へと僅かに顔を傾け、少年にかすかにうなずいて見せた。彼の宝石のようだった瞳には、かつてのような輝きは既に消え失せていた。
ムカールはアルブラートの将来を心配するかのように、しばらく少年を見つめていたが、アルブラートの姿の輪郭はぼやけ、よく見えなかった。彼は今度は、「アレクサンドル」と必死で呼ぶオルガの方を向いた。母が自分の右手を握る感触に気がついたが、母を見るのが辛くなり、眼を閉じた。
最後に彼は、アデルのか細い声を聞いた。アデルの顔はもうほとんど見えなかった。アデルに抱かれたアザゼルは、父を慕うような甘えた声を出し、小さな手を彼の方へと伸ばした。ムカールは涙を流し、娘の方へと手を伸ばしかけたが、もはやその手もまったく動かなかった。
突然、彼は最期の断末魔に襲われた。ムカールは喘ぐように激しい息をつき始め、額が汗でぐっしょりと濡れた。しばらく病人の苦しげな吐息が静かな病室に響いたが、ムカールは最後に深く長い息を吐いた。すると、たちまち何もかも動かなくなった。空気の流れさえ止まってしまったかのようだった。
皆、一瞬何が起きたのか理解できなかった。だがアルブラートは静まり返った薄暗い室内に、再び凍るような霊気を感じた。ムカールの体から、ムカールの姿が白く輝く眩しい光に包まれて浮き上がり、それは病室の窓から外へと流れて行った。
「......ようやく終わったか......アレクサンドル......もう苦しまなくて良いのだ......私の王国で......今度こそお前は玉座につくのだから......」
それは、昨夜聞いたゲオルギオス2世の声だった。
あのギリシャ王の怨霊が現われたために......ムカールの生気が魔界の力で吸い取られたのか......何て恐ろしい......
ザキリスは青年の脈をとり、首を振った。医師は、ムカールに向かい、静かに十字を切った。
「......お亡くなりになられました......」
1961年4月28日午前0時15分だった。ムカールがアデルと挙式してから僅か1週間後のことだった。

アデルはムカールに取りすがり、何回も彼の名を呼んだ。
「ね......ムカール......嘘でしょう......?いつもの......冗談なんでしょう......?お願いだから―早く目を覚まして......」
応答は無かった。だがアデルは、いつものように彼の頬を両手で包み、その額に接吻した。彼女はムカールの体が徐々に氷のように冷たくなるのを感じると、床にくずおれ、激しく泣き伏した。
アデルの沈痛な泣き声は、小さな病室を重苦しい空気で満たした。オルガは涙を流しながら、息子の髪を何回も撫ぜていた。彼女は20年間、懸命になって一人息子を探して来た自分の人生を振り返ると、何もかもなし崩しに消え去ったように思えてならなかった。
アイシャも青年の死という現実にショックを隠せなかった。ムカールが昨年の夏、病院まで高熱を出しながら、自分を迎えに来たことを、彼女は深く悔いた。彼女もアルブラートにすがりながら、嗚咽が止まらなかった。
だがアルブラートは眼の前で起きた出来事が、とても信じられなかった。彼はただ一人、涙を流さなかった。ムカールの魂は、また戻ってくると思い、その場に立ち尽くしていた。青年の姿を脳裏に焼き付けようとしているかのように、彼はムカールの顔をいつまでも見つめていた。
アルブラートは、ベッドから垂れ下がっていた青年の右手を黙って握り締めた。ムカールもまた、いつものように握り返してくれると信じて疑わなかった。だが何の反応もなかった。青年の手は既に硬直が始まりつつあった。アルブラートは、彼の手を静かに、微動だにしない胸にそっと置いた。
それから何時間、何日が経過したのか分からなかった。アルブラートは、気がつくと、たった一人で青年の棺の前の椅子に腰掛けていた。ムカールの遺体には、胸まで薄い衣がかけられ、その回りを華やかな花々が埋め尽くしていた。青年は眠っているように見えた。だが、生きた花に囲まれた彼の顔は、既に亡くなった人そのものだった。
外は薄暗く、部屋の隅に小さな明かりだけが灯され、亡者の顔をかすかに照らし出していた。アルブラートは、夕方なのか真夜中なのか、全く分からずにいた。これから自分は何をすればいいのか、見当もつかずにいたが、ふと、青年の死後、医師からオルガ・エレーナの手紙を受け取ったことをぼんやりと思い出した。
―アルブラート・アル・ハシム様
あなたが「ムカール」と名乗っていた私の息子アレクサンドルの最愛の友であることは、充分理解しております。私は、夫のバシリエフスキーに、あなたが素晴らしい音楽家であり、息子の大切な親友であったことを何度も説明致しました。ですが、夫はアラブ人に偏見を持った人です。特に、あなたがパレスチナ人であることを毛嫌いし、葬儀の最中にテロを起こされては大変だと言うのです。
息子の妻であるアデルをも、夫は「アフリカ人などが葬儀に参列することは許さない」などとなじるのです。どうか、バシリエフスキーのこんな乱暴な無教養な発言をお許し下さい。いつか私はあなたとアデルが息子の墓を訪れることができると信じております。
1961年4月29日 オルガ・エレーナ・バシリエフスキー
彼は、その短い書簡を受け取ったのは、今朝だったのか、昨夜だったのかはっきりしなかった。ただ、ザキリスが「ムカールの葬儀はエレヴァンで、5月1日の朝に」と言ったことは記憶に残っていた。
アルブラートはゆっくり立ち上がると、部屋のカーテンを少し開けてみた。街はまだ賑やかに活動しており、夕焼けがカイロの街を赤く染め、アザーン*
の祈りの声がいつものように耳元まで響いてきた。
彼は、その声がいやに大きく聞こえ、耳障りに感じた。遠くを眺めると、いつかムカールが感嘆した城塞のミナレットがライトアップされている光景が見えた。アルブラートは宝石を散りばめたような、見事なカイロの夜景が虚しかった。
いくら美しいミナレットでも―死んだら何もならない―俺はあの光景を見ることができる......でもムカールはもう何も見れない......話すことも―笑うことも―音楽を聴くことも―もう何もできない......
アルブラートはカーテンを閉め、再び棺の前に座り直した。漠然と、今は4月29日の夕方なのかと考えた。彼は、オルガから託された手紙の内容を思い返すうちに、激しい憤りと哀しみが込み上げてくるのを感じた。
アルメニア大公というのは本当にアルメニア人なのか......迫害と虐殺の歴史を生き抜いた人ではないのか......
パレスチナ人は―イスラエルからは敵視され......
他国の人々からは「テロリスト」としか思われない......
でも人は―自分の生まれてくる国や民族を選べないんだ......
パレスチナ人なんて―「ゲリラ」や「テロリスト」の代名詞じゃないか......
ムカールの葬儀にも参列できないなんて......
もう俺は―パレスチナ人であることを止めてしまいたい......!
* アザーン(adhan): イスラムの礼拝の刻限を知らせる呼びかけ。モスクの塔の上などから、肉声で朗詠する。

だがアルブラートは、ほんの1週間ほど前、青年から婚礼衣装を贈られたことを思い出した。その時ムカールは、「誇りを持ってパレスチナ人の伝統を受け継いでいってほしい」と言ったのだった。
あの時、婚礼衣装を着て見せたっけ......
そうしたら、ムカールは「これが見ておきたかったんだ」と言っていた......
もう彼は、自分でも分かっていたのかもしれない―6月の俺の結婚式には出席できないと......
彼は、己の民族性を否定する心を、青年の遺した言葉で打ち消そうとした。棺の中に眠るムカールを見つめていると、彼と初めて出逢った雨の日や、一緒に馬車に乗り、音楽院や地中海を見に行ったり、共に暮らしたサイダのホテルでの日々が浮かんでは、また消えていった。
また、エジプトに亡命し、カイロの街を散歩し、共に語り合った日々―自分の忌まわしい過去を彼に打ち明けた日のことをも思い浮かべた。
あの時は苦しかった......それでも彼は俺を受け入れてくれた―俺の罪の意識を必死で否定してくれた......
あのことは彼にだけ話すつもりだった......でもアイシャにも告白してしまったんだな......
アルブラートは、ムカールに苦しい過去を話すことで、逆に青年をどんなに悩ませたことかと悔やまれた。自分はムカールの存在に頼り切っていたのだと思った。ムカールが死んだ今、今度はアイシャに打ち明けたことを考えると、自分の罪業の念が再び鋭いメスで切り開かれ、醜い膿が彼女の方へと流れていくような恐怖に身震いした。
なぜアイシャに話してしまったんだ......
アイシャも俺には「罪がない」と言ってくれる―それでもあの怖ろしい経験は俺の頭から消えないんだ......俺は自分の苦しみを人に告白して―その人の苦悩を土台にすることでしか生きていけないのか......
彼は青年の死への哀しみと、アイシャへの告白を後悔する気持ちとの間で、もがき苦しんだ。この苦しみから立ち直り、再び楽器を手に取り、演奏できるとは到底思えなかった。
彼は深い溜息をつきながら、うなだれ、両手で頭を抱え込んだ。するとその時、ズボンのポケットに肘が触れ、何か紙片が入っていることに気がついた。
ポケットから取り出してみると、それは、ムカールが挙式の日に、彼に依頼したポール・エリュアールの詩と、自分の贈った詩篇だった。これらは、ムカールのアパートの机の引き出しに入っているはずだった。アルブラートは、いつの間に、どうやってこの二つの詩篇をポケットに入れたのか、全く覚えがなかった。
彼は、独りで棺の前にいる今この時を、ムカールと共有する最後の時としたかった。今を逃しては、自分だけで青年を追悼することはできないと思った。
アルブラートは、棺の中から白い薔薇を一輪、そっと抜き取ると、二つの詩篇を一緒に重ね、端から細かく折り畳んだ。それを薔薇の茎に丁寧に結びつけると、他の花々の下の方に、目立たないように差し込んだ。
だが腰を椅子に下ろそうとした時、ポケットから別の紙片がカサリと床に落ちた。拾ってその紙を広げた途端、ムカールの筆跡が目に飛び込んできた。それはムカールが彼に宛てて書いた手紙だった。
―この手紙を君が読むのは、きっと私が死んだ後でしょう......私がただの冷たい亡骸になっても、どうか悲しまないで下さい......
アルブラートは、この手紙の日付を見て、ムカールが、婚礼の2日後に遺書を書いていたことにショックを受けた。彼は、青年が自分の死を予感しながらアデルと挙式し、レストランの演奏会に来て贈り物を届け、そして母親と対面したのだと思いながら、何回も遺書に目を走らせた。
次第に、ムカールの書いた文字がぼうっと霞んできた。涙がしたたり落ち、故人の筆跡を滲ませた。アルブラートは青年の遺書を手にしたまま、棺の中の友人の顔を見つめた。低い呻き声が、喉から絞り出された。彼は目をつぶり、肩を震わせ、逝ってしまった友の前で泣いた。
こんなに......こんなに俺のことを心配してくれていたのか......壊疽に冒されて......死の恐怖に慄いていたんだろうに......いつも陽気に振る舞ってたな......もう一度あの口癖を聞きたいよ......「俺は馬鹿だな」って......俺は最近言ったっけ―「そんなの聞き飽きた」って......こんなことになるなんて思わなかったよ......俺の方が大馬鹿だよ......ムカール......
それから数時間が過ぎた。ザキリスと二人の看護婦が部屋に入ってきた。医師は、棺の前で項垂れて座り続けているアルブラートに、今夜は自分の家で休むようにと勧めた。
「もうこれで最後のお別れをして下さい―ご遺体を安置所に移しますので」
アルブラートはゆっくり立ち上がると、青年の顔をじっと見つめ、胸に置かれた彼の右手を握った。その手は石のように硬く、ナザレの荒野の深い穴のように冷たく凍っていた。看護婦が、緑色のシートを棺の上に被せた。白いベッドの上に置かれた棺は、こうしてアルブラートの目の前からどこかに行ってしまった。

アルブラートはひどい疲れを感じた。ふと目の前を見ると、アイシャがいた。アイシャは、彼に、「ムラートはもう2日間も何も食べていない」と言った。彼は、アイシャに母の死の真相を告げ、その後、ムカールが亡くなったことが、遠い昔のように思えた。
アイシャは彼を食卓に連れて行った。そこには、ザキリスと夫人のザカートがいた。ザカートは、アザゼルを抱いてあやしていた。彼女は、食事をとるようにと彼に勧めた。だがアルブラートは黙ったまま、食事に手をつけようとしなかった。
「アルブラート、食事をして下さい。あなたは、あの部屋に2日間も座りっぱなしだったんですよ......それから、ぐっすり眠らないと―アイシャは二晩、私の家に泊まりましたが......彼女は、あなたのことを心配していてね」
医師がこう言うと、アイシャが続けて話した。
「ムラート、アデルはアザゼルとオルガ夫人と一緒に、明日の朝、エレヴァンに発つ予定だったのよ......それなのに、今日のお昼から行方不明になってしまったの......部屋に書き置きを残したままで」
アルブラートは夢から覚めたように、驚いて彼女を見た。
「行方不明......?アザゼルを残して......?」
アイシャは、彼にアデルの走り書きを見せた。
―私はオルガ様とご一緒に、住み慣れたアラブの国々を離れ、見知らぬ異国に行こうとしていました。でも、アルメニアでは政治的にも実権を握っているというバシリエフスキー大公が、私のムカールの葬儀への参列を許しません。
オルガ様は、私を本当の娘として迎えたいとおっしゃって下さいますが、私は大公の目を怖れながら暮らしていくのは耐えられません。アザゼルと二人だけでカイロに暮らしたいと思いましたが、この娘はオルガ様にとって、ムカールの大事な忘れ形見です。
アザゼルと別れるのは辛くてたまりません。けれども、もう他に方法がないのです。皆さんのことは忘れません。どうか私を探さないで下さい―
アデルの筆跡は、所々乱れていた。午後の2時頃、買い物に出かけると言って、アザゼルをアイシャに預けたまま、そのまま帰って来ないのだとザカートは言った。7時頃、心配したアイシャが、アデルのアパートに行って、その手紙をムカールの机の上で見つけたのだと、夫人は説明した。
「......アデルはあんなにアザゼルを可愛がって―大事に育てていたのに......いっぺんに両親を失ってしまったんだ......アジーは......」
アルブラートが茫然としながら呟くと、医師は後悔の表情を見せた。
「私がムカールにオルガ様を会わせなければ―こんなことにはならなかったかもしれません......私も、バシリエフスキー大公という方が、あんなに人種的偏見を持った人とは思いませんでした......ムカールがもし大公の暴言を知っていたなら、激怒していたでしょうね―私は彼に申し訳が立ちません」
アルブラートは、ザカートに抱かれ、嬉しそうに甘えた声を出しているアザゼルを見ると、ムカールが「女の子が生まれたらいい」と言って、「アザゼル」と命名したことや、ほんの4、5日前、娘をベッドの傍らに寝かせてもらい、あやしていた彼の姿が思い出され、哀しみが一層増した。
それでも、夫人に促され、ようやく食事を始めたアルブラートに、ザキリスは少し安心し、彼に話しかけた。
「アルブラート、あなたにもお気の毒でした......私はムカールの葬儀に参列しますが、あなたもアデル同様にそれが不可能になってしまいました......
それで......あなたさえ良ければ、カイロの市民墓地にムカールの墓碑を建てることはできます―いかがですか」
アルブラートは、黙って考えこんだが、ムカールの思い出の残る、この街に墓碑を建てるのはかえって辛いと言った。だが何か、亡くなった友の魂を慰め祈る場が欲しいと返事をした。医師は、しばらく思案した後、キプロスではどうかと提案した。
「キプロス......?」
「私の父はキプロス島のニコシアの生まれです。少年時代をそこで過ごして、アテネで陶器商を始めましてね。私はアテネで生まれましたが、父はよく幼い私を故郷に連れて行ったものです......ニコシアでしたら、ムカールの育ったレバノンや、このカイロも望めるでしょうし......」
アルブラートは医師の厚意に深く感謝し、その話を承諾した。
翌朝、ザキリスはアザゼルを夫人に抱いてもらい、空港に向かった。夫人は空港で待っているオルガ・エレーナにアザゼルを預けるのだと言った。アルブラートとアイシャは、医師宅の玄関先で、ムカールの遺児と別れた。彼は、アザゼルの小さな顔に輝く黒い瞳に、再びムカールの瞳の黒曜石のようであった美しい光を見い出した。
さようなら、アザゼル......
アルメニアで大きくなって幸せに暮らしておくれ......
ムカールがいつもお前を見守っているから......
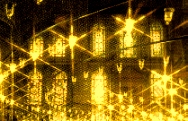
六月の初旬になった。ザキリスはニコシアの丘に、ムカールのための墓碑を建てる場所を見つけたと、アルブラートに報告した。アルブラートは医師に、その墓碑に刻む碑文をメモにして、渡した。
それから1週間後、アイシャとの挙式を目前にした頃、彼は完成した墓碑を見るために、医師とアイシャと共に、キプロスを訪れた。
彼は生まれて初めて飛行機に乗り、ギリシャの地に降り立ったのだった。観光客などで賑わうニコシアの街から30分ほどタクシーに乗り、その後、海の香りのする丘へと向かってしばらく歩いた。
途中、休憩をしながら、丘を登りつめた。岬のようにそそり立った丘の上に、ムカールの墓碑がひっそりと建っていた。それは重厚な、黒い大理石で造られていた。アルブラートは改めて、自分の書いた碑文が彫り刻まれたその墓碑を眺めた。
宝石の瞳と大理石の美
神に愛でられし 天性の知と光
そのすべてが融合し 神の化身であった君 天に昇りし君の魂よ どうか安らかに眠り給え
アルブラートは、碑文は英語で書き、青年の名も自分の名も敢えて刻まなかった。彼は、これを匿名の者の墓碑としたかった。そうすることで、青年は自分にとって、ギリシャ王の私生児ではなく、永遠にレバノンで出逢った「ムカール」であり続けることができるような気がした。
それでも彼の26年の人生は何だったんだろう......彼は生まれ故郷も親も知らずに生きてきた......その生の終わりにアルメニア国籍を取得しただけで―彼はただ「生きている」ことだけが幸せだったんだ......身分も何もない一人の人間として......
彼はアイシャと共に、その墓碑の前に花を添えた。青い地中海が目に眩しく、風は初夏の芳しい花々の香りを運んできた。彼はニコシアの丘にこうして立っていると、自分の人生の軌跡が、このキプロスを中心に、地中海の中で円を描いているように思えた。
ベツレヘム......ヨルダン......
イスラエル......シリア......レバノン......そしてカイロ......
もうこれ以上どこにも行かない......カイロでアイシャとずっと一緒に暮らすんだ......
医師は、ムカールはアテネで生まれたが、政情の不安定なアテネに匿名の墓碑を建てることは、王政反対派の目に留まり、かえって故人の魂が落ち着かないだろうと言った。
三人は、ニコシアの街まで降りた。ホテルで1泊して、カイロに帰る予定だった。アルブラートは足が再び痛み出したため、観光は今日は止めてホテルに直行しようと思った。ホテルの前の街路で、数名の若者たちが音楽を演奏していた。
彼は4月の末から指がこわばるようになって以来、演奏をしていなかった。思わず彼らの演奏に足を止めて、聴き入った。哀愁を帯びたギリシャの旋律に、アルブラートは不思議と惹きつけられ、自分もまたウードとカーヌーンを手に取り、弾ける日が訪れるのではないかとの希望がかすかに湧いた。
アルブラートは、楽人たちの楽器の中に、ウードに似たものがあることに興味を示した。医師は、あれはブズーキだと教えた。
「ギリシャの伝統楽器です。どことなくウードに似ているでしょう―興味をお持ちなら、アイシャとの婚礼の記念にお贈りしますよ」
アルブラートは驚いて、返事に躊躇していたが、ギリシャという異国で珍しく奥深い音楽に触発されている自分、また、ウードに似通った楽器を手元に置けば、今すぐにでも何かを演奏したいと願っている自分自身を見い出していることは分かっていた。
彼が微笑んで、快諾すると、ザキリスは彼とアイシャをホテルの部屋に案内し、すぐにブズーキを買いに街に出かけた。
ザキリスはお土産だと言って、アイシャにギリシャの民族衣装も買ってきた。アイシャは喜んで、その服に着替えて見せた。精緻な白いレースを編みこんだ短いヴェールを被り、赤いブラウスに、美しく華やかな花の刺繍のほどこされた白いドレスは、色白のアイシャによく似合っていた。
「アルブラート、アイシャはまるでギリシャの娘さんのようですよ―こんなにギリシャの民族衣装が似合うとはね。生粋のキプロス娘以上に美しい」
アルブラートはそのアイシャの姿を見るうちに、ムカールの死後、暗い洞窟のようだった自分の心に、明るい太陽の陽射しが差し込むような気持ちになった。彼は医師から贈られたブズーキを手に取ると、弦を思わずつまびき始めた。
アルブラートは、弾いたこともないその楽器を、自在にかき鳴らし、アイシャの美しい姿を描いていた。そんな彼に、アイシャもザキリスも驚いた。彼の奏でる音楽は、ウードの旋法と、たった今、街角で聴いたギリシャの民族音楽とが見事に溶け合った素晴らしいものだった。
アイシャは彼に飛びつき、抱きしめた。
「ムラート......!指がまた動くじゃないの......!また演奏できるようになったのね......やっぱりすごい才能じゃないの......!」
アルブラートは自分でも驚き、感動していた。彼は、ムカールが死の前日に、「お前の指は必ず治る」と言ったことを思い出した。
「......先生のおかげです......ギリシャに連れて来て下さって―ムカールも言いました―指は必ず治ると......きっとムカールがあの丘から僕を見守ってくれているんです」

ニコシアからカイロに戻り、5日経った。6月18日になった。アイシャは16歳の誕生日を迎えた。アルブラートは、彼女とのかねてからの約束通り、この日に彼女と挙式した。彼らは、ムカールの贈ってくれたパレスチナの婚礼衣装を身につけた。
二人は、最初、誰もいなくなったムカールのアパートで式を挙げようと考えた。だが、アルブラートは、青年とアデルの婚礼の日が思い出されて辛くなると言った。結局、自宅で、ザキリス夫妻とレストランのオーナーを招いて簡素な式を挙げることになった。
オーナーのジャハルは、二人の姿に深い感銘を受け、そうしてパレスチナの衣装を身につけて舞台に立ったらどんなに映えることかと残念がった。ジャハルは、1枚のレコードを二人に手渡した。
「これは、カイロのラジオ局が流した君たちの演奏を、イギリスのレコード会社が20曲にまとめて発売したんだ」
ジャハルは、このレコードが、アルブラートが演奏活動を休止している間に、またたく間にこのカイロだけで2万枚売れたと報告し、その売上金の20万ポンドだと言って、小切手をアルブラートに渡した。
「ミリオン・セラーとまではいかないが、大した人気じゃないか......!若いのに、これだけの大金を手にするとはね。それもこれも、二人の優れた才能の賜物だよ。アイシャにも、いい話がある。オペラ座がアイシャに、来月から出演を依頼してきたんだ」
アイシャは驚いて、アルブラートと顔を見合わせた。アルブラートは喜んで、アイシャにその話を引き受けるよう勧めた。
「アイシャはどこでも歌うことができるよ......度胸がいつでも据わっているんだから」
二人は婚礼の日に、思いがけない贈り物を受け取り、この上ない幸福に包まれた。ザキリスは微笑んで、この挙式を機会に、アルブラートにギリシャの国籍を贈りたいと申し出た。
「もちろんあなたさえよろしければ―正式に私の養子となって頂ければ、ギリシャの国籍を取ることができます。アルブラート、私の養子になって頂けますか」
「僕が先生の―先生の息子に......?本当に僕でいいんですか......?」
「あなたほど優れた人が私の息子になってくれるのなら―私はこれ以上の望みはありません」
こうして、アルブラートは19歳の6月から、ザキリス医師の養子となった。
医師は彼を本当の息子として、生涯見守り続けた。
ザキリスのアルブラートへの呼びかけは、徐々に親しさを増したが、アルブラートは医師を父と思い、感謝しながらも、いつも遠慮がちに「先生」と呼んだ。
挙式が済み、アルブラートはアイシャと初めての夜を迎えた。
カーテンの隙間から差し込む月明かりの中に、白い花嫁衣裳のアイシャの姿が浮かび上がっていた。アルブラートはベッドに腰掛け、アイシャの肩を抱き寄せた。彼は、アイシャのドレスの肩の中に手を滑りこませると、彼女の白いうなじに口づけした。
とたんに、アイシャは、何かに怯えるように、彼を押しのけるような仕草をした。アルブラートはドキッとし、彼女から体を離した。アイシャは薄い毛布を頭から引っ被ってしまった。アルブラートはうろたえ、しばらく彼女の様子を伺っていた。
「アイシャ......こんな時にふざけるなよ」
彼は、アイシャから毛布をそっと取り除けた。今度は、アイシャは何も抵抗しなかった。アルブラートは、彼女を抱きしめ、接吻すると、ベッドに横になった。彼は、高鳴る胸を抑えながら、アイシャのドレスのボタンをひとつずつ外すと、白い胸の中に顔を埋めた。白い月明かりの中で、少しずつ、花園の扉が開き始めた。
アルブラートは、その花園の中を歩いていた。辺り一面に咲き誇る色とりどりの花々の中にある蕾の群れが、先を争うように、次々と花開いていった。彼は、神秘の楽園の奥へと進んで行った。一番奥まった所に、火の灯った燭台に囲まれ、真紅のビロードに包まれた宝石が輝いていた。
これがファイザル......キャンプの長老の言っていた「矢で射止めよ」という秘密の宝か......
アルブラートは、その宝石に向かって、黄金で作られた矢を放った。その瞬間、その宝石は細かく砕け、甘い蜜の香りを漂わせながら、彼を覆い尽くした。彼は恍惚としながら、目をゆっくり閉じた。こうしてアルブラートは官能の夜に酔い痴れていった。
翌朝、アルブラートが目を覚ますと、もう昼の12時近かった。
彼は、側でまだ眠っているアイシャを見た。彼女の白い頬は、いつも以上に薔薇色に輝いていた。アイシャは白いレースの下着が肩から少しはだけ、白いふくよかな肌に、漆黒の長い髪が流れ落ちていた。アルブラートは、起き上がり、しばらく彼女の姿に見とれていたが、ベッドのシーツの一部が鮮血に染まっているのに気がついた。
彼は、その血を見たとたん、まったくの別世界に誘われていく気持ちになった。アイシャに気づかれないように、白いタオルでシーツをそっと覆うと、アルブラートはシャワーを浴び、婚礼衣装の長衣だけに着替えた。挙式後、3日間はその衣装を身に付けているのが古くからの慣習だった。
彼は二人分のコーヒーを入れ、サイドテーブルに置いた。その香りで、アイシャが目を覚ました。
彼女は、アルブラートを見ると、顔を赤らめた。ジーンズやシャツといった普段着ではない、パレスチナの伝統衣装を着たアルブラートの姿に、アイシャは惚れ惚れとしていたが、シーツの血にハッとしたように、またベッドにもぐりこんでしまった。
アルブラートが彼女の手を取ると、アイシャはその手を払いのけた。
「アイシャ......何でもないよ」
「いや!私を見ないで!あなたには乙女心が分からないのよ」
「乙女......?アイシャはもう乙女じゃない。立派な新妻になったんじゃないか」
「新妻......?嫌ね、そんなこと―いきなり言わないで!」
アイシャは起き上がると、アルブラートに枕を投げた。彼は笑ってその枕を受け止めると、彼女のそばに静かに置いた。
「朝っぱらから威勢のいい奥さんだな―でももう昼だよ、アイシャ」
アルブラートは彼女と並んでベッドに腰掛けた。アイシャは彼の笑顔につられて、少し恥ずかしそうに笑ったが、次第に涙が滲んできた。彼女は、彼に抱きついて、すすり泣いた。
「ごめんなさい......ムラート......私、いつまでも子供みたいに乱暴なことして......ムラートと本当に結婚できたのね......とっても嬉しいのに......」
●Back to the Top of Part 14
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- アニメ!!
- 【中古】 幻魔大戦(Blu-ray…
- (2024-11-14 14:54:38)
-
-
-

- 経済
- 2024.9.3.財界オンライン:2024-09-03 元…
- (2024-11-12 00:09:27)
-
-
-

- 楽天ブックス
- ハズレ属性【音属性】で追放されたけ…
- (2024-11-28 00:12:25)
-
© Rakuten Group, Inc.



