砂漠の果て(第18部「異郷」)

青い男は、駱駝を鞭打つと、薄暗がりの砂漠の彼方へと去って行った。マーディは、ホテルに戻ると、アルブラートを感心したように眺めた。
「あんたは音楽家なのかい。どおりで、金持ちで立派な身なりをしていると思ったぜ、うん。だが、なぜル・ラフが、あんたが音楽家だなんて知っているんだ」
「シェリフの―シェリフの、アブドゥルカリームが、俺のレコードを持っていたんだ......それに、シェリフからもらったカーヌーンで、ラティカという踊り子の踊りの伴奏を頼まれたんだ」
「そうか、シェリフが何か贈り物をするってことは、あんたは相当気に入られたんだな。それで、その―目的の、蜃気楼の幻は見ることができたかい。亡くなった奥さんに会うことはできたのかい」
「......ああ......本当に―蜃気楼が立って......女の幻が俺に近づいてきた......その幻は、本当に―死んだ彼女だった......でも、これもマーディのおかげさ。50ポンドは、ちゃんと返すよ」
マーディは、いつもル・ラフから、砂漠の集落までの案内料として、50ポンド差し引かれるのだと断ったが、アルブラートは構わないと言って、彼にお金を渡した。
アルブラートは、ホテルの自室に戻ると、顔と手を洗い、運ばれてきた夕食をとった。半日身に着けていたガラベーヤを脱ぐと、鞄に入れてきた普段着に着替え、ベッドに横になった。急に、アレクサンドリアではザキリスが心配しているのではないかと思い、フロントに行き、電話を借りようとした。だが、その古びた電話は、アレクサンドリアには繋がらなかった。
彼は、再び部屋に戻ると、ベッドに腰掛け、今日あった事柄をあれこれ思い返した。ベッド脇の鏡を改めて見た。砂漠に1日近くいたためか、日焼けし、余計に浅黒くなったように見えた。なぜ、あのル・ラフが自分を「アラブの王子のようだ」と誉めるのか、分からなかった。
「―お前も、その外見は一生変えることはできない。お前は、どこから見てもアラブ人だ」
あの青い男の言葉が思い出された。アルブラートは、ムカールの姿を思い起こした。
ムカールには、アラブの血など一滴も流れてはいなかった......彼は、ギリシャとアルメニアの混血で―結局はヨーロッパ人と全く変わらなかった......俺も彼と同じように色白だったら―せめて外見だけでもアラブ人であることを忘れられるのに......
再び、ル・ラフの、「アラビア語すべてを忘れ去らないと、ヨーロッパでは暮らせない」という言葉が蘇って来ると、不安と心細さに襲われた。彼はひどく疲れて、ベッドに寝転んだが、尚もそのことを考えた。
あの男が言ったことは、全く理に適っている......
「アラブを捨てる」などと言って、実は俺は、漠然とした気持ちでそんなことを言っていたんだ......でも......「考える時も、独り言を言う時も、寝言を言う時も、アラビア語を使わない」―そんなことができるだろうか......
現に、今だってアラビア語でものを考えているじゃないか......
だがアルブラートにとって、「アラブを捨てる」という決意は、もはや確固としたものになっていた。今更それを翻すことなど考えられなかった。
ムカールは、外見はアラブではなくても、レバノンで、アラビア語で育った―だからこそ、彼の意識はアラブ人そのものになった―そうだ......ル・ラフの言ったとおりだ......俺が今度は、ムカールと全く逆のことをすればいい......
パリに行くのなら、フランス人と同じように、すべてフランス語で生活するんだ......フランス人になりきるんだ......フランス語で頭を満たすことが肝要なんだ―そうすれば、アラブであったことを、すべて忘れてしまうことができるんじゃないか......
彼は、深く溜息をつくと、体を起こし、シェリフから譲られた碧水晶を絹の包みから取り出した。それをベッドサイドの小テーブルに置き、しばらく眺めていたが、やはりどうしても、ただの透き通ったガラス玉にしか見えなかった。彼はひどい疲労感を覚え、いつしかベッドでうとうとと眠り始めた。
だが寝入って、3時間ほど過ぎた頃、何か眩しい光を感じ、アルブラートは目を覚ました。枕元の水晶が、きらきらと輝き、青い光を放っていたのだった。彼は不思議に思い、その水晶を手に取り、本当に何か映るのだろうかと、じっと目を凝らした。
最初は、徐々に、白く整ったどこか西洋の街並みらしきものが見えてきた。緑溢れる並木道のそばに、遊覧船の浮かぶ大きな川が映っていた。その映像は、5秒ほどすると消え、今度は、豪奢な彫刻の施された、雄大な門の映像が浮かんできた。アルブラートは、その門に見覚えがあった。
これは―ムカールの美術書で見たことがある―彼が、あの本を開いて、俺に教えてくれたんだ―ああ―そうだ......これはパリの凱旋門じゃないか......
次に浮かんで来たのは、ピアノを練習している自分の姿だった。その側には、やっとよちよち歩きを始めたアリの愛らしい姿も見えた。
この映像も5秒ほどで消え、次に、幼女を膝に抱いている自分と、自分たちに話しかけている男性の姿が映った。アルブラートは、その幼女と男性の姿に目を見張った。
この女の子は―アザゼル......アザゼルじゃないか―なぜアザゼルがパリにいるんだ......それに―この男の人は―ああ......あの人だ......デュラック―ロベール・デュラック先生じゃないか......
ガリラヤ湖の病院でフランス語を教えてくれたデュラック先生―先生はあれから、パリに戻っていたのか......
アルブラートは、ザキリスが話していた「パリに知り合いがいる」というのは、このデュラック氏を指しているのではないかと思われた。
デュラック先生が、俺のレッスンを引き受けてくれるのなら―パリでの生活も―すべてフランス語で暮らすことも、抵抗が少ないかも知れない......懐かしいロベール先生......
彼は、翌朝、スーツに着替えると、マーディに、マルサ・マトルーフまで送ってくれるよう頼んだ。彼らは、8時に朝食を済ませると、9時にはチェックアウトし、ジープに乗り込んだ。
「本当に、あんたがそんなに有名な音楽家だなんてな―まだまだ若いのに、レコードまで売れて、良かったじゃねぇか。俺も、そのうちアレクサンドリアで、あんたのレコードを買うよ。ええと、あんたの名前は......」
「アル・ハシム―アルブラート・アル・ハシムと言うんだ」
「ああ、そうか。いい名前だな。俺ぁ、レコードなんてな、買ったことも聴いたこともねぇのよ。安アパートにゃ、でかい声の女房と、子供が6人もな、年中うじゃうじゃしててな、そんな高級な暮らしをしたことなんて、ないんでな。でもあんたのレコードは絶対買うよ。大家の奴が、ステレオを持ってたから、それで聴くしかねぇがな」
マーディは、アルブラートのレコードに夢中になっていたが、アルブラート自身は、BBC やボストンとのレコード契約をどうしようと考えていた。もうウードもカーヌーンも弾くことがないなら、契約を打ち切らないといけない―そのことを思うと、再び、不安と寂寞とした感に捉われた。
それは、「アラビア語いっさいを忘れ去る」決意とほとんど同じだった。
マルサ・マトルーフの街が近づいてくると、マーディは、急に思いついたように彼にこう言った。
「なあ、あんたは昨日の朝、マトルーフのホテルで、パレスチナ人の訛りを見破られて、なかなかシーワ・オアシスへのジープを紹介してもらえなかったよな―あんたは、英語ぐらいは達者なもんだろ。ホテル街に並んでいるタクシーの運転手に、俺があんたを『外国帰りの音楽家だ』って紹介してやるから、その代わり、あんたは、アラビア語を使わずに、英語だけを使うんだ―この手はいけるぜ。そうしたら、すんなりとアレクサンドリアまでタクシーで帰れるからな、どうだい」
アルブラートは、自分が漠然と考えていたことを、マーディから提案されて、はっとした。
「......アラブ人ではなく―外国人になりすます―そういうことなのか」
「ああ、そうさ。頭は使いようだ。あんたは、アラブ人にしか見えねぇけどな、使う言葉で、相手の対応は違ってくるってもんよ。マトルーフ辺りのタクシーの運転手は、英語を使えるお客には一目置くからな」
アルブラートは、アイシャの亡くなるずっと以前、レバノンのサイダで演奏活動を始めた頃から、パレスチナ方言を他のアラブ人に知られたくない思いから、レバノンではフランス語で、カイロでは英語のみを使っていたことを思い出した。
その頃は、演奏のステージ上だけ、外国語を使っていれば良かった。仕事が終われば、友人や恋人と、自由にアラビア語で話ができた。だが、その友人も恋人も失われた今、外国語のみで暮らしていくということに、何か心の大きな母体となるべき基盤が跡形も無く崩れ去る虚しさを感じた。
マトルーフの街には、午前11時過ぎに着いた。マーディは、約束通り、タクシー乗り場に行き、ある運転手に話を持ちかけた。彼は、満足そうにジープの所に戻ってくると、アルブラートに笑いながら言った。
「なあ、あの一番端のタクシーが恐れ入ってオーケーしたぜ。俺ぁ、あんたのことを『ロンドンの演奏旅行から帰ってきたばかりの、一流の音楽家がお客さんだ』って話したんだ。あとは、あんたが英語で『アレクサンドリアの駅前まで頼む』と言えば大丈夫だ。200ポンドは、まぁ仕方がないがな」
アルブラートは、マーディと握手をして別れ、そのタクシーに乗り込んだ。タクシーの運転手は、アルブラートとほぼ同じ年頃で、英語には不慣れな様子だった。アルブラートが英語で行き先を告げると、彼は恭しくドアを閉め、滑るようにタクシーを出発させた。
やっとアレクサンドリアに到着したのは、午後1時近かった。アルブラートは、運転手に200ポンドを支払うと、タクシーを降りた。ザカートの実家は、駅から15分ほど歩いた所にあったが、アルブラートの足では、ゆっくり歩いても、30分はかかった。彼は、以前よりも足が悪くなっていることに不安を覚えた。
家に辿り着き、玄関をそっと開けると、ザカートが驚いたようにロビーに立っていた。そばには、ナフマに抱かれたアリがいた。ザカートは、微笑みながらも、涙ぐんで、アルブラートを抱きしめた。
「......まあ、アルブラート......シーワ・オアシスまで行ったなんて―アイシャの幻にそんなに会いたかったのね......可哀想に......でも無事に帰って良かったわ」
指をしゃぶっていたアリは、父親を見ると、甘えた声で「アブ」と呼んだ。アルブラートが抱き上げると、アリは、こらえ切れなくなったように、激しく泣き出した。アルブラートは、そんなアリを見ると、なぜこの可愛い子を置いて、砂漠にまで出かけたのだろうと後悔した。
だが、「私の魂はアリの中に生き続ける」という、アイシャの幻の声を思い出し、再度、愛児を見つめ直した。その言葉と、アリの姿を重ね合わせても、不思議とアイシャへの激しい想いは沸き起こらなかった。彼は、ようやくアイシャへの愛の苦悩が薄らぎ、アリだけを愛することができるという希望の兆しを見出せたと感じた。
アリの泣き声を聞いて、奥からザキリスが顔を出した。アルブラートは、ザキリスに、急に家を出たことのお詫びを言おうとしたが、なかなか言葉にならなかった。ザキリスは、目に涙を滲ませ、自分の息子をじっと見た。アルブラートは、ザキリスのこんな表情に、自分が砂漠でどんな体験をし、どんな決意に至ったかを話すのが、ためらわれた。
「......申し訳ありません―先生―オアシスのホテルから電話をかけたんです......でも―繋がらなくて......ご心配をおかけして......」
アルブラートが口ごもりながら、こう言いかけた途端、ザキリスは彼の肩を強く抱き寄せた。アルブラートは、ザキリスがこんなに感情を表に出すのを初めて見た。
「本当に―本当に無事に帰って良かった―数日前に、シーワ・オアシス付近の砂漠で、観光客が遊牧民に襲われて―殺害される事件が起きていたんだ......その時は、他人事だと思って、気にも留めなかった―まさか―アルブラート―君がそこに行くとは思いもしなかった......私は―君を失ったら......そう思うと、一睡もできなかったんだ」
アルブラートは、こんなにまで自分を愛する家族がいるのに、なぜアラブを捨てたいとまで思うのかと、あんなに固かった決意が揺らぎそうになった。
「昼食はまだなんだろう―食事をして、一休みをしたら、私の部屋に来なさい、アルブラート」
彼は、ゆったりと広いリビングで、ナフマの用意した昼食を取った。昨日の今頃は、砂漠の奥地で、シェリフの天幕にいたことが、嘘のように思えた。
食事が済むと、彼は医師の部屋に行った。
「一昨日、パリの友人に電話をしてね―君のことを話すと、彼は即座に了承してくれたよ。今は、シテ島に住んでいるが、来月には音楽院の近くに転居するそうだ」
ザキリスは、アルブラートに、その人物のメモを渡した。そこには、「コンセルヴァトワール教授 ロベール・カイエ・デュラック」との名が記されてあった。アルブラートは、碧水晶に、昨夜、デュラック氏が映ったことで、予想はついていたが、それが現実になったことに改めて驚いた。だが、表情は変えずに、黙ってそのメモを見つめていた。
「私が、君の名を言うと、彼は、『その少年は知っている』と言うんだ。アルブラート、君はこの人と知り合いなのかね」
「―ええ......僕が、シリアの病院にいる時、16歳の年末から、17歳の夏までの9ヶ月間、フランス語を教えに来てくれた先生です」
「そうか―まったくもって、奇妙な偶然だな―氏は、君のことを、『ベイルートの音楽院入学を希望していたために、フランス語を教授した』と言っていた。それなのに、その音楽院には行かず、今なぜカイロにいるのか、と不思議がっていた―私は、その間の経緯をうまく話せなくてね......
パリに行って、君が教授に、どんなことがあったのか―話すことは出来るかね」
アルブラートは、デュラックと別れてから、ペイルートへの線路が爆破され、止む無くザハレに留まり、その後、南部のサイダに向かったことを思い起こした。だが、それからの出来事を、デュラックに口頭で説明すること自体が、アラブ世界を思い起こすことになる―そう思った。
パリでロベール先生に会ったら、ベイルートに行く途中、せっかく頂いたお金を盗まれたことを話さなければならない......
サイダの街で、音楽院に行くつもりだったのに、ムカールの治療費のために、ザハレで受け取った1万ピアストルもの大金を彼に与えたことや―音楽院入学をあきらめて、ホテルで演奏をして働いたことや―治安部隊に狙われて、カイロにザキリス先生と亡命したことや―ムカールとアイシャが死んだことや―
挙句の果てに、アラブ世界と決別するに至った経緯を説明する.....
そんなことは―また苦しい思い出の繰り返しになってしまうじゃないか......一体どうしたら......
アルブラートは、何とか得策はないかと悶々と考え続けた。ようやく、彼は重い口を開いた。
「......これは―すべて、僕自身の問題です......先生がうまくお話できないのは当然のことです―僕が、ロベール先生に、要点だけをまとめた書簡を書きます―僕も、あまりにも、ここ数年、いろんなことがあり過ぎて―とても言葉では説明しきれませんから......何もかも、先生に甘える形になってしまって、申し訳ありません」
「いいや、そんな他人行儀にかしこまらなくてもいいんだよ―でも、アルブラート、そういう丁寧さは君の生来の気質であるし、美徳でもある―デュラック氏が君のことを今でも懐かしく、大事に思って下さるのは、君のその愛すべき性質のためだね......」
ザキリスは、アルブラートのことを心配し、一睡もしなかったためか、ひどく疲れた様子だった。医師は、目をこすり、くしゃくしゃに乱れた髪を掻き揚げると、眼鏡をかけた。アルブラートは、ただ黙って医師の姿を見ていた。 やがて、ザキリスは、書棚から、古ぼけた地図を取り出すと、それをアルブラートに手渡した。
「......どうも眠れなくてね......君がアイシャの幻に会いたいばかりに、あんな砂漠の奥地まで行ったかと思うと―君が不憫でね......
だが私も、昨夜は、ムカールの幻を寝室で見たんだ」
「......ムカールが―先生の部屋に......?」
「ああ―私は、正直言って、あのような類のものは信じられなかった......
幻影や、亡霊といったものは―だが、人間の心が弱っている時に―亡くなった者は姿を現すんだね......ムカールは、こう私に言ったよ......
『アルブラートは、砂漠でアイシャの幻影を見ることができた―彼がパリに行っても、どうか彼の心の支えになってくれ』とね......」

アルブラートは、ムカールが医師に告げたという、「彼の心の支えになってくれ」との言葉に、何か秘密が暴かれた時のような困惑を覚えた。
もしかしたら―ムカールは生前に、先生に、俺の収容所での経験を話していたのかも知れない......ムカールは、自分の命がもう残り少ないと感じて......だから、俺のあの恐ろしい告白を、先生に託すしかないと―そう思ってすべて話した......彼は先生の病院で事務をしていたんだ―いつだって話すチャンスはあったんだろうから......
アルブラートは、考えただけで身震いし、気が遠くなるほど忌まわしいあの事件を、ムカールに告げ、アイシャにも告げ、そしてザキリスにも告げた。だが、その告白を聞いた者同士が、その件について話し合ったかと思うと、まるで、大衆の前に殺人犯として顔を曝し、公開処罰を受けているかのような、屈辱感と罪悪感に襲われた。
アルブラートは、恐る恐る、ささやくような声で、ザキリスに尋ねた。
「......ムカールは......先生に―僕の告白を......すべて話した......そうなんですか」
ザキリスは驚いて、目を見張った。彼は、ムカールから、アルブラートの過去を洗いざらい聞いたことを、「決して他言しないように」と頼まれたことを思い出し、つい不用意なことを口走った、と反省した。
「―いや、私はムカール自身から何も君の過去の話は聞いていない。私が知っているのは......カイロ警察から聞いたことだけだ......きっと、ムカールは、あの世から、君がアイシャを失ったことを見ていて―それで、『心の支えになってほしい』と語ったのだろう......私を信用してくれないか、アルブラート」
アルブラートは、ザキリスの口調から、多少疑念が残ったが、それでも、この人の言うことには間違いはないと確信した。
ザキリスの声は、いつも穏やかで、深い叡智と的確で鋭い判断力と共に、愛情溢れる理知の持ち主である印象を相手に与えた。彼の風貌は、医学者でありながら、美へのイデアを追求し続ける古代ギリシャの哲学者の如きものだった。
ウィリアム先生......この先生に、18歳のあの日、サイダのホテルで出会ったんだ―この先生に出会わなかったら―俺は今頃どうなっていただろうか......アラブ世界を忘れ去っても―先生のことは、生涯忘れることなんてできない......
アルブラートは、医師を見つめると、遠慮がちにうなずいた。ザキリスは、安心したように溜息をついた。
「その地図は、もう20年も前のパリの地図だ。デュラック教授が今住んでいるシテ島は、ここだな―コンセルヴァトワールは、パリ市内に同名の、市立パリ音楽院がいろいろあるが、教授が教えている音楽院は、パリ国立高等音楽・舞踊学校だ。コンセルヴァトワールと言えば、この音楽院をまず指すんだ。ほら、このマドリッド通りにあるだろう―だが、これはもう古いから、新しい地図を買わなければならないな」
アルブラートは、漠然とその茶色に変色した地図の地名に目を通していた。それらの地名は、読んでいくうちに、何かの呪文のように思えてきた。
リュ・デュ・ロデオン......リュ・デ・サン・ペール......ヴルヴァール・デュ・ラ・ヴァスティーユ......ラ・ヴィラ......ラ・ヴィラ・マイヨー......ああ、このシテ島に、ムカールの教えてくれたノートルダム寺院があるのか......
彼は、サイダに着いた日に、ムカールと馬車に乗って、サイダ音楽院を見に行ったことを想い起こした。彼が、その音楽院を「パリのノートルダム寺院のゴシック建築を真似て造ったんだ」と説明してくれたのが、つい最近のように思われた。
その地図は、英語とフランス語とで併記されてあった。アルブラートは、ふと、ザキリスは、普段は自分とアラビア語で話をしているが、自分独りの時は、やはりギリシャ語で考え事をするのだろうか、と考えた。
「先生......先生は、ご自分の母国語は―ギリシャ語なんですね」
「そうだよ―それがどうかしたのかね」
「それなら―ご自分で何か考えたり―独り言を呟く時は、ギリシャ語を無意識に使っておられるのでしょう」
「......そういえば、そうだな―生まれた国の言葉は、年老いても忘れることはないだろうな......ただ、私の母は、英国人とエジプト人の混血だったから―それで、私も自然と英語とアラビア語を覚えたんだ。君や、妻のザカートと話す時は、自然とアラビア語になってしまう。言葉というのは、不思議なものだね」
ザキリスの、「生まれた国の言葉は、年老いても忘れることはない」との言葉に、アルブラートは、表現し難い苦痛を感じた。だが、この機会に、自分が決意したことを話してしまいたかった。
「先生......僕は―『アラブを捨ててヨーロッパに行く』とお話しました―
でも、自分でも『アラブを捨てる』ということの具体的な意味を理解していなかったのです......僕は、シーワ・オアシスから駱駝で2時間もかけて、トゥアレグ族の集落に案内されました―その部族の中でも、温厚な性質で、高い教養を身につけている、サヘール族に客人として丁寧にもてなしを受けました―
その一族のシェリフの甥が、『アラブを捨てる』という僕の決意について、具体的な方法を教えてくれたんです......『アラブを捨てるのなら、自分の母語であるアラビア語すべてを忘れ去ることだ』と―僕は、彼のアドバイスを何度も考えてみました......彼の言葉は的をついていると......だから、僕は心に決めたんです―パリに行ったら、アラビア語はすべて忘れ去ろうと......」
ザキリスは若者の話を聴いた後、しばらく考え込んでいた。
「君の言うことは―自分独りでいる時も―考え事をする時も―すべて母語を使わないと......そういうことなのかね」
アルブラートは瞳に苦渋の色を滲ませながら、医師を見た。
「......そうです―そうしないと―いつまでも僕はこの社会に捉われたままで―意識がアラブに縛られたままで......本当の意味でアラブ人であることを忘れ去ることはできない―意識してアラビア語を使わないのではなく......アラビア語が意識から完全に消滅するところまで行き着かないと―そう決心したんです」
「君のその選択は―ある意味では間違ってはいない......少なくとも、パリで不自由なく暮らしていくには、それぐらいの語学力が必要だから―しかし―また別の意味では―それは―君にとっては不幸なことなのではないか......私はそう思うんだが」
「......僕の―僕の本当の不幸は―アラブであることです......今までの21年間を、記憶から抹殺してしまいたい......それができて、初めて幸福になれるんです」
ザキリスは、アルブラートにとって、母語を記憶から消滅させることが、真の幸福足り得ることではないと感じていた。
どんな遠い異国に暮らしても、またその異国の言葉にいかに通じようとも、生まれた時から身につけてきた母語というものは、自分が自分であるための存在感の基盤であり、自分の魂の帰っていく港であり、母の懐と同様の深い大地なのだ―彼は、そうアルブラートに言いたかったが、実の母を亡くしているこの若者には、そのようなことは言い難かった。
彼が母語を記憶から抹殺すること―今までの21年間をなかったことにするということ―それが「幸福だ」というのは、恐らく全くの嘘だ......彼は、彼なりに悩みぬいて、そう判断したに過ぎない......アイシャがあんな事件に巻き込まれて、あんな残酷な死に方をしなければ―彼はこのまま、カイロで幸せに暮らしていたはずなんだ......
「......君の言うことはよく理解できる―私は、君の決意は生半可なものではないと―決して翻すことはないと分かっている......しかし、君は―名前はどうするつもりなんだね」
医師にこう尋ねられて、アルブラートはハッとした。
そうだ......この名前―名前こそ、アラビア語を忘れる以前に―生まれた時から身についているものじゃないか......馬鹿だな―なぜ気がつかなかったんだ......!
「名前こそ、君がアラブ人であるまず第一の証なんだが......でも、もう君を私は煩わせたくないのでね......名前はいつでも変えることができる―それで......アリのことなんだが......あの子は君とパリに行って、そのままそこで大きくなる―そうすると、あの子の故郷はパリだということになる......それでいいんだね?」
アルブラートは押し黙り、じっと考えていた。名前に関する解決策はどこにも見出せなかった。彼の、自分の名や息子の名に対する愛着の念は、すぐさま振り切れるものではなかった。彼は、名前のことは曖昧なまま、ただ機械的に答えた。
「そう―そうです......アリは、ギリシャ系フランス人として育てます」
ザキリスは、アルブラートの瞳を見つめながら、この若者とは不思議な縁があると思った。
アルブラートのこの悲劇的な表情をたたえた大きな黒い瞳に、私は深く魅せられたんだ......3年前の夏に、シドンに滞在が決まった時、非常に評判の良い演奏家がいるとの噂で、あのマルヴェーラというホテルに宿泊を決めたんだ......私の音楽好きは母の影響だった―
そして初めてサロンで演奏しているアルブラートを見た時に、何かを感じたんだったな......
この少年とはもしかしたら、長い付き合いになるのではないかと......
「......そうか......さあ、もう話はこれくらいにしよう―君も疲れたろう。休みなさい―ああ、そうだ。あと数日で、デュラック教授から楽譜集が届くから、その後お礼の手紙を書いたらいいね―その―なぜ今アレクサンドリアにいるのかということも添えて」
「楽譜......?」
「そうだよ、楽譜だ。音楽院受験まで、あと7ヶ月しかないし、楽譜の読み方の基礎をパリに行く前にマスターしておかないと―君は、ずっと即興演奏をしていたから、楽譜を見るのは初めてだろうし......」
アルブラートは、医師に促されて、アリのいる部屋へ行った。アリはここ数日で、這うことができるようになっていた。赤ん坊が自由に動き回れるように、部屋にはベビーベッドと、ソファー以外には何も置いていなかった。
アリは、ベッドの中ですやすや眠っていた。アルブラートは、小さな息子の柔らかな、桃色の頬を撫ぜ、頭の黒い巻き毛にそっと触れた。アリは、顔立ちが鮮やかなほどはっきりとしてきて、ますます可愛らしさが引き立ってきた。
肌は、やや褐色がかっているが、アイシャに似たのか、色白な方だった。
アルブラートは、そんなアリを見つめていると、再び、自然と涙が溢れてきた。何ともやりきれない想いで、彼はベッドの側を離れ、ソファーに横になった。先ほどの、医師の言葉が何度も頭に浮かんだ。
「ギリシャ系フランス人」として育てるのに、アリは外見はそんなに不自然じゃない......でもさっきの先生は何だか変だったな―俺を煩わせたくないと言いながら、「名前こそ君がアラブ人である証だ」と言うなんて......かえって俺を煩わせているじゃないか......でも―先生は一晩中寝ていないんだ......だからあんな思慮のないことを言ったりしたのか―
だが、アルブラートは、自分の間違いにすぐに気がついた。
いや、そうじゃない......思慮がないのは俺の方じゃないか―先生は、俺のことを心底心配してくれているからこそ、名前のことを言ったんじゃないか......「煩わせたくない」というのは、先生の俺への愛情から出た言葉なんだ―名前を変えずに、どうやってアラブ世界を離れることができるんだ......?全く俺はどうかしている―アリだって......将来この名前のままでは困るだろうに......
彼は、深い溜息をついた。自分の名を、すべてギリシャ風に変えてしまおうかとも考えた。だが、それを実現するのは大変な勇気が必要だと感じた。名前を変えてしまうと、それこそ、自分の存在を見失うような不安がつきまとうのではないかと怖れた。
もうしばらく何も考えたくないと思い、彼は、ソファーで仮眠を取ろうとした。だが、数分もしないうちに、アリがベッドで目を覚まし、愛らしい声を出しながら、父親の方へと這い寄って来た。アルブラートは、疲れていたが、アリの眼差しが、自分を求めている様子を見ると、思わず抱き上げずにはいられなかった。
アリは、父親の胸にしがみつき、愛くるしい声で、何回も父親を呼び、小さな美しい顔をかしげて、アルブラートを見た。アルブラートは、1歳にも満たない幼子の、驚くべき体の温かみと、心臓の活発なリズムを愛おしく思い、しばらく抱いては頬ずりを繰り返した。
やがて、父親の抱擁に満足したアリは、体をひねって、両手を床に伸ばした。アルブラートが床におろしてやると、アリは、嬉しそうに部屋を這い、歓声を上げた。ソファーに腰掛けて、様子を見ていると、アリは、ベビーベッドの後ろにあるクローゼットのそばに這っていき、その扉を小さな拳で叩き始めた。
アルブラートは、何かおもちゃでも入っているのかと思い、クローゼットの扉を開けてやった。するとそこには、彼がアリのためにカイロで買ってやったウードとカーヌーンが布に包まれて置かれてあった。アリは、父親を振り向くと、指をくわえ、それらの楽器をパンパンと叩き、挙句の果てには、引きずり出そうとした。
その二つの楽器は、カイロで爆破事件が起きる直前まで、彼がアリのために演奏してやっていたものだった。彼は、その楽器を見るのがたまらなかったが、アリが乱暴にその楽器を引きずろうとしているのを見て、慌てて楽器を取り出してやった。
赤子は、布を払いのけると、はしゃぎながら、アルブラートのそばに這い寄り、弦を夢中でかき鳴らしては、得意そうに父親を見て笑った。そして、弦を指差すと、再び指をしゃぶり、彼を見上げた。アルブラートは、もうウードやカーヌーンを弾くのが辛く、息子のためと思っても、弦に触れることが出来なかった。
「アリ......父さんはね、もうこの楽器は弾かないんだよ。弾いてやりたかったけれど、もう駄目なんだ......ごめんよ、アリ」
父親の表情や言葉の雰囲気で分かったのか、アリは急に泣きじゃくり始めた。アルブラートは、アリを抱いてなだめようとしたが、赤ん坊はその手を払いのけて、部屋の隅に這っていき、なかなか泣き止まなかった。
アリの泣き声に、ザカートが慌てて部屋に入ってきた。彼女は、楽器と、泣いているアリを見て、すぐに状況を察し、アルブラートに謝った。
「ごめんなさいね、アルブラート......置き場所がなかったものだから、このクローゼットにしまい込んでしまって―アリには、何か別のおもちゃを買ってあげましょう。それで、気が紛れてくれたらいいのだけれど」
2日後、イスラエルはアレクサンドリアの空港、海上封鎖及びカイロ間との鉄道運行停止をすべて解除した。それから数日後、パリのデュラック氏から、アルブラート宛に、楽譜と書簡が届いた。書簡には、このように書かれてあった。
―懐かしいアルブラート
4年前、ダマスカスで別れた君と、再びパリで出会うことになるのは、私の大きな喜びです。なぜ君がベイルート音楽院に行かず、カイロで暮らしていたのかは、敢えて尋ねません。ただ、パリに君が来るのなら、ぜひ私の家で下宿して欲しいとお伝えしておきましょう。
また、私の所には、数名、ピアノを習いに来る人がいます。その中で、アルメニアから亡命してきた子爵夫人がおられます。不思議なことに、その子爵夫人は、君の名をご存知なのです。そのご婦人には、アザゼルという、もうすぐ2歳になる養女がおられます。
子爵夫人は、君がパリに着いたら、ぜひ相談したいことがあるとおっしゃっておいでです。どうかその件をよろしくお願いします。また、楽譜は大事なものですから、充分目を通しておいて下さい。
1963年1月12日 ロベール・カイエ・デュラック
アルブラートは、碧水晶で見たように、今度はアザゼルが現実にパリにいることに驚いた。彼は、その書簡を医師に見せた。医師は、書簡に目を通した後、真剣な調子で言った。
「実は2日ほど前、例の大公妃から私も手紙を受け取っていてね。あの方は、今までずっと、アザゼルをアルメニア大公には内緒で養育されておられたそうだ。大公は、ムカールのことを、あの方の本当の息子だとは認めて下さらなかった―だから、ムカールの葬儀は、実に貧しいあっさりとしたものだった......おまけにアデルを野蛮なアフリカ人と軽蔑しておいでだったからね、夫人はアザゼルの存在を知られたら、必ず大公から捨てて来いと言われると怖れておいでだった。
夫人は、それで、ご自分の別荘に、まだお若いグロズヌイ子爵夫人を呼んで、アザゼルの養育を頼まれたんだ。でも、とうとう大公にそれが分かってしまってね―そのために、子爵夫人は内密にパリに逃れたらしい。
だが、1年程前からパリに、ギリシャの王政反対派の一味が侵入し、王族の血縁関係者を洗い出しているそうだ。今ギリシャは軍事政権が実権を握ろうとしている―アザゼルは正式ではないが、ギリシャ先王の孫娘だから、このままだと危険に曝されかねない。子爵夫人は、大公妃から、君の話を聞いて、アザゼルの身元を君にすべて委ねたいと望んでおられるそうだ」
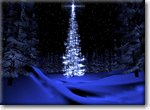
アルブラートは、ムカールの葬儀が粗末に扱われたとの話に、激しい怒りを覚えた。
「なぜそんな......バシリエフスキー大公というのは、貴族階級なのに、なぜムカールをそんな扱いに......僕は、彼の葬儀は、凡人の近寄れないような立派な荘厳なものだったに違いないと―ずっと思っていたのに......」
医師は、悲しげな表情になり、悔やむように呟いた。
「あの大公は、夫人に『どこの馬の骨を拾って来たんだ』と悪態をついたんだそうだ......十字架も、私は当然優れた材質のものが選ばれると思っていた―でも、結局はみすぼらしい木の十字架が使われた。彼の名も刻むことは許されなかった」
アルブラートは、アルメニア大公に激しい憎悪を抱いた。
俺のことは、パレスチナ人だ、テロリストだと言って、葬儀への参列を拒んでおきながら......アデルを「野蛮人」と蔑んでおきながら......本当の野蛮人はお前じゃないか......!アルメニア大公め......!
「......ところで、アザゼルのことだが......ギリシャの軍事政権を樹立させようとしているグループの影には、実は『闇の狼』と呼ばれる恐ろしい暗殺集団が存在している―彼らは、自分たちのことを『アイオロス』と呼んでいるが、今はギリシャでアイオロスと言えばその集団を指すんだ」
「アイオロス......?」
「ギリシャ神話で、風の支配者をそう呼ぶんだ。要するに自然界の支配者、神のことだな。まあ、貴族階級の者を風のようにさらっていくから、そんな名を勝手に自分たちにつけたんだろう―昔、ムカールを宮殿から誘拐し、トルコの孤児院に放り込んだのも、その『闇の狼』という集団らしい。今、ヨーロッパで暗躍しているのは、その集団の息子たちだ―彼らは、ギリシャから亡命した貴族階級の者や、王族関係者すべてを、今度は誘拐し、抹殺しようとしている」
「でも、アザゼルは―ギリシャ王室からは、血縁関係者だとは知られていないはずです......ムカール自身も、オルガ夫人も正式の親族とは認められないままだったのに......なぜその誘拐犯に、アザゼルがギリシャ王の孫だと分かるんですか」
「私もよく分からない部分が多いのだがね―あのような暗殺集団の情報網は実に緻密で、組織も細部に渡って管理されているそうだ。ギリシャ王室の歴史に関する情報なら、そういう輩には簡単に入手可能だ......ヨーロッパ中のあらゆる新聞やゴシップ誌を集めれば―ギリシャ先王の亡命の足取りや、オルガ夫人との間に息子をもうけたこと―さらに、オルガ夫人はアルメニアの名門の出だから、夫人の行動なども調査することができる......密偵が必ず、狙った貴族の人々にはつきまとっている可能性もあるんだ」
アルブラートは、まだ生後1ヶ月のアザゼルをそっと抱き上げた時の感触を思い出した。彼は、ムカールとの思い出に繋がるアザゼルに会い、自分が彼女を養育すれば、アラブとの縁がなかなか切れないと苦しんだ。だが、最愛の友人の遺児が、今どんな風に育っているのか、会いたくてたまらない衝動にも駆られた。
アジー......アジーと俺とは同じだな......いつもいつも、何か恐ろしいものに追われて―逃げ惑って―正体を隠そうとして......親も二人とも失って......
「......僕がアジーを養育する―僕が、貴族階級ではないから......でも、ヨーロッパ中にそんな恐ろしい暗殺集団が潜伏しているのなら、アジーは、カイロで―先生のもとで育った方が安全ではないでしょうか」
「......私も、それを考えたんだがね―先日、ザカートが双子を妊娠していることが分かったんだ......彼女は、もう43歳で、初産とはいえ、体力が持つか分からない―それで......アザゼルを任せられるのは、君しかいないと判断したんだ」
アルブラートは、養父であるザキリスに実の子供ができたことを知り、驚きかつ喜んだ。彼は、にっこり微笑んで医師に祝辞の言葉を贈った。
「先生にお子さんが......本当のお子さんが生まれるんですね―しかも一度に二人も......本当に―本当におめでとうございます」
ザキリスは、アイシャの死後、アルブラートの笑顔を見るのは初めてだった。彼は、安堵感が心に広がり、胸が温かくなるのを感じた。またアルブラートの笑顔の純粋で素朴な美しさ、素晴らしさに改めて深い感銘を受けた。
この子は以前から、ムカールに似たところがあると思っていたが......それは瞳だな―眼の雰囲気がどことなく似ているんだ―だがムカールの瞳は完成された宝石の光を放っていたが―アルブラートの瞳は自然の美しさを持っている......思わず人を引き込まずにおれない、大自然の神秘の美を目前にした時のような感動を味わうことのできる素晴らしい瞳をしているんだ......
「ありがとう―結婚して18年目に子供を授かるとは思わなかったよ。でも、アルブラート、君も私の大事な息子だ......双子が無事に生まれたら、その子達は、君の小さな兄弟になるんだ」
「ええ、分かっています。先生は―僕の大切なお父さんです―ヨーロッパに行っても......お父さんのご恩は......一生忘れません......アザゼルのことは......デュラック先生のお手紙にあるように―グロズヌイ子爵夫人とよくお話して、僕が大事にお預かりします」
アルブラートにとって、ザキリスは養父であったが、自分の父だと思いながらも、その存在は非常に大きく、実に多様な想いを重ね合わせていた。ザキリスは、腕利きの外科医であり、自分の危機を救い、人生を安定させてくれた人であり、財産家でありながらも、貧しい人々の医療費を免除してくれる稀有な寛大な人であり、また詩や音楽や文学に詳しい知識人である―
そのことをいつも感じているアルブラートは、ザキリスが自分を養子に迎えてくれたのが信じ難かったし、こんなに優れた人の息子である自分自身は、取るに足らない者と思っていた。そのために、医師を親しげに「お父さん」と呼ぶのは、とてつもなく恥ずかしく、勇気がいることだった。
だが、「お父さん」と口に出して呼べる人が自分にいる―そのことを思うと、胸がいっぱいになり、自然に涙が頬を伝って零れ落ちた。
ザキリスは、自分の実の子ができたことに、素直に喜びを表現してくれたアルブラートへの愛しさがますます膨らんだ。また、彼が涙を流しているのは、自分に子が授かったことへの感動のためだと思い、目を細めて、この若者の、褐色に輝く若々しい顔をじっと見入った。
アルブラートのパリへの渡航手続きは、その年の1月下旬にすべて済んだ。それまでのほぼ2週間で、アルブラートは、デュラック氏が送ってくれた楽譜すべてを読み終わり、基本は全部覚えてしまった。彼にとって、西洋音楽の楽譜は、最初は読んでいて興味深い記号の羅列であったのが、最後には美しい音楽を奏でる大事な宝物になっていた。
ヴァイオリンの楽譜は、まず最初に夢中になり、3日ほどで、ほぼその概要を覚えこんでしまった。ピアノの楽譜は、やや抵抗があったが、読み進むうちに、昔の恐怖は薄れ、ショパンやバッハの曲の解説に魅了され、いつしか、それらの曲を自由に演奏できたらどんなに素晴らしいだろうと思うまでになった。
渡航準備も済んだ1月25日、アルブラートは、ザキリスがクラシックのレコードを何枚も持っていたことを思い出し、ショパンやバッハなら何でもいいから聴いてみたいと相談した。医師は、ステレオのある部屋に彼を案内し、レコードの聴き方を説明した。
「まずステレオに電源を入れるだろう。そして、ここにレコードをセットして、針をそっと回転しているレコードに落とすんだ。曲が終わると、自動的に針はもとの位置に戻るからね」
アルブラートは、ショパンの「幻想即興曲 作品66」をセットし、わくわくしながら、針を静かに下ろした。途端に荘厳な音が鳴り響き、激しいスピードでピアノが華やかに奏でられ始めた。彼は、その煌びやかな音の光に包まれ、大きな感動に身を委ねながら、その曲をじっくりと聴いた。
その曲が終わると、再びレコードに針を下ろした。彼は、同じ曲を5回聴くと、今度は、バッハを聴こうと思った。レコードが整理されてある書棚を開けると、数十枚もあるコレクションの中から、バッハを探した。その中の1枚を抜き出し、レコードジャケットを何気なく見た途端、アルブラートは愕然とし、そのレコードを床に落とした。昔の悪夢の黒雲が彼を覆い尽くし、彼はその場に力なく座り込み、そのまま気絶してしまった。
アルブラートは誰かが勢いよくドアを開け、室内に入ってくる音に気がつき、意識が戻った。だが彼の目の前に立っていたのは、猟銃を構えたアルバシェフ大佐だった。アルブラートは震え上がり、その場から逃げようとしたが、銃口が彼の些細な動きも逃すまいと狙っていた。
続いて、大佐の側に、黒いドレスに身を包んだ母マルカートが立っているのを見た。母は、後ろ手に縛られ、手錠を掛けられたまま、悲しそうに息子を見下ろしていた。
馬鹿な......!なぜ死んだはずのあの男がここにいるんだ......でも母さんは......?母さんもここにいる......じゃあ母さんは死んでいなかったのか......!
アルブラートは、勇気を奮い起こし、今が大佐を殺す絶好の機会だと決心すると、アルバシェフに話しかけた。
「その猟銃を俺によこせ......!俺が、母さんを撃ってやる......!」
すると、大佐は、ニタリと笑い、不気味な声で呟いた。
「お前も相当な凄腕と見える。よし、この女を一発で撃ち殺せ」
アルブラートは、大佐から猟銃を受け取ると、始めは母に銃口を向けた。母は、おびえた少女のように、よろけながら後ずさりした。だが、彼は、すぐさま銃口をアルバシェフに向け、素早く引き金を引いた。凄まじい音と共に、アルバシェフは口から血を吐き、その場にどうと倒れ、息絶えた。
アルブラートは、急いで母の手錠をはずし、縄を解いてやると、彼女の手を握って、その部屋から走り出た。
「母さん......!やっと自由になれたんだ......!早く逃げよう―アイシャを探しに行こう......!」
だが、マルカートは首を振って、その場を動こうとしなかった。
「駄目よ......もう遅いわ―アイシャも、もう死んだのよ、ムラート......
それに、私はこの城に閉じ込められて―アレクサンドルのお墓にもお参りできないのよ......私はあのバシリエフスキーが恐ろしいわ―アザゼルを捨てられそうで......グルジャーノフ家の財産を、すべてあの大公は私から奪ったのよ―」
そういう母は、いつしかオルガ・エレーナになっていた。アルブラートはぞくりとし、恐る恐る先ほどの部屋に戻ってみた。彼が殺したと思った大佐は、バシリエフスキー大公の遺体に変わっていた。
なぜ......!あの大佐を殺すことができたと思ったのに......それじゃ―俺は―母さんと、アルメニア大公まで殺してしまったのか......!
アルブラートは、その部屋を走り出し、廊下に出たが、もはや母も、アルメニア大公妃もその場にはいなかった。彼は、母を呼びながら、廊下を走り続けた。だが、曲がり角で、誰かが自分の腕を掴んだ。その人物は、抱きかかえるように、彼をソファーに寝かせた。アルブラートは、その人が誰とも分からず、ただ、相手の胸に顔を埋めて、全身を震わせながら泣き叫んだ―
「......本当に申し訳ないことをした......アルブラート」
その声の主は、ザキリスだった。アルブラートは泣き腫らした顔で、医師を見上げた。彼は息が苦しく、心臓が恐ろしいほど激しく脈打っていた。何かを言おうとしたが、唇が思うように動かなかった。
彼は、数時間ほど眠り、再び目を覚ました。その部屋は、ザキリスの書斎だった。アルブラートは、別の部屋で、自分がレコードを聴いていたことを思い出した。しかし、その後、気を失い、何もかも分からなくなった―それから母と話をしたが、あれは夢だったのかと気づくと、途端に心が乱れ、絶望感に打ちひしがれた。
あの男が......あんな男がバッハのピアノ曲を弾いていただなんて......畜生......!けだもめ......
●Back to the Top of Part 18
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月14日分)
- (2024-11-27 23:49:17)
-
-
-

- 読書
- Wedge 2024年10月号 読了
- (2024-11-27 22:33:15)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- ちょっと気味の悪い話をしますが最近…
- (2024-11-25 12:21:24)
-
© Rakuten Group, Inc.



