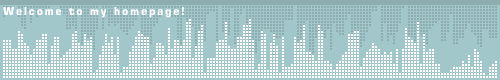音円盤アーカイブス(5月6月)

DUからつい最近購入したテナーカルテット盤で、HPで試聴してそのスタン・ゲッツを思わせる艶やかなトーンと、歌心溢れるアドリブにこれはいけそうだと判断して買い上げた。
おおっ!ショーターの「ぺネロープ」も演っているではないか!
1曲目はケニー・バロンの名曲「VOYAGE」ときた。こんなところからもJOE ROBINSONというテナー奏者がゲッツつながりなのが、垣間見れる。
アウトしたフレーズを使わず、中音域から高音域にかけてゲッツによく似た音色で端正なスタイルで吹奏するので、早いフレーズも一音一音はっきり聴こえてきてそんなところからもとても歌心のあるプレイヤーなのが分かる。
3曲目のバラード「IN TIME」ではその非凡な表現力の真価が発揮される。
このレコーディング時(2001年)40歳だったというが、このバラード表現には一本とられた。若すぎても、年老いてもできない、まさに男盛りの今しか吹けないような、苦みばしって渋くハードボイルドなんだけれども、ほんのりした甘さが見え隠れする極上のナンバー。
JOE ROBINNSONは1982年にサキソフォンを始め、1984年にカンタベリーからロンドンへ移住して、自身のグループの他スタン・サズルマン、トミー・スミス、ウィントン・マーサリス、テレンス・ブランチャード、カーク・ライトシー、ピーター・キング、などと共演した経歴があり、学校で音楽の講義も受け持っているという。
ピアノのJOHN DONALDSONはイアン・バラミーのグループに在籍していたこともある有能なピアニスト。
このアルバムでもソロにバックに活躍している。
惜しむらくはリズムがベース、ドラムとも少し弱いか?
もっとも自己主張の強いリズム隊だと、フロント主導型のバランスが崩れてしまうわけで、そこらへんが微妙なんですけど・・・
6曲目のショーター「PENELOPE」のカバーは珍しい。他にあまり聴いた記憶がない。
先の5曲とは曲調のためか、ROBINNSONの表現も幾分ミステリアスな成分を含んでいる。
全7曲、7曲目は5曲目のセカンドテイクなので、CDで40分ちょっとは短いような気がするが、演奏が充実しているのでこのくらいの収録時間で充分満足できると思う。
メンバーはJOE ROBINSON(TS)JOHN DONALDOSON(P)SIMON THORPE(B)SPIKE WELLS(DS)
録音は2001年8月12日

去年の春先、駅前の「グルーヴィン」で安く手に入れた。
冴えないジャケットのクレジットを見て即買いを決め込んだ。
DAVE LIEBMAN,PAUL BOLLENBACK,TONY MALABY,ERIC FELTEN ,DREW GRESS等有名どころが参加。製作が1992年となっている。というと有名どころもリーブマンを除いて、今ほど名が知れていない比較的初期の演奏が記録されているなという計算が働いた。
スタンダードが結構入っている。
トニー・マラビーがスタンダードをどんな風に料理しているのであろう?
家に帰って早速プレイボタンを押してみる。
様々なフォーマットで演奏されているのであるが、デイブ・リーブマンとトニー・マラビーに焦点を絞って聴いてみた。
リーブマンがソプラノサックスで3曲、クインテットで演奏されていて、トニー・マラビーの方はTP,TB、G,にスリーリズムのセプテットの編成。
リーブマンが「BEAUTIFUL LOVE」とリーダーCRAIG FRAEDRICHのオリジナル2曲、トニー・マラビーが「SO IN LOVE」「SOCIETY RED」「WHAT IS THIS CALLED LOVE」他1曲を演奏している。
リーブマンはいつもの如くクロマティックなラインを織り交ぜながらメロディック、ハーモニック、リズミック三つの面からアプローチを試みて緩急自在なプロフェッショナルなソロを展開している。リーダーのトランペットはアップテンポのオリジナル曲で冴えをみせているが、リーブマンとの力量の差を正直感じると言わざる得ない。
トニー・マラビーは10年以上前から今の吹きすさぶと形容してよいようなスタイルを既にこのレコーディング時に持っており、個性的なトーンでもってオリジナルなプレイを展開している。もっとも今なら吹かないような、フレーズ、ジャズ演奏でのクリシェなんかが入っていて微笑ましい。
現在の姿を認識しているからというのもある程度言えるのかもしれないけれども、やはりビッグネームや話題のミュージシャンは若手の頃や下積み時代の演奏にもなにか他と違うきらっと光る個性を持っているのだなぁと思った。
1992年作品 WASHINGTON D.C.
 HOT HOUSE RECORDSから1985年にリリースされたレコードで、10年以上前に岡山のLPコーナーで買った。大好きなチャールス・マクファーソンとダスコ・ゴイコヴィッチがメンバーに入っていたからに他ならないのであるが、ベースのLARRY GRENADIERの最も初期の録音(ひょっとして初吹き込み?)プレイが収められているレコードでもある。
HOT HOUSE RECORDSから1985年にリリースされたレコードで、10年以上前に岡山のLPコーナーで買った。大好きなチャールス・マクファーソンとダスコ・ゴイコヴィッチがメンバーに入っていたからに他ならないのであるが、ベースのLARRY GRENADIERの最も初期の録音(ひょっとして初吹き込み?)プレイが収められているレコードでもある。1曲目は「BLUES FOR RED」レッド・ガーランドに捧げられた曲だと思う。
LARRY VUCKOVICHのピアノタッチにガーランドの影響が強く窺えるので、間違いないだろう。実際、歯切れがよく軽快なタッチとブロックコードの多用がガーランドを連想せずにいられない。まずは腕試しといった感じの後は、マクファーソンの「FEEBOP」に続く。
ゴイコビッチとマクファーソンの二菅で演奏されて、快活でありながら両者ともベテランらしい余裕を感じさせるプレイでソツのなさを見せつける。
ゴイコビッチはこの頃の方が現在のプレイよりハードな印象で、反対にマクファーソンは音色が現在の方がより肉厚なトーンになった様に感じる。録音のせいかもしれないけど・・・。
3曲目はスローテンポで「INVITATION」をピアノトリオでプレイ。
アル・ヘイグの同曲が名演で有名だけれども、ブコヴィッチの演奏もなかなか捨てた物じゃないです。でも、ここは、マクファーソンのアルトをフィーチャーして聴きたかったのが本音のところです。
4曲目はVUCKOVICHのオリジナル作で、中近東の旋律っぽいテーマが二菅で奏された後、ピアノ、アルト、トランペットとソロが続く。モードでアドリブを取っているマクファーソンやゴイコビッチは最近のプレイではあまり聴けないとおもうので、少し珍しいといえるか?
5曲目はバラードメドレーでマクファーソンが「EMBRACEABLE YOU」ブコビッチが「LUSH LIFE」ゴイコビッチが「YOU DON`T WHAT LOVE IS」を演奏していて、この辺が最も各人の持ち味が発揮された演奏だと感じる。
ラストの「星影のステラ」では、ラリー・グラナディアがテーマを取るが、ここもマクファーソンにテーマを演奏してほしかったところ。アドリブはしっかりとっています。
触れなかったがEDDIE MARSHALLも歯切れのよいシンバルワークでセッション全体をしっかりサポートしていると付け加えておく。
録音は1983年8月26,27日1984年12月27日

昨年の2月にDUから通販で入手したCDで、トランペットワンホーンものなので、どんなものかなぁと買ってみた。ピアノの替わりにギターが参加したカルテット編成。
TORE JOHANSENは1977年生まれのノルウェーの若手トランペッターでトロンハイムの音楽学校で1996年から2000年にかけてジャズを学んだ経歴の持ち主。
このアルバムは3枚目のリーダーアルバムで、このアルバムに参加しているギタリストHALLGEIR PEDERSENとドラマーROGER JOHANSENのオリジナル作品とスタンダード「IF I SHOULD LOSE YOU」「A NIGHTINGALE SANG IN BERKELY SQUARE」「EVERY TIME WE SAY GOODBYE」、チック・コリアの「WINDOES」が収録されている。
バンドのメンバーは全員70年代生まれと若いが、彼らの音楽的嗜好はこのアルバムを聴く限りオーソドックスな4ビートジャズ中心のメインストリームなものの様だ。
TOREのトランペットは北欧の清楚でマイナスイオンをたっぷり含んだ空気の様に、爽やかで気持ちよい。
音色にジャズ奏者が一般的に持っている陰りやくぐもったところ、ダークネスな部分があまり感じられない。かといって明るいわけではなくて、朝靄のような乳白色した印象といったところか。
スタイル的にも実直で難しいプレイはあまり行わない。
聴いていて悪い気はしない・・・が個人的にはもう少し汚れたというか、捻くったところが音色的にも、スタイル的にもあった方が好みなのは私が古い人間なのか?
時々棚から取り出して聴きたくなるアルバムなので、好きな部分もあるのだけれど・・・
メンバーはTORE JOHANNSEN(TP)HALLGEIR PEDERSEN(G) OLE MORTEN VAGAN(B)ROGER JOHANSEN(DS)
録音は2002年7月22日

今月になってDUから通販で入手。
好きなツーテナーもので、おまけにピアノレスなので二人とも思いっきり暴れてくれている。ドラムはジム・ブラックで4ビートプレイがたっぷりと聴ける。
NYダウンタウン派のエラリー・エスケリンがこのリーブマンとのセッションでどういう演奏を繰りひろげているかがキーポイントのCDだと思う。
エスケリンは思ったよりまとも?なプレイを展開している。
アドリブに入るとリーブマンに比べるとやや抽象度の高いフレーズが入らないことはないが、むやみやたらに音を外したりフリーになることも無く、楽曲に沿ったプレイを展開。
エスケリンは、hatLOGYで現在展開している自身の音楽での非常にオープンフォームなタイプの演奏でアブストラクトな音色の変化が感じられる多彩な表情をみせてくれているが、こういうストレートな楽曲(タッド・ダメロン「GNID」や「WHAT IS THIS THINGS CALLED LOVE」)でのプレイもそういう自身の持ち味を残したままオーソドックスなプレイスタイルも立派にできる事を証明したと思う。
最もエスケリンの曲、3曲目「YOU CALL IT」などはフリータイプの演奏でエスケリン以上にリーブマンの血管ぶち切れプレイが聴ける。
5曲目の「WHAT IS THIS THING CALLED LOVE 」はコニッツの「SUBCONSCIOUS LEE」(リーブマン)とタッド・ダメロン「HOT HOUSE」(エスケリン)が同時に吹奏されて、スリリングであるとともに種明かしがされているようで、ジャズを聴くことの満足感を味わえる1曲だと思う。
7曲目ではウェイン・ショーターの「VONETTA」が演奏されている他はリーブマン、エスケリンの楽曲。
この種のバトルセッションはお手のものであるリーブマンに充分引けをとらない演奏を展開しているエスケリンのプレイは特筆されてしかるべきものがあると思う。
リーブマンとエスケリンのことに終始してしまったが、リズムセクションの素晴らしさも付け加えておきたい。
特にジム・ブラックの4ビートプレイの素晴らしさに感服した。
この人どんどん凄くなっていてこういうストレートなプレイでも大物の風格を見せるようになってきていると思う。
メンバーはDAVE LIEBMAN(TS)ELLERY ESKELIN(TS)TONY MARINO(B)GIM BLACK(DS)
録音は2004年5月30日 NYC

オランダの若手女流アルト奏者のリーダー作品。
GWに「ノルディックサウンドヒロシマ」に頼んで入荷してもらった。
オランダの女性アルト奏者というと、ジャズではキャロリン・ブロイヤーが有名だが、このTINEKE POSTMAもひけをとらない有望な人材。
このアルバムではクリス・ポッターが賛辞を書いている。
アルトの音色はダークネスな成分を含んだジャズ向きのサウンドで、フレーズもストレートで淀みなくよく歌ったもので好感が持てる。
ピアノのROB VAN BAVELにフェンダーローズを弾かせてこれが、楽曲を活かしていて好印象を抱かせるアレンジになっている。
このデビューアルバムでも自身のオリジナル曲を中心に演奏しているが、1曲目や5曲目などミディアムからアップテンポの曲に魅力を感じる。楽曲の中に俗っぽくならない程度にキャッチーでポップなメロディーを挿入しているところにが、上手いと思う。
ジャズは曲や演奏が分かりすぎても面白くないし早く飽きがくる。反対に難しすぎても馴染むのに時間がかかったり挫折して聴かなくなるケースが多い。
TINEKE POSTMAはその辺の塩梅が良くわかっているのか、微妙なバランスでジャズ入門者もベテランのファンも納得させる結構イイ曲を書くと思う。
メンバーはTINEKE POSTMA(AS,SS)ROB VAN BAVEL(P,EL-P)JEROEN VIERDAG(B)MARTIJN
VINK(DS)
録音は2003年4月19,22日
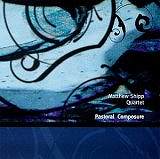
MATTHEW SHIPPをちゃんと聴くようになったのは、実はとても遅くて21世紀になってから。(リーダーアルバムという意味)「OUT THERE」誌上で結構話題にされていたし、どんなピアニスト、音楽家なのか気にはなっていたのだが、聴いた事はこのCDをN山さんから借りるまでなかった。
この時全部で4枚マシュー盤を借りて聴いてみた。
この作品以外はhatLOGYでトリオのものや、ジョー・モリスとのデュオも良かったのですが、自身のレーベルという事で、THIRSTY EARのこの作品を選んでみた。
マシューのピアノはタッチが重い。ヘビーウェイト級の筋肉の躍動感、パワーを嫌でも見せつけられる。
身体能力の差というものを、管楽器やドラムなどの打楽器ではないのにこれほど感じさせるピアニストはここ最近ではマシュー・シップが筆頭に上げられると思う。
2曲目の導入部のよじれた感じで入ってくるラインなど、聴いていてゾクッと来るぐらいかっこいい。
マシュー・シップの面白いエピソードをひとつ。
一日に何度も自分のレコードを置いているレコードショップに売れたかどうかチェックしにくるそう・・・今はどうか知らないが・・・
マシューの音楽は多様性に富んでいて、その全貌は未だに私は分からないのだけれども、
こういうストレートな演奏でもとても個性的なピアノを弾いて非常に才能のあるミュージシャンだと思う。
このアルバムではROY CAMPBELLがマシューの音楽をよく理解した鈍い輝きを発したトランペットを吹いていてアルバムの出来に貢献している。
勿論、WILLIAM PARKER,GERALD CLAVERのリズム隊といっていいのか?有機的なパルスを常に発信し続ける鉄壁なサポートなのは言うまでもない。
録音は2000年1月6日 NYC
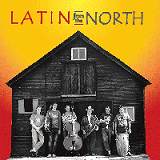
去年のGW明けに倉敷の「レコード屋」で買ったもので、\690でこの時は10数枚珍しいCDを買い込んだ。通常のプライスだったら、このような存在を全く知らないCDは買うのに勇気を要するけど、\690だったし、曲もカル・ジェイダー、ジョビンの「白と黒のポートレイト」、ショーティー・ロジャース、ヘルメート・パスコールの曲、「TANGERINE」などをやっているので、少し期待して買ったのだと思う。
PLAZA JAZZ TRIOというトランペット、サックス、パーカッションの編成でラテンを演奏するグループとSTEKPANNAという北欧のギタートリオの全く別のふたつのトリオが合体して一つのグループになったというユニークなグループ。
そんなバンド結成までのヒストリーが信じられないほどしっくりした一体感のあるバンドサウンドになっていて、躍動感溢れるラテンサウンドが繰りひろげられている図式。
ギターのMADS KJOLBY OLESENはフィンランド出身のギタリストでそのプレイは、そのせいかスタイリッッシュでクールな印象を受けて、全体のバンドカラーの舵取り役、制御装置の役割を担っているように感じる。
GEORGE HASLAMの轟音バリサクや活きのいいペット、グルーブしまくったパーカスを北欧勢(ベースはスコットランド出身だが)のギタートリオ隊が微妙なコントロールを施してトータルサウンドとしてのバランスを保っているように思える。
5曲目MADS OLESEN作曲の「MATUSALEM」はそんな北欧のひんやりした空気感とラテンのホットネスがうまくブレンドされた彼らのバンドサウンドの特徴がよく顕れた曲だと思う。
6曲目の「タンジェリン」もクラブのフロアで映えそうないい仕上がり具合。
こんなCD、あの時「レコード屋」に寄らなかったら一生知らず仕舞に終っていただろう。
そう思うと一枚の作品との出会いは一期一会なんだとつくづく思うのであります。
メンバーはSTEVE WATERMAN(TP,FLH)GEORGE HASLAM(BS)MADS KJOLBY OLESEN(G)
STEVE KERSHAW(B)ROBIN JONES(PER)PETTER SVARD(DS)
録音は2003年4月17日 OXFORD
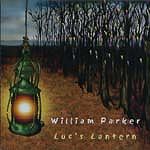
WILLIAM PARKER(B)
ERI YAMAMOTO(P)
MICHAEL THOMPSON(DS)
1 ADENA
2 SONG FOR TYLER
3 MOURNING SUNSET
4 EVENING STAR SONG
5 LUC'S LANTERN
6 JAKI
7 BUD IN ALPHAVILLE
8 CHARCOAL FLOWER
9 PHOENIX
10CANDLESTICKS ON THE LAKE
RECORDED BROOKLYN NY 2005年作品
アマゾンでWILLIAM PARKERを検索してみるとペーター・ブロッツマンのリーダー作なんかも含めてだが33件と思いのほか多作で、録音が多い。
このマシュー・シップ主宰のTHIRSTY EARやAUM FIDELITY,LEO等フリージャズ~アンダーグラウンド系レーベルが主な吹き込みレーベルなんだけれども、どの作品を聴いても信念を曲げない一貫した音楽が展開され、その音楽の中心には自身のぶっといベースサウンドがサウンドの中核を形成しているのは言うまでもない。
パーカーの入ったレコードは今から4半世紀以上前に、だいぶ前になくなってしまった梅田の「大月楽器」で「生活向上委員会ニューヨーク支部」(自費出版)を買ったのが最初で、ジャケには梅津和時や原田さんと一緒にパーカーも写っているんだけれど、皆凄く若く、モノクロのピンぼけ写真が自費出版のレコードだということを感じさせる。
それからは、やはりデビッド・S・ウェアの作品でパーカーのプレイを耳にし続けてきた。その轟音でありながらソリッドなベースプレイはデビッドの音楽に今では必要不可欠なサウンドと言っても過言でないだろう。パーカーのベースじゃないと音楽がパワー不足に陥って推進しないような気がするのだ。
前置きがながくなったけれど、この新作はピアノトリオ作品で日本の山本恵理がピアノを担当している。関西を中心に活躍している新進ピアニストで生演奏は実際聴いた事がないのだけれど、このCDで素晴らしいプレイを展開している。
1曲目「ADENDA」のテーマから今までのパーカーの音楽からは想像できないメロディー、甘口加減に?マークが最初は頭に浮かぶのだけれど直ぐにその音楽の素晴らしさに耳を奪われる。
寺島さんが先日、SJ誌で言ってくれた。「きれいなサウンドだけのヨーロッパピアノトリオはもう終わりにしようではないか!」
もちろん、ヨーロッパのピアノトリオにも素晴らしいものが現在もリリースされてはいるが、美メロで美しいだけの演奏で、心にひっかかるメッセージが少ないものも、乱売されている状況。ベテランピアニストの作品や日本企画のピアノ作品に特にそれを私は感じる。ジャズの演奏はそのプレイの中に行間の音というか、プレイヤーの生き様や哲学、信念みたいなものが音のメッセージとして聴いて何か心に引っ掛かる、伝わってくる演奏じゃないと聴いている意味が私はないと思うのだ。
この作品はそういう日本企画のピアノトリオをこぞって買っている方に、一度心を真っ白な状態にして聴いてもらいたい。
一音、一音の音の情報量、パワーが全然違うと思う。お仕着せ企画でないミュージシャンの本当に演りたい音楽(プロデューサーはある意味必要だと思う)を捕らえた作品に勝るものはないのだ。
このウィリアム・パーカーの新作はそういう意味でパーカーの違った側面(メロディーや情緒)にスポットが当てられた興味深い一作だと思う。

今や中堅テナー奏者になったラルフ・ムーアの20年前の作品で、新譜でリリースされた時に岡山の「LPコーナー」から通販で買ったもの。
最近は以前の様なリーダー、サイドマンとしてのレコーディングも一段落したのかアルバムクレジットにラルフ・ムーアのクレジットを見る機会が減ってしまったように感じるが、このアルバムが吹き込まれた80年代半ばから90年代半ばにかけて、CRISSCROSS,RESEVOIR,LANDMARK,CONCORD,MONS、DREFUYS等リーダー、サイドマン参加作が頻繁にリリースされていた。
ラルフのテナーサウンドは男性的なたくましくよく引き締まったトーンでアップテンポ、ミディアム、スロー、つまりブルースやバラード何でも難なくクリアする技量をもちあわせ、共演ミュージシャンからの信頼も厚いタイプだと言えよう。
唯、注文をつけるとすれば、あまりにもソツなくこなしすぎるのではないかという点。
プロフェッショナルとしての仕事は充分過ぎるほど完璧に為し遂げるのだけれどそれから先のもう一歩踏み込んだプレイがこの人の演奏には見受けられないのだ。
楽器の表情にももう少しニュアンスというか、柔軟性があってもいいと思うし、プレイスタイルももう少し冒険するようなところがあってもいいのではないかと思うのだ。
実力はあるのだからこのままでは、惜しい気がする。
近年のベン・ライリーの作品でテナートリオ盤にムーアが入っていたが基本的にこの頃とスタイルはほとんど変化していない。
それが個性だと言われればそれまでだが、なにか勿体無いような気がするのは私だけだろうか?
まだまだ、現役バリバリの年代なのだから、自分がジャズ界を牽引するくらいの心意気で
もうひと暴れしてくれる事を願う。
黒人メインストリームテナーのムーアみたいなタイプは意外と少ないので、もっと頑張って欲しい。
メンバーはRALPH MOORE(TS)BRIAN LYNCH(TP,FLH)KEVIN EUBANKS(G)BENNY GREEN(P)
RUFUS REID(B)KENNY WASHINGTON(DS)
録音は1985年12月21日 VAN GELDER RECORDING STUDIO N.J.
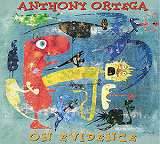
伝説のVANTAGE盤が50年代初頭のはずだから、約40年後の録音ということになる。ANTHONY ORTEGAは伝説でもなんでもなく、現役バリバリで活躍していたのだった。
フレッシュサウンドから出たVANTAGEの復刻盤を10数年前に聴いた時、衝撃を受けた。
パーカー周辺のビバッパーとは、一線を画する突然変異的というか、異端と言うか、宇宙人というか、何か変なのである、エキセントリックなのだ。
ドルフィーがジャズシーンに現れる何年も前にこんなアルト奏者がいたことに驚いた。
60年代にはフリージャズに傾倒して、その頃の演奏はhatLOGYから何枚か出ているらしいけど残念ながら未聴である。
このアルバムでは再びメインストリームなジャズに戻ってきたオルテガの演奏が録音されている。
スタイル的には誰のスタイルでもないオルテガ自身のオリジナルな語法を持っているのが
凄いと思う。そして本質的に50年代のVANTAGE盤の吹き込みの頃と変わっていないのがもうひとつ凄い!
2曲目「AVIGNON」でのホリゾンタルで思索的、ハイブロウなソロはまさにワン&オンリーなものだ。映像美やメランコリーの要素も感じ取れる。
3曲目のアップテンポの曲でもいくつになるのだろう?年齢を全く感じさせないフレッシュで多感でアバンギャルドな構成美に溢れるオリジナルな解釈は、聴いていて惚れ惚れする。
ピアニストのMANUEL ROCHEMANが全編に渡って心憎いサポートを行っていてアルバムの出来に貢献している。
4曲目はソプラノサックスによる美しいバラード。
6曲目「MOON'S AGO」もすこしラテンのテイストが入った出色のバラード。
ムーディーになったり、アブストラクトになったり、メランコリックになったり、ドルフィーのように馬の嘶き系の音を突然発したり、変幻自在の吹奏に圧倒され納得させられてしまうのである。
ラストは唯一他人の曲で、マル・ウォルドロンの「WARM CANTO」。
バスクラのSYLVAIN KASSAPが入り、オルテガはフルートをプレイ。
メンバーはANTHNY ORTEGA(AS,SS,FL)MANUEL ROCHEMAN(P)DIDIER LEVALLET(B)
JACQUES MAHIEUX(DS)
録音は1992年4月6日

先週末、広島駅の地下街で大きめの中古市が開催されて、地元の「グルーヴィン」の他に仙台「ディスクノート」や富山「レコードマーケット」など有名店の出店があったので行ってみた。
土曜日の夕方で結構、黒山の人だかりが出来ているではないか。
会場への歩が自然と速くなる。
1時間ほどかけて会場のJAZZコーナーのCDをひと通りチェックして、小脇に抱えた十数枚の選定作業に入る。予算は一万円以内と決めていたので約半分に絞り込まなければならない。こういう時は名前を知らないミュージシャン、知らないレーベルやアルバムを買う方を優先する。ハズレも時々あるけど、思わぬ素晴らしいCDやミュージシャンを発見することが、今まで多々あるからだ。
結局8枚買って8千円ちょっとだったので、結構いい買い物ができた。
このCDは最後の最後まで買おうか止めようか迷っていたのだけれど、DISKNOTEの店員さんの薦めもあって買う事にした。
チェコのジャズなどほとんど聴いた事がないけど、ショーターの「UNITED」を演っているのを聴きてみたいのも買った理由のひとつ。
ハモンドオルガン、ギター、ドラムスからなるトリオ演奏のCDで、一部ボーカルが加わる。
ギターのROMAN POKORNYはとても歯切れのいいよく歌うプレイを信条とするテクニシャンだ。ブラインドで聴いたならおそらくSAVANT、HIGHNOTE,MUSE,HALFNOTE近辺のレーベルに吹き込んだアメリカのミュージシャンによるものだとほとんどの人が思うだろう。
彼らが中欧の人間だと思わせる要素は演奏される音楽からは皆目見出す事が出来ない。
それほど、本場のJAZZの匂いに溢れたプレイを展開していて、片や国民性、ナショナリズムに溢れた個性的で優秀な作品が様々な国々からリリースされる一方こういう具合にグローバル化されたというか、アメリカのジャズと聴いていてなんら違和感を感じない等レベルのメインストリームジャズがあまり馴染みのない国からも発表されるという現状に、現代ジャズ界の二分化現象を感じる。
3曲に男性ボーカルが入るが、その曲ではエスニックなテイストが感じられ、南の島の風が吹いてくるような曲調でアルバムのアクセントになっている。
メンバーはALBERTO MARSICO(ORG)ROMAN POKORNY(G)PAVEL"BABY"ZBORIL(DS)
DAN BARTA(VO)
録音は2002年5月
レーベルのHPがあり、アルバムが試聴できるのでアドレスを載せておきます。
興味のある方は聴いてみてください。
www.arta.cz
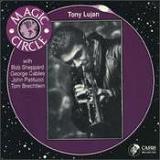
昨日と同じく先日の中古市で買ったCDで、バックのメンバーの名前で興味を持った。
BOB SHEPPARD,GEORGE CABELS,JOHN PATITUCCI,TOM BRECHTLEINという豪華な顔ぶれで、リーダーのTONY LUJANだけが無名。
ジャケのデザインもダサくて最初オールドジャズのオムニバス盤かなんかかなと思ったぐらい。メンバーのクレジット見過ごしていたら1秒後には次のCDに目が移っていただろう。
1曲目から結構ゴリゴリのモードサウンドで特にジョージ・ケイブルスのプレイが冴えている。TONY LIJANはクラーク・テリーが率いるALL-STAR YOUTH BIG BANDのトランペットセクションの一員として全米とヨーロッパを巡業したそうで、その後はラスベガスでフランク・シナトラやトニー・ベネットのバックバンドで演奏したり、ジョニー・グリフィン、テテ・モンテリュー、ブランフォード・マルサリス、ジョージ・ケイブルス、クリス・ウッズと共演したりレイ・チャールス、ジェラルド・ウィルソン、ビル・ホルマンのビッグバンドで活躍した経歴の持ち主。
このアルバムはLUJANのファーストアルバムであり、一曲を除いて全曲自身の作曲による力の入れよう。当然演奏にもガッツが漲っていてフレディー~ウディー・ショウラインの活きのよいプレイが収録されている。
BOB SHEPPARDやGEORGE CABLESの演奏もリーダーのやる気に感化されたのか今日のより成熟したイメージのプレイよりずっとアグレッシブなプレイをしていて全体のバランスが整っている。
TONY LUJANはその後もリーダー作をコンスタントにリリースしていて日本ではほとんど知られていない人材でも結構聴かせるプレイヤーがまだまだたくさんいることを実感させる。
1990年作品

7,8年前に中古盤で手に入れたもので、ツートロンボーンもののCD。
ツートロンボーンと言ったらJ&Kが最も有名だが、このアルバムではANDY MARTINがスライドトロンボーンを、MIKE FAHNがバルブトロンボーンを吹いている。
1曲目ショーターの「ONE BY ONE」からジャズを聴いている幸福にひたれる。
リーダーのDICK BERKはじめ全員があまり名前の知れたミュージシャンではないけれど、チームワークとアレンジの勝利というか、エンターテイメントの精神溢れる満足度の高い作品となっている。
フロントのトロンボーン二人のそれぞれの楽器特性を活かしたソロのやりとりが、素晴らしく聴いていて楽しい気分を味わえる。
「MOANIN'」のグルービーなフレーズの応酬、テーマの合奏もツートロンボーンだと新鮮に聴こえる。
5曲目ベーシストのPHIL BAKER作曲「GUANTANAMO」は灼熱の太陽に照り付けられた土の匂いと乾いた空気を感じさせるアフロテイストの入ったラテンナンバー。
クラブのフロアなんかでプレイしても盛り上がるんではないかな?
6曲目は「LESTER LEFT TOWN」ピアニストTAD WEEDがテーマを取る。
軽快なアクションと歯切れのよい指捌きでフレーズを弾きこんでいく奏法に好感が持てる。
8曲目はトム・ハレルの名曲「SAIL AWAY」。
全員の一体感溢れる誠実な演奏ぶりが気持ちいい。
決して一般的な意味での名盤ではないけれど、時々棚から出して無性に聴きたくなる個人的B級グルメ盤といえよう。
メンバーはDICK BERK(DS)ANDY MARTIN(TB)MIKE FAHN(TB)DAN FAEHNLE(G)
TAD WEED(P)PHIL BAKER(B)
録音は1995年10月26日

アルゼンチンのピアニストSANTOS CHILLEMIの1990年作品。
去年11月ディスクユニオンの通販で購入したもの。
バックのメンバー(EDDIE GOMEZ,PETER ERSKIN,LOUIS SCLAVIS)で興味を持ってどんな音楽が展開されているのか荷物が届いて真っ先に聴いてみた。
SANTOS CHILLEMIのピアノ、EDDIE GOMEZのベース、PETER ERSKINEのドラムスのトリオにERIC SEVAのサックスが5曲、LOUIS SCLAVISのクラリネットが2曲、JUAN-JOSE MOSALINIのバンドネオンが2曲で参加している編成。
そんな小編成のグループであるにもかかわらず、飛び出してくる音楽は極めてカラフルだ。音の万華鏡、メリーゴーラウンドと言ったら良いのだろうか、トラックが進みにつれどんどん、音の表情が変化していく。
色彩感や光の陰影、遠近法そういう絵画的な美術面を感じさせるサウンドスケープが展開される。
スクラヴィスはじめ強力なインプロバイザーを上手く自身の作品(パレット)に有能なソロイスト(絵の具)として使いこなして理想の音楽(絵)を作り上げている。
かってチャールス・ミンガスがやったのと同じ様に、自身の音楽を表現するにあたり強者の個性を最大限に発揮させつつ自分の思わんとするサウンドにフィットさせていく方法が
見事な形で展開されているのではないか?
一聴とっつきにくい音楽に感じるかも知れないが、奥行きの深いカラフルで表現力に溢れた強力な音楽が展開されていると思う。
録音は1990年10月11日~14日 NYC

2003年秋にアマゾンから購入したCDで、ANGELICA SANCHEZがこのアルバムにも参加しているトニー・マラビーの奥さんであるのはつい最近知った。
ANGELICA SANCHEZはメキシコ系アメリカ人でサウスフェニックスで育った。
最初の音楽体験はエルトン・ジョンやボーイ・ジョージなどで、ジャズとの出会いは高校生になってから。デイブ・ブルーベック、MJQ,マイルス、アントニオ・カルロス・ジョビンのレコードを聴いたらしい。
ピアニストとしては最初のアイドルはマリアン・マクパートランドであった。
アリゾナ州立大学でジャズを専攻したが、音楽を本当に学んだのは大学外での演奏活動であったそうだ。
彼女の作曲方法はこのアルバムでも実践されているようにメンバーの音楽性、個性を見据えて曲作りを行うというもの。
どおりでトニー・マラビーが吹奏するのにフィットする曲だと感じた訳だ。
彼女の曲は一聴捕らえどころの無い浮遊感覚溢れる旋律が多いので、一般的にはメリハリのない没個性的な曲とマイナス評価されがちかもしれないが、よく聴いていてもどこからが作曲でどこからがアドリブなのか境が分かり難い構造の曲になっていてそこが狙いのひとつなのではないかと思う。
ウェイン・ショーターが最新のインタビューで「音楽には聴こえない音楽を作りたいんだ」という発言をしていたが、ショーターの音楽もコンポジションとインプロビゼーションの垣根を取り払ったサウンドを指向しているように感じた。
この両者の目指しているサウンドは意外と共通する部分があるのかも知れない。
そして一聴感じるのは、機嫌でも悪いんじゃないだろうかと思うような簡単に入り込めない取っ付き悪いサウンドが展開されている点ではないだろうか?
メンバーはANGELICA SANCHEZ(P)TONY MALABY(TS)MICHAEL FORMANEK(B)
TOM RAINEY(DS)
録音は2001年6月24日 NYC

一昔以上広島駅前の「レコードステーション」で中古で安く手に入れたレコード。
ユルトルジュ自身のCARLYNEレーベルからリリースされたアンティーブジャズ祭でのライブ盤。メンバーがJEAN-FRANCOIS JENNY-CLARK,ALDO ROMANO,ERIC LE LANNと最高の顔ぶれで期待に胸が高鳴った。
ルネ・ユルトルジュのオリジナル「DIDI'S BOUNCE」から最高のジャズサウンドが流れてくる。テナーのJEAN-LOUIS CHAUTEMPSはジョー・ヘンダーソンとジョージ・コールマンを足して2で割ったようなアグレッシブでコクのあるプレイを披露。
エリック・ル・ランも負けじとバッピッシュなフレーズを連発。
そういうプレイはお手のものとリーダー、ユルトルジュも煌びやかなピアノを弾き、ジュニ・クラークとアルド・ロマーノはソロにバックに切り込み深く素晴らしいプレイを見せつける。
「SOLOR」のテーマをJEAN-FRANCOIS JENNY-CLARKが素晴らしいピッチカート奏法で奏でる。この人のベースプレイは聴いていて飽きることがない。ロマーノのレガートも凄くシャープでこの二人のリズムセクションのソリッドさと言ったら当時の最高峰ではないだろうか?フロントプレイヤーよりリズムに耳が奪われる曲。
モンクの「PANNONICA」はCHAUTEMPSのチャーリー・ラウズを一瞬彷彿させる。
ラストは再びユルトルジュの作品「RECIDIVE」。ロマーノのドラムソロに続いてテーマ合奏の後、ル・ランの味のある真のバップテイストが感じられるトランペットソロへ継がれる。ここでのル・アンのソロはそれくらい快心の出来で、このソロでこの作品の価値が高まったと言っても過言でない。
こんな最高の演奏を聴けたアンティーブの人達が羨ましい。
メンバーはRENE URTREGER(P)JEAN-LOUIS CHAUTEMPS(TS)JEAN-FRANCOIS JENNY-CLARK(B)ALDO ROMANO(DS)ERIC LE LANN(TP)
録音は1980年 ANTIBES
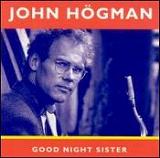
SITTELって知ってる?という他愛も無いダジャレが一部ジャズファンで流行った事があるけど、そのSITTELから1993年にリリースされたJOHN HOGMANというテナー奏者のCD。
出てから2年後の1995年の今頃岡山の「グリーンハウス」で買ったはず。
1曲目「THEODORE」ロリンズのファーストネームを引き合いに出すまでもなくフレーズや音色に50年代ロリンズがそのプレイに宿っているのが分かる。
全体的に保守的な50年代のハードバップやウエストコーストサウンド(HOGMANはバリトンを吹くとジェリー・マリガン・ライク)が展開されているのであるが、所々にアクセントで挿入されるシンセサイザーの装飾音にこれは現代の録音なのだと改めて実感する次第。
5曲目のボッサリズムの「A SENTIMENTAL GENTLEMAN」なども曲調から当時のサウンドだはありえないサウンド。
6曲目は良質なウェストコーストサウンドの再現。ULF JOHANSSONがサイ・タフ、JOHN HOGMANがリッチー・カミューカの役割を見事に演じきっていて彼らの力量がこの点からもよく分かる。7曲目はHOGMAN作曲のアルバム表題曲の甘い雰囲気のバラード。
7曲目もご機嫌なテーマをもつ4ビートハードバップワンホーン作品。
続いてチェット・ベイカーで御馴染みの「LOOK FOR THE SILVER LINING」対位法的なアレンジが再現される「I CAN'T BELIEVE THAT YOU'RE IN LOVE WITH ME」。
アルバムを聴き進めるにつれ、ハードバップよりウエストコーストよりのサウンドが多いことに気付く。3:7くらいの比率かな?
どちらのスタイルで演奏しても彼らの中でリアルタイムな音楽として愛情をもって演奏されているので、ナチュラルで説得力あるサウンドが展開されている。
ラストは再びシンセの響きをバックにHOGMANのよく唄うテナーサウンドとギターのリズムカッティングに彼らは現代のミュージシャンなのだと一人納得するのだ。
メンバーはJOHN HOGMAN(TS,BS,SYNTH)KNUD JORGENSEN(P)BENGT HANSSON(B)JOHAN DIELEMANS(DS)THOMAS ARNESEN(G)ULF JOHANSSON(TB)
録音は1992年10月12,13日 UPPSALA

フィンランドの新興レーベルTUM RECORDSから最近リリースされた作品。
AHMED ABDULLAHはサン・ラ・アーケストラ関係で名前は知っていたけれど、リーダーアルバムは所有していないし、参加作品もウィリアム・パーカーの新作のところで少し触れた「生活向上委員会NY支部」くらいしか持っていなかった。
TUM RECORDSのHPで全作品の1~2曲フル試聴できて、この作品も聴いて良かったので買う事にしたのだ。
このアルバムではジジ・グライス、オーネット・コールマン、セロニアス・モンク、フランク・ロウ、サン・ラと自身のオリジナルを演奏していて自らの60年代から現代までの音楽生活を振り返り俯瞰するような選曲がされている。
AHMEDのトランペットが鳴り響き演奏がスタートすると、どす黒くメラメラと鈍い光を発しているような情念を感じさせる60年代~70年代にかけての黒人ジャズのソノリティーを隠そうとしてもとめどなく溢れてくる印象を受ける。
当時のジャズの歴史をリアルタイムで体験し、自らも実践していなければ出てこないであろう音群が現代のシーンにて違和感なく展開されている事に驚嘆する。
決して古いという印象は受けない。前を向いたパワーのある音楽。
当時の一部のジャズにあった人権運動、宗教、政治がらみの要素も感じられず、自身の考える音楽が純粋に語られていると思うのだ。
そして過度に重過ぎることもなく、等身大のプレイで現代的なマナーで語られていることに好印象をもつ。
ABDULLAHと等価の輝きを発しているのはBILLY BANG。
今日、ジャズはグローバルな状況のもと様々な国の多様なジャズが同時進行で多発的、多元的に存在しているが、彼らの演奏を聴くとあの時代を体験してきた黒人にしか表現できないジャズが確実に今も存在しているのだと実感する。
メンバーはAHMED ABDULLAH(TP,VO)ALEX HARDING(BS)BILLY BANG(VLN)ALEX BLAKE(B)
ANDREI STROBERT(DS)
録音は2004年5月10日 NYC

イタリアの中堅、いやベテランテナー奏者MAURIZIO GIAMMMARCOの1993年録音盤で、彼は1952生まれとライナーに記載されているので、41歳の時の作品ということになる。
1曲目からメンバー全員が快調に飛ばしていて、MAURIZIO GIAMMARCOはじめ、ピアノのMAURO GROSSIもモーダルなプレイで切れ味鋭いところを見せてくれる。
PIERO LEVERATTOも硬質なトーンでソロにリズムに素晴らしいベースプレイを披露。
こういうベースを鋼のようなベースと言うのだろう。
MAURIZIO GIAMMARCOは1976年以来自己のグループを率いて、この作品がリリースされた1993年の時点で既に40枚以上のレコーディングに参加、4枚のリーダーアルバムを録音している。これまで共演したミュージシャンもCHET BAKER,DAVE LIEBMAN,MARK DRESSER,BILLY COBHAM,FRANCO AMBROSETTI,GEORGE GRUNTZ,GIOVANNI TOMMASO,
ENRICO PIERANUNZI,ENRICO RAVA,BRUNO TOMMASO,GIORGIO GASLINIと挙げればきりがない。オールラウンド型のプレイヤーでモーダルな急速調の曲でも唄ものでも器用にこなすタイプで、マイケル・ブレッカーなんかと同じ様にどんなシチエーションでも自身の個性を最大限に表現できる職人質気質も持ち合わせているサックスプレイヤーだと思う。
このアルバムは全曲GIAMMARCOの作品で、曲良し、演奏良しのメンバーの一体感あるサウンドが捕らえられた代表作の一つに挙げられると思う。
メンバーはMAURIZIO GIAMMAROCO(TS,SS)MAURO GROSSI(P,KEY)PIERO LEVERATTO(B)ANDREA MELANI(DS)
録音は1993年7月18,20日

デイブ・リーブマンがジェイムズ・マディソン・ユニバーシティー・ジャズ・アンサンブルと1992年に録音したコルトレーン曲集。
デイブ・リーブマンはコルトレーン集をOWLやARKADIAレーベルでもリリースしているし、ビックバンドとの共演盤も結構多くて、古くはDRAGONのトルファンビッグバンドとのものから近作のブダベストジャズオーケストラのものまで、7,8枚あるはずで、そもそもリーダー盤、参加作品とも凄い枚数をリリースしている。
その作品数は自身のディスコグラフィーで知ることができるが、コンプリートにコレクションしている人はいるのだろうか?
リーブマンは80年代以降ソプラノサックスに特化してその音楽性を深めていったのは有名な話だが、このアルバムでも年々壮絶さを増す凄い演奏を披露している。
リーブマンの演奏を聴いていると一徹にひとつの事(ソプラノサックス)に集中した事によって常人にはおよそ到達しえない境地まで達した意志の強さを感じる。
グロスマンの様な天才性はないけれども、演奏のムラはなくて、常にハイクオリティーな
レベルの高い演奏が聴ける。
この人の功績はコルトレーンの音楽を自己のフィルターを通して普遍化し、その芸術性を歪めることなしに発展させた事にあると思う。
リーブマンの欠点としては、その生真面目さからどうしてもリーダーアルバムにおいて特に学究肌の音楽性が表現されがちで、小難しい演奏になりがちなのであるが、近年ソロイストとしては鬼気迫る表現にますます研きがかかり絶好調だと言える。
そろそろ集大成といえる最高傑作がこの2,3年の間にでるのではと期待しているのだ。
メンバーはDAVID LIEBMAN(SS)GUNNAR MOSSBLAD&THE JAMES MADISON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE
録音は1992年3月19,20日

先月の中古市で手に入れたCDで、CARLA MARCIANOはイタリアの女流アルト、ソプラノサックス奏者。このアルバムは彼女のデビュー作で、なるほど初々しい雰囲気の作品である。
アルバムタイトルの通り彼女のスタイルはコルトレーンそのもので、これはいささか今の時代においていくらなんでも時代遅れではないか?
コルトレーンを尊敬し敬愛する気持ちは十分理解できる。
パッショネイトなサックスの吹きっぷりとコルトレーンマナーを習得し情熱をもってジャズ演奏を行っているのは理解できるのだ。
しかし、今は70年代ではないのだ。
現代のサックス奏者は多かれ少なかれ皆コルトレーンの音楽に影響されていると言って過言でない。
コルトレーンを学び体得した後、皆がその呪縛から逃れ自身のスタイルを確立するのに苦労しているのが実情だと思うのだ。
CARLAはプロのミュージシャンなので、これから自身のスタイルを早く作り上げる必要があると思う。
コルトレーンのコピーだけで今のジャズ界やっていけるほど甘いもんではないと思う。
メンバーはCARLA MARCIANO(AS,SS)ALESSANDRO LA CORTE(P)ALDO VIGORITO(B)
DARIO DEIDDA(B)DONATO CIMAGLIA(DS)
録音は2001年9月
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 気になる売れ筋CD・DVD
- 【先着特典】H+ (通常盤)(並べてH+ea…
- (2024-11-26 20:15:33)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- JOHN WETTON / CONCENTUS: THE JOHN …
- (2024-11-20 00:00:08)
-
-
-

- 音楽のお仕事♪
- 音楽会🎹伴奏、フルート伴奏、うさこ…
- (2024-11-26 06:19:07)
-
© Rakuten Group, Inc.