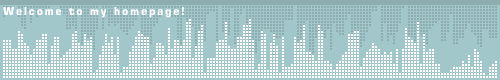音円盤アーカイブス(2005年12月)

軽やかなマーチリズムに導かれて瑞々しいメロディーが奏でられる1曲目「LAND THAT I LOVE」はあの9/11テロにインスパイアされて出来た曲らしい。
そう思って聴くと悲しみを乗り越え新たに生きる希望を歌っている曲に聴こえてくるから不思議なものだ。こう書くと重々しいテーマの大そうな曲かと思われがちだけどそうではなく、柔らかいハーモニーが印象的な優しい雰囲気の曲であります。
表面上は静かで穏やかなのだけでれど、内に秘めた力強い意志と決意が感じられる曲でもあります。
2曲目の「WALTS FOR NICOLE」は可愛らしいテーマ―が印象的なワルツで、ビル・エヴァンスの「DEBBIE」に向こうをはったのでしょうか?
3曲目「ONCE UPON A TIME」も軽やかなフォービートの良曲。
4曲目はピアノソロで、このトリオ(第3作目)の前は、ピアノソロ中心のアルバムが2枚出ていただけにソロ演奏はお手のもののようだ。
STEAGERの曲は色でいえばペールトーン、ないしはパステルカラー。 ぐんとひきつける強烈な旋律がないかわりに、曲全体の響きや柔らかなハーモニーで魅了する。
STEGERはじめ、このトリオの3人ともバークリー音楽大学の教授であり、息のあった協調ふりを見せている。
7曲目「AUTUMN RAIN」枯葉舞い散る街路に雨がしとしとと降りしきる寂寥感がよくでた美曲。
8曲目「MISTRAL」はこのアルバムでもっとも明るい色調の曲だけど、それでもどことなくうら寂しい雰囲気がするのはSTEGER作品の一つの個性だと思う。
全10曲、きっと永年の愛聴盤にできるピアノトリオ盤になると思います。
メンバーはELLIOT STEGER(P)JOSH DAVIS(DS)JON HAZILLA(DS)
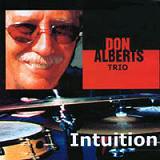
11/29日に入荷した作品の中で試聴した時より、実際に聴いてみて思った以上に良かったのがこの「DON ALBERTS TRIO」と「ELLIOT STEGER TRIO」の2作品。
そんな訳で「JAZZ IN AUSTRALIA」の予定を急遽変更してこの2作品のレビューを致します。
ジャケットの下半分がドラムセットの写真なので、このアルバムのリーダーDON ALBERTSはてっきりドラマーなのだと思っていた。
これはこちらの早とちりでDONはピアニスト。だったらピアノの鍵盤にすりゃいいのに・・・。何か理由があるのかしらん。
このアルバム、メロディストには大歓迎される一作じゃないかと思います。
全編、メロディーの洪水のようなアルバム。
あまりにも躍動感溢れた美メロ続きなので、聴き過ぎにご注意ください。
歌謡性の高い曲は、あまりにも集中して聴くと飽きるのも早いのです。
これは私が聴いてきた経験則から言っているのですが、それにしても、「ONE FOR HELEN」「ROSE PATINA」「NO NOT YET」「ESMIRALDA」「MY HEARTED BEST」「LITTLE DANCER」・・・うーん、曲を全部書くことになる。
全部良曲、捨て曲なしの内容保証アルバムとはこんな作品のことをいうのではないでしょうか?
勿論プレイもしっかりしているのは言うまでもありません。
何っ、甘口すぎるって、その通り、大甘口の一作であります。
でもこんな作品もコレクションにあっていいでしょ!
何千枚、何万枚コレクション持ってても「俺は一体何を効いたらいいんだっ!」っていう瞬間が必ずあるもの。
そういう時のための緊急避難用CDとして、「VENTO AZUl RECORDS」営業部一同自信をもってお薦めする一枚であります。
ちなみに、私の緊急避難曲は3曲目「ROSE PATINA」と4曲目「NO NOT YET」です。
メンバーはDON ALBERTS(P)BUDDY BARNHILL8DS)FRANK PASSANITINO(B)
CURT MOORE(PER)4曲参加
録音は2001年4月10日、5月8日6月12日 CA

「JAZZ IN AUSTRALIA」第5弾!
2000年春にSYDNEYで録音されたALISTER SPENCE TRIOの作品。
このトリオのデビュー作品であり、第2作目「FLUX」はオーストラリア2004年度ベストジャズアルバムに選定されています。
この作品、正直言って最初聴いた時、1,2曲目が少し抽象度高めの作品なので、
ポール・ブレイ系の長時間試聴が疲れるピアニストかと思って覚悟して望んだのでありますが、3曲目くらいから向こうの方から次第にこちらに擦り寄ってきたのが実感できた。
ブレイほど感覚派ではなく、かといってキース・ジャレットほど聴きやすいスタイルでもない。
初期のスペースジャズトリオでのエンリコ・ピアレヌンツィを彷彿させるところもあるし、左手の低音使いや青白い情熱を感じさせるところなどブラッド・メルドーを思い浮かべたりもする。
3曲にサンプラーが用いられており、正統派ピアノトリオファンの方は眉をまげるかもしれないけど、エフェクト的に使用されているのであまり気にならないと思う。
聴く回数が増すにつれ、だんだんと親近感がましてきて愛着度がわいてくるトリオ作品です。
ほら、いるでしょう。人づきあいでも、初対面では人見知りする人が・・・
付き合う間にお互い分かり合い無二の親友になるというケースが・・・
そんな感じのアルバムじゃないかと思います。
メンバーはALISTER SPENCE(P,SAMPLER)LLOYD SWANTON(B)TOBY HALT(DS)
録音は2000年4月3-5日 SYDNEY

「JAZZ IN AUSTRALIA」第6弾!
アルトサックス奏者のGRAEME NORRISが1995年ブルックリンのSYTEM TWO STUDIO(音が良いので有名)で録音したクインテット作品。
ネット検索してもGRAEME NORRISのバイオが掲載されているサイトがなかったので、ほとんど情報らしきものがないのですが、2003年の時点で、クインテットによる演奏活動は続いているようです。
但し、このアルバム録音の時とメンバーは変わっている模様。
このアルバムはオーソドックスな2菅編成によるモードジャズの模範的な演奏と言ってよいのではないだろうか?
当時95年の日本のジャズシーンでいうと、ちょうど、大坂~原クインテットがあてはまるんじゃないかと思う。
伝統的な手法を真っ直ぐ受け継ぎつつ、若くてフレッシュな感性とオリジナルな音作りに対して真摯な態度で望む姿勢。
GRAEME NORRIS QUINTETと大坂~原クインテットの共通項ではないでしょうか?
アルバムにはビリー・ストレイホーンの「JOHNNY COME LATELY」[BLOODCOUNT」以外はすべてNORRISはじめメンバーのオリジナルで固められている。
個性という点ではもの足りない面も見受けられるけれども、メンバー全員のコミュニケーションがいきわたったグループエキスプレッションが素晴らしく、作編曲、
演奏マナー、要はジャズに対する真っ直ぐな思い、清らかさまで感じられて聴いていてとても爽快な気分になる作品だと思います。
4曲目の「BLUE NIGHTS」でのROD MAYHEWのフリューゲル、6曲目の急速調のモードナンバー「COCO」でのメンバー全員のスパーク度、7曲目「SUMMER DANCE」でのスローライフな雰囲気など聴き物も多い。
そしてそこには一貫して自然と一体化したオーストラリアという土地柄からイメージされる風通しのよいナチュラルなイメージが流れていると感じるのはわたしだけだろうか。
メンバーはGRAEMENORRIS(AS)JANN RUTHERFORD(P)ROD MAYTHEW(TP,FLH)NICKI PARROTT(B)ALAN TURNBULL(DS)
録音は1995年2月9,10日 BROOKLYN,NY

今までありそうでなかったキース・ジャレット集、これがこのアルバムに関心をもった一番の理由です。
実は、キース・ジャレット、私、苦手なんです。
苦手と言うか、大学時代にジャズ喫茶でキースに対してあまりいい思い出がないのです。
例のあれである。3時間くらいいると、へたすると2回聴くはめになる。
あれを、「ケルンコンサート」を・・・。
たしか弓道部の胴着のままでやって来てこればかりリクエストする女子がいたっけ。とにかくよくかかっていて、そのうちTVのイメージソングにも使われたはずだ。あとは、やはり「マイソング」ですね。
これを聴きながら、何もやることがなくて煙草吹かしながらジャズ喫茶の小さな窓から流れ行く雲を見るのが好きでした。
そんなわけで、アメリカンカルテットもヨーロピアンカルテットもソロ作品も特に個人的なこれといった思い入れがなくて、キースに対して親近感を抱いたこともほとんどなかったというのが実状で、それ以前のアトランティックやボルテックス時代、マイルスやロイドのグループでのプレイを聴いても凄いなとは感じてもこちらから積極的に聴こうという気持ちにはならなかったのです。
周りには、熱心なキースファンがいて「サンベアコンサート」を発売当日に買った人間もいたのですが、私自身がそれに感化されると言う事はなかった。
キースの参加しているアルバムで持っているものといえば「TALES OF ANOTHER」ぐらいのものだったと思う。いまでこそスタンダーズのアルバムを数枚所有しているが、今でもそれぐらいのもんである。
そんなキース門外漢の私がこのアルバムを聴いて、その作曲の素晴らしさに驚いています。
キースのファンからしたら「今更なにを分かりきったこと言ってるんだ」というところでしょうか?
勿論、このアルバムのプレイヤーULF WAKENIUSはじめトリオ3人の演奏能力の高さもあると思う。
この三名のプレイヤーは、最上の素材を最高の腕前でしたてあげ極上の1品を提供する一流のシェフの役目を果たしているといえる。
素材のよさを最高に引き出しているところは、さしずめ一流のフランス料理のシェフといったところかな。
キースの曲を楽しみながら演奏していて、必要以上に自分のカラーを出さない大人のプレイ、それでいて表現したい事は明瞭にこちらに伝わってくるのだ。
先に書いたようにさしたるキースに対して思い入れがある訳ではない私でも、このアルバムを聴いてブラジル音楽でいうところの「サウダージ」を感じるくらいだからましてやキースファンが聴いたら「泣き」の一枚になるのでは?
メセニーの「ミズーリ」と同じくらい、愛聴盤になりそうな気配。
メンバーはULF WAKENIUS(G)LARS DANIELSON(B)MORTN LUND(DS)
録音は2005年5月21,22日
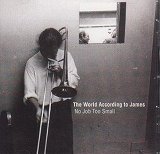
JAMES GREENINGというトロンボーン奏者(このアルバムではチューバやポケットトランペットも吹いています。)の「THE WORLD ACCORDING TO JAMES」というバンド名がつけられたグループによる1998年の作品。
ニューキャッスル生まれのJAMES GRENNINGはオーストラリアを代表するトロンボーン奏者の一人で、現在オーストラリアン・アート・オーケストラのメンバーの一員である。今までにBernie McGann 、 Tim Hopkins, Mike Nock, Vince Jones, Judy Bailey and James Morrisonと演奏活動をともにし、ビリー・ハーパー、マーク・ヘリアス、日野皓正と共演、マリア・シュナイダー・オーケストラ やチャールス・ミンガス・トリビュート・ビッグ・バンドでのソロイストを務めたことがある。
このファーストアルバムはそんな豊富な経験をふまえたうえで、満を持して自身のオリジナルな音楽を表現した作品といえよう。
GREENINGはトロンボーン以外にポケットトランペット、チューバ、DIDIJERIDUなど様々な菅楽器を駆使してバリエーションをだしている。
ピアノレスでポケットTPとANDREW ROBSONのASが一緒に鳴り響くときなど、オーネット・コールマンのカルテットを思い出させる瞬間があるかと思えば、FSNTの新しいアルバムを聴いているかのようなサウンドが出てきたりで、おもちゃ箱をひっくり返すかのような多彩で賑やかで躍動感溢れるサウンドが展開される。
地元オーストラリアでも絶賛され、2002年にはセカンドアルバムがVITAMIN RECORDSからリリースされたようであります。
オーストラリアン・ジャズのバリエーションの豊富さをしめす作品だと思う。
メンバーはJAMES GREENING(TB,P-TP,TUBA,DIDIJERIDU)ANDREW RPBSON(AS)STEVE ELPHICK(B,COR)TOBY HALL(DS)
録音は1998年2月20日

オーストラリアのギタリストDAVID SMITH と巨匠JACK WILKINSの1994年シドニーでの完全デュオライブアルバム。
2人は1979年以来の友達であり、いままで幾度となく共演を積み重ねてきた間柄のようで、この作品は永年のプランがようやく実現したアルバムといえよう。
CD番号はDSM112とあるので、頭文字をとった自費製作もアルバムであるのがわかる。
こういうギターデュオやトリオ作品ばかりリリースするJARDISというジャズギター専門レーベルがあるけど、それらの作品に勝るとも劣らぬ出来映えになっていると思う。
1曲目は「ALONE TOGETHER」アルバムタイトルにしただけあって、力のはいった長尺のトラック。14分17秒、ソロの順番はJACK WILKINS、DAVID SMITHの順番。
集中力が途切れることなしに、両者は素晴らしい会話を見せる。
技量的に比較すると、やはりJACK WILKINSに歩がある事は否めない。
しかしDAVID SMITHも充分すぎるくらい健闘したプレイをみせている。
それにしてもウィルキンスの流麗で洗練されたギターテクニックは、完成の域に達したといってもよいだろう。
うっとりするほど素晴らしいフレーズがごく自然に紡ぎだされ、まるでガラス細工のように細やかで繊細なプレイも危なげない。
匠の技、ここにきわまれりというところだ。
選曲はスタンダード中心で、ジャンゴ「NUAGES」ルグラン「YOU MUST BELIEVE IN SPRING」「ALICE IN WONDERLAND」「BODY AND SOUL」「IF I SHOULD LOOSE YOU」全6曲。
10分越えの作品が多いが、だれることは全くない。
むしろ、2人の丁々発止としたプレイが存分に聴けるのでこれぐらいの長さの方が良いのではないかな?
ギターファンは必聴の隠れ裏名盤だと思う。
メンバーはDAVID SMITH(G)JACK WILKINS(G)
録音は1994年11月26日、12月2日 SYDNEY,AUSTRALIA

BERNIE McGANNのサックス、CARL DEWHURSTのギターをバックにSUSAN GAI DOWLINGというボーカリストがスタンダードナンバーを6曲吹き込んだCD-R。
海外のアーティストの作品には時々こういったCD-R作品が時々あって、ウェブ上にその断り書きがあまり書いていないので、商品が届いて「ありゃ、りゃ」ということがある。
この作品、おまけにインナーはPC用プリンターで印刷したもののようだし、おまけに青いボールペンで裏にSAMPLEと書かれている。
ひょっとしたら、実際にはリリースされずに、見本だけに終わった作品かも知れない。
そんなことを思い巡らしながら、名前も聴いた事のないオーストラリアのおばちゃんボーカリストの唄を聴いてみる。
顔に似合わず(失礼!)なかなか可愛らしい声で丁寧な歌唱は好感が持てる。
BERNIE McGANNのサックスも絶妙のタイミングで唄にオブリガードをつけ、間奏では素晴らしくオリジナリティー溢れたサックスを披露。
微妙なピッチのずらし具合や音のかすれ具合など、一歩間違えるとミストーンと間違えられるようなスリリングで歌心溢れたプレイは経験に裏づけされた職人技。
ギターのCARL DEWHURSTとのコンビネーションも抜群の相性をみせており、2人でSUSAN GAI DOWLINGの唄を盛り立てている。
インティメイトな雰囲気で進められたレコーディングはきっとSUSAN自身快心のセッションだったことだろう。
ところで、この作品ちゃんと発売されたのだろうか?
メンバーはsUSAN GAI DOWLING(VO)BERNIE McGANN(AS)CARL DEWHURST(G)
録音は2003年 SYDNEY

「JAZZ IN AUSTRALIA」第10弾
女性ピアニストCATHY HARLEYがBERNIE McGANNらベテラン勢を従えて録音した1995年クインテット作品。
1969年生まれというから、彼女が26歳の時の作品ということになる。
マイク・ノック、ベニー・グリーン、ジミー・スミス、エリス・マルサリス、ケニー・バロンから教えを受け、今までに作曲と演奏、両方でオーストラリアのジャズアワードの受賞経験がある。
全体的に彼女の作品は、モーダルな響きを大切にした、それでいてオープンエアーというか外側へむかって拡がっていくような印象を受けるものが多い。
つまり、ミュージシャンにとってインスピレーションがどんどん湧き上がってくるアドリブのしがいがあるワクワクする曲ということにならないだろうか?
BERNIE McGANNやトランペットのWARWICK ALDERのプレイがいつにましてはりきった調子に聴こえる。
もちろん、CATHY HARLEY自身のピアノもスタイリッシュで、カッコよい。
スタイル自体はエバンスからハンコックを消化した現代的なピアノスタイルといえるけど、このアルバムは演奏、作曲どちらが勝つでもない、イーブンな自身の音楽を表現したかったのではないかと思う。
全曲モードナンバー中心の2菅クインテット作品ということもあり、歌もの指向、スタンダード指向のファンのかたには少々きついかもしれないけど、プレイ派指向のかたには是非一度耳のしてもらいたい隠れた良作だと思います。
メンバーはCATHY HARLEY(P)BERNIE McGANN(AS)WARWICK ALDER(TP)CRAIG SCOTT(B)ALAN TURNBULL(DS)
録音は1995年2月1,2日 SYDNEY

当時、平井和正の小説に心酔していた中村誠一がその主人公「ウルフ」をテーマに巣してリリースした1978年作品。
裏のジャケットの顔写真が皆、若い。あたりまえか?
ジャズとフュージョンの中間をいくような今の耳で聴くといささか緩い感じのする演奏なのですが、1978年という時代の空気感がとても良く出た演奏になっていて決して悪くはないと思います。
中村自身の天然の明るさというか、エンターテイメント精神旺盛な部分が良く出ているアルバムだと思う。
逆に言うと、ひとつのアルバムにいろんな事をサービス精神のあまり詰め込もうとしすぎるあまり、焦点がボケるきらいがあったことも事実。
このアルバムも、その嫌いがないでもない。
最近はストレートジャズ一本に賭けたアルバムが多くて、聴きごたえのあるものが多い。
で、この昔のアルバムと最近の演奏のもの、どちらをよく聴くといったら、この「WOLF'S THEME」のほうなのですね。
高瀬アキのフェンダーローズによる、スタンダード演奏を聴ける作品なんてこのアルバムぐらいじゃないですかね?ほんと。
メンバーは中村誠一(TS,SS)大徳俊幸(P,KEY)高瀬アキ(P,KEY)岡本昌三(B)古沢良治郎(DS)岸田恵二(DS)
録音は1978年4月10,11,26日

このアルバムの顔見ても、最近のファンは直ぐに分からないのじゃないかな?
何故なら、トレードマークの髭がないからです。
言ってる事も若いというか、必死で自分のジャズに取り組んでいたことが窺えることがライナーノーツに書かれている。
「僕自身の現在の音楽は、既成のトロンボニストを破壊し、かつトロンボーンのビューフルな面を出して行きたい。そして、表面的にはダーティーでも、ガッツのあるハートをもった音楽をやりたい。さらに、自分の音から日本人である事が感じられれば最高だ。コルトレーン、日野皓正が精神的支柱である。」(向井滋春)
のちに、フュージョン、ブラジル音楽、レゲエと多岐に渡る音楽を展開していく向井の姿からは想像もつかないジャズに対する頑なな思いが伝わってくる。
音楽性の幅がこの頃にくらべ物凄く拡がった向井であるが、(今はチェロも弾く)トロンボーンの音自体は既に確立されていることに今更ながら驚く。
30年以上前の録音なのに、多分ブラインドホールドテストで初めて聴いても、多分向井の演奏だと分かるだろう。
それぐらいの個性の持ち主なので、スイングジャーナルの人気ポールウィナーズを永年に渡って維持できるのだと思う。
このアルバムを聴いて個人的に思い出したことがあります。
ジャズを聴く前のことなので、いまだにはっきりしなくて、どなたか覚えている方がいらっしゃつたら教えていただきたいのですが・・・
確かナショナルのTVCFで、多分1974,5年ころ流されていたと思う。内容は、ジャズを志す若者が誰かの家に集まって演奏しだすという映像で、記憶が正しければ、編成がTB,TS,P,B,DSのクインテット編成だったような気が・・・
なにぶんジャズを聴きだす前の中学生当時の記憶なので自信がないのですが、それが向井のクインテットの様な気がするのです。
向井さん本人に聞けば簡単な事だと思うのですが本人に直接会ったことがないもので、どなたか教えて下さい。
たわいない事で、どうでもいいことなんですが、30年ちかく心の奥に引っ掛かっていてもやもやしていることのひとつなのです。
ところで、このアルバム、70年代中央線ジャズのいいところが染み出たいい作品だと思う。もっともその頃中央線ジャズなんて言葉はなかったと思うが・・・
メンバーは向井滋春(TB)高橋知己(TS,SS)土岐英史(AS)元岡一英(P)古野光昭(B)亀山健一郎(DS)大徳俊幸(ELP)今村祐二(PER)
録音は1974年11月9,18日

最近、ミュージシャンからメールが頻繁に届く。
昨日はBILL RISBY,何日か前にはJOE CHINDAMO。
お買い上げ有難うというサンクスメールには、違いないのだけどそれだけには終わらずに今後のレコーディングスケジュールや再プレス情報、演奏スケジュールなども一緒に教えてくれるのでありがたい。
TONY PACINIなんて今度新作でリリース予定のソロピアノ演奏の音楽ファイルをMP3で送ってくれたもんね。ついでに書くと。ピアノトリオでの新録予定もあり。
一昨日なんか、御大JIM HALLがメールをくれた。
もっともこれは、自動返信メールだと思うけど・・・
入荷すればアップ致しますがARTIST SHAREからホールの新作がリリースされました。(全世界で5000枚限定、入手方法はインターネット販売のみ)
ジェフ・キーザーとのDUO演奏です。
ネットの時代になって、ミュージシャンもダイレクトに世界中のファンとの交流をスムースに図れるようになって便利になった反面、個々への対応、営業努力が必要とされる時代になってそれだけ大変になったともいえる。
ダウンロードの時代になり、ますます音楽の等価やありがたみが以前に比べ安価で簡単に誰もが入手するのが可能になった反面、ジャズファンの一般的な姿、依然かわらずソフト(それがLPであれ、CDであれ)に執着する姿はおそらくそんなに変わらないのではないかと思う。
それだけ、ものとして持つことへのこだわり、コレクター的なベクトルの高い人種の集合体だと思うのですね、自分を含めて・・・
只、ジャズCDといえど一枚あたりの販売量は減少傾向を描くだろうと思う。
大手レーベルがどんどんミュージシャンの首を切っていく現状をみればよく分かる。良く売れているジャズCDのタイトルを見れば、それが実際はジャズではないのが分かるだろう。
元来、ジャズのCDが何十万枚も売れるわけがないのである。売ろうとするほうが間違っている。無理に売ろうとするから、市場分析がはじまる。
ミュージシャンとレコード会社に間に軋轢が生じる、音楽が本意でないスポイルされたものに陥りやすくなる。
今後極端な言い方かもしれないが本当に良質でコレクター心をくすぐる作品は、近い将来、手売りによって売られていくようになるかもしれない。(つまりネット販売でミュージシャンからファンにダイレクトに)
すでにそういう動きは顕著で、ARTIST SAHREのような集合体、パッケージとダウンロードの抱き合わせ販売などの動きも見守る必要があると考える。
山下洋輔がジャズミュージシャンは1人1民族だと、言い得て妙な説明をTVでしていたが、今後ジャズファンも持っているCDが皆違う1人1民族になる可能性も無きにしも非ずというところだ。
全世界で500枚とか1000枚しかプレスされないCD(ちょっと極端かもしれないが、それでも1,2万枚)を、入手してファンとしての満足度を高める。
これじゃ、昔に逆戻りだね!BLUE NOTEの輸入盤が月給の三分の一くらいした昭和30年代に・・・違うのはリリースされる種類、当時の数百倍の種類が全世界から毎月のように新譜でリリースされるわけだ。
ちょっと面白いのではないかと思う。
ファンもセンスと見極めが今以上に要求されるようになる訳で、そのあたりの切磋琢磨がジャズ鑑賞屋としての価値を高めるのではと夢想している今日この頃なのです。
CHINDAMO盤に少しも触れなかったけど、オーストラリア盤オリジナルで澤野盤と微妙に音質が違います。ジャケは勿論。
曲は御馴染みの曲なので保証つきです。
メンバーはJOE CHINDAMO)P)MATT CLOHESY(B)DAVID BECK(DS)
2002年作品

アップするのが、こんな時間になってしまった。
遅れていたアメリカからの荷物がまとめて本日の午後どーん(でもないか)と到着して、受注分の仕分けとショップHPへのアップ、お客様へのメール連絡等で結構忙しかったのです。
さっきこのCDを、入浴アンド晩飯後の一枚として、2階の自室で聴いてきたところです。
今、PCでもう一度再生しながら聴いているところなのです。
実はこのCD,最初に発見してから2ヶ月以上経過してようやく今日入荷したのです。
告知されてからディーラーのもとになかなか入らなかったのですよ。
直ぐに仕入れようと思ったのはまずジャケットの雰囲気。
ボーカルの場合、これはとても重要な事なのですね。
なんか、50年代のベツレヘムレーベルやキャピトルのジャケットのような雰囲気で
聴いてみようという気になったのです。
もちろん、歌も大事。歌も大事なんですがルックスと雰囲気もおなじくらい大事かもしれない。
試聴してみて唄も想像以上に良かったのですね。
スモーキーな表情をところどころ醸し出しながら、あるときは清楚に、またあるときは可憐に、ジャージーでスインギーな場面の創出も若いのに結構板に付いている。
このアルバムは彼女STEPHANIE PORTERのデビューアルバムなのですが、どうしてどうして結構やるもんです。
ノラ・ジョーンズよりずっとジャズ度は高いし、売りだしようによっては第二のダイアナ・クラールのような存在になれるのではないかと思ってしまうほどポテンシャルを感じる。
しかし、この作品は自費制作。これが現実。
ダイアン・クラールも結構下積み時代があったからね、彼女もこれから分からない。
売れてほしいと思う1枚です。
実は今日はわざとアップしませんでした。
一日だけ自分だけのものにしたかったから・・・ごめん。
明日はアップして試聴できるように致します。
2005年作品

イリノイ出身の知られざる黒人トランペッター、ORBERT DAVISの2004年作品。
このアルバムで初めて名前をしったのだけど、地元シカゴでは、結構有名な存在のようで、3000以上のテレビ、ラジオコマーシャルの録音するかたわら、有名なミュジシャンとの共演も多くて、ジャズミュージシャンとしての評価も高いようです。
オリジナルにショーター、ハンコック、ガレスピー~パーカーの曲が収録されています。
まず、2曲目「HAMMER HEAD」を聴いてみて欲しい。
近頃、小難しくない胸のスカッとするラッパを聴いていないという方にお薦めです。のりは60年代BLUENOTEのリー・モーガン、フレディー・ハバードの諸作ののりといえばよいでしょうか?
ウィントン一派の妙な権威主義的なものが鼻につかないのが良いです。
ORBERT DAVISのプレイは、デビュー当時のロイ・ハーグローブのような、素直な吹奏ぶりがとても好印象です。
トランペットのスキルはこの上なく高い。音自体がぶ厚いし、ハイノートも良く出ています。なにより音楽に対する集中力を感じさせるところが評価できる。
排気量が高いので、バラード吹いても余裕を感じさせるところがいいですねぇ。
ハーグローブに触れてはたと思いついたのですが、ハーグローブ、ウォレス・ルーニー、ラッセル・ガン、ニコラス・ペイトンまでもが電化サウンドの方にうつつを抜かしていると言うと言い過ぎかもしれないけど、実際、音楽的成果の充実したアルバムは少ないように思う。
みんな、マイルスやりたいのかなぁ、それともセールス的にやはり期待できるのでしょうか?
彼らのペットはアンプで増幅させなくても充分魅力的なものなので、ストレートな演奏のアルバムもたまには期待したいところです。
そんな、電化アルバムはもういいやと、お嘆きのあなたにこのアルバムをお薦めいたします。
2001年の「PRIORITY」もお薦めです。
メンバーはORBERT DAVIS(TP)ARI BROWN8TS)RYAN COHEN(P)LORIN COHEN(B)KOBIE WATKINS(DS)DEE ALEXANDER(VO)2曲に加わる。

EDSという血液の難病に立ち向かいながら、演奏活動を続けるNOAH BAERMANが30歳を迎えジャズを演奏し続けることの喜びを録音したライブアルバム。
こう書くと病気を売り物にしているようで、嫌なんですけど、そんな予備知識なしに聴いてもこれは中々のピアノトリオアルバムだと思う。
オープナーはトラディショナルの「WADE IS THE WATER」。
何年か前、チャールス・ロイドが取り上げていて知った曲なんですが、BAERMANのバージョンは、ピアノを弾けることの喜び、好きなジャズを再び演奏できる喜びが伝わってくる。この日のライブに集まった聴衆の暖かい拍手にも演奏が素晴らしいものであった事が表れている。
難病とたちむかうピアニストで思い出したのが、ミッキー、益田幹夫のこと。
数年前に出たアルバム「黒水仙」1曲目「イン・ナ・センチメンタル・ムード」の出だしの数秒は思わず背筋がぞくっとしたことを思い出す。
不幸なことに病気が再発してピアノを弾くのが再び困難になっているらしい。
早くよくなってカムバックされることを切に願う。
BAERMANはといえば、快調そのもので、「YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS」や「NEFERTITI」では深く沈みこむ叙情性やを、ケニー・バロン「518」のようなアップテンポの曲では疾走感、スパークする感じが出ていてなかなか聴かせるのです。
前作はロン・カーター、ベン・ライリーをサイドメンに迎えた作品で本人に注文をオーダー済みなのですが、こちらの入荷も今から楽しみです。
なにはともあれ、暖かいライブコンサートの雰囲気に溢れた録音盤だと思います。
メンバーはNOAH BAERMAN(P)HENRY LUGO(B)GEORGE MASTROGIANNIS(DS)
録音は2003年12月4日

やあ、困った! 困った!
資料がなんにもないのである。
持っている3枚のリーダー作にも経歴が書かれていないし、ネットで本人のバイオグラフィーを調べようとしても載っていないのである。
分かる限りのことを綴ってみよう。
ボブ・フェレルはこれまでに3枚のリーダーアルバムを吹き込んでいる。
1 BOB FERREL QUARTET/TIME TUNNEL(BFM-001)1996
2 BOB FERREL QUARTET/BON VOYAGE(BFM-002)1997
3 BOB FERREL-TED CURSON (JAZZBANK MTCJ-1044)2002
1枚目、2枚目はレコード番号からも分かるように自費出版である。
3枚目は日本のマイナーレーベルからリリースされた。
単刀直入に言ってしまおう。
フェレルの音楽を聴いているとそんな経歴とかなんとか細かい事はどうでも良いと思ってくる。 音である。曲のよさである。
この人本当にトロンボーンが好きなんだろうなぁ・・・そう感じずにはいられない音。太くてツヤがあり決して重くならず、リズムにふんわり乗っていく軽やかさももっている音色といったらわかるだろうか? 派手すぎず、かといって目立たないわけではない、ちゃんと自己主張している音。そして音の大きさ、パワー。
やっぱり、絶対的な体型の違いってあると思う。骨格や筋肉の量、肺活量が違うのである。日本人のプレイヤーが10の力のうち8くらいで吹いているところを5か6くらいの配分で吹いているんじゃないだろうか?
フランク・ロソリーノ、ビル・ワトラス、カール・フォンタナ、クリフトン・アンダーソン、ジム・ピュー、名プレイヤーは、全員大きな体してるのでは?
特に管楽器でもトロンボーンはジャズで使われる楽器のなかでも肉体的要素、身体的アビリティーが問われる楽器なのではないか。
このCDはスイングジャーナルのLPコーナーの広告欄に小さく写真が載っていたのを
全くの勘で購入したもの。2000年に、LPコーナーで買ったんではなくて博多のキャットフィッシュレコードから送ってもらった。
一曲目のラテン調の曲にいっぺんに心を奪われてしまった。
コルトレーンのブラジリアやトロンボーンの名曲ラメントも入っている。
カルテットのメンバーは固定していてマイケル・コクレイン(P)カルビン・ヒル(B)ヨロン・イスラエル(DS)となっている。
マイケル・コクレインのピアノがソロでもバックにまわってもいつものように唄っていてとても素晴らしく、曲がふくらんでカルテット全体に伝わり一丸となったスイング感溢れるパーフォーマンスが繰りひろげられている。
だが、このCDの主人公はリーダー ボブである。
持ち前のパワーだけに流されず、細やかな音楽的交感をカルテットのメンバーとして、確固たる主張をもって統率し、引っ張って曲を完結させる手腕は賞賛してよいと思う。
マーサ・エリントン率いるデューク・エリントン・オーケストラにも在籍していたことがあり、今までにエラ・フィッツジェラルド、サラ・ボーン、ナンシー・ウィルソン、ディジー・リース、ケニ-・ギャレット、マルグリュー・ミラー、ベニ-・パウエル、スライド・ハンプトン、チャーリー・パーシップ、マーカス・ベルグレイブ、ジョー・ワイルダー、エディー・ヘンダ-ソンなどと共演歴がある。
EDISON PROJECTというのがあり、100年以上前のトーマス・エディソンが開発した
ワックスシリンダーに直接録音した演奏が2曲収められている。
決していい音じゃないが、思ったより悪い音でもない。
1800年代末にタイムスリップさせてくれる音・・・
2004/8/8に書いたものの再掲載です。
トロンボーンファン、ラテン好きは必聴です。

ニューオーリンズの期待の新星、TROY ANDREWSは、6才の時既にフレンチクォーターの街角でバンドリーダーとしてプレイしていたらしい。
マルサリス兄弟、テレンス・ブランチャード、ドナルド・ハリソン、八リー・コニックJr,ニコラス・ペイトンらが卒業したNOCCAの出身である。
NOCCAというと、ジャズの伝統とブルースの精神に根ざした極めて正統的かつアカデミックな音楽イメージがまとわりつくのだけど、TROYの音楽を聴くとそういう感じがあまりしないのです。
これは、幼少の時から現場で生身の音楽、ジャズを演奏することによって学んできた事によるものなのであろうか?
不思議とウィントンに代表されるスノッブ性、権威主義のようなものが感じられないのだ。
そして、このTROY ANDREWS,トロンボーンとトランペット二つの菅楽器を吹く。
1曲目、2曲目はトランペットを吹く。アルバムジャケットの裏にはトロンボーンをかかえた写真が載っている。
どちらが、メインの楽器なのか、ここでちょっと困ってしまった。
おまけに、私はこういう両刀使いというか、2種の異なる楽器を演奏するミュージシャンが苦手というか、どっちつかずで進んで聴く気にあまりならないときている。
例えば、アイラ・サリバン・・・
もっとも、同じ管楽器なので、木管楽器ほどの違いはないだろうけど。
3曲目はボーカル入りなので、4曲目でトロンボーンのロングソロが聴ける。
どっちがいいかって?
うーん、現時点ではトランペットのほうかもしれない。
実際、フューチャーされている曲数もソロの時間もトランペットの方が多いと思う。しかし、トランペットは強者がひしめいている非常に競争の激しい楽器部門だ。トロンボーンのプレイにはまだまだ荒削りだけど将来的なポテンシャルを感じさせるのだ。
おまけに、トロンボーンははっきり入って人材不足、ついこの前まで、J・J・ジョンソンが王様に君臨していたし、カーティス・フラーやスライド・ハンプトンがまだまだ幅を利かせているほどだ。
若手もでてきているが、圧倒的なリーダー的存在はいない。
本人がどう考えているのかは分からないけど、メインの楽器をトロンボーンにして
やっていくのも、名前を売っていくためのひとつの選択肢じゃないかと思う。
余計なお世話だとはおもうけど・・・
このアルバムの8曲目「BYRDIE」(ジェイソン・マルサリスのドラムソロも良い)なんかを聴くにつれそんな風に思った次第。
メンバーはTROYANDREWS(TB,TP)JAMES MARTIN(TS)BILL HUNTINGTON(B)JASON MARSALIS(DS)MICHAEL PELLERA(P), guest ELLIS MARSALIS(P)IRVIN MAYFIELD(TP)KERMIT RUFFINS(VO)JOHN BOUTTE(VO)
録音は2004年12月3日

オハイオ出身のドラマーPAUL SAMUELSがグレッグ・オズビーを迎えて録音したストレートジャズ作品。
こんなに、ストレートな吹奏を繰りひろげるオズビーのサックスを聴くのは何年ぶりだろう。リーダー作ではまずありえない、この奏者の原点に立ち返ったかのような吹奏ぶり。そこには明らかにキャノンボール・アダレイのフィーリングが見てとれる。
80年代中盤、ウィントンの新伝承派(日本だけの造語)のネオバップムーブメントの向こうをはるように台頭してきたM-BASE派の一員として台頭してきたオズビーであるが、ここ最近は伝統回帰の動きをブルーノートのリーダー作でも見せてきている。
しかし、リーダー作ということもあり、100%本音でしゃべっていないというか、
リーダー作である以上何らかの気負いやアーティスティックであることへのこだわりがあると思う。つまり、役者が舞台で主役はるときに素顔のままで演技しないのと同じ様にミュージシャンも演ろうとする音楽に化粧するわけである。
それが作曲であり、編曲であり、リズムアレンジに該当するのかしらん。
バンドリーダーの場合プレイ自体も何らかの作為性が働くものだと思う。
サイドメンの時とリーダーの時と全く同じエモーションで演奏するミュージシャンはまずいないのではないか?
自分がリーダーの場合誰だってサイドメンの時よりは緊張感が高まるし、逆にサイドのときはリラックスした感じで出来るのだと思う。
結構リーダー作よりサイドメンでのプレイのほうがいいミュージシャンっているでしょう?最近ではエリック・アレキサンダーがそうかもしれない。
このオズビーもどちらかというとそうかもしれない。
オズビーのプレイはこのアルバムで脱力していて、素顔の演奏なのである。ジャズを自分のものにしようと必死であった若い時を自身で回想しているかのようなプレイといったら良いだろうか?
それでいて、オリジナリティーを感じさせるところがやはり、只者でない。
一流はなにやっても一流であることを実証したアルバムだと思う。
PAUL SAMUELS(DS)GREG OSBY(AS,SS)DAN WALL(ORGAN)JAMEY HADDAD(PER)
録音は2005年4月

今年の春先に中古盤で入手して名前を知った中堅トランペット奏者の2003年のアルバム。トランペットの先人達へのトリビュート物となっている。
すなわち、マイルス、フレディー、ウディー・ショウ、モーガン、ブラウン、クラーク・テリー、ドーハム、ガレスピーというラインナップ。
曲は、NARDIS,INTERPID FOX,TOMMRROW'S DESTINY,CEORA,DAAHOUD,SHEBA,SHORT
STORY,TIN TIN DEOとなっていて口ずさめるくらい御馴染みの曲を選んでいる。
そして、メンバーがこれまた、粒揃いというか旬のミュージシャンを揃えていて期待が高まる。CONRAD HERWIG(TB)YOSVANNI TERRY(TS)MIGUEL ZENON(AS)JOHN BENITEZ(B)EDSEL GOMEZ(P)といったところ。
そして、BELLA RECORDSというこの会社はメキシコのレーベルのようですね。
1曲目のナルディスはともかくとして、この曲をラテンにアレンジは個人的にどうも・・・
2曲目フレディーの名曲「INTERPID FOX」何時聴いてもカッコいい曲です。
TONY LUJAN初め、ハーウィッグ、イーゼル・ゴメス、ソロイスト皆が、突き抜けるほど青いメキシコの空のようなカラッとしたアクティブなプレイを見せてくれる。
昨日からこの時期珍しい大雪に見舞われて外はこのアルバムで展開されている音楽と正反対の風景がひろがっているのでありますが、心の中はカラッとした湿度が少ない乾燥した夏の風景がひろがっているのでございます。
そこで飲む冷たい缶ビールは多分うまいだろうなと・・・
実際は下に貼り付ける外の画像の景色を見ながら、暖房の効きすぎたパソコン部屋で焼酎お湯わり飲みすぎでいささか酔いがまわりつつこんな文章を綴る冬の午後4時のVENTO AZULなのでした。
録音は2003年12月3日

先月仕入れた作品が小気味よいLAハードバップサウンドで、聴きごたえのある作品だったので、同時録音された本作「BALLADS」も仕入れてみました。
題名通り、唄とトランペットでバラードナンバーを表現した作品。
まず、ファッションは明らかに50年代のチェットを意識したもの、髪型もそう。
ルックスは残念ながらチェットには勝てないというところか!(笑)
唄も中性風ウィスパーボイスがチェットを連想させる。
トランペットは50年代マイルスですね、はい。
「I'LL BE SEEING YOU」「NATURE BOY」「FOR ALL WE KNOW」といかにも、マイルス、チェット気分のナンバーに続く4曲目はオリジナル「DREAMING OF MEMPHIS」。
マイケル・フランクスが作りそうなタイプの曲でこれもなかなか良いです。
「BUT NOT FOR ME」をボサノバ仕立てのアレンジして、これも素敵です。
ギター、ヴァイブラフォン、パーカッションが効果的に使われていて、こういう楽器の使用はイージーリスニングに陥る危険性もあるのだけど、そこはうまくジャージーなテイストを失わないよう調整してあるのでご心配なく。
リラックスしたさりげないシーンの演出にもOKだし、スピーカーの前でじっくり聴いても充分満足感を得られる作品だと思う。
あまりとやかく細かいことを言わずに単純にBIRKEYの唄と演奏を楽しめば良いアルバムだと思います。
メンバーはNATE BIRKEY(TP.VO.PER)JAMIESON TROTTER(P)JIM CONNOLLY(B)COUGAR ESTRADA(DS,PER)RUBEN ESTRADA(VIB)DANIEL ZIMMERMAN(G)MATT WROBEL(G)JOE WOODARD(G)
録音は2001年2月 CA
一度、このブログを書き上げてブラウザを閉じて受信メールを開けたらなんと、
NATE BIRKEYからメールが一時間前に届いていた。
嘘のような本当の話。
添付しておこう!!
どうやら、NATEのCDを買った最初の日本人のようだ。
hello masaki,
thank you for purchasing my cd ,hope you've received it and are enjoying the music!
i think you are the first person from japan to have purchased one of my cds! if you like it, please tell your friends.
perhaps i will someday soon be playing in japan - that would be great.
let me know if you'd like to hear from me if that happens.
best wishes,
nate birkey

このCD2ヶ月以上前から情報はキャッチしていたのですが、一昨日ようやく入手致しました。
「電車で轟」のfunky-alligatorさんが買った動機と同じく、私もSEAMUS BLAKE 目当てでした。
そしてこの作品、いつになくSEAMUSのストレートなプレイを耳にする事が出来るのです。
若手新御三家、マーク・ターナー、クリス・チーク、シーマス・ブレイク(ちなみに90年代御三家はジュシア、ポッター、アレキサンダー、70年代御三家はブレッカー、リーブマン、グロスマンかな?)の中で最も分かりやすくストレートな吹奏をしてくれるシーマスでありますが、この作品ではとりわけ選曲にもよるのだろうけどブルックリン派独特の揺らぎ感のある浮遊調のサウンドが薄れいつになく分かりやすいフレーズを多用しているのを感じる。
1曲目がなんてったってショーターの「BLUES A LA CARTE」ですからね。
最近ではイタリアのSPLASC(H)から出た作品でのマーク・ターナーやもうじきFSNTからリリースされるクリス・チークのリーダーアルバムも、以前より皆、分かりやすいフレーズを多用しているのが傾向としてあり、彼らの間で少し音楽的に新しい動きがあるのか、気になってしょうがない。
シーマスのテナーサックスの高域から超高域にかけて、フラジオで巧みなフレーズをあやつる技量はいつ聴いても素晴らしいものがある。
もちろん、60年代のジャズではないので必要以上に熱くなったり、情感を込めたりする事はない。そこは現代のジャズメン、表現領域にある一定の線引きがなされていて根幹にはスタイリッシュ、クールネスといったものが流れている。
そのレベルがこの作品に関して、少し60年代のほうへベクトルが、ぶれているといえばよいだろうか?
この作品のリーダー、CHRIS HIGGINBOTTOMは1977年ロンドン生まれで、11歳でドラムを初め2002年の秋にNYへやって来た。
バードランド、ブルースアレイ、ディアヘッドインなどの店に出演、ゲイリー・バーツ、エリック・ルイス、マーク・マーフィー、イングリッド・ジェンセンらと共演したことがある。
作曲もよくする若手有望株のドラマーだと思う。
アーロン・ゴールドバーグはピアノとフェンダーローズを曲によって使い分けるが相変わらずカッコいいピアノを弾いている。
「THE SORCERER」でのソロなんて、本家本元ハービーよりハンコックを感じさせる?
現代若手ミュージシャンによるワンホーンものを何かお探しの方には今旬の一枚としてお薦めしたい。
CHRIS HIGGINBOTTOM(DS)SEAMUS BLAKE(TS,SS)AARON GOLDBERG(P)ORLANDO LE FLEMING(B)
録音は2004年8月11日
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 気になる売れ筋CD・DVD
- 【先着特典】H+ (通常盤)(並べてH+ea…
- (2024-11-26 20:15:33)
-
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪12/23『日経エンタテイン…
- (2024-11-26 13:07:15)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治サインポスター掲示2『FUK…
- (2024-01-22 04:00:09)
-
© Rakuten Group, Inc.