全281件 (281件中 1-50件目)
-
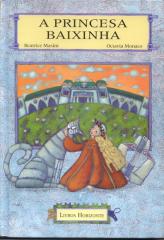
オクタヴィア・モナコ。
売れ残り本の話ばかり続くけど、今日もそのネタで。洋書の絵本。イタリアの絵本らしい。タイトルは、「A PRINCESA BAIXINHA」。意味はわかりません。PRINCESAは、英語のプリンセスでお姫様のことだろう。そのくらいの想像はつく。表紙の絵に描かれている女の子が、そのお姫様か。さてそこで、なんでこの本をここで取りあげることにしたのか。それは、この絵の描き手のことが気になったから。お話の内容は、イタリア語だけにさっぱり、だけど、絵はとっても雰囲気があって気に入ったのだ。すごいオリジナリティがあるという感じではないけど、色使いとか、タッチとか、かなりいいセンスをしていると思う。で、名前をチェックすると、OCTAVIA MONACO(オクタヴィア・モナコ)とある。有名なイラストレーターなのかな?他にも何か書いてるのだろうか?アマゾンで調べてみたら、洋書ではヒットしない。和書で2作ヒット。「クリムトと猫」(西村書店/2005年)「アマチェム星のセーメ」(汐文社/2006年)新しめのアーチストのようですね。「クリムトと猫」の解説読むと、この本でイタリア・アンデルセン賞を受賞しているらしい。イタリアでは既に、注目、評価されているってことですか?日本でも、例えば絵本雑誌とかで、ちゃんと紹介されたりしてるのだろうか。気になるけど、今のところわかったことはこのくらい(別にろくに調べたワケでもないし)。ちなみに手元にあるこの本は、1999年に発行されたもの。外国の絵本って、絵さえよければ読めなくても売れたりするものだから、一度売れ残ったからって、あきらめず気長に売っていくか。オクタヴィア・モナコを誰かに届けたい、そういう思いが生まれてきました。
2009年11月30日
-
100均の売れ残り、どうよ。
「幸せを招くジュエリー風水」「面白いほどよくわかる相対性理論」「殉死」(司馬遼太郎)「ロスト・レイセン」(マーガレット・ミッチェル)「句集蛮朱」(糸大八)「侠客狂言集」「沈黙の岬」(田中光二)「小説葉隠」(奈良本辰也)「タンタラスの虹」(渡辺喜恵子)「女の戦後史1・昭和20年代」店(古楽房)の店頭100均の売れ残り。この先の売り場はない。けど、タイトルだけ並べてみると、なんとなく面白そうな本に思えるのが不思議。「女の戦後史1・昭和20年代」は、朝日選書の1冊なので全然珍しくない、どこにでもある本。一人1テーマの短い評論が集められている。全部で34人=34テーマ。個人的に興味あるのは、「『ひまわり』-中村メイコ」「洋裁学校-鈴木博之」「『君の名は』-佐藤忠男」……、というか、読んでみたくなるテーマ、けっこうあって、挙げてたらキリがなくなりそう。朝日ジャーナルに連載してた記事らしく、中身はしっかりしてそう、読み応えありそう。それでも本は売れない。それが現実。棄てる前に読んでみるか。「タンタラスの虹」の渡辺喜恵子なる著者、まったく知らない。1975年、新潮社から発行されてる本。新潮社から出るなら、それなりの作家?巻末に著者紹介もない。調べてみるか。ウゲッ!!直木賞作家じゃん!!!いくら文学に弱いと言ったって、一応古本屋だぜ。いいのか、それで。と、我が恥をさらすようだが、事実だったので、正直に告白しました。もっと勉強せねば。以下、ウィキペディアからの一部転載。1914年(大3)生まれ、1997年(平5)没、秋田県出身。1959年『馬渕川』で直木賞受賞。『みちのく子供風土記』には幼少時の鷹巣のことなども記載されている。長編三部作『原生花園』のほかに、画家青木繁を描いた『海の幸』がある。主な作品に『プルメリアの木陰に』、『南部女人抄』、『啄木の妻』、長編歴史小説『南部九戸落城』などがある。なのだそうだ。ふーん。で、私の持ってる本、「タンタラスの虹」。ハワイ移住者のもとに写真花嫁として嫁いだ一女性の生涯を描いた作品で、前年刊の「プルメリアの木陰に」と翌年刊の「風に咲くプァマレ」を合わせ三部作を成しているものらしい。装幀は野中ユリ。さっきまでどうでもいい本だったけど、ちょっと気になる本になってしまった。「小説葉隠」の著者、奈良本辰也は本来は歴史学者だよね。小説も書いていたのか。『葉隠』とは言わずと知れた武士道の原典のような本。なんて知ったようなことを言いつつ、ボクもそれ以上はなにも知りはしない。この本は、『葉隠』の著者(正確には口述者)、山本常朝(神右衛門)の一代記とのこと。「野性時代」に連載したものらしい。『葉隠』のことを知ろうとするときの入口にはふさわしい本かも。ちなみに著者には、『葉隠』の口語訳本もある。武士道に関する本もある。読みもせずに処分するにはちょっと惜しい、かな?田中光二「沈黙の岬」は、量産系大衆文学作家の作品なので、いちいちつきあえないと、パスしようかと思ったが、いきがかりなのでちょっと書いとく。田中光二って、戦後の無頼派作家、田中英光の息子というのが通り相場、というイメージだったけど、今じゃ、田中英光って誰?って感じなのかな?この作品「沈黙の岬」については云々する気もないが、UFOハンター・シリーズというサブタイがついてて、ある程度中身が想像できる感じ。田中光二は読んだことがないけど、面白いの?って、読めばわかる、ってか!?「侠客狂言集」は、昭和初期、春陽堂から出てた「日本戯曲全集」の一冊、第35巻。いちいちタイトルは挙げないが、全7作が収録されている。今でも上演される機会のある芝居なんだろうか。伝統芸能の世界には疎いのでわからないが、「侠客狂言集」という標題には、ちょっとそそられるものがある。木版画が挟み込まれているのも贅沢。豊国画、岩井半四郎演ずる白井権八の図。収録作品より注目?100円なら、売れてもよさそうなものなんだけど…。この春陽堂版「日本戯曲全集」、売れた例しがないなあ。「侠客狂言集」のタイトルで「日本の古本屋」で検索してもヒットしない。けっこう稀少じゃないの?この本でしかなかなか読めない作品もあったりして…。誰か、読みたい人、いないのかなぁー。100均の売れ残り=処分本を前にして、ホントに価値ないの? という疑問から、とりとめなく書き連ねてきたが、疲れたからここでやめる。けど、マジ、このまま処分するには惜しいような気がしてきた。とはいえ、商売。値段のつかない売れない本、抱えるワケにもいかない。早い話、本が多すぎるのがいけないのだ。見切るのが商売、と、誰かが言ってた。感傷に意味はない。わかってるんだけど、ね。ホントに買いたい人いませんかー。
2009年11月28日
-
長田幹彦『青春時代』。
今、手元に『青春時代』という本がある。著者は、長田幹彦。長田幹彦なんて言われても、「誰よ、それ」ってな答えしか帰ってきそうにない。それがほとんどの人の正しい反応だろう。ボクだってたいして知らない。文学史を読んだり、昔の作家の回顧録や交友録などを読んでれば目にする作家ではある。けど、実際に長田幹彦その人の作品を読んだことはない。特別の思い入れもない。が、この本、それこそ彼の回顧録。彼が知りあい、つきあってきた明治末から大正時代の文人たちの動向も描かれていて、それなりに貴重な証言本になってる、ように思う。なので、探してる人もいるんじゃないか、そこそこの値段ですぐに売れそう、なんてトラタヌ勘定して、あれこれ手を尽くして売りに出したがさっぱり。つい先日のサブナード「古本浪漫洲」の催事の300円均一企画に出してもダメ。売れ残って戻ってきた本を整理しつつ、さてこの先どうしようかと思案しているのが、今。見限って処分するのは簡単だけど、なんか惜しい、というか後ろ髪を引かれるような感覚。中をパラパラすると、例えば彼が最初に文壇と関係をもった「明星」=新詩社に関する話、「パンの会」のドキュメントなどは、まさしくその現場に居合わせた当事者ならではのエピソードが盛り込まれていて、永井荷風をゲストに招いた日の模様など、憧れの人を目の当たりにした高ぶり、緊張感が伝わってきて面白く読める。当時の人気女優、松井須磨子と一緒した一夕のことは、ちょっとした読物仕立てで、須磨子の素顔が垣間見れる。と、興味深い話題がいろいろ詰まってるのだけど、いまどき、「明星」も「パンの会」も松井須磨子も、もうたいして人の気を引かないのかね。ボク的には、ハマりのネタなんだけど……、さ。ということで、もう売りに出してもしょうもなさそうだから、自分の蔵書に加えておくことにするか。パラパラと目を通しただけだから、一度ちゃんと読んでみてもいいか、ってね。ここからは蛇足。長田幹彦の代表作は「祇園夜話」という作品らしい。当時のベストセラーだという。今でも簡単に入手ができるのだろうか、安く買えるなら読んでみてもいいかなと思い、ネット検索してみた。アマゾンではヒットしない。「日本の古本屋」では、戦前の新潮文庫版が2点、大正時代の春陽堂版が4点掲載されている。文庫版の最低価格は2500円。金額自体はさして高くもないだろうけど、そこまで払って読みたいと思うような金額でもない。が、春陽堂版は、上下本で全て30,000円以上。それって、長田幹彦がどうのじゃくて、装幀を担当した竹久夢二の価値みたい。表紙を飾る夢二美人の木版への人気のよう。なるほどね。長田幹彦、忘れられた作家の一群のひとり。古書市場に出てきたら、少し気にしてみよう、かな。入手できたとしても、たぶん売れそうもないけど…、ね。
2009年10月07日
-
イベントいろいろ。
昨日夜、新宿サブナード「古本浪漫洲」の搬入を終えて、今朝の今は、フッと気持ちが緩んでいるところ。とはいえ、たぶん一瞬のこと。10/4(日)に組合主催の大掛かりな「古書の日」イベント、『日本の古本屋博』が予定されていて、明日あたりから、準備が佳境に入っていくだろうから。それ以外にも、来月末(10/31)には、自分が主宰する催事『ちいさな古本博覧会』が控えていて、今回は4回目だけに、世間的認知を今まで以上にしっかりとしたものに固めていきたいと思い、いろんな併設企画を準備して力を入れてやってく予定なので、それがけっこうタイヘン、なのだ。今回の一番のポイントは、ボクが参加・運営協力しているもうひとつの催事『本の楽市』との連動企画として組み立てたこと。『本の楽市』は、これまでは、「座・高円寺」のホールがメイン会場だった。が、今回は、都合よく使える期間がなかった(この時期は、ちょうど『高円寺フェス』が「座・高円寺」でロック・フェスをする予定)。なので、特別企画として、「楽市」メンバーのうち、高円寺に店を構える本屋が主体となり、お互いの店の品物を少し入れ替えて、それぞれの店に他の店の売り場コーナーを設置するという“シャッフル企画”を実施することにした。『ちいさな古本博覧会』と同じ、10/31(土)に始まり、『高円寺フェス』が実施される11/8(日)に終るというスケジュール。点を線にし、面に広げようという狙い、なワケです。この1週間、高円寺が、三つのイベントの相乗効果でおおいに盛り上がる。と、そんなイメージを抱きつつ、それが実現できるよう、いろんな企画を鋭意固めているところ。現在進行中の企画をいくつか、宣伝を兼ねて披露すれば、まず、博覧会と楽市の共同企画と銘うって、「夢二の詩に音をのせて~セノオ楽譜・夢二表紙絵展と演奏会~」というのをやる。セノオ楽譜とは、大正から昭和初期にかけて、洋楽文化が大きく花開いた時期、音楽普及を企図して発行された楽譜。大正ロマンを代表する抒情画家竹久夢二は、その表紙絵を数多く手がけ、セノオ楽譜のシンボル的存在にもなっている。また、夢二は、詩も多く提供しており、「宵待草」はその代表作で、今でも歌いつがれている曲として有名。そんな夢二の表紙絵楽譜を約30点ばかりですが、茶房高円寺書林店内に展示し、初日(10/31)と最終日(11/8)に、夢二が詩を書いた楽曲だけ、譜面を音にしてみようというのが今回の企画。「宵待草」以外の、今では忘れられた夢二詩の曲を今に甦らせようという趣旨。どうですか、聞いてみたくなりませんか?もうひとつ、力の入っている企画が、「人形作家Kao-キャトランドーレの世界展」。これは、ボクの店、古楽房でやる企画。「博覧会」の初日、10/31(土)から1ヶ月、11/29(日)までやる。間に、これも演奏会やトークのイベントを2回ほど入れる計画。Kaoとは、本名堀内薫さんという人形作家。キャトランドーレとは、猫と人間の合いの子のような顔立ちをした妖精。キャトランドーレたちが活躍する、「水晶幻想」という物語世界を自ら創造して、そこに登場するキャラクターを木や陶器、いろいろな自然素材を駆使して創りつづけている。その数、すでに100体以上、壮大な物語世界の登場人物たちだ。最近では、キャラだけてに飽き足らず、背景世界の造形にも凝り始めている。今回の展示は、そのの物語世界を、「古楽房」店内に再現する試み。書店という本来展示目的で作られていない空間の中、本と本、棚と棚の合間に異空間が現出するというイメージを想定。どんな、ファンタジー世界が店に構築されるのか、ボク自身が楽しみ。他にも、高円寺店巡りクイズや高円寺フェス内ミニ楽市企画なども予定。「博覧会」期間中に、会場の西部古書会館でやるイベントも準備している。“高円寺と本”をコンセプトにしたフリーペーパー「こ・ら・ぼん」も近々創刊する。あー、やることがいっぱいだーー。でも楽しい。楽しいということが、人生一番。しんどいことでも、楽しんでやれればそれでいい、じゃない?ということで頑張らず頑張ろう。
2009年09月29日
-
システム手帳復活か。
古本屋になるずっと以前、広告関係の仕事をフリーでやってた時代、シテテム手帳は命綱だった。すべてのスケジュールがそこに書かれていた。一日に打合せや、原稿の締切、撮影やイベントなどの現場作業、覚え切れない予定がそこに詰まっていた。時には、分刻みというのもまったく過言でないくらいハードなスケジュールに追われる日々が続くことも。今、振り返れば、もうずっと昔のことのようで実感もないけど…。前の仕事をやめた理由はいろいろあるのだけど、そんなハードさに音を上げたという側面は否定できない。古本屋になって、悠々としたペースでのんびり仕事しよう、スケジュールに終われない仕事がいい。と、思った。システム手帳とはおさらば。の、ハズだった。実際、古本屋になった最初のころは、一日店番しながら、ネットに出品本を入力、というスタイルで、時間のゆとりは充分にあった。なにか動かなければならないような予定は1週間に1度くらい。メモとかしなくても頭の中に記憶させておけばコトはすんだ。が、最近、また超過密なスケジュールの日々が続くようになった。望んだつもりもないけど、アレコレつい手を出してしまう性格のようで…。それはそれでいいのだけど、困るのは、予定ややるべきことを、うっかりしてしまうことが増えたこと。予定が多すぎて覚えきれない、というより、なんか年をとって記憶力がマジ減退している感じ。さっき記憶させたハズのことを、そのソバから忘れていく、みたいな。同時にいろんな記憶をプロットしておくことができず、トコロテン式にひとつのことを記憶させると前の記憶が押し出されてこぼれる、みたいな。なんてこった。年をとるというのはそういうことなのか!!!???けど、それじゃ仕事にさしつかえるので、またシステム手帳を復活させなきゃならないか、と真剣に思ってる。なにせ、アナログ人間なので、ケイタイでスケジュール管理なんてこと、できないし。さて、今日は、久々に一日事務所(倉庫だけど)の予定。処理しなきゃなんない事務仕事がいろいろ溜まっている。来週は、ほとんどゆっくり机に座ってられる時間がとれそうにない。日がな、机仕事に徹しましょう。
2009年09月06日
-
商売無縁だけど…。
ドトーの8月だった。9月に入ったら、少し楽になるだろうと思っていたが、ちっともそんな気配はない。なんで??秋に向けて、いろんなイベントが続々控えていてその準備でタイヘン。9/20は、西荻ブックマークのボクの回。開高健と高校からのつきあいという鈴木豊(ゆたか せん)さんによるトーク。芥川賞をとって、一躍時の人になる以前の開高について、その若き日の素顔を語ってもらおうという企画。鈴木氏しか知らない開高の姿が見えてくるはず。詳しくは、http://nishiogi-bookmark.org/で。定員100名にまだ充分余裕がありますので、興味を持たれた方はぜひご来場ください。10/4日は、組合の古書の日のイベント。なかで「体験古本市場」というコーナーがある。そこでは、一般の参加者の方に、「古本市場」で実際の売り買いをしてもらおうというもの。古本屋になった気分を楽しんでもらおうという意図。市場には、いろんな取引の入札形式があるのだけど、「椀伏」という今では行われてない入札のやり方を、デモとして、ショー的に復活させようという企画も盛り込まれている。お椀のフタを使って入札するユニークなスタイル。戦前は普通に行われていたようだけど、戦後30年代には廃止されたのだという。先日、実際の「椀伏」を経験したことのある組合の長老方が集まって、実演と解説をしてくれた。なんだか、古きよき時代を彷彿とさせて、なかなか興味深かったけど、これをショーとして仕立てるとなると…。どうなりますか。11月には、自分の店「古楽房」で、人形作家Kaoさんの展示企画を計画している。それについては、またの機会とするけど、どれもごれも、「即売展」ような直接すぐ商売に直結する企画じゃない。西荻BMと組合「古書の日」はいわずもがな。即売催事を半減させて、売りの減少が確実ななか、その補填対策に取り組まなければならない時期に、そっちになかなか手が回らない。いいのかね、こんなんで。とも思うけど、ま、商売一筋というのもの、あまり自分向きではないし…。いいとしよう。けど、正直、人を楽しませるイベントを作るってことは、苦しいこと、だね。んー。
2009年09月04日
-
「本の楽市」終了。
昨日で、座・高円寺の「本の楽市」が終わった。最終日なので、終日店番。いいことか、悪いことか、たいして忙しくもなかったので楽チン。久々に、少しゆったりまったりした気分を味わった。今回は、会場の座・高円寺で話題になるような企画が用意されてなかったので集客的には今一。「本の楽市」だけの力で、人を集められるようしていかなきゃ、というのがこれからの課題か。集客はたいしたことはなくても、個人的にはむしろ思った以上に人が来てくれてた気がする。もっとダメだと思ってた。今回のレベルがスタートのラインとするなら、そんなに悪くはない、と思う。最終日の昨日は、一般参加の「一箱市」。炎天下をイメージしてたけど、あいにく雨。暑い中、来場してくれたひとのためにと、冷たい飲み物販売も企画されてたけど、ちょい空振り。店番やってた「にわとり文庫」さん、ご苦労さま。けど、本を売るだけじゃなく、飲食も伴うような催事が、ある意味、縁日的感覚、お祭り気分を盛り上げるのに一役買うワケだから、やれてよかったと思う。まずは既成事実づくりから、という理解でいいんじゃないかな。昨日は、プロの古本屋も「一箱」仕様に模様替えして販売。在庫量が縮小されたので、個人としては、売りはまったく期待してなかった。一般の「一箱」のおつきあいと割り切ってた。のに、さ、期間中で一番の売上げを稼ぐとは?なんなのさ?バイトくんがせっせと値札を書き換えてくれた値下げ効果だね、きっと。けど、売上げに貢献したのは、劇場関係者がまとめ買いしてくれたせい。舞台装置関係の高めの本が売れた。親と子の本が会のテーマだったのに、そんな本で稼げたとは。けど、劇場関係者もお客、なら、そっち系を充実させるほうが売れるのか、って?次回は、そのあたり少し戦略的にやってみてもいいかも。といいつつ、次回がいつかは、まだ未定。手探りだった1回目、2回目の経験を踏まえて、3回目は、今後につながる形を固めるつもりで取り組む必要がありそう。もっとがんばりましょう。
2009年08月03日
-
果てしなき戦い。
「千里の道も一歩から」「ローマは一日にしてならず」昨日、倉庫整理をしていて、片がついたのは、いわゆる「氷山の一角」程度の量。まだまだ、相当の量の本が、放置されている。忙しい合間を見つくろって手をつける、というようなやり方じゃとても追いつかない。多分、増える量の方が減る量より確実に多い。それはまず間違いない。古書催事を今の半分くらいに減らすなら、もうそんなに本を持ってる必要はない。どんどん処分すべし。なんだけど、セコい性格のせいか、なんも考えず全部市場、みたいな方法がどうしてもできない。一本一本の束をほどく度、「これはまだネットで使える」「店ならなんとかなるんじゃないか」「どうせ市場に出してもろくな値段になりそうにないなら、均一がまだましか」…、…、…。などと、踏ん切りの悪いことといったら…、自分であきれるくらい。けど、ま、それが自分のスタイルなら、それはそれで、時間をかけつつゆっくりやっていこう。というのが、冒頭の諺の心境。ただ、本が増えないなら、時間が解決するだろうが、本は知らない間に増殖していくからなぁ。果てしなき戦い、なんだよなぁ。ゾッ!!
2009年08月01日
-
ちょっと休憩…。
今日は朝から、倉庫の在庫整理。8月7日・8日の「城北展」と12日から始まる「リブロ池袋古本まつり」の準備も兼ねて。朝からずっとやってるのに、まったく片付いた気がしない。それだけ、ほったらかしになってる荷物が大量にある、ということ。それも、ホントくだらない荷物ばかり。催事の300均一にも使えそうにないモノがぞろぞろ出てくる。だから、やれどもやれども、催事の荷物もろくに作れない。ただただ、疲れる。それだけ。あー、疲れた。休憩。……………昨日は、組合の支部総会があった。4時からだけど、その前に神田本部で、広報部会も。神田から高円寺まで車で移動。3時過ぎに出て、余裕で間に合う予定、だった。が、途中ちょっと小用があったので、そこに寄ってたら、とんでもないハメに。早稲田通りが中野の手前から、まったく動かなくなった。普通にスイスイいけば、10分もかからない距離。結局、会議に30分も遅刻してしまった。こういうのも、マーフィーの法則、っていうのかね。さて、と。片付け&荷物づくり、再開するとしますか。
2009年07月31日
-
あづま通りは古本ストリート!?
西部会館の即売会「中央線展」を終えた。いやー、サイテー。会全体も、個人的にも。これって、一即売会だけの問題じゃなく、全体的な傾向、潮流。たぶん、もう止まりようがないような気がする。古書市場全体の構造的な要因が潜んでそうだから。「即売会は役割を終えた」とまで言い切る古本屋さんもいるくらい。ま、まだ一概に断定はできないだろうけど、大きな視野でみれば、間違いではないと思う。少なくとも、今のスタイルの会館催事に限定すれば、先の見通しは暗い。時代に合った催事の方法を見つける必要に迫られている。政治の世界じゃないけど、構造改革が急務、だね。西部古書会館のそばに、24日(金)にブックマートがオープンした。会館をちょっと先に行って、あづま通りとぶつかる角。以前は、ポプラというコンビニがあった。あづま通りには、去年の暮れ、ボク自身、「古楽房」という店を出した。既に、老舗筋の「越後屋」、古本酒場で有名な「コクテイル」、ヒップホップ系のCDなんかも充実している「ZQ」、非組合系の「十五時の犬」はいかにも本好きに受けそうな店、さらに貸本の「大竹文庫」と、ユニークな古本屋が集まっていた。そのゴチャマゼのユニークさが面白く、自分もイベント・スペース・タイプの古本屋というコンセプト(今、ちょっと方向転換中だけど…)で出店したワケ。どうせなら、もっといろんな古本屋さんが集まって、不思議な魅力の古本ストリート、なんてことになったら面白いんじゃない、なんて思ってた。そこに、ブックマート。んー、大手かよ。ま、いろいろあるのがいい、ってことでいえば、それも歓迎、か。客筋がバッティングするワケじゃなし。むしろ、シンボルタワーとなって、マグネット効果を発揮してくれればいいか、ってね。でも、オープン当日、なんか店内、閑散としてたなあ。初日は、人でごったがえすくらいじゃないと…。計算狂ってんじゃないの?この場所に進出したのって、高円寺という土地柄だけじゃなく、古書会館がすぐ近くにあるというのも理由の一つじゃないかと思うけど、会館催事のお客さんが、ブックマートまで足を伸ばしたという形跡はあまりなさそう。決定的に客質が違う、ということか。相乗効果は、期待できない、ってこと???早期撤退しそうな予感、も??あづま通りに人の流れを作るために頑張ってほしいものだけど、ね。あ、それと、あづま通りの早稲田通りからの入口の角にも、古本屋?らしき店が出現してた。古本専門じゃなく、雑貨なんかも扱ってるみたい(そっちがメイン?)。いつのまに?ぜんぜん気がつかなかった。車で通り過ぎたときにチラッと確認しただけなので、実態はよくわからない。気になるから、今度ちょっと寄ってみよう。んー、あづま通りの古本ストリート化は、見えない力によって着々と進行してる、か???
2009年07月27日
-
昨日の続き?
次に書くのが、また4ヶ月後というのもナンだから、頑張って(?!)今日も書く。今日は、午後からずっと組合の仕事。組合運営の古書検索サイト「日本の古本屋」を管理しているTKIというセクションの会議。これが長い。月に1回の会議だから、議題がいっぱいあって、半日かけても足りないくらい。それでも、この春に実施したリニューアルやクレジットの導入のフォローも落ち着いたとこで、少しゆったりしてきたけどね。正規の会議が終わった後の、有志による延長戦も定例。それを終えて帰ると深夜。んー、もう何の作業もできない。明日は、座・高円寺の『本の楽市』の搬入日。出品しようと思ってる荷物の値づけが、ほとんどできてない。どうするんだーーー!!!間に合わないのは、ほぼ確実。前に使った荷物の残りで格好だけつける、しかないか。って、そうやっていつも、ごまかしてお茶を濁して終わり。意味ないなぁー。結局、昨日の結論、「催事を減らそう」に行き着くワケだ。『本の楽市』はやめない、けどね。割り当てられた売り場は、会議用長テーブル1台と、品物もたいした量は置けないから、売上げもたかがしれてる(それでも売る人は売るのだが)。けど、売上げ以上にイベントとして楽しい。まず会場が「座・高円寺」という劇場のホールというユニークな場所。だから、来るお客さんも、いつもの会館催事の古書マニア系とまったく異なる。そして、新刊本屋さんや、古書組合に属してないインディペンデントな本屋さん、さらにはアーチストなども巻き込んだメンバー構成が新鮮。一般参加の一箱や、お楽しみイベントもある。ただの古書催事というより、高円寺のお祭りという考え方が核にあるから、これからの広がりに期待がもてる。ここをベースにしたフリーペーパーの創刊準備号も、今回発行されたし、この先は独自のサイトも計画されている。参加していることに意義があると思えるのがうれしい、のだ。これからは、そんな催事だけあればいい、って感じかな。意図したワケではなかったけど、なんだか昨日の続きの話になってしまった、ね。
2009年07月16日
-
なんとんなくの今の気持ち。
4ヶ月ぶりに書きます。今日、これから長野に出張。その前にちょっと空いた時間。妙にうれしい。先週の土・日に即売展をこなしたばかりだが、そろそろ即売展の整理を始める必要があるな、と感じた。今、大小合わせて年24回の即売展をやっている。月2回ならさほどの負担でもないだろうと増やしてきた。けど、最近、それが負担になってきた。一番の理由は、今年になり、店を開いたことだろう。やはり、店には手がかかる。半端にやると、半端な答えしか出てこない。店にもっと注力するには、他のなにかに割いている労力をカットするしかない。で、即売展より店。と、今は、そんな感じ。特に、会館催事の魅力が失せている。売上げも、この2,3年ずっと右肩下がり。自己努力だけの問題ではなさそう。不況だけの問題とも言い切れない。一番の問題は、マンネリ感じゃないか、と思ってるけど、今日はそのことに突っ込むもりはない。なにはともあれ、催事を今の半分くらいにしよう。キャパいっぱい、というのはダメだ。常に、2割から3割くらいは余力のあるような状態にしていたい。なんて。ま、ムリかな?そんな余力が作れるほど、安定した経営状態じゃない。し、それよりなにより、余力が生まれたら、きっと、次の新しい何かに手を出すに決まってるから、ね。けど、それでいいのだ。マンネリの催事をダラダラ続けるくらいなら、なにかもっと別の可能性のあることにチャレンジするほうが面白い、楽しい。同じ時間、体力、気力なワケなら、さ。気持ちが弾むようなことに投入したいから、ね。
2009年07月15日
-
あぁ、タイヘン。
3月、だよ。いつのまに?、だよ。あまりに忙しすぎる。一日、フルタイムで動いているのに、処理しきれないことがどんどん山積みされていく。なんてこった。「やれる限り、なんでもやる」の精神で、アレにもコレにも手を出してしまうそのツケ、だ。もはや、「やれる限り」の限界は、とっくにオーバーしてる気が。そろそろ、「やらない」という選択、「やめる」という決断が必要、かな。などと言いつつ、今はとにかく、今やらねばならないことを、なんとかヘマらないようにこなしていく、のみ。そうして、気がつけば、しらないうちに月日が過ぎていたりする、ということの繰り返し、ってコトか?ま、そういう生き方もアリ、ってコトで。いいか?!4月11日(土)、12日(日)に『ちいさな古本博覧会』第3回目開催する。去年、今までとは違う新しい催事を作ろうと立ち上げ、今回が3回目。第1回目には、確かに、従来の古書催事の客層とは明らかに異なる人が来てくれたという手ごたえがあった。イケる、という予感を感じた。けど、2回目は、それをもう一段階上のレベルに持ち上げるということに結びつけられなかった観が残った。その反省を踏まえ、3回目は、確実な成果をあげねば、という気合でいたのだけど…。思うほどの活動ができてない。忙しさの理由にはできない。なんか、少し、やり方を変えてみる必要がありそう。その場の売りだけを目的にするのではなく、「新しい顧客層を開拓し、店をプレゼンテーションする場と機会を創る」というコンセプトは、これから絶対にやってかなきゃならないことだと信じている。けど、その方法論は?まだ模索中。答えはない、今のところ。Try & Try & Try、Try、Try …。「やることに意義あり」?「継続は力」?って、ぐだぐだ考えてても始まらない。3回目の開催まで、あとひと月余り、フライヤーがまだできてないぞー!!なんとかしろーー!!!なんとか、せねば。あぁ、タイヘン。
2009年03月01日
-
暮れも正月も、ない。
アレアレという感じで、数えれば、今年もあと4日だよ。もともと、大晦日だろうが正月だろうが、365日のうちの1日だと思ってるから、残り4日だからといって、特別な感慨もないのだけど、今年のうちに片づけておかなければならない仕事がいろいろあるのは確か。高円寺の店「古楽房」(組合には支店扱いにする)の本格オープンを1月からと宣言してるんで、その準備がタイヘン。什器類の運び込みからレイアウト、商品の陳列、ディスプレイ。力仕事だ。いやいや、その前に、店に並べる本を揃えなきゃ。毎月、テーマ・ショップにして商品を入れ替えるという構想。その第一弾は、「アート系」をテーマにしようと思ってる。たまたま最近あった宅買いで、図録や画集がかなりあったから、それでやれそうと思いついた。しかし、かなりある、といっても、店一つ埋めるだけの量じゃない。いいものも混じってるけど、全体のレベルはそこそこ程度。もうちょっと、グッとインパクトが与えられる品が欲しい。のだけど、ボクは、一時美術系から撤退するつもりで、持ってた本をほとんど処分してるので、補充が効かない。特に単行本に、コレといったモノがない。映画本とかをテキトーに交ぜつつ、ごまかすか。「古楽房」は、イベント型テーマ・ショップであるとともに、collabonet_project(古本屋の集まり)のメンバーによる共同店舗という性格も持ち合わせている。なので、そのメンバーからも少しずつ商品を出してもらえることになっている。コクテイル書房は、絵はがきを出すと言ってる。常田書店は何を用意しているのか知らないが、あそこのアート系の品物はけっこう強力だから期待大。とんぼ書林さんは、なんと、こけし!!ちょっと場違いな気もするが、不思議な店の感じが出たら、それはそれで面白いかも。アートなんていうと、妙にスカした印象が先行しがちだから、ね。裏切るのもいいかも。店を一緒にやってる関くんも、自分の屋号を作って、参戦してくれる。彼はけっこうスゴい写真集を持ってて、それを出すと言ってる。森山の『写真よさようなら』などは、学生時代、同時代的に買ってるのだ。目玉のひとつになる、ね。とかなんとか、一応カッコはつきそうだけど、なんせ、自分の荷物、作るのはこれから。正月明けは、イルムスの目録原稿も出さなきゃならないし、正直、正月なんてのんびりしてられない、ぞ。
2008年12月28日
-
暗い時代に前を向いて。
派遣社員の解雇だとか、内定取り消しだとか、景気の後退感は、いよいよ高まるばかり。古本の世界でも、「本が売れない」という声がアチコチから聞こえてくる。古本なんてのは、不要不急の類のモノだから、サイフの中身が寂しくなれば、買い控えされてしまっても、しょうがないね。客の買い控えで市場が縮小するのも問題だけど、ボク的には、それ以上に競争の熾烈化がタイヘンな問題に思えてる。縮小しているハズの市場なのに、そこに参入してくる業者はどんどん増えてる。特に、アマゾンなんかでは、その傾向が著しいように思える。誰かが入れば、誰かが押し出される、トコロテン状態。勝ち組、負け組なんて言葉はキライだけど、ウカウカしてると、あっという間に押し出されて、「生活できません」なんてことにも。いつ首を切られるかわからない派遣社員の人たちとほとんど同じような不安定感の中にいるように思える。シビアだね。ホント、こんなにシビアなのに、古本商売しようと思う人たちが続々現れるなんてのは…。不条理だ。けど、それでもどうでも、やるしかない、前に進むしかない。どうすれば、もっと売れるのかを考えて、できること、可能性のあることに、不断にチャレンジし続けていくしかない。結果は後についてくる。ま、坂本龍馬の心意気だよ。たとえ、ドブに落ちて死ぬとしても、前向きに死にたい、みたいな。ね。組合の仕事のついでで、洋書会を覗く。なにげに札を入れたら、かなり落ちてしまった。洋書なんて、まったく取り扱い範疇外の商品なのに…?。アマゾンでも、催事でも、一応は売り場はあるし、ケガはしないでしょってだけの理由。だって、安いんだもの。古本屋なんてのは、やっぱいい加減な商売なんですか、ねぇ。って、そんなバカみたいなコトしてるのは、オレだけ、か???。ボンダイさんからは、「よく買うねえ、売れてるんだねえ」なんて言われる。誤解だって。河野書店さんには、「洋書会入るか?}と声をかけられる。英語は読めてませんってば。けど、考えてみると、中央市会とか、明治古典会とかほとんど行かないのに、洋書会ではマメに買ってる。やっぱヘンかも。
2008年12月10日
-
寒い冬に向かって。
日々、ずいぶん寒くなってきた。倉庫事務所のエアコンの効きが悪くなってきた。寒さが厳しくなったせいかと思っていたが、どうやらフィルターに汚れが溜まってるようだ。「フィルター洗浄」という表示が出ている。確かに、古本を扱う仕事をしていると、ホコリだらけになる。古い黒い本なんか、ただポンとその辺に置いただけで、ページの間から煙のようなホコリが立ち上がるのが見えたりする。そんなホコリを一年吸ってたら、そりゃフィルターも詰まるだろう、って納得。自分の肺も、同じか? なんて想像すると……。肺には、着脱可能なフィルターなんてないワケで、はい洗ってキレイになりました。なんて、都合よくいかないワケで。ゾゾッ。マスク必携かなあ?設置されてるのは、業務用のデカいエアコンなんだけど、それって、フツーにフィルターを取り出して洗えるんだろうか?よくわかってない。業者に頼むと、バカにならない費用がかかるらしい。今月に入って、ウチの犬が、なんかの拍子に、突然椎間板ヘルニアになって、後肢がマヒしてしまった。昨日まで、うるさいくらい動き回ってた犬が、突然、動けなくなった。本人に、その自覚がなく、動けないのに、動こうとするする姿が痛ましかった。手術しなければ完治はしないらしく、先週、手術した。そこで予定外の出費が発生し、バイト代やら、市場の支払い用にと思ってたお金が消えたとこ。さらに、ウチの家のエリアが、プロパンから都市ガスへ切り替わることになり、その工事代も年内に工面しなければならなくなった。そこに来て、新店開店なんてことも始めた。当然、いろんな出費が嵩んでいる。おい、おい、おい、どうすんだよう!!!こんな状況で、フィルターの洗浄代なんで用意できっこない。寒い冬を過ごす覚悟を決める、か。
2008年12月09日
-
<本のお祭り>
新しい店の名前は、「古楽房」と名付けた。単なる当て字。母体がcollabonet projectだから「こらぼ」。ま、へ理屈をこねれば、「古本を楽しむ部屋(房)」と考えていい。房は、ぶどうの房のように、粒が群がり集まっている状態のことでもあるから、「個々のメンバーが集って、協同で活動していく」collabonet projectの主旨を表してもいる。って、それもこじつけだけどね。ま、そんなこんなで、昨日、『ちいさな古本博覧会』のメンバーが「古楽房」に集まり、次回の計画について話しあった。『ちいさな古本博覧会』は、今回が3回目。古書催事として、新しい顧客層の開拓というのが、大きなテーマだった。過去2回、実際に会場に来てくれる人たちをみると、その成果は充分に達成されつあるという手ごたえは得た。けど、まだまだ数的には物足りない。もっと広がり感がほしい。それは、告知力不足で、まだまだ知られていないということ。それはそうなんだけど、それ以上に、内容的にまだ「古本博覧会」のオリジナリティというのが出せてないということもでもある。早い話、面白くて、得して、驚きがあって、タメになって………、内容さえしっかりしてれば、来てくれた人の心にはミートできるはず。感動は感動を伝える。人から人、取り立てた宣伝はしなくても、伝わるものは伝わるハズ、なのだ。だから、これぞ『ちいさな古本博覧会』といえる、「他の古書催事にはない何か」をみつけて、創出していくことがきっと大切なんだろう。と、そんな心意気で、まずは、メンバー自身が、楽しめるそんな企画をいろいろ考えてます。『ちいさな古本博覧会』は、。とにかく面白く、とにかく賑やかに、とにかくノリノリに、本が好きな人たちなら、なにがなんでも行きたくなる場、そんな場になれれば、と思ってます。ps.)「古楽房」では、11日から、プレ・オープン企画として、「店頭【100均】ワン・コイン市」(仮称)を年内いっぱい(28日まで)開催します。新店舗の場所は、杉並区高円寺北2-34-6。「古本博覧会」の会場・西部古書会館から、あづま通りに入り、古本酒場コクテイルのちょっと先、右手、林医院の向かいです(古楽房の看板はまだついてません)。高円寺に来た折には、ついでで覗いてみてください。
2008年12月07日
-
毎月店が替わる店。
今日は、資料会の大市だ。ボクには関係ない。けど、大市で、ガンガン売り買いしている同業者はいっぱいいるワケで、自分がいかにショボい商売をしているのか、痛感させられますね。そんなショボい商売しかできない身でありながら、やろうとすることは、けっこう金のかかることばかり。ほとんど身の程知らず、かも。というわけで、新しい店、先月末に契約完了。前の店の内装が一部残っているので、それはそのまま使わせてもらうことにする。しかし、こんど借りる店、なんとトイレがついていない。店の入ってる建物はマンションと一体となっており、前の店は、建物のオーナーが経営していたらしく、トイレ(あるいは事務所)はマンションの一室を使ってたようなのだ。なので、トイレの設置だけは手を入れざるを得ない。それが、だいたい明日で完成。金曜日には、内部を掃除。土曜日から備品を運び込む予定。10日に、電話とネット回線がつながる。というような流れで、11日から、前の日記にも書いたように、店先だけでも営業することにする。看板もできてないし、内部もまだ未完成なので、あくまでプレ営業だけど。店内での営業は、ちょっと変ったコトやってみようか、と目論んでいる。10坪ある店の半分は、事務所兼倉庫として使う予定なので、実際使えるスペースは5坪。5坪の店では、今の大型化の時代、なかなか店の魅力を出すことが難しい。なら、固定的な店として営業するより、月ごとに店が変っていくみたいなイベント的な展開のほうが面白いんじゃないか、なんて。店は、常に新鮮なほうがいい。毎月、新しい店が開店する、というやり方でそれを形にしてみては、という発想。催事をいつもやってるから、あるタイミングに合わせて、商品を作るということには慣れてる。それをよりコンセプチュアルに専門店ぽく作って、ローテーションで回していく、なんてのが面白いと思ったり。自分で、異なる顔を持ついくつかの店を経営するんだ、というような気合で。たまには、他の店に場貸しで出店してもらってもいい。ひと月だけの臨時店舗として。とにかく、基本の考え方は、ただのフリー・スペース、なんでもできる、なんでもやっていい場ということ、だね。とりあえず、新年1月から、自分でトライしてみる。たいへんなのは、コンセプトにあわせた商品をいかに仕入れられるか、だね。ちょっと気合入れないとできない、ぜ。
2008年12月03日
-
要らない本で家賃を稼ごう。
この土日は、即売展だったけど、そっちはバイト君に任せて、ボクはひたすら溜まってた本の整理にいそしんだ。一日、フルで事務所(実際は倉庫)仕事というのは、最近、ほとんどなかった。なんか、ホッとする。って、くつろいでちゃイケないんだよ。手がつかずに、「そのうち」と放置したままにしといた本が、山積み。市場で買った本、宅買いで買った本、催事から戻ってきた本、ネット出品ではじかれて催事用としてストックされた本、あれやこれや。ちょっとずつ、整理にかかるものの、一日やったって、たいして捗らないのは、なぜ??本が多すぎるってことだな(ほとんど、あってもなくてもいいような、しょーもない本ばかりなのに)。しばらくは、買うのをやめて、一旦、倉庫を空にするくらいの気持ちで整理しなきゃどうにもならない、かねぇ。検討してた店、ほぼ契約という段階に。契約しても、開店準備もあるから、実際に店として営業できるのは、年明けからだろう。が、店頭の外売スペースを使った均一コーナーだけでも、先行的にやってしまうというのはムリじゃない。「古本屋ができるよ」という予告宣伝を兼ねるようなかたちで、12月に入ったら、即始めてみるか。としたら、一人即売展感覚で、徹底放出作戦を展開してみるというのも手。要らない見切り本は、どんどんそっちに回すとするか。し、なにより、開店準備期間中でも家賃は発生するのだから、店頭でガンガン稼いでくれなきゃ困る、ということでもある、のだ。店頭でしっかり、家賃分稼げれば、しめたものだ。って、獲らぬ狸、かな???
2008年11月24日
-
なんとかなるでしょ。
某古書店主と車を同乗した。目録メインで商売をしている人。総合的なもの、専門的なもの合わせて、年間10回くらい発行しているという。ちょうど、今日校正しなければならないという次号を見せてくれた。ほとんど、ボクには無縁の本ばかりが並んでいる。聞くと、2万5千円以下の本は入れてないのだとか。平均価格が10万円以上で、総点数1000点以上だというから、総額は1億以上、ということになる。1冊1000円程度の本をせっせせっせと売ってる身には、だだただ、へー、ほー、と感心するのみ。目録で食ってる人のスゴさだね。同じ古本屋、なんて言っても、まったく次元の違うところで生きてる、って感じ。けど、そういう商売を続けていくのも、仕入れとか作業の大変さとか、決して楽なのかどうかは、わからない、けどね。持続するのは、けっこうシビアなような気もする。ま、なんにしても、今のボクには他人事だ。店を閉めたばかりで、1年間ほどは、雌伏の期間として力を蓄えよう。なんて、考えてたのに、ちょっとしたキッカケがあって、年明けくらいに、また店をやろうという気になっている。とは言っても、純然たる店という感じじゃない。倉庫外の活動拠点、と言ったらいいかも。「古本博覧会」の事務局機能や一時的な倉庫という側面も持たせたいと思っている。一応、格好だけは店としての構えをもって、せめて家賃くらいは売り上げられればというもくろみ。まだ、店は探しているところで、決まってはないのだけど、ね。しかし、このつい何か新しいことをしたくなる性格ってのは、困るね。お金の溜まることがない。けど、ま、所詮、お金はフロー、天下の回りものだと思ってるし、人生も動き続けてるほうが生きてる実感があっていいと思ってるワケで。しんどいことは、ファイトの源くらいに考えてりゃいいという楽観主義者なので、ね。なんとかなるでしょ。
2008年11月14日
-
街との接点づくりから。
組合の仕事で、神田の会館に行く。既に来週の「東京古典会大市」の準備でワサワサしている。引き荷を置いている2Fでも建て込みが始まっている。残っている荷物は、落札者に今日中に引き取ってもらわなければならない。管理部と事業部の理事が総出で、残置状況をチェックしている。これから、電話かけまくり作戦が展開されるのだろう。というワケで、通常市は今日までで、一週休み。洋書会をチラッと覗く。本来、洋書は自分には関係ない。けど、洋書会にもときどき和書が出てくる。洋書会に出てきた和書は狙いだ。かなり安くゲットできることも、稀ではない。来会者が限定されているので、競合することなく落ちたりすることがあるから。今日は、けっこう和書が出てた。全体の荷が少ないので、「けっこう」なんて言ったってせいぜい十数口なんだけど。どうしても欲しいという品物はなかったけど、安ければいいやと、気になる品に、ほぼ最低価格レベルの金額を書き入れて、入札封筒に突っ込んでいった。かなりテキトー。いくら、洋書会が安いと言っても、さすがにちょっとムリかなという数字だったので、落ちるとは思ってなかったが、1点だけ落ちてた。小泉八雲関連の口、一束。落ちてみれば、この口は、束の冊数が少なかったので、札を入れるかどうか迷った口だった。あえて入れたけど、これに関しては、必ずしも安かったとも言えなさそう。ま、落ちるべくし落ちた、ということか。なんとかなるでしょう。「ちいさな古本博覧会」を、どうすればもっと盛りあげられるか、そのことが念頭を離れない。古本商売をしているより、そっちのほうに力が入ってる感じ。第3回の開催日時も、既に決定しているからには、準備活動も、もう始まっていると捉えていい。大きな課題のひとつは、「いかに来場者の数を増やせるか」、まずはそれに尽きる。そのためには、ふたつのことが重要。「博覧会」に行きたくなるような、魅力的な内容になってること。そして、そのことが充分伝えられるよう、告知PRを徹底すること。だろう。内容に関しては、どんなに新企画を入れてみても、単なる「古本即売会」のイメージで留まっていては、ちょっとつらそう。というコンセプトを設定しているのだから、もっとお祭り感覚で捉えられるようなイメージに転換していくべきだと思っている。本に関する面白い話題に溢れている、楽しい場。まだ、大括りなイメージだけど、というような。それと、会場を「西部古書会館」にしているのも、大きなネックなのかも。会場費が安い、会場にお客さんがついている、ということから、リスクが少ないということを優先して決めた。しかし、靴を脱いで上がらなければならない。古ぼけた建物、一見倉庫のようでパッとしない。なにより、古書マニア以外、ほとんどの人に知られていない。棚が固定なので、フレキシブルな会場構成ができない。などなど、使ってみたら、使いづらさのほうが目立ってきた。それは当初から想定済のことではあったが…。しばらく会館でやって会の力をつけてから、外に飛び出していこう。というのが、戦略だった。そういう戦略のもと、古書会館をメイン会場にしながらも、としては、高円寺という街を取り込んで(長期的には、中央線沿線も)、より広がりのある催事を目指したいという意向があった。2回目は、それに少しチャレンジしてみたのだが、正直、それが中途半端で、まったく準備不足を露呈しただけに終わった。大反省点。しかし、とば口が開いたとまでは言えないまでも、とにかく、とっかかりはつけられたと思う。次回も、一応、西部古書会館を会場として実施することになっている。「街に広げる」という課題は、次回に持ち越しだ。とりあえずは、街と、ひいては、街のなかにあるいろいろなスポットとの接点づくりから地道に始めることから、かな。そう思ってるところ。
2008年11月12日
-
『ちいさな古本博覧会』-一段、階段をあがるために。
催事の連続週間が終わり、組合の仕事での金沢出張も終え、やっと人心地がついたところ。とは言っても、バダバタと目先の仕事に追われてばかりいたので、その間、ペンディング、先送りしていた仕事が山となっている。まったく永遠の蟻地獄状態だよ。因果な商売だ。今年春(5月)に立ち上げた『ちいさな古本博覧会』という催事、この11月の1-3日にかけ、第2回目を敢行した。第1回目は、ノリだけで、「せーの」でやって、いろいろ問題はあったけど、ある手ごたえ、可能性をしっかり感じ取ることができた。特に、一番うれしかったのは、普段の古書催事には、ほとんど足を運ばないような、古書マニアではないフツーの人たち、若い男女が多く立ち寄ってくれたこと。それが大きな収穫だった。で、1回目を踏まえての2回目の今回。当然、1段階ステップ・アップしてしかるべきなのに、結果的には、同じ地点でウロウロしただけに終始した観。前回の問題も、ろくにクリアできていない。それは、要するに、運営サイドの怠慢。痛く、痛く、反省。しかし、その反省から見えてきたことがたくさんあった。『ちいさな古本博覧会』というのは、やっぱり、あまたある古書催事とは、本質的に違う催事なのだ、ということ、というか、違う催事として育てていかなければならない、ということを痛切に感じた。フツーのお客さんは、古書マニアのように、まとめて本を買ってくれない。欲しい本がなければ、そのまま立ち去ってしまう。そういう人たちだ。商売を成り立たせようと思うと、一筋縄ではつきあえない。しかし、彼らだって、本に興味があるからこそ、会場に足を運んでくれたワケで。実際、知らない本を面白がって手にとって、連れの人と会話を弾ませている姿などをみると、スレからした古書マニアより、彼らに「ホラ、こんな本どう?」みたいな感じで、本を届けていきたいような気分が盛り上がる。古書マニア相手の市場というのは、既にほぼ顕在化された市場。そして、クローズされた市場。さらに、徐々に減少化していっている市場(特に、催事において)。彼らは、商売にはおいしい人たちだけど、彼らだけを相手にしていては、いつか未来は行き詰まってしまいそう。そんな危機感が、ボクにはある。だから、古書マニアではない、フツーの人たちへの可能性に賭けてみたい。そう思う。けど、これはたいへんなコト。それもきっと事実。今の倍、いや数倍のひとたちが来てくれなければ、ホントの商売にはならない。そのためには、『ちいさな古本博覧会』というのが、単なる古書即売会という枠のなかに納まっていてはダメなような気がする。もっと広がりのある、あるムーブメントとしての理解が必要になっていくように思う。本を買いにいくため、としてだけでなく、『博覧会』に行くこと自体が楽しいというようなモチベーションが生れるような…。ちょっと壮大なイメージすぎる??かもしれないけど、目標は大きすぎるくらいが、ファイトが湧いてくる。頂上は高ければ高いほど、チャレンジのしがいがある。が、当然、一気にひと飛びで到達できるワケはない。即、こうすれば解決、なんて特効薬のような策も見当らない。不断に続けていって、少しずつ成果を積み上げていくことが大切なんだろう。1段ずつステップ・アップしながら、ね。いろいろやるべきことはある。企画もある。永遠の蟻地獄状態のなか、さらにやるべきことを増やすなんて、まさに地獄の底に進んで落ち込むような行為、かも。けど、逆を言えばそれをやり遂げられれば、永遠の蟻地獄からの脱出も可能に思えるのだが…。とにかく、一段、階段をあがるために。『ちいさな古本博覧会』は、来年、4月11日(土)・12日(日)に、第3回目を開催します。
2008年11月11日
-
こんな一日。
『大均一祭』の荷物の運び込みを始める。この企画、通常の催事につきものの値札をつけない、というのがミソのひとつ。値札貼りの作業というのは、実に厄介で手間のかかる作業なのだ。それをつけない、とすることで、出品量の確保がきわめて容易になる。だからこそ、可能な企画、なんだけど…。出品量が多くなるということは、それだけ搬入作業の負担が増える、ということなのだ。とにかく荷物を積んで運んで下ろして、積んで運んで下ろして、その繰り返し。完全に肉体労働者。前回は、ボクの1tワゴンで、東村山と高円寺の間を6往復した。今回は、一度に積む荷物の量を増やして、4往復ぐらいで片付けたい。ま、どっちにしろ、しんどさは同じ、なんだけどね。資料会を覗く。均一祭に補充できそうなネタがあったら、安く落ちないものか、と思い、雑本の山にせっせと格安の札を入れていった。しかし、そう「あわよくば」の、うまい話はない。さすがに、値段が安すぎた。けど、落ち値をみたら、五十歩百歩の金額、もう一ふんばりすれば取れる値段。その金額でも、まったく困らない程度の値段。なんだけど、「均一祭」の基本は、手持ち本の処分が目的。なので、ワザワザ仕入れるというのは、ある意味本末転倒。掘り出し感を演出できるというほどのネタでもないし、落ちなきゃ落ちないでいい、のだ。昼飯を食べながら、次回『ちいさな古本博覧会』(11/1-3予定)の企画の打合せ。新企画をいろいろ考える。前回より、一段階進化した催事をめざしたい。けど、前回同様、まだ時間はある、なんて思ってる間に、準備期間がわずか2ヶ月となってしまった。けっこうヤバい。前回の反省がぜんぜん生きてない。とはいえ、いろいろ面白い企画アイデアが出た。とにかく、楽しめる古本催事、それを実現させたい。頑張りましょう。市のあと、組合総会に出る。支部の総会には出てたけど、全体の総会は、組合に入ってはじめて。面白かった。組合には、いろんな古本屋がいて、それぞれいろんな考え方でやってるんだな、ということを改めて感じさせられた。し、なにより、組合というものがどういうふうに動いているのか、が少し垣間見えて、なるほど、という感じ。古書業界が不振で、厳しい環境下にさらされている中、組合の役割ってなんなんだ?ってことを思った。そのあとの懇親会は早々に切り上げて帰ったけど、もう何もする気になれず、ルーティン・ワークをさぼってしまった。正直、疲れました。
2008年08月27日
-
大均一祭。
今度の週末、土・日、『大収穫祭』という催事をやる。古本放出バーゲンと銘うってる。土曜日はオール200円均一、日曜日はオール100円均一という安さが売り。今回は、2回目。前回やったのは6月。単価が単価なので、売上げ全体はたいしたことはない。けど、大半の品はもう原価回収済みの、売れ残り系の品物。そんな品物が、最後のご奉公と、稼ぎをつくってくれる。それはそれでありがたいこと。お客さんも、ここぞとばかり大量に買っていく人も多く、それなりに受けたという実感はあった。で、2回目決行となった。が、業界の一部で顰蹙を買ってるというウワサもあるようだ。たぶん、そんな価格破壊につながるような催事をやられては、他の催事が売れなくなる。というようなのが、言い分なんだろうと想像する。けど、ボクとしては、コレこそが、今の古本業界の現実の反映だと思ってる。まともな値段では、まったく売れもしない品物を、ただ抱えているワケにはいかない。それでは商売にならない。じゃ、売れない品物は、どうするのか。廃棄するしかない。どうせ廃棄するなら、その前に格安で捌いてしまおう、というのが企画意図。実のとこ、今の古本市場(しじょう)、そんなどうにもならないような品物であふれかえっている。それが現実。本が多すぎて、本余り状態。それも、何度も言うようだが、売れない本が、である。実際、ボクが昨日市場(いちば)に出した本も大半が、値もつかず止まってしまった。まだまだ本としての寿命は十分にありそうな本でも、そこそこレベルの半端な本を欲しがる業者はいない、ということの証明。結局、みんな、そんな本をなんとか処理したいと思ってるのだから、わざわざ買おうなんて奇特な業者はいない、ということだ。アマゾンMPでも、1円とか、0円とか、ダダで持ってけと言わんばかりの品物がゴロゴロしてる世の中。それをおかしいと言っていては、現実から取り残されるだろう。そっちのほうが現実なのだという、理解から先を考える必要があると思う。売れない本をどう売るのか?結局、バーゲンの手法が一番じゃないのか。それが、ボクの考えなのだ。今、百貨店なんかでも、ちょうど「夏物一掃バーゲン」の季節だ。売れ残ったモノは、バーゲンで処分する。コレって、昔からあるまっとうな商法だと思う。だいたい、通常の催事でも、「均一コーナー」を目玉にしてるものが多い。その「均一コーナー」を会場全体でやるってだけのことだから、そこにもロジックの矛盾はない。「大均一祭」は、あってしかるべき催事だと思うんだけど、ね。けど、処分バーゲンはあくまで処分バーゲン。カンフル剤のようなもの。処分バーゲンだけで市場(しじょう)は成立しない。それじゃ健全な市場(しじょう)とは言えない。ちゃんとしたものがちゃんと売れる市場(しじょう)があってこそのバーゲン、なのだ。だから、そういう催事もまたあってしかるべき。という考えで、ボク自身、『ちいさな古本博覧会』という企画も同時に推進している。この企画の最大の狙いのひとつは、「新規顧客の開拓」。今の催事の客に、催事用のネタを提供してるだけでは、催事自体がジリ貧になる。しかも、同じような催事が毎週のように開かれていては、業者も客も疲弊していく。そういう危機感からスタートした企画でもある。店が一番売りたい品物を買ってくれるお客さんは、努力して探し出す必要がある。市場(しじょう)は、刈り取るだけの場ではなく、育成していくことも重要。そんな視点から、ただ売ることだけを目的としないPR重視型の催事として立案した。この『古本博覧会』と『大均一祭』は、いわば両極でありながら、二つで一つという相対企画でもある、のだ。『大均一祭』は、だから、ただ闇雲なムチャ売り、安売りの企画ではない。そこのところは、わかってほしいよね。もし、快く思ってない同業者の人がいるとしたら、ね。
2008年08月26日
-
本はあっても、ない。
市場に出す荷物を作ってるけど、本が多すぎて、いいかげんウンザリする。催事3回分くらいの荷物が溜まってる。冊数にすると3000冊(150本)くらいか。古本屋の在庫としてはたいしたことないけど、それをジャンル別、値段のつきそうなモノ、つきそうにないモノなどと、仕分けするとなると簡単な量じゃない。やってもやっても減らない感じ。それも、催事返りの荷物だから、正直、たいしたモノは入ってない。どれもこれも、いわゆる「雑本」というヤツばかり。5本、10本単位で荷物作って、やっと数千円の値がつけばいいか、ってレベル。それもあって、ウンザリ度はさらに倍化する。その程度のモノだから、もう仕分けもせずにメクラで括って、イッセのセで右左方式に出してもいいのだけど…。ついつい、仕分けしてみたくなる。セコセコな貧乏性の性分が、根っから身についてるようだ。どうしたもんかね。そんなゴミ本なら、まだまだいくらでもあるのに、さて、いざ目録用の品を探そうとすると、ない。どこにもない。さーて、締切延ばしもそろそろ限界。今日あたりに原稿を送らなきゃならないんだけど…。困った。最悪、ネットに出してるモノを流用するしかない、か?なんだか、その場しのぎだけで、食いつないでるって感じ。疲れる、ね。もっと、まっとうな品物でまっとうに商売できるようにしなきゃ、とは切実に思ってるけど…。ま、しばらくはムリかな?って、そんな日は永遠に来ないような気も…。今のやり方がボクには合ってるのかもしれないし…。なんて、考えてるより、とにかく今は今やるべきことをやるだけ、ってことさ。さー、荷造り再開、だ。
2008年08月24日
-
時間がない。
ブログを続けて書いてこうという意思はあるのに、こうしていざ開くと、3ヶ月ものブランク。あれ、いつの間にそんなに時間が経ったの? って感じの日々。とにかく、時間がない。時間に追われている。メチャ忙しいというワケではないけど、常にやるべきこと、やらなきゃなんなんないことが、そこに控えて待っている。目の前のそれらを消化していくだけで、一日は終わる。まったく。古本屋って商売は、好きでなきゃやってられない、よな。8/19(水)に西武百貨店での催事が終り、8/30,31の「第2回大均一祭」まで、少しはゆっくりできるかな、なんて思ってたけど、とんでもない。今日は、これから月曜の中央市に出品する荷物を作らなきゃならない。待ったなしの仕入れの支払いが溜まっているので、きっちり金にしなきゃなんないから、しんどい。ひとまず、午後に一便として運び込んでおいて、追加分を、月朝に二便として持っていくということになりそう。日曜も、出品荷物づくりでつぶれそう。午後のその後は、廃業した同業者の店の整理の手伝い。荷物を代理出品するため。商売を止めたその古本屋さんの一言吐いたフレーズ、「こんな状況じゃ………」。まさに真の言葉。零細な古本屋の多くは、同じ気持ちを抱えながらやてるのだろう、な、と思う。それだけ、古本業を取り巻く状況は厳しい。他人事では、ない。ホントに。今週の火曜に締切があった目録の原稿も、まだほとんど手つかずで残っている。さすがにそろそろ提出しなきゃなんない。モノ選びをしてる時間がありそうにない。そこらの品物で間に合わして、お茶を濁すしかない。けど、それをやったら、注文はまずない。経費分が出るか出ないかという悲惨な状況は、ほぼ決定的。そんな目録、やる意味ないよ、なんだけど、催事と目録はセットだから…、つらいね。本来、目録は催事本番前に、利益を確実に稼いでおくためにあったハズのもの。それが、コスト負担の要因でしかなくなってしまってる。困ったもんだ。目録のスタイル、変えてみようか、な。絶対の勝負ネタだけを1ページ1点のみ。1点1殺!!って、死ぬのは、こっちだね、間違いなく。そんなことより、問題は、目録を書く時間をどうやって作るか、ってこと。まったく見えない。ヤバい。
2008年08月23日
-
いらない本を溜めてるワケ。
西部の振り市。先月から、月2回が月1回の開催に変わった。そのせいか、荷物が多い。客の少なさは変わらないけど…。今日は、ボクとしてはほとんど声を出さなかった。さすがに倉庫に荷物がいっぱいになってるので、まずそれを整理することから始めなきゃ、というワケで。倉庫にある荷物の大半も、振り市で買ったもの。だから、整理すると、ほとんどはツブシ本になる。新しい倉庫は、目の前が古紙の処理業者なので、ツブシ本が溜まったら持ち込むことにしている。たいした金額ではないけど、値段をつけて買ってくれる。200キロくらい持っていって、ま、昼飯が食える程度。それでも、こっちにはゴミなんだから、ありがたいことで…。ただ、今は、ホントにしょうもない本以外、少し、在庫として溜めている。6月(14、15両日)に、西部会館で『大均一祭』という即売会をすることにしたから。全品200均、100均、といったノリでの投売り市。コクテイル書房とオヨヨ書林の三人だけで実施。なので、一人当たり、約20台、本数にして240本。1本20冊と換算すれば、4800冊を分担する計算。市の大山や、振りでガンガン買えば、その程度の本を集めるのはとくに困りはしない。金額もしれたもの。ただ、催事までの置き場所は、となるとちょっと問題。企画をした段階では、10坪くらいのフリースペースがあったので、それでもまったく問題はなかったのだが、4月末に、常田書店の倉庫として、一部貸与することになったから、急に狭くなってしまった。正直、ジャマ。たいして価値もない本を、徒に持っているってのはあんまりいい気分ではない。さっさと催事を終えて、すっきりしたい気分。催事で売れ残った本は、そのまま即、ツブシに回そう。昼飯何回分になるかなあ。
2008年05月20日
-
疲れても、走れ! ブッ倒れるまで、走れ!
古書催事を開催して、終わった。そのことに費やしたエネルギーの大きさは、我ながらよくやった、と思う。正直、疲れた。この疲れが報われるものかどうか、は知らない。どうでもいい。2回目をやろうという声の大きさに後押しされて、また次に向って走るだけのことだ。疲れたから、休む、というのは今はあまり考えたくない。疲れが限界を超えたら、ブッ倒れるだけのこと。ブッ倒れるまでは、やる、のだ。何を?未来の可能性として信じられること、を。何かの突破口となりうるようなこと、を。そして…面白いと思えることなら、それでいい。最近、自分がやってることは、まったく古本屋じゃないな、と思う。あんなにこだわってた店も閉めたし、本を売るのは人任せだし、売ってる本は売りたい本ではないし…。不動産やさんや運送屋さんもどきの仕事?(儲けにならないことは仕事とは言わないって?)ばかり。周りが見たら、あきれるだけ、だろうな。3年間(非組合員時代は入れないで)、古本屋やってみて、「このままでは先がない」「5年後も今と同じ状況、同じやり方でいるのなら意味はない」、そう思った時から、とにかく何か変えていこう、新しいことにトライし続けよう、そう決意した。「将来のための今」。思ったことを思ってるだけでは、絵空事。やる、やるといい続けても、形にしなければ、ウソ。動くことから始めたい。そう切実に思った。短兵急に答えを求めず、目先の計算ばかりをせず、「信じる」ということを信じる。宗教じゃないけどさ。それができてれば、ブッ倒れても悔いはない、ってね。疲れても、走れ!ブッ倒れるまで、走れ!だよ。
2008年05月15日
-
前言撤回。
日記をHPに移行すると宣言したばかりなのに、朝令暮改のごとく、前言を撤回します。HPの日記では、出品した本に限定したコメントを掲載したほうがいいと判断し、タラタラと、とりめもない話題は、引き続き、ここでお気軽に書いていくことにする。5月に新しく始める古書催事のことには、既に少し書いておいたけど、だいたいの概要が固まってきた。催事のタイトルは『ちいさな 古本博覧会』。気持ちは壮大、でも規模はささやかに、のココロです。今、その準備でなにかと気忙しい。自分が言い出しっぺで立ち上げた催事だから、なんとか成功に結びつけるべき責任を感じている。しかし、いろいろ手探りのことが多く、これでいいのかな、と自問しながらの進行。実際の忙しさ以上に、気持ちがワサワサしてる感じでなんとなく落ち着かない日々だ。
2008年04月08日
-
さようなら。こんにちは。
ホームページを新しくした。これまで、ホームページ・ビルダーで独自に作っていたけど、作業に手間がかかり、ほとんど更新できずにいた。ほぼ、1年フリーズしたままの状態だった。1年経って、月日だけは、今のものと思えても、実際は去年の情報、なんてことになったら、笑い話にもならない。さすがに、それでは来てくれる人にも失礼(動いてないサイトだから、ほんど来る人もなかっただろうけど…)。で、新規まき直しで、おちゃのこネットに新しいHPを立ち上げることにした。おちゃのこネットは、同業者で使ってる人も多く、知ってはいたが、規格的なものでなく、個性のあるHPへのこだわりもあって、敬遠してた。が、実際、運営できなきゃ、個性もへったくれもない。技術が伴ってないのだから、基盤を用意してもらってるのに、乗っかるほうが賢い、ということなんだろう。昨日、登録し、なんだかんだトライして、やっと一応の格好がつくかなというとこまでこぎつけた。もっと、スイスイと簡単なのかと思ってたが、意外にめんどくさかった。これで更新バッチリ、かとなるとちょっと自信ない部分も…。けど、ショッピングカートがついてるのは、ありがたい。とにかく、作った以上は、作りっぱなしとならないよう、気を引き締めて続けていきたい、と切に思ってるけど、ね。で、そのHPにブログ=「店長日記」がついてるので、今後、日記はそっちに書いていこうと思う。従って、タラタラと続けてきた、この楽天のブログは、本日にて、ひとまず終了ということにします。お世話になった皆さま、ありがとうございました。おつきあいついでに、新HPの方もご贔屓いただければ、うれしい限りです。新HPのアドレスをご案内いたします。http://paradis.ocnk.net/では、楽天ブログではお別れですが、新HPにて、今後とも、よろしくお願いします。
2008年04月05日
-
四月になれば…
「四月になれば彼女は」というタイトルだったと思うけど、確か、サイモン&ガーファンクルの唄にあった。毎年、四月が近づくと、ボクの頭の中には、このフレーズがリフレインするようになる。「四月になれば…」四月ってのは、入園、入学、新入社と、期変わりの季節。なにか新しいことが始まる予感に満ちた季節。ボクの店も、4/2でちょうど3年になる。この機会に、いろんなことを一新してみたい気持ちが今ググッーと溢れてきている。今企画している催事も、3月いっぱいに全て目処をつけたい。ホームページも、ずっとほったらかしだったので、先日閉鎖、あらたなHPを立ち上げてみたい。店も、いろんなことで手が回らなくなってる状態なので、このまま続けていくことに疑問が生まれている。一旦、白紙にしてみるのもアリかと考えてる。店を閉じるというのは、店にこだわりをもってるボクとしては、ちょっと忸怩たる思いってヤツだけど、戦略的後退という考え方もあるワケで。今は、ムリに開けてくことは負担が増えるだけという事実は否めない。去年の暮に、自宅の近くに大きな倉庫を借りて、そこで作業することが多くなった。そこをベースに将来に向けてのいろんな布石を打っているところ。今は、そっちに力を入れていくことが一番大切だと考えている。この3ヶ月間で、トライアル時期は終了させて、あたらしいビジネス・システムとして構築していくことに真剣になっていく必要を感じている。一人の身で、あれもこれもはできっこない。二兎追うものは一兎も得ず。虻蜂取らず。それだけは避けなければ。四月になれば…。
2008年03月26日
-
ここから本番。
この土日に、レギュラーで参加している古書催事があり、自分らで企画中の催事の進行が滞っていた。予定が少し遅れつつある。いかん。今日から、遅れを取り戻すべく、ギアチェンジしなければ。まずなにはともあれ、専用ブログの立ち上げと、最初のチラシ制作を仕上げることが即の仕事。急ぎ、原稿を作って制作スタッフに渡した。とりあえず、催事開催告知だけを目的としたもの。具体的なイベントなどについては、まだまだこれからが固めの作業。なんだか、追っかけ追っかけのアタフタ状態。それでも、ゲスト店もほぼ半数の目処がたち、なんとか格好はつきそうな段階まできたので、少し安心。これからは、この企画に専念して、考えられる限り考え、動ける限り動いていこう。
2008年03月24日
-
声かけ運動。
5月の催事に参加する主要メンバーが集まって、大枠概要や、スケジュール、予算の確認作業した。企画段階から、いよいよ実施モードに突入した。とはいえ、まだまだクリアしなきゃなんない課題も多い。当面、ゲスト参加店を募るという作業に専念しなきゃなんない。主要メンバーだけだと、会場(西部古書会館)の棚の半分くらいしか埋まらない。残りの半分のスペースをゲストで埋めようという計画。声をかければ、協力してくれそうな店はだいたい想定していたから、なんとかなるだろう、とタカをくくってはいた。けど、実際声をかけて、NOと言われる店が続出してしまったら、計画自身がポシャる懸念はなくはないワケで…。早速、声をかけはじめたら、意外に、すんなりOKの返事をもらえてうれしい限り。とりあえず現時点のNOの店はいない。といっても、まだ声かけしたのは、5店舗だけだけど。こちらの希望としては、棚2台をやってほしいのだけど、さすがに2台だと負担のようで、1台ならという条件つきの店がほとんど。自分が相手の立場だったとしても、たぶん、同じように答えるだろう。気持ちはわかる。つきあってくれるだけ、ありがたい限り。3月いっぱいに、全ゲスト店が決まるよう、ひたすら声かけ運動を続けねば。
2008年03月16日
-
面白がり屋。
日記を再開したと思っても、しばらく続くとまた中断。毎度繰り返しのパターンでしょうもないけど、忙しくなると、どうしても日記まで手が回らない。精神状態が、日記の気分でなくなるのだ。忙しいのは、今やほぼ慢性状態。常に、なにかに追われてる気分がつきまとって離れない。なんとかしたいけど、しばらくはどうにもならなそう。だいたい、忙しくても、そこに更に余計な仕事を付け足して、忙しさに一層の拍車をけるようなことばかりしてるワケで。たぶん、そんな性分なんだろう。というような状況で、今度、新しい古書催事を立ち上げようという企画をしている。会場は既に押さえた。開催時期も決まっている。5月10日(土)、11日(日)の2日間、西部古書会館にて。時間も場所も決まったものの、企画の詰めや、参加店舗の確定がまだできていない。まったく新しい催事なので、事前のPRが重要と思い、開催一月前には、告知を開始したいなどと思いつつ、その作業もなかなか進展してない。開催まで、2ヶ月、正直、準備期間としては、待ったなし状況である。ヤバいぞ。西部の古書会館での開催だけど、内容的には、今までの催事とはまったく異なった発想のものとして実現したい、そんな野望のもとに企画を立ち上げたのだが、いったい、どこまで思い通りに実現できるのか………?構想だけでかくて、結局、設計が不完全なまま空中分解なんてことにならなきゃいいけど…。ね。やろうとしてるのは、それだけじゃない。3月の半ばからは、古本酒場コクテイルで、昔懐かしい映画のプレスシート展なんかも予定している。以前、市場で買って、目録用になんて思ってたプレスが約100枚ほどある。目録は、去年の春に出そうと思ってたのが、1年経っても、まだ目処がたたない状態。プレスも眠らせたままにしておくのはもったいないから、店のPRついでに、日の目にさらしてあげようという狙い。コクテイルでは、5月にも別の企画も準備しているところで、いったい自分は古本屋なんだが、どうだか、最近はよくわからないような活動ばかりしている。けど、毎日、ただ黙々とネット作業だけするのはつまらないワケで。要は、自分は、面白がり屋なんだろうな、なんて思う次第。儲かることより、面白いことをやりたい、って、ね。面白いことやって儲けられたら、当然、それが一番、なんだけど、さ。なかなか、ね。自転車操業でもなんでも、走れているうちはいいのだ、と言い聞かせながら、今日も、明日も、ひたすらペダルをこぎ続ける日々、だね。
2008年03月07日
-
「目録」がダメなら「場」で勝負…?
「中央線古書展」の目録原稿の締切が昨日だった、というのに、間に合わなかった。「間に合わなかった」というのは正しくないかも。不可抗力的なニュアンスは妥当じゃない。ハナから締切を守る意思がなかった、のだから。つまり、確信犯。なぜって、目録用のネタがない、から。単純にそれだけのこと。できれば、もうパスしたい、のだが、目録代をタダ取られるのはイタすぎる。単価1000円レベル品物なら、別に困りもしないが、そんなの乗っけたって、たいして注文は期待できない。わずかな注文が来たところで、「焼け石に水」「砂漠に涙」ってヤツ。労力だけがバカバカしい。そんなら、いっそ、万単位の金額をつけられそうな品物を1ページ1点だけ載っけて、一か八かみたいな賭けに出るのもありかも、なんて真剣に考えてる。万単位の品物なんて、どうせ指折り数える程度しか持ち合わせないんだから、さ。情けない。が、締切は、待ってくれない。今日、明日あたりで目処をつけねば。結局、ページを埋めるだけの目録でゴマかすしかないんだろうな。毎度のことだけど、「場」で頑張るしかない、ってことだね。「中央線展」は、昨日が締切だったワケだが、「古書愛好会展」は、昨日が目録の配布日。「愛好会」のネタもお寒い限りの内容なのは、同様。初日だから、FAXでの注文がいくつか入ってきたけど、まさしく、そこそこ数は来ても、金額はたかが知れたもの。このペースだと、経費をクリアするのがやっとってとこか。想定済みのこととはいえ、悲しい、ね。やっぱり、「場」で勝負するしかない、ってことだ。しかし、「場」の荷物も「中央線展」の目録を仕上げない限り手がつけられないワケで…。あぁー、どんなるんだかなー?
2008年02月20日
-
振り市は面白い。
振り市から帰ってきた。最近のボクのメインの仕入れ先は振り市なのだ。振り市の荷物は、正直、半分以上はクズネタ。振り市は荷物の捨て場なんて言われ方をしてるくらい。なので、買いに来る人もほとんどいない。今日も、経営員を除けば、6、7人ほど。だから、なかなかセリにならない。たいがいは、最初に声をかけた人に落ちる。だいたい声をかける人自体、ほとんどいない。ボクは、そんな品物でも、なんか気になる点が少しでもあれば、とりあえず声をかけることにしている。こういう場に書くには、はばかられるほどの安い額だけど…。それでも、大半は落ちてしまう。振り市の後は、いつも大量の荷物を持ち帰ることになる。そして、その多くは、値段をつけることもなく、廃棄本に回してしまうような品物なのだ。じゃ、一体なんでそんな品物を買うんだ? と問われれば、実は、一見ゴミのように見えるそんな品物のなかに、けっこういい値段で売れるモノがこっそり隠れ潜んでることが間々、というか、しばしばあったりするから。以前も、ゴミとの格闘という話題の日記を書いたが、そのゴミとの格闘を厭いさえしなければ、格安で、おいしい品物をゲットすることも、まれではない。そこが、振り市の面白さ。いわば、ギャンブル的な醍醐味。入札市は、どっか予定調和的な部分が強いから、こういう気分はあまりない。とはいえ、すべてカス、ハズレってことも、当然ある。ギャンブル性の反面として、それは覚悟しておかなくてはならない。というところで、本日最大の収穫!!金子國義のオリジナル・リトグラフが2点。ホリプロ30周年記念として特別に制作されたもの。本来、4種揃いのものの一部だけど、それでも本物。外装袋は、かなり汚れていたが、中のリトグラフはキレイなまま。出品者は、薄汚れた袋だから、おそらく中も見ずに出してしまったのだろう。買う側も、ボクを含め、誰も注目することなく、他のしょうもない品物ともにメチャ安な値段で落ちそうになったところで、買い手の一人が、たまたま中を開けてみたら、金子のリトグラフだったことが、判明。そこから、いきなりセリがオーバーヒート。結局そこそこの値段にはなってしまったが、それでも神田の市場に出てたら、もっとつくことは間違いなく、多分、1点分程度の値段で落とせたから、収穫は収穫だ。けど、最初に声をかけた値段で、そのままボクに落ちてたら…、なんて思うと、ちょい悔しい。ま、いつもいつも棚ボタはないということではあるが、逆を言えば、そんな棚ボタだってありうるよ、ということ、なんですね。
2008年02月19日
-
お客さんは来たが…。
昨日は、ウチの店としては、珍しいほどに客がやってきた。チェーン来店のような状況。そんなこと、開店来、記憶にない。日曜日だからってだけのことじゃなかろうに、いったいどうしたというワケだ???しかし、しかし!!まともに本を買っていく客はほとんどいない。なんてこった!ウチの店は、店頭商品は「3冊100円」。市場に出しても、どうせ値段のつかないような品だし、廃棄する前に一旦並べておこう、というノリで出してるモノ。で、買ってくれる本は、みんなソレ。捨てたいような品物がお金になってくれるのは、ありがたいし、品物が捌けるのはうれしい。が、しかし、それだけでは、店の売上げにはほとんど貢献しないワケで…。悲しい。30冊売れても、1000円だから、ね。単価1000円のものが30冊なら、3万円、なのに…。なんて、取らぬ狸計算してもはじまらない。日頃、閑古鳥の鳴く店にお客さんが来てくれただけでも「よし」としておこう。
2008年02月18日
-
お宝が見つかったものの…。
昨日の西部良書市で仲間の古本屋から、ブログがスゴイことになってるよと言われ、超久々に開けてみたら、確かに、H系の書込みがズラズラズラ…、と。んー………。空家も放置しっぱなしだと、ゴミ捨て場となり、果ては、廃墟となっていくワケで。ブログを廃墟化してはならぬ、と重い腕を上げてキーを叩きはじめた次第。それにしても、コメントの削除も一苦労だったぞ。今日は朝から、宅買い。ダンボール箱で20箱以上あるとのこと。ちょうどあさって、目録の締切があり、そのネタがなく困ってたところ。その買い物だけで、最低1ページ(50冊)くらい作れたらラッキー、てな期待を込めて参上。が、ダンボール箱は20箱以上どころか、20箱にも満たない18箱。それもミカン箱だよ。ミカン箱は小さいし、本のサイズとピッタリしないから、中に詰められる本の数もたかがしれてる。宅配便のダンボール箱なんかに比べると、ほぼ半分くらいの量。少し、ガッカリ。で、中開け始めたら、いきなり芥川龍之介全集、それも旧版。しょーもない、マンガや文庫。これじゃいくらあっても、値段つかねえぞ。目録のネタにもなんにもなりゃしないぞ。と箱を放り投げてしまいたくなる衝動を抑えつつ、さらに開けてると、急に本の色が変わってきた。真っ黒な戦前の本たちが顔をだしてきた。ホコリまみれの、それらの本のなかから、オー、出てきたぞ。山六郎・山名文夫共著の『女性のカット』はどうだ。スゴイじゃないか。大正末年から、昭和にかけ、プラトン社から発行されていた雑誌「女性」に発表された挿画カットを集めたもの。完本は、函つきだけど、これには函はない。けど、本の状態はけっこういい。「日本の古本屋」みたら、魚山堂さんが、完本で9万円の値段つけてるじゃないか!やった!!他の全部がダメでも、これ1冊見つかっただけで、今日の買取りは十分に満足モノ。けど、すぐ目録に出してしまうのも、もったいない。しばらくは、手元であたためておきたい。結局、目録ネタの決定的不足は解消されない、ぞ。困ったもんだ。
2008年02月17日
-
疲れただけの倉庫整理
今週一週間、平日は店を休業にして、倉庫整理をした。あまりに要らない本が溜りすぎていたので、一度、一気に整理しないと、永遠に手つかずのまま、のような気がして。しかし、それにしても、どうしてこんなにしょうもない本ばかり溜め込んでたんだろう、ボクは。我ながら、あきれてしまう。捨てるものは捨てて、なんとか市場に出せそうなモノはせっと荷造り。けっこうな量の荷物ができたけど、こんだけ市場に持っていっても、たいした金額にはならないだろうなぁ、なんて思うと、疲れただけバカみたい。これからは、無駄な在庫は極力もたない。徹底スリム化作戦を実行しようと思う。「ストックからフローへ」それが合言葉、だ!で、昨日、市場当日。約4分の1がボー(値つかず)。そんなものか、な。市場の現実はキビシイ、ぞ。
2007年10月21日
-
買うのは簡単だけど、後がタイヘン
埼玉の大市に行ってきた。朝、出発する間際、一緒に行く約束をしていた店の人から、熱が出たのでキャンセルするという連絡が。ボク自身、同伴者がいるということで、「ま、行ってもいいか」という程度の動機だった。なので、急に気が萎えて、行くのを止めようか、と思った。が、とりあえず、態勢がもう行く構えになってたので、そのノリのまま行くことに。結果、正解。欲しい傾向の品物が、かなり集中して出ていた。同じ出品者だから、まとまった大口の買いとかがあったのだろう、と読んだ。過去の経験から、こういう出方をするときは買っといたほうがいい、そう学習している。かなり頑張って札を入れた。最近では、久々に強く入れた。さっき市の担当者から、連絡があり、おかげさんで、相当量落ちたらしい。少し頑張りすぎたか?神田の感覚では妥当な金額のつもりで入れたのに、どうも、かなり余裕で取れてた様子。ふーん。ま、なんであれ、欲しい荷物が取れるのはいいことだ。ただ、取れすぎは後がタイヘン。支払いのために、今度は要らない荷物を市場に出さねば…。買うのは簡単だけど、うまく売るのは簡単じゃないんだよなぁ。なんか苦手なんだよな、ボクは、売るのが、ね。
2007年10月02日
-
お楽しみはこれから
「売れない」というフレーズを禁句にしなきゃ、と思う。そのくらい、なにげに口をついて出てくる言葉になっている。困ったもんだ。市場に行けば、あいかわらず大量に品物が出ている。しかし、欲しいモノがない。というか、欲しいものには高くて手がでない、ってだけのこと。安くて旨みのありそうなものはないか、と、物色するのだが、そんな都合のいい品物はない、ということ。「一山いくら」の品物と格闘するのに、いいかげん疲れてきた。そろそろ売り方を変えなきゃなんないな、と考えてる最中だけど、これで大丈夫なんていえるような決定的な打開策もありそうにない。今日よりは、明日がまだいいはず、と信じて進むしかなさそう。「働けど…」と、啄木の歌が聞こえてくるのは、空耳だということにして…。日記を再開して、いきなり暗い話になってしまった。それが現実、なんだとしても、永遠に続くのではやりきれない。なんで古本屋になったのか、意味がない。売れなくても、なんとか食っていけるなら、あとは、どう楽しく面白く、商売できるか、とそう考えたほうがいいような気がする。「売るための方法」はなかなか見えないけど、「商売を楽しむ方法」なら、いろいろありそうだ。「売れない」「売れない」とボヤいてるより、「商売を楽しむ方法」をみつける努力をしていきたいね、これからは。と、そんな気持ちで、ブログ日記、またボチボチとやっていくことにしよう。
2007年10月01日
-
ゴミあさりのクセ
昨日、ずいぶん久しぶりに中央市会に行ってみた。何ヶ月ぶりだろう。ひょっとしたら、半年近く行ってなかったかも。中央市会の値段が高騰していて、なかなか荷物がとれない、という話はしばしば耳にしていた。それは、ボク自身、市に行ってたころ、既に感じていた。市に行かなくなったこと自体、あまりに高い、という印象が強くなってきてたせいもあるかも。で、支部の市だけで済ますようになった。商売のことだけ考えれば、それでまったく困らない。値段はメチャ安いし、即売展向きの品物にも事欠かない。アマゾン向きの新刊ネタもちゃんと手に入る。それも、神田あたりよりかなりお安く。困るのは、目録向きのネタとか、自分が専門にやろうとしている映画関係の本などが都合よく出てこないこと。久々の中央市会、そんな品物が出ていることを期待していた。が、期待に反して、ボクの食指が動くような品物はなかった。しょうがないから、取れて良し取れなくて良しの札を適当に入れておいた。そしたら、1口を除いて全滅。なるほど、高いや。自分のなかでは、そんな強い札ではないにしても、充分勝負できる金額を入れたつもりだったのに。買えない市では魅力もないけど、やっぱ、今一番荷物が集まるのは中央市会であるのは確かなのだから、これを機にまたマメに足を運ぶことにするかな。月1くらいで勝負ネタと出会えればいいやくらいの気持ちでね…。ところで、取れた1口だけど、これ、まったくしょうもないゴミ山。13本あって、使えそうなのは2、3本ほど。そのなかに、いくつか気を引くのがあって札を入れた。こういうネタなら、ほかに狙う人がいないから取れるってことか。ところが、持って帰って中をチェックしたら、拾えた本の半分くらいに線引。それも、ちゃんと評価して値踏みした本が全てそう。いくらゴミ山でも、これはヒドい。ゴミ本のなかに、いい本を混ぜて抱き合わせで買わせるのは、市場での常套手段。とはいえ、ゴミ本はともかく、見せ筋の本もゴミでは話にならない。即、事故処理。13本全部突っ返してやろうかとも思ったが、線が鉛筆なので、なんとか消せば生かせそうなものも混じってたから、とりあえず値引き交渉からはじめることにする。こういう本を堂々と出す業者の神経も信じ難いが、それって、結局、そんな本でも買うボクみたいな業者がいるから、ということでもあるのかな。ゴミのなかからお宝が見つかることも珍しくないから、つい、そういうのを狙ってしまうクセがついてるようだ、ボクは。あーあ、中央市会にゴミあさりに行ったつもりはないんだけど、な…。
2007年05月29日
-
脚のしびれと記憶の闇
脚がしびれて、力がはいらない感覚。たぶん、昨日、呑みすぎて脚が二日酔いなんだろう。胃の調子は、それほどでもないのに…、ヘンな感じ。そのしびれる脚で、神田の古書会館に行く。市場がメインの目的じゃない。事務局にちょっとした用があった。しかし、行ったついでだ。中央市会を覗く。中央市会は、実に久々。あいかわらず、品物があふれている。欲しいものがありすぎて、困るくらい。近く締切りがある目録のネタがないので、何かないかと物色する。面白そうなのはいくつか見つけたが、どれも小さな束ばかり。値段もお安くないのは明白。数冊くらいなら手に入れることができても、それではページの飾りにしかならない。なんて、だいたい目録ネタを一気に100冊集めようなんて、元からムチャというものだろう。常日頃から、マメに集めておくことが大切なんだよ。と、自分を戒めつつ、それでも一応は札をいれておこうと思ったとたん、筆記用具がないことに気がついた。使い慣れた「勝負ペン」はいつも小さなバッグのポケットに入れてある。そのバッグは、いつもぶらさげてる手提げの中に入ってる。ハズだったのに、手提げの中に、肝心のバッグがない。ペンなんかはどうでもいい。そのバッグには、キャッシュカードやケイタイなども貴重品も入れてある。それが失くなったとしたら……。ヤバい。エッ、なんで、、、、どこでなくしたのだ?一瞬、冷や汗。もう、入札どころの気分ではなくなった。昨日は、呑み過ごして終電を逃してしまった。タクシーで帰ってもいいのだけど、タクシー代をケチりたくなって、自家用タクシーを呼び出す。それが到着するまで、近くの店に入った。小半時いたか。で、ケイタイに「着いた」という連絡があり、店を出た。この時点までは、確かにケイタイはあった。バッグは、どうだったか???したたかに呑んだ酔っ払いに、昨日の記憶を正しくたどれ、なんてことは、やったことがない綱渡りをしろというようなもの。できっこない。入札を見切って、店に戻り、大捜査作戦。ケイタイを鳴らしてみたが、誰も出ない。聞く人もいないだろうから、留守電に伝言しても意味はない。一番の可能性は、最後に寄った店だけど、どうせ昼には連絡つかないだろう。当てはないが、一応、家に電話を入れてみる。返事は「ない」という答え。ンー。もし、どこからも出なかったら…。金融関係に電話したり、交番に届けたり、とか煩わしい作業をしなければならないのか、と思うと気が重くてやりきれない。忘れ物大王のボクは、過去に何度そういう経験を繰り返したことか。あまりに痛い作業の繰り返しに懲りて、ここしばらくそういうことがなく、とても平穏に過ごせてたのに………。そこに、電話のコール。家から。クルマの中にころがっていた、という報告。あっけなく見つかる。いろんな意味で肩の力が抜けた。脚のしびれが、またぶり返してきた。
2007年05月07日
-
結果的に棚卸し
1週間ほど、緊急の用で田舎に帰っていた。田舎から戻ってみたら、棚の本の並びがメチャクチャになっていた。留守番を頼んでいたカミさんが、注文本が捜しにくいと勝手に変えたのだ。というか、変えようとして手をつけたものの、途中で放棄してしまった残状というのが正しいか。ウチの店の棚は、おおまかに、定番本とそれ以外の本というふうに分れている。今は、定番本は、映画・演劇・美術にほぼ限定している。それ以外の本は、すべてゴッタ扱い。ネット出品した本を、出品順に端から並べている。ま、商売的に言ってみれば、「最新出品コーナー」という感覚。なので、ジャンル分けなどはされてない。それどころか、同じ著者の本でも、あっちこっちバラバラになっている。一見、まったく整理されていない棚のよう。が、それでも、ちゃんと棚管理リストがあり、それと照合すれば、どこに何があるかはすぐわかる仕組みにはしている。しかし、カミさんは、その棚管理リストをチェックすることすら面倒がって、タイトルを「アイウエオ」順に並べようと思い立ったワケだ。けど、棚の並べ替えってヤツが、意外に手がかかることまでは思い至らなかったとみえる。「カ」行が終わるあたりまでやって、力尽きたようだ。それも、とりあえず、グルーピングしたという段階でストップ。早い話、バラバラでもちゃんと整理がついてた以前の状態から、秩序もなにもない宇宙創世記、カオスの様相を呈すありさまに変わってしまっただけのこと。これじゃ商売にならない。しょうがないから、半日かけて、元の状態に戻す。まったく………、である。ただ、そのおかげでというか、期せずして、結果的に棚卸し作業ができた。ネットに出してると、売り切れてるのに、データ削除がされないままの本とかが、つい残ってたりするものだから、ちゃんと在庫チェックができたことは、いいことだ。いわゆる「ケガの巧妙」ということにしておこう。
2007年05月04日
-
尻切れでゴメンナサイ。
先週は、市の品物づくりに追われて、目いっぱいだった。3日間専念して、約30口70本の荷物を作った。3日間で、できたのがこれだけというのは少し情けない。けど、狭いスペースで仕分けをしながら本をまとめていると、どうしても時間がかかるのだ。売上は、なんとかギリギリ目標の金額は作れたけど、ほんとに中途半端な本の束って、値段がつかないね。なんか、売る意味もないくらい。かといって、自分で売ろうとしても、売れない本はどうしても売れないのだから、他の業者も同じ感覚なんだろう。あえて、高いお金払ってまでそんな本はいらない。もっとちゃんと確実に売れる本が欲しい。それが、みんなの本音のはず。売れる本が毎日のように飛び込んできてくれないものか。なんて、都合よく世の中は運ばない。ハズなんだけど、実は、この土日でなんと9件の買取が集中して発生した。こんなこと未だかつてなかった。ビックリ。春の椿事、ってヤツかい?っても、そんなスゴい本ばかりじゃないけど、ね。と言いつつ、少し収穫をご披露しようと思って、書きはじめた日記だけど、書いてる時間がなくなってきた。もったぶっただけで終わるけど、ゴメンナサイ。中身のなくなった日記じゃアップする意味もないけど、ここまで書いてきたついてでアップしときます。
2007年04月25日
-
一日、荷造り(疲れた)
今日は一日、荷造りday。土曜の優良書市に出すための品物。ずっと、倉庫に眠りっぱなしの本を一掃して、新しい本と入れ替えたいと思いつつ、なかなかできなかった。チョロチョロと出品してはいるが、出す以上に買ってるようで、一向に減らない。今日は、一念発起、なにがなんでもの気合で荷物造りにとりかかる。気合を入れたのには、理由があって、マジに売りを作らないと、払いきれない支払いが待っているから。んー、もっと余裕で商売したいもんだけど、なかなか自転車操業から抜け出せない。困ったもんだ。けど、思い切って、ガンガン荷造りして、棚がどんどんスカスカになっていくと、なんかすっきりしてくる。溜った垢を洗い落としてる気分。今日で、だいたい50本くらい作った。本口なので、1本あたりの金額はたかが知れてる。労力に見合うほどの売上は期待できないかも。それだけ、くだらない品物を後生大事に抱えてたってことだ。しょうもないことで…。明日も、引続き荷造りの予定だけど、明日はもっとちゃんと値段がつきそうな本を選んで組まなきゃな。とにかく、そうやって、一旦、空腹状態にしておけば、また心機一転、新しい荷物を入れる欲も出てくるだろう。これからは、「良品適正在庫」厳守の心構えでやってかなきゃ、な。また、同じ状態になっちゃ意味ないんで、ね。それにしても疲れました。フーッ。
2007年04月18日
-
ニセモノかホンモノか
仕入れ本のなかに、団鬼六の「鬼六将棋三昧」という本があった。この本自体は、どうってことのない本。が、見返しに献呈署名が。宛名はと見ると、えって感じの井上光晴。SM小説の大家団鬼六と純文学畑代表みたいな井上光晴がどこで結びつくワケよって、ミスマッチ感にビックリ。将棋つながりってこと?井上光晴って、将棋好きだったりするのか?なんて、考えてたら、鬼六の本がもう1冊出てきた。と、その本にも署名があった。しかし。しかし、なのだ。なんで? ぜんぜん筆跡のタッチが違うじゃん。とても同一人物の字とは思えない。専門家の筆跡鑑定士なんかじゃなくても、一目瞭然にわかる。楷書と崩し字の違いとか、そういうレベルじゃないのだ。つまり、はっきり言って、どっちかはニセモノということ。そうして眺めると、さっきの将棋本がいかにもウソぽく感じられてきた。字も、書きなれたサインなら、ササッとすべるように書けていいはずなんだけど、妙にギクシャクした字。宛名もサインも同じタッチで、字のヘタな高校生が書いたみたいな素人くささ。かなりの確率でニセモノと思えるのだけど、確定できる術がない。もうひとつの方にしたって本物と断言できる保証はないし…。どっかに、著名人の真筆のサインを集めた鑑定参考書みたいなものとか、ないのかね。古書組合でそういうの、整備して発行するとかしてくれないものかねぇ。ボクみたいに、どこでも修業もせずに、いきなり古本屋になる人たちが、これからますます増えてくるワケで、業界の信頼形成のためにも、そういう鑑定資料みたいなものを共有財産として継承していくってことも大切なんじゃないか、なんて思ったりする。ま、なんにしても真偽不明である限り、しょうがないから、サインはないものとして売るしかないだろう。落書き扱いもしないけど、ね。けど、一度疑問が生じてきたら、今まで扱ったサイン本も本当にホンモノだったか、なんたが怪しい気も。サイン本がどれも、ニセモノに見えてきたりしたら困るね。売るに売れなくなるよ、まったく。
2007年04月13日
-
市場帰りで
今、市場から帰ってきた。映画の本が5本口で出てた。半分以上が、すでに持ってる本。一部を除けば、高く売れる本もない。というか、安くても売れそうにない本がけっこう交じってる。正直言えば、そんなに欲しいと思う口ではなかった。けど、映画本を志向している以上、やっぱり取りにいくしかない。とにもかくにも、まずゲットしといて、後のことはそれから考えればいいやって、感じ。で、取れるには取れたけど、なんとなく、半分くらいは市場に返すことになりそうだね。結局。それ以外の札を入れた本は、ほとんど討ち死に。ひとつだけ、美術関係の束(8冊)が取れた。中身はほとんどわからず、なんとなく面白そう、という感覚だけで入れた札。いいんだろうかね、こんないいかげんな取り方で。ま、そういう本は、ヒモを解いて、ひとつひとつ吟味することが楽しいワケで。お楽しみは、これから。結果、泣きをみることもあるけど、ね。それともうひとつ、しょうもない本まで買ってしまった。新書17本口というヤツ。中に交じってた1冊の単行本が気になって、ほとんど冗談で札を入れた口。なんたって、17本、想定約400~500冊の新書のまず全部が、100均ノリの本、というかゴミ箱直行という本と言ってもいいくらい。いくら冗談でも、よくそんな口に札を入れたものだと、自分が自分にあきれてしまう。どうやら、誰もそんなバカなことをする気になった人はなかったみたい。無競争で取れていた。ま、それでも即売催事で使えそうな本が、そこそこ拾えそうなので、いいことにしておこう。
2007年04月12日
-
振り市の行く末
西部の振り市。今日はやたら品物が少なかった。ふだんも少ないのだが、それにぐるぐる巻きに輪をかけたくらいに少ない。そのうち、そしてなにも出なくなった、なんてことも。あまりに少ないので、買いたいような本もないだろう、今日は買わないことにしておこう。そう思いながら臨んだのだけど、結局、なんだかんだと買ってしまった。クズもいっぱい混ざってる、というかほとんどクズなんだけど、そのなかにいくつか気になるモノをみつけると、つい声をかけてしまう。なんたって、安いから。商売考えたら、振りを無視する手はないワケでね。なのに、振りにやってくる人も、極端に少ない(他の支部は知らないが…)。品物に魅力がないと決めてかかってるんだろう。それは正しい。スゴい本はない。けど、ソコソコの本ならけっこう拾える。しかし、こう安くちゃ買う側はラッキーだけど、出す側になるとうれしくないワケで。品物がどんどん少なくなっていくのも、当然だろうね。やっぱ、そのうち、自然消滅ってことになるのかね?ありうる、ね。
2007年04月11日
-
商売そっちのけ
昨日はなんだかノリが悪くて、ネット出品作業がメチャかったるかった。そんなところに、ひとりのお客さんが。最近、ときどき来るようになった老人で、テレビの仕事をしてた人みたい。店の棚の下に、キネマ旬報が無造作に突っこんである。開店したときの棚塞ぎとして、とりあえず埋めとけって感覚で突っこんで、ずっとそのままにしてあるヤツ。値札もつけてないので、欲しいお客さんがいたら、その場で値づけするしかないのだが、欲しいお客さんなんて、まずいない(開店以来、2人だけ)。なので、手つかずのまま、ただの棚の飾り、というかほとんど棚のゴミクズ同様の状態だった。ただ、戦後すぐくらいから、そこそこ揃っているハズだから、一度ちゃんと整理しなきゃ、とは思ってた。お客さんが、それに目をとめて、昭和22、3年ごろのはないか、と問いかけてきた。背になんの表記もなく、ボロボロになってる、薄っぺらいのがそのころの号だから、捜さなくてもすぐわかる。それらの号を手にとりながら、「懐かしいなあ」を繰り返す。いわゆる青春の思い出なんだろう。映画を見始めたころの教科書だったとか。当時、東宝のプロデューサーだった藤本真澄の文章が印象的だったとか、いろいろ語ってくれた。ったって、こっちは生まれる前の話だし、ただハァハァとうなづいてるしかなかったけど。どうせなら、買ってってくれればうれしかったのに、懐かし話だけで終わってしまった。で、一旦引っ張り出したついでで、やっとこ整理作業をしてみようか、という気になった。冒頭に書いたように、ネット出品に飽いてたので、ちょうど渡りに船という感じで。埃だらけの表紙を磨いて、ボロボロになった背を丁寧にボンド補修する。そんなにして、いくらの値段もつかない品だけど、少しはまともな状態になると、それだけでうれしい。キネマ旬報の創刊は、大正8年のこと。戦争時、休刊状態になっていたのが、昭和21年3月に「再建1号」と銘うって復刊される。再建号は、昭和25年春ごろまで発行されたのち、ふたたび休刊状態に入る。ほぼ半年後の10月、こんどは「復刊1号」となって生まれ変わる。編集長が水町青磁から、清水千代太に、発行元が「キネマ旬報」発行所からキネマ旬報社に変わる。編集同人の入れ替わりもあったのだろう、復刊号の同人には、植草甚一や双葉十三郎などの名前も見えて興味深い。ボクが持ってたのは、「再建6号」からだけど、6号は表紙が取れてるから商品にはならない。実質7号から、79号まで、数冊欠で揃っている。79号が「再建」版の最終なのかどうかは調べきれてないけど、時期的にはその可能性は高い。が、休刊をほのめかす様子はさらさらない。ということは、休刊は突然のことだったのではないだろうか。お家の事情とか…。そのあたりの経緯もちょっと調べてみたくなった。クリーニングや補修をしながら、パラパラと中身に目を通してると、つい読み始めたりして困る。見たことのある映画の紹介や批評があったりすると、当時の評判が気になってしかたないし、まったく知らなかった映画(当然そのほうが多いのだが)を発見するのもとても楽しい。「再建8号」(昭和21年11月)を見てると、伊丹万作の追悼記事が2つほど載っていた。そうか、伊丹万作は、この年の9月に亡くなっていたのだ。「再建9号」(昭和22年1月)には、昭和21年度封切映画一覧というのが掲載されている。21年度と言っても、昭和20年8月、つまり終戦直後からの映画の一覧になっている。戦後最初に作られた日本映画は、松竹の「そよかぜ」(並木路子が「りんごの唄」を歌ってデビューした映画)なんだけど、その公開が10月11日。それ以前に3本(松竹で1本、大映で2本)の映画が公開されている。早いのは、8月31日だ(松竹の「伊豆の娘たち」と大映の「花婿太閤記」)。まさに終戦直後。つまり、それらの映画は、終戦前につくられてた映画なのだが、そんなこんなが、いろいろわかって、なかなか興味深いリストだ。とかなかとか、書き連ねていると切りがなくなるのでやめる。そんな有様で、昨日今日、まともに仕事してないようで、なんだかな、って感じ。だけど、商売より、そっちが面白かったりする、ってのは事実なんだよな、困ったもんだ。
2007年04月07日
全281件 (281件中 1-50件目)
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 五月山動物園 ウォンバットライブカ…
- (2025-02-18 13:59:25)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 「仕事のモヤモヤを手放すノート術」
- (2025-02-18 12:10:30)
-









