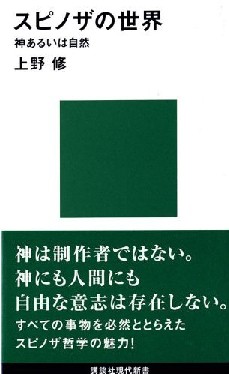
「スピノザの世界」
神あるいは自然
上野 修 2005
ネグリ&ハート
を
読み進めるとスピノザという名前の連呼には、まいってしまう。とにかくこれを読んでおかなくてはならないのだろう。マルチチュードという言葉を言い出したのはスピノザだ、という意見もあり、いやホッブズだ、という意見もある。いずれにせよ、このキーワードで検索していくと、現代思想を検索するには役にたちそうなので、この言葉の出自の背景を知っておくことは必要になってくる。
17世紀最大の哲学者の一人である。神(自然)が唯一絶対の実体であるとし、汎神論を解いた。アムステルダムの裕福な亡命ユダヤ商人の家庭に生まれる。名はヘブライ語でバルフ、ラテン語でベネディクトゥス、いずれも「祝福されし者」という意味である。小柄で、イベリア半島出身のユダヤ人の血を思わせる黒い髪と印象的な眼をしていたという。
p3
「ちょっと待ちたまえ」というスピノザの声がする。「ペテロに言ったイエスのせりふじゃないけれども、すっこんでいろサタン、と言いたいな。君は人間のことばかり考えていて、神のことをまるで考えていない」。
p4
さぁ、ここから何が切り開かれていくのか、今のところは未定だ。さてさて、私はこのブログで「地球人スピリット」をジャーナリスティックに探求しようとしているのであった。その過程で遭遇したのが、マルチチュードであったし、スピノザであった。これらの概念はきわめて難解であることが多い。しかし私は、その難解なものに触れつつ深入りしない、という態度を連ねていきたい。とにかく、日々、何かをブログに書く、ということがメインなのであって、精緻な思索を深めるのは、次の段階だと思っている。
マルチチュードという概念は現代思想を探索するには、便利な指標となってくれそうだ。だが、今のところ二つの違和感というか、不快感が残っていた。まず、ひとつには、マルチチュードという言葉にスピリチュアリティが抜けているのではないか、ということであった。
ところが、ネグリ&ハートの仕事はスピノザに影響されているのであり、また、それを発展的に止揚してきたものであってみれば、スピノザの人となりを理解することによって、そのスピリチュアリティの在りかを推測できるのではないか、ということがあった。
幼少にしてユダヤ社会で教育をうけながら、懐疑的となり、異端のかどで教団を破門され、ユダヤ人共同体から追放されたのが23歳。レンズ磨きをしながら、当時の新思想デカルト哲学をほとんど独学で学んだという。スピノザの人となりは、批判者からも「有徳な無神論者」p4と呼ばれるほど高潔だったという。この人を読み進めるには、新たにデカルトやフォブズ、マアッキャベリなどにも触れていかなくてはならない。そのへんから、マルチチュードのスピリチュアリティを掘り起こしていかなくてはならない。ちょっと遠大なことになってしまいそうだ。
二つ目の違和感というか不快感は、マルチチュードという概念は、どうも複数形、あるいは多数形らしい、ということであった。私にとっての地球人スピリットという概念は、強く個人性が強くでていてほしいのだが、どうやら、このマルチチュードという言葉は多様な様態をした群集といニュアンスがあるらしいということだった。しかし、この点に関しては、シングラリースという言葉がバランスをとってくれそうだ。
個物の「個」に当たるラテン語には「パルティクラリース」と「シングラリース」がある。『エチカ』(スピノザの主著・引用者注)は「シングラリース」の方を好んで用いる。それには理由がある。「パルティクラリース」だとパート、つまり同類全体の中の個別事例という意味になってしまうが、「シングラリース」ならシングル、すなわち他のどれとも似ていない特異な、単独の、一つっきりの、という意味になる。
p178
なるほど、このシングラリースを基礎としてでてくる複数形が、マルチチュードであるなら、納得感はある。先日 読んだ
「ネオ共産主義論」
では
、「シンギュラリティー」という表記ですでにでていた。
近年、イタリアの哲学者アントニオ・ネグリを初めとして、多くの人々は共産主義という言葉をあまりストレートに使いたがりません。むしろ「マルチチュード社会」というスピノザ的な言葉を盛んに使っています。マルチチュードとは「多数」「群集」という意味で、つまりは「多様な個性をもった集団」ということを意味します。
マルチチュードに対応する言葉として、シンギュラリティーがあります。これは、直訳すると「風変わりなこと」「単一なもの」という意味で、要するに「二つとない唯一つのもの」を表しています。すなわちマルチチュードとは、同じような人間の集まりではなく、「唯一人しか存在しない、個性あるシンギュラリティーの集まり」「個性に満ちた人間の集合」という意味があるのです。
(中略)スピノザは、人間の身体は、実はそれぞれあたかも糸のようにつながっているというのです。そして人間は欲望を表現することで、そのことにそれとなく気づくのです。
(中略)バラバラの利己心をもった人間が、「喜び」という感情によって結び付ついた姿こそが「マルチチュード」なのです。お互いが連帯することが喜びであり、またそれによって個々人の個性もなくならず、むしろ発展する関係にある、こうした主体がマルチチュードというわけです。
「ネオ共産主義論」
p238
なるほど、このように親切丁寧に読み解かれると難解と思われるスピノザもなるほど、と分かってくる。しかしながら柄谷行人はこういっている。
ネグリとハートは、スピノザからマルチチュードという概念を引き出したというのですが、それは強引な読みかえです。というのは、マルチチュードはもともとホッブスが使った言葉であり、それは自然状態にある多数の個人を意味します。個々人が各自の自然権を国家に譲渡し、マルチチュードの状態を脱することによって、市民あるいは国民になるわけです。その点で、スピノザも同じ意見です。ただ、ホッブスよりも国家に譲渡しなくてもよい自然権を広く認めたということが違うだけで、スピノザもまたマルチチュードを肯定していないし、それに期待もしていない。
「世界共和国へ」
p216
このような読み方があるわけだが、「新書365冊」なかで宮崎哲弥は柄谷行人の「世界共和国へ」についてこういっている。
柄谷はまるでホッブズやロールズのような手つきで、カントに関する通念を傾倒させます。世界共和国はいかにして成立するか。それは「戦争」、言い換えるならば国家が本源的に孕む攻撃性や敵対性によってだとこの本は断じています。「理性の狡智」ではなく「自然の狡智」こそが世界共和国を齎(もたら)すのだと。
「新書365冊」
346
柄谷は、もっとマルチチュードに触れているので、近々また再掲する予定。さて、いま読み始めている「デモクラシーの冒険 」で
姜尚中
はこういっている
。
(政党は)ネグリとハートが「帝国」で提示したマルティチュードの可能性を抑圧し、コントロールする機能があるんじゃないかと疑っています。つまり、グローバル時代において、一国の枠を超えた多様な連帯を志向する人々の可能性を、国民国家の内部に封じ込めようとする機能です。
「デモクラシーの冒険」p102
と次々とリンクしていくのだが、かなり入り組んだ難解な思考が続くが、このブログでは、ニワカ新書読みとして、広く薄くをとりあえずのスタイルにして、お気軽散歩を続けていくことにする。そして、スピノザのあの声を聞き落とさないでおこう。
「ちょっと待ちたまえ」
-
その男ゾルバ<2> 2007.07.30
-
ネットは新聞を殺すのか 2007.07.30
-
投資信託にだまされるな! 2007.07.30
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




