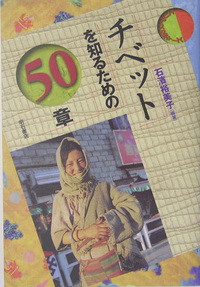
「チベットを知るための50章」
<1> エリア・スタディーズ 石濱裕美子 2004/5 明石書店
チベットという”国”がこの世から姿を消しておよそ半世紀の時がすぎた。しかし、今なおチベットは人々の口の端にのぼり、その文化は人々を魅了し続けている。チベット文化の存続を願う人びとは年を追うごとに増え、チベット文化に対する認知度はかつてないほど広く、深いものとなっている。
国を失っても、そのアイディンティティが崩壊するどころかよりいっそう鮮明となり、さらに外国人までまきこんでひろがってきたその理由は何であろうか。言わずと知られたことだが、チベット文化、とりわけ仏教文化には国境や民族を越えて通用する普遍的な性格があるからである。
p4
オンマニペメフン、蓮華の中の宝珠、の例えどおり、チベット密教は、地球上のスピリチュアリティをクリスタライゼーションしたのではなかっただろうか。それはそのマンダラの世界が、
神聖幾何学
に通じるところにも、なにごとかあるように感じる。そして、そのチベット密教が「開かれ」地球上に広がることによって、蓮華化、あるいはマトリックス化しつつある、という感じがする。そのマトリックス化にはインターネットやメディアの力が大きく力を添えている。
この本はよくできている。もし、秘教チベットへの問いかけが1931年ヒルトンの
「 失われた地平線」
だったとするなら、その答えがこの本「チベットを知るための50章」といえるかもしれない。もし、主人公のコンウェイがこの本を読んでいたら、もっとシャングリ・ラを楽しめただろう。あるいは、作家ヒルトンがこの本を一冊持っていただけで、もっと別な小説に仕上がっただろうと思うと、感無量なところがある。
チベット史は歴史を通じて観音菩薩の祝福を受けているとされたことから、チベット人は朝な夕な観音の六字真言「オン・マニ・ペメ・フン」を唱え、その慈悲に感謝する。
p14
1957年、チベット人ロブサン・ランパの半生を記した「第三の眼」という本が出版された。これはチベット人によって書かれたはじめてのチベットものということから、出版直後の18カ月で30万部という驚異的な売り上げを記録し、この本を通じて多くの人々がチベットに興味を持った。(中略)1958年に私立探偵のマルコ・パリスがロブサン・ランパの正体を1910年生まれのイギリス人シリル・ヘンリー・ホスキンスであることを暴露し、「第三の眼」の売れ行きはぴたりととまった。
p73
このへんは、チェロキー少年の自伝と思われていた
「リトル・トリー」
が、実はKKK支部のリーダーでもあったラジオ番組の作家アサ・カーターであることが、後日発覚して
話題
を読んだことを連想させる。
最近では、欧米人のみならずインドにあるチベット人の寺院でもコンピュータを利用してDTPによるチベット文字のテキストが出版されるようになってきた。またアメリカ人が主体となって、テキストのコンピュータ入力を進めるプロジェクトや、現在では入手困難なテキストをスキャナーで読み取り、PDFかして配布するプロジェクトも始まっている。
p63
まさにこれは、チベット密教のロータス化、マトリックス化、シンギュラリティ化を連想させて、興味深い。
「カーラチャクラ・タントラ」はインドで仏教が滅びる直前に成立し、インド仏教を包括するような内容の巨大な経典となっていると同時に、絶望的な状況の中で将来、仏教王権による理想国シャンバラから仏教軍が異教徒を調伏に来るとという予言を行なっている。
p91
マンダラ世界を地上に作る
「祈り」のシンボルがひしめくチベット建築
p174
私たち日本人の住まいには、「祈り」を感じさせるものは、もはやほとんどない。日本人にとって神社仏閣の類は「外」にある特別なものだが、チベット人は、あくまで日常から「内」にあるものととらえているのだろう。生活の場にあたかも寺院のような空間を作り出そうとする姿勢の中に、信仰が今なお重みを持っているチベット人の精神性を感じることができる。
p179
「チベット文学の代表作は?」との問いに、即答するのは難しい。口承文学という限定を加えれば第一に、「ケサル大王物語」を推す。
p198
チョギャム・トゥルンパの
「勇者の道」
は、このリンのケサル大王に捧げられている。いちど
「 チベットの民話」
でもダイジェストを読んだが、もうすこし長い本も見つけておいた。
チベットで生れた「隠された聖地」の伝説は、イギリスの小説家ジェームス・ヒルトンによって、世界の理想郷シャングリラに生まれ変わった。ヒルトンは小説「失われた地平線」の中で、チベットの深い谷底にはシャングリラという名の理想郷があり、そこに住む人々は精神的に浄化され、所有欲も権勢欲もなく、みな文化を愛する幸せな生活を送っていると記した。シャンバラを連想させるシャングリラという名称といい、その聖地の描き方といい、ヒルトンが中央ユーラシアの探検家たちが祖国に持ち帰ったチベットの聖地伝説を換骨奪胎してシャングリラを構想したことは明白である。ヒルトンの生み出した理想郷シャングリラは、やがて「秘密の理想郷」という意味の一般名詞となり、かつてはアメリカ大統領の避暑地キャンプデービッドや第二次世界大戦中のアメリカ軍の秘密基地を指す暗号として用いられ、現在はポップスの題名からホテルチェーンの名称に至るまでのエンターテイメント分野で幅広く濫用されている。滅び行く仏教徒を慰める聖地の名が、レジャー用語に生まれ変わって世界の人々に慰めを与えている現状は、喜ぶべきことか、悲しむべきことか。
p247
持って瞑すべし。
-
ヘッセの水彩画 2007.11.04
-
ヘルマン・ヘッセ 雲 2007.11.04
-
わが心の故郷 アルプス南麓の村 2007.11.04
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




