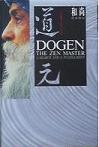
<1>よりつづく
「道元 その探求と悟りの足跡」
<2>
父の家も、母の家も、道元を祖とする仏教の寺の檀家だった。だから、道元は割りと身近にいた感じがする。10代で座禅会に参加するようになった伊達政宗ゆかりの禅寺も道元を祖としていたし、インドから帰ってきた時に最初に迎えてくれた友人も、道元を祖とする寺のお坊さんだった。農業を学んだときに、田んぼの中にポツンとあった禅寺に行って友人達と坐ったものだが、ここもまた道元を祖とする質素なお寺だった。
長じて結婚した妻の実家もまた道元を祖とする寺の檀家だったし、その妹が嫁いだ先も、さらに別な道元を祖とする禅寺の檀家だった。他の親戚も、どういう因縁なのか、道元を祖とする禅寺の檀家がほとんどだ。道元が興した福井の永平寺にも短い間ではあったが訪れたこともあるし、みやげ物のすりこぎは、今でも我が家で活躍している。まわりを見渡せば、ほとんどが、道元、道元、という私の環境なので、仏教、といえば、道元、というのが、ごくごく自然な感覚だった。
Oshoが最期の講話シリーズ
で、ZENを取り上げ、その中に道元を取り上げた時、それは当然だろうと、わが意を得たり、という感じで納得していた。だから、あまり本を読まない時期だったとしても、この本がでた92年10月には、すぐ購入した記憶がある。同時期にでた 「空っぽの鏡・馬祖 」
にはほとんど目を留めなかったのに比べると、雲泥の差だ。馬祖については、いまでもほとんど知らないが、多分Oshoが講話で触れることがなかったら、馬祖という名前さえ知らないで一生を終えたと思う。
だから、どこかで、ああ、このOshoの道元で、決まり、という想いが、少なからずあった。だが、しかしである。この本を手にとって、私の読書は遅々として進まなかった。翻訳者は敬愛するガタサンサである。その後、 アートユニティとしてオーラソーマの販売元
に邁進していくとしても、当時の彼の、Oshoへの愛は本物だった。その姿勢に間違いがない。「序文」を書いているのは、あの紀野一義氏だ。しかも異例の8ページという長文だ。出版元も長年Oshoの出版に関わってきた OEJ
だ。なのに、なぜか、私の心ははずまなかった。
あれから何年も過ぎて、私の傍らにあった本をなんどかめくりはじめたが、最後まで読み通したことはなかった。ほかのニューズレターなどで内容は分かっていたし、同じシリーズの類書と、どう違いがあるのか、そんなことさえ良く判明しなかった。
今回、このブログを進めるにあたって、次第次第にOshoのほうに打ち寄せられ、しかもZENシリーズを読むことになるに従い、この「道元」は、私にとっては、新たなる意味を持ち始めた。
道元は、あまりにも私にとって身近すぎた。ごく当たり前の風景でさえあった。であるがゆえに、Oshoからあらためて道元を聞くと、すこし違和感があった。ちょっと違うぞ。私の道元は、こうだ。そういう思いがわずかながら、あった。気がつかなかったが、あったのだろう。このOshoの道元にチャンネルをあわせるには時間がかかった。
Oshoは、意味的には和尚であっても、Oshoの和尚はOshoなのだ。だから、いくらOshoが禅を語ろうとも、それは禅ではなく、ZENなのだ。その伝でいくと、道元は道元であってはならないのだ。すくなくとも、私独自の道元に固着している限り、Oshoがいうところの道元は、いまいち理解できないことになる。私にとって、ここは、道元を一度、OshoのいうところのDogenとして、飲み干す必要があるようだ。
Dogenといわれると、ドガンとかドゲンじゃ、とか読みそうで、おっとっと、となる。でも、ここは、私の場合は、OshoのDogenをきちんといただく必要がありそうだ。Osho---ZEN---Dogenをそれぞれ別物ではなく、不可分のいったいのものと見て、それを味わいつついくことでこそ、私にとっての、和尚も、禅も、道元も、リフレッシュして、生まれ変わることができるのではないだろうか。
-
究極の旅 <1> 2008.04.29
-
一休道歌 <5> 2008.04.29
-
OSHO ZEN TAROT <2> 2008.04.27
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments





