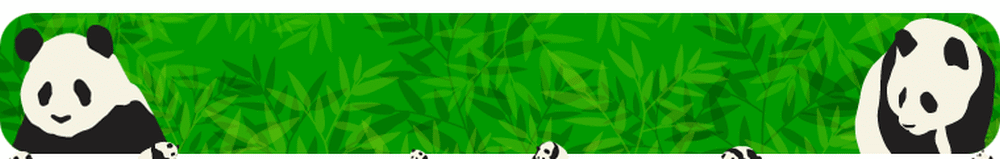PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: 及び腰か勇み足な書評

最近読んだ法律書の中ではめずらしく、全くその通り!と全面的に賛同できる記述があったので、長くなりますが引用しておきます。
73から74頁です。
「刑法の行為規範性を重視し、相当因果関係説ないし客観的帰属論の枠組みを用いて、より具体的な行為規範を提示しようとする見解は、人は、一般に法律及び法律実務に照らして自らの行動を決定するものだという前提に立っているといえる。しかし、人が自らの行動を決定するときに法律を、ましてや判例等による法解釈を参照することは、すくなくとも通常のことではないであろう。理由は必ずしも明らかではないが、普通、人は、人を殺してはいけないということを、自分自身において知っている。そして、人が自己の行動を決定する際には、訴の自らの判断にしたがうのが、むしろ通常であろう。法学部の学生でも法律家でもないほとんどの人は、詐欺罪の構成要件を詳しくは知らない。しかし、それに類することをするのはよくないと、もともと知っているから、それを行わないのである。
このような決定の仕方は、判例つきの六法と首っ引きで、どこまでが許されどこからが許されないかを逐一確認してから行動を決定するというやり方と比べ、はるかに健全である。そうだとするなら、刑法の第一の責務は、人に違法性を判断するための材料を与えることではなく、人の内発的な決定を尊重することにこそ置かれるべきであろう。人々の内発的な決定を尊重するということは、法令や判例、まして学説によって、「このような行為を行っても処罰はされません」と示してあげること、そして、そうして構築された規範に違反していない場合に処罰を否定することとは、全く別のことである。法が、人々の決定を尊重するためにできることは、事前に行為規範を示すこととは正反対に、法律から自由に、自らの良心にしたがって行動した人に対し、法律が不当な責任を負わせることのないように、事後的に努めること以外にはないと思われる。」
こういった視点は「因果関係論」に限らず、あるいは刑法に限らず、法律解釈全般に妥当することだと思うんですよね。私自身もそれらしいことをブログのあちらこちらで書いているつもりなんですが、こういうしっかりした文章として表現できないんです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年02月23日 13時06分52秒 コメントを書く
[及び腰か勇み足な書評] カテゴリの最新記事
-
佐藤英明『スタンダード所得税法』 2009年05月04日
-
大内伸哉『雇用はなぜ壊れたのか-会社の… 2009年05月03日
-
コリンP.A.ジョーンズ『手ごわい頭脳… 2009年05月02日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.