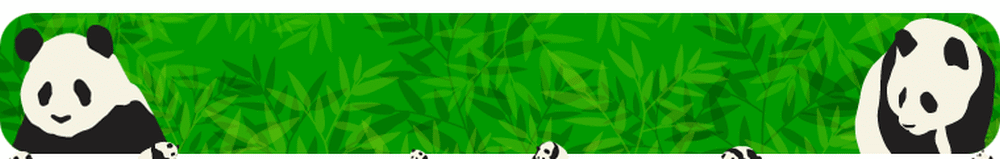PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: いたづらにむつかしい刑法

「なお財産上の利益の移転は暴行・脅迫から直接、不法に生じていなければならないとされる。したがって唯一の相続人が相続を目的として被相続人を殺害した場合や被害者の死亡後、経営者会議の議決により経営権を獲得する目的で、被害者を殺害した場合には、強盗殺人罪は成立しない。相続は死亡から直接生じるものの、それ自体は適法な法現象であるし、会議の議決は死亡から直接生じるものでも、また不法なものでもないからである。」(リーガルクエスト刑法各論140頁)
ここでは、財産上の利益の移転が暴行・脅迫から「直接、不法」に生じなければならないという「理由」から、そこでかかげる事例において強盗罪を否定するという「結論」が導かれています。
じゃあ、「直接、不法」が必要な「理由」はどこからでてくるのかというと、どこにも書いていません。
おそらく実際には、そこでかかげる事例において強盗罪を成立させるべきでないという感覚があって、これら事例を強盗罪から除外するために、「直接、不法」という要件を付加した、というところではないかと思います。つまり、表向きはあたかも「演繹」的に答えが導かれたかのように書いてありながら、実は、事例の側から「帰納」的に要件が作り出されたのでは、ということです。
それが法解釈として正しいかはともかく、それはそれでひとつの証明方法には違いないのですが、帰納によっていることをきちんと明記してほしいわけです。
先日の日記 で引用した小林憲太郎先生の一文があてはまるんじゃないかと思うんですが、「共通了解」があるから論証なしでもかまわないってことですか。
けど、相続事例や経営者交替事例で強盗罪を否定することには共通了解があるとしても、処罰感情が一致しない事例がでてきたときには、ある人は「直接」だといい、ある人は「直接」でない、といい出すことが予想できます。で、このままでは結局のところ、当該事例を処罰すべきか否かという生の処罰感情でしか、説の優劣を決することができなくなります。
また、「不法」かどうか、というのも、もし相続事例で強盗罪が成立するという結論をとるならば、そこでいう相続も「不法」な利益の移転となるわけです。つまり、不法でないから強盗罪が成立しない、あるいは、不法だから強盗罪が成立する、というのは順序が逆であって結論先取りなわけです。
こういうことはこの本だけに限られるわけではありません。むしろ、この本は最近の本の中では 『アクチュアル刑法各論』 と並んで優れているほうであって、理由付けなしにあたかも当然のように論述が進んでいくような本は他にもあるわけです。けども、このような優れている本であってもこういう記述があるんですね、ということを言ってみただけです。
残念ながら、書かれてあることを正面から読むだけでは法律書を理解できないこともあるわけです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月13日 13時36分57秒 コメントを書く
[いたづらにむつかしい刑法] カテゴリの最新記事
-
精神分析する自分を精神分析する-自己言… 2007年08月10日
-
ロボットはパイロット搭乗型よりも遠隔操… 2007年08月08日
-
これは総論ではないのか。 2007年05月18日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.