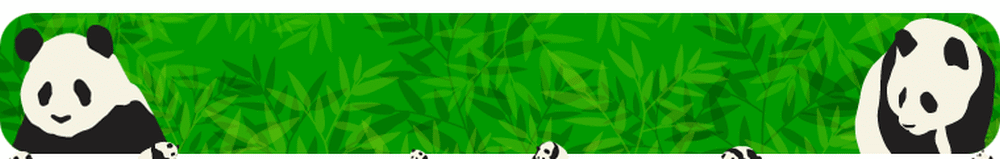PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: ついつい批判的にみてしまう会社法
【定期購読1年(12冊)】法学教室
以前の日記
落合先生の見解を、私なりの言葉を勝手に補って表現すると次のようになります。正確な要約ではないので、以下の解釈は落合先生の見解ではなく、二元説のうちのある一つの解釈モデルということにしておきます。
1 423条1項
423条1項の「任務を怠った」には、任務懈怠(客観)と過失(主観)が含まれる。
任務懈怠(客観)の存在は責任を追及する側が、過失の不存在は役員側が、それぞれ立証する責任がある。このことは立証責任の分配に関する一般論から導かれる。
2 423条3項
423条3項は、任務懈怠(客観)の存在を推定するもの。過失(主観)は423条1項ですでに役員側にその不存在の立証責任があるから転換する必要なし。
3 428条1項
428条1項は、役員側が過失(主観)の不存在を立証しても責任を免れることはできないとするもの(無過失責任)。
結論自体はこういうことでいいんだと思いますが、この解釈によると条文にいう「任務懈怠」につき
1 423条1項→客観+主観
2 423条3項→客観
3 428条1項→客観
と1と23とで異なる意味に解釈しなければならなくなります(ちなみに、423条1項と同条3項が同義(客観+主観)だとすれば、12と3で異なる意味ということになります)。なお、3が客観であることは文言上動かしがたいでしょう。
形式的にも実質的にも満足できる解釈をするには、やっぱり、423条1項に「ただし、任務を怠ったことが役員等の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とか入ってないとどうしても難しいよね(これを入れると任務懈怠はすべて「客観」で揃います)。
この但し書きを入れなかった理由を邪推するに、あらゆる事案において常に「任務懈怠(客観)+過失(主観)」と二元説だけで押し切れる(「二元説一元論」と命名します)わけではなく、事案によっては「任務懈怠(客観と主観の総合判断)」と一元説的に判断せざるをえない場合もある(「一元説・二元説二元論」)と考えたんじゃないですかね。
だから、423条1項のような原則規定では、本文(客観)+但書(主観)と明確に区別した書き方をしないでそのへんはぼかしておいて、例外規定の場面で必要な限度で客観と主観を区別した書き方をすると。そうすると、条文間の不整合ははじめから織り込み済みですか。
・
もし二元説で割り切れないとすると、やや複雑な状況が発生します。
「自己取引」の場合は、428条1項が明確に二元説の立場に立つことを前提にしていますので、
423条3項 任務懈怠(客観)の不存在を役員側に負わせる
となります。
まあ、実際は「任務懈怠(客観)」の中で過失(主観)的なものが考慮されてしまうのかもしれませんが、建前としてはそれは428条1項により禁止されていると。
(自己取引を除いた)「利益相反取引」の場合、上では423条3項は過失(主観)については触れていないと書きましたが、これは「二元説一元論」を前提とした解釈にすぎません。
「一元説・二元説二元論」によれば、423条1項には
2 任務懈怠(客観と主観の総合判断)
の二つの類型があることになります。
そして、1の場合で立証責任を
任務懈怠(客観)→追及側
過失(主観) →役員側
と分配した場合には、423条3項では任務懈怠(客観)だけを転換すればよいわけです。
けど、2の場合には、主観と客観を区別することができないわけだから、
423条1項 任務懈怠(客観主観の総合)を追及側が立証すべき
423条3項 任務懈怠(客観主観の総合)の立証責任を役員側に転換
と、3項でも、客観だけを取り出して推定することはできず、主観も含めて推定することにならざるをえないはずです(ただ、総合判断の場合、主観と客観の総合にとどまらず、根拠事実と障害事実をも総合的に判断せざるをえない場合もあるので、立証責任の転換といっても、実際上はそれほどの効果はないのかもしれません。)。
つまり、423条1項に二つの類型が含まれることにあわせて、423条3項でも、客観のみを推定する場合と客観主観をともに推定する場合とがあるということです。
まとめると、
1 自己取引の場合(二元説を前提)
423条1項 任務懈怠(客観)を追及側が立証
過失(主観)の不存在を役員側が立証
423条3項 任務懈怠(客観)の不存在の立証を役員側に負わせる
428条1項 過失(主観)の不存在の立証を認めない
2 利益相反取引の場合
ア 二元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(客観)の存在を追及側が立証
過失(主観)の不存在を役員側が立証
423条3項 任務懈怠(客観)の不存在の立証を役員側に負わせる。
イ 一元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(総合)の存在を追及側が立証
423条3項 任務懈怠(総合)の不存在の立証を役員側に負わせる
3 それ以外の場合(通常の場合)
ア 二元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(客観)を追及側が立証
過失(主観)の不存在を役員側が立証
イ 一元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(総合)の存在を追及側が立証
(総合判断の場合の評価根拠事実と評価障害事実の区別は省略)
落合先生が引用されている田中亘先生の見解は、利益相反取引の場合には二元説により理解し、それ以外の場合には一元説により理解する、というもののようですが、ここでわたしが書いていることは、自己取引を二元説のみによって理解し(二元説一元論)、それ以外の場合は一元説及び二元説によって理解する(一元説・二元説二元論)、という考えなわけです(一元論と二元論の二元論)。
わたしの考えの根拠となっているのは条文の書きぶりのみであって、実質的な根拠はとりあえず何も考えていません。ただ、この考えでも、1や2アの場合に任務懈怠の意味が一致しないという問題は解決できていません。
なお、自己取引の場合でも一元説が相応しい事案があるのかもしれませんが(二元論の一元論)、きりがないので考えないことにします。
( 次回 へつづく)
○会社法
第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
3 第356条第1項第2号又は第3号の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
1 第356条第1項第2号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
第356条(競業及び利益相反取引の制限)
1 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
以前の日記
落合先生の見解を、私なりの言葉を勝手に補って表現すると次のようになります。正確な要約ではないので、以下の解釈は落合先生の見解ではなく、二元説のうちのある一つの解釈モデルということにしておきます。
1 423条1項
423条1項の「任務を怠った」には、任務懈怠(客観)と過失(主観)が含まれる。
任務懈怠(客観)の存在は責任を追及する側が、過失の不存在は役員側が、それぞれ立証する責任がある。このことは立証責任の分配に関する一般論から導かれる。
2 423条3項
423条3項は、任務懈怠(客観)の存在を推定するもの。過失(主観)は423条1項ですでに役員側にその不存在の立証責任があるから転換する必要なし。
3 428条1項
428条1項は、役員側が過失(主観)の不存在を立証しても責任を免れることはできないとするもの(無過失責任)。
結論自体はこういうことでいいんだと思いますが、この解釈によると条文にいう「任務懈怠」につき
1 423条1項→客観+主観
2 423条3項→客観
3 428条1項→客観
と1と23とで異なる意味に解釈しなければならなくなります(ちなみに、423条1項と同条3項が同義(客観+主観)だとすれば、12と3で異なる意味ということになります)。なお、3が客観であることは文言上動かしがたいでしょう。
形式的にも実質的にも満足できる解釈をするには、やっぱり、423条1項に「ただし、任務を怠ったことが役員等の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とか入ってないとどうしても難しいよね(これを入れると任務懈怠はすべて「客観」で揃います)。
この但し書きを入れなかった理由を邪推するに、あらゆる事案において常に「任務懈怠(客観)+過失(主観)」と二元説だけで押し切れる(「二元説一元論」と命名します)わけではなく、事案によっては「任務懈怠(客観と主観の総合判断)」と一元説的に判断せざるをえない場合もある(「一元説・二元説二元論」)と考えたんじゃないですかね。
だから、423条1項のような原則規定では、本文(客観)+但書(主観)と明確に区別した書き方をしないでそのへんはぼかしておいて、例外規定の場面で必要な限度で客観と主観を区別した書き方をすると。そうすると、条文間の不整合ははじめから織り込み済みですか。
・
もし二元説で割り切れないとすると、やや複雑な状況が発生します。
「自己取引」の場合は、428条1項が明確に二元説の立場に立つことを前提にしていますので、
423条3項 任務懈怠(客観)の不存在を役員側に負わせる
となります。
まあ、実際は「任務懈怠(客観)」の中で過失(主観)的なものが考慮されてしまうのかもしれませんが、建前としてはそれは428条1項により禁止されていると。
(自己取引を除いた)「利益相反取引」の場合、上では423条3項は過失(主観)については触れていないと書きましたが、これは「二元説一元論」を前提とした解釈にすぎません。
「一元説・二元説二元論」によれば、423条1項には
2 任務懈怠(客観と主観の総合判断)
の二つの類型があることになります。
そして、1の場合で立証責任を
任務懈怠(客観)→追及側
過失(主観) →役員側
と分配した場合には、423条3項では任務懈怠(客観)だけを転換すればよいわけです。
けど、2の場合には、主観と客観を区別することができないわけだから、
423条1項 任務懈怠(客観主観の総合)を追及側が立証すべき
423条3項 任務懈怠(客観主観の総合)の立証責任を役員側に転換
と、3項でも、客観だけを取り出して推定することはできず、主観も含めて推定することにならざるをえないはずです(ただ、総合判断の場合、主観と客観の総合にとどまらず、根拠事実と障害事実をも総合的に判断せざるをえない場合もあるので、立証責任の転換といっても、実際上はそれほどの効果はないのかもしれません。)。
つまり、423条1項に二つの類型が含まれることにあわせて、423条3項でも、客観のみを推定する場合と客観主観をともに推定する場合とがあるということです。
まとめると、
1 自己取引の場合(二元説を前提)
423条1項 任務懈怠(客観)を追及側が立証
過失(主観)の不存在を役員側が立証
423条3項 任務懈怠(客観)の不存在の立証を役員側に負わせる
428条1項 過失(主観)の不存在の立証を認めない
2 利益相反取引の場合
ア 二元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(客観)の存在を追及側が立証
過失(主観)の不存在を役員側が立証
423条3項 任務懈怠(客観)の不存在の立証を役員側に負わせる。
イ 一元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(総合)の存在を追及側が立証
423条3項 任務懈怠(総合)の不存在の立証を役員側に負わせる
3 それ以外の場合(通常の場合)
ア 二元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(客観)を追及側が立証
過失(主観)の不存在を役員側が立証
イ 一元説が相応しい事案
423条1項 任務懈怠(総合)の存在を追及側が立証
(総合判断の場合の評価根拠事実と評価障害事実の区別は省略)
落合先生が引用されている田中亘先生の見解は、利益相反取引の場合には二元説により理解し、それ以外の場合には一元説により理解する、というもののようですが、ここでわたしが書いていることは、自己取引を二元説のみによって理解し(二元説一元論)、それ以外の場合は一元説及び二元説によって理解する(一元説・二元説二元論)、という考えなわけです(一元論と二元論の二元論)。
わたしの考えの根拠となっているのは条文の書きぶりのみであって、実質的な根拠はとりあえず何も考えていません。ただ、この考えでも、1や2アの場合に任務懈怠の意味が一致しないという問題は解決できていません。
なお、自己取引の場合でも一元説が相応しい事案があるのかもしれませんが(二元論の一元論)、きりがないので考えないことにします。
( 次回 へつづく)
○会社法
第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
3 第356条第1項第2号又は第3号の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
1 第356条第1項第2号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
第356条(競業及び利益相反取引の制限)
1 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ついつい批判的にみてしまう会社法] カテゴリの最新記事
-
会社は商人ですよ。 2008年03月04日
-
条文解釈のお作法-会社法の読み解き方(… 2007年05月23日
-
伝わらないこと。 2007年05月17日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.