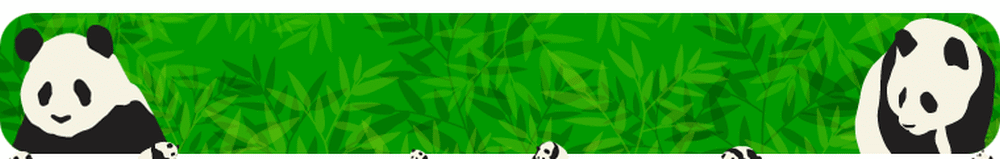PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: 及び腰か勇み足な書評

・ある程度勉強の進んでいる人が、刑事法の歴史や基本原理の説明が手薄な教科書を補うために使う感じでしょうか。「さしあたっての」実益はなさそうですが、徐々に効いてくるといううことになるでしょうか。少なくとも、これを入門書とするのは難しいと思います。
・原理原則から説き起こすというのは、非常にいいと思うんですが、それが個々の解釈論にどうつながってくるかを十分に例示してくれていないので、抽象的な理解に止まってしまいます。
・「憲法」に基礎をおいた刑事法学ということが書かれています。でも、たとえば、刑事訴訟法において、被害者の人権を被告人の人権よりも強調する立場も、その逆の立場も、それぞれ主観的には憲法に基づいた主張をしているつもりなわけで、憲法を基礎においたとしても、かなり大きな幅があるということです。
そもそも、憲法学自体においても、「比較考量論」という判断手法があったりするわけで、憲法を持ち出しても一定の立場が導かれるわけではありません。なので、憲法に基礎をおくというだけでなく、具体的に、憲法を用いるとどういう解釈論が展開されるのかを、例示して欲しかったということです。
・テキストという位置づけのせいで、どうしても制度の概説が続いてしまうわけですが、原理原則や歴史の部分、あるいは平川先生自身の見解をもっと深くから論じてくれれば、読み応えのある本になったのに、と残念な気がします。
刑事法に限らず法学全体について論じた本ですが、その好例として存在するのが、平川先生の師匠である団藤重光先生の 『法学の基礎』 なわけです。「の基礎」つながりということで、平川先生のこの本にも同じような期待をしてしまったわけですが、さすがに今の時代、学生のニーズには逆らえないんでしょうか。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[及び腰か勇み足な書評] カテゴリの最新記事
-
佐藤英明『スタンダード所得税法』 2009年05月04日
-
大内伸哉『雇用はなぜ壊れたのか-会社の… 2009年05月03日
-
コリンP.A.ジョーンズ『手ごわい頭脳… 2009年05月02日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.