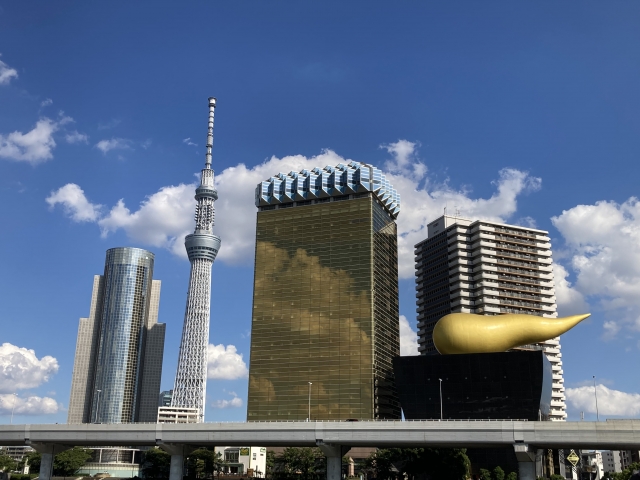季節の物<タケノコ>
タケノコキンピラ
材料
たけのこ450g(中1/2個程度) ・・たけのこの硬い部分がいいよ
お酒大さじ2・・・私はゆず酒を使ったよ
醤油大さじ3 砂糖(ザラメ)20g みりん小さじ1
(砂糖みりん醤油の割合は1:2:3でもいいよ)
鷹の爪 1本 粉山椒少々 油 少量 ごま油 少量 ゴマ少々 水150CC
タケノコを下処理しておきます
1、たけのこの硬い部分(根の方)をせん切りにする。
繊維に沿って切ってね。そして鷹の爪は種を除いたほうがいいかもネ(種と綿の部分が一番辛い)小口切りにしまあ~す。無ければ・・赤唐辛子でもOK
2、フライパンに油少量と鷹の爪を入れて火にかけ香りが出たらたけのこを加えて炒めま~す。鷹の爪を炒めすぎると・・悲惨だよ~。喉はイガクなるし目は痛いし・・まるで喘息患者だぁ~~っ。
お酒を入れてアルコールをとばしてから水・醤油・砂糖・みりんを加えて汁気がなくなるまで煮詰める。
3、汁気がなくなったら山椒を入れゴマをいれてから鍋肌にごま油を加え(なんだかゴマで誤魔化していない?)香りがたてば出来上がり!完全に冷めてから冷蔵庫へ。1週間程度は大丈夫だと思う・・多分。
ポイント
ザラメがなければ普通の砂糖でもいいよ。でも種類によっては甘過ぎるかもしれませんので調節してみてねネ。辛いものが苦手な方がいる場合は鷹の爪は入れずに食べる時に一味等を振ればいいカモ。
タケノコの保存
うの花漬
材料
タケノコを下処理しておきます
タケノコ1に対して、おから1、塩1(1:1:1)
1,おからは1日陰干ししてから使います。
2.陰干ししたおからに塩を混ぜておきます。
3.下処理したタケノコを漬けます一番下におからと塩を混ぜたものを敷き詰めて後は、これとタケノコを交互にはさんで漬けておきます。 これでOK
使う時きによく茹でてそのまま冷まします。その後水を2~3回取り替えて使用します。
塩漬け
材料
タケノコ2kg 塩 0.8kg 食塩 : 15g 重石5kg 水0.5リットル
タケノコを下処理しておきます タケノコの下処理
1.漬け込む時は、たる底にふり塩をし、タケノコはすき間なく塩と交互に入れ、塩は上にいくほど多くします。
2.タケノコは水の上がりが悪いので差し水をします。
3.水が押しぶたの上に上がったら石を軽くし、水がひたひたになるようにします。
食べる時は1~2日間塩出しをしてから調理します。
乾燥タケノコ
1.鍋に水を入れて火をつけておきます。
2.ふたつわりにして節の所を取ります。(節をつけて乾燥させてもかまいませんが出来上がりがきれいですし、乾燥も速いようです)
3.鍋に節を取ったタケノコを入れ。アク取りを入れます。タケノコが煮えるまで炊きます。(米ぬかがない時はお米でも味噌や小麦粉を入れてもかまいません)
4.煮えたら乾燥させます。(時々場所を変えたりひっくり返したりします)たけのこが煮えたらすぐ乾燥させたが良いようです。(味は変わらないようですが干し竹の子の色がきれいに出ないようです)
5.乾燥できたら天気のいい日に太陽に当ててt天日乾燥させます。
6.からからに乾かしてビニール袋に入れて保存します。
メモ
茹でたタケノコをそのまま冷凍すると、繊維ばかりになっておいしくなくなりますが、水と共に冷凍すると、大丈夫です。 たけのこご飯にしたり、煮物などに調理した後、煮汁ごと冷凍してもいいです
© Rakuten Group, Inc.