-
1

スイス人は英語を話す?
先週からフランス語の勉強を始めました。 ガイドブックには、「スイスではドイツ語、フランス語、イタリア語が公用語で、スイス人は何ヶ国語も話せるのが普通」だとか、「電車の車掌さんでも英語を含め4ヶ国語が話せる」とか、「どこでも英語が通じて感心する」など、あたかも英語ができれば何も困らないかのごとく書かれていますが、それは正しくありません。 普通の人でも、大学で勉強していたことがあったり、両親の国籍が違って、いくつかの言葉がわかるという人は勿論います。 また、観光客が訪れる有名な観光地で働く人や、観光客の多い氷河特急などの車掌さん、ジュネーブの国際機関で働く人や、エリートサラリーマンは話せるでしょう。 でも、それは、どこでも皆が英語を話すし、通じるということではなく、日本でも京都の土産物屋では、店員に英語が通じるというのと同じです。 こちらで生活する上では、フランス語ができないとどうしてもダメということが多々あります。 例えば、家に不具合があり修理を頼む。各種保険を申し込む。子供の誕生日にケーキを注文する。ほしい品物があるかどうか聞く。電話の申し込みをする・・・。 市場のおばさんや電気工事のお兄さん、市内バスの運転手、アパートの管理人さんなどは、まず英語はできません。日本と違い、大学生がお店のレジやウエイトレスをしていることはまずないので、スーパーでも通じません。 通じないレベルも筋金入りで、一桁の数字すら通じません。 また、住居用洗剤の使い方や調味料の表記、電気製品の使用説明書、住居に関する設備費値上げや、工事のお知らせなど、英語のものはまずありません。 ということで、ジュネーブでより便利に生活するために、旦那とともにフランス語を始めました。 さて、最近髪がまとまらなくなって困ってますが、言葉ができないので美容院へ行く勇気がありません(笑)。今の目標は、一人で美容院に行って髪を切ってもらえるようになるというところです。
2005年12月03日
閲覧総数 458
-
2

ヨルダン ペトラ遺跡(3)
ペトラ遺跡の写真の続きです。またまた地図(5)からということで、エル・ハズネの全景(5)です。写真などで見ていたものより大きい、というのが第一印象。紀元前1世紀~後2世紀くらいのもので、高さは43mあるそうです。昔は建物の一番上にある壺に宝物が入っていると信じられていて宝物殿と呼ばれてますが、調査の結果、こちらは霊廟だということです。内部ですが・・・(6)砂岩の模様がとてもきれいです。しかし、中には何もなく、これ以上奥は入れません。地下もあるみたいなんですけど、解説図などはないので、これ以上の事は不明です。このエル・ハズネの前は広場になっていて、飲み物やお土産も売ってます。ラクダや馬車も客待ちしているので、こちらで価格交渉して乗ってこの先に進むなり、戻るなりも可能です。さて、ツアーはここで解散。2時間半後にバスに集合となりました。ここからは自由に遺跡を見学することになります。エル・ハズネの右手からさらにペトラの奥へ。地図では(7)です。ここからが遺跡めぐりの本番。エル・ハズネは遺跡の入口ですから、ここで満足してはいけません(^^;)。この辺りには特別に名前も付いていませんが、墓が並んでいます。矢印のところの人を見てもらえばわかる様に結構大きいものです。 近くで写真を撮ってみました。ここも砂岩の模様がとても見事です。実物は写真より赤色が強く綺麗です。この先には両側の崖が開けて広い場所に出ます。円形劇場などもありますから、この広場はペトラの繁華街?だったのかもしれません。地図では(9)です。まわりの崖には住居跡らしい穴が一杯。写真を見てもらえば、山の上の方まで岩が人工的に垂直に削られていることがわかると思います。この広場から左側に山へ登る階段があります。え・・・・?登るの????(^=^;) 30分以上登ると祭壇、住居跡、オベリスクなどが並ぶ場所もあるそうですが、そこまではいけません。広場が一望できる高さまで登り、記念撮影。子供たちはもっと登ると言いましたが、もちろん却下(^^;)。階段を降り、円形劇場に向かって奥へ進みます。 円形劇場。その先の場所(11)。崖の上には立派な墓の遺跡が一杯並んでいます。そこまで登って見学に行けます。近そうにみえますが、遺跡が大きいので上まで結構遠いんです。なので、もちろん行きませんが(^^;)。(行ったら集合時間までに帰れません)ここの墓の崖の下に茶屋がありますので、遺跡を見ながら休憩する人がたくさん。遺跡の下の崖にはトイレもあります。 更に道を進むと柱廊通りが見える場所まで来ます(12)。遠すぎでよく見えませんが、拡大すると・・・。奥の方にまだまだ遺跡は続いています。しかしそろそろ集合時間前1時間を切りました。戻らねばなりません。時は2時過ぎで一番暑い時刻。がんばって歩きましたが、シークを抜けたあたりでもうバテバテ。時間も迫ってますのでシーク入口(2)で客待ち馬と交渉して、入口まで馬で戻ることにします。へばっていた子供らも、馬に乗るとなったら急に元気に。馬は引いてもらえるので子供でも大丈夫です。 ということで、無事集合時間ちょうどに戻ることができました。それにしてもペトラは広いです。時間が取れれば宿泊して午前中の涼しいうちに奥まで見学するのがいいと思います。でも、欧米人の中には暑い午後にリュックを背負って山の奥へ登っていく人たちも・・・。チャレンジするにはくれぐれも飲み物と帽子をお忘れなく。次回はペトラ以外のオプショナルツアー体験をご紹介します。
2008年08月17日
閲覧総数 1015
-
3
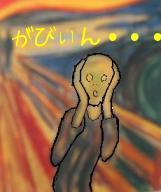
ジュネーブで子供の学校を決める(小2長男編・1)
ジュネーブに限らず、どこの国でも、海外で子供の教育をどうするかは最大の難問の一つです。 ジュネーブには、全日制の日本人学校はありません。 よって、現地校(公立)かインターナショナルスクールかを選ぶことになります。 現地校ならば自分で歩いて通えるし、学費はタダ。インターは送り迎えが必要で、学費は1年で最低でも170万円はします。何も問題なければ現地校に入れたいのですが、勿論、そう簡単な話ではありません。 スイスの現地校は、フランス語です。それに加え、小学校4年生からドイツ語も始まります。 幼稚園ならともかく、小学校以上に編入するとなると、全く言葉がわからなくても、家庭で何とか授業をフォローし、宿題も仕上げていくようにと考えるのが普通でしょう。 ジュネーブは外国人も多く、公立学校でもフォロー体制は一応ありますが、子供の力だけでフランス語の授業をこなすのは勿論不可能。家でも毎日誰かがフランス語←→日本語の翻訳フォローで勉強を見なければなりません。 うちの場合、親のフランス語能力は、ゼロで、フランス語では子供に何もフォローしてやれませんから、家庭教師をつけることになります。 しかし、家庭教師をつけて、フランス語をフォローすればそれでいいかというと、まだ問題があります。 数年後に日本に帰国する場合、帰国後に問題があったのです。 日本出発前に家のある横浜の区役所、公立中学に帰国子女の受け入れについて問い合わせたところ、文部科学省からの予算が減ったため、横浜市の公立中学帰国子女受け入れ校制度や、それに付随するフォローの体制が昨年から無くなったことを知りました。 隣の学区の中学が帰国子女指定校だったので、歩いて通えるし、お金もかからずラッキー。と思っていたのに、 大ショック・・・ 「現地では補習校しかないのですが、帰国後公立中学でも大丈夫なんでしょうか?」と、率直に聞いてみましたが、言葉を濁されるばかりでした。 その後相談した小学校の担任の先生は、もう少しはっきり「公立で無理な場合、帰国子女として中学校受験も視野にいれ、英語の学校の方が良いと思います。」と、言ってくださいました。 調べたところ、私立の帰国子女入試では、多くの学校が「英語の試験」を課していて、フランス語だと、受けられる私立中学校は限られます。 フランス語で受けられる学校でも、「受けられる」というだけで、実際には英語で受験する子の方が断然多く、入学後の体制も、「帰国子女は海外全日制日本語学校か、英語教育のどちらか」として、帰国子女クラスと授業内容が設定してあったりして、フランス語では、普通のクラスでも、フォロークラスでもニーズに合わず、難しいようでした。 その他、海外子女教育振興財団にも相談したところ、現地校の勉強は「話せればいい」程度に考え(早い話、投げ打って(^_^;))、現地でも日本の通信教育や問題集、インターネットなどフル活用し、家庭で日本の教育をメインにして勉強させる親御さんもいらっしゃるそうです。 ジュネーブで、国語と日本の社会、理科をよくフォローして帰国すれば、公立に進むことも十分可能なのかもしれません。 そうすれば、インターに行ったつもりで、浮いた学費の何百万円かのお金は、子供の習い事や、長期休暇の旅行、将来の教育資金にためたり・・・ということもできるでしょう。 でも、実際に自分たちがどこまで日本の学習内容を家庭でフォローできるのか? 子供が現地校の勉強の方が気に入ってしまった場合、どうしたらよいのか? そんなことは行く前には勿論わからなかったので、上の子はやっぱりインターに入れるほうが安パイという結論になりました。● 子供の学校をどうするのか考える時に、役立つ本新・海外子女教育マニュアル第4版 海外子女教育振興財団 編 財団のホームページには、在外の日本語教育情報、帰国時の受け入れ校情報、Q&Aなど、役立つ情報が多い。個人でも利用できるが、赴任の場合は会社が法人会員になっているかどうか確かめるとよいと思う。問い合わせ 財団法人 海外子女教育振興財団 03-4330-1341(代)
2005年12月16日
閲覧総数 2155
-
4

【フランス】実はニースのビーチは・・・
ニースは恐らくコートダジュールで最も知られたリゾート地。 海岸線は長いし、海の色はそこそこ大きな町にしては驚くほど澄んで美しいし、海水浴には最高! に思えますが・・・思わぬ落とし穴が・・・( ̄△ ̄;)。 実はニースの海岸は・・・。 石・・・・。 ○○○ ○○○○○○ 石・・・・。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 石なんですよ~海岸が・・・(^=^;)。 尖った石はなくて丸いんですが、小石レベルじゃない石なんです。見えにくいですが・・・石の大きさは大体手のひらよりやや小さいくらいでしょうか。 なので、残念ながら、砂で堤防を作ったり、砂に埋まってみたりすることはできません(-_-;)(え?そんなことしない?)。 石ですので、水底では波の動きで水中に砂が舞い上がらず、よって透明度が高く美しく見えるんです。 大人が海を見ながらビーチで寝転がってる分には、水の色は綺麗だし、砂で荷物やなんかが汚れないからいいんですけど・・・子供はちょっとつまんないかも。 下が石なので、パブリックビーチでは敷物を敷いてもガタガタで固め。 ニースではやっぱりお金はかかりますがプライベートビーチがいいと思います。 プライベートビーチの利用方法は前述したとおりです。 なお、お天気がいい日は、石なだけあって、足元は熱い様です(^^;)。 ビーチサンダルをお忘れなきよう。 ニースの街については、冬の南仏旅行の日記にさらっとふれてありますので良かったらそちらを見て下さい。
2007年08月14日
閲覧総数 2814
-
5

レザークラフトで使う道具・カッター
レザークラフトの本には、当たり前のように革を裁断する道具として革包丁の解説が載っています。でも、実は私はあまり使ってないのです(持ってるけど)。じゃあ何を使ってるのかと言うと、カッターナイフです。え?カッターで革が切れるの?はい。切れます。スパスパ切れますとも。(以前の日記のボストンバッグも、ショルダーバッグも財布も、ほぼカッターで裁断)今メインで使ってるのは日本の誇るオルファのカッターで、刃は黒刃。これがもう使いやすいのなんの。実はレザークラフトを始める前に、シャドーボックスをやってた時代がありました。カッターを駆使して平面の紙の絵を立体的に見せる手芸です。これくらいのだと、1つ作るのに毎日細々とした作業を2~3時間やって、約1ヶ月。こんなのを何年もやってれば、そらカッターナイフの使い方に慣れますとも。(カッターは厚みのあるものを曲線で切るのが難しいという向きもありますが、カッターの種類を揃え、切り慣れれば曲線も切れるようになります)最初は私もセオリー通りに革包丁を使っていたのですね。が、革包丁は大変なんです。研磨が。革を裁断してると、刃物はすぐに切れ味が落ちます。ある程度までは青棒でその場で軽く研磨してごまかしながら使うのですが、毎日使ってれば定期的に砥石で研がないと切れ味をキープできません。砥石で研ぐには①荒いものから細かいものへ、砥石を2~3個②砥石自体の面も削れてくるので、砥石を砥いで平にする砥石とぎ③角度がうまく決まらない場合には(まあ、たいてい最初は決まりません)、角度を固定する包丁砥サポーターが必要で・・・下手すると砥ぎの道具だけで2万円くらいかかってしまいます。幸い家に砥石はあったので、最初は頑張って自分で研いだりしたんですが、簡単ではありません。まあ、簡単だったら、台所用品売り場に「簡単!包丁とぎ!」が売ってることもないし、スーパーで「研屋来店!包丁とぎます!」催事が行われることもないし、「砥師」というプロも必要ないでしょう。逆に言えば、専門のプロがいるくらいには刃物の研磨は難儀なことなのです。で、革包丁を使い始めて半年くらいたった時、砥ぎながらふと思ったんですね。私がしたいのは革でものを作ることで、包丁を砥ぐことじゃない砥いでる時間を、革ものづくりに使ったほうがよくない?そのころ、たまたまとある工房を覗いた時、プロの方が普通にカッターナイフで革を裁断してたのを見たこともあり、その思いに至った後は、割り切って革包丁をとぐのをやめて、使い慣れたカッターナイフを使うことにしました。切れ味悪くなったら、ポキッとやれば砥ぐ必要もなく、作業を中断することもなく、速攻で切れ味復活。快適です。ただ、革漉きだけはカッターナイフではうまくできません。なので、手漉きが必要な時は、漉き専用に作られた刃物で薄い1.5ミリ厚の革箆(今は入手困難)を使ってます。誤解しないでもらいたいのですが、革包丁を使うなと言ってるわけではありません。カッターナイフを使い慣れていない場合は、革包丁の方が使いやすいそうですし。(私はカッターを使い慣れちゃってたから公平な比較ができませんが、他の複数の方からそのように聞いてます)。何が言いたいのかというと、セオリーといわれているやり方は、あくまで一般論であって、必ずしも自分に当てはまるわけではないということです。レザークラフトではそういうことが非常に多いです。教本も教室も、盲信するのではなく、やりにくいと思ったら自分にあった方法を見つけて取り入れていくのが大事と思います。LeatherWorks幸守
2020年03月20日
閲覧総数 803
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- クリスマスの飾りつけ キャンドルス…
- (2025-11-26 07:39:45)
-
-
-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…
- 【11/28 09:59迄 半額】北海道加工 …
- (2025-11-27 15:44:50)
-
-
-

- コストコ行こうよ~♪
- 11月のコストコ 2回目♪
- (2025-11-25 21:32:39)
-







