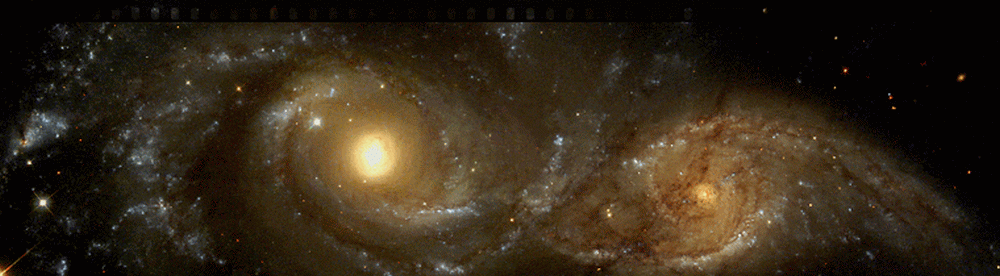-
1

感動実録!!奇跡3万キロの母子旅
昨日5月8日放送の奇跡体験!アンビリバボー はとても感動いたしました。感動実録!!奇跡3万キロの母子旅 99歳母の夢、チベット 孝行息子の決断 2008年5月8日放送感動実録!!奇跡3万キロの母子旅99歳母の夢、チベット 中国の最北端、中国黒龍江省塔河は発展が遅れ村人たちの生活は苦しかった。そこで細々と農業を営んでいた王一民(ワンイーミン)さん74歳は、99歳の母と二人暮らし。一民さんはしばらく他の土地に暮らしていたが妻を亡くし、父が亡くなり母が一人になったので一緒に暮らすようになったのだ。 足腰の弱くなった母は、この10年アパートの6階にある家から一歩も外に出ていなかった。思えば母は辺鄙な村で全てを犠牲にして生きてきた。一家は5人家族で、父親は小さな印刷所を経営しており家にはほとんど帰らなかった。苦しい生活の中、母は子供たちに少しでも栄養のあるものを食べさせようと毎日畑仕事の重労働をこなしてきた。 だが第二次大戦が終了し日本軍が撤退すると、共産党と国民党による激しい内戦が勃発し、やがて共産党が支配するようになると、父は国民党員だったというだけの理由で15年の獄中生活を強いられた。さらに一民さんは鉱山に追いやられ強制労働、家族はバラバラになってしまった。 ようやく鉱山から解放されたものの無一文の一民さんは農業で細々と暮らすしかなく、ようやく母と一緒に暮らすことができた頃には、元気だった頃の母に何もしてあげることができなかったことを悔いる日々だった。 母が元気なうちに何かしてやりたい、そう思っていた一民さんは、母の「この年までどこにも出かけられなかった。世の中はどんななんだろう?」という言葉であることを思いついた。母をリヤカーに乗せて自転車で引っぱり、世の中を思い切り見学する旅行に出かけようというのだ。 どこに行きたいか尋ねると、「チベットに行きたい」という。世界で一番標高が高いことから「天に最も近い場所」と言われるチベット高原。中でもチベット仏教の象徴であるポタラ宮があるラサは特に神聖な場所として中国国民の憧れの場所だ。しかし塔河からラサまで、人が歩ける道のりはおよそ1万キロ。74歳の老人がリヤカーをひいて行ける距離ではとうていなかった。 だが村から出たことのない母に地図を見せても縮尺が理解できず、「この道をずーっと行けば簡単じゃないか」「どうせならあちこち見て回ってからチベットに行こう」と喜ぶ姿に一民さんは無理だとは言えなかった。 チベットに行きたいという母の強い気持ちと喜ぶ顔に出発を決意した一民さんは、さっそく準備を始めた。自転車を改造し、母が乗れる荷台を設置した。荷台は母が横になれる程度にとどめ、四方に窓を大きくとった。2000年5月1日、二人はラサを目指して出発した。出発してほどなく、母は辺り一面に咲く菜の花畑に目を奪われた。10年ぶりの開放感だった。 二人の食事は完全に自給自足だった。所持金が少なかったため、外食などの無駄な出費は極力控えた。夜は野宿だったが、5月とはいえ夜になると氷点下になった。 塔河の町を過ぎるとでこぼこ道や坂が多くなり体力的に苦しくなった。母は無理をしすぎる息子を思いやり、「疲れたから少し休みたい」「急いで得することは何もないよ」と伝えた。二人にとって夢のような時間が流れた。 だがゆっくりしすぎるわけにはいかない。穏やかな春のうちに距離を稼ぎたかった。だが74歳の体は徐々に言うことをきかなくなっていた。次第に坂が多くなり、路面も悪化した。そしてついにリヤカーは一歩も前に進まなくなってしまった。 疲れ果てた一民さんが一人の村人を見つけ、どうか一晩だけ泊めて欲しいと言った時だった。村人はリヤカーに乗る母を見て「老人をこんなところに閉じ込めて旅をするなんて無茶だ」と腹を立ててその場を去ってしまった。母は一民さんに「人の言うことなんて気にしなくていい」と慰めた。二人の目の前には多くの困難が立ちはだかっていたのだ。 悪天候と路面の悪化でリヤカーが一歩も進まなくなると、一民さんはリヤカーに繋いでいたロープを肩にかけて引っ張り始めた。荷台の重さを上半身で支えることで手足への負担が軽くなって進むことができたのだ。 こうして長い坂道を乗り越えた。だがしばらくするとロープが肩に食い込み血が流れた。汗をかくと傷口にしみ込み激痛が走った。それでも一民さんは歩を進めた。 そんな時、中国では100歳まで生きる人は少ないため、母の年齢を聞いて会いたいと集まってくる人々が現れた。彼らは家に泊めてくれただけでなく、料理をふるまってもてなしてくれた。長生きしてまた寄ってください、という心温まる言葉を受け、一民さんは再び前に進んだ。 母の体力を考え、休憩をとりながらゆっくりと進んだ。一民さんはそのうち坂が苦にならなくなった。74歳にして足に筋肉がついたのだ。 出発してから1ヶ月。一民さんが地図で自分たちのいる場所を指すと「自分が生きているうちにチベットにたどり着けるのかい?」と母は高齢からくる死への不安をもらした。そこで一民さんはチベットにたどり着くことだけでなく、母に道中でも楽しんでもらおうと思いある場所を目指した。 それは海だった。山だらけの村から出たことのない母が初めて見る海。母は世界の広さを実感できたのだ。 中国きっての海岸リゾート地、秦皇島で静かな休暇を過ごそうとしていたところ、偶然二人の旅を知ったマスコミが殺到し、親子は一夜にして有名人になった。現代最高の親孝行と報道されたが、一民さんの「母との時間を無駄にしたくない」という意向から、取材は最小限にとどめられた。 スタートから4ヶ月、首都北京に入った。見るもの聞くもの全てが初めてのことばかりで、二人は北京での生活を満喫した。市内の観光名所を心ゆくまで母に見せてあげることができた。たまには美味しいものを食べさせたいと、一民さんは肉そばを1杯だけ注文し母に食べさせた。だが母は少ない肉をしきりに息子の口に運んで食べさせた。北京で楽しい思い出をつくり、数日後にふたたび走り出した。 いつしか季節は秋になっていたある日の朝。母のうなり声で目覚めた一民さんは、母が高熱を出していることに気づいた。だが一日中走っても医者どころか民家すら見つからない。一民さんの体力も限界に近づこうとしていた時、ようやく見つけた病院はすでに閉まっていたが必死に呼びかけると医師が出てきた。 「母を看てください」とやっと伝えると、一民さんもその場に倒れてしまった。 危険な状態だったが、医師が寝ずに看病してくれたお陰で母は朝には峠を越えていた。親子の旅をテレビで知っていた医師は親孝行の旅に感動していた。 だが母は数日間の入院が必要で、一民さんは今後の旅について考えざるを得なかった。 だが、母の体を心配して旅は無理ではないかと言う一民さんに「お前さえ大丈夫ならチベットに連れて行ってくれ。もう迷惑をかけるようなことはしない。頼むからチベット連れて行ってくれ。それまで死なないから」と母は答えた。もはやチベットへの旅は母の生きる糧になっていた。 退院の日、一民さんは医師にお金の相談をしようとした。すると医師は「70歳以上の老人は無料」と書かれた張り紙を指差した。だが一民さんは、その張り紙が昨日まではなかったことを知っていた。若くして両親を亡くし親孝行できなかった医師は、自分にできることをしようと思ったのだと話してくれた。人々の暖かさを痛感した出来事だった。 冬になり寒さが厳しくなると、一民さんはより温暖な南の観光地を巡りながら進み、春を待ってチベットを目指すことにした。母は元気を取り戻し、同郷の人が営む飲食店でふるさとの味を堪能した。お祭りがあると母が満足するまで見入った。 旅に出てから7ヶ月、上海に入った。民家に泊まったある日のこと、一民さんは母の大好物のうどんを作った。この日は母の100歳の誕生日だったのだ。 こうして上海で新年を迎えた頃、一民さんは取材の席で知り合った一人の紳士から「楽にチベットに行けると思うからエンジンをつけてあげたいのですがいかがですか?」と思わぬ言葉を聞かされた。 だが一民さんはエンジン音で母との会話がなくなることを恐れ、せっかくの申し出を断った。 続く
2008.05.09
閲覧総数 1001
-
2

感動実録!!奇跡3万キロの母子旅 2
続くから 上海から少し南の杭州では12世紀に活躍した有名な武将、岳飛の像を見物した。苦労した人生を取り戻すかのように、母は安らかな時間を過ごした。 リヤカーは険しい山道の続く福建省に入った。300キロの山道が続く難所で、距離を稼げずに春を迎え、塔河を出発して1年が過ぎ去った頃。元気だった母が目に見えて弱ってきた。その頃は中国の最南端である海南島に着く頃で、母は「地の果て(最南端)に天の先(チベット)、両方に行けるとは」と喜びを口にした。その数ヶ月後、親子はついに中国本土の縦断に成功したのだ。 だが母はこの頃、日中居眠りをすることが多くなっていた。食欲もほとんどなかった。病気ではなく、年齢からくる体力の衰えだった。 海南島からチベットのラサまでは5000キロ。これから道はさらに険しくなり、そこからまた故郷の塔河に帰るのに3年はかかる。母も故郷のことを口にすることが増えてきた。一民さんは、母は言い出した手前帰りたいと言えないだけではないのか、と思うようになっていた。 今から故郷を目指せば来年には帰ることができる。だがチベット行きをあれだけ楽しみにしていた母に旅の中止を告げたら、さらに元気をなくしてしまうのではないかとも心配した。一民さんは決断を迫られていた。 2008年5月8日放送感動実録!!奇跡3万キロの母子旅孝行息子の決断 故郷の塔河を出発して2年。母の願いを叶えるべくチベットへ向かうか、それとも体のことを考え引き返すか。一民さんは悩み抜いた末、故郷に戻る決断をした。そのまま戻ると気づかれるかもしれない、さらに帰り道でも新しい景色を楽しんでもらおうと行きとは違う道を選んだ。母をがっかりさせないよう、チベット行きを諦めたとは絶対口にしなかった。 母はその頃、何をするのもおっくうになった、そろそろ潮時かもしれない、と口にした。もう未練はないが、もう少しお前と生きていたい。そんな母の言葉に一民さんはひっそり涙を流しながら必死にペダルをこいだ。 だが思っていたよりも早く、母は道が違うのではないかという疑問を持ち始めた。長い旅で地域による民族の違いがわかるようになっていた母は、チベットに向かっていないのではないかと思ったのだ。 一民さんは覚悟を決めた。「今はチベットに向かっていません。母さんが行きたい所ならどこでも連れて行ってあげたかったのですが、行けない所もあったんです。許してください」。 母は「迷惑をかけると知らずに無理を言った自分が悪かった」と一民さんに謝った。いろんな所を見物できただけで十分楽しかった、これ以上望んだらバチが当ると言った。 真実を告げて心の重しは取れた。しかし握りしめた母のその手は出発前に比べて小さくなっていた。一民さんは涙を止めることができなかった。残された時間は少ないと思われたが、どんなに急いでもふるさとに戻るには1年はかかる。 チベット行きを諦めて故郷に戻る道中、チンタオで取材を受けた時のことだった。記者が、母との旅は十分したのだからもう止めて、自分も北に用事があるので一緒に飛行機で帰らないか、と提案した。 一民さんは最後の決断を下した。母に「もう旅をおしまいにしよう」と告げた。母ももう元気はないからと納得した。2002年冬、二人の旅は幕を閉じた。走行日数900日、走行距離2万キロにも及んだ。リヤカーはチンタオから運んでもらうことにし、飛行機と電車で塔河に向かった。 故郷に戻った当初は元気だった母も年が変わった2003年、102歳になった頃から少しずつ衰え、数ヶ月後、ハルビンの病院に入院した。そして意識を失ったり取り戻したりを繰り返し、うわごとで「チベットはまだかい」「旅が一生の中で一番楽しかった。ありがとう」と言いながら、103歳の誕生日の2日前、息を引き取った。 一人になった一民さんは母を失ったショックで憔悴しきり、食事も喉を通らず酒ばかりあおる日々を送った。生きる希望を失っていた一民さんはある日目覚めると、突然現れた母に「酒はもう止めなさい」と叱られた。そして「お腹が空いた」と言われて好物のうどんを作り、あの旅を思い出すかのように二人で一緒に食べた。 ふと気づくと、どこまでが幻でどこまでが夢だかはわからなかったが、しっかりうどんを食べていたことは現実だった。天国に行ってなお自分を気遣ってくれる母に自分は何もしてやれないのかと思った一民さんは、また旅に出ることにした。 一民さんは母の遺骨と二人分の食料を荷台に乗せて再びリヤカーを漕ぎだした。目指すチベットまではおよそ1万キロ。しかし中国では遺骨を他人の家に入れてはいけないしきたりがあるため、以前のように民家の世話になることができなかった。3日に一度は栄養剤を飲み自分のペースでゆっくり進んだ。 だが、北京を過ぎた山道で脱水症状により倒れてしまった一民さん。通りかかったトラックに発見され病院に運び込まれると、医師にはこの先は無理だと告げられた。高度が上がり空気が薄くなるため、老人がリヤカーでチベットまで行くのは不可能だというのだ。 だが、西安までは空気も大丈夫だしリヤカーでもよいが、西安に着いたら交通局を訪ねるようにと言った。医師の友人が力になってくれるはずだという。 自分がチベットに向かう途中で倒れたら母はもっと悲しむだろう。一民さんは2週間で西安に着くと医師の友人を交通局に訪ねた。庭に案内されると、そこにあったのは巨大なエンジン付きのリヤカーだった。飛行機ではなくどうしてもリヤカーで行きたいという一民さんの気持ちを尊重したプレゼントだった。 中国全土が彼の母を思う気持ちを応援していた。一民さんはその暖かい配慮を背に、母の遺骨を乗せてチベットに向かった。そして母と旅を始めてから5年、全行程は3万キロを越え、ついに念願のチベット・ラサに到着した。そこにそびえるポタラ宮で母との最後の別れの祈りを捧げた。人生で一番楽しかった、ありがとう、と一民さんは言った。まさに母の臨終の言葉と同じだった。 一民さんはこの旅を終え、2年前に脳梗塞を患い多少の言葉の障害が残ったものの、現在は介護施設で元気に生活している。 今でも思い出すのは母との旅。取材で一民さんは、「坂に苦労していると、いつも母は自分も手伝えないかと声をかけてきた。母はいつでも子供のこと優先なんです」と笑いながら答えた。 一方で母も旅での心中を「息子に苦労させるのが切なかった。荷台に座ってどれだけ涙を流したか。うちの子は本当に孝行者です」と話していた。
2008.05.09
閲覧総数 243
-
3

アグネス・チャンや黒柳徹子の関わってる日本ユニセフやユニセフには絶対募金しないでください!!!
アグネス・チャンや黒柳徹子の関わってる日本ユニセフやユニセフには絶対募金しないでください!!!ユニセフと黒柳徹子のあやしい関係http://blog.goo.ne.jp/hienkouhou/e/846ae5244903efb3c5cab852ee3ef3a9上記のページのコメントも読んで見てください。2006年12月18日 日本ユニセフの募金の箱を飲食店とか会社の社員食堂とかで散見する。以前、知人とあの箱からゼニをくすねたら犯罪になるのだろうか、と言って笑ったことがあった。むろん冗談であるが…、しかし個人で募金箱内のゼニを失敬すれば犯罪であっても、これが組織的に行われているとなると、犯罪ではなくなる不思議がある。 先日も新聞5段の広告で、ユニセフだか日本ユニセフだかが募金を訴えていた。 「みなさまのご支援で、大切な子どもの命を守るために、例えば次のような活動できます。1. 3000円で---栄養不良を改善し、はしかなど子どもの命を奪う感染症にかかりにくくするビタミンAを688人の子どもに1年間投与できます。2. 5000円で---子どもが蚊にさされてマラリアにかからないよう、殺虫剤を施した蚊帳を子どものいる家庭8軒に届けることができます。3. 10000円で---6つの感染症(はしか、ポリオ、結核、百日咳、ジフテリア)の予防接種を5人の子どもに施すことができます。」などとある。すべて援助が製薬会社がもうかるように誘導しているのが笑える。 この広告には、老いたるオードリー・ヘップバーンが慈愛に満ちた表情でアフリカの幼児を抱いている写真が載っている。 ユニセフは3000円募金するとこんな援助ができ…とカネを無心しているが、こんなことは例によって大ウソである。 『援助貴族は貧困に巣喰う』(グレアム・ハンコック著 朝日新聞社)という本があって、ユニセフにかぎらず国連付属の国際組織の実態が見事に暴かれている。朝日新聞は、新聞はボロだが書籍にはたまにいい本を出版する。これは褒めていい。 題名からは何のことかわかりにくいけれど、「援助貴族」とは、ユニセフとか、ユネスコ、WHO、IMFなどなど無数にある国連付属機関に関わる偉いさんから末端職員までの人間を指している。彼らがアフリカその他貧困にあえぐ人々を食い物にして「貴族」なみの豪奢な生活を送っていることを言っている。 日本人を含めて地球の北側の“裕福な”国民が、善意の寄付と税金を注いで貧しい人を援助しようとする、その莫大なカネを、彼ら国連付属機関の「援助貴族」どもが巻き上げるのである。その結果、南の貧しい人々をますます貧困に追い込んでいるという、恐るべきメカニズムをこの本は告発している。 ざっくりと説明すれば、例えばあなたが善意でユニセフにポンと1万円を寄付したとする。さて、そのうちいったいいくらが本当に貧困で苦しむ人の手に渡るか、ご存知かな? ま、1000円分も届けられればかなり良いほうである。まずほとんど届かないと思っていい。ユニセフが「活動資金」としてガッポリ横取りする。偉いさんたちは、国際会議と称してパリやニューヨークにしょっちゅう出張するが、その飛行機のファーストクラス代金は、あなたの善意のカネから使われる。世界各地の暮らしやすい都市に事務所を構え、その家賃も潤沢な善意の寄金からいただく。 残りの寄付金を形ばかり現地アフリカの国に持っていくとする。ところがそういう国はほとんどが、首長が独裁者であって、そこでまたガッポリ独裁者のふところに入ってしまう。さらに待ち構えているのが、欧米の企業群である。先の「3000円で何ができるか…」にあるように、薬品や食糧にバケるのであるが、そこにビジネスが発生する。薬品会社や食糧品会社が、その援助資金と自社製品を交換するのである。 例えば某アフリカの国でマラリアの薬が必要だとして、その必要な薬ではなく、製薬会社や食品会社が売りたい薬商品(多くは賞味期限切れの)を、某国に売るのである。だからマラリアの薬が望まれているのに、どういうわけか幼児に避妊薬が配られたりするのだ。 ユニセフなどは、個人や企業の寄金だけでまかなっているのではない。日本なら日本の国民の税金からも、なんだかんだで巻き上げている。それに、災害があると顕著だが、募金の主体になるのは赤十字以外ではマスメディアである。津波、地震、台風の被害、あるいは歳末募金とかだとマスメディアに募金が集められる。マスコミは何度も書くが、すべてユダヤ=イルミナティの走狗なのだから、こういう「援助ビジネス」に上手に使われるのである。 いずれ彼ら「援助貴族」どもの犯罪を取り上げようかろ思うが、要するに、ユニセフとか赤十字とかの寄付とは、はじめから欧米の「援助貴族」どもが裕福に暮らすために考えられた仕組みなのであって、善意のかけらもない。 しかしそれにつけても、マスコミはこういう国連機関の破廉恥な実態を知っていながらいっさい報道しない。それは彼らも「お仲間」だからである。 話は飛ぶが、せんだって、黒柳徹子司会のテレビ番組『徹子の部屋』がなんと30年に達したとか、話題になっていた。黒柳徹子は、もう70を超えてなお現役でテレビに出ているけれど、昔は本職は女優であったはずだが、今は映画にも舞台にも立っていないようだが、それでもあのような番組がつづくのが不思議である。 年配の人は覚えているだろうが、昔テレビがモノクロの時代に長寿番組に「兼高かおる、世界の旅」があった。兼高かおるが、世界中を旅して、それをテレビ(たしか日曜朝だった)で見せる趣向であった。あれも非常な長寿番組だった。そこが黒柳徹子の場合とよく似ている。 本ブログ「ユダヤ人基礎講座」でちらっと触れたが、兼高と黒柳はともに、東京品川区にある香蘭女学院の出身である。香蘭女学院は日本聖公会を母胎にしている学校法人であり、日本の聖公会は英国国教会の出先機関である。日本聖公会はだからフリーメースンと一体と考えてよい。 日本聖公会は、教育機関としては立教大学、立教女学院、 桃山学院、 神戸松蔭女子学院大学、プール学院や聖路加病院などを手掛けてきた。従って、フリーメースンはこれと見込んだ子どもをこうした学校に入れていわば英才教育を施すのだろう。 黒柳はユニセフ大使とかで世界を歩きまわっている。兼高と同様フリーメースンの組織的援助ないし指示命令で動いたと考えられる。 『援助貴族は貧困に巣喰う』には日本人ジャーナリストの座談会が掲載されていて、黒柳徹子とおぼしき人物についてその活動の様子が暴露されている。貧困国に「あるとびきり有名なタレントが来た」というのだ。そのタレントは、首都のホテルにドンと居座っていて、貧困うずまく難民キャンプなんかには出向かない。 機関の職員が適当な、写真撮影に適した場所を探しだし、そこへ「有名タレント」を車や飛行機でお連れする。そこで、例えば結核病棟に行って、瘠せほそった子どもを抱いた写真を撮り、いくらかの鉛筆なんかのプレゼントを子どもたちに配って、そうそうに立ち去る。そのときの写真が、ユニセフだか日本ユニセフだかの宣伝に使われるのである。 黒柳徹子で不思議なのは、彼女が貧困と疫病の難民キャンプに行きながら、あの妙ちくりんな(やたらに手のかかりそうな)髪型をしたまま、実にこぎれいな格好で、塗りたくった厚化粧で写真に収まっていることなのだ。お姫さまのような旅行をしてきて、ちょっと難民の子に触って、ギャラをもらって帰るという様子以外に考えられない。難民キャンプや結核病棟ならば、そんな銀座を歩くようなきれいな髪をセットして、1センチの厚さはあろうかという白粉を顔にまぶして、しゃれた服なんかで行けるはずがない。ユニセフ親善大使なんて笑わせるな。しかもそれを「お仲間」のマスメディアが、テレビのニュースで放映する。ひどく場違いな黒柳を映しだしてくれるから、カラクリを知ることができるが…。 冒頭に紹介したヘップバーンもおおかたそうやって、宣伝用に連れていかれて、写真に収まったのだろう。国連付属機関はそのように、世界の有名人を使って宣伝する。それにアホな大衆が騙されて、寄付をする。黒柳さんがあんなに熱心にやっているのだから、少しは寄付しなくちゃ、という気分にさせられる。そういうビジネスを「援助貴族」がやっているのである。だから、ユニセフも黒柳もみんなビジネスでやっていることなのだ。
2011.03.15
閲覧総数 2372