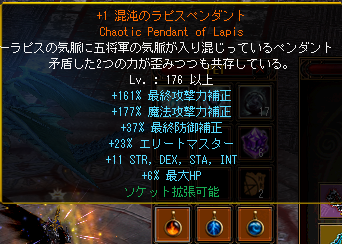novel> 夜を走る。
気がつけば、お父さんは一升瓶を枕にして眠る人だった。それが私にとって当たり前のことだったので、世の父親と云う者は、酒をあおって一日を過ごすものだと思い込んでいた。
世の中に母親と云う存在があることは知っていた。お父さんは母親のことを死んだと云っていたけれども、我が家にその存在がないことには疑問も抱かなかった。
きっと、私の家庭は変わっていたのだろう。そうして、それが私の日常だったのだ。
私にはお兄ちゃんがいる。無口で、けれども友達の多いお兄ちゃんだ。お兄ちゃんはいつも私に優しくて、いつも傍にいてくれた。
親の代わりに祭に連れて行ってくれたり、色んな面倒をみてくれた。そんなお兄ちゃんが私は好きだった。
朝、目が覚めると窓の外は暑い陽射しだった。私はむくりと起き上がり、顔を洗いに階下に降りた。
「お兄ちゃん。」
お兄ちゃんが先に洗面所に立っていて、歯を磨いていた。お兄ちゃんは私を一瞥するとまた鏡に向かった。
「もうすぐ夏休みね。」
「……。」
「高校生の夏休みってうちらのより少し早いんだよね。」
……。
「いいなあ。」
いつも私達の会話はこんなものだった。私が話し掛けても、お兄ちゃんは黙ったまま。けれども決してお兄ちゃんは話を聞いていないわけでもなく、これが当たり前のことだったのだ。
朝食もとらずに、私は髪の毛を二つに束ね、制服に着替えた。居間には、お父さんがいつものように焼酎の瓶を枕にしていびきをかいている。畳やテーブルの上にはだいぶ前から散乱しているビールの空き缶や、酒の一升瓶が林立していて、つけっぱなしの灯りに反射しててかてかと輝いていた。空気が重く、湿っていて、かすかなアルコールのにおいに鼻の奥が痛くなる。
「お父さん、風邪引くよ。」
私がそう云ってもお父さんは反応を見せない。時折寝返りを打つだけで、いびきだけがうるさく居間の中で響いていた。
「やめとけよ。」
部屋に入ってきたお兄ちゃんが、後ろからそう云った。お兄ちゃんは不機嫌な顔つきで、お父さんを睨み付けていた。お父さんはそんな二人に気付きもせず、眠り続けていた。お兄ちゃんは振り返り、居間を出る際に舌打ちすると、学校へ行ってしまった。
私は取り残されたような気持ちだった。それでも鞄を握りしめると、ドアを開け、家を出た。湿った風が頬に触れた。
学校を終えて帰宅すると、居間の方からテレビの音が聞こえてくる。きっとお父さんがいつものように酒をあおりながら見るともなしに見ているのだろう。私が小さく「ただいま」と云って自分の部屋へ上がろうとすると、お父さんは私の帰宅に気付いていたらしく、
「杪、来い。」
そう奥から聞こえた。
たまにあること。私はたまに、お父さんを包み込まなければならなかった。それがなにか、だいたい知っていた。そうしてそれがどうして、私なのか分からなかった。
きっと、お母さんの代わりなのだろう。
痛みは消え、溶かされていく。お父さんは子供に戻り、甘い一滴を零し、私は母親となり、子供を受け入れる。
「きっと、甘えたい年頃なのよ。」
近所に住む叔母さんはいい人で、ちょくちょく我が家の様子を見に来てくれた。母親のいない私達を心配しているのだろう。その度に芋の煮ころがしや、野菜のたっぷり入ったシチューを持ってきてくれた。お父さんはその時だけは「普通」の父親のように、叔母さんに接していた。
「いつもすいません。助かります。」
お父さんが云う。とびっきりの笑顔。酒臭い体を隠すように小さくなる様は、気の弱い感じに見えた。叔母さんはいつもの笑い声をあげながら、「いいのよ。いっぱい作り過ぎちゃうし。」と今日は焼き魚を、ちょうど三人分持ってきてくれた。
「そう云えば、あの子たち、もうすぐ夏休みね。うちの子ったらアメリカにホームステイするって聞かないの。で、結局来月から行くことになっちゃって。」
「それは立派なことで。世界に興味を示すことは良いことですよ。」
「そんな、もう。こっちもお金かかってしょうがないわよ。」
叔母さんは大袈裟に困った、という顔をしてみせた。傍にいた私は二人のやり取りを見ながらこの時が一番落ち着く時だ、と思う。叔母さんのいる時は世間一般の父親に戻る。私はその時の背中だけを見て、ある程度まともな人間に育つことが出来たのだ。後の父親は、抜け殻だ。
叔母さんが帰ると、お父さんは居間に戻り、また一升瓶の蓋をあけた。
「杪、魚もらったぞ。」
家のことは殆ど私が受け持っていた。洗濯も、食事も私がやっていた。お兄ちゃんは帰りが遅いし、たまにいても部屋にこもりっきりで、この何年間は一緒に食卓を囲んだことなどなかった。
「まだあたたかいな。」
お父さんは酒の肴に焼き魚をつまむ。私は焼き魚をおかずに、一昨日からジャーに入りっぱなしの灰色の御飯を食べる。
「もうすぐ、夏休みだな。」
「うん。」
「なにか予定はあるのか。」
「なにも。」
「そうか。」
「うん。」
………。
「杪、」
「なに」
「お父さんのことダメだと思うか。」
「ダメだと思う。」
「そうか。」
焼き魚はあたたかくて、やたら小骨が多かった。皮はこんがりとこげ色で、口に入れるとぱりぱりと香ばしかった。
お父さんは黙って酒を口にして、やたらうるさいだけのテレビを見ていた。
「旨いな。」
ぽつり、お父さんが呟く。
「旨いね。」
私が答える。
食卓の上には、焼き魚が一匹、残っていた。
夏休みに入って、私達は家の中でぼうっと過ごす毎日が続いた。それぞれがそれぞれの部屋で本を呼んだり、音楽を聴いたり、酒を呑んだり、変わりのない毎日だった。その日も布団の上で去年買った雑誌に読み飽きて、ぼうっと天井を眺めていた。
「あきた。」
私は立ち上がり、背伸びをすると、するすると部屋を出て、階段を降りる。玄関には靴を履きかけのお兄ちゃんがいた。
「お兄ちゃん、」
お兄ちゃんは私の方を振り返った。
「どこか行くの?」
「散歩。」
お兄ちゃんがそう言い捨てて、ドアをあけ、外へ出るのを追うように、
「私も行く。」
靴を履いて玄関を飛び出た。
外は蝉の声でうるさく、鋪装された道路からじりじりと熱が沸き上がってくる。お兄ちゃんはもう先を行っていて、私は小走りに追いかけながら、うるさい髪の毛を持っていた輪ゴムで一つに縛った。
「どこへいくの?」
「散歩だから分からない。」
お兄ちゃんは妹のことなど気にとめることなく、自分の足取りで両脇を民家や商店で挟まれた道を歩いた。
通りは午後の暑さにゆるんでいて、行き交う人々もだるそうに流れる汗を拭いていたりする。お店を営む人は客なみ少ない時間帯に煙草をふかし、込む時間までをだらだらと待ち望んでいた。
だらだらの坂道を登る。電信柱が坂の頂上まで連なり、自転車が空の青の中を横切っていく。私達は軽く汗を流しながら、通りを歩いてゆく。
「お兄ちゃん、あっち。」
私はお兄ちゃんを呼び止め、角の方を指差した。その奥は、電信柱の頭と木々の緑の景色が民家に挟まれた狭い路地に縁取られていて、背景には大きなビルと工場がそびえていた。向こう側は坂になっているらしい。ここよりも地面の高さが低いのだ。
「こんなところ、あったんだ。」
私はため息をつくように呟き、「行ってみようよ。」とお兄ちゃんの腕を引っ張った。
そこは坂道ではなく、階段があった。一段下の風景は乏しいくせに広大で、階下から延びる道が遠く知らないところまで続いていた。
「降りてみよ。」
私はお兄ちゃんの腕を引っ張りながら鉄で作られた階段を一段一段降りていった。一つ降りるとカツーンカツーン、もひとつ降りるとカツカツーン、さらに降りるとカカツーン。二人の足音が響く。引っ張られていたお兄ちゃんはさり気なく私の手を振りほどき、横一列になって歩く。漸く階段を降りると、大地の下の街角は、ありふれた知らない場所だった。私達は暫くその場に佇み、木々からこもれ出る陽の光や、誰かの生活のにおいのする家々を眺めまわしたりした。玄関先で自転車が寝転んでいたり、まるまる太ったぶち猫が塀の上を歩いている。ひとつ低い大地に降りただけなのに、肌に感じる温度が違っていた。暑いと云うよりも、寒いと云うよりも、むずがゆい。空気がとげになって私の体中をちくちくと刺すのだ。それは私の体温が変わったからなのだろうか。
やがてお兄ちゃんが足を進めた。私は兄の背中を追うようについていった。
「お兄ちゃん、道知ってるの?」
……。
「戻り方ちゃんと覚えてる?」
……。
お兄ちゃんは黙って歩き続ける。
何ケ所か角を曲がり、のろのろと犬が横切るのを見送って、似たような街並を進み行くにつれて、私はここが今、あの階段からどのくらい離れているかも分からなくなった。しかし、それでもお兄ちゃんについていくと、やがて目の前に大きな廃工場が建っていた。
全体的に薄暗く、雑草がセメントの割れ目からところどころ伸びている。私達はゆっくりと工場の中に入った。
中はさらに薄暗く、割れた窓から陽の光が眩しくこぼれ落ちているだけで、風が吹いているらしく、トタンの打つ音が響いていた。
歩くと、足と地面の擦れるのが聞こえてくる。かつてここが、何の工場だったのか分からない程何もなくて、広い空間は、長い間誰も寄せつけなかったように思われた。
「すごいね。」
私はこんなにも広くて暗い場所を見たことがなかった。
「ほら、あそこにドアがある。」
そう云って指差したのは私達が入ってきたところとは反対側のドアだった。先刻の入口側が正面だとしたら、こちらは裏口と云うところだろう。私達はそのドアを開けて外に出た。
「バスだ。」
お兄ちゃんが最初に呟いた。雑草の生い茂る中に小さな観光用らしきバスが置かれていたのだ。雨風にさらされて、ところどころ錆がきているが、窓ガラスは割れておらず、まだ走りそうな気さえした。お兄ちゃんはバスのドアに手をかけ、思いっきり力を込めて引いてみた。隙間に長い間雨水が入り込んでいたらしく、錆び付いたドアは重そうにガリガリ音をたててゆっくりと開いた。
中に入るとむっとした空気が私の体にまとわりついてきた。外よりも蒸し暑い。だらだらと流れていた汗は一気に溢れだし、肌着の感触が気持ち悪かった。中は普通に街を走るバスと変わりはなく、ただ座席がはずされて、あちらこちらといろんな方向を向いていた。
お兄ちゃんは、窓をひとつひとつ開けてまわり、外の自然な空気が風となって汗ばんだ私の腕を撫でていった。
「すごいね。」
私は独り言のように呟いて、バスの中を見回す。大きなハンドルのある運転席。低い天井。窓の景色。
「このバスも走っていたんだよね。」
お兄ちゃんは窓を全て開けると、座席に目をつけ、動かしはじめた。暫くすると座席がくっついて、結構な大きさのベッドが出来上がった。お兄ちゃんはベッドの完成を見て、息を弾ませながら私の方を向いた。
「ここを、俺達の部屋にしよう。」
そう云った。
私は頷いた。
◆
バスの中を掃除して、残った座席でベッドを組み、いらない布団を運び込み、雑誌やお気に入りの小物を持ち込んで、最後にお兄ちゃんが小さなラジカセを持ってくると、バスは二人の部屋になった。さっそくベッドに横になる。かたくて、眠りにくい。けれどもその感触は不思議に嬉しさを込み上げさせた。
「私の新しい部屋。新しいベッド。新しい天井。初めまして、こんにちは。私、杪っていいます。」
ひとり呟いて、微笑む。バスはクラクションも鳴らすことが出来ず、静かにその場にあるだけだった。お兄ちゃんはバスの中を見回したり、外に出てバスの周りをうろちょろしたり、かと思うとまた中に入って雑に置かれた雑誌を眺めたりした。
窓から風が吹き込んでくる。蒸し暑い部屋の中が少しだけ柔らかくなる。
「杪、これ見つけてきた。」
外に出ていたお兄ちゃんが手に何かをさげて入ってきた。
「こいつでバスに絵を描こう。」
お兄ちゃんの持ってきたペンキは水色で、他にも色がたくさんあったことを告げると、寝転がっている私の頭の隣に紙を広げ、床に坐ると、鉛筆を走らせはじめた。
「なにしてるの?」
「デザイン。」
お兄ちゃんはちょっとした絵描きだった。幼い頃からよく賞を取ってきては隣の叔母さんに誉められた。鉛筆を持つその姿に表情はないけれど、活き活きと右の手が動いて、すぐに絵が描き上がった。
奇妙な笑みを浮かべた三日月が足を生やして、おでこについている灯りをたよりに走っている。その向かう先には目を大きく見開いた太陽が浮かんでいた。
「おかしな絵。」
私はそのままの感想を口にした。
「太陽に近づけば光に呑まれて見えなくなってしまうのに、月は夜を走っているんだよ。」
お兄ちゃんは呟いて、鉛筆を投げ捨てた。
赤や黄色や青、緑。バスはきっと素敵な色に染まるだろう。
暇があれば私達はバスに行って絵を描いた。お父さんは相変わらず居間で酒をあおって二人のことに殆ど感心を示さなかった。ただお兄ちゃんがふと外出する時、私はお父さんを包み込まなければならなかった、それだけだ。
太陽の輪郭を描き、赤で染め上げる。何かをくり抜いたような大きな目からは、黒いペンキが垂れ、はっきりとした目玉は私を貫く視線だった。
「そんなに見つめても私には何もないのよ。」
そう云って笑うと、はけを持ったお兄ちゃんは舌打ちをしながらも色を塗り続けるのだった。
その日は夕方から近所で祭があって、部屋の窓から微かな下駄の音が響いてきた。東の空もうっすらと赤くなっていて、賑やかな雰囲気が伝わってきた。
叔母さんがやってきた。「今日、お祭りでしょう?浴衣持ってきたのよ。私のお古だけど。」
叔母さんはそう云って、家に上がると、真直ぐ私の部屋に行き、着せてくれた。お父さんはさぞびっくりしただろう。居間に叔母さんが入ってきたら、即アウト。散乱したアルコールの空き缶が叔母さんの目に飛び込んで大騒ぎだったろう。
叔母さんが持ってきてくれたのは、紺地に蝶模様の、帯の色紅く鮮やかなものだった。「素敵でしょう。」と叔母さんが微笑む。肌着を脱いで、袖に腕を通す。さらさらの感触が心地よい。暫くして、漸く浴衣に着替え終えたとき、お父さんが部屋の扉をノックして入ってきた。
「いつもすみません。」
お父さんは苦笑いを浮かべ、そう云った。
「いいのよう。うち男ばっかりだし、誰かに着てもらう方がいいでしょう?」
叔母さんは大きく笑うと、
「けど、本当、似合うわねえ。」
しみじみ呟いた。
叔母さんが帰ると、私は浴衣の感触に嬉しくなって、外に出た。祭に向かう人々がアスファルトに擦れる足音を立てている。私はひとつにまとめ、お団子にしてもらった髪の毛をいじりながら、祭のある神社の鳥居をくぐった。
雑踏、甘い焼きりんごのにおい。遠くで聞こえる鈴の音。本堂へ通じる小路の両脇は眩しい灯りを放つ夜店で固められている。その間を人々が様々な表情を浮かべて行き来している。私はとりあえず本堂にお参りしようと人込みを縫って小路を進んでいった。
五円玉の転がる音。鈴を振って、両の手たたいて掌を合わせる。何を願うでもなく、そう教えられてきたことをそのままやった。神様を怒らせないように、丁寧に、私が憎まれないように。
振り返り、賑やかな小路へと引き返す。叔母さんが握らせてくれた千円札でなにかやろう、とうろうろしていると、学校のクラスメートなんかが声をかけてくる。
「杪じゃないの。久しぶり。」
「全然夏会わないけど変わってないわね。」
そうやって笑顔をこぼすクラスメート達は誰もが誰かと一緒で、洗い髪に浴衣姿でみんなかわいかった。家族でやってきている子もいて、ひとりなのは私とさっきすれ違った中年の男ぐらいだった。
そういえば今年の夏、誰の家にも遊びに行ってない。
もともとお酒に溺れていたお父さんが私に包み込まれるようになった昨年の暮れから、私はどうも変わったらしい。けれど、別にそれがどうしたと云うのだろう。私は私でしかいられないのだ。私は、杪なんだ。
かわいい、鮮やかな色のヨーヨー釣りに目を引かれて、二百円を支払いやってみた。ピンクに黄色の渦がデザインされているヨーヨーを釣り上げる。店の兄さんが「お、やったな、嬢ちゃん。」と釣り上げたヨーヨーの水滴を拭き取って手渡した。
ヨーヨーをぱとぱとやりながら小路を歩く。他になにをやろうか、と歩きながら考えていると、鳥居の方からお兄ちゃんがやってくるのが見えた。お兄ちゃんの周りには三、四人の友達らしい人がいて、お兄ちゃんもその人たちの話に少し笑みを浮かべていた。
私とお兄ちゃんの距離がだいぶ近づいたところで、私に気付いたお兄ちゃんは、軽く私を見下ろしただけですれ違って行った。人込みの中でその集団はなぜか際立って見えて、私は彼等のあとを追いかけてみることにした。
あれこれと夜店を覗いては、イカやたこ焼きを買って頬張っている。友達の多いお兄ちゃん。これまでもこういう風景を見たことがあったが、本当にお兄ちゃんが出かけるときは誰かがいる。
「あっ。」
ふと目を離した瞬間、お兄ちゃん達が他の集団ともめていた。何か言い掛かりをつけられているようで、髪の毛を染めた集団の人達はお兄ちゃん達を引っ張っていった。私もついて行く。二つのグループは神社の裏側、人気のないところにやってきて、言い掛かりの続きをやりはじめた。建物の影からその様子を見ている私には、やはり何を云っているか分からない。やり取りはエスカレートして、ついに金髪の男がお兄ちゃんの仲間に殴り掛かってきた。体が地面に転がる。それを皮切りに男達はそれぞれの拳を出し合った。私は浴衣の襟を握りしめて、そこから前にも後にも動けずに、固唾を呑むばかりだった。
お兄ちゃんに男が殴り掛かる。それをかわすと、お兄ちゃんは右の拳繰り出して腹部に打ち込んだ。男がうめき声をあげて膝をつく。お兄ちゃんはその頭に蹴りいれて、地面に倒れた男の髪を握って持ち上げると、何度も腹に拳を打ち込んだ。何度も、何度も何度も何度も。男は完全に倒れ込む。
髪の毛を染めた男達は、辛そうな顔をしながらその場を走り去ると、お兄ちゃん達は嬉しそうに笑い声を上げながら、一番活躍したお兄ちゃんの肩をたたいたり、揺さぶったりして誉めたたえた。お兄ちゃんはあまり嬉しそうでもなく彼等の礼讃に笑みを浮かべていた。
「お兄ちゃんの、知らない顔。」
そのまま家に戻って部屋に行き、開け放した窓際に座り込んだ。生ぬるい風が入り込んで重いカーテンが揺れる。もうすぐ花火があの家の屋根から打上がって来るだろう。
お兄ちゃんの知らない顔。絵を描く掌が拳を作る。鋭い眼。何が厭なのか分からないけれど、何かが厭だった。
でも誰にも見せてない部分なんて私にも、叔母さんにもあるんだろう。みんな持っているんだ。気付かないだけで、お父さんにだって。 そう、きっと。
だから、気にすることなんてないんだ。
花火が打上がる。あの屋根の上にきれいな大輪が花開くと、続けて小さな花々が紫色の背景に一斉に描かれた。空を裂く音が鼓膜を揺さぶる。私は赤や、黄色や青の光に魅入られて、窓から吹く風に頬をさらしていた。
「杪、いるのか?」
お父さんが私の返事も待たず、ドアをあけた。私はちらりと振り向いて、お父さんの手にビールの缶が握られているのを見ると、戻す視線はまた花火の大輪だった。お父さんは私の傍に坐り、同じように空を眺めているようだった。
「きれいだな。」
「そうね。」
お父さんの手が、浴衣越しの肩に触れる。そのままお父さんは、そろそろと私のうなじを撫で、優しく押し倒した。私はされるがままに、息をとめて、襟を開く力はお父さんの温度を保って、私を剥き出しにしようとした。
白くて、赤い。
私のへこんだ胸は、お父さんのおしゃぶりで、衣擦れの音は、眠れる赤ん坊の子守唄だった。そうしてやがて私は子守唄になった。お父さんを包み込むための、子守唄。入ってくる。
「なにやってるのっ。なになになにっやってるのっ。」
突然の声は叔母さんだった。お父さんは雫をこぼし損ねて、私の中で涙を吹き上げた。そのまま青い顔で、叔母さんに対して小さくなって、子供のままだった。私ははだけた細い体につうっと落ちる感情を抑え、目を見開いて私達を見る叔母さんの視線に耐えるだけだった。
叔母さんはその日、我が家の惨状を全て目にして、洋服に着替えさせられた私を抱きしめた。
「かわいそう、かわいそうに。あんなひどい目に遭っていたなんて。いつもあんなことされていたんでしょう?本当のお父さんにあんなことされて、かわいそうに。」
そうして坐り込んで俯いたお父さんを睨むのだった。
アルコール臭い居間では、麒麟が朝日に向かって転がっている。札幌をひと越え、麒麟は朝日に辿り着く前に八海山にぶつかり足取りをとめた。どこからやって来たのだろう、百年の孤独が私達を見つめていた。
叔母さんがかぶせてくれた毛布の上で、野うさぎが走っている。
お父さんは居間に染み付いたお酒のにおいに、いいわけもできる筈がなく、うなだれているばかり。どやどやと我が家に入り込んでくる叔母さん一家の軽蔑の目が注がれる。瓶やら空き缶やらで囲まれたお父さんのお城は一瞬にして潰されたのだった。
◆
お父さんは叔母さんの粋な計らいで、アルコール中毒患者を更生させる施設に送られることになった。そのおかげで私達兄弟は、施設に入れられる始末だった。
お兄ちゃんがあの事件を知ったのは、その翌日、家に帰ってからのことで、少しだけ不機嫌に、舌打ちをすると部屋にこもってしまった。
叔母さんは、そんなお兄ちゃんを部屋から出そうとする。
「元君、出て来なさいよ。あなたが辛いのはよく分かるわ。こんな状況下で文句も云わずずっと耐えて来たんでしょう?叔母さんにも辛い気持ち、分かるわ。元君や、杪ちゃん程じゃないけれど。でもね、出て来て話さなきゃならないの。杪ちゃんとお父さんの、その、関係と云うか。そう、他にもお父さんと話し合わないといけないと思うの。元君はもうしっかりと物事が理解できる歳なんだから。叔母さんはね、家族が一番大切だと思うの。なんでも語れる、心から信じあえるのはやっぱり家族なのよ。帰れる場所はここしかないのよ。離れちゃいけないの。これから本当の家族ができるために話し合いましょう。ね?ね?ね?」
叔母さんの言葉は階下にいる私にも聞こえるくらいなのに、お兄ちゃんは洞窟に閉じこもった神様だった。でも、神様は何もしてくれない。叔母さんの必死な声はどこか滑稽で笑みをもらし、脱ぎ捨てられた浴衣はしっとりと濡れていた。
怒られないように、丁寧に。私が憎まれないように。
お父さんが家を出る前夜、私達は本当に久しぶりに家族揃って食事をした。すっかり片付けられた食卓の上に出来合いのおかずがならぶ。鶏の唐揚げに、肉じゃが、白菜の入った白和え。すべては私が買い揃え、味噌汁を作り、米を炊き、部屋にこもったお兄ちゃんを引っぱりだして、食卓を囲んだ。こういうふうに夕食をとるなんて何年振りかのことだから、私はこの出来合いの料理は本当はビールやら焼酎が化けているのではないかと思った。お酒の林立する姿は、まさに我が家そのものだった。
無言で箸が進んで行く。
「おかわりは?」
私はお母さんを演じてみる。お兄ちゃんが黙って茶わんを差し出す。ジャーの白い御飯は湯気がたっていて、もわっとした空気が私の顔を襲った。無言の食卓。私はそれでもお兄ちゃんに笑みを浮かべながら山盛りの御飯を手渡すと、これが我が家なのだと嬉しくなる。
家族の定義が人それぞれにあるとして、私は血のつながりとか、信頼関係とか、そう云ったものを信じない。それよりももっと単純に、一緒にいること、それが当たり前だと考えもしないその空間自体が家族を構成しているのだと思ったりする。
私達は一緒に食卓を囲む、と云うことをこれまで殆どしたことがなかった。家族で食事をすると云うことが一番家族らしい行為だとは全く思ってもいなかった。だからこそ思う。こうしていられることがなんて家庭的なのだろうと。
願わくは、世の中すべての家族が、食事時に「これが家族なんだ。」と思うことがないように。
お父さんが口を開いた。
「これは全部杪が作ったのか?」
「違うよ。出来合いだよ。」
出来合いの家族。
「この味噌汁もか?」
「これは私。」
「そうか、旨いな。」
「旨いね。」
「本当に旨いよ。」
「ありがとう。」
「もう一杯おくれ。」
私はお父さんのおかわりを初めて受け取った。
後片付けの最中、お兄ちゃんはまた部屋に戻り、お父さんが見ているであろうテレビの音が茶わんを洗う音とぶつかった。手の濡れた感触、泡。そして急に私の背中に温度があった。お父さんの体温だ。
「お父さん…。」
それはもう何度も感じた温度だった。お腹で、背中で、私の中で、腕で足で全身で。でも今日のその温かさは何故か湿っていて、私の体は立っていられない程だった。
「麻由…。」
お父さんの呟いた名前は私のものじゃなかった。それは私が幼いときに聞いた、
「お母さんの名前…。」
私は、呟いた。
私だけが辛いんじゃない。
お父さんにも過去があって、
お兄ちゃんにも影があって、
お母さんにも、きっと。
そうなんだ。
きっとみんなそうなんだ。
だから、
私だけが悲劇の中にいるんじゃなくて、
それはあまりにも自分だけすぎて、
叔母さんも、友達も、
ドアの向こうの猫さえも、
すぐ傍に嵐が控えているんだ。
◆
その夜、私は寝つけずに、家を出た。通りはもう眠りについているのに、街灯が道路を赤く照らしていて、変に明るく、生ぬるい空気がまとわりついてきた。誰かと誰かにすれ違う。二人は夜の小さな笑い声を落としながら手を繋いでいる。触れあう掌には何が伝わっているのだろう。私はまだ、知らない。お父さんをいつも包み込んでいたのに。分からない。
角を曲がると暗闇が民家に縁取られていて、私はその闇に向けて歩みつづけた。
階段に当たる。ぞうりの左足で踏み出して、階段を下ると、足音がずるずると引きずられる。降り切るとそこはいつもの低い温度はなく、灯りもなく、私は勘を頼りにあの場所まで進みはじめた。
バスはそこに佇んでいて、月明かりにてらてらと輝いていた。今日は満月だ。空が紫に染まっている。描きかけの太陽と月の絵がうっすらと浮かび上がって、太陽の肌は赤紫だった。
満月の薄い空の背景にバスの黒い骨組と、運転席に人影が見える。「お兄ちゃんだ」とすぐにわかった。
「お兄ちゃん、なにしてるの?」
私が訊くと、
「走ってるんだ。」
そう云って、ハンドルを動かしていた。
右に左に、アクセルを踏み、ギアを切り替えて、また右に左にハンドルを動かす。ライトもつかないのに凝っと前を見て、お兄ちゃんはこの夜、バスを走らせていた。その傍らで、私は眠るのに毛布もいらなかった。
朝。まだ太陽もでない頃。お兄ちゃんは浅い眠りから覚め、バスの扉を開け外に出た。
「なにやってんだ?」
お兄ちゃんはバスに向かってはけを持っている私にそう訊ねた。
「描いてるの。」
途中で終わっていた太陽と月の絵に、はけでもって色を染める。その作業も終わり、私は太陽と月の間にもうひとつ描きたそうとしていた。
「何を描いてるんだ?」
「女の子。」
暫くして描き上がった絵は赤い着物を着て、横たわって眠っているおかっぱ頭の少女だった。奇妙な笑みを浮かべている月と、目を見開いた太陽の狭間で、安らかな微笑みをたたえていた。
「…うまいもんだな。」
「そうでしょう。」
今日、お父さんは家を出て行く。そうして私達も家を出る。嵐を避けるために。でも嵐はいつでも生まれ、追いかけてくる。逃げることは出来ない。いつも、嵐は、自分の夜から生まれてくる。
バスは、夜を走る。
「杪、どうした?」
お兄ちゃんが云った。
「大丈夫。」
私が答える、
「少し吐き気がしただけ。」
屈んでいた体を持ち上げ、喉に込み上げてくる感情を抑え、二人並んでバスを見る。悲喜こもごもの思いを抱いた月と太陽に挟まれて、穏やかな表情で眠る少女は、どこに行くともなしに私達のバスに乗って、揺られていた。
何故か、胸の膨らむ思いがした。
© Rakuten Group, Inc.