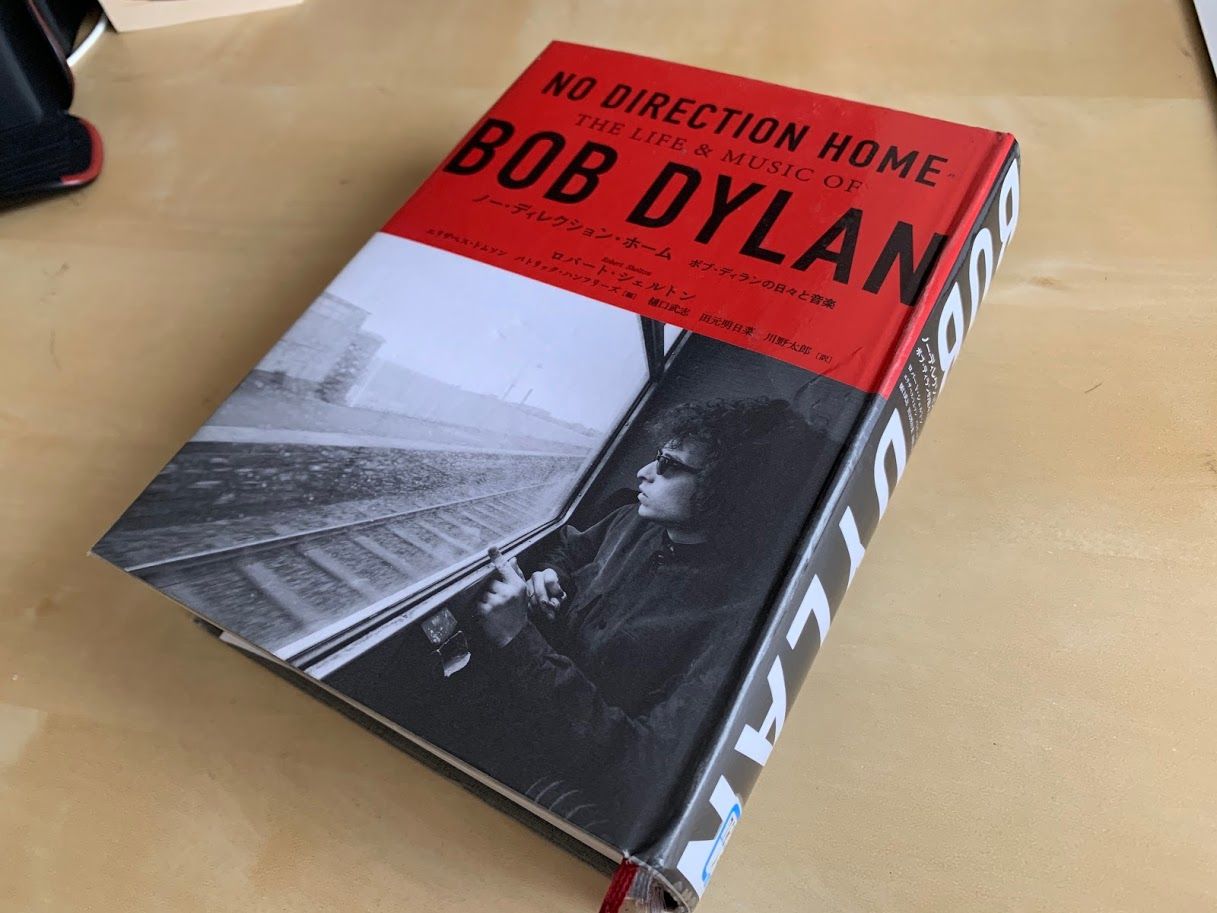7月
8月
9月
10月
11月
12月
2020年06月の記事
全1件 (1件中 1-1件目)
1
全1件 (1件中 1-1件目)
1
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- Jazz
- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…
- (2025-11-02 07:32:37)
-
-
-
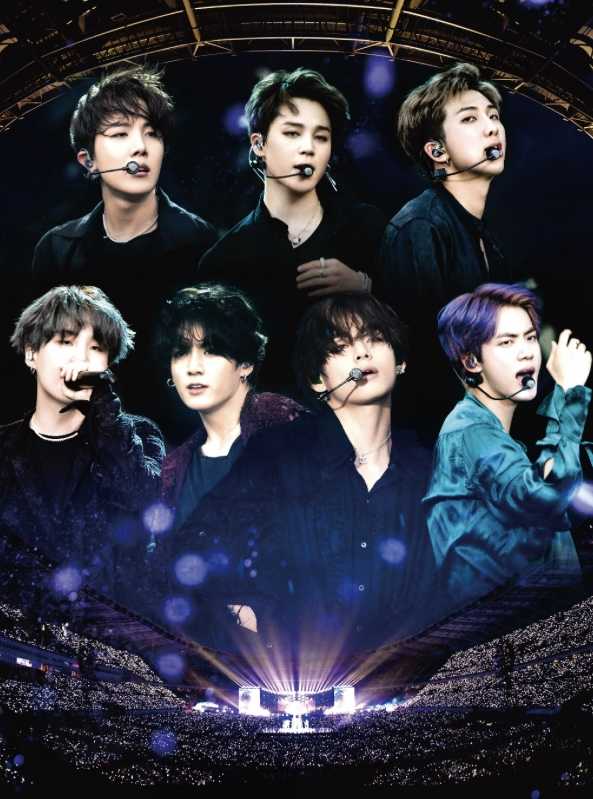
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-
-
-

- ライブ・コンサート
- 明日開催・モンゴル音楽コンサート@…
- (2025-11-23 09:00:06)
-
© Rakuten Group, Inc.