我が指のオーケストラ

山本おさむは寡作であるが、その作品には、作者の作品に対する真摯な気持ちが感じられて、好きなマンガ家の一人である。
最初の出会いは、青春マンガの 「僕たちの疾走」 。これは、「博多っ子純情」と並ぶ、教養マンガ(少年が大人になっていく課程を描いたと言う意味での)であった。
その後、実話によった原作を元に 「遙かなる甲子園」 で、沖縄聾学校が野球部を作って、高野連の規則を突き破り、甲子園出場を目指すまでの話を描いた(後に映画化される)。
この「我が指のオーケストラ」は、それに続いての原作のマンガ化、そして同じく聾の世界に関わった話である。
原作は主人公の娘さんである川淵依子が書いた 「指骨」 。
時代は大正から昭和へ移ろうとする頃。音楽で外国への留学を夢見る青年であった主人公が、その夢が破れて教員として赴任したのは、耳の聞こえない子供達が集まった聾学校であった。
しかし、子供達との交流を通じて、音の聞こえない子供達にも、手話という方法によって、心を通じ合わせる事が出来、それは心の中に響く音楽なのだという事に気づく。
しかし、時代は折しも、聾唖教育に口語が取り入れられ始めた時代。
手話は、口話の学習をじゃまするものとして聾唖教育の場から排除されようとしていた。その思想の根底には、しゃべれるのが正常の状態で、聾唖は異常だとする差別的な考えがあった。
しかし、一部の者には口話が上手く収得できても、全く不可能な者達も居る。本来心の成長を獲得するはずの学校の教育が、単なる発音練習の場になってしまっていることに彼は危惧を抱き、彼が校長を務める大阪市立聾学校は、日本で唯一手話を排除しない学校になる。
文部大臣を前にして、全国聾唖学校校長会総会でただ一人、手話を擁護する立場として彼が演説する場面はこの作品の白眉である。
喋れない事は決して異常ではない。手話は聾唖者達の中から自然発生して来た言葉である。それを健常者が取り上げる事は許されない。
口話に適する者は、口話にて、不適な者は手話を併用して、ひとりの落ちこぼれもなく、適正な教育が受けられるように。それが彼の主張である。

この作品は決して手話の事だけを描いた話ではない。
この時代、聾唖であると言うことは社会的に差別され、貧困と直接結びついた。聾唖者=貧困者、社会の底辺であったのである。
その彼らの視点から、その時代が描かれる。
米騒動で、どうして貧乏人は米が食べれなくなったのか、関東大震災では朝鮮人が暴動を起こすという根も葉もない噂で大勢虐殺された。朝鮮人かどうかを見分けるのに、「50円50銭」と発音させるのである。「コチューエン、コチュッセン」と発音すれば朝鮮人だと・・。そして聾唖者も殺された。その発音が出来ないばかりに・・。
聾唖者であるばかりに、彼らは社会から阻害され、非人間的な扱いをされ人権までも危うくされる。その怒りや悲しみが彼らの視点から描かれるのである。
口話教育によって手話を取り上げられた少年が、絶望の中で持病の肺結核を悪化させ、その最期に手話で話がしたいと、校長になっていた主人公を家に呼び手話で語り合いながら最期を迎える場面では涙がにじんできた。
大学病院勤務時代に当直室にこのマンガを忘れていたら、次の日の当直の後輩がこれを読んだらしく、「うるうる泣いちゃって・・妻に読ませたいので貸してくれますか」と言われた記憶がある。(彼の妻は泣かなかったそうであるが・・)
山本おさむは、この作品の後、障害を持つ人たちが、自立して社会に出ていくための作業場を作る話を 「どんぐりの家」 で描く。これが今のところの彼の代表作と言えるであろう。
近作では、若くして夭逝した棋士、村山聖の生涯を 「聖」 という作品で描いている。この作品で、主人公が腎臓病で亡くなった場面を描いていたときに、彼の長年連れ添った妻も、同じ病気で亡くなったそうである。
その気持ちは如何ほどに辛かっただろうかと思う。
彼の作品に感じられるのは、その登場人物達に注がれる暖かい視線と、その作品に入っていく真摯な態度である。
最近はずっと原作物ばかり描いているが、是非彼のオリジナルの話も読みたいものである。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- あさって、ジンのI’ll be there 楽し…
- (2024-10-23 23:53:52)
-
-
-
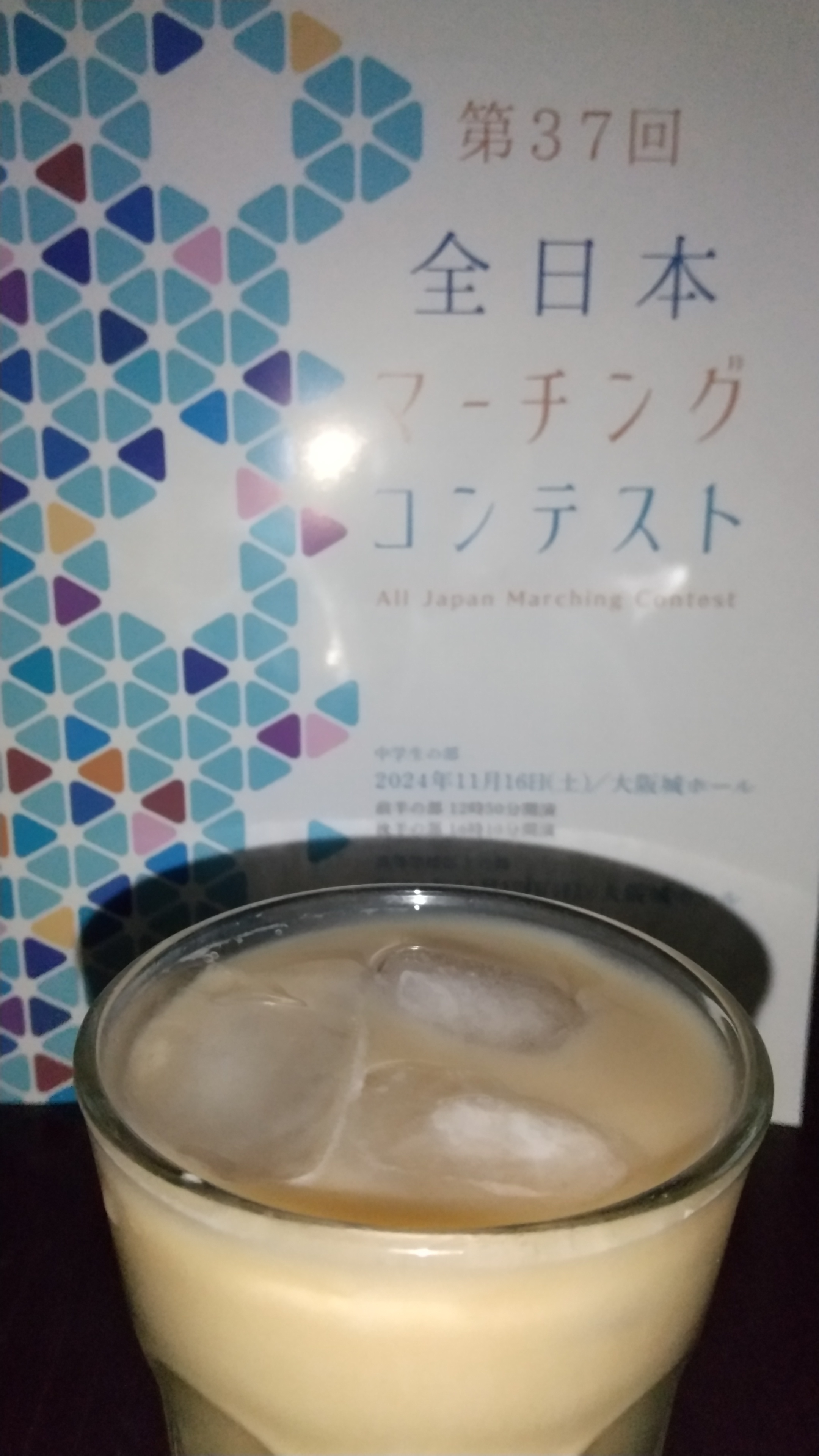
- 吹奏楽
- マーチング全国大会 金賞
- (2024-11-25 06:27:11)
-
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- John Wetton & Richard Palmer-James…
- (2024-11-28 00:00:10)
-
© Rakuten Group, Inc.


