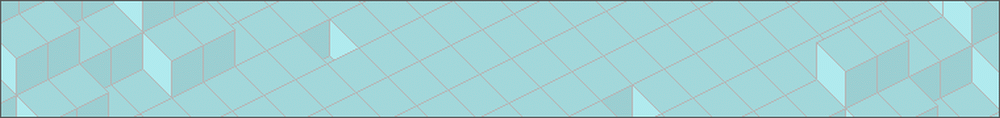全746件 (746件中 1-50件目)
-

河内家菊水丸さんの出陣式から…
7月12日(土)に、すでに感動的な「河内音頭を聴く会」が終了しましたが、そのまえに今年の菊水丸さんの出陣式報告をしておきたかったので、ひとこと??? タイトルにあるように、昨年の大病、手術から1年を経ての「出陣式」大阪警察病院の主治医から、その後のご報告や、今後のサポートについての力強い言葉があり、心からホッとしたことでした。いつもながらの野中広務元議員の開会のご挨拶から始まり、ふるさと納税や、河内音頭でのご縁の地方の首長さんや議員さんのご挨拶が続きました。そしてお仲間の芸人さんたちもご一緒に「鏡割り」! 三条史郎さんの「太鼓」、石田雄一さんの「ギター」で菊水丸さんが登場されると大喝采でした。石田さんが「ネコ大好き人間」というのをはじめて知りました。お仲間があってうれし~い!お近くで初めてギターのバンド?が「ネコ柄」であることを発見!かわい~い! この出陣式のご報告にこだわったのは、パーティーの途中に登場した「少年音頭取り」の木村君。菊水丸さんが自分の子供の頃を髣髴とさせるような、またその頃の自分以上の音頭が取れる…と絶賛の小学生の特別出演にたいへん感激しました。あの独特の節回しと、また長い「歌」を本当に上手に歌ってくれた木村君。菊水丸さんも特別に「後継者」を望んでおられるわけではないでしょうが、こんなに若い世代の、菊水丸さんが河内音頭を始められた頃を思い出されるような木村君が現れたことは本当にうれしい出来事だったと思います。八尾市出身で、地元の少年と言うのもいい。木村君、今後にオバサンは絶大に期待しています!!! がんばれ木村君! こうして、出陣式を経て、2週間後、TSUBAICHIで「第4回河内家菊水丸の河内音頭を聴く会」が催されましたが、満員御礼。菊水丸さんの素晴らしい公演で、参加者は感動の渦に包まれました。次にまたご報告します。 大好きな菊水丸さんと!!!(ルンルン)。
2014/07/17
-

6月27日の遊劇体リーディング会
娘の所属している劇団「遊劇体」では、この度、舞台公演ではなく、朗読会として泉鏡花の作品をとりあげていくという試みを開始。夜に、場所が大阪であったことも幸いし、遊劇体ファンでもある山寺さんと一緒に参加した。何と大阪市北区兎我野町にある雑居ビル内のポレポレというバーが会場で限定30名と言うことだったが、果たして30名入場できたかどうか??? 第1回目は『通夜物語』の部分を、参加者全員にも「台本=原作コピー」を公開しながら2回公演だったが、1回目の後、主宰者のキタモトマサヤ氏が注釈や解説をしてくださり、内容のみならず、鏡花の意図、表現の変化やその経緯などの説明もあり、その後の2回目は舞台での役者の演技以上に、「朗読」というシンプルなスタイルを通じて、より自らの頭の中で『通夜物語』の展開の面白さが感じられ、貴重な楽しい経験をさせて頂いた。キタモト氏の泉鏡花作品に対するこだわりについて、あらためて鏡花作品の魅力も含めて、泉鏡花の人と生りや、鏡花作品の時代的評価、そして当時の社会的影響など聞かせて頂き、よく理解できた。そして、キタモト氏の、世界の古典的戯曲であるシェイクスピアやギリシア劇などへの回帰への納得や、日本的でかつ新しい戯曲の演劇への挑戦として「泉鏡花」があるということにあらためて感心した。娘がすぐれた脚本家、演出家の下で芝居ができる、学ばせて頂いていることがありがたいとも思えた。理屈っぽい私には、「なぜ?」という前提、納得があっての理解であるので(笑)、娘の女優生活も意義あるものに思えるのは、身びいきそのものかもしれないが・・・。 7月、8月とこの形式で、朗読会(リーディング公演)が行われるとのこと。そして、本公演は、10月17日~20日まで、久しぶりに京都の五條会館で予定されている。演題は、『お忍び』今から楽しみだ。
2014/07/13
-

明日香万葉朗唱の会講座風景
講座風景のお写真を頂きました。 明日香村公民館は、大ホールだけでなくお部屋に「日の丸」と「明日香村章」が掲げてあります。私の机には、受講生の方が毎回お花を添えてくださいます。今日のお花は、紫陽花と半夏生。季節感がうれしいです。 今月で2年目に入りました。来月ははじめて万葉バス旅行。暑い盛り?ですが、明日香村の方々にとっての閑期だそうで、聖地水の吉野へ行く予定です。芋峠越えができないのが残念!
2014/06/26
-

アスカム頑張ってます!
今日は月1度の明日香村万葉朗唱の会の万葉講座。明日香村での時間を有効に使うべく、時間刻みの行動開始。まず、甘樫の夢市でお買い物。夏野菜が増えてきました。安くて新鮮!万願寺とうがらし、ピーマン、トマト、なすび…。主婦のお買い物を終えて、お目当てのアスカムのジェラートショップへ。今日はおかも御用達の「チョコミント」(ウフフ)と、明日香村の特産の「巨峰」のダブルです。ご主人の乾さんともお話をする機会もあり、貴重なお話を伺いました。明日香村出身の乾さんが、サラリーマン生活から転身されてのジェラート店は、ご自身で農園で栽培した果実・野菜を素材に、自らジェラートを作っておられます。「そんなに手のかかったこだわりのジェラートだったんだ…」とびっくり。「美味しい…。」今後の目標や夢なども伺い、大いに共感しました。大好きなアイスクリーム、季節ごとの明日香の風味を求めてまた来ますね! そして、この胸に1ポイントの缶バッジ。(写真がワイド過ぎた!)同じアスカムの雑貨屋さんのオリジナル商品。200円です。早速、購入し、意気揚々と付けて講座に出かけて行きました。手軽で、明日香村ならではの「高松塚壁画」良いですねえ。 そして、雑貨屋さんの一角にある「マダム.ビー」めずらしいオリジナルのドレッシング屋さんです。自ら企画・考案のドレッシングを商品化して売っておられます。手作り感がいい。ドレッシングも今やサラダだけでなく、和え物の調味料として和食もオールマイティです。今日は試しに「お酒のあてにもよい」と言う、白みそじいさんと生姜ばあさん?の白みそジンジャードレッシングを買ってみました。冷ややっこやもろみがわりに良さそうです。 幕明けからまだ間もないですが、今までにない明日香風?何か新しい波動を感じます。みんな、明日香村で、活気あるふるさと目指して頑張ってる!では私も元気を得て、万葉講座へ・・・。
2014/06/26
-

大和三山を行く!
宝塚売布のコープカルチャーで、年2回の「万葉の旅」を実施している。制約があってバス旅行ができないため、おおよその目安は「大阪9時頃集合、歩く距離は6キロくらい、現地で4時頃には解散してほしい」とコープからのミッションで計画を立ててみる。第1回目はもちろん明日香村をご案内したが、その後は山の辺の道を近鉄朝倉駅から4回に分けて、近鉄平城駅まで北上した。また大宇陀のかぎろひの里を訪れたこともあり、その時の旅の思い出を詠んでくださった安原さんの短歌が「柿本人麻呂賞」を獲得され、私たちにとってもよい思い出となったことはうれしいことだった。そして今春は、受講者の希望で「大和三山」に行きたい…と三山を登る?ことになった。耳無山139m、香具山148m、畝傍199mというどれも200mに満たない小さな山であるが、コープミッションを満たすことができるか、悩みながらではあったが、割愛も可能なので、当日、ともかくコースの行けるところまで行こうとスタートした。前日まで天気予報の状況が悪く、「雨」の予報もあったが、おかげさまで何とか降らずおまけに、曇り空であったため、太陽の照り返しに遭うこともなく歩けたので、結論から言うと、大和三山もすべて登り、全コース14キロを歩いた。と言うより、私と違い歩き慣れておられないカルチャーの方々が、よくぞこの距離を歩いてくださったことの感心と持久力にしみじみ感謝した。 巻1の2、舒明天皇が国見をされた香具山の万葉歌碑の前で記念撮影。「天の香具山」です。さて、大宇陀で詠まれた短歌が入賞された安原さんが、先日「先生にだけお見せします。」と大和三山を歩いた時の歌を私に下さった。「世界遺産 登録目指すと 老い人は 耳成山口神社清むる」「咲垂るる 楝の花の 下に立つ 万葉人の 心となりて」「紅白の 庭石菖を 愛で行けば 藤原京址 揚げ雲雀鳴く」「いづこよりか 春蝉の 声しみ通る 橿原神宮 神苑深く」「万葉人の 心を帯びて 汗しつつ 畝傍山頂 目指して行けり」「畝傍山に のぼり来たれば 晴れやかに 金剛葛城二上連山」歌の場面の思い出が、よみがえってくる。本当に素敵な歌日記である。そして、安原さんが一緒に下さった同人誌に「万葉集を学びつつ」というエッセイを載せておられた。コープカルチャーの講座の様子や講師の私のご紹介を過分にして下さっており恐縮したが、学んでいく上で生まれる「さまざまな疑問」について触れておられ、「万葉人」の感性に賛嘆しつつ、万葉集へのさらなる探究を楽しみにしておられる。拙い講師で申し訳なく思うとともに、今後もみなさんの万葉集への期待にそうことができるよう、私もしっかり勉強しなくては、とかえって励まされた気分でもある。2009年秋から始まった宝塚コープカルチャーも、もうすぐ満5年を迎える。今後もアットホームな「万葉家族」でありたいものだ。
2014/06/23
-

神戸新聞記事から
NHKの朝ドラは春から「花子とアン」が始まり、案の定、母は村岡花子に興味を示し、「赤毛のアン」をはじめ、モンゴメリーの「アンシリーズ」を読み漁っている。私はNHKの連ドラは、もう長~い間見たことがないのだが、それなりにメディアなどで情報は伝わってくるので、前回の「ごちそうさま」の共演者が私生活でも恋愛中?などサイドニュースなどもなんとなく把握できている(笑)。数日前、神戸新聞の夕刊の「随想」という記事に、文芸春秋社の社長の平尾隆弘さんのエッセイ「ブラックバーン先生へ」が掲載された。読み進むにつれて、ブラックバーン先生のメッセージの素晴らしさに感動した。学生時代に得たもの、培われたものに対する感謝は、いまだ実感することが多い。しかし、今時を経て結果、自分にとっての思いは、かつて昼下がり通信で「あの日に帰りたい」という文章を書いた時に、賛否両論のご意見を寄せて頂き、恐縮したことがあったが、私は再び平尾さんのご意見で大いに力づけられ、自分自身に納得している。村岡花子さんもミッションスクールの東洋英和女学院だが、私も私立の女子校に学び、学校方針、教育目的と言うものを常に教えられながら育った。学生の頃は深い関心もなく、理解も不十分なまま、むしろうっとうしく感じたり、先生の話をギャグにしながら過ごしたものだが、いまだにその時の「教え、学び」が断片的にもしっかり残っていて、同級生と話をしても大いに想い出話として花が咲く話題となる。教育はすぐに成果の出るものではなく、こうして子供心に刷り込むように植えつけて行くものだとつくづく思う。今の若者には、このブラックバーン先生のはなむけを胸にがんばってほしいと思う。そして、年を経て人生を振り返った時に、平尾さんが書かれたように、「あの頃が一番楽しかった!」と人生を支えてくれた青春時代を懐かしむことは大いなる誇りだと思うのだ。記事を添付します。
2014/06/07
-

TSUBAICHIに「ちんどん屋」がやってきた!
企画の私が楽しみにしていた「ちんどん屋がやってくる!」。昨日、TSUBAICHIにやってきました!ちんどん通信社(東西屋)の林幸治郎リーダーと3人の女性ユニットで登場。2時間近く、演奏やお話、南京玉すだれ、皿、いやボールまわしや、曲芸などを織り交ぜながら、圧巻のエンターティナーぶりを発揮して下さいました。めづらしさと、興味深さで一杯の私たちは、何もかもが新鮮な驚きもあって、すっかり楽しませて頂きました。 今回はクラリネットではなく、コルネットトランペットとアコーデオン。 そして、おなじみの「ちんどん」の組み合わせ和製ドラムセットの編成でした。日本的楽器の鐘、太鼓、大太鼓がアメリカのドラムセットを意識して、組み合わされたものを「かついで動く…歩く」ことになり、その音楽集団は店舗などのオープンの「儀式」に出演されたり、宣伝マンとしてのお仕事が多いので、このようにみなさんに鑑賞されるような音楽ではない…と謙遜されていましたが、サロンではきっとやりにくかったことでしょうね(笑)。じんたと言われる曲想は、「美しき天然」などなつかしかったこと…。富山県で始まった「全日本ちんどんコンクール」いうのも、林さんグループは何と優勝歴11回という日本で有数のチンドン屋さん。「日の出」のバランス芸を披露して下さったななちゃんは、先日行われた大会で見事入賞された曲芸です。 最後に私たち観客の質疑応答にこたえてくださいましたが、パリやロンドン公演のエピソードや、「ヤオハン」ニューヨーク出店にも出演など、国際的な活動ぶりも聞かせて頂きました。また今回依頼のきっかけとなった、神戸大学のちんどん部から、卒業後、今は団員として活躍しておられる仮屋崎さんに、その時の経緯をうかがったり、立ち入った事まで聞かせて頂きました。東西屋さんはみなさん仲良く、全体で25名ものファミリーで活動中です。出演者で演目もいろいろだそうですので、またちがった方々のパフォーマンスも見てみたいと思いました。第1回の日本の伝統芸に親しむシリーズにふさわしいサプライズ企画に自己満足しています。チンドン屋華やかかりしころの、貴重な写真を見せて頂きながら、日本の社会の進化と共に歩んできた「宣伝部隊」の方々のことを学ぶことができました。明日もまた、どこかの開店祝いや、お店の宣伝に町を練り歩かれることでしょう。なつかしさと、伝統的に時代のニーズに合わせながら守っておられるチンドン屋の皆さんにあらためて拍手を送りたいと思います。さて、このように、子供のような目でみつめてみたい日本の伝統芸に親しむシリーズの2回目は6月15日の「目からウロコの雅楽」です。乞う、ご期待ください。
2014/06/01
-
教会のオルガン奉仕で・・・。
教会から、オルガン奏楽の依頼が前日に入り、急遽だったが時間は作れたので昨日、仁川カトリック教会の葬儀ミサのオルガンご奉仕をしてきた。葬儀ミサで弾くのは久しぶりで、ドキドキのところに、お見送りするご婦人がコーラスをなさっておられたので、グループの方々がミサ中に合唱をされるというオプションもあって、私に打診があったようだ。練習をするので早めに来てほしいということで、1時間くらい前に行ったが、既に練習が始まっていた。みなさんは聖心女子学院の同窓生のコーラスグループだった。「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を故人に捧げられたが、さすがカトリック校出身の方々で、ミサの聖歌もしっかり歌って下さり、信者の方も多かったように思う。故人はまだ60代で、演奏中、涙しながら歌われているお仲間の姿を見ながら、私たちもこうして友人を見送ることがいつか訪れることの現実と、見送るより見送られた方が幸せなのだろうか…などと、いろいろ考えさせられてしまった。女学生の頃からの絆はまた親、兄弟とは違い、共有した「私たちの人生そのもの」である。みなさん、なつかしい「あの頃」を思い出しながらお見送りをされたに違いない。あの頃、人生に終わりがあるなんて想像もできなかった私たち…。老いた両親を始め、友人、自分のことに置き換え、深く考えさせられたひとときだった。ともかく、毎日を大事に生きること…。では、今日も元気で!!!
2014/05/30
-

祝! 吉野清華先生米寿記念書作展
私は小学生の時から書道を習っていましたが、神戸市垂水区に住んでいましたので、地元には安東聖空先生と言う有名な書家がおられ、そのお弟子さんの吉岡政子先生に師事し、段位もとりました。中高時代は、授業の選択で書道は学びましたが、それっきり。大學を卒業して後、西宮に転居しましたが、どうしても書道を続けたくてご紹介を受け、母と共に入門?したのが、吉野先生です。私もその後、結婚し、娘を出産し、娘が歩きだすまでの間、わずか3~4年でしたが、再び「筆を運ぶことの楽しさ」を得て、やっぱり好きなんだ!と思った次第です。その後も母は続け、お弟子さんの向井先生には私の娘や、甥も姪もお世話様になり、家族が吉野門下であったといっても過言ではないと思います。その吉野先生が、米寿を迎えられたというのも驚きでしたが、先生個人の展覧会であり、お祝い申し上げたい気持ちと、作品を観たいという気持ちで、限られた会期中だったので、あわただしく出かけてきました。久しぶりにお目にかかった先生は、杖をついておられましたが、柔和な表情で、元気にこの記念すべき時を迎えられたことをお喜びでした。 もちろん万葉歌の作品も多く、興味深く拝見しました。やはり時の流れはすごい! 先生の「書」の素晴らしさをよりひきたてる「紙」「表具」の多彩と素晴らしさに圧倒されました。ますます豪華に進化してます。 そして興味深い「百人一首」も!すごいなあ。 先生の作品、み~んなTSUBAICHIでご紹介したいです。いやほしい!!!(笑)。作品の中で私が感慨深かったのは、先生自らが詠まれた歌の「作品」でした。先生を献身的にサポートしてこられた優しいご主人様を亡くされた後、転居され、おそらくその頃から詠まれた歌ではないかと思います。大変しみじみとした多くの歌の「書」は、まさに先生そのものだと感じました。どうぞお元気で、ますますのご活躍をお祈り申し上げるばかりです。そうそう吉野先生の恩師が安東聖空先生でした?!。今回、安東先生の「歌」もたくさん書いておられましたが、そもそも安東先生ルートのご縁で私たちは吉野先生をご紹介して頂いたのか、もうすっかり忘れました。でもご縁は不思議なものです。なつかしいひととき、また書道をやってみたくなりました! 吉野先生、本当におめでとうございました。
2014/05/26
-

「夢」いっぱいの明日香村。
きょう、新しい発見をしました。(今頃?)以前から夢市や夢耕社など、明日香村のお店の名前に夢がついていることに、気がついていましたが、今日昼食ではじめて行った「旬菜館」は「夢の旬菜館」だし、4月オープンの飛鳥民俗資料館のチャレンジショップは、「明日香夢(アスカム)」だし、あと「夢の楽市」もあります。おー、明日香村は「夢」にこだわっていたんだ!とあらためて感心。 ずっと気になっていた石舞台手前の新たな施設訪問。おみやげ品とレストランの館です。「おー、夢の旬菜館なんだ」とここで、「夢」に気がつきました(笑)。飛鳥駅近いレストラン「言霊」のシェフのプロデュースだそうです。 自分で2品選ぶマイサイズ→「米菜豆」ランチです。今日私が選んだメイン料理は「黒豚の肉団子」と「旬菜キッシュ」その前に前菜があり、「冷ややっこ、切干大根のトマトパスタ風、スナップえんどう」キャベツのポタージュ・・・となかなかお洒落です。キッシュもパサツキもなく、美味しい! メニュー、雰囲気、景色…食べながら「ここは明日香?」明日香村の変化を実感しました。時代の波が寄せてきている、そんな感じです。6つのメイン料理から2品を選び、楽しむランチに、オリジナルドレッシングも! これは、ユニークな飛鳥四神にちなんだ4種類ですが、抹茶&クリームとか、新玉ねぎ、黒豆、梅酢など、オリジナルテイストで、プレゼントにもぴったりだと思いました。腹ごしらえも終え、講座に向かいました。昨年6月から始まった講座も今日で丸1年。明日香村に来れる幸せを感じながら、講座会場に向かいました。ごちそうさまでした! 追記 明日香の地産地消のベジタブルランチは、ヘルシー女子にぴったりです。お洒落なランチを一度ご経験ください。1300円なり!
2014/05/22
-
ちょっと興奮! 見てね!!
今年、阪神なんば線が開通して5年です。(TSUBAICHIも5周年!)三宮からなんば、ひいては近鉄奈良まで乗り換えなく、移動ができるようになりました。私は奈良女子大学に行くことも楽になりましたし、平城京遷都1300年記念行事をはじめ、古都奈良へ出かけることが、何と身近になったことか。阪神間の通勤客は、地下鉄に乗り換えることなく、なんばに出られるのも大きな魅力です。さて前置きが長くなりましたが、奈良県の「記紀・万葉プロジェクト」という、観光行政の目標で、主に近鉄などが中心となってイベントが催されてきました。しかし、阪神なんば線の開通によって、阪神沿線の古代史ファンの方々に多く門戸を広げたこともあり、このたび阪神電鉄が5周年記念イベントとして、地元沿線ではじめての講演会を企画されました。8月後半から開始、選ばれた会場は阪神間で代表される武庫川女子大学です。千田稔氏、菅谷文則氏、影山尚之氏、中西進氏…と錚々たる先生方の登場に、色どりになるでしょうか(汗)、万葉うたがたりコンサートの機会も頂きました。また時間・参加申し込み方法など詳細は追ってお知らせいたしますが、実は、今日阪神電鉄からうれしいご連絡がありました。1、阪神電車内で5月25日~イベントのつり広告が出ます。2、またB1サイズのポスターが、5月26日から駅構内に張り出されるそうです。豆粒みたいな写真でも、私たちの写真が車内広告として人目に触れるなんて、初めての体験です。何だかうれしはずかしカンカンブリキ!もし阪神電車に乗られる機会がありましたら、見つけて頂けると幸いです!楽しみ…。
2014/05/21
-

TSUBAICHI 5th anniversary 万葉うたがりコンサート
1部のつばいち音楽会に引き続き、第2部は万葉うたがたりコンサートサロンが、大阪市に立地しているので、今回のテーマは「万葉のなにわを歌う」。案外、「大阪」いわゆる万葉の摂津・河内・和泉の歌を部分的に紹介することはあっても地域や土地の様子などを「万葉のなにわ」と体系立てて歌い上げることも少ないので、ご紹介するにはよい機会だったと思う。・つばいち問答歌(サロンのテーマソング)・春つれづれ(大阪市生野区)・恋忘れ貝(大阪市住吉区)・葦鶴悲し(東大阪市)・言問ひ橋(柏原市)・鴨山考(河内長野市)・逢合橋(交野市)・生駒山を恋ふる歌(奈良県生駒市)・二上エレジー(大阪・奈良県境)演奏については、西本君がたくさんユーチューブにあげてくれたので、ネット検索ができるようになり、みなさんに見て頂く機会ができたことは、ありがたい限りだ。プログラムの曲目がすべて終わったのちに、私たちのセレモニー!5周年をみなさんにもご協力頂き、全員で「おめでとうコール」を唱和して頂きながら、クラッカーを打ち鳴らしお祝いした。なんて楽しいんでしょ! 最後はやはりこれでしめくくり。「サンバDEツバキ」です。ツバイチオーケストラで後ろに控えていた私も最後には前列で歌わせて頂いた。 90分もの長いステージだったが、全体で大体2時間くらいと目処をつけておられた方は、ちょっと帰りを焦らせてしまった。ごめんなさい。でも私の予定通りだったので、あしからず…。うたがたりの仲間がそろって万葉うたがたりのコンサートを支えてくれたことに心から感謝。アッコちゃん、愛ちゃん、裏方もお疲れ様でした。 5周年を記念したTSUBAICHIの2日間に亘るイベントも無事に終了し、一応ほっと一息。オープンをした時以来、久しぶりにスタッフで打ち上げもでき、仲間のみなさんにも喜びを共有してもらった。さて、6年目・・・スタートしました。
2014/04/22
-

つばいち音楽会special version
2日目の記念イベントはもちろん「万葉うたがたりコンサート」でしたが、新たな歌姫の紹介もかねて、うたがたり会のメンバーそれぞれの個性を発揮してもらう機会にしました。サロンでは、レッスンに来られている方や趣味で音楽を楽しまれている方も多いので、1年に1度(正確には9カ月周期)つばいち音楽会を開催しております。そして、今回はspecialと銘打って、万葉うたがたり会の登場と言うことになりました。おかもと山寺さんは、もちろんエレクトーンとピアノです。ユーミンの「ひこうき雲」「春よ来い」そしてデュオでトルコ行進曲。(老眼の二人、ドキドキです。)笑 そして、新たな歌姫、上未歩さん。まったくのクラシック育ちで、きょうのステージも初マイク、初うたがたり、初衣装…初づくしで緊張の機会だったと思います。音楽会なのでご自身の選んだ曲、中田喜直の「霧と話した」でした。意味深な失恋ソングだとは、この機会まで知りませんでした。 そして貴重な器楽演奏はバイオリンの村田道代さん。体調が悪かったので、心配していましたが、何とか無事にステージをこなし…。私たちにプロ根性は必要です。マスネのタイスの瞑想曲をしっとりと聞かせてくれました。 5月には初めてのともちゃんライブを企画していますが、園田知子さんに今回は私が歌ってほしかったジャニーズファミリーの嵐の歌う「ふるさと」を披露してもらいました。紅白歌合戦の企画から生まれたこの国民ソングは、学生の合唱コンクールの課題曲にもなっています。私たちもうたがたり会で歌っていきたい、その初回ご披露となりました。ピアノ伴奏は、新ユニットのメンバーでもある砂原由季子さん。 そして、ソロのトリは山口ひとみさん。リサイタルを経てますます輝きを増す歌姫に私たちも刺激を受けながら、またうたがたりにも協力を仰ぎながらの彼女の選んだ歌は、原爆被爆少女が希望を繋ぎながら折鶴を折る姿を歌った「祈り」。「折ることは祈ること」とメッセージソングをしみじみと聴かせてくれました。 「つばいち音楽会」でしたので、コスチュームも個人に任せました。思いがけず個性も発揮されたのではと思います。そして最後は砂原由季子アレンジの全員演奏の「藤村メドレー」で締めくくりました。予定通りの45分! それぞれの音楽世界が繰り広げられたひとときでした。 忘れてはならないもう一人のメンバー、浦井章子さん。彼女も音楽仲間ですが今回もMCでお手伝いをしてもらいました。彼女曰く「先輩に頼まれると断ることができない…」という本音を聞き、今後も積極的に協力を仰ぎたいと思っております。あっこちゃん、ありがとうね! ということで、あらためて万葉うたがたり会のメンバーのご紹介ができてよかったと思っています。私自身も作曲をしながら、今では「作品」と歌姫のイメージが重なっていくので、よりイメージが鮮明になるように思います。今年作りたい曲がいくつかあり…、がんばります!
2014/04/19
-

スイーツ・パーティ、いかがでしょうか!
2014/04/18
-

TSUBAICHI5周年!「恩師犬養先生を語る」
2009年4月10日にオープンしましたオカモサロンTSUBAICHIも、無我夢中で過ごす毎日が、はや満5年となりました。あらためて感慨深い思いです。万葉うたがたりの活動拠点であり、仲間の音楽活動の場でもあり、また、万葉発信地としてスタートしましたが、手探りでのサロン経営は今から思うと(今でも)本当に気楽なことでした。今後もひたすら「楽しく」続けていけたら・・・と願うばかりです。お祝いのお言葉だけではなく、たくさんのお祝のお品を頂戴し、重ね重ね恐縮いたしました。 皆様ほんとうにありがとうございました。さて5周年を記念して、2日間にわたり記念イベントを致しました。 初日の12日(土)は、私の大好きな犬養先生にこだわりたくて、山内英正さんと中西久幸さんにご講演をして頂きました。 山内さんはサロンがオープンしてから、何回か「炉辺談義シリーズ」として、犬養先生のお話をして頂いていました。今回は5回目。そして山内さんも甲陽学院を定年退職されたので、お話をして頂くだけでなく、山内さんの「労いの会」も催したくて、懇親会には名物のTSUBAICHI宴会部が出動いたしました(笑)。 もう一人の講師、中西久幸さんはサロンでも和歌文学講座シリーズの講師をはじめ、蓄音機カフェの案内人であり、サロン立ち上げのときからお世話様になっている恩人です。そして中西さんの「犬養万葉かるた」の分析や、私たちの気づかない「犬養万葉」ファミリーの仕組みや特徴をよく観察しておられ、今回はぜひにとご講演をお願い致しました。お互いが仲間うちであるので、客観的にあらためて自分たちの在り様を知ることができ、興味深い内容でした。甘党の山内さんのスウィーツパーティーはあらためてご紹介したいと思います(笑)。犬養先生を通じてのご縁が、清原先生の教え子の方にも広がり、万葉風土研究会の方々が多く来てくださって犬養ー清原ー山内の万葉ネットワークも繋がり、絆を確認できたことをうれしく思いました。 大阪近辺だけではなく、茨城、和歌山、富山、愛媛、奈良などからもご来場頂きありがとうございました。
2014/04/18
-

親心
母も高齢化し、持ち物を「断捨離」する年齢になっているので、私には迷惑なくらい何かにつけ、「譲る」方法で、押しつけ、処分をしている。友人などは、「ありがとう」って素直にもらえばいいのよ…と言ってくれるが、私にしては別にほしくもないものを…と腹立たしいことの方が多い。最近思いがけず、母が使い始めた懐中時計を見つけた。大きさと言い、文字盤と言い、老眼の私には見やすい手頃な大きさの時計だ。実は私は時計を探していたのだ。というのは、コンサートや万葉講座など、時間を確認しながら仕事をする立場なので、今までは腕時計を使っていたのだが、だんだん見えにくくなってきたことと、腕時計はつけかえをするので、忘れることもあり、常備しておくためにも卓上時計を購入しようか、どうしようか思案していた。また、バーゲンの時期でもあり買い物のついでに…と思いながら立ち寄れずにいた。珍しく母のものを、私が感心しながら誉めたと言うこともあったからだろう。昨日、車で母を送った時に「これプレゼントね!」と、お誕生日でもなく、特別の日でもないのに、手渡されたものがこの時計。母と同じものだ。通販でも求めたらしく、「復刻鉄道時計」とある。その時代ポッポ屋さんが持っていたものだろうか。腰につけて、発車、停車のたびにこれで確認をしていたのか、想像をしているが、ともかく見やすい。こうしてプレゼントされるとうれしく、ありがたいのに、素直にすぐにありがとうと言えない私。だって、この年で過保護極まりないもの…。しかし、私の昨年からの懸案は解消しそうだ。4月のオカモゼミから使用しよう。この紙面の中でこっそり「お母さんありがとう!」これは形見の品の意識かもしれないな。今、東京で娘が芝居をしている最中である。父と娘を通して、家族の葛藤・絆・犠牲・孤独…いろいろ孕んだ問題を提起している。そのような現実に恵まれない人もたくさんいる中で、還暦も過ぎてなお、いまだに親の庇護のもとにあることを反発もし、複雑な心境も残るが、やはり心底感謝しないといけないと思った私。
2014/03/30
-

娘の東京公演はじまる!
このたびは、所属劇団ではなく、客演として「燈座」の芝居に出演させて頂いてます。3月20日~23日の大阪公演が終わり、今日から30日(日)まで東京で引き続き公演です。私もサロンの行事が重なり、宣伝するどころか、見に行く時間を捻出することで精一杯だったので、やや心残りです(笑)。この度の「父を葬る」と言うタイトルの芝居は、出演者も3人だけです。脚本家の石原燃さんのカラーがよく出た、強いメッセージの作品でした。父と娘の親子間の絆、日雇い労務者の格差社会での生き方、捨てられた家族の犠牲、そして東日本大震災以後の労働者の人権…などなど、日頃恵まれて暮らしている私たちに対して、「見えない部分・現実」をつきつけられたような気がしました。いつもは娘の芝居に対して…感想などがあるのですが、今回は芝居を超えた「舞台上の現実」に深い哀しみと同情を感じ、気持ちだけでも共有することの大切さをしみじみ考えさせられました。上演後、いつもアンケートに感想を書くのですが、はじめて何を書いてよいか、戸惑いを覚えましたし、こんなことは初めての経験でした。それから、時間を経て思うことは、娘が演じた芝居に対するインパクトが強くて、役者がどうのこうの…というレベルではありませんでした。そっか~、「演劇」と言うものは役者がこのような伝達の「ツール」として生かされることにあって、娘はそれに応じた芝居ができていたのだと思えます。体力的にも精神的にもしんどい芝居だと聞いていましたが、この芝居はきっと、娘の女優生活の中の代表作と言えるものになるでしょう。ネット、新聞、マスコミにも芝居の紹介がいくつか掲載されましたが、その中で娘の紹介に「遊劇体の看板女優」と言うのがありました。「遊劇体」は小劇場演劇の小さな劇団ですが、その中でも「看板」と言ってもらえるくらいの存在になっているとすれば、母としてはうれしいことです。今日からの東京公演、一人でも多くの方に見て頂ける事を願っています。 3月27日(木) 19時 28日(金) 19時 29日(土) 13時と18時 30日(日) 15時 前売り3000円、当日3300円です。
2014/03/27
-

TSUBAICHIライブ「山口ひとみコンサート」で新たな扉がひらいた!
2014年のTSUBAICHIライブは、3月から始まりました。21日の春分の日は、古川忠義さんのギターのソロコンサート。そして23日(日)には、山口ひとみさんのスプリングコンサート。このたびは、彼女の方からの企画と申し出で、とてもうれしいことでした。定員がありますので、早々にチケットが完売してしまい、キャンセル待ちで結局来て頂けなかった方もあり、私たちは「ごめんなさい」と申し上げるしかありません。2012年秋のビルボード大阪の山口ひとみリサイタルで、音楽監督をしてくださった宮川真由美さん(ピアノ)と、ギター奏者の愛川聡さんのお二人の布陣に、テノール歌手加藤ヒロユキさんのゲスト出演もあり、大いに内容のあるプログラムでした。山口さんは万葉うたがたり会の歌姫ですが、いつもそれを意識において、ステージでも披露してくださり、今回も私の「恋歌」をライブの序章として歌ってくれました。 宮川さんのアレンジと、丁寧な山口さんの歌とで、オカモの歌とは思えない名曲に聴こえました。私もうっとり聞き惚れました。 ギターの伴奏だけでの「恋心」。いい感じでした。ギタリストにこだわった訳がわかります。 サブタイトルが「男と女の愛の物語」でしたので、山口さんの当日のテーマカラーも「赤」。1部では、新曲に挑戦。お客様のために新たなレパートリーをご披露することの意欲に感心しながら、中島みゆきの「糸」「化粧」。「化粧」は歌そのものが、ジャパニーズ・シャンソンでした。森山良子の「あなたが好きで」はとても美しいメロディが印象的でした。 ゲスト出演の加藤ヒロユキさんは、山口さんが憧れ、尊敬する先輩歌手ですが、私たちが加藤さんとご縁を得たことが、今日の山口さんの活動範囲というか、音楽世界が拓けたきっかけとなりました。山口さんと加藤さんが一緒にステージに立って唄えたらいいのに…と思っていたことが、とうとう昨日のライブで実現したのです。言霊だ!二人の歌唱力、パワー、押し出し(華)、レパートリー、歌手としての共通点も多いように思っていましたが、ライブを経てから、今後の相乗効果の方がより楽しみになりました。 日本語曲はあまり歌われない加藤さんが、「日本語曲」を意識されたように、山口さんも得意のドイツ語ではなく、英語、イタリア語、スペイン語、フランス語…と「原語」で歌う歌については大いに加藤さんに学ぶところがあるでしょう。また二人ならば、オペレッタや、ミュージカルなど、ジャンルの幅も広げられそうで、可能性がいっぱいあります。また、私たちが喝采するステージを作ってほしいものです。 満員のお客様に心から感謝。さて、山口さんのいるうたがたり会としては、いよいよ4月13日のコンサートに如何に期待して来て頂けるか…と内容も練りつつあります。メンバーが活躍することは、ボスの私としては励みともなり!?うかうかしていられません。ともかく山口さんお疲れ様でした。また新たな扉開きましたね!
2014/03/24
-

母の誕生日
一緒にミサに与ることはできなかったが、お誕生日記念の今朝、私はオルガン当番だったので、そのお恵みに感謝した。昭和7年3月16日生まれの母はきょうで満82歳になった。いつの間に・・・。水浦神父様のお説教は、ご復活を迎える準備の四旬節期間であるため、聖書の箇所と今日のテーマ「キリストの変容」について話して下さったが、ルカ福音書に記された「山に登って祈られた」ことから、私たちに対して「神との積極的な対話」を促して下さった。祈りは「お願い」にはなっていないか、祈りは神様への感謝と賛美もより大事であることを話された。ほんとだ…。今朝もミサの中で、お願いと感謝が入り混じった私だったが、もう私のことはよく御存じ!!!(笑)。神様よろしくお願いいたします…。 さて、今からは、プライベートタイム。奇しくも阿倍野ハルカスへ行ってきます。明日香村の画家、烏頭尾先生の絵画展に…。午後からは女人舞楽を鑑賞に…。アカデミックな春の一日、活動開始!!!
2014/03/16
-

ナイス・ミセス!
サロンTSUBAICHIの立地している大阪市北区の大淀の界隈は、便利なところだが、JR福島が最寄でもあり、「福島エリア」と言った方がわかりやすいかもしれない。今福島というと「食べ物屋さんの激戦地区」として、テレビ、雑誌などをにぎわす「安くて美味しい店」の代名詞的場所となっているようだ。その中で、音楽サロンと言うのは、希少価値があるが、パッと見て様子がわかりづらいこともあり、サロンも今春で満5年をむかえるが、入るのに少し敷居の高いところがあったようだ。しかしようやくご近所に住まわれる方々にも認知されてきたようで、私たちのカルチャーやイベントに参加される方が増えてきたことはうれしいことだ。その中のお一人で、お子さんも結婚・独立され、今や悠々自適な生活の中で、遺憾なくその能力を発揮されておられるご婦人がおられる。60の手習いとおっしゃったが、着物をリメイクして新たに「洋服」として甦らせ楽しんでおられるのだ。私も着物が好きで、母が嫁入りごしらえに人並みに準備してくれた着物も、なかなか着る機会も少なく、母には事後承諾で、いくつかリフォームしてかつての着物を洋服として楽しんでいるが、着る機会が増えたことで、今は母も納得してくれている。絞りのコートをワンピースに、留袖をチュニックに…とお出かけ着として活用している。 そんな私に興味深いご趣味のご婦人と出会えたことで、話題が盛り上がっている。先日はばったりお目にかかった時に素敵なワインカラーのリメイクのコートを着ておられ、手作りの技とデザインやセンスとの良さを大いに感心した。私がまた作品を見せてくださいな…とお願いしていたので、昨日、サロンに来られたついでに私に1つ作品を見せてくださった。オカモカメラマン、撮影させて頂きました。色合いも深い緑で渋く、絵柄も「和」のテイストなのだけれど、デザインが斬新。 ご本人の希望で、お洋服を中心にご紹介。袖口の模様は「散華」を写し取って描かれたもの。「音声菩薩」も描かれていた。ボタンも生地に絵付けをしたクルミボタンである。凝ってます! 背中は、「風神・雷神」の二神。手拭いに描かれた絵を生地に描き写されたそうだ。もはや着物のリメイクではなく、新たな生地素材になっている。すごい!そして、ちゃんとリバーシブルになっていて、違った表情のコートに変身。勝手ですが、素敵なご本人のお姿をご紹介させて頂く。中島さん、どうぞ! この格子のような柄行もドルマン風スリーブのデザインで、袖口に向かって大きさが集約されていく感じがすごくお洒落で素敵です。オカモ大絶賛ゆえ、ブログに掲載させていただいた。着物を着こなすのも素敵だが、こうして眠っている着物に新たに命を吹き込むことの技と着る楽しさを教えられる。ご自身で作られるだけではなく、依頼の製作も多いようで、うらやましく思いながら拝見させて頂いたが、昨日はお手製の伊予柑ピールの蒸しパンの差し入れもあり…。謙遜されるけれど、器用に多彩にご自身の時間を贅沢に楽しんでおられるのが素敵。私はまた次の作品、楽しみにしておりま~す!
2014/03/11
-

ライブハウス体験
万葉うたがたり会の歌姫、山口ひとみさんが、一昨年の歌手生活20周年記念のコンサートをきっかけに、歌手活動の範囲がぐんと広がり、多忙な毎日だ。実力派なので、新たな環境でも臆することなくステージを精力的にこなしている。一昨日は、現在定期的に出演している心斎橋のアートクラブ(ライブハウス)での出演だった。 当日、昨秋のお店主催のアートクラブ祭で、ゲスト出演された鈴木綜馬さんが来店されて歌われる、共演者の一人として山口さんもキャスティングされていたことで私も久しぶりにアートクラブへ。鈴木綜馬さんは、知る人ぞ知るのミュージカルスターだそうで、娘も知っていた(汗)。劇団四季の出身者だけあって、市村正親さんを思い出させるような、独特の語り口、笑顔のオーラ、お客さま目線のエンターティナーぶりには歌以上に圧倒された。 おばさんのツッコミとしては、いやいやサロン経営者でもあるお客様の私の感想としては、ジーンズのような普段着でのステージは(シャツの着替えはあったけれど…)ライブと言えども、お客様がそれなりの気分で来ていることを思うと、出演者としてやはり、それなりの敬意、演出・工夫は必要だと思う。歌声、声量などに恵まれておられる分だけ、それで十分勝負と思っておられるのであろう…。うーん!合間にマスクをされていたが、歌唱のたびに水を補給しておられた。調子が悪かったのか、今は歌手が舞台途中で水を飲む姿は当たり前のようになってしまったが、私はいつも違和感を持っている。私はアート祭の時に初めて聞いた綜馬さんの「クッキー」というオリジナル曲に惹かれ今回も期待していたので、聞けて満足だったし、6月のCDリリースが楽しみだ。また「愛の賛歌」で披露された情熱的で切ない訳詞は、まさにピアフの世界だった。確かに原語を日本語、男女の立場に訳すことの難しさはあるのだろうと思う。でも、綜馬さんの訳詞、山口さんもメモしたかな。山口さんは、私が期待するミュージカルナンバーをご披露したので、私はとても満足。ミュージカルナンバーの音楽的スケールの大きさと明るさ、歌唱世界が彼女にぴったりだと思う所以。どんどんミュージカルレパートリーを広げていってほしいな。 お客様の私ですら、出演者の歌唱、衣装、選曲、エンターテーメントの違いを感じるのだから、毎回、いろんな出演者と過ごすことは、山口さんも勉強になることだろう。いろんなステージをこなして、苦労も多いことだろうが、ますますビッグに、私たちを楽しませてほしいと願っている。しかし忙しくなりすぎてもたいへん。万葉うたがたりの看板も背負ってもらっている現在、私も歌姫をより大事にしなきゃと、自らを戒めております(笑)。
2014/03/09
-
光輝高齢者のパンフレットから・・・。
面白かったので、抜粋します。結構、今の私でもなるほどと思うことあって…。困ったこっちゃ!・改札を通れずよく見りゃ、診察券・ボランティア、するもされるも高齢者・歩こう会、アルコール会と聞き違え・クラス会、食後は薬の説明会・目には蚊を、耳には蝉を飼っている・誕生日、ローソク吹いて立ちくらみ・延命は不要と書いて、医者通い・飲み代が、酒から薬に変わる年・中身より、字の大きさで選ぶ本・深刻は、情報漏れより尿の漏れ・日帰りで行ってみたいな、天国へ・起きたけど、寝るまで特に用はなし・まだ生きるつもりで並ぶ、宝くじ・目覚ましのベルはまだかと、起きて待つ・お若いと言われて帽子を脱ぎそびれ明るく、楽しく、過ごすことが「幸喜高齢者」ですね!
2014/03/01
-
ボランティアに思う・・・。
ごく能天気に感謝状を頂いたことが思いがけなくうれしくて、FBにアップしたところ、びっくりするくらいの反応のツリーがつき、やや戸惑っている。ボランティア活動は本当にさまざまで、東日本大震災に関連したボランティア活動は報道で紹介されながら、継続的に私たちの目にもよく映っている。今冬の大雪で、都会から若者が雪おろし、雪かきに馳せ参じ、若い力が役立った。社会的なものから、身近な家族間の生活にまで、いろんな状況でボランティアの必然がある。このたび、感謝状を頂いた今は「音楽療法もどき」でデイサービスに来ておられる方々を対象に「音楽を通じて」歌ったり、リズムをうったり、手足、体を使って表現したり…と要素を入れながらのカリキュラムであるが、やはり究極の目的は、音楽を通じて、楽しく元気が出るひとときを過ごすことに尽きる。20名近くの人々は、それぞれに個性も違い私と気持ちが通うのに個人差があるが、それでも無理やり(笑)オカモワールドに引き込み、カリキュラムそっちのけで?自分の家族と過ごすごとく和気藹々と楽しくやっている。私が帰る時に笑顔で「また来てね」と言われると、また皆さんが喜んで下さる時間を持ちたいと思ってしまうのだ。その積み重ねが、あっという間の10年だった。その前の10年は、クリスマスだけのボランティアをしていた。ピアノレッスンの生徒さんに準備していたクリスマスにお菓子と一緒に準備して、後天性重度障害児の西宮市の施設に伺い、子供たちにお菓子を渡して、ひとときを一緒に過ごす…と言う1年に1度のことだったが、この時に、考えさせられることがあった。この施設を教えてくれたのはそこに勤めていた犬養ゼミの後輩で、健常な子どもがある日から、事故や病気で重度の障害児となった時に子供だけでなく、その親の苦悩などを聞かせてくれた。そして、日々心身ともに大変な介助仕事をしている彼女に対して私なりのささやかな支援のつもりで始めたことだった。でも私の気持ちと裏腹に「施設」は補助や援助を受けることに慣れてしまっていて、「善意」がどこかあたりまえになってしまっていたように思う。「私」はいつでも自己満足の奉仕であるから、見返りを求めるものではないけれど、はじめの感謝が、いつのまにかあたりまえとなり、後輩が結婚退職したのちは、次はあてにされて…と変わって行った。私のささやかなクリスマスプレゼントをこどもたちに…という思いを届ける以前に、施設へ行くことに抵抗が強くなってしまった。ただ、とりあえずは10年は続けようと思ったし、そして終えた。かつて母も初孫のつかさが生まれた時に、うれしさと感謝の気持ちで、教会から奉仕に行っていた療育院に寄付をしたそうだが、お礼の言葉、電話1本もなく、なしのつぶてだったことに、とてもむなしい思いだったと述懐していた。お礼を言ってほしいと言うのでもなく、届けた善意が、「志」などについて、「施設」は慣れていて、感謝よりも当たり前になっている傲慢を感じたと言った。私も同じような疑問を持ち、決して納得できるボランティアでなかったことが1つの教訓となった。その後、自分の教会活動もままならぬくせに、私にできることはないだろうか…と考えていた頃、偶然、知人で聖ヨハネ学園の児童養護施設に支援をしておられた方に紹介して頂いたのがきっかけだった。そして同じ組織のミスブール記念ホームのデイサービスで「音楽療法」を担当してほしいということで、今に至っている。そこでは、私が直接ご老人や、障害者の方々に接して、個々に励ましたり、笑顔を提供したり、コミュニケーションをもつことが、私には楽しい。犬養先生や祖父母のことを思い出したり、また両親も十分に対象年齢なので、一緒にできればいいのに…とも思いながら、私のサービス精神も加わって、みなさんに感情移入しながら、やっている。2か月に1度とは言え、仕事仲間の理解もあり、私の時間が作れることもありがたいことだ。そして、私のこだわりはここでも「万葉」。ワンポイント万葉ということで、必ず毎回、私の万葉歌を聞いて頂きながら、『万葉集』をご紹介し、魅力を伝えている。オリジナル音楽療法も10年が一区切りと思っていたが、浅田真央ちゃんではないが、1つの目標を達成して、次回4月は約束しているが、私の去就についても次はハーフ・ハーフかな。
2014/02/25
-

バレンタインの2月
2月14日、バレンタインデーがやってきた。世間一般のクリスマス同様、イベント化、またはビジネス化されて定着し、女性から男性へ「愛が告白できる」公の日とし、またそのしるしにチョコレートを添えて…と言う習慣がそれなりの賑わいとなっている。しかし我が家では、弟の霊名が聖ヴァレンティヌスで、聖人の祝日としてまた祝う日でもある。バレンチヌスは、恋人たちの守護聖人として信仰されてきた。また、2月14日は彼の殉教の日であり、彼の名をとって、バレンタインデーとされている。弟にとっては、家族から「チョコレート」をもらうことは、また意義があることなのだが、本人はおそらくそんな意識はないように思われる(笑)。なぜなら、2月15日から確定申告の時期に入り、税理士としてはもっとも忙しい時期であるからと言いたいのだが、なんとそのような時期に弟は再び「忙しさの中で自分に挑戦をする」第?弾をやっていたのだ。 先日の大雪の翌日の2月9日、武庫川で行われたハーフマラソン10キロ完走のメール!普段から忙しいなりにランニングしているのを見かけることはあったが、10キロも走るとは!いつの間にエントリー? いつの間に練習? なんで今の時期?とびっくりしたが、昼下がり通信にも書いたが、その後も信念に沿ってモチベーションを保ち続けていることに?感心した。次もあるかも。(笑)私も刺激をされて、負けてはいられないと思ったものの、新年早々体調不良や、アクシデント続きで、今年になってなかなか自分のペースが作られない。ちょっと悔しいと思いつつ、私も新年を迎えた時と同じように仕切り直し…かな。
2014/02/17
-
老兵は死なず…。
マッカーサーの有名な言葉で「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」と、役目を果たし終えた人は、表舞台から静かに去っていくことを述べた名セリフが思い出される。都知事選で、細川さんと小泉さんのタッグマッチは実らなかった。前日からの東京の大雪で、最終日の選挙運動も大変だったし、当日も投票率も上がらず、過去3番目に低い46パーセントは、有権者の半分も投票をしていないと言うことなので、選出された舛添氏は本当に「当選した」「信任された」と言えるのだろうか。選挙の投票率の低さは、有権者の無関心というのか、「選挙権」の重みを自覚していない人が多いのか、政治に我々の声が届かない無念さか、自分の1票を無駄にしている人が多い。残念なことだ。前ブログで「老人力」を述べたが、敗れたものの二人の「反対勢力」は、一石を投じたように思う。論評は小泉さんの集票力の衰えを指摘し、細川さんの選挙戦を批判した。しかしきっと彼らは表舞台からは去ったとしても「信念」を曲げることなく、脱原発を訴え続けることだろう。訴え続けていってほしい。争点が「脱原発」と言うことで、国会では「原発再稼働」についてこの期間封印していた懸案を、議決に向けてあからさまに再開した。3月11日がまた巡ってくる。福島の悲劇はまだ終わっていないのに、やはり政治家には「対岸の火事」なのだろう。ともかく細川さん、小泉さんお疲れ様でした。私の回りには70代、80代の方々がたくさんおられるので、育まれた精神と愛国心と日本人意識をしっかり学びたいと思う。「老兵は死なず。静かに見つめることあり、消え去るべからず」と言いたいものだ。
2014/02/10
-

TSUBAICHIネット美術館
音楽サロンですが、時々「作品展」を開催させて頂きます。写真展や、書道展や、絵画展など、ギャラリーTSUBAICHIに変身します。オカモサロンと言うことで、今まで私が買い求めたものや、また頂戴した作品や珍しいものなどをホームページで、「オカモの笑倉院」としてご紹介していましたが、HPでの掲載は途中で滞ってしまったかわりに、サロンができましたので、季節や行事によって展示したり、飾ったり…と自らが密かに楽しんでいます。また、TSUBAICHIに来て下さるお客様も多彩な方が多く、お親しくなるにつれていろんな「才能」を聞きだす?のは、私の特技かもしれません(笑)。昨年からTSUBAICHIカルチャーに参加して下さるNさんが、ご趣味で「絵画」を書いておられることを伺いました。そして、複数描かれた作品が「富士山」と伺い、富士山大好き人間の私は見たくて見たくて「是非一度見せてくださいませんか?」とお願いしておりました。Nさんは、素人の作品なので…と固辞しておられたのですが、私の思いを聞き入れてか、先週思いがけず持参して下さったのです。ラッキー! 富獄36景の「赤富士」を思わせるシーン。新幹線から見るなだらかな円錐形の形容ではなく、なかなか立体的でゴツゴツした感じ…と思いきや、やはり山梨県側からみた富士山の姿を描かれたそうで印象がずいぶん違います。「なまよみの甲斐の国…」の富士山です!そして、遠慮がちに見せて下さったその他の作品。私のために持ってきてくださいました。涼やかな上高地の橋のあたりからの有名ポイントの風景。 今は廃線となってしまった北海道の、愛国駅行きの「幸福駅」の駅舎。 絵画の背景はひたすら広がる大平原だそうです。さすが北海道! 山や海が迫った場所ではないだけに、モノトーンの世界が寂しさも感じさせるよう…。そして、いくつか描かれた「富士山」のもう1作です。 まさに、冠雪も陽光に包まれた、また風合いの違った「赤富士」です。青空からすれば、夕陽かもしれません???勝手な解釈でごめんなさいですが、ともかく「富士山」に出会えて幸せな私。是非サロンに飾らせていただきたく、お願いして1作をお借りしてしまいました。今サロンへ来て頂きましたら、メインの壁面に展示した「富士山」を見て頂けますよ!Nさん、ありがとうございました。いつか、TSUBAICHIでの個展を楽しみにしております!!!
2014/02/08
-

明日香村の春
2月2日には飛鳥坐神社で、西日本の3大奇祭の一つと言われる有名な「おんだ祭」が行われます。神社はきっと今頃準備で大変なことでしょう。ちょっとお天気が心配ですが…。 明日香村、大和ひいては日本の国の五穀豊穣を祈って、農耕民族の日本人の信仰と祈りのご神事が今も続いています。普段は静かな境内も「福の神」にあやかりたい人々の群れでいっぱいになります。私は毎月講座で明日香村へ伺っているので、お正月に敬意を表しにご挨拶に行ってきました。年中咲いているという「桜」も有名ですが、やはり坐神社ではすでに桜の開花が始まっていました。 久しぶりの坐神社には、犬養先生揮毫の歌碑がありますが、なんと昨年2基が建立され増えていました。1基は、境内の階段の横に「三諸の子守歌」(オカモいわく)が…。 もう1基は拝殿手前の桜の木の横に…。加夜奈留美神社と同じ歌? 建立が飛鳥古京を守る会となっているのですが、この会はすでに解散して消滅した会。今頃なんで…なんだか釈然としない感じ…。想像の域ですが、残金・浄財の還元のような気がしてならないです…(とひとりごと)。しかし、坐神社の見どころが増えて、大変にぎやかになりました。そうそう、私が犬養万葉顕彰会の会長をしていた時に、会員のおひとりから申し出がありました。それは、犬養先生と一緒に歩いた和歌山県の「糸我」の桜の枝を持ち帰り、挿し木をしたところ植木鉢で手に負えなくなったので、明日香村の犬養先生のゆかりの場所に移植して育ててほしいという申し出でした。移植地に悩んでいたところ、坐神社の飛鳥弘文宮司が快く引き受けてくださり、宮司自らの手で植え替えてくださいました。1メートルくらいだった桜が、「糸我の桜」がこんなに大きくなっていました。残念ながら、花は一度も咲いたことがないそうで…。どうしてかしらん??? 飛鳥坐神社の正面も整備が進み風景がより美しくなりました。さて、明日どれくらいの方々が訪れることやら…。ニュース報道があることでしょう。私は、サロンで加藤ヒロユキさんのラジオ番組「涙のラブレター」の公開イベントがあり、見に行くことができません。残念!!!
2014/02/01
-
がんばれ、老人力!
東京都知事選の選挙運動の真っ最中だ。猪瀬前都知事の辞任で、思いがけず世の中に少し刺激が生まれた。それも安倍政権や、霞が関を揺さぶるような「抵抗勢力」であることが愉快だ。「殿、ご乱心」と言わしめた、細川前総理の76歳の出馬のメッセージは何だろうか。その細川さんを全面的に支えるのも前総理大臣の小泉純一郎氏。二人の総理経験者が、今世間の人たちに訴えなければならない現実を考える。私の母は、昭和7年生まれの81歳。戦中派である。母が還暦を迎えた時に「孫や子の将来」を案じて市民運動に参加していったことは、今でもその行動力に感心する。普通の専業主婦だった母が今の私の年齢となって、社会参加をし始めたのは、限りある人生において「今自分にできること」への使命感からだったように思う。そして、まず食物の安全性から始まり、行政の不条理に義憤を感じ、市民オンブズマン活動などでも活躍した。また大前研一さんの「国民主権」の平成維新を実現する会にも参加し、今振り返ってもよくやったな…と感心するくらい社会活動にかかわっていた。今は年老いて、勇退したが、心情は当時と変わらず、社会を見つめる視線は今も変わらないようだ。そんな母や、今もなお、続けておられるお仲間もみんな年を重ねられた。見まわしてみると、市民運動も母たちに続く世代が育っていない。それは、伝統的な技を継承することや、文化・芸能活動もしかりで、後継者の不在はどの分野でも同じ状況のようだ。なぜ、世代観ギャップが生まれてしまったのだろう。戦争や被爆体験などや、平和・社会運動などで、活動されている人たちは、高齢化され、激動の昭和時代を生き抜いてきた経験を語り伝えていく使命を強く、余生に託しておられる。万葉のお仲間を見回しても、積極的に歩き、参加し、感動を求められる方々は60代以上の方々だ。「昔の日本はよかった」と懐古趣味ではなく、昔の日本と違い、「今はどこに向かって行こうとしているのか」「日本人であることの誇り」「これからの日本ために」と、愛国心や政治の貧困、社会の腐敗、教育の未熟を日々不安に感じておられる方々が、まさに母たちの世代なのだ。人生で体験されてきた激動の昭和時代を語り継ぎ、その経験を踏まえて教訓としたり、同じ轍を踏むことなく…という切実な思いを私たち子どもたちはしっかり受け止めているだろうか、理解できているだろうか、はなはだ疑問である。戦争や被爆、被災や現実が何もかも風化しようとしている。私はいろんな場面で70代、80代の方々の行動力やパワーに遭遇することが、偶然だとは思わない。戦後の日本を支えてきた人々が、未だに日本を支えていたのだ。細川さんが、政界を引退した時に「野に下っても違った角度から日本のために尽力を惜しまない」と言われていた通り、今日まで環境運動やNPO活動で水面下で活動されてきたようだ。東北大震災を経て、福島原発の被爆地は未だ解決も見ていないのに、東京電力を税金で支えて、検証もなく日本の他地域の原発を再稼働しようとしている政府、交付補助金に頼る自治体の様子を見ていると、日本は誰のための国家であるのか問いたくなる。「原発廃止」を明確に掲げて「一石を投じた」二人の元総理の勇気をたたえたい。たとえ当選できなくても多くの「老人パワー」の行動がお二人に象徴されているように思えてならない。私は選挙の結果もそうだが、東京都民の意識に注目している。
2014/01/28
-
歌会始めに思う。
きょうは、サラ・ブライトマンと取りだめていたNHKの「歴史ヒストリア」を「鑑賞」した。BGMではなく、画面をしっかり見ながらという行為が自分ではめずらしく、貧乏性で「何かしながら…」と思うけれど、このたびはまあいいかとと思いつつ、画面を眺め入る。さて、15日は皇居の歌会始めだった。今春のお題は「静」それこそテレビのホッとニュースで様子を知ることができたが、やはりすべての作品の秀逸は天皇陛下の御製と感じ入った。時代背景と共に本当に自然に表現されている。「慰霊碑の 先に広がる 水俣の 海青くして 静かなりけり」このような歌を詠まれるお人柄に心うたれる。そして、私はやはり皇后陛下の「母」ならではの身近さ詠われたお歌も素晴らしいと思った。「み遷りの 近き宮居に 仕ふると 瞳静かに 娘は言ひて発つ」美智子さまと落ち着いた清子さまのご様子が手に取るように想像できる(笑)。やはり現代的短歌より、私は受け入れやすいのは、やはり万葉人なのかも(笑)。 平成万葉はまだまだ続く…。
2014/01/17
-
これも日常なのね!
新年早々、インフルエンザで、久しぶりに寝込んでしまったが、仕事を持っている立場としては、思いがけない生活の混乱に、まともに落ち着いていられない半面、人様から隔離される病だけに、一定期間「ひたすら家で過ごす」ことの両極の状況を今、楽しんでいる私がいる。13日夜発病14日半信半疑で診察ーインフルエンザA型判定(診察室でも判定直後から隔離!)11月初めには例年のごとく予防注射もしていたし、しても意味がないと思うほどインフルエンザには縁のない私だっただけに、ありえへ~ん(泣)。帰宅後、タミフル服用開始。体も心も重く、寝間になだれ込み昏々と睡眠。翌朝まで自分でも感心するくらいよく寝た。朝、37度7分が、夜には37度1分に。15日朝には、36度1分の平熱に近くなった。やはり熱が下がると昨日は停止していた頭も体も動き始め、「やる気」が出てきた。医師に、インフルエンザの回復マップをもらっていて、完璧に守ると、21日に社会復帰と言うことになっているので、ともかく数日間は「自宅蟄居」と言う生活を如何に過ごすかを考えた。まずインフルエンザ完治、体力回復、睡眠不足解消があってのことだ。15日は、それでもまだ体を動かすことが大義で、ずっとたまっていたVTRをいろいろ見た。特に「八重の桜」総集編4章を一気に見て、会津藩の悲劇や、八重が歴史に翻弄される姿に大いに涙したが、肝心の「新島八重」の後世の社会貢献や生き様が省略されていて、NHKの意図も総集編で理解できたような気がした。VTRの他には、日中のテレビ番組の同じようなニュースソースにちょっとうんざり。東京都知事候補の件、相模原の少女の生還、自衛艦の衝突事故…。16日の今日は、あらためて「音楽」を聞いた。一度は見たVTRだったが落ち着いて聞きたかったのだ。「クリスマスの約束2013」「SONGSポールマッカートニー」「SONGスペシャル松任谷由美」小田和正の音楽に対する姿勢にあらためて感心した。また彼の作曲の東北大学の学生歌に感動した。少し家事をする気分にもなり、インフルエンザの空気を入れ替えるべく、窓を開け放したが、日中は寒くもなく、職場ではありえない心地よさだ。穏やかな気分で、ブログを書く気分にもなった。急に「江分利満氏の優雅な生活」というタイトルが頭に浮かんだ。「オカモの気ままな静養日記」なのだが(笑)。明日、17日は阪神淡路大震災から19年目が巡ってくる。自宅にいて、おそらくテレビも新聞も終日伝えていくことだろう。例年、しっかり向き合って思い返すことのできなかった私にとって、貴重な機会だとも思っている。そして、当時からもまた19年生かされたことに感謝をしながら、しかし、19年前のあの悲惨な現実を決して忘れてはならないと思うのだ。時々、娘と震災の時の話をすることがあるが、被災した者しかわからないであろうあの恐怖感は、生死の大きな運命の針、紙一重のことだったと思うこと。その分、「生かされること」の重さを強く感じているし、人生をより深く生きたいと思っていることは共通しているようだ。緩やかな自由な時間。きっとこんな過ごし方は、もう少し老境に入ってからのことだと思うので、とても貴重な経験だと思う。サロンで頑張っている山寺さんには申し訳ないのだが、私は開き直って楽しく個人ライフ。明日は、本を読んでみようかな。そうそう、朝晩寒い毎日、家にいると1日暖房しなくても体の余熱で過ごせることに驚き!睡眠の大事さ、日中の太陽光に感謝。今日は今年最初の満月でした。
2014/01/16
-

第2回 入江泰吉写真展はじまります!
明日、1月10日から10日間、入江泰吉写真展始まります!昨年3月、私のサロンで、「第1回入江泰吉万葉写真展」を開催させて頂きました。この時は、大阪府立大学と入江泰吉記念奈良市写真美術館・高岡市万葉歴史館の共同企画による「萬葉寫眞簡」という、ポストカード普及のための「写真展」でしたが、ご来場頂いた方々には、喜んで頂いた上「次回はぜひ入江さんの仏像写真が見たい…」など、入江泰吉さんの素晴らしい作品の数々に対して、「写真展」を再び開催してほしいという声を頂いておりました。私も、入江さんの仏像や古美術写真などが大好きで、「万葉」に特化しない本来の作品を見たいと思っていましたので、私も再開催を強く望んでいた張本人でもあります(笑)。音楽サロンですので、本格的なギャラリーでもなく、手狭な限られた空間での展示ですので今回は12点ですが、珠玉の12点だとも感謝しております。前回は、萬葉寫眞簡PRという目的もありましたので、大阪地区開催の写真展という名目で、私どもが会場を提供させて頂いた形ですが、今回は、私たちが自発的に入江展をさせて頂きたいという希望に応じてくださいました。そして内容も「大和古寺とみほとけ」と決定して頂き、わがままな依頼を快く受け入れて、作品の提供に応じてくださいましたことを心から感謝いたしております。2014年の新春を飾るサロン行事として「大和古寺とみほとけ」展を開催させて頂くことは本当に光栄なことです。何人の方々が、足を運んでくださるか、楽しみですし、私たちも格調高い作品であらたまったサロンの空間で、心静かにこれからのうたがたり活動のこと、サロン展開のことをゆっくり考えてみたいと思います。
2014/01/09
-

仕事始めは明日香村から…。
今年は穏やかで、温かいお正月でした。天気予報通り、週末からは寒気が強まり…との予報通り、仕事始めの5日は、暦の上でも「寒の入り」。甲子園を7時半に出発するときは、温度は2度で今季もっとも寒い朝?のようでした。人口6000人の明日香村ですが、その中では「大字」という、ブロックごとに住民の方々の自治組織があり、それぞれの集会所を中心に懇親を深めたり、行事があったり、連帯の形があります。私はこのたび、明日香村奥山地区の「新年例会」の今年第1回目の「講話」の講師として、招かれました。推薦者が私と親しい稲淵の小倉さんでしたし、半年前からの明日香村の万葉講座の経験も信頼して頂けた理由の1つだと思います。朝10時からの講演に合わせて、早くに出発したのは、主催者からのご依頼で「万葉衣装で」ということでした。確かに、お正月ということもあり、「お正月らしさ」を演出するのに、漠然と着物を着ようかな…などと思いましたが、奥山総代で、お世話役の米川さんが、きっぱり「先生、万葉衣装でお願いします。」とおっしゃったことで、始めはコンサートでもないのに…と思っていましたが、いざ着替えてみると「万葉」にこだわる私の新年の晴れ着はやはり「万葉衣装」かもしれない!と素直に納得したことでした。奥山の集会所は着替えるところがないので…と米川さんのご自宅を提供してくださり、あたたかくぬくめて頂いたお部屋でゆっくり着替えさせて頂きました。大きなお屋敷で、旧家ならではのなつかしい間取りのお部屋ですが、犬養先生の「七瀬」の歌の色紙をかけてくださっており、片隅にはなんと私たちが今興味深い、蓄音機が! レコードは「かわいい魚屋さん」でした。勝手に写させて頂きました(汗)。やはりなつかしい往時をしのばせるものが家庭には残っているものですね…。うれしくなりました。ご自宅と集会所は50メートルほどですが、お正月でくつろいでおられるお嬢さんを動員し、衣装を着た私を送り迎えしてくださいました。本当にありがとうございました。60名ほどの「ダイジ」の方々の集いで、「明日香を言祝ぐ~いや重け吉事」という題でお話をさせて頂きました。みなさん熱心に聞いてくださり、恐縮でした。なんと聴衆? ダイジのメンバーに私の講座に参加してくださっている、上田さん(左)と教育委員長さんの米川日出子さん(右)がおられ、少しホッとしました。明日香村でお顔見知りになっていてもご住居までは知らないので、「奥山」に住んでおられるということがよくわかりました(笑)。 そして、雑談の中で、千葉ロッテのドラフト1位入団の荻野貴司君が、何と、この奥山出身だそうです。私もあまりの身近な話題にびっくり! 本日明日香村出身のヒーロー発見!阪神タイガース情報とともに、これからチェックします! 頑張れオギノ!!!そんなこんなで、新春の明日香村スタートの仕事始め、無事に終了いたしました。きょう1月6日からは、サロンも再開。日常が始まりました。さて、2014年はどんな展開が待っていることでしょう! 楽しみ…。
2014/01/06
-

2014年、おかも歌碑!
年末に行けなかったので、お正月に表敬訪問。交野市私部西の逢合橋のふもとのおかも万葉歌碑です。お身拭いではありませんが、やはり新年を迎えるのに歌碑をきれいにしてあげなくては…とぬれ雑巾持参で行きました。今年のお正月は本当に好天で穏やかな3が日でした。青空に映えた歌碑の風景もなかなか美しく…。 この歌碑の存在がいまだに信じがたい「現実」ですが、私に揮毫と言う機会を与えて頂いたことが、幸運のなにものでもありません。歌は、地元のこだわりの万葉ファンタジーである「七夕歌」群からで、歌碑の歌は「折り句」のように「彦星・織姫・逢合橋」の3つが詠われたものにこだわられました。巻10の2040歌。そして地元で活躍されている、イラストレーターの方が描かれた「絵」入りの画期的な歌碑です(微笑)。歌碑はもはや私の分身でもあるので、「今年もよろしくね。」という挨拶と、「多くの人が足を止めて、歌碑の所縁にきづいてくれるといいね。がんばってね!」とエールを送ってきました(笑)。 7月7日に七夕飾りがはためく逢合橋に、お正月は「交野戎」の旗が!!!えびす神社はどこにあるのだろう…と思いながら、ひとしきりお正月風景を撮影。私のお正月の予定が1つこなせて、ちょっと一安心。 今年は万葉講座のお仲間をお連れしたい場所でもあります。
2014/01/03
-

2014年は犬養歌碑に初詣。
新年、あけましておめでとうございます。あわただしく2013年と2014年の区切りの時間が過ぎてしまいました。黒豆は炊いたものの、お掃除も中途半端、買い物も銀行も人混みで嫌気がさし、途中で帰宅する始末。それでも新年を迎えられる「現代」に、私自身「新年を迎えること」の新たな気持ちや、緊張感に欠けることを恥ずかしく思っています。「忙しい~…」という弁解は、単なる自己弁護にすぎないことに気付きながら、流される私に「喝!」です。今年は初めて新年を自宅ではなく、出かけていましたので、初詣は是非にと決めていた犬養先生の揮毫歌碑にご挨拶に行ってきました。 名張の夏見廃寺の大伯皇女の万葉歌碑です。娘とドライブでしたので、歌碑が私のこだわる「二上エレジー」の歌でもあることで、元旦に娘と一緒に散策できたことをとてもうれしく思いました。国の史跡でもあるので、大伯皇女が晩年過ごしたと言われる昌福寺の礎石を見たり、平成8年に万葉うたがたりコンサートをした場所を尋ねられ、なつかしく説明しながら、ひとときを過ごしました。娘たちの劇団もここで「野外劇」でもできればいいなと思いました。夜、ライトアップされたこの場所で、妖しい泉鏡花の世界が表現されるのもありです(笑)。 夏見廃寺周辺はもちろん、人影もなく、静けさに満ちていました。「犬養先生、今年もがんばります! やさしく見守っていてくださいね!」とお願いしてきました。ブログを見てくださる皆様にも心よりご支援をお願い申し上げます。
2014/01/01
-

初めて炊いてみました!
1昼夜かけて、「黒豆」を初めて炊いてみました。まあまあのできあがりに、ちょっと自信をつけたりして…(笑)。2013年も多くの方々に温かいお志を頂きましたが、特に万葉故地の方々には、名産品であったり、旬の農作物だったり、「福袋」の様な貴重なお品をたびたび頂戴いたしました。皆様のそのお気持がありがたいのと、私のあつかましさと甘えで、おかげさまで何度も何度も豊かな気持ちにさせて頂きました。ありがとうございました。今年の締めくくりはこれです。 明日香村で新春に講演をさせて頂く奥山の米川さんから、「黒豆」をたくさんに頂戴しました。「採れたままで、掃除も洗いもしてないけど…」と頂いた黒豆にどなたかにあげようか、どうしようか…と思っていました。まさにタイミング良く、後輩の加納真美さんが、大學の講師というキャリアウーマンでありながら、大変家庭的な「マメ」(豆?)な方で、なんでもこなされます。そして、先日2日かかりで、親しい方々のために黒豆を炊いてプレゼントをなさったことを伺い、感心した矢先でした。一度、自分で炊いてみよう!と思い立ったのです。(笑)昔と違い便利なお鍋もあり、お砂糖とお醤油があれば…と「ともかく」の作品?ですので、次回はもっと上手に炊けそうです。お砂糖の種類や、お醤油のこだわり、それから今回足りなかった「錆びたくぎ」と重層とか、お料理レシピを見ると足りないものだらけ…(汗)。でも味見をしてみるとまあまあなので、まあいいか!もともとお料理は嫌いではないのですが、時間的に「手抜き料理」や速攻料理が得意の私ですので(笑)、1昼夜かけてというのもお正月準備らしくて良かったと思います。黒豆を頂いたことと、毎年母からの味を作られる後輩の近況などが、思いがけないチャンスとなりました!年末きょう1日、あとは何年か越しの「かたづけ」の戦々恐々です(泣)。
2013/12/31
-

頂いた「椿の花」二題
もういくつ寝るとお正月♪の歌がふさわしいカウントダウンの時期になった。26日に明日香での万葉講座を終え、私の今年の仕事納めとなったが、その時にいつもかいがいしくお世話をして下さる勝川京子さんが、「先生、我が家に咲いた椿です…。」と、枝ごと切ってきてくださった。白い椿。もう咲き始めたことに、びっくりした。 帰宅してみると、日本郵政からの不在票が入っている。五島列島の松本さんからだ。私にむべを下さった方だ。私は仕事上、時間的な制約があるので、いつ受取ろうかな…と思っている矢先に差出人の松本さんからお電話を頂いた。「五島の椿」を入れてくださっていたので、心配されていたところ、私が不在だったので、日本郵政から折り返し、松本さんに連絡があったらしい。再び私に届いたころには、もうお花もダメになってるかも…と松本さんの残念そうなお言葉にびっくり。ええっ、五島列島からも椿の花がやってきたのだ?と椿の偶然に驚くやら、今度は2~3日の遅配ロスが気になり、お花の状態が気になること…。結局、今朝ようやく届いた箱を、ドキドキしながらあけたところ、やはりぐったりはしていたが、「水仙」の馥郁たる香りがあふれ、そして椿の小枝が松本さんの作られたお野菜の上にともに入っていた。おまけに名物のカンコロ餅も入っていて、まるで「福袋!」。お花達には「ごめんね」と言いながら、急いで花瓶に水を張って、がんばれがんばれ…と。 手狭で殺風景な我が家の玄関が、今、お花であふれている。そして箱から出した時に、こぼれおちたお花は、可哀そうなので水に浸してやり…。五島の椿は赤、ピンク、白とまるで「五弁の椿」のようだった。華やかで素敵。 年末を迎え、節目の、ふと気持ちが緩んだ時に、明日香からも三井楽からも「椿の花」をプレゼントして頂いた偶然に、すごく幸せな気分だったことと、今年もご苦労さまと私に頂いたご褒美が「椿の花束」だったことは、まさに神様の計らいとしか思えない。水仙の香りと、椿の花に満たされてただいまルンルン気分です。
2013/12/28
-

再会と素敵なお食事タイム
茨城県の筑波山のふもと、下妻市在住の大木さんが久しぶりに大阪へ。大木さんは地元東歌研究会の代表でもありますが、筑波山神社をはじめ、個人でいくつも万葉歌碑を建立されて、それを地元に寄付し、ふるさと発信、貢献の大きな原動力となっておられます。ご縁を得てからずいぶん経ちますが、平成22年11月に、筑波山神社に犬養先生の墨書をもとに高橋虫麻呂の「筑波山歌」の長歌の歌碑を建立された時には、なんとその歌碑の裏面には提供者として私の名を刻んで下さいました。恐縮でこんな光栄はありません!さて、再会とはもちろん大木さんともお久しぶりですが、写真に一緒に写っておられる中国人の唐さんとおっしゃる、経済学者でもある若手大学教授と再会を果たしました。大木さんが平成23年に春日大社に「大和しうるはし」の歌碑を建立され、除幕式の時に初めて唐さんご夫妻にお目にかかりました。日本語も達者で、素敵なご夫妻でした。きょうは、その時以来の再会のひとときでしたが、大木さんとお二人のお出会いに私もお誘い頂き、とてもうれしいことでした。昼食をしたのは千里ニュータウンの桃山台にある「スコーネ」というフレンチのお店でした。千里ニュータウンの秋景色を楽しみながら到着しました。唐さんの行きつけのオススメのお店ということで、お昼のランチでしたが、いやいや贅沢なメニューで、とても美味しく頂きました。せっかくの機会でしたので、前菜の次のメインデイッシュ以外はみんな違うものを注文…。(お味見のトレードはしましたが)笑 前菜もこだわりの無農薬野菜をピクルスにされたり、手作りのニシン漬けや、お肉のパテや、スモークサーモンなど具だくさん。色目もきれいです。そしてメインは、肉・豚・魚で、大木さんチョイスは「蝦夷シカのステーキ、ブルーベリーソースがけ」。蝦夷シカと聞いて「鹿肉」に話題が及び、大木さんのご趣味の狩猟の経験談を聞かせて頂き、興味深かったです。 そして私はイベリコ豚の赤ワインソースがけで、よく言う「共食い」でした! すべてたべたことのある唐さんは、舌平目のムニエル、ホタテ添え! 話も弾みながら、美味しいお料理に舌鼓を打ちました。そして手作りデザートは、パンプキンプリンとガナッシュのケーキです。 唐さんのオススメのお店の理由は、とても簡単でした。こだわりの食材に腕で「美味しい」ことと、シェフと奥様のお二人のお人柄にあるようでした。それがアットホームな雰囲気で、堅苦しくないフレンチレストランになっていて、唐さんも常連になっておられるのでしょう。きょうは、私が「スコーネ」の宣伝部長として、ご紹介させて頂きました。次回は、「ワイン」も選びながら、シェフご自慢のお料理を食べたいと思いました。大木さんはなかなかこの場所が覚えられないということでしたので、大阪へ来られた時はいつでもご案内いたしますよ!!!(笑)千里ニュータウンも「紅葉スポット」がいくつかあるようです。気持ちの良い、昼下がりでした。唐さんは春から中央大学へ転勤されます。「スコーネ」のことを思うと、きっとおさびしいことでしょう!
2013/12/07
-

仁川カトリック教会と神父様への感謝…。
5年前に福江島を訪れた時に、今後、もう来る機会がないかもしれない…という寂しさがありました。その私に神様がくださったチャンスが10月5日からの長崎・五島列島巡礼の旅でした。甲子園教会で受洗してから信者歴は30年近くなりましたが、震災の道路事情で行けなくなり、仁川教会へ移籍してからはや18年です。仁川教会には私にとって身近な五島列島出身の司祭が司牧しておられ、浜口神父様(故人)や、永尾神父様には特にお親しくして頂きましたし現在は水浦神父様に導いて頂いています。いつもミサのオルガンを労ってくださる水浦神父様が、それを察して昨年のうちから、「岡本さん、来年楠原教会の献堂100周年の記念ミサがあるので、一緒に行きましょう。日程が決まったら知らせますからね…。」と声をかけて頂き、願ってもないチャンスに「万難を排して参加する」ことを心に決めていました。今年になって提示された予定日は、高岡万葉まつりと重なっていましたが、1日のずれがあったので、高岡は初日に朗唱の出演をして帰宅、翌日「五島列島巡礼の旅」に出発しました。私の五島の旅はいつも福江島の三井楽町の「万葉イベント」が目的でしたので、今回水浦神父様と旅した「巡礼の旅」は、今までと違った角度で「五島列島」を学ぶことができ、かくれきりしたんの里として、迫害を受けたり棄教を迫られる中、教会や史跡を通して信仰を貫き通した先人の生きざまにあらためて感銘を受けました。先日の万葉講演のヒントとなったことも多くありました。そして、水浦神父様のご出身の水ノ浦教会の教区の楠原地区に念願の教会堂が建てられて100年ということで、献堂の感謝のミサが捧げられました。長崎から司教様も参列され、いつもは静かであろう教会の周辺は、信徒、訪問者、私たちのような巡礼者で大賑わいでした。 折しも台風23号が通過し、24号が到来する間の「佳き日」でした。奈良女の後輩、洗川さんのご家族も楠原教会の信者さんでした。この巡礼の旅があって、その後、1か月後に「三井楽町」へ伺えたことが、私には本当に偶然ではないようなお恵みを感じております。「初めての巡礼の旅」に導いてくださった水浦神父様に心から感謝を申し上げたいと思います。同行の仁川教会の信者さんとお親しくなれたことも幸いでした。その仁川教会のご厚意で、信者以外には使用することのできない、仁川学院のコルベ講堂で大岡美佐さんが、コンサートを予定しています。素晴らしいパイプオルガンがありますので、私のオルガンの師である尼子愛子先生に演奏をお願い致しました。多くのご協力を得ながらコンサートを開催できますことを感謝しております。この機会をもって、彼女は万葉うたがたり会から脱会することになりました。この会場、場所を提供できたことが、結果的に私の最大のはなむけとなりました。数年間、万葉うたがたり会の歌姫として皆様に可愛がって頂きましたことに御礼を申し上げ、「私の聖地」で素晴らしい足跡を残されることを念じております。
2013/11/22
-

魅力がいっぱい、三井楽町。
ブログの記事もなかなか時系列で書けないのですが、FBに「三井楽万葉まつり」について写真中心にご報告しましたので、ブログでもう少し書き加えます。三井楽町は平成17年の市町村合併まで、福江島の中でも独自に「西の果ての万葉の里」として地元発信を努力しながら続けて来られました。万葉ファンの誘致をはじめ、施設や環境作りにも取り組まれ、犬養先生の揮毫歌碑建立や遣唐使ふるさと館の建設、地ビール産業など、平成の時代とともに地道な努力が実を結び、有数の万葉故地として、しっかりと定着しました。私たちも万葉うたがたりコンサートを3回させていただいています。しかし、合併により五島市となってからは、市の一部地域となり、今までのような独自で個性的な活動ができなくなったばかりか、経済的な負担の精算などで、町の活気が失せて行きました。平成20年に私が個人的に訪れた時には、遣唐使ふるさと館は「道の駅」と呼ばれ、お土産ものであふれていた棚が半分くらい空っぽで、その代わりに福江港のターミナルが玄関口として、大変立派になっていたことを思い出します。今年の夏頃に、かつて役場で中心になって町づくりを果たされた谷川さんから連絡を頂き、五島市となってから、三井楽町は「万葉まつり」として参加しておられた2月の「椿まつり」も市の方針で、今後行事がなくなるかも…ということに対して、妥協しながらやってこられた行事がいよいよなくなってしまうことの危機感と、もう一度地元の活性のためにも私たちのような全国に広がる万葉ファンの協力を仰ぎながら、再び三井楽町の有志を中心にがんばっていこうとしています…と伺いました。そこで私には急遽11月に行うことになった「万葉まつり」の講演者を推薦してほしいという依頼でした。私も候補の一人ではありましたが(笑)、急な行事の決定で、秋の行楽シーズンは既に予定の詰まった人ばかりでした。私も打診された2日間の予定では無理だったのですが、17日だけなら…と16日に深夜便の博多からのフェリーでならば、17日の出演は可能と言うことを申し上げていましたら、白羽の矢が…それでチャンスを頂いたわけです。講演内容には「いつも皆が聞いて知っているような話(荒雄かな)ではなく、これからの三井楽町のためにヒントとなるような話などを中心に…」とご希望がありました。内容はずいぶん自身で検討しました。結果、私の話が皆様にどのように伝わったかは気になるところですが、反対に朝から予定されたプログラムは、子供たち中心に作られていましたが、それぞれになかなかレベルが高く、おそらく地元では子供たちにしっかりとふるさと教育が行われているのだと言う実感を持ちました。その潜在力を如何に育て生かすかがこれからだと思いますし、並行して、地ビールに替わる焼酎生産や、電気自動車のレンタルや、しまとく通貨という金券サービスなど、五島市の新たな取り組みに、三井楽町も対応して、環境・設備面でも変化を遂げようとしておられる途上であることを垣間見ました。人も環境も整いつつあります。私自身がこの機会を楽しみにしていたこともありましたが、4年前に訪れた時からは明らかににぎわいがありましたし、みいらくの遣唐使ふるさと館は「五島市」の象徴である!という言葉をもれ伺い、あらためて心強く思ったことでした。遣唐使の寄港地、万葉歌の荒雄伝説、五島の椿、そして極めつけは天智天皇の「むべ」でしたね。きりしたんの隠れ里として有名ですが、古代からの歴史がいっぱい刻まれた、やはりここは「万葉のふるさと」でした!!!
2013/11/21
-

2014年度版「猪名川万葉植物園だより」カレンダーに寄せて
つらつら椿株式会社で制作致しております、万葉花カレンダー「猪名川万葉植物園だより」も今年で4刷目の2014年版ができあがりました。このカレンダーの制作を思い立ったのは、それまで20余年の長きにわたってお親しくして頂いていた、山口県下松市の万葉花写真家の岡田憲佳さんが、毎年素晴らしい「万葉花カレンダー」を制作しておられました。私もカレンダーに限らず、絵葉書や万葉花を網羅した文庫本や、岡田作品が大好きでした.「岡本さん、万葉花の撮影は自然光で、朝にだけ撮影するのですよ。」と、自然に咲く花の美しさや表情を、自然のままに撮り続けることにこだわっておられました。そして私はいつものように、「岡田さん、今年のカレンダーはいつできあがりますか?」とお尋ねしたのが3年前です。お電話の向こうで「岡本さん、もう高齢になってしまって、今年から作るのをやめました。」とのお返事にはしばし絶句しました。その後、今年5月にご逝去の報が届き、何とも言えない寂しさがございました。「万葉カレンダー」がもうないのだというショックと、私も毎年岡田作品を自分の作品のように自慢げにご紹介をしていましたので、それを楽しみにしてくださっている方々からのお問い合わせもありました。それが「TSUBAICHI猪名川万葉植物園だより」の制作を思い立ったきっかけです。岡田憲佳さんのカレンダーは、もはや「芸術写真、作品」でしたが、私は恩師犬養孝先生のご功績のひとつである『万葉集』を身近に広めることが、万葉カレンダーの魅力、発信力でもあったと思っておりましたので、なんとかならないものかと思いました。幸運なことに、大先輩でいらっしゃいますが、同じ犬養先生の門下である、木田隆夫さんが、定年退職されたのち、自宅の山林に万葉植物を植栽され、今では100種類以上の万葉植物を愛情を注ぎながら育てておられますが、四季折々楽しめる万葉植物園として、私たちにも公開してくださっていました。ひょっとして万葉歌に関わる草木花を猪名川万葉植物園のご協力でご紹介できるのでは・・・と私が手探りで制作をさせて頂いてからはや4年目となりました。写真家でもあり、自ら印刷会社を経営しておられた岡田憲佳さんの「カレンダー」にははるか及ばないものですが、万葉花を愛する私たちの思いを託した、また万葉歌で、古代人が植物に寄せて詠った心情を少しでも理解して頂けるのではないかとこだわりを持って作らせて頂いたカレンダーです。岡田憲佳さんが亡くなられた今、「万葉発信」の遺志を引き継がせて頂いているという自負を持って、あらためて感謝と追悼の意を申し述べたいと思います。「岡田さん、ありがとうございました。」そして一人でも多くの方々に一年を通じて楽しんで頂ける万葉グッズとしてお求め頂ければ、幸いに存じます。 こだわりの「椿」の表紙は、友人の朝熊純一さんが書いて下さいました。多くの方々のご協力、愛情のつまった作品ができあがりました。
2013/11/20
-

父の誕生日
10月20日は、美智子皇后のお誕生日の方が有名ですが、実は私の父の誕生日でもあり…(笑)。五島列島巡礼の旅から、あわただしく時間が過ぎましたが、今朝1カ月ぶりのオルガン奏楽のお当番で、ようやく所属の仁川教会のミサに与ってきました。旅で少しお親しくなれた水浦神父様にもお目にかかり、ホッとしました。2週間のうちにすっかり秋寒の雨の朝となり、家を出てからやっと明るくなったくらい…。時は流れていきます。いろいろお祈りすることがありました。高岡・五島・東京と予定通りにすべてのことがはかどったこと、犬養先生の命日祭を無事終えて、谷中で報告できたこと、留守中の深堀神父様のご逝去、うたがたりのこと、今になって信頼関係の揺るいだ私の未熟と無念、体調…と感謝や、お見守りやお恵みを願い、回心や…とあれこれ抱えての御ミサですが、ちょうど父のお誕生日に教会へ行けたこともありがたいことでした。満85歳になった父、来年も元気でお誕生日が迎えられますように…と心から思います。教会では10月は「ロザリオ」の月。私のご奉仕した7時ミサのあとは、9時から子供ミサがおこなわれますが、きょうは「ロザリオ祭」で、子供たちがかつぐ「マリア様の輿」がおいてありました。とても華やかで美しい!しばし見とれていました。 きょうのクリス神父様のお説教も「マリア様と共に歩んで頂き、神に近づく…」。聖母マリアは、本当にすべての人々の「お母さん」です。聖堂にもマリア像が飾られ、ライトアップにはちょっと驚きましたが(笑)、象徴的だったので、電気も消された聖堂でしたが、写真を撮らせて頂きました。 では、今から出勤します! 今日はサロンレンタルですが、「発表会」で子供たちの発表だけでなく、講師演奏もあり、ヤマハ音楽教室の頃の賑わいを髣髴とするような1日になります。いろんな音楽に浸って心の安らぎを得られるのは、本当にオーナー冥利です(笑)。
2013/10/20
-

やっぱり『万葉集』は魅力的!
萬葉学会の感想を少し…。10月12日(土)初日は講演があり、「乾 善彦先生の万葉集仮名書歌巻の位置」と 「品田悦一先生の畸形の文法~近代短歌における已然形終止法の生成」を 拝聴した。 乾先生は『万葉集』の仮名を分析され、表記の個性や木簡資料との差異、部立ごとの特徴など、字母の細やかなお話から、構成、成立論にまで及ぶ考察に、今更ながら「研究の視点」を学んだ。品田先生は、近代短歌歌人の一人「斉藤茂吉」研究で、すでに著作もおありだが、講演では、近代短歌に多く見られる疑似古典語法とも言える「文語」に着目され、万葉の言葉を使いつつも(お手本のようにしながら)その言葉の既成概念からいかにして遠ざかるかという斉藤茂吉作歌の手法などを伺ったが、元をただせば『万葉集』で見られる文法の形があって、近代の短歌表現にどのように享受されているかという興味深いお話だった。 翌日は朝から、研究発表があり8人の方々の発表を伺った。特に興味があったのは昨年学会に入られたとおっしゃる帝京大学の木下先生で、ご専門は薬学の方である。昨年の石見の臨地研修旅行でお知り合いになった。そして、今年早速に発表される題が「日中間で見解の異なる海石榴はツバキ・ザクロのどちらか」と「海石榴市」にこだわるオカモにとっては大変興味あるものだった。萬葉学会では初めてパワーポイントが用いられ、資料に加えて花の写真や図などを説明してくださり、ユニークな発表直後には思わず拍手が起こったほどだ。私も椿は中国になく、中国へ輸出されて字があてられたというのは聞いたことがあったが、遣唐使の携えた天皇からの献上品の一つに「椿油」があったことや、中国にはない椿の花によく似た「石榴」が、海外から取り入れたものとして「海石榴」という字が当てられたのでは…とか、また、中国の文献などを参考にしながら、本草学と文学表現から「ツバキ・ザクロ」の考証を伺い、私も直前にちょうど五島列島へ行き、隠れキリシタンのバラに代る貴重な花として自生する「ツバキ」の話を聞いたばかりであり、日本古来の貴重な植物であったので、花十字として信仰されたことや、三井楽町には遣唐使ふるさと館があるが、ツバキ油が遣唐使の持参した高級贈答品であったことにひとり感心し、私の中での共通の話題に驚くばかりであった。木下先生ありがとうございました。 また、学生さんや万葉学者に交じってUCLAからトークィル・ダシーさんとおっしゃる米国の研究者が「万葉集巻1・2の歌がほぼ年代別に配列されているか」という、成立論について発表された。流暢な日本語にも安心したが、歴史とは天皇の言行、言動を中心とした世界であり、万葉歌の配列がそれによって意図的に編纂されているのでは…と年代順と別の系譜の論理が働いているのではないか…と発表された。日本人であってもなかなか理解のむづかしいことを、外国人研究者もこうして日本文学について研究をされているのだとうれしく思いながら聞き入った。 その他、宣命の文章が何を参考として作られたかという考察や、人麻呂歌から詠む女性像や『懐風藻』の序から、編者の知識や教養の出所を中国文献を検索して考察してみる発表や、古写本の「読み」や歌の配列を検証したり、本当に『万葉集』の切り口というのか、いろんな角度からの研究対象になり得る引き出しの多い、魅力的な「歌集」なのだと改めて感じた。私は「万葉愛好家」と自認しているし、客観的に『万葉集』についていろんなことを知りたいという立場なので、質疑応答で、研究の内容・方法・発表について様々なアドバイスがなされる様子を見ながら、多様な話題を素朴に聞いて楽しませて頂いた。 代表の内田賢徳先生のご挨拶にもあったし、私も同世代なので漠然と感じたことだが、かつての著名な万葉集研究者の引用が少なくなり、それだけ研究も進化したということなのだと思うが、私も少しさびしく感じた。また、芳賀先生が辛口で今後の研究に対する姿勢として、文献の扱いや研究の視点をどこにおくか…ということなどを語られたが、個人にではなく、確かに今の若い人たちには大事なことだと思った。先人の苦労を思えばコンピューターの普及や資料の豊富さなどで、研究が安易に作業化していないか…と実際に思う。時代を経て、萬葉学会も徐々に変化しつつあるのだろう。わたしも大いに刺激を受けて帰宅した。やっぱり『万葉集』って楽しい。 帰宅した翌日、14日の朝、最期の朝顔が咲いて「おかえり」って迎えてくれた。花の形も変形したいびつなものだったが、とても愛しい。最後までつきあってくれてありがとう!
2013/10/17
-

谷中墓参
9月28日に西宮神社で犬養孝先生の15年命日祭を終えたことは、HPのトップページでもご報告した通りです。そして、ちょうど10月に東京大学で萬葉学会が予定されていましたので、上京の折に谷中の墓参を楽しみにしていました。平成10年10月3日がご命日ですので、タイムリーでもありました。私にとっては上野駅からもはや歩きなれた道です。 ちょうど3連休ということで、墓地内の各所で「谷中まつり」が行われており、お花見と言い物見遊山のスポットでもある「谷中墓地」の微笑ましく庶民的な様子を改めて実感しました。帰りは日暮里から駒込経由、東大前へ。谷中墓地から紅葉坂を下って…。 東大というのは、4年前に甥の卒業式で、さも親のような顔をして参列しましたが、その時も犬養先生の「学び舎」を追憶したくて、赤門をくぐったことを思い出します。昨年2013年の萬葉学会が、東京大学で行われる予定を聞いた時、「萬葉」が東大で語られる機会が訪れたことと、母校でもないのに懐かしい気持ちがしました(笑)。ピアノのレッスンで2回東大に来たことも理由のひとつですが…。 東京大学文学部棟。広い構内で会場にたどり着くまでに、もう銀杏の落ちている銀杏並木を抜けたり、初代学長の石造の前を通ったり、また、大学の新たな施設建設のために、発掘調査をされているところもありました。 レンガの積まれたあとや、井戸など、歴史的遺物のようです。東大は関東大震災でもその後の火災等で、図書館の書物が焼けてしまったり、資料が消滅してしまったり…と痛手も多かったそうですが、偶然に持ち出されて唯一残っていた校本萬葉集」の版に用いたと思われるゴム印を学会当日、特別に公開してくださいました。会場校としてご挨拶をしてくださった月本雅幸先生が、以上のような話題や、大学図書館の震災などを経て歩んできた歴史や、残存の貴重な資料のお話など、大変矯味深いお話を流暢にしてくださり、とても印象的でした。 私は亀井君(東大法学部卒)の大学で合唱の伴奏をするのに、ピアノのレッスンに2度伺いましたが、学生会館には、複数のグランドピアノがあり、その時に音大でもないのにすごいと思いましたが、なんと文学部の教室にもやはりヤマハのグランドピアノが置いてありました。品田先生の駒場にはパイプオルガンもあるとか。とても贅沢な設備がうらやましい。 懇親会で、月本先生もドイツで10年ほどピアノレッスンをされたと伺い尊敬してしまいましたが、東大の男子学生の二人に一人はピアノ経験がある…と聞き、勉学と両立する優秀な子どもたちの現実?に、改めて東大生は教育環境の恵まれたこどもたちでもあることに羨望がありました。肝心の学会の内容については…、またあらためて感想を書くつもりです。谷中で犬養先生と再会することから始まった東京の旅は、帰りの新幹線に乗車する前に親友とも再会できました。昨年還暦旅行で帰りに撮った「東京駅」。やはりライティングされて、きれいでした。私のようなオノボリさんは写真を盛んに撮っていました。もちろん私も! 「KITTE]という旧東京丸の内郵便局をリニューアルした商業施設で食事をして、つもる話をしましたが、時間切れ…。また来るね!と約束をして帰途に…。彼女のお誕生日の前日でもあり、少しでも会えてよかった。再び東京駅での記念写真です。充実した1泊2日の東京。翌日の臨地研修はキャンセルして、翌日のTSUBAICHIでのサロンコンサートの準備のため帰宅しましたが、楽しかった!!!
2013/10/16
-

凛とした強さを学ぶ・・・。
今朝の朝顔です。 きょうも2輪咲きました。1本の茎だけのお花なのに10輪は数えました。遅咲き、晩稲…tと表現してFBでご紹介してきましたが、この時期に咲くことの稀少価値より、「ど根性」に近い生命力だけに私自身が驚きとともに、力づけられているという毎日です。昨年やはりほったらかしていた鉢から「桔梗」が育ち、紫と白の2本だった桔梗が、仲良く「白地に紫色の斑が入った桔梗」が1本咲いたことをブログでご報告しました。そのようなズボラな私がやはりほったらかしていたフラワーボックスから思いがけず見つけた「二葉???」普通なら、種をふやかし、それから土に蒔いて育てる「朝顔」の手順もないどころか、この水不足、暑い夏を超えて8月に二葉を出したこの「力」に私はなんだか、愛しくて、健気で、孤高の「強さ」にすごく感動したのです.1本だけの細い細いツルで9月半ばからほぼ毎日咲いてくれます。もうそろそろ終わりかな…とまだまだついた小さなつぼみを確認しながら「ありがとうね」と話しかける毎日。1日のはじめの清らかでさわやかな「気」を私に伝えてくれていることに感謝しながら、来年こそはきちんと「朝顔」を生育する心機一転を図ります(汗)。
2013/09/28
-

西宮えびす神社観月祭。
今年の仲秋の名月は、望月と満月が一致する貴重な「月」であったようだが、等彌神社の観月コンサートの宵から、連日晴れ渡った空に「月」が美しく輝き、19日の当日までに毎晩帰宅の夜道が、心弾んだことだった。その9月19日当日には、西宮文化協会のご依頼で、西宮えびす神社の観月祭の後の、夕食会「月見の宴」で、万葉うたがたり会のゲスト出演の機会を頂いた。時間的、また場所的条件からも考慮して、今回は万葉うたがたり会を代表して山口ひとみさんに出演してもらった。ピアノ伴奏も山口さんと呼吸の合う宮川真由美さんにお願いし、万葉曲と秋の風情を味わって頂く音曲をご披露した。 観月祭は、一般公開で、本殿の前に集合。まだ薄暮だったが、吹き抜ける風が心地よかった。 午後6時から祭典が始まり、神官により祭壇に供物が並べられ、祝詞の奏上などのご神事があり、その後、奉納の舞楽「原笙会」の女人の舞を初めて拝見した。友人のお嬢さんが社中におられたり、噂には聞いていたが、このたびご招待を頂き、じっくりと鑑賞することができたのは幸運だった。 古代衣装の女性4人による「柳花苑」の舞いと、またかぐや姫の「平安の舞」は、現代曲(東儀秀樹氏の曲)でアレンジされた舞いで、メロディーのある雅楽もよかったし、私たちはしばし女性の舞いのあでやかさと、時代を異にした幻想の世界にひきこまれたような気がした。かぐや姫は、衣装も時代もコラボしたかのようなファッション?にも見えて、舞楽と言えど、現代を意識した形への試みをされているかのようにも思えた。 関係者なのか、女人舞楽のファンなのか、ビデオやカメラで撮影をされている人も多く、私も隙間からようやくとれたショットだった。この観月祭が一般に公開されていることを知らなかったので、もっと多くの方々にも知らせてあげて、この風雅なひとときをみなさんにも味わって頂きたいものだ。ただ、ご神事・奉納の舞いで、宴席が遅れたため、山口さんのステージの開始が遅れ、準備していたアンコール曲がカットされたのは残念だった。でもお食事は、東京竹葉亭の「お月見特別料理」。御馳走様でした。帰りの月も美しく、今年の月夜は本当に素晴らしい中秋の名月だった!
2013/09/23
-

仲秋の名月、2題
今年は、奈良県の桜井市とご縁が深くなり、5月には、桜井市市民会館を守る会の総会で、講演をさせて頂いたり、先日は「大和さくらい万葉まつり」で古代衣装パレードの出演があったり…と2年前から三輪恵比須神社で万葉講座をさせて頂いていることから広がった輪でしょう、まさに「海石榴市」のえびす様に感謝です。三輪恵比須神社のご紹介もあり、桜井市外山(とび)にある等彌神社の佐藤宮司より、仲秋の名月に行われる6回目の「観月コンサート」に万葉うたがたりの機会を頂きました。実は私は「とみ神社」は知りませんでした。鳥見山が榛原から見える山だと思っていたので、桜井の鳥見山のふもとの等彌神社をこの度しっかり認識することができ、幸運でした。人も集まりやすいように、毎年「敬老の日」と決めて行っておられますので、月齢には多少誤差があります。 リハーサルを終えて見えた月です。3日後に満月の夜を迎える月です。この抜けるような青空も、これは前日からの台風18号の日本全国に絶望的な被害や影響を与えながらの翌日、台風一過のウソのような光景です。朝から雨も残り、テレビでは近畿一円「大雨洪水警報」は発令され、渡月橋の周辺の桂川の氾濫を目にしながら、「きょう、本当にやれるのだろうか…。」と半信半疑で2台の車に分乗して、万葉うたがたり会は現地に向かいました。途中淀川の河川敷も水につかっていて、びっくり仰天。しかも淀川大橋からこの状況を写真で写そうと言う人たちの姿も多く…!?確かにめったにない光景が広がり、私たちはますます戦々恐々の気分でした。台風の後は、手のひらを返したような穏やかな日となり、神社の中では、コンサート決行のためのあわただしい準備がなされました。雨でずぶぬれのところからの舞台づくりで、神社の方々も氏子さんも、またイベント会社の方々も内心はおだやかではなかったはずです。みなさんのおかげで、お客様も集まってくださり、時間通りのスタートとなりました。その後は、「楽しかったコンサートのひととき」です。 コンサートの後に「サンバDEツバキ」が聞きたかった…と言う声を頂き、ありがたく思いましたが、今回は初めて聞かれる方への導入もあり、オープニングは「月の歌」メドレーでスタートしましたので、ごめんなさいでした。40分の時間を頂き、夏の夜の夢・ムーンライトセレナーデで「月」を思って頂き、あとは「桜井市」を意識して三諸の子守歌、「忍坂」の風音を聞いて頂きました。 そして今回は、等彌神社…と言うことで、万葉歌碑もある「跡見山雪」の歌を是非作曲して記念にプレゼントしたいと思い、新曲「ホワイトロマンス」という曲をご披露しました。恋の歌なので、若々しく大変軽やかなポップス調の曲になりました。またみなさんに手拍子を頂きながら、歌えたらうれしいことです。最後まで多くのお客様に残って頂き、ご一緒に出演した岸さんや大西さんに、佐藤宮司も加わって全員で「ふるさと」を合唱しました。この等彌神社の近くにお住まいの方々をはじめ、鎮守の森で、音楽を通して満月を愛でながらふるさとに心を寄せるなんて、なんて贅沢なのだろうと思いました。月は時間とともに高くのぼり、神社の杜の木々を通してこんな様子に見えました。 本当に「月のかつら」を髣髴とさせます。神社の池にも映った月を佐藤宮司さんに教えて頂き、思わず歓声! 2つの月を楽しませて頂きました。「月がとっても青いから、遠回りしてかえろ♪」…いやいや、自宅に直行して11時半でした。長い激動の一日。終わってみれば穏やかで心豊かな時間だけが印象となって残っています。
2013/09/22
-

誕生日を迎えて・・・。
どうしてもブログに書いておきたいことがあった。沖縄旅行のことだ。FBには、小出しで、旅の思い出を切り取って、早々に友人・知人たちに披露したが、やはりこのたびの「旅」は、私たち親娘が、日本の歴史上、理解をしておかなくてはならない、実際に現地を自分の目で見てみたい「歴史と歩む沖縄」だった。戦時中を生き抜いた両親は、過去二人で日本各地をほとんど旅しているが、「飛行機」という母の苦手意識がネックとなり残念ながら「沖縄」だけ、旅していない。「戦争」の頃、やはり女学生だった母が、同じく沖縄戦にかり出された「ひめゆり」以下、同世代の方々を偲び、追悼したいという気持ちを持ち続けていることは、ずっと知っていたので、急場に決めた私たちの旅であったが、沖縄を選択したことを大変喜んでくれた。そして母の分も一緒に祈ってきてほしいと思いも託されていた。「お花代」まで預かり、親子3人の思いを胸に「沖縄」に向かった。もちろん久しぶりに親娘でバカンスを…と思ったものの、お互いの共通の時間を作り出すことが、並みの苦労ではなく、この2泊3日が限度だった…。でも行き先を「沖縄」に決めた時に、「美しい海・沖縄料理・美ら水族館・ぜいたくな宿」など、旅ならではの希望と共に、「沖縄の戦地に佇む」ということについては、娘と自然に共通の目的であったことは、うれしいことだった。折しも8月15日の直前には、テレビ・新聞などで「終戦特集」の報道が多く特集されたが、いつもならば特別な意識をせずに見ていたニュースも、さすがに旅を「沖縄」に決めた後はとても気持ちが惹かれた。特にTBSの『テレビ未来遺産“終戦”特別企画 報道ドラマ「生きろ」~戦場に残した伝言~』と言う、今も「沖縄の神様」と慕う人たちがいる戦中最後の沖縄県知事、島田叡(あきら)の実話のドキュメンタリードラマを見たことも幸運だった。沖縄に降り立って、レンタカーでまずひめゆりの塔のある南部地方糸満市へ。 左後方は、併設されたひめゆり平和祈念歴史館。女学生の証言集などを見ると、あまりのむごさと、淡々と綴られた日記の重さにあらためて沖縄戦の犠牲を無念に思う。 母の分も娘とともに、花を捧げ、やっと現地に立てた実感を感じた。引き続き摩文仁の丘へ。県の平和記念公園として、資料館、塔など、多くの関連施設が、建てられている。そして出身県で分類された墓碑銘の場所は、テレビなどでよくみていたはずだったが、正面の抜けるように青い空、青い海、広がる水平線に、本当は静謐な島であるということを思い知らされた気がした。 二人で黙って海を見ているだけで、不幸な歴史とうらはらな素朴な島、沖縄を思い、怒りや悲しさがよけいに募ってくる。戦争はなんだったんだろう。沖縄戦はなんだったのだろう、と思う。 そして、沖縄県知事の記念碑へ。島田さんのご遺体?は見つかっていないそうだ。終焉の地とされている。兵庫県出身者であり、兵庫高校と聞くと身近な感じがした。 沖縄戦で、沖縄の人たちは米軍ではなく、日本兵のための犠牲となり多くの人が亡くなった。翌日、首里城や今帰仁城跡などを見学し、沖縄が「琉球王国」としての独立国の遺跡が多く残っていて、御嶽と言う祈りの聖地や、聞得大君という女王国である独自の信仰や風習の残っているのを見て、感心した。沖縄県に本土復帰は果たしてよかったのか。世界遺産にも登録されているが、琉球固有の文化や遺跡に今回魅せられた。当初、想像していた喧騒も全くなく、嘉手納基地のそばを通った時だけ、米軍基地の規模や、近さや、Yナンバーの米兵の車なども見たが、2泊3日で回った沖縄は、最高の空・海・自然美に恵まれた素晴らしい風土だった。時々にふれあう沖縄の人々は、愛想がよくて、優しく親切だった。そして観光で賑わい、潤う島であることは間違いはない。そう思うと基地移転などもってのほか、これ以上環境破壊をするべきではない。基地問題も微妙だが、「撤去」が望ましいが、まず「凍結」。辺野古へなんてとんでもないような気がする。沖縄の人たちの島の誇り、観光立国の沖縄を思うなら、現状維持しかないのかもしれない。テレビでよく見る大規模集会は本土からの人が多いと聞いた。私たちが感じた古い琉球王国の名残の多い島、沖縄は、道州制が叫ばれている今こそ、「独立国家」としての狼煙を上げたいくらいだ。戦争の爪痕が色濃く残り、払拭したいのに、未だに「戦争」のための米軍基地として甘んじなければならない沖縄の現実に、同情もある。でも私たちにとっては、穏やかな島、美しい島として大ファンになった。また是非訪れたいと思っているし、娘とは2月の残波岬のタイガースの春季キャンプに来てみたいね!なんて…。万葉と同じ、現地に立って理解できることの多さに教えられた旅だった。
2013/09/13
-

もうすぐ4才
久しぶりに対面。母のベッドの抱き枕の上が、お気に入りのはな。なんとなく、優雅にいや、怠惰に過ごしている風情。 はなにいつも、なんでも譲りっぱなしのひなは、籐椅子の上でお昼寝。椅子の色目が濃いので、写真的にはよくないですが、パチリ。 秋冬ファッションの先駆けで、毛皮の私たちですが、残暑お見舞い申し上げます。いや、もう暦ではすっかり「秋」でした!
2013/08/24
-

8月25日(日)サロン講座のご案内。
4年目となった、中西久幸さんの「和歌世界の散策シリーズ」と銘打った、この文学講座も毎年世相や、歴史の注目度に呼応して、タイムリーな話題を提供して下っているが、今年はNHKの大河ドラマが、「八重の桜」という新島八重を取り上げていることもあり、人物についての学びもあったが、特に「和歌世界のさくら」についてお話をして頂いている。今回は「桜シリーズ」の3回目で、今回は特に季節も合わないことに中西さんはひたすら恐縮されたが、私たちは、最終回を楽しみにしている。資料では1、「春雨と菜種梅雨」2、万葉集の「春雨」3、勅撰和歌集の「春雨」そして、4、「さくらこ」伝説等、お話をして頂くことになっている。また、おまけに、先日話題に上った「君が代」についても和歌の見地から解釈をしてくださるそうで、私は講座後の議論が今から楽しみでもある。TSUBAICHIの誇る文学カルチャーに、ぜひお越しくださいませ。
2013/08/23
-

桜井市等彌神社の大學百合まつり
9月16日(月・祝)に、神社の境内で、神社主催の観月の夕べの宴がありますが、万葉うたがたりコンサートをさせて頂くことになりました。実は私、「とみやま」という山は、万葉で宇陀郡榛原町の鳥見山しか頭になかったので、ご紹介頂いた時に、「???」という状況だったのだが、諸説ある1つに桜井市の「とみやま」説があり、下見に伺った時に、西麓に立派な規模の大きい等彌神社があり、あらためて、神社や、背景や、いろいろ興味がわいた。その時に、8月17日に「百合まつり」があると聞いていたので、気になっていたので、前日から出かけていたが、その足で神社に向かった。 この百合は「高砂ゆり」という種類で、この時期に咲く。奈良の率川神社の「百合まつり」は有名だが、こちらはササユリで、6月17日に行われる。なんでも堀口大學という明治生まれの詩人が、ゆりの種を寄贈されたことから、神社で大事に育て、毎年花を咲かせる時期に記念して、「大學百合まつり」を行っておられるそうだ。自生している百合も多い中、拝殿の前に、奉納された百合の鉢が並べられていた。参道の入り口には、文学碑が並んでいる。 佐藤春夫の句碑 佐藤春夫、堀口大學の友情文学碑 堀口大學の歌碑 そして、大學の句碑 …と、駐車場横に並んで建っているが、もちろん神社の中に万葉歌碑が3基建立されている。私の大好きな百合の花のお祭りというのが、うれしかったし、猛暑のさ中であっても杜を吹き抜ける風は、爽やかで心地よい。ホームページのトップにあげた写真は、ゲスト出演の桜井混声合唱団の方々…。演奏には間に合わなかったが、素敵な舞台の姿をとらえることはできた。良かった! お月見の演奏に向けて、ただいま「跡見山雪の歌」新曲を製作中。間に合いますように…。夜半のコンサートですが、奈良方面の方々には是非、お越し頂きたいと思っている。
2013/08/22
全746件 (746件中 1-50件目)
-
-

- 楽器について♪
- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…
- (2025-11-23 00:18:07)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- サーカスパフォーマーまおのライブ
- (2025-11-23 13:17:54)
-