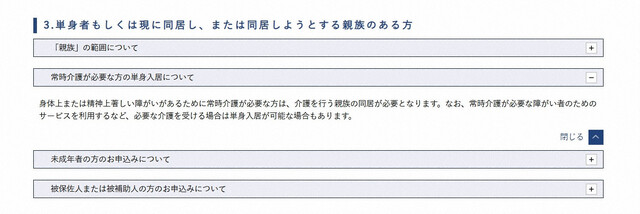六章
[六章]
「おとうさん、おとうさん、目を開けて。 おとうさぁん」 昇は遠くで呼ばれているような気がして振り向いた。
そのとたん目が覚めた。
見慣れない物が目に入り意識がもうろうとしていた。
心配そうに覗き込んでいる直美の顔があった。
「ああ、今起きるから」と答えると「起きなくてもいいのよ。やっと気がついたのね」と直美が言うので
「何言ってるんだ。すぐ起きるさ。夕べはろくに飯食ってないので腹が減った」と言って起き上がろうとすると
頭がズキッとして体中が痛かった。
直美は泣き出して「お父さん、よほど打ち所が悪かったのね」と言った。
そしてナースコールをして看護婦に「今、気がつきました」と告げた。
すぐ看護婦と医者が部屋に来た。
医者は「ここがどこだか判りますか」と尋ねた。
直美が「先生、主人は判ってないようです」と昇の代わりに答えた。
医者は「奥さん、大丈夫です、大丈夫です」と言って直美をなだめた。
そしてもう一度昇に向かって「ここがどこだかわかりますか、田中さん」と尋ねた。
昇は「病院のようですが、どうしてここにいるのですか」とけげんな顔付きで昇は聞いた。
医者は「あなたは昨日の夕方、奈良駅の近くで車にはねられたのですよ」と言って昇の顔を見た。
それからペンライトを当てて反応を診たり、舌を出させて診たり、胸に聴診器を当てて
診たりしながら「痛い所はありませんか」と尋ねた。
昇は「特にありません」と答えた。
医者が「座れますか」と言うので昇はベッドの上に起き上がろうとしたら、頭が重くて、割れそうなほど痛く思わず
顔をしかめた。
それを見て医者は制止する仕草をしながら「あっ、いいです、いいです。 そのまま寝ていて下さい」と言った。
昇は「先生、昨日私が事故に遭ったのですか」と尋ねると医者は「そうですよ。交差点で飛び出したのですよ。
覚えていませんか」と言った。
昇はそんなバカなと思いながら「いや、全く」と答えた。
心の中では「夕べは茂子と一緒に京都にいたのに」と思っていた。
「交通事故なんてそんなものですよ。 心配はいりません。 除々に思い出しますよ」と言って医者は昇を慰めた。
「すると、今日は16日ですか」と昇が言うと「そうですよ、もう大丈夫ですね。
心臓の方もしっかりしましたから」と医者は言った。
「奥さん、もうご心配はいりません。しばらく入院をしてゆっくりすれば体の痛みも取れて良くなりますよ」と直美に言った。
直美は「ありがとうございます。 あのう、お腹が空いたと申しておりますがどんな物を摂らせたらよいでしょう」と尋ねた。
看護婦が「もうすぐ夕飯のお時間ですからお粥が届くと思います。
それ迄、待てないようでしたらジュースでも差し上げて下さい」と言って二人は出て行った。
昇は狐につままれたような面持ちであった。
直美は涙を拭きながら「あなた、良かったわ。 このまま死なれたら私、どうしょうかと思ったわ」と言うので昇は
「何をバカな事を」と言った。
昇は「どうなったの」と直美に尋ねた。
直美は昇の顔を見ながらゆっくりと説明をしてくれた。
昨日、すなわち7月15日の夕方、昇は駅へ向かって急いでいた。
赤信号に変わったのに気付かず歩道から飛び出したという。
そこへ青信号になった側の車が発進をした。
ほんの少し接触しただけなのに昇はハズミで後へ転倒して後頭部を強く打ったらしい。
免許をとったばかりの若い運転手は驚いて降りてきたがグッタリしている昇を見てパニックになり、周りにいた人が
警察と救急車に連絡をしてくれた。
現場検証を終えて青年は父親を伴って病院へ来てくれたという。
外傷性のショックで一時的に脈が欠退して皆が心配したそうだ。
夜中の11時過ぎ頃に脈が安定を見せ始めたので子供達だけ家に帰した、と直美は言った。
青年は吉田圭一という19歳の学生であった。
その親子も夜中まで病院にいてくれたらしい。
直美は「突然飛び出された吉田君の方が迷惑をこうむったかも知れない」と言った。
そして「何をあんなに急いでいたの」と尋ねたが昇は「俺はそんなに急いでなんかいなかったよ」とふてくされて答えた。
「でも、見ていた人はすごい勢いで飛び出した、と言っていたそうよ」と直美は言った。
昇は事故に遭ったという事そのものが飲み込めなかった。
かといって京都の祇園祭の人込みの中にいたなど、とても言い出せない。
そんな事を言えばますます頭の具合が悪く思われそうだ。
今は直美も医者も気を使ってくれているので急いでいた事には触れてこない。
しかし昇は確かに祇園祭の人込みの中に茂子と一緒にいた。
どう考えても合点がいかない。
どういう事なんだろう。
いくら考えても判らない。
昇は傍にいる直美に「直美、俺は出かける時、どんな風に言ったかな」と尋ねた。
直美は「学生時代の友達から連絡があって急に祇園祭に行く、と言って出かけたわ。誰だったの。連絡をしなきゃ」と言った。
「去年は行かなかったかい」と聞くと「今迄、祇園祭のギの字も言わなかったのに帰ってくるなり祇園さんに行くと
言ったので驚いたもの。 初めての事よ。もう少し前から判っていたら私も子供達も連れて行って貰ったのにって夕べ、
お父さんの顔を見ながら話してたのよ」と言って直美はそこでクスクスと笑った。
昇は「何がおかしい」と聞いた。
「だって・・・」と言いながら直美は昇の顔を見て又笑った。
「頭を強く打ったからなのか、うわごとが多くて、そのうわごとも子供みたいでおかしくて」と言って笑った。
昇はドキッとして「どんな事を言っていたの」と聞いた。
「タコヤキ、だとか綿菓子、だとか、カキ氷、だとか、すごいね、とも言っていたわ。
何を見ているのかしらって話してたのよ」と直美は嬉しそうな顔で話してくれた。
昇は、体はこの病院にあったのに魂だけが祇園祭に行ったのだろうか、と思ったがすぐそんな非科学的な事を、と打ち消した。
今迄、昇は非科学的な事は信じなかった。
若い頃から弁証法だの科学的社会主義だの、唯物論だのと学習会や研究会に行って昇自身も講師を努めた事があるくらいだった。
この世の全ての物は科学的に証明できるものである。
科学的に証明できないものは何もない。 そんなものは人間が妄想の中で作り上げたか、
何かに洗脳されて思い込んでいるのに過ぎないだけの事である、と考えてきた。
しかし、今回のこの出来事はどうしても説明がつかない。
やはり頭を強く打ったせいなのか、と考えた。
しかし、駅に向かっていた事も事実だし、タコヤキだの綿菓子だの、カキ氷だの、のフレーズは確かに夕べ昇が口にしたものだ。
夢、うつつの中で単なるうわ言を言ったのに過ぎないのか。
茂子が待っているという事だけが脳裏にあってそれであんな幻の世界をさ迷ったのか。
昇は考えれば考える程判らなくなる。
昇は幻の世界でさ迷ったのに違いない。
あの、お香の店だって本当にあるかどうかも判らない、と思った。
しかし、待ち合わせの場所へも行かなかったから茂子は怒っているだろう、と思うと胸が痛んだ。
茂子は住んでいる所を東大阪のマンションとしか教えてくれなかった。
正確な住所も電話番号も教えてはくれなかった。
連絡のしようがない。
その内又、連絡があるだろう。
昇はそう思う事にした。
それより生徒達の成績表の作成が気になった。
直美にその事を言うと「校長先生が心配しなくていい。このまま夏休みに入って頂いて結構です。とおっしゃって下さったわ。
生徒達には心配ないのでお見舞いには行かなくていい、と言っておく、と言われたわ」と言った。
昇は「そうだった、俺がいなくても教頭も校長も他の先生もいるのだった」と直美に言うともなしに言った。
直美は「何をブツブツ言ってるの。それより静かにやすんだら」と笑いながら「メッ」としたがその顔は安堵からか綻んでいた。
そこへ夕食が届いた。
半流動食のようなお粥とペチャペチャした卵料理と梅干とお浸し、そして汁の多い味噌汁がトレーの上に載っていた。
昇は「こんなの、寝る迄持たないよ」と不平を言った。
直美は「贅沢言わないの。 良くなったらおいしい物を何でも作って上げるから」と言った。
一週間が過ぎて昇は退院をした。
[七章へ]
© Rakuten Group, Inc.