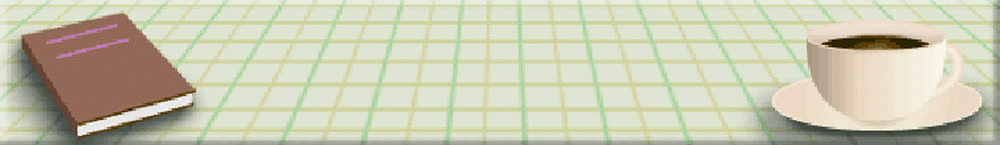改革全般に関する本
著者名:野中郁次郎 勝見明著
出版社:日経BP社
紹介:イノベーションの本質を人と組織の観点からとらえます。
感想:以下の点に共感しました。(2004年8月読了)
・「競争に勝つ」という相対的価値の追求は、勝った時点で消える可能性があります。これに対し、絶対価値の追求の根底にあるのは「自分たちは何のために存在するのか」という根本的な問いかけであり、それは普遍性を持って未来へとつながっていきます。
・「守・破・離」とは、武道や茶道などの日本の伝統から継承された概念です。「守」は基本の型を守り、模範どおり真似することです。最近日本の企業でもはやっているベンチマーキングは、まさしく守です。「破」は基本から抜け出し、試行錯誤して自分らしさを発見していく段階。「離」は基本から脱し、まったく新しい独自の型を創造し、生み出すことです。
・「非常識なことではなく不常識なことを、不真面目ではなく非真面目にやれ」とは創業者本田宗一郎の言葉だが、「常識を打ち破る」ことの大切さを説いたのも、既存の常識にとらわれない商品コンセプトへの挑戦を絶えず求めたからだ。
・「ホンダではお前の提案、夢ないなといわれるのがいちばん落ち込みます。われわれがつつかれた評価会も、チームが本気でお客さんに対して夢を提供しようとしているかどうか突っ込む。だから、評価会は裁判ではなく、これでいいのかどうかの意思統一会。ホンダでは最後は役員を含めて一丸になるのです」(井上)
・論争は、白か黒か、善か悪かという二項対立でものごとをとらえ、一方を抹殺しようとしますが、対話はこれとは本質的に違います。「私はこう思う」という人と、「いや、私はそうとは思わない、こう考える」という人が向かい合いながら、互いに対立する点を許容し合い、互いの長所をなるべく活かす新しい視点を見出して、より高い次元の命題を生み出し、限りなく真実を探求していく。こうした創造的対話こそが弁証法にほかなりません。
・同じ浜松で生まれ、二輪車メーカーから四輪車メーカーへと発展した企業にホンダとスズキがあります。ホンダが夢から入る目標志向の会社であるのに対し、スズキはコストダウンから入る目標志向で入り口は違いますが、共通しているのは、どちらも本質追求型だということです。スズキのコストダウンの背後にはやはり経営者のロマンや夢があり、十分に創造的です。
・元気のある経営者の多くは、最後は数字で目標を表現します。日産のゴーン氏も「日産リバイバル・プラン」やそれに続く中期計画「日産180」において明確に数値目標を設定しました。キャノンもキャッシュフローの数値指標を最も重視する経営を行っています。
・数字は、誰にもわかりやすい共通言語です。しかし、ただの数字を掲げるだけでは、誰も動きません。その数字の奥にどのような深い意味があるのか、そして、どこで生まれたのか。企業の意志、信念、ビジョン、思い、チャレンジ、戦・・・・等々に裏付けられ現実にもとづいたとき、数字は組織に明確な目標志向を根づかせることができるのです。
・アメリカの創造的企業3M社は、イノベーションに必要な役割として「メンター」「スポンサー」「チャンピオン」の三つを掲げています。
・メンターは個人的なつながりを持つ教師役、スポンサーは本人が正しい道からはずれないように責任を持つ人、チャンピオンは新しいアイデアを持って、まわりを説得し実現していく人、といった意味合いです。
・アメリカの研究者が実験を行ったところ、「世界の任意の二人は通常六段階程度の友人知人の連鎖でつながっている」ことがわかりました。つまり、知人友人を六人程度たどれば、世界中の誰とでもつながっている。これがスモールワールド・ネットワークの理論です。
・場のダイナミズムをナレッジマネジメントの面から見ると、ナレッジは与えれば与えるほど膨らむ性質を持っていることがよくわかります。
・リーダーが高質の暗黙知を持ち、その知識やノウハウをみんなにどんどん与えていく。それによって壁が次々ととり払われるとともに、組織の中で知の創造のうねりが生まれる。
・「最高の自社製品を時代遅れにする最初の会社になろう(Be the first to make your own best products obsolete.)」―これはアメリカの創造的企業3M社で語られている言葉です。日清食品に求められているのもこれと同じ自己否定の論理です。
・創業者松下幸之助の語録に、「お客様の欲しがるものを売ってはあかん、お客様の喜ぶものを売りなはれ」という言葉がある。
・ジブリが主客一体の「We are a part of the environment」であるとすれば、ディズニーは主客分離の「We are outside of environment」です。
・理念なき市場隷属のマーケティングと、理念を持ち実践しながら学ぶオタクとでは、どちらが強いか。顕在化したニーズは顧客に聞けばわかるが、誰が聞いても答えは同じになる。顕在化していない潜在的ニーズの地下水脈は、実践を通して自ら掘り下げながら見出す時代であることを、海洋堂の躍進は示している。
・「自分は何をやりたいのか」―この問いに明確に答えることのできる人がどれほどいるでしょうか。特に企業のミドル層以上の人々は、この問いを自らに向けて発すること自体があるでしょうか。
・日本の現状はどうでしょうか。多くの企業を回って感じるのは、特にミドル以上の層が「分析マヒ症候群」ともいうべき症状に陥っていることです。何かというとすぐ分析が始まり、「市場の状況はこうであり、競合他社はこういう状態にあり、したがって、我が社のとるべき最適なポジショニングは・・・・」といった具合に傍観者のスタンスで仕事と関わる。
・あるいは、自分の会社をことあるたびに批判する。リストラが進む中で会社に対する信頼を喪失し、夢も思いもなく、ただ人事評価システムから外れないようにと上からいわれたことを要領よくこなしていく。主体的な当事者意識の決定的な欠如、実存性の欠落、これが日本の企業が抱える最大の問題です。
・現場で直接経験する。媒体を極力排除し、リアリティに限りなく近づき、暗黙知の世界に入っていく。物語の主人公たちは、今の日本のミドルたちがどこかに置き忘れてしまった知の作法をごく自然に実践していました。
・セブンーイレブン・ジャパンの鈴木敏文会長兼CEO(イトーヨーカドー会長兼任)はことあるたびにこう語ります。「われわれの競争相手は同業他社ではなく、日々めまぐるしくニーズが変化する顧客そのものである」
・鈴木氏は社員たちに対して、「お客のために」という言葉を使うことを禁じているそうです。
「お客のために」と考えたとき、無意識のうちに過去の経験や既存の常識をもとに、お客とはこういうものだ、こうあるべきだと「決めつけ」をしているというのです。これは認識や分析の世界です。そして、うまくいかないと、「自分はお客のために努力したのに・・・・」と自身の認識や分析のズレは反省せず、顧客を責め始めます。
・こうなると、顧客にとっての理想の追求というイデアは消え去り、顧客をありのままに知覚することもなくなって、もはや仮説を生み出せなくなります。だから、大切なのは、「お客のために」ではなく、「お客の立場で」考え、明日の顧客が求めるものを探り続けることだと社員たちに繰り返し語るのです。
・『エクセレント・カンパニー』では、超優良企業の優れた点として矛盾を昇華する方法を知っていることが挙げられ、また、『ビジョナリーカンパニー』では、優れた企業は「オア(or)の抑圧をはねのけ、「アンド(and)の才能」を活かすべきであるとしています。
・オアの抑圧とは、逆説的な考えを受け入れず、矛盾する力や考え方は同時に追及できないとする二元論的な見方であり、アンドの才能とは、さまざまな側面の両極にあるものを同時に追求する、陰と陽を同時にいかなるときも競争させることであるとしています。(以上)
書籍名:カルロスゴーンが語る「5つの革命」
著者名:長谷川洋三著
出版社:講談社
紹介:いかなる変革も人間が中心であると説きます
感想:以下の点に共感しました。(2004年6月読了)
・会社の社長という者は、誰も本当にそうなるとは思っていないことでも自信を持って語る必要があります。大事なことは、実績で判断してもらうことです。当初の危機的な状況をわかっている人から見れば、実績を出すまでにどれほど苦労があったかわかるはずです。変化のきっかけは動き出しています。お客さまは、われわれの、価格が手ごろで品質のよいクルマを求めています。
・最高の経営というのは、徹底したトップダウンもよくないし、完全なボトムアップもよくない。やはりその中間のバランスをとるのがよいのだと思います。トップダウンは、危機的状況においては非常に重要だと思います。危機的状況のときには、乗組員は船長からどういう状況にあるのか、目的地はどこなのか、どう問題を解決するのか、優先順位は何なのか、を聞きたいからです。
・ゴーンは購買コストの劇的な切り下げにも躊躇しなかった。「これまで購買を担当してきた人々の『これまでずっとこの価格でやってきた』という反論に対して、私は、こう言った。『過去にどうやってきたかはどうでもいいことです。私が聞きたいのは、これからどうするつもりかということです』」
・「われわれは燃えさかる甲板(バーニング・プラットフォーム)から逃げ出さなければならないのです。自分の家が火事のときには、安閑としていられないはずです。危機感の薄い社員は目覚めなければならない。過去八年のうち七年間も利益が出ない会社は、危機以外の何物でもないことを自覚させる必要があるのです」
・2000年10月の中間決算の直前、インタビューした私にゴーンはこう強調した。
・「なぜ日産の業績を回復させることができたのか。成功の理由の第一は、燃えさかる甲板があったことです。燃えさかる甲板にいつまでもいることはできない。そこに潜在的なパワーがあったことです。26年間も市場シェアを低下させ続け、精神的にも負けグセがついていた日産社内の人間では立て直すことができなかった。
第二の理由は、正しい方向を選択できたことです。われわれはどういう状況にあるのか的確な診断をし、進むべき正しい方向を示すことができた。最初の第一歩が正しい方向であれば、次を引き出す力が出るし、自信がつくのです」
・「戦略はトップが知っているだけではなく、従業員と分かち合うことが重要なのです。戦略は情勢の変化に素早く対応し、絶えず見直さなければなりません。弱点を見つめれば解決の方法も見つかります。個々人に見返りを約束すれば、収益をあげる意味がより具体的になります。
社員には自分たちがどこに行こうとしているのか絶えず知らせる必要があります。戦略と目標を明示されることによって社員たちは鼓舞されるのです」
・ゴーンは販社訪問の一週間前から、訪問先の販売店から資料を取り寄せるなど、綿密に下調べをする。担当役員を同席させるのは、問題のスピーディな解決のほか、現場の意見を直接聞くことで問題意識を共有する意味もある。
・「はたして、生まれながらのリーダーというものは存在するのでしょうか?その後、その人がリーダーになれるかどうかは、その適性を延ばす環境にいられるかどうかによって決まってきます。ですから、こちらはそういった環境を用意して―つまり、チャンスを与えて、その人がチャンスを活かせるかどうか見ればよいのです。もちろんその過程で落伍者や挫折者も出るでしょう。しかし、こうしたことが常に行われていれば、ある企業にとって十分に必要な数だけ、優秀なリーダーを育てることは可能だと思います」
・「私はよく、外国人だから改革ができたのではないかと、よく言われます。しかし、外国人だったことは、むしろマイナスだったと思います。なにしろ日本語がわからないのですから」
・「マネジメントには、コミュニケーションが大事です。従業員が言うことに耳を傾け、よく理解し、より深く踏み込んで人の考えを読み取らなければならないのに、相手の言っていることがわからないのでは話になりません。外国人だからしがらみないと言えば聞こえはよいのですが、その代わり過去の経験もないから、みんなが知っていることがわからない場合も多かった」
・ラグロヴォール神父が教えてくれたのが、可能な限り簡潔に考え、自分の考えをわかりやすい方法で表現し、自分でやると言ったことは必ずやり遂げるという教訓だった。
・日本では何か複雑な問題が起こると、非常に単純な形で対応します。つまり行動を起こさないという対応です。問題に関心がないと行動しません。人が行動しないということは、問題が明確でない、あるいは問題の所在に納得していないことを示しています。ラテンでは、理解できなくても人々は行動を起こすものです。たとえ自分が求めていたものに合致していなくても、自分なりの理解で行動します」
・企業が活力を失って業績低迷に陥る原因は、突き詰めれば経営者の劣化にある。成功した経営者は従来の路線を変えたがらず、経営者が交代したとしても、往々にして社内の人脈や取引先とのつながりなど過去のしがらみにこだわって大胆な改革ができない。しかし、活力を失ったのと同じ方法で経営をするのでは、業績を短期的に回復できても、持続することはできない。
・企業を変えるには、経営危機の本質的な問題をとらえ、異質な企業文化を超えて改革を実行できる人材が必要なのである。
・「インターナショナルの分野では合理主義を貫くが、ローカル分野は国によって違う。とりわけ人事政策は、アメリカでは合理主義を貫いても、人口密度の濃い日本では日本に合う戦略がある」というのがキャノンの御手洗の考えである。
・大事なのは結果を出すことです。私は、人々に自分のアイデアや感触を知らせるために来たのではありません。私は日産を安定させるために日本に来たのです。どれだけ早く日産が再生するのか、どれだけ日産が強くなるのか、によって評価されるのです。ですから、ほかのことは忘れて、結果を出すことにだけ専念しました」
(以上)
書籍名:マニフェスト
著者名:金井辰樹
出版社:光文社新書
紹介:「世論」や「気分」に惑わされずに政治を見る眼を養う方法としてマニフェストの見方を紹介します。
感想:以下の点に関心を持ちました。
・マニフェストは「政権公約」と訳される。実は、この訳語は、われわれ東京新聞政治部が最初に選んだ言葉だ。
・マニフェスト(manifesito)は本来、「宣言」とか「声明書」などの意味を持つ。マルクス・エンゲルスによる「共産党宣言」の「宣言」もマニフェスト。飛行機の搭乗者名簿も「マニフェスト」だ。
・日本の場合、これまでマニフェストというと、「産業廃棄物の流れを把握する管理票」のことを指す言葉として理解されていたようだ。
・英国のマニフェストは有料だ。だいたい2ポンド前後だから400円程度ということになるだろうか。これが選挙前になると、本屋はもちろん、駅のニュース・スタンドにも平積みされ、数十万部も出回るという。大ベストセラーだ。
・カネを払って政党の公約を買うという感覚からして日本とは違う。売上金は、各党の貴重な選挙資金になることは言うまでもない。
・ブレア氏は、選挙中の演説で「私にはやりたいことが3つある。教育、教育、そして教育だ」と訴えている。これと並行しながら同党は、政策10項目のうち5つの超目玉政策を名刺サイズの紙に書き込んでばらまいた。
・欧米諸国に共通していることは、公約に対するこだわりが日本よりもはるかに強いということだ。多少の差はあるが、ウイッシュ・リストと断言できる国は見あたらない。
・自民党の公約は、官僚がつくっているのだ。法案などの大半を官僚がつくっているのは当然として、政治家を選ぶ公約まで官僚がつくるのは驚きではないか。
・米国などでも「バンドワゴン現象」といって、勝ち馬に乗ろうとして有利な候補に支持が集中することは少なくない。
・欧米の新聞社は大統領選などの際、投票日にどの政党を支持(エンドース)するかを明確にする。どちらかというと保守的な新聞は共和党候補を支持し、リベラルな新聞が民主党候補を支持する傾向があるのは確かだが、民主、共和両党の政見について、連日膨大な紙面を割いて論評、検証した上で、最終段階でどちらを支持するのかを発表する、という新聞も少なくない。(以上)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 離婚はいけないことなのか?
- (2025-11-30 08:43:17)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 中川大志、橋本環奈との「公園キス」…
- (2025-11-30 15:00:05)
-
-
-

- たわごと
- SNSでぐっときた言葉
- (2025-11-30 09:04:37)
-
© Rakuten Group, Inc.