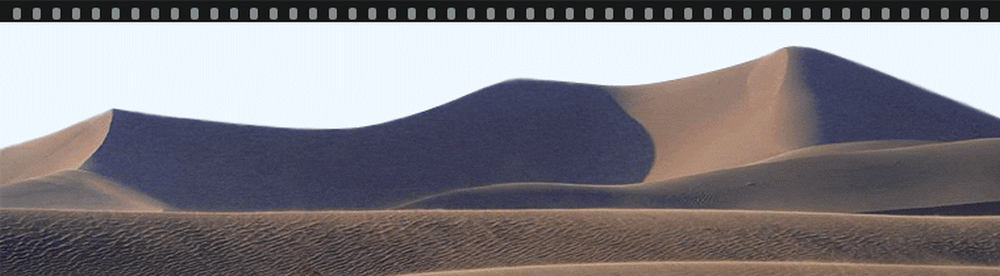****************
ある夜、神がやってきた。
「いや、ここのところ、忙しゅうてな、済まなんだ。え、何、書くのを止める? 今更何言うてんのや、アホくさい。自分の力不足を痛感した? ああ、そら、確かに、今のお前は力が足りん、そやけど、未来永劫、足りひんことなどあるもんか。それに、今、お前が、周りの子ぉに書いたってる話な、あれ、ええやんか。欲しがられるんやろ? 書き写したりされてんのやろ? 冊子にまとめたら思いの外売れたんやろ? あれ、頑張ってみいな。あれ、出版社にも送ったり。え? 迷惑ちゃうか? 何言うてんね、それが向こうの商売やろが。迷惑やったら断ってきよるがな、万が一、万が一やで、上手いこといったら、こっちも潤う、向こうも潤う。悪い話やないで? な?」
神さまは口車のプロだった。私はまたもや乗せられた。出版社に、自分の作品を送り続けて数年、ついに「書いてみるか」と誘いがあった。持っていたネタを数本、一つの書き出しを送ってみた。だが、私の作品は求められるものに至らなかった。丁寧な断りが届き、掴みかけたチャンスの喪失に混乱し、狼狽え、諦めきれずに数年もがいている間に、ようやく一つの問いが浮かんだ。
なぜ、私は書いているのか。
すでに、欲求不満解消だけではなくなっていた。身近の読者は、就職や結婚、出産や子育てなどなど、一身上の変化で減りつつあった。描きたいと思って書いた作品と、周囲の求めも噛み合わなくなりつつあった。書くことの喜びも残っていたが、それに伴う心身共の負担も重くなっていた。
私は神さまに訴えた。書くべきか、書かざるべきか、それが問題、どちらを選べば良いでしょう、と。神さまは非常にそっけなく、こう宣われた。
「書こうが書くまいが、まあ、どっちでもええで。お前の人生や、好きなようにしたらええ。ここで書くのをやめたら、今まで書いてきたことはどうなるね、とも言えるやろうが、人生にムダはつきもんやしな。物にならへんとしたら、この先のムダは省ける、ちゅうもんや」
うむ、そうか。では、止めてしまえと思い始めた私に、神様はいよいよ本領発揮、一筋縄ではいかない手管の数々を見せられた。
まず、新聞や小冊子に投書が載り始めた。読者の便り、詩、意見、短歌まで乗った。投稿作品も評価された。地方の文学賞佳作、童話のアイディア賞や佳作、小エッセイ佳作。作品をまとめて出していた個人誌も、一つのシリーズが終わると、周囲に望まれて次のシリーズを出すような段取りとなった。加えて、色々な機会に、あらゆる人が、何度も何度も尋ねてくる。
「それで収入を得ているプロの作家でもないのに、なぜ書き続けているんですか」
書いていることの意味。
自分が何を目的としているのか。
それを一番知りたいのは私だった。
自分が楽しむためなら、発表する必要はない。人に楽しみを与えるためなら、在り方に悩む必要はない。お金のためなら書くことに拘らなくていい。名誉を得たいならもっと認められやすい道を探せばいい。なぜ、ある物語を、まとまった収入にさえならず、掲載される媒体が待っているわけでもなく、誰が読むとさえも考えずに、最善の努力をして、或いは周囲に迷惑をかけても、書き続ける必要があるのか。
私は書くことで何を得ているのだろう。
手探りのまま、書き手として何か仕事があるのかと、色々なものに手を出してみた。二次創作に踏み込み、WEBゲームのライターを請け負ってみた。どれも読者を得て喜ばれ、熱狂的に支持されることもあった。だが、なるほどこちらかと喜び勇んで、その分野に進もうとする度に、仲間を失い受け入れ先を失い、新たな場所も能力不足と判断されて、得ることは叶わなかった。
再び書き手の私から、世界が遠のいていった。いやむしろ、世界は私が書き手であることを望んでいないようにしか思えなかった。
恐らくはきっと、私は書き手である必要はないのだろう。いつかの問いは、なぜいつまでも見当違いの方向ばかり探し歩いているのか、本分たるものをちゃんと見極め、それに全力を尽くせという神さまからの遠回しな警告だったのだろう。ならばなぜ、この道に引き込んだのかと詰りたいところだが、それもまた人の身には分かりかねる何かの理由によるのだろう。
私は他の誰より自分の不出来さにがっかりした。
****************