吉田政治の「遺産」-終焉から50年
吉田政治の「遺産」~ 終焉から50年(2004/12/04)
(1)分かれる評価
ツケ残した 改憲の回避
東京の目黒駅近く、国立自然教育園の森に囲まれて 東京都庭園美術館 がある。
古くは 朝香宮邸 、戦後は 外務大臣公邸 となり昭和三十五年の日米安保条約改定のとき、批准書の交換場所にもなった由緒ある建物だ。
首相就任直後外相を兼ねていた吉田茂はこのアール・デコ式の洋風建築と庭を好み、しだいにここで政務を執るようになった。貴族趣味といわれた吉田らしいところだ。政治家や官僚たちを呼びつけることも増え「目黒の公邸」はワンマン政治の代名詞のようになった。
昭和29(1954)年12月7日、この「目黒の公邸」は朝から閣僚をはじめ与党自由党の若手議員たちが詰めかけ、異様な雰囲気に包まれていた。
この年に起きた 造船疑獄 と、これに対する 犬養健法相の指揮権発動< などで、民心はすでに吉田政権から離れていた。
民主、左派社会、右派社会の野党三党は前日の六日、内閣不信任案を提出、もともと吉田内閣は少数与党であり成立は不可避の情勢だった。自由党の大勢も「退陣しかない」となっていた。
それでも政権に固執する吉田は衆院解散により、中央突破をはかろうとした。
与党幹部や閣僚を集めたのはそのためだった。だが、最も頼りとする自由党ナンバー2で副総理の 緒方竹虎 は説得をはかる吉田を、こう突き放した。
「どうしても解散するというのなら、議員を辞めて福岡の田舎に引っ込む」
それを聞いた吉田はプイと二階の居室に上がった。都合七年二カ月に及んだ長期政権が終焉(しゅうえん)をつげた瞬間だった。
◇
それから五十年たった今年四月十六日、「目黒の公邸」からさほど遠くない目黒区駒場の東大先端科学技術研究センターでその吉田政治が俎上(そじょう)に載せられた。
元タイ大使の岡崎久彦氏が主宰するNPO法人岡崎研究所などが開いた「日本政治外交史シンポジウム」である。
特にその第三部「占領・独立そして現在」で、吉田の外交・安全保障政策をめぐり、岡崎氏と五百旗頭真(いおきべ・まこと)神戸大教授らの間で激論が交わされたのだ。
※詳細は五月四日付の本紙(東京発行)で報じてあるが、焦点となったのは、日本の再軍備と憲法九条の改正問題だった。
吉田は、昭和21(1946)年五月、首相に就任する。日本国憲法ができた年である。
そのときから、九条の戦争放棄について「 自衛のための戦争も許されない 」との立場を表明、国務省顧問ジョン・ダレスら米側の再三にわたる再軍備要求を拒否しつづけた。
昭和25(1950)年、(6月25日)朝鮮戦争の勃発(ぼっぱつ)にともない連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサーの指示で警察予備隊を設置、これが自衛隊となった後も「 自衛隊は戦力なき軍隊 」などと強弁し、九条の改正にもガンとして応じなかった。
五百旗頭氏はこの吉田の対応に理解を示す立場で論じた。
「当時日本はまだ貧乏で、対ソ、国防に限られた資源を投入するより日米安保という方向を選んだ。それに米ソ二超大国がず抜けていく中で、それ以外の国は軍備にしゃかりきにならないのも賢明だ、と思うようになったのではないか」
その上で「独立、愛国、親英米の筋を戦後日本の機軸とし、安全と繁栄の基礎作業を行った」と、その 経済優先主義 を高く評価した。
これに対し岡崎氏は「吉田の発言にはこだわりの匂(にお)い、あん畜生という匂いがある」という表現で吉田批判を展開した。
「憲法九条を論じていたときすでに(自衛戦争は認めるという解釈が可能な) 芦田修正 が入り、占領当局もこれを了承している。しかし吉田がそのことを認識していたかどうかもわからない。後は 売り言葉に買い言葉的に(再軍備を拒否する)発言を繰り返し、一度言うと強情に変えなかった 」そして
「 一番の問題は、再軍備せず、憲法改正せずと言うばかりで、再軍備の可否、憲法改正の可否について一切論じようとしなかった 。それが国民の混迷を招いている」と述べた。
両者の違いは、吉田の再軍備・憲法改正拒否に合理的な理由を見いだせるかどうかにあるようだ。
だが、七年余りの政権運営の間に何度もチャンスがありながら、あえてやらなかった。
そのことが、例えばイラク復興支援に自衛隊を派遣するだけで、憲法解釈をめぐる「神学論争」を繰り返さなければならない、安保論議の不毛さというツケを後世に残したことは事実だ。
吉田は戦後のさまざまな改革から独立、日米安保体制など実に幅広い実績をあげている。そのことは認めつつ、終焉から半世紀の機に、再軍備・憲法改正の問題を中心とした検証を試みたい。
(皿木喜久)
◇
造船疑獄
海運業界再建のための計画造船をめぐり、海運業界や造船業界から政官界へ贈収賄がなされた事件。政治家を含む71人が逮捕されたが、 佐藤栄作自由党幹事長の逮捕請求を犬養法相が拒否 し、事件の核心はウヤムヤのまま終わった。
※(2004/05/04)
◆日本政治外交史シンポジウム(2-1)
歴史から日本の国家戦略を考えようという「日本政治外交史シンポジウム」(NPO法人岡崎研究所・東大先端科学技術研究センター主催)が先月中旬、東京都内で開かれた。
『陸奥宗光とその時代』など政治外交史の通史を書いている岡崎久彦元タイ大使を中心に、外交史などの専門家6人が出席、第1部「日清戦争、日露戦争を経て」、第2部「二つの世界大戦と戦間期」、第3部「占領・独立そして現在」にわたり意見を交わした。
議論は計6時間近くに及んだが、日露開戦100年に当たり、近代日本の国家戦略に関心が集まっているだけに白熱したものとなった。いくつかのテーマにしぼり、内容をリポートする。(皿木喜久)
◇
【出席者】
▼岡崎久彦氏(元タイ大使、NPO法人岡崎研究所所長)
▼五百旗頭(いおきべ)真氏(神戸大教授)
▼北岡伸一氏(東大教授)
▼坂元一哉氏(阪大教授)
▼井上寿一氏(学習院大教授)
▼御厨(みくりや)貴氏(東大教授)(進行役)
◇
≪日清戦争、日露戦争を経て≫
■「半島中立化」構想に注目 井上氏
■軍事力の均衡 確立なく無理 坂元氏
第一部で焦点となったのは、日清(一八九四-九五)、日露(一九〇四-〇五)両戦争や日露戦後の韓国併合をどう見るかだった。
まず岡崎久彦氏は両戦争期を「 日本民族の興隆期 」とし「国が伸びているときは、人々が意欲にあふれている。日清戦争のとき二十歳ぐらいだった人がその後の文明や文化を担った。その意味で 夢のような時代 だった」と述べた。
坂元一哉氏は「ヨーロッパだけで国際秩序は語れないという流れを作ったのが日露戦争だと思う。非西洋の反撃の嚆矢(こうし)としてアジアの発展をもたらせた。その意味で国際政治上の二十世紀の始まりは一九〇四年だといえるのではないか」と日露戦争の意味を評価した。
一方、井上寿一氏は岡崎氏の「興隆期の勢い」という見方は肯定しつつ「歴史の教訓の学び方は多様であり、例えば日清戦争や韓国併合はほんとに避けられなかったのかという、もうひとつの可能性を見なおしてみるのもいいのではないか」と提起した。
具体的には、日清戦争のときに明治の元勲、山県有朋が「朝鮮半島を永世中立国にすることが新興国日本の安全保障政策として最も現実的だ」としていることに注目、当時「朝鮮半島をめぐり日本が侵略されず、侵略もしない第三の道が考えられていた」と指摘。
「戦争も国家建設の一環で、単純に安全保障政策の観点で戦争になったのではないので実現性は少なかったが、現在の半島情勢を考えるとき、何らかの意味で中立化が実現可能なものとして構想できるのではないか」と述べた。
韓国併合については、「日本は当時の国際法規に照らし、欧米諸国の動向もみながら、形式的には任意の形をとるようにし、慎重に進めていた。もし無理だと思えばやらなかったのじゃないか」と、場合によっては別の選択もあったことを指摘している。
これに対し、坂元氏は「政策の評価は、もしその政策をとらなかった場合、どうなったかという点から考えるべきだ」との考えを示した。その上で
「例えば 日露戦争を避けた場合には、ロシアの東アジアへの影響力、軍事力は高まる。特にシベリア鉄道はどんどん(極東に向け)進む。そのままにしておいてはならないという直感で戦争を選んだ 」
「朝鮮半島の中立化は話し合いでもできたのではないかとの意見もあるが、 それはバランス・オブ・パワー(軍事力の均衡)が確立していて可能になる。 そうでなかった から(回避は)無理だったと思う 」と述べた。
岡崎氏は「私は明治から現代にかけての外交の通史を書いたさい、それが日本人にとって得になったか損になったかの観点でみた」とした上で「日清・日露は勝ったのだからいい。しかもあれだけの良い国をつくってくれた。そういう戦争をやらなくてよかったと考える必要はないんじゃないか」と“歴史のイフ”に疑問を呈した。
ただ、後の太平洋戦争については「そうした国を潰したのだから、イフについていくらでも考えている。シナ事変(日中戦争)以降はそうだ」とした。
日韓併合についても「それをやらないとロシアをもう一度(朝鮮半島に)引き込むことになり、仕方なかったと思う。問題は植民地政策だっただろう」と述べた。
最後に御厨貴氏は「岡崎さんの『陸奥宗光とその時代』や『小村寿太郎とその時代』には、“気概”という言葉が出てくる。学問的に歴史を描く場合には吹き飛ぶ言葉だが、岡崎さんはそれを書きこんだ」と指摘した。そして
「 明治日本の興隆期を背負ったのは明治の人々の気概ではなかったか。明治日本では体制派にしても反体制派にしても、国家がすぐ手の届くところにあり、よく見えていた 。だからいろんな論争が起き、明快な答えを出し得たのではないか」と見解を示した。
≪二つの世界大戦と戦間期≫
■米国世論に苦労した日本 北岡氏
■日英同盟の廃止は致命的 岡崎氏
大正から昭和前期を扱った第二部で、まず主要なテーマとなったのは「大正デモクラシー」と、幣原(喜重郎)外交の評価だった。
幣原は大正デモクラシーと政党政治隆盛期の一九二四(大正十三)年から満州事変(一九三一年)まで二度にわたり外相をつとめ、対英米中心の協調外交を展開した。
大正デモクラシーについて岡崎氏は「戦後の新憲法のおかげで日本が民主主義になった、などというのはとんでもない間違い。日本人はずっと前からデモクラシーを経験している」と指摘、そのデモクラシーの発露である政党政治のもとでの幣原外交を高く評価する立場をとった。
その大正の政党政治が滅んだことについては、チャーチルの「デモクラシーは最悪の政治だが、世の中に存在する他の政治よりはましだ」という言葉を引き合いに「 当時は(政党よりも) 藩閥や軍閥の方が廉潔 であり、そちらの方が良く見えた からだ。現在は他に選択肢がないから民主主義が定着している」との持論を展開した。
北岡伸一氏は日本の近代を「海洋国家」の流れを軸として考えるべきだとし「海洋国家として生きていくには、朝鮮半島の南岸を他国に渡すわけにいかなかった」と、日清・日露戦争の意味を述べた。
さらに、幣原外交については「幸い大陸のロシア、中国の脅威が弱まり他の外交を展開できた」と、同じ海洋国家である英米重視となった歴史的意義を強調した。
その上で、米国と協調しながらも移民法などさまざまな問題があったことについて「岡崎さんは アメリカの世論は世界の独裁者 だと述べているが、幣原外交をふくめ日本はアメリカの大きく揺れ動く世論とどう付き合うか苦労した国だ」との見方を示した。
ただ、その 幣原が駐米大使時代に行った日英同盟の廃止 については、岡崎、北岡両氏とも厳しい批判をした。
北岡氏は「冷戦が終わったとき、これからはマルチ(全方位)の時代だという意見もあった。しかし吉野作造が述べているように、同盟はあること自体に意味がある。現代でも日米同盟を堅持しつつアジア諸国との間に関係を醸成することが可能なように、日英同盟を守りながら米国などとの関係を保てたはずだ」と指摘。その上で「もし日英同盟を維持していれば日本政治の内側の暴走に歯止めをかける力になったはずだ」と述べた。
岡崎氏は「 これまでの時代を振り返ってみて、どこに致命的失敗があったかといえば、日英同盟の廃止と真珠湾攻撃の二つしかない 。満州事変も三国同盟も、失敗を回復しようとすればできたが、この二つは回復不能な失敗だ」と断言する。
そして「日英同盟があれば、満州事変はやらなかっただろうし、やっていてもリットン報告書で収束できた」「真珠湾では堂々と宣戦布告しておれば、普通の戦争であり、あれほど悲惨な結果にはならなかった」と言う。
一方、幣原協調外交に終止符を打つことになった満州事変について、北岡氏は次のように述べた。
「当時日本からアメリカに渡った移民は約十万人。満州へもざっと十万人だった。対米移民は政府から何の支援も受けないまま何とかやっていったが、満州は満鉄その他政府や準政府機関の人間で、現地の人との競争に勝てるわけがない。やがて日本が満州にもたらした安定の上に、大勢の漢民族がやってきて圧倒的多数を占めた。それを軍事力で抑え込もうとしても難しいことだった」
井上氏は「満州事変は日中関係からは合理的説明はできない」と述べ、こう分析した。
「当時の蒋介石の国民党は武力対立する余裕はなかったし、幣原外交を信頼して、幣原が軍部を抑えてくれると思っていたから、双方のナショナリズムの対立で起きたとは考えられない。そうではなく、戦争が原動力となって国内政治体制を変える、国家改造を行いたいとの考えが強かったのではなかったのか。しかし、国家改造のためには明治憲法を改正する必要があり、そこまでしてやろうという人はいなかった」
岡崎氏は「日英同盟廃止は幣原喜重郎、真珠湾攻撃は山本五十六という当時の最高の頭脳の持ち主がやった。結局はアメリカをよく知らなかったのだろうが、当時世界中が米国をわかっていなかった。それは後々までそうであり、日本がその分析を始めたのはつい最近だ。 二十世紀は多くの国がアメリカに振りまわされ、滅んだ と言っていい」と結んだ。
◆日本政治外交史シンポジウム(2-2)
≪占領・独立そして現在≫
■安保混迷招いた吉田首相 岡崎氏
■経済充実と安保締結評価 五百旗頭氏
第三部での議論はほとんど、日米関係を軸に 軽軍備、経済重視の路線を引いた吉田茂元首相の「吉田外交」への評価 に費やされた。
初めに五百旗頭真氏が「戦後の日本人が求めたものは平和であり、安全であり、経済繁栄だった。吉田は、平和条約と同時に日米安保条約を結ぶことで安全への答えを出した。ただ、その 代償として日本の自立性には問題を残した 」と問題提起した。
具体的に、吉田は日本の独立に当たって米国からの再軍備要請に抵抗を示し、憲法改正にも消極的姿勢を貫いた。
この点について五百旗頭氏は「吉田以外の首相だったら再軍備しなさいと言われれば『ハイハイありがとう』とやっただろう。吉田とすれば、まだ日本は貧しいからいずれ再軍備をすればいいという考えだった。しかしその後、アメリカとソ連という二超大国の冷戦構造が強まるのを見て二国以外は軍備にそれほどシャカリキにならないのも賢明なことではないかと考え、問題を先延ばしにしていったのではないか」と述べた。
坂元氏も「再軍備問題は吉田に対する批判のあるところだ」として、この点に触れた。
「吉田は(再軍備に反対だった)マッカーサーの支持を得るために再軍備しないというタテマエでいこうとした。一つは経済が回復していないのに再軍備はバカげているという思いであり、もう一つは日本の再軍備に対する諸外国の恐怖心があれば、日本が望んだ“寛大なる講和”が難しくなると考え、とりあえずやめておこうということではなかったか」
その上で「問題は、ではいつ(再軍備を)やるのかを示さなかったことであり、 講和が思い通りになった後も二年以上政権の座にありながら再軍備要請を聞かなかったこと だ」と疑問を呈した。
岡崎氏は「吉田には、ほんとうに先の先まで読んでいたのか、自分のこだわりや感情で外交方針を決めていたのではないかと思われるところがある」と、吉田外交批判を展開した。
特に安全保障問題では「 再軍備せず、憲法改正せず、と言うだけで、再軍備や憲法改正の可否について全く論じなかった。憲法改正についての認識があったかもわからない 。ダレス(元米国務長官)の再軍備要請を退けたのも、単に強情さからではないか。 鳩山一郎 や 芦田均 なら全然違っていた はずで、その後の安保論争の混迷もなかった」と述べた。
これに対し五百旗頭氏は「米国も日本が再軍備を急ぐより経済社会を充実させるということに理解を示していた。吉田の人物論はどうでもよいことであり、むしろその荒っぽい手法で、親米英路線をつくり、反対も多かった日米安保を締結した。戦後日本の行き方を決める立派な仕事をした」と反論した。
★ だが、岡崎氏はこれに対し「それは 吉田以外の誰でもそうやったであろうことで、吉田以外ならもっとうまくやっただろう ということを言っている」と再反論した。
最後に岡崎氏は日本の今後の外交の進むべき道として「イラク問題は日米同盟を強化する絶好のチャンスだ。 アメリカが苦しいときに日本に助けられたいという状況になったら、日本は大丈夫だ 」と述べた。
◇
日英同盟
日本とロシアとの緊張が高まっていた1902(明治35)年、ロシアの力に対抗するために日本と英国との間に結ばれた同盟。イギリスは日露戦争に当たって情報や武器調達で日本に援助を行い、第一次大戦では日本は同盟にしたがって参戦した。しかしその後、米国などから同盟に対する批判が高まり、1921(大正10)年失効となり、代わりに 日米英仏4カ国条約 が結ばれた。
(2004/12/05)
(2)不幸な出発
「自衛」否定した勇み足
敗戦から十二日後の昭和二十年八月二十七日、元駐英大使、吉田茂は外務省時代の同僚でドイツ大使などをつとめた来栖三郎に長文の手紙を書いた。
後に『吉田茂書翰』に収録され、吉田の政治信条や人となりを示すものとして有名になった。
「敬覆(けいふく) 遂に来るものが来候(そうろう)。 もし悪魔に子供がいたらそれは東条(英機)に違いない (この一節だけ英文)。今までの処、我(わが)負け振(ぶり)も古今東西未曾有宇の出来栄(ばえ)と申すべし。皇国再建の気運も自ずからここに蔵すべし。軍なる政治の癌(がん)切開除去。政界明朗、国民道義昂揚…」
不穏当な言葉づかいもものかは、敗戦による軍の解体に快哉(かいさい)を叫んでいるのである。さらに軍攻撃は続く。
「嘗(かつ)て小生共を苦しめたるケンペイ(憲兵)君、ポツダム宣言に所謂戦争責任の糾弾に恐れを為し…其(その)頭目東条は青梅の古寺に潜伏中のよし。…ザマを見ろと些(いささ)か溜飲を下げおり候」
吉田は終戦直前の昭和二十年四月、九段の憲兵隊に連行された。近衛文麿が戦争の早期終結を天皇に内奏したいわゆる「近衛上奏」に関与した疑いだった。
戦火に追われあちこちの収容先を転々とし、四十日後にようやく釈放される。ここにはそうした憲兵や軍トップの東条英機元首相らに対する憎悪ともいえる感情がにじんでいる。
吉田が本当に「軍嫌い」であったかは意見の分かれるところだが、少なくとも軍部が主導権を握った昭和前半の歴史を憎悪していることは間違いない。だが、それが現実の政治に反映されるとどうなるのか。
吉田は来栖への手紙から間もない二十年九月、 東久邇宮内閣の外相 に起用される。
翌二十一年五月には首相に就任、政治家としての本格的スタートを切るが、前回取り上げた政治外交史シンポジウムに参加した坂元一哉阪大教授は手紙の「軍なる政治の癌」の問題点を指摘した。
「切開除去といっても、ほんとうは病気の部分だけを取らなければならなかったのだが…」。
必要も不必要も関係なく すべての軍事力を否定 してしまったというわけだ。
そのことがあからさまに出たのが首相就任直後の六月二十八日、衆院本会議での新憲法をめぐる論戦だった。質問したのは共産党の野坂参三である。
「戦争には二つの種類がある。一つは正しくない戦争。日本の帝国主義者が起こしたあの戦争、他国征服、侵略の戦争である。侵略された国が自国を護(まも)るための戦争は正しい戦争である。この憲法草案に戦争一般の放棄という形でなく侵略戦争の放棄とするのが的確ではないか」
これに対し吉田はまず「近年の戦争の多くは国家防衛権の名において行われたことは顕著なる事実」とし、「正当防衛による戦争があるとすれば、侵略を目的とする戦争をする国があることを前提としなければならない」と述べた。
さらに「正当防衛権を認めるということ自身が有害であると思う」と、 自衛のための戦争そのものを否定してしまった のである。
共産党嫌いの吉田とあって、まさに売り言葉に買い言葉といえなくもない。
しかし二日前の二十六日にも進歩党議員の質問に「第九条は自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄したもの」と言いきっている。「信念」だったのだろうか。
猪木正道・京大名誉教授は著書『評伝吉田茂』の中で、この答弁を「勇み足」と表現している。 日本の国防論議にとって実に大きな「勇み足」だった 。
吉田自身がその後、自らの発言に縛られることになったからだ。
昭和二十五年一月、国会での施政方針演説では「(憲法の)戦争放棄の主旨に徹することは自衛権の放棄を意味するのではない」と述べた。
この年(1950(昭和25)年)の元旦、マッカーサー連合国軍総司令官は年頭の声明で「この憲法の規定は、 相手側から仕掛けてきた攻撃に対する自己防衛の権利を否定したものとは絶対に解釈できない 」と表明した。
吉田としてはその「虎の威」を借りて、初めて前言を修正しようとしたのだ。しかし、たちまち左翼陣営などから「食言だ」との批判を受けると再び沈黙してしまう。
※食言:しょくげん:「書経(湯誓)」(一度口から出したことばを、また口に入れる意)前に言ったことと違うことを言うこと。約束をたがえること。うそをつくこと。
サンフランシスコ講和条約締結後の昭和27年3月6日の参院予算委でも「憲法は自衛のための戦力を禁止していない」と発言する。
だがこのときも批判を受け、四日後には「 自衛のための戦力でも持つ事は 再軍備 であり、その場合は憲法改正を要する 」と後退するしかなかった。
ほかにも、マッカーサーの指示で警察予備隊を設置したとき「これは断じて再軍備ではない」と強弁し、 自衛隊を「戦力なき軍隊」 と述べるなど迷走を繰り返し、安保政策の混迷を招いた。
それもこれも最初の「勇み足」が根底にあった。
(皿木喜久)
たまたま反響みつけたので。12/06
[ ID:364 ] 04年12月06日(月) 08:48:23 辻貴之
吉田茂の負の遺産
いま産経新聞に、 吉田茂の「遺産」 と題して論文が掲載されています。
私自身、吉田茂が残した政治の功罪はプラス面のほうが大きかったと考えています。なにしろ、あの戦後復興に果たした手腕は見事なものがあったと考えるからです 。
しかしながら、負の遺産も少なくありません。今日の日本の置かれた状況を考えると、とりわけその思いを深くします。
昭和二十五年六月、アメリカ国務省顧問ジョン・フォスター・ダレスが講和をめぐる交渉のため来日します。(この来日中に朝鮮戦争が勃発します)
講和に当たって再軍備を求めたダレスに対して、吉田はその要求を断ります。その理由というのが「日本は再軍備に伴う経済費用や国民一般の激しい抗議に耐える余裕がない」(産経新聞)というものです。
ダレスにとって、「国の基本である国防を、経済や国民感情にまかせるということが、どうしてもりかいできなかった」(産経新聞)のである。
昨日も多くの人々と話をする機会がありましたが、少なからぬ人がいまの日本を憂いています。 その原点にあるのが「国を守る気概」の喪失です 。もちろん、それには左翼の影響が大きなものがあります。しかし、吉田茂にも、その責任はあるように思います。
と言うより、岡崎先生の言われてるのは「あの程度のことは吉田以外の「誰(といっても芦田均・鳩山一郎ダケをご指名で、まさか共産党ほかを考えていっておられるわけじゃないでしょうけど)でもやっただろうしもっとうまくやっただろうが、肝心なやらなければならないことを吉田はやらなかった」と 全否定 してるんだけどネ。
それにどう答えるかだが。
それに無関係だけど、この論文の表題ネ。偶然「吉田政治」は、あの詐話師のペンネームと同音でまいったわ。
吉田清治...w コレだったら罪のみで簡単だわな。
(2004/12/06)
(3)不思議の国
黙殺した九条の芦田修正
議会での新憲法審議で、当時の首相、吉田茂は「第九条は自衛のための戦争も認めていない」と述べ後世に禍根を残した。
だが、猪木正道・京大名誉教授は『評伝吉田茂』の中でこう書いている。
「吉田首相の勇み足はさいわいなことに憲法改正案特別委員会とその小委員会において、芦田均小委員長の努力により是正された」。そのはずであった。
昭和21(1946)年6月28日、帝国議会に連合国軍総司令部(GHQ)からの新憲法草案を審議するための 憲法改正案特別委員会 が設置された。さらにその中に、修正案を練る 小委員会 が設けられた。ともに委員長は、与党自由党の 芦田均 だった。
小委員会は8月20日、九条について二カ所の修正を行う。
ひとつは「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という第一項の前に「 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し 」という一節を加えた。
もう一つは、第二項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」の前に「 前項の目的を達するため 」と挿入した。
いずれも芦田自身の手になるといわれるが、特に後者の修正の意味は大きかった。
これによって 国際紛争解決のための戦力は持てないが、自衛のためには保持できるという解釈が成り立つ からだ 。
芦田は外交官出身の政治家で、この後日本民主党を結成、二十三年三月首相となるが、この「芦田修正」に対する史家の評価は高く、猪木氏も「歴史的功績を残した」と書いている。
重要なことは、芦田修正をGHQ側が即座に了承していることだ。高柳賢三元憲法調査会長らによる『日本国憲法制定の過程』IIには、次のようなGHQ内のエピソードが記録されている。
修正案を見て、起草のメンバーだった民政局のピーク博士がホイットニー局長にこのことを伝え「この修正は日本がディフェンス・フォース(自衛のための軍)を保持し得ることを意味すると思うが」と述べたところ、ホイットニーに「あなたはそれがよい考えであるとは思わないか」といわれ、彼もそう思ったので引き下がった。
ホイットニーは言うまでもなくGHQの幹部であり、このことをマッカーサーも了解していたことは間違いない。 この時点で現憲法でも再軍備が可能なことにお墨付きを得た といってもよさそうだ 。
ところが肝心の吉田は芦田修正を無視しつづける。
退陣後に書かれた吉田の『回想十年』には、その意味について全くといっていいほど触れていない。外務省の後輩である芦田への対抗心だったかもしれないが、その後も「再軍備はしない」との姿勢を貫くのである。
岡崎久彦元駐タイ大使も政治外交史シンポジウムで、芦田修正についてはGHQの実力者であったケーディス民政局次長が「これでいいんじゃないか」とOKを出していたという事実をあげ「ものごとのいちばん大事なことが動いているときに、吉田がそれをわかっていたか。あれがきちっとわかっていたらその後の答弁も変わってきたはずだ」と述べている。
吉田がこのチャンスに方向転換しなかったことは後々の政府の憲法論議にも影響を及ぼす。つまり 政府が自衛隊は憲法違反していないというのは、国家には本来的に自衛権があるとの理論にもとづくもので、芦田修正による解釈にはよっていない のである。
吉田はこの後、いったん政権を片山哲と芦田に明け渡すが、昭和23(1948)年10月、再び首相となる。
そして昭和25(1950)年6月には米国務省顧問、ジョン・フォスター・ダレスが初めて来日、吉田との講和をめぐる交渉にのぞむ。
ダレスは、極東における共産主義の浸透を恐れる米国の意を体し、講和に当たって日本が 再軍備 するよう強く求めた。
しかし吉田は「日本は再軍備にともなう経済費用や国民一般の激しい抗議に耐える余裕がない」と述べ、はねつける。
米国における戦後日本研究の第一人者、ジョン・ダワー氏の『吉田茂とその時代』によれば「ダレスはこの一戦で出鼻をくじかれた思いであった」。そして、後に「まるで(童話の)不思議の国のアリスになったような気持ちになった」と述べているという。
ダレスには、 国の基本である国防を、経済や国民感情に任せる ということが、どうしても理解できなかった のだろう。占領側が再軍備を勧めているのにもかかわらず。
(皿木喜久)
(2004/12/07)
(4)マッカーサーのくびき
二人三脚の 元帥とワンマン
1948(昭和23)年2月26日、米国務省の政策企画室長をつとめていたジョージ・ケナンは空路、日本に向けて旅立った。
飛行機で太平洋を横断してくるのはまだ、大変な時代だった。
『ジョージ・F・ケナン回顧録』によれば、シアトルからアンカレジ、それにアリューシャン列島の小さな島で給油しながら 三十数時間 かけ東京に着いた。途中でヒーターが故障し、体は凍りつくようだった。
ケナンが 命がけで日本にきた 理由はただひとつ、連合国軍総司令官のダグラス・マッカーサーと会い、「説得」することだった。
ウィンストン・チャーチルがソ連など共産主義の脅威を「鉄のカーテン」と呼んだのが二年前のことだった。
ケナンの来日当時、米国務省はその「封じ込め」に躍起であった。
ところが、西の防波堤となるべき日本はといえば、 占領軍のマッカーサー元帥らが「 昔の君主に等しい役柄を楽しんでいた 」 (同回顧録)状態で、国務省の世界政策になど聞く耳をもっていない。
ケナンは回顧録で「マッカーサーの日本」を次のように酷評している。
「日本は全く武装解除され、非軍事化されてしまっていた。ソビエトの軍事拠点によって半ば包囲されてしまっていた。にもかかわらず、日本の防衛についていかなる種類の対策も占領軍当局によって講じられていなかった」
それなのに「マッカーサーの占領政策の本質は、日本の社会を共産主義の政治的圧迫に抵抗できないほどに弱いものとし、共産主義者の政権奪取への道を 開くことを目的に立てられた政策の見本 のようなものだった」。
ケナンは他の“使者”同様、国務省を代表してマッカーサーに、日本の再軍備に道を開くとともに、公職追放を緩和して改革を推進させるよう進言するつもりだった。
しかし、マッカーサーはケナンの話に耳は傾けたものの、再軍備を認めようとはしなかった。
マッカーサーが憲法上自衛権が認められるという芦田修正を承認していながら、かたくなに再軍備を拒否する姿勢について、岡崎久彦氏は政治外交史シンポジウムでこう述べていた。
「彼は日本の占領政策を成功させるためには天皇制を維持するしかないということを信念としていた。そのためには他のものは犠牲にしていいと考えていた」
天皇制と軍の双方を残しては日本は戦前と何も変わらないという、他の戦勝国の批判をかわせないという意味だろう。
( つまり、次期大統領選挙出馬という「私望」のために八方美人演じてたと )
ソ連をはじめ共産主義の脅威を国務省ほどに感じていなかったこともあった。
一方、昭和二十三年十月に再び政権に就く吉田茂は、早期に講和を結び独立することだけを外交官である自分の使命としていたようだ。
このため、同じ早期講和論者であるマッカーサーに頼るしかない。それだけにマッカーサー施政下に吉田が再軍備をすることはできなかったのだ。文字通りの二人三脚だった。
もっとも、戦後を代表するジャーナリストのひとり、阿部真之助は『現代政治家論』の中で「国内的には手のつけられないワンマンも、対外的には理想型の イエスマン であった」と、吉田のマッカーサー傾斜を批判している。
( 平たく言えば、「虎の威を借る狐」ってことでしょw )
だがそのマッカーサーも、昭和25(1950)年6月25日朝鮮戦争が起きると、吉田に対し警察予備隊という名の「再軍備」を命じざるを得なかった。
さらに翌昭和26(1951)年四月にはマッカーサー自身がトルーマン米大統領に解任された。
吉田にとっての「くびき」はとれたのである。
しかも、米側は昭和28(1953)年十月になると、訪米した 自由党政調会長、 池田勇人 と国務省極東担当の ロバートソン との会談で、三十二万人の陸上兵力を求める など、矢のように兵力増強を求めてきている。
朝鮮戦争特需 で経済も良くなっていた。
そうした追い風にも吉田は相変わらず自衛隊を「戦力」と認めない。
ならばといって、「戦力」を持つための憲法改正も拒否しつづけた。
マッカーサーのくびきがはずれ、独立も回復、吉田は名実ともに絶対的ともいえる権力を得てしまった。
その 権力を離したくないため 、国内左翼を中心とする「逆コース」といった批判を押し切ってまで、自衛隊を軍として認知したり、憲法改正に踏み込んだりすることをさけた 。
今から見れば、そうとしか思えない。
(皿木喜久)
( 講和前は仕方ないとしても、その後もこのままだったということは、確たる「理念」「国家観」には全く縁遠い、単なる権力の亡者でしかなかったとw )
(2004/12/08)
(5)保守本流の幻想
「憲法」避けた後継者たち
吉田茂は、駐英大使や外務次官などをつとめた戦前の大物外交官の一人だった。
それだけに、戦後間もない昭和20年9月、東久邇宮内閣の外相に抜擢(ばってき)されたのはひとつの必然と言える。
だが翌昭和21年5月、幣原喜重郎内閣の後を受け、首相に就任したのは、文字通り棚からぼた餅(もち)だった。
戦後日本を担うであろう政治家は衆目の一致するところ 鳩山一郎 だった。元衆院議長、鳩山和夫の長男で、大正四年に衆院初当選を果たした生粋の政党政治家である。
戦後間もなく、芦田均、安藤正純らとともに自由党を結成、その自由党が昭和21年4月の総選挙で、過半数には届かなかったが第一党となった。社会党とともに幣原内閣を倒した後、総裁の鳩山に旧憲法下の組閣の大命が下る。
ところがいよいよ組閣という5月4日、鳩山は突然GHQによって 公職追放 される。
( 民生局の悪党「ケーディス」の仕業w )
日本国民にとっても寝耳に水であった。鳩山は戦争中翼賛選挙に非推薦で立つなど、軍部の政権とは距離を置いていたからだ。
鳩山のパージについて、政治学者の増田弘氏は著書『政治家追放』の中で「もし日本側が占領の意思に反逆するなら、GHQはその名誉と威信にかけて、その者のパージをも辞さないという、多分に“見せしめ的恐喝”という政治性を伴っていた」と指摘している。
要するに幣原続投のシナリオを描いていたGHQが「反共」をかかげるなどで気に入らない鳩山の内閣を潰(つぶ)すため、文相時代の滝川幸辰京大教授追放など、戦前の“アラ”を探し出して追放したと言っていい。
だが、鳩山は追放されながらも機敏に動く。外相の吉田をくどいて自由党総裁に引っ張り出し、身代わりの首相にすえた。これによりGHQが次善の策と考えていた社会党政権を阻止したのだ。
鳩山は昭和十二年、欧州を外遊したさい、ロンドンで駐英大使の吉田から歓待を受けた。二人はそれ以来の仲である。だがそれより鳩山にはもっと現実的な計算があった。吉田がマッカーサーに受けがよく、GHQを通りやすいことや、 吉田なら政治への執着がなさそうで、自らの追放が解除されれば、政権を返してくれるとの読み だった。
事実、吉田は『回想十年』の中で、総裁就任を要請されたとき「本来政党というものに気が進まなかった」「長くやろうという気はなかった」と書いている。当時の吉田の正直な気持ちだっただろう。
しかし、一年半の下野を経て昭和23(1948)年10月、二度目の政権についたとき、 吉田はすっかり政治好きの権力者 となっていた。
マッカーサーの庇護(ひご)のもと池田勇人、佐藤栄作、増田甲子七といった優れた官僚出身の政治家を周辺におき、 ワンマン といわれる強引な政治を進めていく。
昭和26(1951)年8月、ようやく追放解除となった鳩山は、憲法改正を掲げ、吉田に政権を返すよう求めるが、吉田は拒否する。
鳩山は追放解除組の 三木武吉、石橋湛山、河野一郎 らとともに吉田側と熾烈(しれつ)な抗争を行い、昭和29(1954)年12月、吉田を倒しようやく政権につく。
しかしすでに七十歳を超えており、改憲を実現するまでのエネルギーは残っていなかった。石橋を挟んで鳩山の後をついだ 岸信介 も改憲派だったが、日米安保条約の改定だけで精いっぱいだった。
神戸大教授の五百旗頭真氏は、政治外交史シンポジウムでこの間の日米間の呼吸が合わなかったことを、こう指摘していた。
「米国がシャカリキに日本に再軍備しろと言ったのは一九五三(昭和二十八)、五四年ごろまでで、そのときは吉田が阻止した。その後朝鮮戦争が終わるなどであまり言わなくなってから改憲・再軍備派の鳩山や岸が出てきた」
その後には池田や佐藤といった「吉田学校」の優等生たち、さらには大平正芳、宮沢喜一ら吉田の「孫弟子」ともいえる政治家が政治の中枢をにない、親英米・経済優先の道を突っ走る。
そして、そうした吉田の流れをくむ路線がいつのころからか「保守本流」と言われ、憲法改正を声高に叫ぶのは、むしろ「傍流」と呼ばれるようになった。
多くの保守政治家たちは「本流」という幻想に安住して改憲論議をサボタージュしてきたといえる。
だが「保守本流」の宮沢元首相は、最近の衆院憲法調査会で九条に限定はしないまでも「国内外の変化に憲法の運用で対応はできるが、限度はある」と改正の必要に言及している。
吉田政治の「負の遺産」 もようやく清算の時期を迎えた。
(皿木喜久)
=おわり
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 見栄体裁病に感染するな!!
- (2025-11-21 07:24:51)
-
-
-
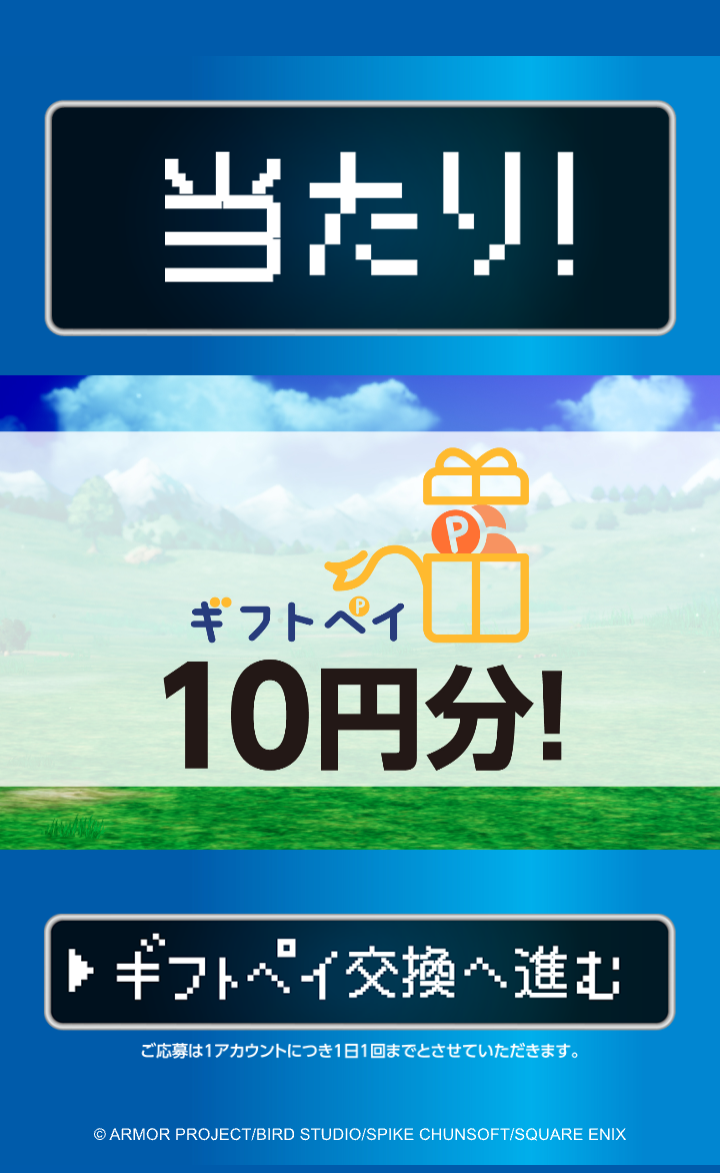
- 懸賞フリーク♪
- ドラゴンクエスト× BOSS キャンペー…
- (2025-11-21 22:13:37)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 【楽天Kobo限定版】似鳥沙也加『ふり…
- (2025-11-22 08:00:05)
-
© Rakuten Group, Inc.



