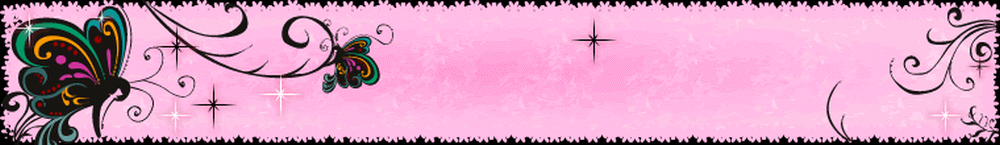エッセンシャルオイル
イランイランという名前は”花の中の花”という意味のマレー語「アランイラン」から由来しています。フローラル系のオルエンタルな香りは、エキゾチックで官能的でインドネシアでは結婚式の夜、2人のベッドにこの花を置くという、なんともロマンチックで美しい習慣があります。それほど男性にも女性にも媚薬的な働きをしてくれ、ストレスや緊張、不安などを取り除いてくれます。古くから香水の原料にも使用された非常に魅惑的な香りですが、強い香りでもあり、過度の使用は吐き気や頭痛をおこすこともありますので、使用の際は十分な注意が必要です。
*******
オレンジスゥイート
誰からも好まれる親しみのあるオレンジの香りは、明るい太陽のように心をあたためてくれます。不安を癒し、くつろぎ感を与えてくれます。同じオレンジの木の花からはネロリ (オレンジフラワー)、葉からはプチグレンのエッセンシャルオイル(精油)が採れます。オレンジの香りは気持ちを明るく元気にさせて、不安や緊張をほぐしてくれます。リフレッシュしたい時や気持ちよくねむりにつきたい時におすすめです。光毒性のある成分を含みますので、お肌への使用後すぐは日光にあたらないよう心がけてください。
*******
カモミールローマン
カモミールという名前は「地面のリンコ」という意味のキリシャ語から由来しているように、フルーティーでリンゴのような香りのカモミールは一度好きになったらやみつきになる根強いファンをもつ香りです。また、学名の中の”nobilis"は「高貴な花」を意味し、リラックス効果が高く、不眠症にも効果があるといわれており、古代より薬草として使われてきました。 エジプト人は発病を治すことから、この植物を太陽に献げ、また、冷却する効果があることから「月のハーブ」ともいわれています。また、カモミールの近くに植えている植物を元気にすることから「植物のお医者さん」ともいわれています
*******
カモミールジャーマン
カモミールジャーマンは、カモミールローマンと同じキク科の植物で、多くの共通点をもっています。香りもフルーティーでリンゴのような香りです。大きな違いとしては、第一にその精油の色です。カモミールジャーマンは濃い青色をしています。どちらオイルも「アズレン」という抗炎症作用をもつ成分を含みますが、カモミールジャーマンの方が多く含みます。カモミールローマン同様、リラックス効果が高く、不眠症にも効果があるといわれており、古代より薬草として使われてきました。 エジプト人は発病を治すことから、この植物を太陽に献げ、また、冷却する効果があることから「月のハーブ」ともいわれています。ローマンに比べ、作用が強いので、お子様にはローマンの方が向いているかもしれません
*******
カユプテ
"カユプテ"という名前は、マレーシア語で「白い木」を意味する「カユ=プティ」から由来しており、ホワイトティートリーとも呼ばれています。この樹皮h白っぽい色をしているためです。甘いハーブ調の香りで、しみとおるような感じです。ユーカリ、ティートリーなどと同じフトモモ科の植物で、感染症と闘い、それを防止するという特性を持ちます。また、この精油は女性ホルモンの一種であるエストロゲンに似た作用を持ち、更年期の障害を軽くするともいわれます。また、虫除けのスプレーなどにも有効です。
*******
カンファー
カンファーは防虫剤の樟脳(しょうのう)の香りとして有名で、非常にしみとおるような香りが特徴です。防虫剤としては、日本のみならず全世界的にも使用されている、歴史のある精油です。そのため、非常に刺激性が強いですので、使用の際は充分な注意が必要です。特に妊娠中やてんかん患者はこの精油の使用は避けた方がいいでしょう。この精油はこのように刺激性がありますが、古来より感染症全般に効果があるともいわれております。
*******
クラリセージ
シソ系のクラリセージは、ハーブ調の草木を感じさせる甘くスパイシーな香りを持ちます。非常に鎮静力が強いため、アロマテラピーではさまざまな場面に登場するオイルのひとつです。リラックス効果が高い分、ものごとに集中するのが困難になりますから、集中したい時は翔しない方がよいでしょう。また、スクラレオール(植物のホルモンと呼ばれています)という成分をふくんでいるため女性にとって不可欠なエストロゲンに似た作用を持ち、女性にとってうれしいパワーを発揮してくれます。脂っぽいヘアをさっぱりさせ、フケ防止にも効果があります
*******
グレープフルーツ
フレッシュで甘いシトラス系の香りで人気の高いオイルです。グレープフルーツの香りをかぐとダイエット効果がある、と某大手化粧品メーカーが発表して以来、愛用している人も多いのではないでしょうか。食欲を減退させ、脂肪代謝率を高めると評判です。このエッセンシャルオイルは食品、化粧品、香水などに幅広く使用されており、その香りはまさにグレープフルーツ特有のさわやかな芳香ですので、ストレスを感じている時などに使用すると幸せな気分になれます。他の柑橘系オイル同様、酸化しやすいため、6ヶ月以内に使用することをおすすめします
*******
クローブリーフ
クローブはアジアが主原産のフトモモ科の植物で、強くスパイシーなしみとおるような香りをもっています。古来より皮膚感染症や歯痛、虫除けなどに使われてきました。クローブ油は非常に強力な作用を持つオイルですので、充分な注意が必要です
*******
コリアンダー
料理の香辛料としても有名で、ピリッとしたスパイシーな香りがします。コリアンダーは古代から薬用され、料理のみならず、香料としても使われてきました。エジプト人はこれを幸福をもたらすスパイスと考えていたようです。また、インドでは肉が腐るのを遅くするために頻繁に用いられてきました。このハーブは現在でも世界各地で料理の材料として使われているように、食欲を促進する作用があり、食欲不振時や消化器系に不快感がある時にベースオイルとブレンドし,腹部をマッサージすると良いでしょう。
*******
サイプレス
地中海にうかぶキプロス島はサイプレスの木が崇拝されていた島として命名されました。古代文化においても、神聖な木として扱われていたようです。サイプレスの材は腐蝕しにくいということもあり、”永遠に生きる”という名もつけられています。森林浴をしているかのように、フレッシュでウッディーな香りがすがすがしい印象を与えてくれます。日本のヒノキの近縁種で香りもにているため、日本人にとってなじみのある心地よい香りです。集中力を高めたい時におすすめです
*******
サンダルウッド
ウッディーで甘く、深みのある香りは、お香としても有名です。サンダルウッドの木は60年ほどで成熟し、そのときに伐採されますが、現在、植樹が伐採に追いつかないことが深刻な問題になっており、近年ではインド政府が介入して植林事業が確実に行われていることが確認されています。古代からも親しまれているオイルで、リラックス効果が高く、神経の緊張と不安を和らげてくれ、幸福感や満ち足りた感情を抱かせてくれます。インド・中国では「万病の媚薬」として珍重されており、催淫特性が高く、特に男性に効果があるようです。
*******
シダーウッド
少し甘めのウッディーな香りです。サンダルウッドを思わせる香りでもありますが、もっとドライでウッディーな香りです。同じ森林系はもちろん、柑橘系、ハーブ系のオイルとも相性がよいため、隠し香的にブレンドするのに適しています。この樹木は古代から大切に扱われており、神殿を造るために使われてきました、それは材質の堅さと防虫効果が建設資材として高く評価されていたためです。オイルは神経が緊張している時や不安にかられる時などに、その鎮静に役立ってくれます。また、ヘアトニックとしての効果も高いので、希釈して使用してみてもよいでしょう
*******
シトロネラ
シトロネラは熱帯地方の各地に野生または栽培されており、その香りは軽く甘みのあるレモンのような香りを放ちます。昆虫を寄せつけず、衣服や動物(ペット)につく害虫を防いでくれます。また、感染を阻止する効果があり、心をすっきりさせ、気分を明るくさせる効果もあると言われています。シトロネラの最も広い用途は、外注忌避剤として使われるもので、市販の虫除け剤を製造するために大量栽培されています。また、石けんや家庭用除菌消毒剤などにもひろく利用されています。
*******
シナモンリーフ
お菓子づくりのスパイスでもおなじみのシナモンですが、その抽出部位は、花、蕾、樹皮、葉など、おのおのから抽出され、それぞれのエッセンシャルオイルは化学成分が異なっており、薬効にも差異があります。その中でシナモンリーフはその屋要が比較的穏やかなため、ほかの部位の精油より好んで使用されているようです。スパイシーで鋭く、ほのかに甘い香りのシナモンは疲れを癒し、心と身体をあたため、食欲をかきたてるようで、クリスマスの時期の香りとしても人気で、雰囲気を演出してくれるオイルでもあります。
*******
ジャスミンアブソリュート
ジャスミンはローズ(バラ)と並んで、最も魅惑的な香りを持つ花のひとつとされており、非常に強く、甘美でエキゾティックな香りです。ローズが「花の女王」と呼ばれているのに対し、ジャスミンは「花の王」と呼ばれてもいます。また、ローズ同様、このオイルを生産するのに大量の花が必要になるため、ジャスミン油は非常に高価なオイルとなってしまいます。それでもジャスミン油の香りはすばらしく、心身を和らげ、ストレスを無くしてゆったりとした気分にさせてくれます。
*******
ジュニパーベリー
お酒が好きな人ならご存知、ジンの香りづけに使われている植物です。心地よいウッディーな香りで、さわやかな森林浴をしている気分になれます。かつてフランスの病院では、長い間、ジュニパーベリーとローズマリーを焚いて病棟の空気を浄化させてきました。これはジュニパーベリーの殺菌効果が高いため、その時代の各種伝染病予防に使われてきたのです。また、この香りは頭脳を明晰にする作用があり、集中したいときにその効果を発揮します。同じ森林系のサイプレスとブレンドすることで、体内にたまった分泌物の排泄を促しますので、肥満やセリュライト対策をしたい方にはよいかも知れません。
*******
スペアミント
ペパーミントに似た香りで、ペパーミントより甘く、おだやかな香りで、ハミガキをした後のような爽快感があります。乗り物酔いや二日酔いに効果があり、気分をシャキっとしてくれます。また、消化器系にも働きかけますので、気分がすぐれない時にティッシュに数滴落として、近くに置いておくとすっきりできます。精油以外にもお菓子やお酒、お茶、料理などの香りづけにも多く用いられています。
*******
ゼラニウム
ローズに似た、甘く芳ばしいフローラルの香り。優雅なやさしい香りで、女性に人気のオイルです。不安な時や落ち込んだ時に、気分を明るくさせてくれます。心のバランスはもちろん、ホルモンや肌のバランスを整えます。スキンケア用としての評判が高く、皮脂分泌のバランスを保つ作用があるため、あらゆる肌質の方に適します。また、身体の中の悪いものを外へ排出してくれる作用があるようです。幸福な気分に浸りながら、身も心もきれいにしてくれることでしょう。
*******
タイム
タイムは高さ30センチほどの低木で、古来よりヨーロッパ諸国で民間植物療法で広く誓われてきました。その香りは甘く強いハーブ調のオイルです。タイムの芳香は疲労感を癒し、病後などの回復に大変役に立ってくれます。また、タイム油は非常に強力なオイルですので、身体の広い部分に使用しないほうがいいでしょう。また、妊娠中は使用しないほうがいいかもしてれません。
*******
タンジェリン
タンジェリンは濃いオレンジ色の果物で、軽くて甘い、柑橘ならではの香りです。マンダリンと植物学的には同じものに属してしる植物ですが、香りはマンダリンに比べ、若干ほのかな感じがします。作用は神経系を緩和させるかウォーターかがあり、ストレス解消や緊張緩和によても役にたってくれます。ビタミンCの含有量が豊富なので、よく妊娠中のアロママッサージに広く利用されるオイルでもあります。このオイルは、他の柑橘系のオイル同様、光毒性を示す恐れがありますので、使用直後に日光にあたることは避けたほうがいいかもしれません
*******
ティートリー
スパイシーでフレッシュなカンファーの香り。古来よりオーストラリアの原住民たちは、感染症をおこした擦傷などにティートリーの葉を利用していました。ティートリーの持つ殺菌作用は有名です。消毒効果が高いため、連鎖球菌やブドウ球菌などのさまざまなバクテリア感染症に対して抵抗力があり、また、抗ウイルス作用、抗真菌作用などもあるため、第二次世界大戦中、治療薬として緊急キットに入っていました。風邪やインフルエンザが流行する季節には欠かせないオイルです。
*******
ニアウリ
ニアウリはオーストラリアに多く生息するフトモモ科の大きな木で、甘くクリアでしみとおるような香りを持ちます。ニアウリの葉が落葉して地面を覆うと、強力な殺菌消毒剤となり、空気がクリアで健康的なものとなり、その周辺はマラリアなどの病気も見られないといいます。その殺菌消毒剤としての効果は、歴史的にも認められており、古来より役立てられてきました。リフレッシュ効果もあり、元気を回復させてくれ、集中力もアップします。
*******
ネロリ
オレンジの花から抽出されるオイルで、上品で華やかなフローラルの香り。リラックスしたい時や穏やかな気持ちになりたい時、ネロリの上質な香りは心地よい幸福感を与えてくれます。”ネロリ”という名前はイタリアのネロラ公国の后妃アンナ・マリナから由来したといいます。后妃はこのオイルを香水として愛用していました。現在もネロリは、極上の香水やオーデコロンの材料として使われています。ネロリは最高のオイルのひとつに違いないのですが、抽出するのに大量の花が必要になるため、非常に高価なオイルであることが唯一の欠点となるかもしれません
*******
バジル
世界各地にさまざまな種類があるバジルは、古来より料理や薬草として利用されてきたシソ科の植物です。その香りは、ハーブ特有のクリアでスパイシーな香りで、気分がふさぎがちな時や、精神的にまいっている時に効果を発揮してくれます。また、集中力を高める効果もあり、感覚を研ぎ澄ましてくれます。通経作用があるため、妊娠中は使用を避けたほうがいいでしょう。頭痛や偏頭痛に対し、かなり効きめがあるといわれています。
*******
パイン
森林を思わせるフレッシュな香りで、疲れた神経を癒し、リフレッシュさせ、落ち込んでいる心を前向きにまた、元気にさせてくれます。このオイルは身体を、温め清潔にすることから、石けんや入浴剤でもよく使用されています。また、部屋の中で香らせることで空気を浄化し、呼吸を深められます。少量でも効果が期待できますので、例えば、松ぼっくりを拾って来て、それにパインを乗じて部屋にかざるのも、趣深いと思います。ペットを飼っている方は、このオイルを使うとノミ退治の役割をしてくれます。敏感肌の方は刺激性があるので、注意が必要です
*******
パチュリ
熱帯地方の低木の植物から抽出されたオイルで、森もしくは土を連想させるエキゾチックで少しスパイシーな独特な香りです。特徴のあるこの香りは香水の成分としてもよく使われています。パチュリ油はワインと同様に年月を追うごとに深く熟成され、質も良くなっていく性質があります。また、このオイルの最も大きい特徴はその収れん作用にあり、ゆるんだ皮膚を引き締めるのに役立つといわれています。また、その香りは食欲を抑制する働きがあるとも言われ、ダイエット時にも利用価値がありそうです
*******
バニラ
非常になじみの深いバニラは、世界中で最もポピュラーな香りのひとつです。バニラはラン科の多年草で豆のようなサヤの形の実をつけます。そのサヤを完熟前に収穫、湯通しして、それを天日乾燥・保温を昼夜繰り返して発酵させたものが、ご存知、バニラビーンズです。そのエッセンシャルオイルの香りはとても豊かで、独特の甘い香りです。元気づけてくれ、リラックスできます。その官能的な香りから催淫剤のような働きもあります。とてもリラックス効果の高いオイルなので、集中したい時には使用を避けたほうがよいかもしれません
*******
パルマローザ
パルマローザはレモングラスと同じイネ科の植物で、かすかにローズに似た、フローラル系の香りで、その香りからローズ油の偽和剤に使われることもあるそうです。また、石けんや化粧品、香水などの成分としてもよく使われています。冷却作用と強壮作用をもち、風邪などの症状の時に方法すると効果を発揮してくれます。また、肌の水分バランスを整える作用があり、乾燥肌の人に適しています。その他、皮膚の再生にも効果があるといわれ、しわにもその効果が期待できそうです
*******
ファーニードル
シベリアモミ。針葉樹のなかにいるようなフレッシュで透明感のある香り。さまざまな感染症対策に力を発揮しますので、風邪やインフルエンザの予防に使うのも一考でしょう。また、呼吸器系に役立つ作用があり、体液や膿、粘液で気管支がふさがった症状に有効だとされています。息切れにもよく、呼吸の通りが楽になるような感じがします。パインとよく似ており、ともに部屋の中での森林浴に最適のオイルのひとつだと思います
*******
フェンネルスゥイート
フェンネルは、地中海地域でさまざまな種類が栽培されていますが、アロマテラピーで使用されるのは、スゥイートフェンネルと言われるものです。少しシパイシーなハーブ調の香りで、ハチが大好きな黄色い花を咲かせる植物で、ダイエット効果のあるオイルとして有名になりました。このオイルの香りは、満腹感を与え、食事の量を減らすことができるそうです。また、皮膚に対してはジワをつくらせない効果があるといわれています。ただ、強力な作用を持つオイルですので、妊娠中は使用を避けたほうがいいでしょう。
*******
プチグレン
プチグレンはオレンジの葉から抽出されるエッセンシャルオイルで、同じオレンジの花から抽出されるのがネロリ油、果皮から抽出されるのがオレンジ油です。同一の植物から三つの異なるエッセンシャルオイルが採れるのですから驚きです。プチグレンの香りは、ややネロリに似た、しかし、ネロリほど強くない、どちらかというと比較的穏やかな、洗練された香りで、疲労感を取り除き、リラックスさせてくれます。また、スキンケアにも向いており、ニキビ肌やふきでものの手入れによく使用されているようです
*******
ブラックペッパー
スパイスとして知られている、あのコショウの果実の精油です。白コショウより黒コショウの方が香りも強く、精油の採れる量も多いので、オイルの抽出には黒コショウが多く使われます。その香りは、おなじみの鋭くスパイシーな香りです。血行を促進し、身体を温める作用があり、その香りは食欲を刺激するといわれています。また、身体に滞った毒素を排泄浄化する作用があるともいわれ、肥満の解消にも役立つオイルと考えられています。強い作用をもつ精油ですので、芳香やマッサージには濃度に充分注意する必要があります。
*******
フランキンセンス
フランキンセンス(和名「乳香」、別名「オリバナム」)は、古来より珍重され、宗教的な儀式の場や医療現場などで使用されてきました。幼いイエス・キリストに、東方の三賢人が献上した物品のひとつと言われています。エジプトの女性はパックの原料として用いており、美容的にも優れた効果期待できるようです。香りは独特なウッディー調で、少し樟脳を思わせるようなすっきりとした感じです。心と身体、空間の浄化に使ったり、感情を安定させ、前向きな気分にしてくれます。
*******
ベチバー
ベチバーは主に熱帯地域に見られるレモングラスに似た野草で、その香りは土を連想させるウッディーな深みのある香りです。根茎から採れるこのオイルは、根が古いほど上質なものが採れ、また、サンダルウッドやパチュリなどと同様に年月を重ねるほど熟成され、質が良くなっていきます。オイルの特長は、その鎮静作用にあり、リラックスさせる作用が大きいことから、「静寂の精油」といわれています。また、血液循環器系を刺激する作用があり、疲労回復や筋肉痛を和らげるのにもよく使われています
*******
ペパーミント
ペパーミント~西洋薄荷(ハッカ油)~は歯磨き粉や消化薬、お菓子、酒など、さまざまなものの香りづけとして利用されてきました。メントール独特のスッとした香りを持つ、ウォータミントとスペアミントの交雑種で、ヨーロッパやアメリカで多く栽培されています。開花直前に採取したものをエッセンシャルオイルの抽出に使用します。軽く透き通ったその香りは、怒りを鎮め、精神的な疲労をやわらげ、気力を取り戻してくれます。また、呼吸器系や消化器系にも効果を発揮します。吐き気や乗り物酔いの時、ハンカチやティッシュに1滴落として嗅ぐと、不快感を鎮めてくれます。
*******
ベルガモット
ベルガモットは、ほかの柑橘類よりフルーティーでやさしい甘さのある香りをもっています。名前の由来は、はじめてこの樹木が栽培されたイタリアの小都市である「ベルガモ」からきています。ベルガモットの木は、樹高2~3メートルになり、その果実は洋ナシのようなかたちをしていて、表面はデコボコしています。オーデコロンにも多く使われております。また、紅茶のアールグレイの香りづけにも使われたりもします。気持ちを明るく、また、軽くしてくれる精油です。しかし、光毒性のある成分を含みますので、使用直後に日光にあたることは避けてください
*******
ベンゾイン(安息香)
ベンゾインは、和名「安息香」と呼ばれますが、これは息を安ずる効果があることからそう呼ばれるようになりました。バニラのような香りを持ち、香水の保留剤としても使われています。ヨーロッパでは昔から、薬の主成分にも使われていました。ベンゾインの樹脂は、樹の幹に傷をつけ、にじみ出た乳白色の分泌液を採取し、空気中に放置して、次第に赤褐色の塊状になったものを溶剤抽出法で抽出します。このオイルは、緊張とストレスを緩和し、気分を明るくしてくれます。バニラと同じく、眠気を誘うので、集中力か必要な時は使用を避けたほうがよいでしょう
*******
ホーリーフ
「ホ-リーフ」というオイルはあまり聞きなれないという方も多いかと思いますが、スキンケア用として人気の高いローズウッドが乱伐による絶滅の危機(ローズウッドの項参照)が表面化し、さまざまな規制が生じてきたため、その代用品としてアロマテラピー業界に広まりつつあるオイルです。ホーリーフはその名の通り、中国産の”ホー”の木の葉から抽出されるオイルで、ローズウッドに似たウッディーで上品な香りを持つオイルです。比較的マイルドなオイルなのでお子様からお年寄りまで幅広く使用できます。また、ローズウッド同様、スキンケアに向いており、そのマイルドさからもお試しの価値アリです
*******
マジョラム
マイルドでライトスパイシーな香りで、花や葉、茎はパスタ料理やソーセージ作りによく利用されています。古代ギリシャやローマでは非常にポピュラーで広く使われた薬草のひとつで、新郎・新婦がマジョラムの花の冠をつける習慣もあったといわれ、幸福をもたらすハーブとして信じられていました。眠りの香りとしてはラベンダーが有名ですが、それと並んでマジョラムの薬草の香りもまたよく眠りをさそってくれます。心身をくつろがせ、身体のエネルギーチャージを助け、生命力を高めてくれるハーブの香りです。
*******
マンダリン
マンダリンは、その昔、この果実が中国のマンダリン(高級官僚)への贈り物にされた伝統があったことから名づけられました。バレンシアオレンジに似た甘くフルーティーな香りで、神経の緊張をほぐし、張りつめた心を明るくし、興奮を鎮めてくれます。非常にマイルドなエッセンシャルオイルですので、お子様からお年寄りまで、幅広く、比較的安心してお使いいただけます。ニキビ肌や脂性肌・混合肌・妊娠線予防にも使えます。だし、光感作用がありますので、肌への使用後すぐに直射日光には当たらないようにしてください
*******
メイチャン
別名:リツェアクベバ。フレッシュでレモンのような柑橘系の香りを持ちます。レモングラスにも近い香りですが、レモングラスより穏やかな香りです。シトラールを多く含むため、香水や石けんにも多く使われています。落ち込んだ時や気分がさえない時、気持ちをリフレッシュさせ、元気を回復させてくれます。デオドラント効果や殺菌消毒作用があるので、風邪の季節をはじめとして、ルームフレッシュナーや芳香浴にも適しています。
*******
ユーカリ
皆さんよくご存知、あのコアラの大好物の植物です。ユーカリの木は世界で最も背の高い木のひとつで、とても丈夫な葉をつけます。オーストラリアの先住民・アポリジニが「キノ」と呼び、傷の手当てをはじめ万病薬として大切ににてきた歴史があります。ユーカリの種類は300種ほどありますが、エッセンシャルオイルの原料となる種は、その一部だけです。興奮した気持ちをすっきりと引き締め、精神を集中させてくれます。眠気を防ぐ効果もあるので、運転中にもおすすめします。また、風邪やインフルエンザの季節には、芳香浴で部屋の空気を浄化してくれ、花粉症に時期には呼吸を楽にしてくれます
*******
ライム
シャープな、にがみのある柑橘の香り。その清涼感でリフレッシュ効果が高く、元気で明るくなります。疲れた心を癒し、エネルギーを回復させる特性があります。また、抗菌・抗ウイルス作用をもち、芳香浴での利用が効果的でしょう。ジンジャーエールやコーラなどの清涼飲料水の香りづけにも用いられています。皮膚につけてすぐに日光に当たると光感作をおこすことがありますので、気をつけてください。
*******
ラバンジン
真正ラベンダーとスパイクラベンダーの交配種。真正ラベンダーとスパイクラベンダーが生育する中間地帯で広く栽培されており、上記2つのラベンダーより丈夫でオイルの収穫も多いようです。石けんや香水などにも幅広く使われておりますが、リラックス効果は真正ラベンダーと比べ、弱いのも特徴のひとつになります。香りはいわゆるラベンダーといわれるものよりライトな感じですので、リラックスではなく、リフレッシュする時に使用するとよいでしょう
*******
真正ラベンダー
ラベンダーは間違いなく、エッセンシャルオイルの中で最も利用価値の多いオイルのひとつです。安全性が高く、子供からお年寄りまで安心して使用でき、まさに「万能オイル」として人気です。心身のバランスを整え、夜寝つけない時に寝室に香らせると、不思議なくらい心地よい眠気がおとずれます。ラベンダーの種類は比較的多く、似た香りをもつものもありますが、ここで紹介しているラベンダーは真正ラベンダーで、いわゆるラベンダーの効果を期待するには、この真正ラベンダー(アングスティフォリア種)をお選びください。
*******
ラベンダー タスマニアン
ラベンダーは比較的種類が多い植物ですが、このオーストラリアのタスマニア島で栽培されるラベンダーは、数あるラベンダーの中でも最高の香りをもつとされ、世界中で人気となっています。その人気のため、タスマニアンラベンダー油の卸価格はここ数年急騰してきており、入手も困難な状態となっております。タスマニア独特の気候環境で独自に生育し、フランスやイギリスなどのヨーロッパ産のラベンダーと比べてマイルドで、格段に豊かな香りをもつとされています。最も広く使われるラベンダーオイルですが、世界が認めたこのラベンダータスマニアンオイル、試してみる価値はありそうです。
*******
レモン
誰もがよくご存知、さわやかの代名詞的な存在で、好感度の高い柑橘系の香りです。気分を明るくリフレッシュさせ、集中力を高めたい時やお部屋の空気を殺菌・浄化にも最適。レモンの木はインドが原産ですが、十字軍の戦いがきっかけでヨーロッパに伝わりました。今では米国のカリフォルニア、フロリダが大規模な産地となっています。このエッセンシャルオイルはレモンの果皮をローラーのようなもので圧搾して抽出しますが、エッセンシャルオイル1kgを生産するのに約3000個のレモンの果皮が必要です。皮膚刺激があるのでベースオイルにまぜるときは1%以下にするのがよいでしょう。
*******
レモングラス
レモングラスはその名前の通りレモンに似た香りが特徴で、古くから香料や儀式、料理などにも使用されてきました。心身をリラックスさせ、新しいエネルギーを注ぎ込むような働きがあります。虫除けに使われることも多く、また、消臭にも効果があります。芳香浴に向いている香りといわれています。
シトラールという成分を多く含んでいるので、敏感肌の方には刺激を与えることもあるので、ベースオイルに希釈するときはその希釈濃度に注意が必要です。
*******
レモンマートル
レモンマートルは、オーストラリアが原産のフトモモ科の樹木で、柑橘系のフレッシュな香りが特徴です。その香りは、レモンよりレモンともいえる、とてもさわやかな香りです。レモンマートルの主成分であるシトラールは、レモンの20倍ほどで、世の中のどのハーブや植物よりも豊富なシトラールを含み、鎮静作用、リラックス効果が高いことで知られてします。また、その消毒殺菌効果から、虫除けスプレーなどを作るときに大変よいオイルとなります。その他、集中力が必要な時の手助けをしてくれます
*******
ローズウッド
ローズウッドは南米・アマゾン流域に生育する常緑樹ですが、近年の乱獲により絶滅の危機が顕在化し、ブラジル政府は、ローズウッドの木を一本伐採するごとに一株の苗木を植樹することを義務づける法律を定めてその保護にあたっています。その香りはウッディーで、その名にもあるようにローズに似た香りを持っています。フランス語で「ボア・ド・ローズ」と呼ばれ、ブラシの柄や飾り棚にも多く使われております。このユニークな香りは私たちの気持ちを安定させ、元気づけてくれます。
*******
ローズアブソリュート
誰からも愛されるローズは純潔と愛の象徴として、また、神に捧げる花として結婚式にもよく使用されます。古代エジプトの女王・クレオパトラや古代ローマ皇帝・ネロにも好まれたこの花は、まさに人の心の花の部分、つまり、恋愛や富、芸術を表現するのに使われきた歴史があります。精神面に対する作用が特に顕著で心の安定とやすらぎをあたえてくれます。水蒸気蒸留法による抽出のローズオットーに比べ、やや安めであることなどから人気の高いローズアブソリュートですが、溶剤抽出法による抽出のため、わずかながら溶剤が残りますので、肌が特に敏感な方はローズオットーを用いたほうがよいかもしれなせん。
*******
ローズオットー
万人に愛されるローズは純潔と愛の象徴として、また、神に捧げる花として結婚式にもよく使用されます。古代エジプトの女王・クレオパトラや古代ローマ皇帝・ネロにも好まれたこの花は、まさに人の心の花の部分、つまり、恋愛や富、芸術を表現するのに使われきた歴史があります。花は午前10時頃に咲きますが、その精油の採取方法は、開花しそうなつぼみを朝露のある時に手袋をして摘み、ときどき手袋にしみた朝露をしぼって花が乾燥しないように作業します。そして、24時間以内に釜に入れ抽出するという、非常にデリケートな製造過程をとります。そのためたいへん高価で、これが唯一の欠点かもしれません
*******
ローズマリー
地中海の陽射を浴びて、元気いっぱいに育つローズマリーは、ラテン語で「海のしずく」を意味します。心身を元気づけるハーブで、ヨーロッパでは虚弱な人のための香りとして使われてきました。邪気をはらい、記憶力を高めるとも言われています。ヨーロッパのある地方では昔、新郎新婦が靴にこのハーブをしのばせ、永遠の誠心を誓いあう習慣があったそうです。14世紀のハンガリー王妃がローズマリーを主原料とした化粧水で美と健康を取り戻し、高齢にもかかわらず隣国の王子に求婚されたという話は有名です。香りはすっきりとしたハーブ調で、やる気や記憶力、集中力を高めたい時にお試しください。
*******
吉野ひのき
日本人ならどこか覚えのあるすっきりとした香りです。切りたての樹木を思わせる清潔感あふれる感覚です。古来よりヒノキ風呂や日本の著名な建造物にも多く使用されていることからも日本を象徴する樹木のひとつです。ヒノキで建てた住宅は百年もつといわれています。この香りにふれていると、どことなくリラックスした気分になれます。是非、ご自宅のお風呂でこのエッセンシャルオイル(精油)を数滴たらしてみてください。秘湯にでも来たような気分になれますから。ただし、作用が強いオイルでもありますので、ご使用の前に必ずパッチテストを行ってからお楽しみください
*******
青森ひば
ヒバは古来から抗菌や防虫などの効能で知られており、日本の古い建造物などにも広く使用されております。ヒノキチオールを多く含み、そのさわやかで瑞々しい香りは、まるで森のなかを散策しているかのような錯覚に陥ります。リラックス効果のみならず、落ち着いて物事を進めたいときに力になってくれる精油です。その用途は多岐にわたり、主な原産地の青森では「医者いらず」といわれおり、実際に青森県はインフルエンザなどの感染数も少ないそうです。
この精油は、同じ「和の香」であるヒノキとも相性がよく、このふたつの精油のブレンドは非常に奥深いものがあります。お試しの価値アリです
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- スピリチュアル・ライフ
- ★11月20日はコンタクト記念日★
- (2025-11-20 08:58:48)
-
-
-

- ダイエット日記
- ダイエット143日目 新しい洗顔、化…
- (2025-11-20 08:05:08)
-
-
-

- 今日の体調
- なんだか風邪っぽい気がします(T_T)
- (2025-11-06 12:17:40)
-
© Rakuten Group, Inc.