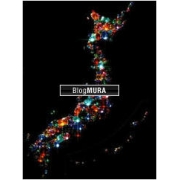PR
Keyword Search
 New!
Pearunさん
New!
PearunさんMちゃんママから長… New! flamenco22さん
^-^◆ 学びの宝庫・…
 New!
和活喜さん
New!
和活喜さんWリーグトヨタ紡織チ…
 クラッチハニーさん
クラッチハニーさん風に向かって クリス…
 千菊丸2151さん
千菊丸2151さんComments
Freepage List
Calendar
![]()
![]()
![]()
「上杉景勝と兼続の最後の合戦」
(六)
上洛を果たした景勝主従は、直ちに家康に謁見した。
上座に天下人となった家康が肥満した体躯を脇息にもたれさせている。
傍らには謀臣の本多佐渡守正信が控えていた。
景勝と兼続は臆した態度もみせず、家康の前に平伏した。
「中納言、上洛が遅かったの」
家康が垂れ下がった目蓋の奥から、鋭い眼光をみせ訊ねた。
「伊達、最上がうるさく上洛が遅うなりました」
景勝が臆した態度も見せず、武骨な口調で謝罪した。
「わしに背いた罰とし改易も考えたが、この正信がうるさくての」
「大御所、我等は貴方さまに叛いた事実はござえませぬ」
「景勝殿、もう言い訳はよい」
家康がくだけた口調で話しを遮った。
「わしが小山から、軍勢を返した時に国境から一歩も踏みださなんだ事を
愛で、反逆の罪は問うまい」
家康は景勝の毅然とした態度に感銘をうけていた。流石は、戦国最強の
上杉謙信の血筋じゃ。その上杉家の家風への評価であった。
「じゃが、条件がござる。会津百二十万石は没収いたす。異存はござるまいな」
「あいや、お待ち下さい」 直江兼続が声をあげた。
「何じゃ、山城守」
「その後の上杉家は如何なりましょうや?」
「会津から直ちに、その方の米沢三十万石へ転封いたせ」
「有り難き幸せに存じあげます」
兼続を制すように景勝が礼の言葉を述べた。
「中納言殿、転封はお帰りになったら直ちにお願いいたす」
本多佐渡守正信が、しわがれ声で告げた。
「畏まりました」
こうして減封のほかはお構いなしの処分で済んだ。しかし、転封までの期限
は厳しいものであった。米沢の町は会津から移った家臣達で大騒ぎとなった。
この狭い米沢城下では、大勢の家臣達の住む家もなければ食う物もない。
直江兼続はこの緊急の時に、人より大切なものはないと一軒の屋敷に入れ
るだけの家臣を住まわせ、炊き出しをして飢えを凌がせた。
上杉家の家臣は棒禄を三分の一に削られたが、誰一人として他家に移る者
はなかった。それだけ主人景勝と執政兼続に魅力があったのだ。
家臣等の生活や城下町の建設は、執政、直江兼続の仕事であった。
景勝も兼続も徳川家康の高齢で近い将来、何が起こっても不思議はないと考
えていた。その為に優れた家臣を多く残して置きたかった。
その一環として兼続は新城下町の造成の際、侍屋敷からはみ出した下級
藩士等、千四百戸を城下の東と南の郊外に住まわせ開墾に従事させた。
所謂、屯田兵制度である。
これらの藩士は原方衆と呼ばれ、薩摩の兵児(へこ)と並び称される頑強な
郷土集団となった。
更に兼続は北方の最上、伊達勢の進攻に備えた新城下町の建設に取り掛か
った。まず本丸を中心とし、半径一里ほどの等距離の位置を選び、五十箇所
以上の寺院を築かせた。むろん一見したら普通の寺院である。
しかし、兼続は寺院が城郭の働きをするように設計したのだ。
本丸を守るように、円錐状にスキ間なく配置された寺院は、堅牢な楼閣とな
り、いざ合戦ともなれば、ただちに巨大な城郭の機能を果たすよう縄張りをし
た。また墓石にも工夫が施された。これを万年堂とも鞘石とも呼ばれ、内部
をくり貫いた立方体の塔に屋根をのせたもので、屋根を外し細木を通せば、
二人あるいは四人で簡単に動かせ、積み重ねれば石塁となり銃眼となった。
こうした配慮をすると同時に、前にも書いたように火縄銃の密造にも意を
配った。更に、兼続時代に鋳造された直江釜と呼ばれる大鉄瓶があるが、
これらはいくつか現存する。硬度が普通の鋳物の二倍もするので重いが、
一朝有事の際には、鋳つぶして兵器の原材料にする為に、造らせたものと
伝えられている。こうした用意周到ぶりを示した直江兼続には、もうひとつ推し
進めた施策があった。 続く