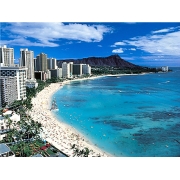PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
まだ登録されていません
カテゴリ: 「京」ものがたり
「ちょっと言いたくなる京都通」として奥深い京都の良さや
京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、
わかりやすく紐解いていきたいと思います。
ぜひ身近に京都を感じてください。
さて、京都の神社仏閣を巡っていると、
素晴らしい庭園を拝観できることがあります。
中でも、力強い石組みとモダンな苔の地割りで構成される
ある枯山水庭園を拝観した際には、しばし時間を忘れて見入ってしまったほどです。
今回は、それほどに心を惹きつけて止まない庭園を作った、
■ 京都には三玲作の庭が結構あるんえ。
重森三玲(1896年~1975年)という昭和を代表する作庭家をご存知でしょうか?
数年前にテレビコマーシャルで三玲作の枯山水が美しい映像で紹介され、「何なのだろう?
この研ぎ澄まされたスタイリッシュな庭は…」と、思った方も多かったようです。
これまでご紹介した「泉涌寺」「東福寺」にも、三玲作の素晴らしい庭園がありました。
重森三玲没後30年以上経った今でもその新しさ、モダンさ、斬新さは少しも色褪せることはありません。
さて、重森三玲とはどのような人物だったのでしょうか? 彼は日本美術学校で日本画を学び、生け花、茶道を研究。
その後作庭に関しては独学で習得したそうです。
庭園家として知られる以前は、「新興いけばな宣言」の発表準備をし、生け花の世界でも革新を起こした人物です。
生け花、茶道、作庭…これらは、重森三玲の芸術活動の3本柱でした。
その中でも、三玲がその生涯をかけて、自身の生きざまを入魂して創作し続けたものが、庭園づくりの石組みでした。
よく、「まるで生け花のように、瞬間的な感性で石を置いていった」と評されますが、それは庭を生け花に見立てたという意味ではなく、庭における石組の奥義と生け花、茶の湯の奥義に共通したものがあり、その根底にある日本の伝統文化の特質を見事に表していたのです。
力強い石組みとモダンな苔の地割りで構成される三玲の枯山水庭園。
その代表作として、京都の東福寺方丈庭園、光明院庭園、大徳寺山内端峯院庭園、松尾大社庭園などがあります。
近年、日本は大きな変革を遂げましたが、重森三玲の庭園は変わらぬ姿でずっとそこにあったのです。
しかし、今また人々の心を惹きつけて止まず"三玲の庭を訪ねる京都"は、崇高で格別なる時間をもたらしてくれます。
重森三玲という人物の真髄に触れるなら、"重森三玲庭園美術館"をぜひお訪ねください。
重森三玲の旧宅は、吉田神社の社家(しゃけ=代々特定神社の神職を世襲してきた家(氏族)のこと)として名高い鈴鹿家から昭和18年に重森三玲が譲り受けたものです。
もともと江戸期の建造物でしたが、三玲が新たに設計して建てた2つの茶席(無字庵 昭和28年、好刻庵 昭和44年)、さらに書院前庭や茶庭、坪庭も自作でつくられました。
新旧融合の独特な威光を放っています。
重森三玲の旧宅そのものが格式ある社家建築の素晴らしさを伝える、ほぼ唯一の遺構として文化財的価値があるものです。(旧宅内の書院、茶室は既に国の登録文化財)
茶の湯を心から愛した三玲の旧宅では、ほぼ各部屋で茶の湯が嗜めるようになっていました。
前庭の絶景を愛でることができる書院でも、茶の湯は行なわれました。
この重森三玲の旧宅の魅力は、庭園が住まいとしての江戸期の建物と調和し、茶の湯を中心にした暮らしにフィットしていることにあります。
ところで、重森三玲は人間的に非常に吸引力のある人で、
多くの人が彼の周りに集まりました。
交流のあった人々は、庭園・建築関係だけでなく、生け花、茶道はもとより、宗教、学術、出版に至るまで幅広く、そうそうたる面々でした。
1950年代から親交を深めたイサム・ノグチもその一人。
彫刻家で家具や照明などのインテリアデザイナーなど多彩な才能を開花させたイサム・ノグチは、世界的にユニークな芸術活動を展開していました。
庭・公園の環境設計を手掛ける際、三玲に相談したことが交友の始まりだったそうです。
三玲が79歳で亡くなった後も、ノグチは京都を訪れる度に三玲を懐かしみ、この旧宅を訪れたそうです。
■ 庭ではなくアートとして見ておくれやす。
美しい日本庭園は、ここ京都には数々あります。
しかし、重森三玲の庭は、通常イメージする日本庭園とかなり異なる印象で、さまざまな寺社に存在します。
どれも鮮烈な個性を放っていますが、それらを全て総括して、重森三玲なのです。
そんな説明をすると、なんだか難しいように思われるかもしれませんね。
三玲の庭の愛で方を重森三玲庭園美術館の館長であり、三玲のお孫さんでもある重森三明氏に尋ねました。
「三玲は普段は穏やかで大人しい人でしたが、内には荒々しい気持ちを常にもっていて、創作活動を通して、世の中を変えたいと思っていた人でした。
日本の庭園芸術は、江戸以降、長い間これといって新しいものが生まれていなかった閉ざされた時期がありました。
そんな庭の世界に根底から地割れを起こすがごとく、時代を揺るがすほどの芸術として登場したのが三玲作の庭でした。
芸術には、作家の何がしかのメッセージが込められているのです。
ですから、三玲の庭は、単に庭だと思って見るのではなく、芸術作品として、作品が訴えようとしている何かを受け止めていただけたらと思います。
こちらにお越しいただいて、三玲の庭を向き合ってもらえば、きっとお解かりいただけると思います」
さらに「三玲の庭は、決まったルールやパターン化されたものでなく、いろいろな素材が、ある意味、微妙な複雑さで同居しています。
また、新しいもののヒントは過去に必ずあり、三玲の場合も、古典や太古の昔の芸術に影響を受けています」
そんなお話を伺って、重森三玲の庭をまた見つめてみました。
時間が止まり、何か崇高な空気が全身を包み込んでくれるように感じずにはおれません。
昭和のモダニズムを追求し、生ききった一人の芸術家の遺功は、あなたが来るのをじっと待っているようです。
※飛び石の上に置かれた、丸い石は、茶の湯の席に招待された方が迷わずに、自分で目的の茶室に辿り着けるための、案内表示となっています。石がある方へは進まず、石のない方へ進んでくださいという意味のものです。
取材協力:重森三玲庭園美術館(重森三玲旧宅・庭園)
京都市左京区吉田上大路町34
電話 (075)761-8776
京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、
わかりやすく紐解いていきたいと思います。
ぜひ身近に京都を感じてください。
さて、京都の神社仏閣を巡っていると、
素晴らしい庭園を拝観できることがあります。
中でも、力強い石組みとモダンな苔の地割りで構成される
ある枯山水庭園を拝観した際には、しばし時間を忘れて見入ってしまったほどです。
今回は、それほどに心を惹きつけて止まない庭園を作った、
■ 京都には三玲作の庭が結構あるんえ。
重森三玲(1896年~1975年)という昭和を代表する作庭家をご存知でしょうか?
数年前にテレビコマーシャルで三玲作の枯山水が美しい映像で紹介され、「何なのだろう?
この研ぎ澄まされたスタイリッシュな庭は…」と、思った方も多かったようです。
これまでご紹介した「泉涌寺」「東福寺」にも、三玲作の素晴らしい庭園がありました。
重森三玲没後30年以上経った今でもその新しさ、モダンさ、斬新さは少しも色褪せることはありません。
さて、重森三玲とはどのような人物だったのでしょうか? 彼は日本美術学校で日本画を学び、生け花、茶道を研究。
その後作庭に関しては独学で習得したそうです。
庭園家として知られる以前は、「新興いけばな宣言」の発表準備をし、生け花の世界でも革新を起こした人物です。
生け花、茶道、作庭…これらは、重森三玲の芸術活動の3本柱でした。
その中でも、三玲がその生涯をかけて、自身の生きざまを入魂して創作し続けたものが、庭園づくりの石組みでした。
よく、「まるで生け花のように、瞬間的な感性で石を置いていった」と評されますが、それは庭を生け花に見立てたという意味ではなく、庭における石組の奥義と生け花、茶の湯の奥義に共通したものがあり、その根底にある日本の伝統文化の特質を見事に表していたのです。
力強い石組みとモダンな苔の地割りで構成される三玲の枯山水庭園。
その代表作として、京都の東福寺方丈庭園、光明院庭園、大徳寺山内端峯院庭園、松尾大社庭園などがあります。
近年、日本は大きな変革を遂げましたが、重森三玲の庭園は変わらぬ姿でずっとそこにあったのです。
しかし、今また人々の心を惹きつけて止まず"三玲の庭を訪ねる京都"は、崇高で格別なる時間をもたらしてくれます。
重森三玲という人物の真髄に触れるなら、"重森三玲庭園美術館"をぜひお訪ねください。
重森三玲の旧宅は、吉田神社の社家(しゃけ=代々特定神社の神職を世襲してきた家(氏族)のこと)として名高い鈴鹿家から昭和18年に重森三玲が譲り受けたものです。
もともと江戸期の建造物でしたが、三玲が新たに設計して建てた2つの茶席(無字庵 昭和28年、好刻庵 昭和44年)、さらに書院前庭や茶庭、坪庭も自作でつくられました。
新旧融合の独特な威光を放っています。
重森三玲の旧宅そのものが格式ある社家建築の素晴らしさを伝える、ほぼ唯一の遺構として文化財的価値があるものです。(旧宅内の書院、茶室は既に国の登録文化財)
茶の湯を心から愛した三玲の旧宅では、ほぼ各部屋で茶の湯が嗜めるようになっていました。
前庭の絶景を愛でることができる書院でも、茶の湯は行なわれました。
この重森三玲の旧宅の魅力は、庭園が住まいとしての江戸期の建物と調和し、茶の湯を中心にした暮らしにフィットしていることにあります。
ところで、重森三玲は人間的に非常に吸引力のある人で、
多くの人が彼の周りに集まりました。
交流のあった人々は、庭園・建築関係だけでなく、生け花、茶道はもとより、宗教、学術、出版に至るまで幅広く、そうそうたる面々でした。
1950年代から親交を深めたイサム・ノグチもその一人。
彫刻家で家具や照明などのインテリアデザイナーなど多彩な才能を開花させたイサム・ノグチは、世界的にユニークな芸術活動を展開していました。
庭・公園の環境設計を手掛ける際、三玲に相談したことが交友の始まりだったそうです。
三玲が79歳で亡くなった後も、ノグチは京都を訪れる度に三玲を懐かしみ、この旧宅を訪れたそうです。
■ 庭ではなくアートとして見ておくれやす。
美しい日本庭園は、ここ京都には数々あります。
しかし、重森三玲の庭は、通常イメージする日本庭園とかなり異なる印象で、さまざまな寺社に存在します。
どれも鮮烈な個性を放っていますが、それらを全て総括して、重森三玲なのです。
そんな説明をすると、なんだか難しいように思われるかもしれませんね。
三玲の庭の愛で方を重森三玲庭園美術館の館長であり、三玲のお孫さんでもある重森三明氏に尋ねました。
「三玲は普段は穏やかで大人しい人でしたが、内には荒々しい気持ちを常にもっていて、創作活動を通して、世の中を変えたいと思っていた人でした。
日本の庭園芸術は、江戸以降、長い間これといって新しいものが生まれていなかった閉ざされた時期がありました。
そんな庭の世界に根底から地割れを起こすがごとく、時代を揺るがすほどの芸術として登場したのが三玲作の庭でした。
芸術には、作家の何がしかのメッセージが込められているのです。
ですから、三玲の庭は、単に庭だと思って見るのではなく、芸術作品として、作品が訴えようとしている何かを受け止めていただけたらと思います。
こちらにお越しいただいて、三玲の庭を向き合ってもらえば、きっとお解かりいただけると思います」
さらに「三玲の庭は、決まったルールやパターン化されたものでなく、いろいろな素材が、ある意味、微妙な複雑さで同居しています。
また、新しいもののヒントは過去に必ずあり、三玲の場合も、古典や太古の昔の芸術に影響を受けています」
そんなお話を伺って、重森三玲の庭をまた見つめてみました。
時間が止まり、何か崇高な空気が全身を包み込んでくれるように感じずにはおれません。
昭和のモダニズムを追求し、生ききった一人の芸術家の遺功は、あなたが来るのをじっと待っているようです。
※飛び石の上に置かれた、丸い石は、茶の湯の席に招待された方が迷わずに、自分で目的の茶室に辿り着けるための、案内表示となっています。石がある方へは進まず、石のない方へ進んでくださいという意味のものです。
取材協力:重森三玲庭園美術館(重森三玲旧宅・庭園)
京都市左京区吉田上大路町34
電話 (075)761-8776
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[「京」ものがたり] カテゴリの最新記事
-
★「京都の祭・時代祭り」 2025.10.22
-
★「五山の送り火」 2025.08.16
-
★祇園祭 毎年7月1日… 2025.07.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.