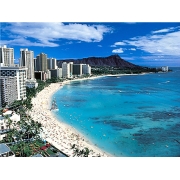PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
まだ登録されていません
カテゴリ: 「京」ものがたり
「ちょっと言いたくなる京都通」として奥深い京都の良さや
京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、
わかりやすく紐解いていきたいと思います。
ぜひ身近に京都を感じてください。
今回は、『時雨殿』という美しい名前の体験型展示施設をご紹介します。
小倉百人一首の選者である藤原定家の別荘「小倉山荘」の
別称「時雨亭」にちなんで付けられた「時雨殿」。
小倉山に程近い嵯峨野で、小倉百人一首の起原、
かるたの歴史など古典文学や日本文化を学んでみませんか?
今回は、ちょっと趣向をかえた夏の暑気払いとして、小倉百人一首の体験型博物館「時雨殿」をご紹介します。
急流で有名な保津川下りの終着点に近づくと、左岸に小高い山が見えます。
この山が、小倉百人一首の発祥の地「時雨亭」があった地です。
「時雨亭」は、小倉百人一首の選者である藤原定家の別荘「小倉山荘」の別称。
その小倉山に程近い嵯峨野で、「時雨亭」にちなんで建てられたのが「時雨殿」です。
「時雨殿」は、従来の博物館とは異なり、最先端のデジタルエンターテイメントを駆使した体感型施設。
百人一首のいろはを知らない人でも、ゲーム感覚で充分に楽しめます。
入館するとまず、石庭の美しさに目を奪われます。
まるでストライプ柄のように敷きつめられた砂利が涼しさを誘う、風流な光景です。
1階は展示室、2階は120畳の大広間があり、1年に1度、全日本クラスのかるた大会が開かれています。
また、2階は江戸時代の「雛かるた」「錦絵かるた」、大正時代の「板かるた」など、様々な時代のめずらしいかるたも展示されています。
ナビゲーターを手にして進むと、京都市街が大きく映し出された迫力ある床スクリーン「フロアビジョン」にたどり着きます。
その上に立って、ナビゲーターを利用すると、自分が行きたい名所まで案内してくれ、京都の街を空中散歩する気分が味わえます。
そして、このフロアビジョンはなんと、巨大な百人一首の70枚の札に変わり、制限時間内で何枚の札が取れるかを競うシステムになっているのです。かるた遊びに童心に戻り、思わず夢中になる人も多いそうです。
フロアを囲むように歌が書かれたパネルが行灯のように、美しくライトアップされています。
パネルの前に立つと歌の朗詠や解説も聞けます。
「久しぶりにあなたに逢ったが、あなたかどうかも見分けがつかないうちに、慌ただしく帰ってしまった。
雲の間に隠れてしまった月のように」という意味です。
解説があるといっそう百人一首が楽しめます。
この歌は、まるで愛しい恋人のことを歌っているようですが、実は数年ぶりにあった幼なじみのことを指しており、久しぶりにゆっくり話せると思っていたのに話せなかった残念さを歌にしたと伝えられています。
調べるほどに面白さがわき上がるようです。
色鮮やかな70枚の札やライティングに写しだされる歌が、絵巻のように華やかな館内。
次は、百人一首に関するクイズ「謎解きの井筒」で、頭をますますブラッシュアップしましょう。
クイズに回答していくと、知的好奇心がかきたてられてきます。
また、「体感かるた五番勝負」では、 歴史上の人物と疑似対戦ができます。
清少納言、蝉丸、大弐三位、紫式部、藤原定家たちと「かるた取り」で対戦し、見事に五人抜きを達成した人は「名人位認定証」が授与されるそうです。
一度、挑戦してみませんか。
※ 「体感かるた五番勝負」での「名人位認定証」の授与は、火曜~金曜のみ開催。
夏休みなどの繁忙期は行っていません。
また、10名以上の団体では代表者数名のみの参加となります。
■ 藤原定家は作家にして鋭いエディターどすわ。
「時雨殿」で楽しく遊びながら、百人一首を体感していくうちに、小倉百人一首の起原について興味が湧いてきました。
その成り立ちについて少したどってみましょう。
百人一首は、100人の歌人の和歌を一首ずつ集めた選集。
そのさきがけとなったのが、歌人、藤原定家によって、「古今集」や「新古今集」などの10の勅撰和歌集から選び抜かれた「小倉山荘色紙和歌」です。
後に、多くの模倣作品と区別する意味から、嵯峨野の小倉山付近にあった定家の別荘にちなんで「小倉百人一首」と命名されました。
藤原定家は鎌倉時代前期に活躍した歌人。
歌道家の子として生まれ、早くから歌人としての才能を発揮し、その活動ぶりはエネルギッシュだったと言われています。
定家は歌人としてだけでなく、「古今和歌集」をはじめ、「伊勢物語」「源氏物語」などを書写し、校訂を加えました。
それらが有名な「定家本」と呼ばれている書物で、日本文学において、後世への貢献は計り知れないと言われています。
すぐれた歌人であり、日記や随筆も書く、作家としての才能にもあふれ、編集者としても厳しく確かな目を持っていた定家。
その人生は、華やかなことばかりではなく、後鳥羽院との確執により、公の場での出座・出詠を禁じられた時期もありました。
承久の乱により、後鳥羽院が隠岐に流されると、西園寺家と九条家の後援を得て復活。
「新勅撰和歌集」の単独撰者という名誉をもたらされました。
そのような紆余曲折の人生にあった定家が鋭い審美眼で厳選した「小倉百人一首」。
本物は色褪せることがないのだという、定家の狙いどおり、800年を経た今もなお、多くの人々に愛されています。
「小倉百人一首」は、100首のうち恋の歌が43首、四季の歌が32首。
恋の歌集と言われるだけあり、恋心を詠んだ歌が目立ちますが、歌風としては、心の機微や日々の心模様、花や山の美しい情景などを耽美的に表しています。
100人の歌人のうち、女性は21人、僧侶は15人です。
清少納言と藤原実方朝臣(ふじわらのさねかたあそん)は恋仲だったと言われ、歌の中にカップルをさがし出すのも楽しいでしょう。
飛鳥時代から鎌倉時代初期まで、約600年の代表的な和歌が時代順に配列されています。
「小倉百人一首」を通して、王朝に生きた人々の心象風景に触れることができます。
■ 「かるた」はポルトガル語で「カード」どすえ。
江戸時代に入ると、「歌かるた」となって親しまれる「小倉百人一首」ではさらに、かるたについても検証してみましょう。
私たちが、現在親しんでいるものは、歌人の肖像画が描かれた「歌仙絵」と呼ばれるものに由来します。
「歌かるた」は、日本の伝統的な「貝覆(かいおおい)・歌貝(うたかい)」と、ポルトガルから伝わった「天正かるた」が融合して生まれたと言われています。
そもそも「かるた」は、ポルトガル語で「カード」という意味。
16世紀に近い天正年間にポルトガルの宣教師と一緒にやってきた船乗りたちが、日本に「カード」を持ち込みました。
それが「天正かるた」です。
「貝覆」とは、平安時代にハマグリを使って行った「貝合わせ」という優雅な遊びのことです。
出されたハマグリの外側を見て伏せられているハマグリの中から、ぴったりと合うハマグリを探すというルールです。
後世になると、ハマグリの内側に源氏絵・花鳥・武具などの豪華な一対の絵が描かれるようになり、さらに、歌が記されることもありました。
そのため「貝合わせ」が「歌かるた」の原型だと言われています。
室町時代に公家の間で楽しまれた、「かるたとり」が、戦国時代に入り、競い合う「歌合わせ」として、宮中を中心に行われるようになったそうです。
江戸時代には、急速に庶民の間にも浸透していき、明治の頃になると、一般家庭でもかるた大会が開かれるようになりました。
昔から左右に分かれて競いあったと言われています。
そして競技としての「かるたとり」が今に残されました。
新感覚の博物館「時雨殿」が位置する嵐山界隈には、「小倉百人一首」の歌碑が点在しています。
「歌碑巡りマップ」もこちらでもらえるので、歌碑を訪ねてみるのも楽しい発見があるかもしれません。
夏バテ気味の心身をリフレッシュできる「時雨殿」。
優雅な遊びを楽しみ優美な石庭を愛でてクールダウンしてみませんか。
取材協力:小倉百人一首殿堂 時雨殿
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11
電話 (075)882-1111
京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、
わかりやすく紐解いていきたいと思います。
ぜひ身近に京都を感じてください。
今回は、『時雨殿』という美しい名前の体験型展示施設をご紹介します。
小倉百人一首の選者である藤原定家の別荘「小倉山荘」の
別称「時雨亭」にちなんで付けられた「時雨殿」。
小倉山に程近い嵯峨野で、小倉百人一首の起原、
かるたの歴史など古典文学や日本文化を学んでみませんか?
今回は、ちょっと趣向をかえた夏の暑気払いとして、小倉百人一首の体験型博物館「時雨殿」をご紹介します。
急流で有名な保津川下りの終着点に近づくと、左岸に小高い山が見えます。
この山が、小倉百人一首の発祥の地「時雨亭」があった地です。
「時雨亭」は、小倉百人一首の選者である藤原定家の別荘「小倉山荘」の別称。
その小倉山に程近い嵯峨野で、「時雨亭」にちなんで建てられたのが「時雨殿」です。
「時雨殿」は、従来の博物館とは異なり、最先端のデジタルエンターテイメントを駆使した体感型施設。
百人一首のいろはを知らない人でも、ゲーム感覚で充分に楽しめます。
入館するとまず、石庭の美しさに目を奪われます。
まるでストライプ柄のように敷きつめられた砂利が涼しさを誘う、風流な光景です。
1階は展示室、2階は120畳の大広間があり、1年に1度、全日本クラスのかるた大会が開かれています。
また、2階は江戸時代の「雛かるた」「錦絵かるた」、大正時代の「板かるた」など、様々な時代のめずらしいかるたも展示されています。
ナビゲーターを手にして進むと、京都市街が大きく映し出された迫力ある床スクリーン「フロアビジョン」にたどり着きます。
その上に立って、ナビゲーターを利用すると、自分が行きたい名所まで案内してくれ、京都の街を空中散歩する気分が味わえます。
そして、このフロアビジョンはなんと、巨大な百人一首の70枚の札に変わり、制限時間内で何枚の札が取れるかを競うシステムになっているのです。かるた遊びに童心に戻り、思わず夢中になる人も多いそうです。
フロアを囲むように歌が書かれたパネルが行灯のように、美しくライトアップされています。
パネルの前に立つと歌の朗詠や解説も聞けます。
「久しぶりにあなたに逢ったが、あなたかどうかも見分けがつかないうちに、慌ただしく帰ってしまった。
雲の間に隠れてしまった月のように」という意味です。
解説があるといっそう百人一首が楽しめます。
この歌は、まるで愛しい恋人のことを歌っているようですが、実は数年ぶりにあった幼なじみのことを指しており、久しぶりにゆっくり話せると思っていたのに話せなかった残念さを歌にしたと伝えられています。
調べるほどに面白さがわき上がるようです。
色鮮やかな70枚の札やライティングに写しだされる歌が、絵巻のように華やかな館内。
次は、百人一首に関するクイズ「謎解きの井筒」で、頭をますますブラッシュアップしましょう。
クイズに回答していくと、知的好奇心がかきたてられてきます。
また、「体感かるた五番勝負」では、 歴史上の人物と疑似対戦ができます。
清少納言、蝉丸、大弐三位、紫式部、藤原定家たちと「かるた取り」で対戦し、見事に五人抜きを達成した人は「名人位認定証」が授与されるそうです。
一度、挑戦してみませんか。
※ 「体感かるた五番勝負」での「名人位認定証」の授与は、火曜~金曜のみ開催。
夏休みなどの繁忙期は行っていません。
また、10名以上の団体では代表者数名のみの参加となります。
■ 藤原定家は作家にして鋭いエディターどすわ。
「時雨殿」で楽しく遊びながら、百人一首を体感していくうちに、小倉百人一首の起原について興味が湧いてきました。
その成り立ちについて少したどってみましょう。
百人一首は、100人の歌人の和歌を一首ずつ集めた選集。
そのさきがけとなったのが、歌人、藤原定家によって、「古今集」や「新古今集」などの10の勅撰和歌集から選び抜かれた「小倉山荘色紙和歌」です。
後に、多くの模倣作品と区別する意味から、嵯峨野の小倉山付近にあった定家の別荘にちなんで「小倉百人一首」と命名されました。
藤原定家は鎌倉時代前期に活躍した歌人。
歌道家の子として生まれ、早くから歌人としての才能を発揮し、その活動ぶりはエネルギッシュだったと言われています。
定家は歌人としてだけでなく、「古今和歌集」をはじめ、「伊勢物語」「源氏物語」などを書写し、校訂を加えました。
それらが有名な「定家本」と呼ばれている書物で、日本文学において、後世への貢献は計り知れないと言われています。
すぐれた歌人であり、日記や随筆も書く、作家としての才能にもあふれ、編集者としても厳しく確かな目を持っていた定家。
その人生は、華やかなことばかりではなく、後鳥羽院との確執により、公の場での出座・出詠を禁じられた時期もありました。
承久の乱により、後鳥羽院が隠岐に流されると、西園寺家と九条家の後援を得て復活。
「新勅撰和歌集」の単独撰者という名誉をもたらされました。
そのような紆余曲折の人生にあった定家が鋭い審美眼で厳選した「小倉百人一首」。
本物は色褪せることがないのだという、定家の狙いどおり、800年を経た今もなお、多くの人々に愛されています。
「小倉百人一首」は、100首のうち恋の歌が43首、四季の歌が32首。
恋の歌集と言われるだけあり、恋心を詠んだ歌が目立ちますが、歌風としては、心の機微や日々の心模様、花や山の美しい情景などを耽美的に表しています。
100人の歌人のうち、女性は21人、僧侶は15人です。
清少納言と藤原実方朝臣(ふじわらのさねかたあそん)は恋仲だったと言われ、歌の中にカップルをさがし出すのも楽しいでしょう。
飛鳥時代から鎌倉時代初期まで、約600年の代表的な和歌が時代順に配列されています。
「小倉百人一首」を通して、王朝に生きた人々の心象風景に触れることができます。
■ 「かるた」はポルトガル語で「カード」どすえ。
江戸時代に入ると、「歌かるた」となって親しまれる「小倉百人一首」ではさらに、かるたについても検証してみましょう。
私たちが、現在親しんでいるものは、歌人の肖像画が描かれた「歌仙絵」と呼ばれるものに由来します。
「歌かるた」は、日本の伝統的な「貝覆(かいおおい)・歌貝(うたかい)」と、ポルトガルから伝わった「天正かるた」が融合して生まれたと言われています。
そもそも「かるた」は、ポルトガル語で「カード」という意味。
16世紀に近い天正年間にポルトガルの宣教師と一緒にやってきた船乗りたちが、日本に「カード」を持ち込みました。
それが「天正かるた」です。
「貝覆」とは、平安時代にハマグリを使って行った「貝合わせ」という優雅な遊びのことです。
出されたハマグリの外側を見て伏せられているハマグリの中から、ぴったりと合うハマグリを探すというルールです。
後世になると、ハマグリの内側に源氏絵・花鳥・武具などの豪華な一対の絵が描かれるようになり、さらに、歌が記されることもありました。
そのため「貝合わせ」が「歌かるた」の原型だと言われています。
室町時代に公家の間で楽しまれた、「かるたとり」が、戦国時代に入り、競い合う「歌合わせ」として、宮中を中心に行われるようになったそうです。
江戸時代には、急速に庶民の間にも浸透していき、明治の頃になると、一般家庭でもかるた大会が開かれるようになりました。
昔から左右に分かれて競いあったと言われています。
そして競技としての「かるたとり」が今に残されました。
新感覚の博物館「時雨殿」が位置する嵐山界隈には、「小倉百人一首」の歌碑が点在しています。
「歌碑巡りマップ」もこちらでもらえるので、歌碑を訪ねてみるのも楽しい発見があるかもしれません。
夏バテ気味の心身をリフレッシュできる「時雨殿」。
優雅な遊びを楽しみ優美な石庭を愛でてクールダウンしてみませんか。
取材協力:小倉百人一首殿堂 時雨殿
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11
電話 (075)882-1111
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[「京」ものがたり] カテゴリの最新記事
-
★「京都の祭・時代祭り」 2025.10.22
-
★「五山の送り火」 2025.08.16
-
★祇園祭 毎年7月1日… 2025.07.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.