
信州伊那谷の卵や
2025年11月22日
■ 木曽谷へ、ひとっ走り
伊那谷の卵屋の僕ら、今回はお隣の木曽谷へ。
昔は塩尻まで出てから中山道を南下して……1時間半。遠かったなぁ〜。
でも今は権兵衛トンネルを抜ければ 40分で木曽
。
そこから北へ15分で 奈良井宿
に到着!午前の仕事を終えてからでも余裕で行けちゃう、便利な時代です。

ここへわずか45分で来られる便利さ
■ インバウンドの波と、宿場町のいま
少し前は平日ガラガラで心配になるほど静かだった奈良井宿。
でも最近は京都・奈良・東京に飽きた海外の方が、レンタカーで訪れていることも。宿場町にとっては、これはこれで必要な流れなんでしょうね。
とはいえ、 静かに歩きたいなら、お隣のちょっと南下した穴場の木曽福島宿
もおすすめ。
美味しいお店も多いし、たぐちさん・かねまるパンさんなど名店もあり。
秋は栗子餅、初夏はほうば巻などなど、季節を感じる名品もあります。

時間をずらしたり、場所を変えるとほとんど人がいないところもちらほらあるのが奈良井宿の良いところ
■ さて、本題。なぜ奈良井宿へ?
今回、なぜ僕が奈良井に来たかというと……
栗子餅? ちがう。五平餅? ちがう。そば? いや、もちろんうまいけどそれでもない。
……と、ちょっと引っぱりましたが、実は 目的が2つ
。
まずひとつめは――

会津屋さん ここのおせんべいを買いに
■ 会津屋さんのおせんべいが食べたかった!
北側のSL広場の駐車場から歩いて10分ほど。
線路を渡り、T字路の左側にある 会津屋さん
。ここのおせんべいが、とにかく美味い!
- 上にクルミがのった甘辛せんべい
- 真っ赤なのに意外と辛くない唐辛子せんべい
この2つが大好きなんです。
味は……ぼんち揚げ? 歌舞伎揚げ? 近いけど違う! 独特のしっとり食感
と手作り感が、もう唯一無二。
写真を撮る前に食べ切っちゃったのは内緒。

江戸時代この街道を歩いて行ったのか~と感慨深く
今回はもうひとつの目的の場所、奈良井駅の方へ。
ちょっと散策するとその途中には大宝寺というお寺が。。。
以前から気になっていたのが、、、お寺なのになぜ???

マリア像がまつられている
なぜ大宝寺に「マリア」がいるのか?
1. 隠れキリシタンの信仰
江戸時代、キリスト教は禁止されていたため、信者たちは密かに信仰を続ける必要がありました。
大宝寺の地蔵尊は「子育て地蔵」を装っていますが、胸には十字架の刻みがあり、隠れキリシタンが「マリア」として信仰していた伝説があります。
2. 発見の経緯
昭和初期に藪の中から発見。頭部や手などは欠けていましたが、子どもが持つ蓮の茎が十字架に見えるなど、マリアを思わせる特徴があります。
3. 寺としての背景
大宝寺は臨済宗のお寺。拝観料(100円)で参拝可能です。
【まとめ】
マリア地蔵は、隠れキリシタンが密かに信仰するために作った像と伝えられています。仏教に偽装し、禁教時代の迫害の痕跡も残る、歴史的なスポットです。
和風と洋風が混在する不思議な空間。
どうりで外国人観光客の方々が入っていくわけだと納得しました。

歩いてきたのを振り返り鍵の手を見る
向こうの突き当たりが 奈良井宿の「鍵の手」。
🔑 鍵の手って何?
江戸時代の宿場町で、 敵が一気に攻め込めないよう、あえて道をカクッと折り曲げた
防衛・防火の構造。「鍵のように曲がっている」ことからそう呼ばれます。

こちら側からむかって行くとちょうど家が正面に
🏘 奈良井宿の鍵の手はどこ?
奈良井宿の中心付近、会津屋さんやきむらやさんの近くに 道が直角に折れているポイント
があります。
奈良井駅から鳥居峠へ向かって歩くとクランクになっていて、すぐ分かります。
🏯 なんでそんな構造にしたの?
① 防衛:
② 防火:
風の通り道を分断し、火事が広がるのを防ぐ。
③ 景観:
街並みに奥行きを持たせる。

2階の軒の下に出ている白い漆喰壁が「うだつ」
◆奈良井宿の「うだつ」とは?
「うだつ(卯建)」は、隣家との境に張り出した 防火壁兼ステータスの象徴
。
立派なうだつを建てるにはお金がかかるため、「うだつが上がる(=出世する)」の語源にもなりました。
奈良井宿では、木曽漆の町並みに溶け込む重厚な造りが見られます。

ガイドさんが一生懸命説明を
やっぱり宿場町は魅力的。欧米や東南アジアの方まで、多く訪れていました。

旅籠の雰囲気を残して

歩いてきた後ろを振り返ると山がすぐそばに。鳥居峠がこの奥
鳥居峠(とりいとうげ)
奈良井宿の北側、中山道の難所。かつては旅人が越えた峠道で、今はハイキングコースとしても人気。
奈良井宿から徒歩で向かえますが、山道なので靴はしっかりしたものを。
※現在は熊出没注意のため、安易なおすすめはできません。

玄関に対して奥行きが、、、横からみるとこんなに長い
奈良井宿の「うなぎの寝床」
間口が狭く奥行きが長い「うなぎの寝床」形式の家屋。
税金対策や防火・防風の工夫であり、1階を商売、2階を住居として使うのに適した構造です。
奈良井宿を歩くと、その奥行きの長さを体感できます。

奈良井宿はこうして街道が細いところと狭いところが続く
夜の風情も良さそうですが、宿場町の中には旅館は少ないので、宿泊は木曽福島などが中心になりそうです。

当時の人たちも見た景色かなと

建物の中をみられたかと
■ そして、もうひとつの目的
会津屋さんから奈良井駅の方へ歩いて、鍵の手を通り過ぎ、さらに200メートルほど。
お団子の「きむらや」さんの並びにある、 笹屋酒店
さん。
ここで売っている 井筒ワインの「生ワイン」
が、時期限定で知る人ぞ知る逸品!一般の酒屋ではほとんど見ません。
ワイン好きなら絶対に飲んでほしい一本です。(ちなみに主は下戸)
■ ふらり旅の締めくくり
帰り際、線路を渡ると電車の音が……「来た来た!」とちょっと得した気分に。
そんな小さな発見も楽しい、奈良井宿のふらり旅でした。
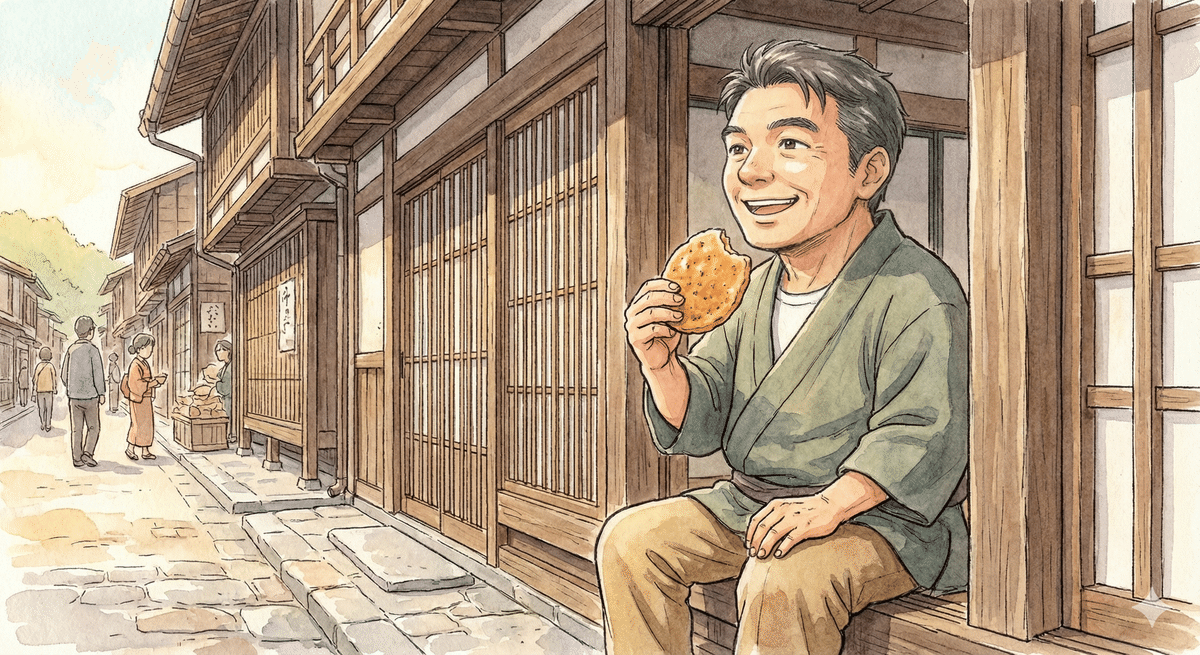
PR
キーワードサーチ
フリーページ
カレンダー









