ICカード75の質問
ICカード75の質問
NTTカードソリューションのHPにこのようなページ
http://www.u-card.co.jp/faq/faq_ic01.html
があったので抜粋転載させていただきました。
(1) ICカードはいつ頃誰が発明したのですか?
→1974年に(仏)ロラン・モレノ氏がICカード製作世界特許を取得しています。
(2) ヨーロッパの方が普及しているそうですが、何故ですか →これにはさまざまな説がありますが、やはり、必要性の問題と考えられます。欧州ではキャッシュカードやクレジットカードの偽造問題が早くから発生しておりカード自体のセキュリティを高める必要があったこと、オンライン環境がなかなか整わずオフライン利用のできる媒体が必要であったことなどがあげられます。フランスでは銀行カードの不正使用率が1987年からの10年間で10分の1に減少したというデータがあります。
(3) フランスではテレホンカードがICカードだそうですが、日本のICテレカと同じものでしょうか? →双方ともICカードであることでは共通です。しかし、フランスでのテレホンカードは『接触式』ICカードで発行されており、日本で導入されたものは『非接触式』のICカードです。フランスは1984年にICテレホンカードが実用化され、日本の非接触ICテレカは1999年3月に発行開始されています。
(4) ICカードにはCPU付きとCPU無しがあるそうですが、どこがどう違うのですか? →CPU(中央演算装置)付きのICカードは、ICカード単体で演算を行うことができます。このため、カードとホスト間の認証や通信データの暗号化に高度な処理を施すことができ、セキュリティを高めることができます。対してCPUが付いていないものはICメモリカードとも呼称され、データを書き込む・読み出すことで利用されます。フロッピーディスクと同じような機能でCPUがないためシステムの開発は容易になります。 ICカードが高機能・高セキュリティと言われるのはこのCPUを搭載できるからこそという言い方もできるのです。
(5) ICカードは、磁気カードなどに比べセキュリティが高いと言われていますが、どうしてですか? →磁気ストライプカードもICカードも専用のカードリーダを介さなければ読み出しができないことは同じです。しかし磁気カードはカードリーダさえ用意できれば書き込まれている内容を読み出すことは容易です。対してICカードはカードリーダを用意しても書き込まれている内容を読み出すことはある程度の専門知識を必要としますし、CPUを搭載したICカードであれば高度な暗号化を実施することができ、これを解読することは非常に困難となります。
(7) 1枚いくらぐらいするのですか? →ロットとメモリサイズ、CPUの有無によりますが、CPU付き1kメモリ1000枚ロットで1000円/枚程度です。
(8) どうして日本ではICカードが普及してないのでしょうか? →様々な要因があり一概には言えませんが、比較的安全な国であったため現金の持ち歩きに危険が少なく現金のカード化自体について需要がなかった、また、組織的なカード偽造などで磁気カードシステムが根本的に脅かされるようなことがなかったこと等があげられます。インターネット等に代表されるEC(Electronic Commerce)への対応という点でもICカード化は加速するものと思われます。
(9) ICカードには大きく分けて、非接触式と接触式があるそうですが、違いはなんですか?→リーダライタとの通信方式が異なります。 『接触式』はカードをリーダライタに差し込んでカード表面の金属端子とリーダライタの接点が接触して電力の供給やデータ通信を行います。世界中で最も多く利用されているタイプです。 対して『非接触式』はカード内部にコイル状のアンテナを内蔵しホストに接続されたアンテナ(リーダライタ)と電源の供給や通信を行います。このためカード表面に金属端子が露出していません。カードリーダにカードをかざすだけで情報のやりとりができる利便性があり、入退室管理等に採用されています。反して電源の供給が不安定になりがちであるためCPUの搭載には不向きです。1999年に発行開始されたNTTのICテレホンカードや2001年開始のJR東日本のSUICAが非接触タイプです。
(以下省略)
(11) ICカードリーダライタの方が磁気カードのものより安価だそうですが、何故ですか? →ICカードリーダライタと磁気カードリーダライターとでは、上位機との接続部と筐体が必要なことでは共通しています。しかしカードとの通信部としてICカードリーダは電気信号をICチップに伝える接点が装備されていればよいのですが、磁気カードには磁気ヘッドが必要となります。また、磁気カードには特定のデータのみを送出するような機能はないため、磁気リーダは簡単なロジックを組み込むことができる様にされているものが多いのです。このため安価なICカードリーダが登場している現在、磁気カードリーダの方が若干高価という状況になっています。
(12) ICカードで複数のサービスが1枚で受けられるそうですが? →ICカードは磁気カードの約100倍以上のメモリを持ち、CPUを搭載することが出来るため1枚のカードに複数のアプリケーションを格納することができます。このため、全く異なったサービスを1枚のカードで処理することが可能なのです。
(14) 携帯端末に装着するSIMカードもICカードですか? →欧州で使用されているSIMカード(Subscriber Id entity Module Card)はICカードの一種です。ただし、サイズは異なり、ICチップに縁取りが付いている程度の大きさです。
(15) ICカードのICチップはいくらぐらいするものなのでしょうか?→ICチップだけを購入するということが非常に困難ですので単価は不明です。カードの 単価から逆算すると数百円ではないかと考えられます。
(16) ICカードの取り扱い上の注意点を教えてください。 →接触式のICカードはプラスティックカードにICチップを貼り付けているため、また、非接触ICカードはカード内部にアンテナ線やCPUが埋め込まれているため、カードの折れや曲げに対しては注意が必要です。また、カードに高熱を加えることも避けなければなりません。
JISでは物理特性や耐熱性の規定があり、カード長方向で2cmのたわみ及び15度以上のねじれを30回/分で計1000回行っても、60℃の温水に5分間浸せきしてもカードの機能を保つこと、カード表面に変化のないこと等が記述されています。
(17) 接触式や非接触式ICカードはどうして動作しているのですか?→接触式のICカードのCPUはリーダライタの接点を介して電源が供給されて動作します。非接触ICカードのCPUはカード内に装備された電池から電源供給を受けるものとカード内は無電池でアンテナから電源を供給されて動作するものがあります。
(23) ICカードを導入しようとしている国レベルのプロジェクトがあるそうですが、その概要を教えてください。
→平成11年8月に住民基本台帳法案が成立したことによって5年以内に住民基本台帳カード(略して住基カード)を希望者に交付することが決定されました。この住基カードはICカード化されることがほぼ決定しています。 また、運転免許証や健康保険証などもICカード化が検討されています。
(24) ICテレカでは通話機能の他にも使い道がありそうですが?→非接触式テレホンカードのメモリの一部にオートダイヤル用のメモリが有って、ダイヤルデータを登録利用することができます。また、今後はIDコードを書き込んで会員カードとしての利用やポイントカード、更には電話機にセットすると表示部に広告画面が出る広告カード等が検討されている様です。
(25) 電子マネーの実験が各地で行われたそうですが、簡単に紹介してください。 →各地で活発な実験が行なわれていますが、小規模なものにとどまっているのが実情のようです。ただし、郵政省が実施しているさいたま市大宮を中心とした郵便貯金の『郵貯ICカード』は注目されています。郵便貯金の自分の口座から最大10万円までをプリペイドエリアに一旦振り替えて、指定の店舗で利用できるというもので、公衆電話やJRの切符も購入できるというものです。プリペイドエリアに振り替えている期間も利息が付くというのも安心感があります。また、渋谷区を中心とした『渋谷スマートカード』はVISAキャッシュで世界最大規模とも言われ業界を代表する実験でした。
(26) ICカードが普及すると本当にユーザにメリットはあるのでしょうか? →今までの磁気カードと比較するとメモリ容量や安全面でICカードの方が圧倒的に有利です。この事を機能として生かしたカードであれば必然的にメリットがあると思います。ただし、発行会社毎にカードを制作して何枚も持っていなければならないとしたら、かさ張って不便な一面もあります。
(27) 盗まれたICカードの中から個人情報などが流失する危険はないのでしょうか?→暗号化されたデータやファイルを開く為の暗号鍵等があってカードの中のデータを読み取るのはかなり困難ですが危険性はゼロではありません。例えば鍵データや読み取りソフトそのものが流失した場合が非常に危険です。従って、信頼のある会社と上手にお付き合いすることが大事です。
(28)出光興産が発行している出光Mydoカードは2000年末で2000万枚以上を発行しています。接触式のS型ICカードです。
(31) 接触式のICチップは金メッキしているそうですが、何故ですか?→ICカードの金メッキされた接触面とリーダライタの接触ピンによる接触接続の方法によって通信を行っていますが、ICカードの接触面や接触ピンが錆びたりすると接触不良が発生します。また金の電気抵抗は金属の中でも一番低いため電気的なロスが少なく安定した通信ができます。カードの見栄えを良くする為にピカピカの金メッキをしたのでは有りません。
(32) カード一枚あたり何グラムぐらい金は使われているのでしょうか?→いろいろ問い合わせたのですが、企業秘密との事で教えて頂けません。ですが色々な話の前後から大体0.01g程度と類推できます。仮に0.01gであるとすると、これを金額に換算すると現在の金相場でグラム千円前後なので計算上は10円となります。ICチップを沢山集めて金を取り出しても割に合いません。
(35) ICカードの発行に関して、領域貸与という考え方があるそうですが。→ ICカードのメモリ内の一部を発行主体とは異なる他のアプリケーション事業者に対し開放することを指します。領域貸与を受けた場合、貸与を受けたメモリ内は発行主体の干渉なく自由に使える場合と発行主体の管理の元にアプリケーション事業者がデータを割り付ける場合などがあるようです。
(36) 非接触式ICカードはいろいろな方式があるそうですが、簡単に説明してください。→
① 通信距離による分類 ・ 密着型(0~2mm程度)・ 近接型(1~20cm)・ 近傍型(1m前後)・ 遠隔型(数m)
② 伝送媒体による分類
・ 電磁結合方式・ 電磁誘導方式・ 共振タグ方式。
③ アクセス(メモリ)方式による分類
・ カードやチップ側がリードオンリーメモリタイプのもの。
・ カードやチップ側がリード/ライトメモリタイプのもの
④ 電源による分類
・電池が不要なタイプ。・電池を搭載するタイプ。
⑤ その他通信方式や通信速度、変調方式等分類。
(38) ICカードで個人認証はできないといわれましたが本当ですか? →本当です。ICカードが本物であるかの認証は暗号やその他の手段で可能です。しかしながら、カードを持っている人が本人であるか否かは別問題です。そこでカード所持者が本人であるかを調べる為には、予め指紋データや虹彩データ等を登録して、実際にカードを持ってきた人の指紋や虹彩等を調べてカード内データと照合し確かに同一人であると言う証明が行われてこそ個人認証です。ICカードは個人認証を行う為のデータの入れ物と考えるべきです。
(41) ICカードを使った電子マネーを発行すると何か法律の規制を受けるのでしょうか? →現行の法律では特にICカードに限定した法規制は有りません。むしろ運用面での法規制を受ける場合が有ります。一般論として関係すると思われる最低限の法律は以下の通りです。
・紙幣類似証券取締法 ・出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律・前払式証票の規制等に関する法律・印紙税法 ・不当景品類及び不当表示防止法。その他、運用する場面に応じた固有の関連法律があります。
(43) クレジットカードの偽造が横行しているようですが、ICカードに替わることで防げるでしょうか?→現行のクレジットカードでは磁気ストライプに記録されたデータが特殊な磁気カードリーダで読み取られてしまう恐れがあります。ICカードでは記録されたデータを読み取る為には、データファイルをオープンする暗号鍵やデータに施されている暗号を解析する必要があり、偽造防止の有力な手段です。
(44) 非接触式ICカードの種類でタイプA、B、Cがあると聞きましたが何のことですか?
→非接触ICカードは市場のほうが先行して実用化が進んでおり、ISO化があとから追いかけている状況となっています。その中でも近接型(ISO/IEC14443)については既に複数仕様のカードが発行されて実際に運用されているため、ISOでは仕様の統一を事実上断念し、それぞれをタイプA・B・Cと呼称して審議しています。
タイプAはMIFAREカードを代表的で主にヨーロッパで普及しているものです。
タイプBはMOTOROLA等が扱っており主に米国が推奨しています。
タイプCは日本のSONYが中心となっておりFeliCaカードがその一種です。
それぞれ使用する周波数帯域など共通する部分は多いのですが、周波数の変調方式や通信速度が異なっており、どれも一長一短と考えられています。
(47) デビットカードって何ですか? →銀行が発行したキャッシュカードそのままで買い物等の支払いができる新らたな機能を持ったカードと言う事で、かっこ良くデビットカードと呼んでいます。買い物等での支払い時、銀行に登録してある4桁の暗証コードを専用端末で入力する事により銀行の口座引き落としができます。クレジットカードは与信限度枠が有って利用最高額の規制が有りますが、デビットカードの場合は預金残高分までであればいくらでも買い物が可能です。
(49) 非接触ICカードの特徴を活かしたシステムにはどんなものがありますか?→非接触式ICカードは機械的な駆動部分や磨耗の心配が無いので頻繁にカード処理をするシステムに向いています。この良い例が非接触式ICカード方式のテレホンカードや定期券でしょう。またカードをかざすだけでしかも読み取り速度も速い為、操作性を買われて入退室管理システムや在室/在館システム、勤務管理システムに向いています。
(50) 非接触ICチップって何ですか? →非接触式ICカードと言うのはカード基材の中にICチップとコイルの組み合わせを埋め込んだものなんです。そしてICチップは半導体集積回路で構成されていてメモリや無線式の通信機能を持っています。最近ではカード形状以外にも時計型、ガラス管封入型、コイン型等いろいろあって、用途に応じて使い分けしています。
(52) 住基カードって何ですか?→正しくは住民基本台帳カードと言います。住民基本台帳における本人確認の為 の情報(氏名、住所、性別、生年月日)をICカードに登録し、全国どこからでも住民票の写しを入手したり、転入・転出の手続ができます。 平成15年8月から本人が申請すれば交付されます。(有料)またICカード内の空エリアの一部を利用して、地域サービスにも利用する予定です。
(53) Suicaカードって何ですか? →本来はSuper Urban Intelligent CArdの略称で『スイスイ』行けるIC・CARDとも言われているJR東日本のSuica定期券とSuicaイオカードの名称です。ここで利用されているカードは非接触ICカードであり、改札ゲートのリーダライタにカードをタッチ&ゴーして利用します。Suica定期券はリライト印刷して再利用できることが大きな特徴です。
(54) スクラッチカードって何ですか?
→IDコードやパスワード等の文字を隠すために、その文字の上に特殊な塗料を印刷したカードのことで、硬貨等の金属で擦ることにより塗料の下の文字を読むことができます。 『Web Money』や『ぷりコール』に利用されています。
昔は、カードの裏から強い光を当てると文字が読めてしまう事がありましたが、現在では塗料が改善されています。
(57) ICカードを拾ったら →現行の法律の範囲では単なる物としての処理となり、例え100万円チャージされている電子サイフ用途のICカードであっても"もの"として処理されるかも知れません。もし電子サイフの中味迄一緒に貰ったとしてもIDやパスワードが判らないとただのカードであり、今後の法整備が待たれている状況です。
(58) ICカードを落としたら →現在の所、使い捨てのICカードはあまり存在しておりませんので、大体が登録制となっており、名前やIDコード等によりカードの所有者が判る仕組みとなっています。従って、カードを落としたらまず、そのカードの発行元に連絡をとりましょう。
(61) ICカードと脅威 →ICカードの中のデータは厳重に鍵がかけられ、且つ暗号化されているので他人に中を覗かれたり複製されたりする事は困難であり、これがICカードは偽造に強い特徴でもあります。一方運用盲点としての『なりすまし』があります。本人が所有する本物のICカードを盗んだりして、本人になりすまして悪用することです。実際はパスワードが設定されているかと思われますが誕生日や電話番号を登録したのでは安全と言えません。また顔写真が印刷されていると言っても簡単に上から他人の顔写真を貼ったりすることができるので、よくよくの事でない限り発見は難しいでしょう。従って、管理を厳重にするならば、ICカードが本物かと言う事意外に、そのカードの持っている人も本物かと言う確認が必要です。
(62) 韓国のICカード事情 →釜山で釜山銀行、国民銀行が中心となってリチャージ式プリペイドカードの『ハナロカード』が発行されています。このカードは交通機関(バス、地下鉄)、タクシー、大手デパート、公衆電話での利用が可能で1998年より運用が開始されました。カードは非接触ICカード・タイプ(A)、最近はコンビネーション型も開発されたと聞いています。 また、同じ釜山に釜山銀行の子会社であるマイビ社が2000年9月より発行している『デジタル釜山カード』があり、交通機関の電子サイフ用途以外に行政カード、ポイントカード、銀行カード、クレジットカード機能が搭載されています。 ICカードは接触EMV、非接触タイプ(A)のコンビカードです。 更に『Kキャッシュ』と呼ばれるICカードがあり、1996年に金融機関共同の電子マネーとして韓国政府が導入決定、2000年3月にソウル駅三同地区で商用テスト、2002年3月から春川市、金海市、大丘市の各自治体で実用化開始されました。このICカードはあたかも経済産業省が推進するIT装備都市構想と同じ趣です。
デジタル釜山カード(mibi)
(63) 香港のICカード事情→香港の6つの交通事業者により設立された合弁会社が運営している多目的の非接触ICプリペイドカードとして『オクトパスカード』(中国語で八達通カード)があります。用途は公共交通を始め駐車場、ファーストフード、コンビニ、自販機、レジャー施設等の80種類以上のサービスに利用可能です。毎日、1100万人の人が様々な交通機関で利用しているとのこと。カードは日本のSONYのFelicaが採用されています。最近は腕時計タイプのオクトパスウオッチも導入されているとか・・・
(64) ETCとICカード →ETC(Electronic Toll Collection)は、有料道路料金所でのキャッシュレス決済を目的とした新しい料金支払いシステムで、料金所で一旦停止することなく、料金支払いができます。自動車と料金所とは電波による通信によって料金データ等のやり取りを行い、実際の料金の引き落としはEMV仕様の接触ICカードを利用しクレジットカード処理を行います。
(67) 『つれてって』カードとは?→赤穂信用金庫、商工会議所、駒ヶ根市役所などが集まって従来のスタンプカードに代わるシステムを検討し、以来長野県の駒ヶ根市、飯島町、中川村での商業活性化を目指しICカードを使用したポイントサービスとプリペイド機能を盛り込んで『つれてってカード共同組合』が運用しています。
カードには共同組合が発行するつれてってカードと赤穂信用金庫が発行するしんきんつれてってカードの2種類があります。
(68) Edyカードとは?
→ソニーグルーブやドコモ等が株主となって設立したビットワレット社が発行する非接触ICカードを使用した電子マネーカードのことです。このカードはSONYのFelicaの技術が使用されておりリアル/バーチャルでの決済に利用できます。リアル店舗ではコンビニのam/pm、品川インターシティ、パーク24等があり、バーチャル店舗ではSo-nete-Mart、e-SCOTT等があります。
(69) 行政ICカードの現状と将来
→現在3つのプロジェクトが活動していると考えられます。
1. 住基カード・・・住民基本台帳法に基づく個人認証用カード
2. 行政カード・・・地方自治体による地域住民向け公共サービスカード
3. IT装備都市カード・・・21のIT装備都市向けの実証実験カード
注、3項は平成13年度3月/末にて実験は終了しました。
なお、これらのカードがバラバラに発行されると所有するカードの枚数が増え、またどこにどのカードを使用するのか混乱する事から、行政カードに公共関連の機能を集約する方向で検討が開始されました。
(70) 健康保健証ICカード
→社会保険庁は主に中小企業のサラリーマンが入る政府管掌健康保険の保険証を同年度からICカードに切り替えて、家族も含む加入者全員に配る計画です。
それに引き続いて、組合・国民健康保険も厚生労働省がカード化を進める予定となっています。カードの中には検診結果や検査情報等を書き込み本人の健康管理や衣料の重複診療を防止することが可能です。
(71) 非接触ICカードの形状 →非接触ICカードの大きさと言えば、テレホンカード形状と思われがちですが、ICカードとリーダライタとは無線による通信なので、カードの大きさや形状の制約がありません。従って、丸や三角のカードが有っても立派に機能します。また非接触ICカードの中にはICチップとコイルが内蔵されていますが、このチップとコイルを取り出して腕時計の中や携帯電話の中に装着することも可能です。香港のオクトパス腕時計は典型的な例でしょう。
(72) IT装備都市カード →平成12年度補正予算172億円を投じて実施する『IT装備都市研究事業』の一貫として、21都市を選定して実証実験が行われ、そこで使用されているカードのことを言います。カードのタイプとしては主に非接触ICカードが利用されています。NTTグループとして参加した都市は、札幌市、山形市、久留米市、会津若松市、横須賀市、藤沢市等があります。 その多くの利用用途としては、地域住民に対する行政サービス(印鑑証明、住民票)、診察券、図書館利用券、プリペイド機能(交通機関、買い物等)等です。
(73) アンチコリジョンとは?→非接触ICカードの通信には無線が利用されています。従って、複数枚のカードを同一通信エリア内で一緒に持っていたとすると、どのカード共同じ周波数の為、通信時にデータが衝突することになります。従って、一定の順序や手続きによって複数枚のカードを識別して読む機能のことを言います。
(74) ICカードと残高確認 →従来のPET式のプリペイドカードの場合、正確ではないにしろ、カードに開けたパンチ穴によってある程度は残額が判りましたが、ICカードになるとその殆どが使い捨てでは無く、何らかの手段でしか残高の確認ができないのが実情です。
現在の所、以下の方法が多い様です。
売上伝票・・残額を印字するもの
Web・・通じてカード残高を知る方法
携帯電話・・・・iモード等を介して確認します。
リライト印字・・カード表面に書き換え可能な印字を行う方法。(現在500~1000回の書換え可能)
JR東日本のSuica定期がその代表例です。
(75) ICカードの将来は?→非接触ICカードに埋め込まれているICチップに着目すると、形状にこだわらない自由な利用方法が考えられます。例えば、携帯電話、時計、指輪、更には体の中等々です。特に体の中と言えば動物(犬、猫)の認証用として日本でも始まっています。更に時代が進むと、確実な生体認証手段の確立とブローバンドの構築により、その人が誰かを認証手段により確認し、通信によりその人のIDを基に決済やアクセス権限等が即時に行われることになります。従って、カードや認証用の物は必要無くなり、本人自身が認証媒体(指紋、虹彩、静脈、音声等)となると考えています。
生体認証は、変らない、忘れない、持運び便利と言う優れた特徴があります。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- フォトライフ
- 源氏物語〔34帖 若菜 50〕
- (2025-11-19 11:30:04)
-
-
-
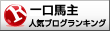
- 一口馬主について
- 所有馬近況更新(25.11.18)クールブ…
- (2025-11-18 20:52:43)
-
-
-

- 何か手作りしてますか?
- ハムスターの革人形を作る その139
- (2025-11-18 20:22:54)
-
© Rakuten Group, Inc.



