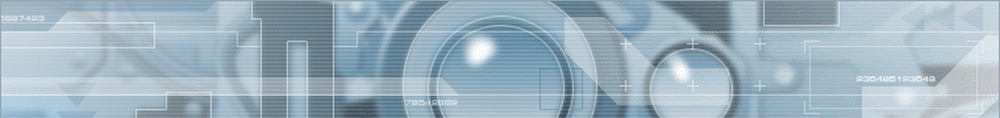前回の続きで今回は実際に試飲したワインについて書いていきます。
ペーターラウアー(Peter Lauer) のワインはアルコールが低め、と前回書きました。
シュペートレーゼ以上の甘口ワイン以外のラインナップはすべて主に三つのカテゴリーFineherb,trocken bis fineherb,trockenにわかれています。中辛と辛口とその中間、といったかんじです。この他に一種類だけ辛口の上としてextra trockenというのもありました。
この分類はアルコール度数で決めているそうです。fineherbが10パーセント前後、TFが12、trockenが13といったかんじでした。13パーセントでも他の国の辛口よりは低く味わいもやさしいです。
ドイツワイン法では規定の残糖以下のものがtrocken、halbtrockenと表記できるのですが(finehelbには規定はなく辛口ではないけれど甘口でもないといったものに使われています)、アルコール度数というのはこの捉え方とは別物です。残糖は全く関係ないのかは聞くのは忘れてしまいましたがたぶん度数だけで表記を決めていると思います。
僕の感想では、この醸造所のこの表記は飲み口ではなくただのアルコール度数の指針でしかないと思いました。この表記ではタイプは想像できないです。ここのワインは、わかりやすくいってしまえば一般的なfineherbという分類の中さまざまなタイプのワインがあるので。
あくまで推測ですが、だからこそ度数による分類にしたのかなと思いました。
通常の等級に値するランクは3つにわかれています。Aylの畑ではなくSaarのいくつかのところのワインを混ぜたグーツワイン(6ユーロ前後)、値段的にもここの主軸のラインナップといえる単一の場所からのもの(8から9ユーロ)、畑の良い立地の場所でさらに古木によるワインに名前がついているもの(12から16ユーロ、ひとつだけ21ユーロ)にわかれていて2009年産だけで13種類ありました。これらすべてが食事にあうタイプです。
試飲はまずはトロッケンの三段階のを飲みながらこのシステムやこの醸造所の基本的なことを説明し、次は少しアルコール低めのものでまたグーツワインから、そしてもう一度と三順このパターンを繰り返し最後に甘口のシュペートレーゼとアウスレーゼを飲みました。

試飲したワイン (明記していないものはすべて2009年産です)
一段階目(グーツワイン)
Fass 16 Trocken
Alt Scheidt Fineferb
二段階目
Fass 25 T
Fass 6 SENIOR TF
Fass 4 F
Fass 3 F
三段階目(アルテレーベン)
Fass 12 Unterstenbersch T
Fass 11 schonfels T
Fass 15 Stirn F
Fass 15 Stirn 2007 F
Fass 9 Kern F
甘口
シュペートレーゼ 2つ星
アウスレーゼ 2つ星 2007
アウスレーゼ 2003
一本ずつ畑の場所や土壌の条件などを丁寧に説明しながらの試飲だったのでいろいろ考えながら試飲することができました。
Ayler Kuppとそうでない畑の違い、Kuppでも場所によって日のあたる時間の長さによる違いや斜面の上と下、あるいは平らになっている部分での違いなど、いろいろな条件のを飲むことができたのはとてもよい経験でした。ひとまとめでAyler Kuppとまとめられていても僕が知っているAylらしいと思える味わいのワインや全く未知の味わいなどととても幅広く、そして畑の特性、個性を引き立てることができるこの醸造所はすばらしいと思ったのでした。
酵母についても語っていて、人口酵母だとどれも似たようなタイプになってしまう、だから畑のポテンシャルを発揮できる天然酵母にしているのだ、と言っていました。
その中で気になったワインを少し挙げます。
二段階目のワインの中でその年の一番良い出来だったもの、醸造所の代表とできるワインにはおじいさんを敬してSENIORとつけているそうでそれが今年はFass6でした。
代表というだけあって、クラシカルだけど非のうちごろのないワインでした。Aylらしい風味とグレープフルーツを感じました。この醸造所を知ってもらうために一本だけ選ぶとすればこのワインが一番適していると思いました。
Unterstenberschは舌で塩味を感じるのですが口の中全体では甘く感じるという面白いものでした。
Schonfelsは100年の古木からの葡萄だそうです。とてもパワフルなのですが酸が少し足りないためか僕にはあまり魅力的には感じませんでした。他の年だと全く違った印象になるかもと思いました。
Stirnは二つの年のを飲んだのですがどちらもにおいが強烈でした。ザールらしくザールにしかないないにおいと風味で僕はこれをザール臭と呼んでいます。09のほうが強烈でそむけたくなるほどでした。熟成したらやわらくなるのでしょうか。
味わいはにおいと正反対でやさしくてやわらかいのが面白いです。07は洋ナシを強く感じました。
どちらも今ではなく5年くらい寝かせた時が一番良いのではと思いました。この場所のは特に長寿なのだと。古木だからというのもあると思います。
僕は09よりは飲み頃が早いであろうと思われる07を購入しました。少なくとも3年は寝かせるつもりです。
Kernはここの他のラインナップとは異なり甘みをけっこう感じます。Ayler Kuppの中でも一番昼と夜の寒暖差が激しい場所だそうで、糖度の高い完熟した葡萄になるそうです。
このワインは残糖が45あるそうで甘みは感じますが、かといって甘口ワインではない、というバランスがとてもすごい思いました。畑の力と醸造の力両方があってこその一品だと思いました。昔からの古典的なドイツワインらしいドイツワインでしかも洗練されているので僕はこれをThe Germany wineと呼んでも良いと思ったほどです。毎年Kernは評価が高いみたいなのですが09はどう評価されるのかが楽しみです。
ただこのワインは他のラインナップと比べると異質なので、このワインがここの代表みたいな捉え方をされるともったいないと思いました。もっと食事にマッチするくらいの中辛こそがここの醸造所の魅力だと僕は思っています。
それに甘みがあるのを苦手とする人がKernを飲んだら他のも飲みたいと興味をひくのに至ることはないと思うので。
甘口では03のアウスレーゼがとてもおいしくて購入しました。今は飲み頃です。
僕がいくつか知っているモーゼルの03の典型的なすばらしいアウスレーゼのように、ボリュームがあるけれど甘ったるくない甘みがとてもよかったです。ミネラルもけっこう感じるからバランスが良いのだと思います。
というようにワインも話もとても興味深くすばらしいひとときとなりました。気がつけば8時から1時間半も試飲していました。でもこれだけ飲んでもまだ10時前ってありえないです。
その後急ぎ目で朝食をとりホテルをチェックアウトしてタクシーでザールブルクの郵便局に行って12本送ったのでした。
アルコールが低めだけれど食事にあうワイン、そういうタイプばかりだけれど似たようなものはなくどれも個性がある、というとても魅力的な醸造所で個人的にも味わいが好きなのでお気に入りの醸造所になりました。最初にきたお父さんからのメールも好意的でフローリアンさんもとてもよい人だったので家族経営の醸造所としても僕はここが大好きです。
また違う年のを飲みに必ず再訪するのは間違いないです。ただ立地が車がないととても大変、というのが辛いです。
ここの醸造所で強く感じたことがあるのですが、それは他のところもある程度書いた後に総括的なところでまた書こうと思います。

前日に撮ったアイラークップです。奥にみえる丘です。とても広い小山なので場所によって条件が異なるのは当たり前だと、話をきくと納得できるのです。
-
ビュルテンブルク シュトットガルト周辺… 2011.09.18
-
ドイツ赤ワインの産地アール地方その2 2011.09.10
-
世界遺産のある街アーヘンと赤ワインの産… 2011.09.05
カテゴリ
カテゴリ未分類
(54)ラーメン
(60)ドイツワイン
(119)東京ドイツワイン協会(ケナー関係含む)
(42)役にたつであろうワインの知識
(17)ドイツワイン 2010年ヨーロッパ旅行編
(29)2010年 ヨーロッパ旅行ドイツワイン以外
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 土地
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 体験
(10)ヨーロッパ旅行 08年12月編
(8)ヨーロッパ旅行 08年1月編
(3)ヨーロッパ旅行 実践編
(11)2012ヨーロッパ旅行 ドイツワイン編
(22)2012ヨーロッパ旅行 (ワイン以外)
(6)日本の土地
(28)ベルギービール
(17)その他酒
(10)音楽
(48)プロレス
(18)日本で買えるおすすめドイツワイン
(7)sakae
(3)2013年ヨーロッパ旅 ワイン以外
(3)2013年9月ヨーロッパ ドイツワイン
(4)2014年9月ヨーロッパ
(2)・2025.10
・2025.09
・2025.07
キーワードサーチ
コメント新着
モーゼルだより mosel2002さん
ドイツワインならメ… 店長@ユースケさん
Loving PURORESU hirose-gawaさん
youi's memo youi1019さん