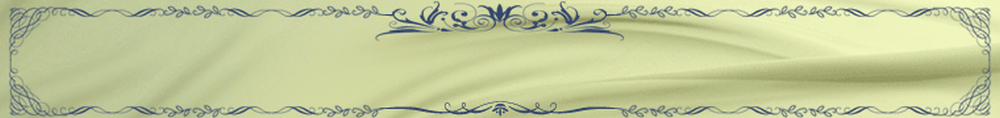夢中な季節
1、 「歌を歌う」
てるてる家族を見ていたら、夏子ちゃんが「ブルーライトヨコハマ」を歌うんだそうで、あぁ、いしだあゆみがモデルなのか、と今更かもしれませんが思ったわけです。僕はあの歌が好きで、いつも母方のおばちゃんと一緒に歌ってたのを思いだしました。
昭和48年頃と言えば、「ブルーライトヨコハマ」をはじめ歌謡曲は、まだ管楽器が中心だったと思います。
管楽器は単音しか出ないので、和音を奏でるためには人数が必要ですが、きらびやかな音、渋い音など、いろいろな表情を持った音を表現できますし、マイク以外は電気を使わないので、昔は歌謡曲やポップスのバンドといえば管楽器が必らずいたわけです。たとえば、初代ウルトラマンの歌を知ってる方は思い出して見てください。ね?ブラスバンドでしょう?
一方、同じ回のてるてる家族の別の場面では、ローリー君が喫茶店で3人組みでフォークソングを歌っていましたが、フォークギターは、「弾き語り」という言葉があるように、なんか、昔の日本人が三味線を弾きながら唄を歌うって言う感じで演奏できるので、手軽といえば手軽な楽器なわけです。
こうして一世を風靡したフォークソングや、エレキギターが前面に出たロックなどの音のありかたが、歌謡曲と融合して行ったと思うんですが、やがて、曲作りには、キーボードがかかせなくなってきました。
1950年代や60年代のロックやポップスのバンドでは、ピアノの他にオルガンとかエレクトーンの音が使われていましたが、やがて70年代、弦、管楽器の音はもちろん、様々な音が出せるようになってくると、広がりのある厚い音を表現できるようになってきたわけです。
ヤマハやローランド、コルグ、といったメーカーが次々にいい物を出してましたが、僕が大学2年生の当時は、比較的手に入りやすいデジタル音源のキ―ボードだったヤマハDX7も、25万円位してました。また、すごく重たかったんです。僕は、ローランドのジュノ106という、6音が同時に出るアナログキーボードを使ってましたが、それも14万円とかだったと思います。
その後、本物のピアノの音やバイオリンの音をデジタル録音した、サンプリングキーボードで、比較的安いのとか…といっても20なん万円してましたけど…色々ないい音のするキーボードが毎年毎年出てきてますね。
それにしても僕が大学生の時に比べて、今のと決定的に違うのは、値段もさることながら、その重さですわ。今のはほんとに軽いですもん。あの頃は、運ぶだけでも一苦労でした・・・・
さて、僕らのサークルでは、5月の春の定期コンサートと10月の秋の定期コンサートがサークルのメインの行事で、大学がある市の市民会館の、200人収容の小ホールを会場としていました。
その時は、大学内外でチケットを売ったり、チラシを配ったり、看板を作ったり、つまり、何から何まで全部自分たちでするわけです。
僕が入った頃のサークルは、他の軽音系サークルと違って全員参加が原則で、サークル内でのオーディションをしないので、どんなに下手でもコンサートに出る事が出来ました。小さなサークルだったからこそ、そういう事が出来たんですが、これは僕が4年の時、サークル員が軽音楽系サークルの中でダントツの最大規模になった時に、オーディション制に変わって行きました。あまりにもバンド数が多くなって、1日ではコンサートが出来なくなったからです。
また、11月には学園祭があり、学校内外のバンドが出てましたが、これは自由参加でしたが、一応オーディションがありました。って、そんなに厳しくなかったですけどね。この他にはサークルの内輪の行事として新入生だけの6月の発表会と、クリスマスの宴会コンサートがありました。
さて、僕らは、新入生バンドの発表会が終わったので、秋の定例コンサートに向けて新しいバンドの編成をする事になったわけです。
もちろん、もうしっかりとメンバーが固まっている所もありますが、新しく組まれるとか、前からあるバンドでも、誰かが入るとか、抜けるとか、そういう事があるわけです。
僕らは、発表会の時にやったメンバー4人に、新入生バンドの発表会の後、途中からサークルに入ってきた短大の1年生2人を入れて組む事になりました。
バンドって言うのは、音楽的に同じような志向の人が集まってするもんなんですが、必ずしも全員の好みが一致していないって事は、プロのバンドでもそうみたいですが、アマチュアバンドでも良くある事です。
僕らの場合、新入生発表会の時に組んだバンドがなかなか良い感じだったんで、それでずっと行こう、と最初は言い合ってたんですが、実際に、秋のコンサートでの曲を選考する時に、若干のズレが出てきたわけです。
なにしろ、発表会で演奏する曲は準備も入れて30分という枠が決まっているので、曲数は4~5曲なわけです。そんな中で、指向の違うもの同士ですから、いろんな意見が出て来るわけです。技量的にも平均してないので、一人がやりたいといっても、別の人が、それは無理だな、って言うのもありますしね。
それで、誰かが我慢すると言うか、そういう状況も出て来るわけです。
で、当時、高校卒業後、2年間社会に出て働いてきて入学してきたという、最年長のドラムのHがリーダーだったんですが、彼の意見で、とりあえず、目先の目標である秋のコンサートでは、途中からサークルに入ってきた短大生2人を入れて、彼女達がしたい曲を俺達でバックアップしようよ、という事になったわけです。来年就職活動を控えている彼女達は、今年一年くらいしかバンド活動が出来ないから、と言うわけでした。
で、ベース担当のSも、リードギター担当のKも、それで行こう、という事になったわけです。・・・僕は、まだまだバンド初体験者ですから、今年一年は勉強のつもりでなんでもしようと思ってましたから、それでOKでした。
・・・って、ほんとはみんな、女の子とバンドが組めるってのが嬉しいって事だったんですけど・・・
ところが、彼女らは、一人はユーミンを、もう一人は八神純子を1曲だけでいいから歌わせて欲しい、そして、ギターもちょっとやってみたいので、好きなチャゲアスの曲を1曲やって欲しい、ということでした。チャゲアスのボーカルは、ドラムのHと、僕がすることになりました。後1曲は、そちらで決めて、って言うもんですから、リードのKがしたがってた高中正義を1曲することにしました。
また、SとHは、その年のポプコンに出るというO先輩の手伝いをすることになり、Kはボンジョビなどをやる先輩のバンドの、僕は浜田省吾をやる先輩のバンドを手伝う事になりました。
ところで、その頃僕はアルバイトをしてました。学費以外は自分で何とかしなければならなかったので、バイトしなけりゃどうにもならんかったわけです。
最初、単発的に入って来る新聞の世論調査とか、駅伝や、国際的なマラソン大会の警備なんかをしていましたが、それではお金が足りず、仕方なく喫茶店のアルバイトをはじめました。僕は決して人に対して明るい態度で接っすることが出来るっていうふうではありませんでしたが、背に腹は代えられんと言う奴で、嫌だと思いながらはじめたんですが、・・・やってみたら、なに、簡単なもんでした。
皿洗いも接客も楽しくって、そのうち厨房にも入るようになり、ピラフとかオムライス、から揚げ定食、とんかつ定食、なんてものも作るようになり、そのうち店長が駆け落ちして逃げてしまうと、オーナーから店長代理になって欲しいと言われ、そこの主みたいになってしまいました。
しかし、安定した収入が得られるし、食事も確保できるとはいえ、週に3日や4日くらいを、3時間4時間したところで給料も知れてるわけです。また、学生をあて込んだ喫茶店でしたから、長期の休みには閉めてましたしね。
それで、1年生の後半から卒業するまで、あいた日とか、長期の休みの時には、深夜の警備や、新幹線の清掃、全自動麻雀卓の修理の手伝い、工場の清掃、プラスチック工場の夜勤、運送会社での荷物の配送、カラオケパブでのカラオケの司会…いろんなことをやりましたが、それらの御蔭で、いろんな社会の面を見ることが出来、それも楽しかったわけです。
何よりも自分自身にとって嬉しかったのは、「俺は、やろうと思えば、ある程度のことは出来る」という自信を持てた事でした。それと、いろんなバイト先の人から、「君がいてくれて良かった」、と言ってもらえた事でした。
高校の時、「お前なんておってもおらんでもどうでもいい。」と言われたことがあった僕にとって、大学時代の僕は、その頃とは打って変わって毎日がとっても嬉しい日々だったわけです。
・・・さて、バンドです。今度は、ピアノを弾きながら、同時にストリングス(バイオリンなどの弦楽器の音)や、ブラス(サックスなどの音)を、キーボードで弾かなければなりませんでした。3台キーボードを置いて、立って弾くわけです。3台っていうのも初めてでしたが、立って弾くって事も、慣れない僕には結構難しかったですね。
そして、歌、です。
チャゲアスはあんまり知りませんでしたので、テープを聞いて練習したんですが、それまで大きな声で歌を歌った事がなかったので、思ってたよりも声が細い事がわかりました。音程も不安定で、思いの他かなりヘタに聞こえたわけです。ちなみに、担当はチャゲのパートでした。「翼」とかなんとか言うタイトルの歌で、声を張り上げて歌う歌でした。音域の広さと、声量の多さが必要だったわけです。
Hとの掛け合いですから、僕がうまくやらなきゃダメなわけで、迷惑をかけるわけにはいきません。それで、ボーカルトレーニングをはじめたわけです。
といっても、本格的に教室に通うなんて出来ませんでしたので、サークルの、歌のうまい先輩や友人に教えてもらったり、本を読んで独習したんですけどね。
下腹部腹筋運動を毎日やったり、浜辺に出ては大きな声を出したり、音程を正確に取るため高校の時の音楽の教科書だったコールユーブンゲンをやったり、ある歌手が、自分はタバコとウイスキーでこういう太い声が出るようになったと書いてるのを見れば、やたらと煙草を吸いまくってウイスキーでうがいをしたり、正確な発音をするために演劇部の友達から「あ、え、い、お、う、」なんてのを習ってやったりしました。
でも、なかなか思うような声は出ません。それでも、いつかは千春さんやチューリップの財津さんみたいに…と思い、取り組んだわけです。
ああ、歌のうまい人はうらやましいな、、、、今でもそう思うんですが、その頃は、もっと切実にそう思いましたね。
で、最後のほうの練習ではHが、おお、けっこういけるんじゃない? なんて言ってくれるくらいにはなったんですが、本番・・・
はじめて大勢の人の前で歌ったので、すごく緊張してしまったわけです。それで、練習のようにはいきませんでした。・・・それでも、歌うことの気持ちの良さ、高揚感はあり、こりゃ歌うのって楽しいわ、と思ったわけです。
お手伝いをさせてもらった先輩のバンドの方も無難にこなし、「良かったよ、今度も頼む」と言われ、「キーボードの断言児」として、その後、常に2つか3つ、時にはそれ以上のバンドを掛け持ちするようになったわけです。全く、幼い頃から中学2年までピアノをやらされてた御蔭でした。ほんとに親に感謝しましたね。その時いやな事が、いつまでも嫌だとは限らないと思いました。
・・・歌の方では、誰も呼んでくれませんでしたけど・・・
そして、チューリップをはじめ、内外のプロのミュージシャンのコンサートに足を運び、アマチュアバンドの発表会にも、行ける限り行きました。楽しむためはもちろん、パフォーマンス、曲の順番の取り方、照明、などなどを参考にするためでしたが、バンドに対する情熱も育てて行ったわけです。・・・千春さんのコンサートには行けませんでした。いつもチケットが取れなかったので・・・それだけは、今でも残念な事の一つになってます。
2、「バンド仲間達」
秋の定例コンサートと学園祭が終わり、翌年の春のコンサートに向けてまたバンドの編成がありましたが、僕らは、同じメンバーのままで行く事になりました。
クリスマスには、サークル内のいろんな人達と隠し芸的なバンドを組んだり、聖歌隊をやったりと音楽遊びをし、冬休み、試験、合宿、春休みと過ごし、2年生に進級。
その頃僕は、バンドやバイトが忙しくなってきたので、思いきって学校の近くの下宿に入る事にしました。
その下宿は、海のすぐそばだったので、毎日浜辺を歩き、海を見ました。ただ海を見てるだけでほっとするんです。
ある日、いつも入り浸ってたSと一緒に浜辺に行った訳です。
すると、険悪な顔をしたにーちゃんがやってきて、「おまえ、何見とるんじゃ!」と言うわけです。
僕は、「海ですけど・・・」と言うと、「俺の顔を見たやろう」と言うわけです。「ガンつけやがったな」と。
「そんなことしてませんが」というと、僕の後ろの方にいたそのにーちゃんの仲間達がぞろぞろ「どーした、どーした」とやってきました。一人、女性もいました。
険悪な顔のにーちゃんと、押し問答をしているうちに、そいつ、Sの原付をけったんです。
僕は怒って、そいつを突き飛ばそうとした所、Sが、まあまあ、と言い、にーちゃんに、どうしろって言うの?と聞くわけです。
するとにーちゃんは、一万円かけて勝負しようや、というわけです。喧嘩をして負けた方が1万円を払うと言う事でした。
「そんなことするかい」と僕が言うと、じゃ、土下座して謝れ、というわけです。
「なに、土下座ぁ?」僕は、相手は5人か、と思い、いざとなったら、と言う気持ちで、「そんなことできんな」と言うと、Sは、「断言児、この人らの言う事を聞いといたほうがいいよ」と言うわけです。
僕も、この人ら、まともに話してどうこういう人達じゃないな、と言う事はわかっていたのですが、それでも土下座は嫌でしたから、だまっていました。
すると、別のにーちゃんが、「お前学生やろう?下宿しとるんやろう?大家さんに話をつけてもらおうか」なんて言うわけです。
「こんなことで呼べるわけねーだろう」と言うと、Sが、いいから呼んできなよ、その間、俺がうまくやっとくから、と小さな声で言うわけです。とにかく、はよ行ってこい、と。
で、僕は、こんなことで、と思いながらも歩いて5分の所にある大家さんのうちに行き、すいません、ちょっと来てもらえないでしょうか、と、お願いし、10分後に戻ってきました。
すると、Sは、もうすっかりにーちゃん達と仲良くなっていて、ああ、もういいよ、って言うわけです。地元出身のSは、自分の知り合いの知り合いがそのにーちゃん達のうちの一人の知り合いである事を聞き出し、それをつてに、わずかの間に全員と仲良くなってしまってました。
険悪な顔したにーちゃんは、まだちょっと不機嫌そうでしたが、他のにーちゃんやねーちゃんは、Sと楽しそうに話してました。そのうちSは、ちょっとけじめとして土下座しといたら、なんて言うわけです。
なんじゃそれ、と思いましたが、Sがにこにこして言うので、仕方なくそうしました。
するとにーちゃん達、おお、悪かったな、けじめさえつけてくれりゃ、もうええぞ、なんて言って去っていきました。
「何がけじめや、ばかやろう。S、お金でも渡したんか?」と言うと、そんなもんあるわけないやろう、とにこにこしてます。土下座なんてさせやがって…と最初は興奮気味でしたが、彼の笑顔を見てると、だんだんと、まあ、いいか、と思えてきました。
Sはそういう感じの人で、いつも何やら鼻歌を歌ってるような感じなんですが、この時に限らず、あるコンテストに行く途中の電車が事故で止まった時でも、僕は、これも運命やな、なんてあきらめかけてたのに、さっと手動で扉をあけて飛び降り、そばに止まっていた軽トラックの叔父さんに事情を説明して会場まで送ってもらったりなど、誰とでも瞬時にして仲良くなるという性格と、突発的な出来事に瞬時にうまく対応するという特技をフルに活用して、その後も何度か僕を助けてくれました。
Sは、ベース担当でしたが、そのくせリズム感が悪く、声もトッポジージョがひしゃげたような声なのでよくありませんでしたが、いつも明るくて、練習の時でも本番の時でも元気はつらつ、あちこち飛び回ったりジャンプしたり、しゃべりも独特の人柄がにじみ出ていたので、とっても受けがよく、つまり、バンドのムードメーカー、花でした。
それに対して僕は、正確な音とリズムを追求して、余裕がないような感じで楽器に向かったり、歌ったりしていて、ともすれば出来の悪さにすぐに落ち込むという感じでしたが、彼は、少々音やリズムをはずしたって音楽を思いっきり楽しむというふうで、その姿は僕はとってもうらやましかったわけです。
彼は彼で、同じような音楽的な趣味を持つ僕が、きまじめに音楽に取り組む姿勢になんとなく感心してたようで、僕らはいつも一緒にいました。
彼の持論の一つに、「フォークやロックの基本って言うのはさ、ストリートで歌うことだよ」というのがあって、ひまな日はあちこちの公園に出向いて二人で歌いました。ある時は、「僕ら、こうやって日本中を旅してるんです」などと言って、ちょっとお金をもらったりもしましたし、花見シーズンにも「知ってる歌しか歌えない半人前の流しで~す」などと言っては、酔っ払い相手に知ってる演歌や歌謡曲を歌っては只で御馳走をいただくというような事もしました・・・今思えば冷や汗もんですが、それはそれで楽しかったですね。
僕らのバンドでリードギターを担当していたKは、高校時代工学部を目指していましたが、落ちてしまい、僕と同じような感じで、一番学費が安いこの大学に入学してきてました。
彼は、ラジオを鳴らし、テレビをかけ、英語のカセットを聞きながら、エレキギターの練習をすると言う奴で、「お前、そんなんして全部わかるんか?」と聞くと、「え?断言児は全部聞こえないの?」なんて言う、超ながら族でした。
そして、彼もほとんど毎日バイトをしてましたが、下宿にいる時は片時もギターを離さないと言う感じで、とにかく1年生のくせにサークルの誰よりも、っていうか、他の音楽系サークルの人と比べて見ても、一番エレキギターが上手でした。
彼の下宿は海水浴場のすぐ目の前にあったので、夏になると僕らは彼の下宿を「海の家」として使ってましたが、そんな時は決まってKが、シーフードスパゲティーとかを作ってくれて、それがまたすごくうまかったんです。
「断言児はさぁ、Sみたいにもっとノってバンドをしたら良いのにな、って思うんだよな、バンドなんだからさぁ、楽しまなくっちゃ」なんていつも言うわけです。「僕はさぁ、高中正義みたいになりたいと思った事もあったけど、ダメだって事、わかってるんだよね。諦めみたいだけどさ、しょうがないよ、凡人なんだから。プロになろうなんて全く考えてないよ。でも学生時代は思いっきりギターで遊ぶつもりなわけよ。でもさ、ほんとに遊ぼうと思ったら、もっともっとうまくならないと遊べないわけ。分かる?断言児?」なんて言うわけです。
そして、ギターの話になると何時間でもじゃべりつづけるという奴でした。
また、やはり僕らのバンドでドラムを担当していたリーダーのHは、働きながら目的の大学に入っただけあって、資格を取るためにかなり勉強してました。僕らは、「亀の甲より年の功」なんていつもからかってましたが、彼は僕らと違って大人で、人格が安定してました。音楽的にはハーモニーのアレンジは彼にかなう人はいないというふうで、作曲もしていて、ドラムのプレイも、どっしりとして安定してました。
「俺もプロになりてぇと思った事はあるけどさ、俺、したい仕事があるんだ。でも、死ぬまでバンドはするつもりだよ。唯一の趣味だからね。」といつも言ってました。そして、「断言児、お前も作曲して見ろよ。どんな曲でもすごい曲にしてやる。」と言うわけです。
その他にも、同級生の中には、ゆーれい屋敷に住んでいた、博多めんたいロックギタリストにして、チェッカーズと何度もコンテストで顔を合わせたというB、音楽一家に育ち、小柄な身体にかかわらず、パワフルなドラムをたたき、サークルの誰よりも音楽理論に秀で、小さな巨人とあだ名のついていたA、幼い頃からピアノやエレクトーンを習い、ヤマハの全国コンテストではいつも最優秀賞候補になってたという、キーボードがめちゃうまい絶対音感の持ち主I子ちゃん、セミプロのバンドで歌を歌ってたというファッションセンス抜群のNちゃん、高校の時ライブハウスで中島みゆきやオリジナルの歌を歌い、レコード会社からスカウトされた事もあるというM香ちゃん、、、、などなど、僕の周りの音楽的な環境は大変充実してました。
先輩の中にも、ライブハウスに出てる人、コンテストに出てる人、シンガーソングライターを目指す人がいて、そのサークルは、僕にとって十分満足できる環境でした。そういう人達に囲まれて、色々な刺激を受けながら、楽しい日々を過ごしていたわけです。
そして、みんなとよく飲みました。下宿でも飲みましたし、天気のいい日は浜辺に出てはサンマを焼いたりしてギターで歌ったりしてました。
そして、そんなとき僕はみんなに、絶対千春さんやチューリップみたいになるんだ、と酔っぱらってわめいていたわけです。
そして2年生の秋頃だったと思いますが、ついに、ポピュラーソングコンテストの一時予選に出ることになったわけです。
3、「ポプコン」
2年生になり、春のコンサートに向けて練習を重ねていました。
同じバンドの短大生2人は、今年は就職活動のため秋までしかバンドが出来ないからということで、春と秋は、彼女達を盛り上げるバックバンドに徹する事になり、尾崎亜美や杏里などとともに、Hが彼女達のイメージに合わせて作ったと言うオリジナルもすることになりました。
僕は引き続き先輩の浜田省吾のコピーバンドを手伝い、それに加えて後輩のバンドでもベースを弾く事になりました。自分でバンドを作るとき、僕がキーボード、ギター、ベースが出来るなら、他のメンバーを集める時に楽だろうと思ったからと、いろいろな楽器に触れておきたかったわけです。
また、バイト先の喫茶店で、歌声コーナーというのを開設する事になったので、サークルの仲間達と順番に5曲くらいずつを、ギターで弾き語りをする事にもなりました。歌うことが楽しかったのと、場数を踏む必要を感じたからでしたが、千春さんの曲とか、小学生や中学生の時に聞いていたフォークソングや、テレビ番組の歌を中心に、フォークソングっぽい僕のオリジナルもちょっとしてみました。
さて、同じサークルに、いつか杉山きよたか&オメガトライブみたいな感じのバンドをやってみたいと思っていた、一つ上の先輩のOさんがいました。彼は1年生の時、かぐや姫っぽい自作の歌を、2つ上の先輩と2人で歌っていましが、その先輩が就職活動のために一緒に出来なくなったので、デュオを解消し、2年生になると自分のやりたかったバンドを作ろうとメンバーを集めた訳です。ポプコンというコンテストに出るためでした。
ポプコンって言うのは、ヤマハが主催するポピュラーソングコンテストの事で、当時は、バンドを組んでいる人達にとっては、プロになるための登竜門の一つでした。
で、1年生だった僕のバンドのベースのSや、ドラムのHも誘われました。Kは、ギターは抜群にうまかったのですが、オリジナルをアレンジする自信がないからと断りました。僕は・・・その時はまだ新入生バンド発表会の直後で、キーボーディストとしては初心者だったので、すぐには使えないという事から誘われませんでした。
しかし、残念ながらOさんのバンドは一次予選を通過する事が出来ず、落選しました。
それでHとSは、来年も挑戦するから付き合ってくれ、とOさんに言われ、2年生になっても、引き続きOさんのバンドを手伝っていたわけです。
で、僕らが2年生になった年、つまりOさんが2回目のポプコンに挑戦する年、Hが、俺達のバンドも今年はポプコンに出ようよ、と言い出しました。
自分の作った歌が、どれほどの評価を受けるか知りたいんだ、と言うことでした。
「H、Oさんのバンドでまたコンテストに出るんやろう?二つも出ていいの?」と聞くと、Hは、「大丈夫。Oさんは、俺がOさんのバンドを適当にするなんて思ってないし、俺のやりたい事を邪魔するみたいなことはしたくないって言ってくれてるんや。」と言うわけです。
それで、Hが短大生2人のために作った歌をコンテストでやる事になり、さらに練習を重ねました。そして、夏前だったか、秋だったかちょっと忘れましたが、いよいよポプコンの第一次予選会の当日となりました。
いつもお世話になってる楽器屋が会場でした。市単位の一次予選に受かれば、地区単位の2次予選、それを通過すれば県単位の3次予選、それを通れば東海とか北陸などと言った地方大会、そして全国大会という段取りだったと思います。・・・記憶が不確かで、違うかもしれませんが・・・
15くらいのグループが出たんですが、中には50過ぎのおじさんが、クラッシックをテープで流して、愛を語る詩を朗読する、なんてのもあって、バラエティーに富んだものでした。
その中で、同じ大学の別の軽音楽サークル出身の先輩達のコミックバンドが、すごく目を引いていました。一言で言うと「よしもと新喜劇」のバンド版といった感じで、これが受かるだろうな、と思っていたら、やっぱり受かってました。
Oさんのバンドは、ベストギター賞というものをもらいましたが、一言で言うと「時代遅れ」ということで、落ちてしまいました。2回目の挑戦もダメだったと言うわけです。
Oさんは、ポプコンじゃダメだ、と言い、もう俺には1年しか残されていないから、別の事を考えると言いました。・・・それには、やがて僕もかかわっていくわけですが・・・
さて、僕らのバンドは、惜しい、と言うことで落選。しかし、ベストアレンジ賞というのをもらいました。
ま、そんなもんだろうと思っていたので、僕は別に落ち込むと言うほどではありませんでした。人の曲だったし、主役じゃなかったからって事もありましたが、それでも曲想をよく練る事と、バンドとしてのパフォーマンスと言う面で、もっと研究しないといけないと思いました。
バンドって、何はともあれ楽曲なわけですが、しかし、仮に楽曲が良かったとしても、正確に音を出すだけじゃダメなんです。きらっと聴衆をひきつけるものが必要なわけですね。ルックスとかファッションも含めて。それも足りなかったわけです。
こうして、僕らの最初のポプコン挑戦は終わり、学園祭の秋のコンサートも終わりました。僕らのバンドは、短大生が抜けるのでバンドをどうするかということになりました。
ドラムのHとベースのSは、Oさんから、もう少し付き合ってくれと頼まれてるからOさんのバンドを続けると言い、ギターのKは、スクエアーや高中正義みたいなフュージョンをやりたいからと、音楽的に気の合う仲間と自分のバンドを組織することになり、1年半続いた僕らのホームバンドは解散する事になりました。
僕は、浜田省吾をコピーする先輩のバンドや、中森明菜をする同級生のバンドを手伝っていたので、ホームバンドがなくなっても、とりあえず何にもする事がないって言うわけではありませんでしたが、Sと飲んでる時に、どうや、俺らのオリジナルやらない?と誘ってみました。
来年は3年生になるし、そろそろ本格的に自分自身の音楽活動をしないと、千春さんやチューリップみたいにはなれないぞ、と言う思いでした。
SはSで、Oさんのバンドは仕事みたいな感じで参加しているんで、遊びの部分がないんだよなァ、なんて言い、それまでも自分でちょこちょこ歌を作っていたこともあって、そりゃええな、オリジナルのバンド、やろやろ、という事になりました。
で、メンバーは?と言う事になったわけです。
ほら、Yは?と僕は言いました。
その年、秋が過ぎてからサークルに入ってきた一学年下のYと言う長淵剛命のフォークギターがうまい奴がいて、そいつは、妙にSと気があい、べったりと言う感じだったので、必然的に僕の下宿にも入り浸るようになってましたが、ビートルズが好きだと言ってたし、音楽的に僕らと合うんじゃないか、と思ったわけです。
Sは、Yならいいな、と言いました。
それでYを誘うと、Yは、ええ?僕を誘ってくれるんですか?それはすっごく嬉しいです、お願いします!と言いOK。
最初は、その3人でアコースティックなロックっぽいオリジナルをやろうと思っていましたが、せっかくSはベースが弾けるし、Yはリードギターが弾けるから、僕がサイドギターをやることにして、ドラムを入れてバンドにしようよ、と言う事になり、一年生の時からドラムを練習しはじめ、今じゃ結構上手になってレディースバンドを組んでいたM子をくどいてバンドを結成しました。
こうして、僕は念願の、オリジナルの歌をするためのバンドを作った訳でした。3年生になったら本格的の自分の音楽活動をやる、と張り切ってました。
4、「レコーディング」
2年生の11月上旬の学園祭のコンサートが終わり、オリジナルバンドをやろうとしていた頃、Oさんからキーボードを弾いて欲しいと頼まれました。
2度も落ちたからもうポプコンはあきらめて別の事を考えようと言ってたOさんは、ポピュラー音楽の専門学校に通っていた友人のつてで、その学校の機材を借りて彼のオリジナルをレコーディングするというのです。
3年生ももう後残りわずかだったOさんは、そのテープを持って、レコード会社に売りこみに行くつもりだったわけです。
そこで、事前に今までのテープを音楽学校の友人に聞かせた所、ベースのリズムが不安定なことと、リードギターが月並みだということ、そして、キーボードの音をもっと厚くしたほうがいいとの指摘を受けました。
レコーディングはその音楽学校の都合で2月にしなければなりませんでしたので、それまでのメンバーではいい録音が出来ないと判断したOさんは、レコーディングのためのメンバーを集めることになったわけです。
そこで、ベースをSから後輩のGに替え、今までリードギターを弾いてたDをサイドギターにして新たにOさんの友達でほかの大学にいたセミプロのギタリストのRさんを入れ、今までキーボードを担当していた人とは別に、もう一人のキーボーディストとして僕を指名したわけです。
「俺の最後のわがままだから」とOさんは言い、Sに、「すまん、許してくれ」と言いました。
Sは、Oさんのオリジナル曲がSの苦手なタイプで、Oさんの要求通りには弾けない事を知っていたので、いいもわるいも、そうしてください、と言い承諾しました。ちょっとさびしそうでしたが、僕とのオリジナルバンドに力を入れられるし、と言うわけです。
こうして僕らは冬休みをはさんで毎日何時間も練習し、年が明けた2月中ごろ、その学校に行き、レコーディングをしたわけです。
レコーディングは、まず機械から流れてくる正確なリズムに合わせてドラムの基本パターンを録音し、次にベース、サイドギター、ピアノ、キーボード、リードギター、おかずが入ったドラム、歌とハモリ、と言う順番で入れて行ったんですが、すごい機材と本格的なレコーディングスタジオに、感激したり緊張したりでした。
Oさんの友達がエンジニアの役で、調整卓の前に座り、いろいろ指示するわけです。
みなヘッドホーンから流れてくる基本リズムを聞きながらそれぞれの楽器を入れて行くわけですが、セミプロのギタリストのRさん以外、慣れてない僕らは何度も録り直しをさせられました。
全てのパートが一日では録音出来なかったので、別の日に残ったパートをもう一度録音し、そうやって全3曲を吹き込みました。
出来あがったテープを聞いてみると、レコードを聞いてるみたいで、これはすごいな、って思えるものでした。
Oさんは、「これを持ってレコード会社をまわって来る」と、しばらく姿を見せませんでした。
僕達も、どこかが拾ってくれるんじゃ…なんて思ってたんですが・・・
やがてOさんが戻ってきて、がっかりしたように「あかんわ」と言いました。
「いろいろ行ったんだけどさ、けちょんけちょんに言われたよ。・・・プロなんて、そうそう成れるもんじゃないって事がよく分かった」と言うわけです。
「音が悪かったんですか?」と聞くと、「いや・・・曲が」と言うわけです。「あの曲じゃ、売れる要素がないって言うわけさ」と。「俺自身にも、スター性って言うかさ、ぱっと見てひきつけられる物があるって訳じゃないって言うし…」
「あのな、H、断言児、自分なりにベストを尽くせば、人が認めてくれるって訳じゃないんや。」とOさんは言い、「もう、プロになるのはあきらめた。俺はもう納得した。お前らも納得するまで頑張れよな。」と言うわけです。
Oさんの気落ちした姿を見ると、今までプロプロと言ってた僕に、急に現実がやって来たような気がしました。
5、「人生について考える」
Oさんのバンドのレコーディングや、僕のオリジナルバンドの構想を練っていた2年生の冬、ある日、サークルの後輩がスキーに行こうと誘ってくれました。
スキーか、やったことないし、一度くらいいいな、と僕は思いましたが、バンドの練習やアルバイトで日程が合わなかったので、すまん、今回は行かれないわ、と断りました。
その後輩は、サークルの同級生、つまり、他の僕の後輩にも声をかけてましたが、みんな都合がつかず、結局サークル以外の彼のクラスの同級生などと一緒にスキーに行きました。
そして、死んでしまいました。
スキーに行く途中、彼の乗っていたバスがダム湖に落ちてしまったのです。
遺体があがったと連絡を受けた僕達は、彼の実家で行われたお葬式に出ました。
その少し前の秋の終わり、僕の祖父が亡くなりましたが、祖父に続いて2度目の、身近な人の死でした。
彼はピアノが僕などとは比較にならないほどすごくうまく、僕が手伝っていた先輩のバンドで、一緒にツインキーボードをする事になっていました。
僕らは悲しみにくれ、帰宅しました。
僕の下宿と同方向にある学生寮に住んでいた、彼と同級生であるサークルの後輩達3人が、「断言児さん、ちょっと寄っていってもいいですか?なんか一人で帰るのも…」と言い、僕の下宿にあがりビールなどをちびちび飲みながら、亡くなった後輩の想い出などを語りました。
しばらくすると、一人が、「あ、あいつが来てる!」と言いました。
僕らは、「え?あいつって、、、、あいつ?」と言い、なんかそういう感じがしてきました。
すると、「あいつが来てる!」といった奴が、急に「俺はお前の分もHするからな!」と叫び出しました。
それが妙にその雰囲気にマッチしていて、そいつに続いて他の2人の後輩達も、「俺もHするぞ!」と叫びました。そして、「ね?断言児さん、いいでしょう?断言児さんもそうですよね?」なんて言うわけです。
僕も、「うん、俺も、あいつの分までHしちゃる・・・」と言い、H、H、と異常に盛り上がりました。
やがてみんなしんみりとしだし、「じゃあ、僕らもう帰ります」と、彼らは帰っていきました。
僕らは、その頃はまだ身近な人の死が実感としてすんなり受け入れられなかったのです。
その1週間ほど後に、新幹線の掃除のバイトを終えて、午前5時ごろ帰宅しようと駅の構内を歩いていると、男性が寝転んでいました。
どうも様子がおかしいので駅の交番に行って警官を呼んでくると、その男性は死んでいると言う事が判明しました。
わずかの間に3度も体験した人の死。
人生ってなんだろう、と思わずにはいられませんでした。・・・しかし、分かりません。その時思ったのは、とにかく、生きてる時にはできるだけ生き生きとしていたい、と言う事だけでした。
僕は、僕のしなけりゃならないと思う事をしていくだけだ、と思ったわけです。
他人にとってはアホらしい夢でも、今それをしたいのならしないでどうする、と思ったわけです。僕だっていつかは死ぬ。死ぬ時、ああ、あの時ああしとけばよかった、なんて思うのはいやだ、と思ったわけです。
春は、もうすぐそこでした
続く・・・
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 万歩計
- こんなに歩いている!
- (2025-01-23 22:18:25)
-
-
-

- ダイエット!健康!美容!
- 働くことは若々しさを保つ秘訣なのか…
- (2025-11-29 22:41:00)
-
-
-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…
- 治らないと諦めていた症状が完治した…
- (2025-05-21 00:28:42)
-
© Rakuten Group, Inc.