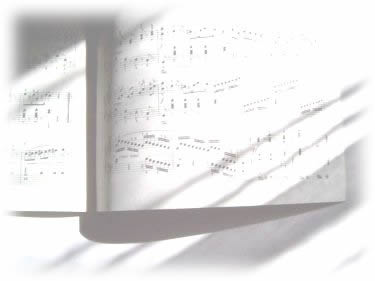ブルックナー交響曲全集
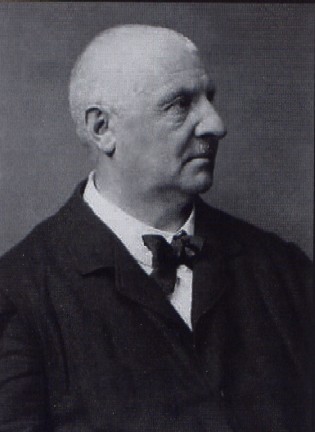
19世紀末のウイーンでブラームスと人気を二分した大作曲家。
現在は演奏会・CDの発売数等でマーラーと共に非常に人気が高い。
リンツ大聖堂のオルガニストであった彼は、寺院でのオルガンの響きを管弦楽で表現しようと試み、 9曲
の壮大な交響曲を書いた。(正確に言うと00番/0番を含めれば11曲、9番は終楽章未完ながら補筆完成版の演奏あり)
優柔不断な性格が災いし、完成した作品に何度も手を加えたため、改訂稿が複数存在している。初心者の聴き始めにお勧めなのは 第4番「ロマンティック」
。親しみやすいメロディ、迫力ある最終楽章は入門に最適。
録音はそれこそ星の数ほどあるが、外国勢に混じって日本の巨匠、 朝比奈隆
の残した録音がいずれも素晴らしい。
初めてブルックナーを聴いたのは結構遅めで、大学に入ってからだった。ベートーヴェンやマーラーと同じく9曲もあって、しかも非常にいかついイメージだったから、なんだかとっつきにくかったのだ。
しかし、最初に聴いた「ロマンティック」のド迫力には、私のチープな再生機械が壊れるのではないかと思ったほど驚いた。その ホルンの咆哮
は、それまでに聴いたどの作曲家の作品ににも ありえない音
だったからだ。
ブルックナーの音楽・旋律は、 ロマン派の中にあって際立って独創的だ
。その和声は他のどの作曲家にも似てはおらず、彼以後も誰も真似は出来ていない。その圧倒的スケールにおいて、 空前絶後の作曲家
だといえるだろう。そんな彼の演奏の中で、私なりに選んだものを呈示したい。鑑賞の参考にしていただければ幸いです。


G.ティントナー指揮/ロイヤル・スコティッシュ管弦楽団 1998年録音
NAXOS 8.554432
1863年作曲。なぜブルックナーの交響曲だけには「0番」やこの「00番」があるのか?この「00番」はブルックナー本人が最初の交響曲作品として自分で認めたものの、まだまだ未熟な点が多いとして習作扱いとした作品なのだ。
この00番はこのティントナー盤での表記がそうなっているのだが、一般には「 交響曲へ短調
」と呼ばれている。この作品、最初からブルックナーを知っていれば「そんな気もする」のだが、40歳にして初めての習作、交響曲としてはお世辞にもイイ出来とは言えない。あくまでブルックナーの全作品を聴いてみたい、という熱心な人向けと言っておこう。(筆者もその一人だが・・・)

E.インバル指揮:フランクフルト放送交響楽団 1992年録音
TELDEC WPCS-6039
前述のティントナー盤がおそらく原典版での演奏であるのに対し、このインバル盤はノヴァーク版を使用しており、特に第一楽章で演奏時間が7分近く異なっている。演奏も彫が深く、録音も優秀。ティントナー盤と聞き比べると、ブルックナーがいかに楽譜をいじくりまわしたかが垣間見えて非常に興味深い。

インバル/ブルックナー:交響曲第0番
E.インバル指揮:フランクフルト放送交響楽団 1990年録音
TELDEC 2292-46330-2
この0番ことニ短調の交響曲は、晩年のブルックナーが青年時代の作品を整理していて見つけ、「 交響曲第0番、全然通用しないもので、単なる試作
」と記した作品と言われている。しかし作曲年については幾説かあり、現在は第1番の後の1869年頃とされている。
総休止など、すでにブルックナーらしさも現れてきてはいるものの、主題が今ひとつはっきりせず、傑作群との差はまだまだ大きいといわざるを得ない。インバルの演奏は颯爽としていて、このちょっとまとまりに欠ける曲を面白く伝えてくれる。

インバル/ブルックナー:交響曲第1番
E.インバル指揮:フランクフルト放送交響楽団 1987年録音
TELDEC 8.43619
1866年作曲。第一楽章の冒頭部にブルックナーの特徴である 異常なほどの反復 がすでに起用されている。さらに大好きなパターンである、第一楽章の主題を終楽章で反復させる方式もすでにおぼろげに姿を現している。ただ、どうにも第一楽章が退屈なのが残念・・・第二楽章のアダージョはすでに確立され、三楽章も反復を多用しつつリズミカル。そして終楽章の劇的疾走感は中々のもの。こういう曲は、インバルがとてつもなく上手なのだ。

E.インバル指揮:フランクフルト放送交響楽団 1988年録音
TELDEC 243 718-2
1872年作曲。この2番は、第一番に比べるとなぜか少し大人しい、ブルックナー「らしさ」がちょっと後退したような作品。割合に聴きやすいけれどもイマイチ主題がはっきりしない為か、現在では殆ど演奏されていないようだ。私もこのインバル盤が初めてだった。
楽天ではヨッフムの名演を

ブルックナー:交響曲第2番/詩篇第150篇

ブルックナー:交響曲第3番@ベーム/VPO
C.ベーム指揮:ウイーン・フィル 1970年録音
DECCA 425 032-2
1873年作曲。第一交響曲作曲の途中でワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」の初演に接したブルックナーは ワーグナー に心酔し、この交響曲を彼に献呈した。印象的なトランペットの序奏に始まり、金管が多用される作風は、ようやくブルックナーの独自性が完全に姿を現した感がある。べームとWPOの堂々とした演奏で聴いてみたい。

ハイティンク/ブルックナー:交響曲第4番
B.ハイティンク指揮:ウイーン・フィル 1985年録音
PHILIPS D32CD-411
1874年作曲。森を隠していた朝靄が、ホルンのゆっくりとした主題提示で振り払われ、輝く朝日の中で自然がその雄大な姿を現わす・・・いわゆる「 原始霧的な響き 」「 ブッルクナー開始 」が完璧なスタイルになって確立された作品。明るく親しみやすい旋律で、彼の作品中最も人気が高い。私も入門はこの曲だった。この曲は、強力な推進力でグイグイ押すよりも、余裕を持って金管を鳴らし、なおかつ上品さを失わない演奏が望ましいと思う。ということで、壮麗で堂々とした演奏を繰り広げるハイティンク盤で聴いてみたい。
このベーム盤も素晴らしいです

ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」

朝比奈 隆指揮:大阪フィルハーモニー交響楽団 2001年録音
EXTON OVCL-00063
1876年作曲。第八番と並ぶ巨大性を誇る「 城塞交響曲
」。
四番が明るい森の交響曲なら、この五番は峻厳な岩山の頂に築かれた城塞を表したような曲なのだ。低弦のピッチカートでゆっくりと導入部が始まり、いきなり金管群が強烈なファンファーレを奏でる。さあ、山に登るかと思うともう総休止。そしてまたファンファーレを繰り返す。なかなか登っていかない。なにせこの登山には90分近くかかるのだ・・・ブルックナーの曲の中でも改訂が多いことで一・二を争い、しかも初版と現在演奏される版とかなりの違いがあるようだ。ブルックナーの全交響曲の中でとっつきにくさでダントツだが、慣れてしまうとなかなか楽しい曲だ。往年の名盤、ケンぺ盤と、がっしりとした演奏がこの曲にもっとも似合う、朝比奈最後の録音を聴いて欲しい。

R.ケンペ指揮:ミュンヘン・フィル 1975年録音
TELDEC 8.43619
2005年に出た名盤です!
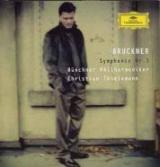
ティーレマン/ブルックナー:交響曲第5番

E.ヨッフム指揮:ドレスデン・シュターツカペレ 1978年録音
EMI 5 73905-2
1881年作曲。第6番は、スケールにおいて5番よりも小さく、美しさにおいては7番に敵わない。しかし、堂々とした金管群の反復の多様と流れるような弦のリズムの融合が小気味良い、なかなかあなどれない作品なのだ。後の7・8・9番の圧倒的な巨大性を現出させるに至る最終過程で生み出された作品、とでもいえようか。 ともすれば中途半端になりがちなこの曲の演奏を、溌剌とした力強さと磨き抜いた美しさで聴かせてくれるヨッフム盤で聴いてみたい。
楽天ではバイエルン響との演奏を。

ブルックナー:交響曲第6番

L.マタチッチ指揮:チェコ・フィル 1967年録音
SUPRAPHON SU3881-2
1883年作曲。ブルックナーの生存中、ライプツィヒで二キシュが初演し大成功を収め、終演後拍手が15分続いたと云われている。第一楽章冒頭の、 チェロとホルンによる雄大な旋律
は一度耳にしたら決して忘れることが出来ない。そしてワーグナーの死を悼む気持ちを綴った第二楽章アダージョの厳粛な美しさは、8番のアダージョ楽章と並んで、ブルックナーの全交響曲中最も美しい音楽だと私は思う。ただ、惜しむらくはあっさりし過ぎの最終楽章。8番と比べてどうしてもラストが軽くなってしまっている。
19種類の演奏を聴いて、中々ベストを絞りきれない。それだけこの曲には色々なアプローチの仕方があることの証明だと思うが、どうだろうか。このマタチッチ盤の雄大無比な演奏は録音の優秀さと相俟って、深く心を打つ素晴らしい演奏となっている。

カラヤン/ブルックナー:交響曲第7番
H.V.カラヤン指揮:ウイーン・フィル 1989年録音
DG POCG-1005
カラヤン最後の録音として名高い一枚。ベルリンフィルと別れ、人工美の極致といえたベルリンフィル・サウンドとも一線を画した帝王の遺言。第一楽章第一主題のふくよかな奏で方は、ベルリンフィルでは有り得なかった音だ。カラヤンのブルックナーで唯一私の好きな演奏。

小澤征爾/ブルックナー:交響曲第7番
小澤征爾指揮:サイトウ・キネン・オーケストラ 2003年録音
PHILIPS UCCP-1093
小澤征爾が満を持して放つ7番。サイトウ・キネンの能力をフル稼働し、艶やかな弦と輝かしい金管のコラボレーションが流麗な「小澤のブルックナー」を紡ぎだした。21世紀のスタンダードと成り得るか、今後のリリースに注目していきたい。

E.E.ステンダー(オルガン) 2001年録音
Ornament Records 11455
最後に変り種のご紹介を一枚。世界初録音、このステンダーというオルガニストの編曲による7番のオルガンのみによる演奏。もともとブルックナー自身もオルガニストであり、彼の交響曲は教会でのオルガンの響を念頭において作曲されたとの通説があるので、大変期待して聴いてみたのだが・・・オルガンのみによる演奏では、旋律が途切れ途切れになってしまい、オケの響のような永続感が無くなってしまうようだ。でも、どうしてもオルガンによるブルックナーを聴いてみたいという方にはピッタリのアイテムだろう。

朝比奈隆/ブルックナー:交響曲第8番
朝比奈 隆指揮:NHK交響楽団 1997年ライブ録音
FONTEC FOCD9184/5
1887年作曲。7番の大成功を受け、勇躍して8番の作曲に取り掛かったものの、完成した曲にはあちこちから改作要求が出された為、作曲に3年を要している。ブルックナーの全交響曲中 最も雄大・劇的
(第九が完成されていたら違ったかもしれないが)で完成度が高く、作曲者も生前に一番高く評価していた曲のようだ。楽器編成も巨大化し、 ホルンが8本に増強
された為非常に分厚い音響を作り出すことに成功している。
あまたある名演の中で私が推すのは、朝比奈隆の97年、N響とのライブ録音。大阪フィルとの録音ももちろん良いが、この録音におけるN響の燃焼度は桁外れだ。両者がっぷり四つに組んだ稀有な名演を是非聴いていただきたい。
カラヤン最後の映像作品。これもいいです。

SMJ カラヤン/カラヤンの遺産(11)ブルックナー:交響曲第8番

K.シューリヒト指揮:ウイーン・フィル 1961年録音
EMI TOCE-59011
1896年作曲。ブルックナー最後にして、未完の大作。第三楽章までが完成しており、第四楽章はかなりのスケッチが残されているため、補筆完成版が作られている。補筆完成版を聴くと、構成上も 8番を遥かに凌ぐ作品
となっていると感じる。 第一楽章からして劇的で、7番などで感じられる人間臭さは消え、人智を超えた宇宙の鳴動のような音が鳴り響く。第三楽章アダージョの祈りは、終楽章の欠落を補って十分な効果を持ち、多くの指揮者たちは未だに補筆完成版を振らない。
この曲のベストを選ぶのは極めて困難だ。今回選んだのは、激しい思い入れや激性の追求から完全に一歩引いた演奏を聴かせるシューリヒト盤。美しい演奏は他にいくらでもあるが、彼の指揮は徹頭徹尾厳しく音楽を磨き上げることまるで修業僧のようであり、この曲の持つ孤高の一面を表現し尽くしている。

ライヴ・イン・ジャパン2000~シューベルト:交響曲第8番「未完成」|ブルックナー:交響曲第9...
G.ヴァント指揮:北ドイツ放送交響楽団 2000年録音
BVCC-34039/40
2000年、ヴァント最後の来日の記録。幸運にも私はこの演奏を生で見ることが
出来た。第三楽章アダージョが終わっても、あまりの素晴らしい演奏に圧倒され、しばらくの間拍手が起きなかった。ヴァントがゆっくりと客席に向き直ってから、満場総立ちの割れんばかりの拍手がいつ終わることもなく続いていた。シューリヒトとは異なる、ヴァント晩年の人間味を感じさせる名演。

ブルックナー:交響曲第9番ニ短調(終楽章付)
アイヒホルン指揮:リンツ・ブルックナー管弦楽団 1992年録音
CAMERATA 30CM-275~6
このフィナーレの演奏に接した時、極めて自然で、補筆されているとはいえ、構成上なんら問題なく感じ、何度も何度も聴き返した事を思い出す。2001年に ヘレヴェッヘ指揮ロイヤル・フランダース・フィルでの日本初演
の際も、非常に深い感動を覚えた。
87年録音のインバル盤で使用している版はあまりにも作りすぎな感じがしたが、その点も修正され、素晴らしい完成度となっている。もちろん完全なブルックナーの音楽ではないにせよ、一聴の価値のある作品に仕上がっていると思うので、是非聴いてみていただきたい。
2005年に発売された「完成版」の詳細な解説付きです

ニコラウス・アーノンクール/ブルックナー:交響曲第9番
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-
-
-

- ラテンキューバン音楽
- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…
- (2025-10-16 12:29:53)
-
-
-

- Jazz
- Jan Garbarek with the Federation o…
- (2025-11-25 22:32:33)
-