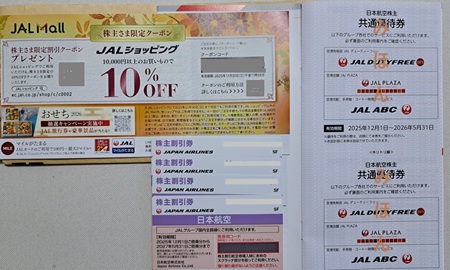全975件 (975件中 1-50件目)
-
引っ越しのお知らせ
引っ越し作業中です↓ http://ameblo.jp/watanabehoumu/
2014.01.25
-
常磐道 広野~富岡間 再開
来月22日にも高速道路<常磐道広野~富岡間>が再開されるという報道があった。約3年ぶりの開通となる。僕も以前には頻繁に利用していたので、きっと景色が懐かしく感じられるんだろうな~ http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/01/post_9005.html避難後、三郷からいわきまでの常磐道を毎週のように往復しているんだけど、この3年間毎回「常磐道広野~富岡間 災害通行止」という電光掲示板を眺めながら運転してきた。その度に「未だ非常時だ」という刷り込みがされていたように思う。その表示が無くなると自分自身も心境が変化するのかな。広野富岡間の高速道路再開を「有料被曝道路」なんて揶揄する人もいるけど、間違いなく復興や廃炉作業の加速化にはつながるはず。そして平成14年度中に常磐道が全面開通するとも報道されている。一気に仙台まで開通すれば復興を後押しするだけでなく、家族が離れて暮らす人達にとっても救いの道になるだろう。家族で一緒にいられる時間が多く作れることになるね。そして今度は常磐線の全面再開と続いていけばいいよね。ちなみにその広野富岡間を車で走った場合の片道の被曝量は0.2マイクルシーベルトで「健康に影響はない」ということだ、が、事故ったり車故障したりはしないようにしないとね。無駄に線量を浴びることになるので。ぶっ飛ばせば被曝量を下げられる!?(^^;) とりあえず来月から富岡には多少行きやすくはなる。過酷な原発事故が起きた福島県の双葉郡のこの地を、超ネガティブなイメージから超ポジティブな地に変えなければならない。事故から不死鳥のように蘇った伝説の地にならなければならない。そして誰もが行きたくなるような夢のある地にならなければならない。それは今いる地元の者が中心となって絵を描き、魂を吹き込まなければならないと僕は思っている。種を蒔かなければならない。そうでしょ? これからですよこれから。くよくよ、ぐずぐずしてらんにぇ
2014.01.23
-
双葉市 誕生
「いずれ町は無くなっぺ」「双葉郡は合併するしかねぇべな」「もう人も戻ってこないんだからやってけねえべ、双葉郡は合併するしかねぇべ」震災原発事故以降多くの地元住民からそういう声を聞いてきた。避難している住民の多くは好むと好まざると、いずれ双葉郡が合併する時が来ることを感じてるんじゃないかな。これまで震災原発事故以降、双葉郡の8カ町村はバラバラに進み、バラバラに政府と対応してきた。そして常々「なんで双葉郡が一つになって交渉しないんだ。」と思っていし、「バラバラにやってたら闘えるものも闘えない」と歯痒く思ってきた。多くの避難者もそう思っていたんじゃないかと思う。うまいようにバラバラに蹂躙させられてしまった感がある。各自治体ごとに別々の餌をぶら下げられて、「他の自治体もやってんだからおたくも我慢してやってください。」「そうしないと不公平になりますから」というようなやり方でうまくやられ続けてきたんじゃないかな。それが過去の公害訴訟でもみられたような「被害者の分断」という日本の政府のやり方なのかもしれない。3年近く翻弄され続け、時すでに遅しかもしれない。しかし・・・双葉郡の合併論、それは事故前に原子力の安全を疑うことのように、双葉郡では議論することさえタブー視されてきたように思う。原発事故後原発の安全神話が崩壊し、原発の安全性が議論されることが当り前になったように、双葉郡の合併論ももはやタブーではなくなった。合併なんてとんでもない、それは最悪だと異を唱える人が今もいるのは事実だ。しかし反対している人に限って、そこに利権があるか、私利私欲に駆られているか、それにすがって生きようとしている人に思える。長い目で公益的な見地に立って考えれば、双葉郡が一つになったほうが知恵も力も結集できる。対外的にも分かりやすく明瞭になり発信しやすくなる。そして何より、もはや双葉郡の各自治体が単独で復興の絵を描くことは事実上不可能になっているし、一つになって双葉郡全体としてのビジョンを描けなければ現実的な双葉郡の復興など無理だ。例えば富岡町だけでの新しい街づくりなんて現実味がない。これからこの地は県外へはもちろん、全世界に対しても、事故の歴史とそこからの復興を発信していかなければならない。そして未来を創っていかなければならない。そして双葉郡は全世界に何百年と注目される屈強な地、伝説の地にならなければならない。そうしていかなければ復興なんていっても中身のないゼネコンの金儲けの復興であり続けるだろうし、いずれ双葉郡は単なる核のゴミ捨て場としか残っていかなくなるだろう。賠償に関する様々な障害、自治体の個々の特殊事情、それらが解決されないまま合併して消滅させられてしまうことへの懸念はある。だけどそれは乗り越えられない障害ではない。やる気があるかないかの問題だと思う。双葉市の誕生。今そういう機運を肌でも感じることができている。機は熟したと思う。できるだけ早く双葉市誕生の産声を聞きたい。
2014.01.20
-
ねずみ取りと殉職した警察官 そしてパパいない
成人の日の休日、家族で上野公園に行ってきた。とても寒くて、さらに娘のジャンバーを忘れた事で夫婦喧嘩もあり、中華を食べて早々と帰ってきた。中華は過門香というお店。僕の大好きなお店で上野か銀座に行ったときは必ずそこで食べるの(*^_^*)おすすめhttp://r.gnavi.co.jp/g223601/さて、上野へ向かう途中突然警察に呼び止められた。いわゆるねずみ取りっていうやつにかかってしまった・・・制限速度が40キロのところ60キロ出てたってことであえなく御用。初めて通る道だったし、60キロくらいで捕まってたら運転なんてできないだろっ!て腹が立ったけどま~仕方ない・・・警察に止められて車外に出て警察車両まで連行されて切符きられたんだけど、チャイルドシートに乗っていた娘が「パパ?」「パパ?」「パパいない~」「パパいない~」と叫んでたらしく、妻は娘に優しく「お父さんはね、警察に連れて行かれちゃったのよ」と説明してくれたらしい。(>_<) 震災の1年くらい前、楢葉町と広野町の境のJヴィレッジ付近の追い越し車線でスピード違反で捕まったことがある。若い警察官と年配の警察官の二人組で、年配の警察官が若い警察官を指導するように違反切符を切られたのを覚えている。その若い警察官の顔はなぜか印象的でずっと覚えていた。そんな彼の顔を震災後新聞紙面で見ることになる。避難誘導中に若い警察官が亡くなったという記事だった。あの時の若い警察官の顔がフラッシュバックした。人生ははかない。今も富岡町の海岸付近に、ぐしゃぐしゃになったパトカーの傍らに彼の慰霊碑が設けられている。遺体は未だ見つかっていないらしい。付近を立ち寄ったときには手を合わせて欲しい。彼の分まで生きよう。彼に捕まったときのことを想い出しながら冥福を祈り、帰宅の途についた。そんな休日だった。
2014.01.17
-
厄年の同級会
正月に中学の同級会があった。厄年に当たる年ということで同級生の有志が幹事になってみんなを集めてくれた。60人近くの同級生が集まった。こういった集まりは10年ぶりだったこともあって一見誰だか分からない同級生もたくさんいた(^^;) 本来は富岡町内でやるはずのこの会はいわき市で催された。それにしてはこんな事情の中たくさん集まった方だと思う。避難している人、家族が避難している人、震災前から関東や関西にいて心配している人、様々の境遇の中集まって楽しいひとときを過ごした。離れていても避難指示区域になっている富岡町や避難している町民を気遣ってくれている人や自分も何かしたいと考えている人も多かった。一方、同じ富岡出身でありながら「避難者の奴らは駄目だ」とか言い出す輩もいて、いろいろ考えさせられる同級会だった。同級生の中には東電社員もいるし、今も福島第一原発で働いている関連会社の人間もいた。第一原発で働く同級生に恐る恐る、どうなの?と詳しく聞くと「いや~正直作業しているけどどうなるのかよく分からない。付け焼き刃的に作業している感じ。批判されるから仕方なくやってる感じ。また爆発することはないと思うけど。」というような返答だった。僕はそれをほろ酔いの中聞いていた。今も暗中模索といったところだろうか。同級生らはそれぞれの立場でそれぞれの人生を歩んでいて、自分の道で頑張っていた。同級会に参加して僕自身やらなければならない事を再認識させられた。そしてその期待も感じた。ますます「俺がやらねば誰がやる」と思わされる正月だった。
2014.01.10
-
避難の終了と賠償金の返還要求
ここ数日、東電が社員に対して賠償の打ち切りや賠償金の返還要求をしているという記事が話題になっている。http://news.yahoo.co.jp/pickup/6102806事故前に賃貸住宅に住んでいた東電社員が、原発事故避難後に賃貸住宅に移り住んだ時点で「避難が終了した」として賠償を打ち切り、あるいは受け取った賠償金の返還を請求されているという。中には千数百万もの賠償金を事実上返還要求されている社員もいるらしい。さらに社員の家族の賠償金の返還も請求されているらしい。狙い撃ちというか、文句の言えないところから賠償金の支出を削っていこうという魂胆なのか。事故直後、東電社員や家族が真っ先に逃げたという話もあるけど、避難して苦境の中生活している状況は皆同じだ。そして避難しながらも決死の覚悟で福島第一原発の廃炉作業に従事している方もたくさんいる。今この瞬間にも第一原発で働いている社員はたくさんいる。その中には私の同級生や知り合いもたくさんいる。加害者である東電とその社員は別人格だし、ましていわんや家族は関係ない。これについて東電は、東電社員にだけ不利益に扱っているものではないとし、同じく一般の避難者へも状況を確認でき次第返還請求していくともとれるコメントをホームページで掲載している。 http://www.tepco.co.jp/news/2014/1233405_5918.html賃貸住宅を借りれば避難が終了なのか?住民票を移せば避難が終了なのか?新しく家を求めれば避難が終了なのか?そうすれば避難生活による精神的苦痛は消えて無くなると考えていること自体、全く避難者の状況や感情を理解してない証拠だろう。ホントあきれる。
2014.01.07
-
新年のご挨拶!?
あけましておめでとうございます。もう正月は終わり。震災原発事故から3度目の正月を終え、今日から仕事始めです。避難者はみんなそうかもしれなきけど、自分自身の心境もものすごく変化し続けています。でも今は前向きだし、常にポジティブです。去年流行った倍返しだって流行語はあまり好きじゃないけど、この際俺の人生何倍もおもしろくしてやれ!何倍も楽しんでやれ!って思う。その気持ちは年々強くなっている。そして今年はその真っ只中に自分がいれたらいいなと思う。 例えば進む道に大きな障害となる岩が立ちはだかり、それを動かすことも、よじ登って乗り越える隙間も無いとしたらどうするだろう。しかも道はそれしか無いとしたら・・・引き返して他の目的地に行き先を変える?その場で岩を眺めながら楽しむことを考える? 俺は進むことを諦めないよ。俺にとってやっぱりその道しか考えられないんだもの。その先に光があることを信じてるんだもの。何としてでも風穴を開けるよ。最初はスプーンでもさ、塀に閉じ込められた囚人が脱獄するようにね(笑)岩の向こうに光があることを信じて疑わない。ポイントはどれだけ信じられるかとその努力をとどれだけ持続できるかだと思う。幸い同じようにポジティブに考えられる仲間や同士が周りにはたくさんいる。みんなで穴空ければいいじゃん。みんないるからさ、この震災原発事故からの逆境を何倍にも好転させてる気がする。風穴は空けられる。そんな力が俺たちにはあるってことを信じて、折れない魂を今年一年貫きたいと思う。宜しく!
2014.01.06
-
ダークツーリズム を考える
「ダークツーリズム」という言葉をご存じだろうか。 インターネットで調べると、災害被災跡地、戦争跡地など、人類の死や悲しみを対象にした観光のこと、とか、人類の悲しみを承継し、亡くなった方をともに悼む旅、という解説がされている。福島第一原発周辺地域の将来を考えたりその方策を探っていくと、この「ダークツーリズム」という言葉に辿り着く。そして実際そうした動きも見え始めていることから最近頻繁に耳にするようになった。みなさんは福島第一原発周辺地域の観光化についてどう思うだろうか?「そんな、観光地にするなんてとんでもない!」「被災者の不幸や痛みでお金儲けするのか!」など、批判的な意見も多いだろう。私も当事者として気持ちはわかる。実際今、誰でも立入ができる旧警戒区域(帰還困難区域を除く)に家を持つ被災者の中には、「我々が家に戻れないのに赤の他人がうろうろ立ち入るのは不愉快だ」とか、「まるで私達の心の中に土足で入られているようだ。」と漏らす人も多い。しかし他方で、我が富岡町のアンケート調査の結果が「帰還したい」と答えた人が12%で前回よりも減っており、今後も減っていく現実を考えたり、世界遺産となった広島の原爆ドームも当初は残すことによって悲惨な記憶を想い出すから撤去して欲しいという反対意見が多かったという話を聞いたり、何より「ダークツーリズム」は災害や大惨事の後に復興する社会を助ける反発力に成り得ると聞いたりすれば、これも1つの手段なのかなと思ったりもする。今の時点で、「ダークツーリズム」が本当に良いのか私個人はなかなか判断できずにいる。ただ今はその是非はともかく、単純に多くの人に現状を知って貰い、政策、賠償、支援に反映して貰わなければと考えているし、それによって風化を防ぐ一助になればとも考えている。私が知っていることは全て発信していこうと思っている、伝えたいと思っている。現地の案内をお願いされれば現状を見て貰いたいと思う。それが「ダークツーリズム」に繋がるかどうかは別にして。
2013.11.12
-
悪化していく現状 今の富岡町
先週の金曜日、平成25年3月25日の富岡町区域再編以来、私自身3度目の富岡入りをしてきました。今更立ち入りレポートをするつもりもなかったけど少し書きます。その状況は3.11のまま、というよりむしろ悪化しています。行く度に悪化していきます。道路は陥没し、崩れそうだった建物は倒壊し、雑草が道を覆い、駅へと続く線路は見えなくなっていました。チェルノブイリのように、被災地の街並みはいずれ森林になってしまうのか・・・そんなことを思い心が痛くなりました。そして改めて何かしなければならないと思いました。今回はテレビ関係者と愛知の教育者と一緒に、同じ富岡町の藤田大さんの案内に同行させてもらって富岡入りしました。彼の案内には同じ富岡町民でも心掴まれるものがあり、案内場所はエグイ場所ばかり。何も知らない人がただ富岡に入るのと、彼に案内されて富岡に入るのとではまるで違った印象になるでしょう。この状況を知ってもらおうと無償で活動している彼に脱帽です。多くの人に真実の姿、生の現状を見てもらうことは非常に大切です。現場に来て多くの人が何かを感じ、全国に発信したり行動を起こしてくれれば風化を防ぐ手助けになるでしょうし、様々な政策が改善されるきっかけになるかもしれません。これまでの2年8ヶ月の政策、賠償、支援は的外れなものばかりだと被災者、被災地では誰もが感じています。それは霞が関の、中央の、机上のものだからに他なりません。お偉いさん方、何度も何度も現場に来てくれよ!って思います。そうすれば状況が日に日に変わっていることも、被災者の気持ちも感じとれるはずです。 うちらも諦めずやり続けなければなりません。うちらしか分かり得ないことがあって、うちらしかできないことがある。だからできることは何でもやっぺよ。https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201607210334956&set=a.1008410903417.1267.1619282385&type=1&relevant_count=1http://www.asahi.com/articles/TKY201310300121.html?fb_action_ids=444987658945920&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22444987658945920%22%3A552240311513301%7D&action_type_map=%7B%22444987658945920%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
2013.11.10
-
高齢者にとっての避難生活
避難から2年8ヶ月、やっぱり高齢者にとっての避難生活はきつい・・・ これまでアパート暮らしなんてしたことがなかった人がほとんど多いだろうし、借家での生活も経験がない人がほとんどではないだろうか? そして自分の故郷を離れることなんてほとんどなかっただろうし、自分の故郷以外での生活なんて想像すらしたことがなかっただろう。定年を迎え、仕事を終え、ある程度の蓄えを持ちながら農作業や釣りや山菜採り、友人と趣味などして悠々自適に暮らしていた。もちろん自分の終の棲家となるはずだった。そんな70代、80代の方々が今、この歳で本気で家を買うことを悩んでいる姿を見るのは忍びない。帰れないことを感じ、自分の生涯かけて貯蓄してきたお金で避難先に家を買うかどうかを真剣に考えているのである。若い世代なら「何度でもやり直せる。」「こうなった以上前を向いていこう。」って思えるだろうし、言えるんだけど、高齢者にとってはそう簡単ではない。これらの余生が不意に壊されてしまったのだ。これが今ままでずっと地道に働いて地元で普通に暮らしていた人達への仕打ちかと思うとまた沸々としたものがこみ上げてくる。
2013.11.07
-
どうなるメロリンキュー
今日の話題ですけど、山本太郎参院議員が10月31日に赤坂御苑で開かれた秋の園遊会で、陛下に直接手紙を渡したということが物議をよんでますね。盛んに報道されていてネットでも批判が大半を占めているように思います。私もどんな罪に当たるのかなぁと気になっていたんですが、なるほど、皇室の政治利用になる可能性があるんですね。いや~この問題はこれからますます加熱しそうですね。私昔から「山本太郎に似てるね」って言われことが多くて(^^;) メロリンキュ-もテレビで見てたし、嫌いじゃかったんですけど、ここ最近の反原発での彼の言動にはいいささか疑問を感じることが多いですね。彼の脱原発本も買って読んでみましたけど同調できない部分も多かったです。それはそうと、この問題も、脱原発の議論もそうですが、肝心の福島第一原発の地元地域や避難住民は蚊帳の外に放って置かれていて、それとは別世界の世間が別次元で騒ぎ立てているような気がしてなりません。除染や賠償や事故処理など現場では問題が山積しているのに、それからは目を背け次から次へと別の話題を世間があーでもない、こーでもないと騒いでいる気がするんですけど、そう思いませんか?
2013.11.01
-
帰還困難区域 帰還できない見通し
政府・与党は、帰還困難区域(年間積算放射線量50ミリシーベルト超)について、事実上「帰還できない」とした上で、移住による生活再建を促す方針を検討しているという報道が出た。(毎日新聞10月30日)これまで2年7ヶ月、帰れる、帰れる、の帰還政策一辺倒で進んできた政府の方針は、ここにきて大きく転換されるようだ。これまで、避難している住民は「帰れるって言ったって実際無理だっぺ!」「帰れないなら帰れないとはっきり言ってくれ!」とずっと嘆き続けてきた。すべての決断が遅すぎる・・・今回の方針転換によって帰還困難区域では、帰還を望む人に対しても強制的に「ごめんなさい。帰還できません。」と印籠を渡すことになるわけだ。さて、それ以外の居住制限区域や避難指示解除準備区域については、これまでどおり「帰れます。」をいつまで貫くのか。このままでは居住制限区域や避難指示解除準備区域の人々の心は宙ぶらりんのままだ。「帰還困難区域じゃないから帰れるって言ったって実際無理だっぺ!」というのが大半の人の心の内だろう。どこかで線引きせざるを得ないんだろうけど。居住制限区域や避難指示解除準備区域でも高線量のホットスポットは点在しているし、度重なる電源喪失や汚染水問題で揺れる危険な状態の福島第一原発の周辺で暮らしていくのは想像しただけでも厳しい。それは例え除染が完了したと言われても同じだろう。居住制限区域や避難指示解除準備区域においては、「帰還する」も「帰還しない」も最大限その個人の選択が尊重されなければならないし、その選択に応じた対策がとられなければならない。
2013.10.31
-
根なし草よ 強く根を張れ!
長い間仕事で家を留守にしていたり、地方を転々とする用事があって久しぶりに家へ帰って来たりすると、「あ~やっぱ家は落ち着くわ~」って思う。たとえそれが借り上げアパートであっても。そしてそんな自分になんか苦笑してしまう。震災から2年7か月以上経って、県外に避難した人は特に、もう戻らないことを決めて新しく家を買う人が徐々に多くなってきたように思う。多くの人がそれぞれの地で、それぞれの新しい生活を始め、まさに地域に根付こうとし始めている。不条理に根なし草になった避難者は必至で根を張り始めてる。それはものすごく前向きで喜ばしいことだと歓迎したい。なぜならその人達と話をすると、皆活き活きと輝きを取り戻して生きていくのを感じることができるから。心の復興を果たしているのを感じることができるから。僕ら遊牧民でもなければ旅人でもない。やっぱり地に足を付けた暮らし、帰る自分の家があるという生活の安定は心の安定にものすごく大きく作用するんだなと改めて最近強く感じている。根なし草よ、強く根を張ろう!あとは良くなるだけ!あとは花を咲かすだけ!僕も頑張る!
2013.10.27
-
まさしく蛇の生殺し状態
うちの義父母も家の購入には頭を悩ませている。そのせいで具合悪くなるほど。年金暮らしで70歳を超えているのに、今更何千万も費やして別に家を買うなんてなかなか決められないですよ。富岡町に帰れば広々とした宅地や田畑、大きな家があるもんだから尚更。家は地震による被害はなく、幸いねずみや動物の被害もなくて、そっくりしているのに。退職して田畑を耕したり、山で山菜や茸をとったり悠々自適に生活していたのに。今は狭いアパートで暮らしていて、家を買うべきかどうか頭を悩ませている。いつまでも狭いアパートで居られない、かといって何の愛着も無い土地に、有り金叩いて家を買う決断もつかない・・・もちろんローンも組めない。富岡町に帰りたい・・・けれど帰っても子供も孫も近寄らない家だ。しかも近くに病院もスーパーも無い所に住まなければならない。そして現実的に帰れるとしても、あと5年、いやそれ以上かかるだろう。流暢に待ってもいられない。どうすればいいのか。そりゃ悩みますよ。まさしく蛇の生殺し状態ですよ。そういう高齢者はたくさん、たくさんいるのです。
2013.10.24
-
仕方なく買う不動産
「先生、何でうちら今更苦労して土地買わなきゃなんねんだべね。帰れば土地なんて売るほど持ってるのに。」このセリフを取引の現場で何度聞いたことか。避難者は買いたくて土地や建物を買ってるわけではない。今の状況から到底帰れる見込みはないし、いつまでも終わりの見えない窮屈な避難生活に耐えられなくて買うのだ。それでも買える余力がある一部の人に限られる。ほとんどの人が買いたくても買えない人で、窮屈な避難生活に喘いでいる。不動産の賠償金を手にした人でさえ、余裕があって買えるわけではなく、精神的苦痛の慰謝料の数年分前倒しで入ったお金等を継ぎ足して購入してるのが現状だ。よく避難者は余りある十分な不動産賠償をもらって、新しい不動産を買い漁ってるみたいに思われているけど、決してそうでは無い。たいていは、他の賠償金をつぎ込んででも早く安定した生活をしたくて不動産を買ってるんですよ。買いたくて買ってるわけじゃない。 だからそれに登録免許税等の税金が課されること自体も腑に落ちないという声を多く聞く。気持ちは分かる。そのとおりだと思う。買いたくて買ってるわけじゃない。仕方なく買う不動産っていったい何なんだろう・・・
2013.10.23
-

決意新たに
今年の司法書士試験にうちの補助者が合格しました。本職としてこれほど嬉しいことはないです。15日に口述試験だったので、試験終わりに仙台で待ち合わせをして食事をしました。いや~めでたい めでたい。がんばった がんばった。私は何もしてないですけど(^^;)気づけば私が合格したのは丁度10年前。もう10年も経ってしまいました。つらく長いトンネルを抜けた、そんな10年前の合格を思い出します。今でも「本当は合格してなかった・・・やばい!勉強しなきゃ!」って夢でうなされて起きることがあります( ;∀;) それだけ必至な青春時代だったんだと思います。私にも恩師がいて、食えない時代にお世話になりました。いろんなことを教わりました。いろんな人の支えがあったから勉強を続けられてきたんだと思っていて、自分が食えるような身分になったら、次の時代の若者の手助けをしなきゃという思いはずっとありました。そしてこれまで受験生を補助者として受け入れてきました。だから今年の補助者の合格は、自分の事のように嬉しいです。そしてやはり福島県の双葉郡の地の合格者は特別です。被災地の被災者の司法というものを担ってもらわなければなりません。地方で泥臭く住民にもまれて、本当の意味での地域に根差した泥だらけの街の法律家になってほしいと思います。そして私も決意を新たに身をただすされた気がしています。震災があって原発が爆発して避難をして、そんなこの地、福島の、司法書士として、その運命を受け入れて、それでも前向きに前向きにやってやろうと思います。私の周りにもたくさんの有志がいます。歴史を作ってやろうと思っています。それが勘違いでも構わない。負けない! 絶対負けない! 何と言われようと諦めませんよ。第二の青春真っ盛りですよ今私は!(^^)!
2013.10.19
-
住民票がないということ
震災、原発事故から2年半が経過しました。仮設住宅や借上住宅を出て、新しく家を買ったり借りたりして、新たな人生を歩み始める人達も徐々に増えてきたような気がします。「いつまでも避難者でいたくない。」そういう声も多く聞くようになってきました。 しかし住民票まで移す人はまだそう多くないようです。新しく居住を構えて新しい生活を始める上で、そこに住民票を移したほうが生活しやすいはずです。「もう避難者扱いされたくない。」「胸を張って新しい地の住民として税金も払っていきたい。」そう思っても住民票を移すことを躊躇う人が多いのは、そこに多くのデメリットと大きな不安があるからだと思います。 震災直後は住民票が無いために、避難先で子供が学校に通えなかったり、親の介護が受けられなかったり、生活のありとあらゆる場面で避難者は不自由な思いをしました。平成23年8月に原発避難者特例法が施行されて、住民票を移さなくても避難先の自治体で教育事務(子供の就学)や医療福祉事務(要介護認定など)に関する手続きが出来るようになり多少改善されました。 しかしそれでも、避難先で住民票無しで生活をしていくには多くの不便が現に存在しています。 住民票が無いために避難先でローンを組めない。キャッシュカードを作れない。事業再開するために店舗を借りようとしたら断られた等々、様々な相談も受けています。 先日宮城県に避難している義母が、駄目だろうと思いつつも、避難先の近くにできる災害復興住宅の説明会を聞きに行ったそうです。住民票が福島県にあるとわかった時点で門前払いされ、「もう自由に立ち入れる区域でしょ?」と冷たくあしらわれたそうです。 今なお避難者が避難先自治体で住民票を移さずに生活していくには、多くの不便があることは私も身をもって感じています。 「それじゃ早く住民票を移せばいいじゃないか。」と事情を知らずに言う人がいるかも知れません。しかし住民票を移してしまえば、まず故郷への選挙権が無くなります。故郷の将来へも、自分の意思の反映ができなくなります。故郷への納税によってそれを後押しすることもできなくなります。その他様々な支援制度や優遇制度が受けらなくなる可能性が出てきます。避難は終了したと解釈されてしまう可能性があるのです。 そして何より、住民票を移してしまえば、東京電力の賠償が打ち切られるのではないか、広報などの情報が入ってこなくなるのでないか、故郷との繋がりが途絶えてしまうのではないかという不安に駆られているのです。 先日ある自治体で実施されたホールボディカウンターによる内部被曝検査においても、避難元に住民票があることが条件とされていて、住民票を県外に移してしまった方は受けられないという扱いでした。このように今後も住民票を県外へ移してしまった方への切り離しの扱いは加速していくでしょう。 住民票を移してしまえば元の自治体のサービスが受けられないのは当然だと言われるかも知れません。住んで無いところに住民票を持ち続けるのは法律違反だと言われるかも知れません。しかし原発避難者は好きで居住を移しているわけではありません。自らの選択による自由意志で移り住んだわけではありません。それを忘れてはいけないと思います。 先日日本学術会議(政策提言や政策意見具申などの権限を有する内閣府の特別機関。)で二重住民登録制度の創設提言がありました。提言では、被災者手帳の交付で支援措置を明確にした上で、長期避難者の二重住民登録を認めるべきだと指摘し、避難先に住民票を移した場合でも避難元自治体の住民の地位も与え、元の自治体の復興計画策定などに関与できる仕組みを整えるべきだと主張されました。 個人的に遅すぎる感はありますが、早急な対応を期待したいと思います。今なお避難者が安心し住民票を移せる環境とは言えません。一刻も早く不安定な生活から脱却できる日が来ることを切に望みます。 ~群馬司法書士新聞提供予定 コラム~
2013.09.25
-
今の心境
俺たちは負けたのか?もう為す術は無いのか?洞穴から出て白旗を掲げ両手を挙げて敵に下る、いつか観た映画の1シーンの中に自分もいるようだ。俺たちは何も間違ったことをしていない。俺たちの主義主張が間違っているとは思わない。今でも。けれど2年半が過ぎ、圧倒的に無力な俺たちはもう敵に下るしかない状況にまで追い詰められている。無力すぎる。敵に下ったって命を取られるわけではない。生活も仕事も自由すぎるくらいの自由が保障されている。これから自分次第でいかようにでもやっていける。そんな人並みの幸せだって否定はしない。けれど俺たちの住み慣れた領土を理不尽に奪われた事実、それだけはずっと突きつけられるだろう。俺は戦おうと仲間を先導した手前、敵に下れば重い罰を受ける。深い傷は生涯消えずつきまとい俺を苦しめるだろう。勝てっこない。戦っても無駄だ。何も出来てないじゃないか。ただ洞窟に立て籠ってるだけじゃないか。もっともだと思う。正直どうやって戦っていいかわからない。みんなそうなんだろう。みんなそんな思いでいるんだろう。必至で生きている生活の傍ら完璧にやるのは俺にも無理だ。結局は自分自身の事であるわけで腹立てても仕方ない。戦車が動かないのは自分の動力が足りないから。でもこのまま籠城を続けても何か突破口を見いだせるかどうかは分からない。両手を挙げて出て行こうか・・・敵の思うつぼだな・・・そんなの最初から分かってるじゃないか・・・一人洞穴を飛び出して突入したって犬死か。一人でもできるけどそれは一人でできること。たかが知れている。2人でやれば3人力になるかも知れない。3人でやれば10人力になるかも知れない。10人でやれば1万力に100人でやれば1億力に。そしたら動かせるかもしれない。可能性は閉ざしたくない気はしている。ちりぢりばらばらに竹槍で来られても一人ずつ潰していくだけ、敵は痛くも痒くもないだろう。お荷物の使えない戦車こんな鉄クズでもいつか動かせる日がくるのかな。それぞれの抵抗で何かの拍子にエンジンがかかり大砲を放つ時が来るのかな。それまで可能性を信じて竹槍1つで抵抗できるかな。反逆の汚名を背負いながら仲間たちの投降を横目に最後の一人になっても闘う覚悟はあるのか?俺は今竹槍を磨ぎながら暗い洞窟で自問自答しているところだ。
2013.09.21
-
子供たちのために何が出来るだろうか?
子供たちに何ができるだろうか? 未来の子供たちにどうやって故郷を残そうか。僕は震災後からそんなことをずっと考えてきた。だけど2年近くが経った頃だろうか、はたして本当に子供たちに故郷を残すことは子供たちのためなんだろうか? 子供たちはそれぞれ別な地で新たな人生を歩み始めている。私達が何が何でも子供たちに故郷のバドンを渡さなきゃと思っていたけど、それは単に大人たちの勝手な思いで、大人たちのエゴなのではないか? 子供たちは望んでないんじゃないか? それって子供たちに負の遺産を押しつけ、負の遺産を背負わすことになるのではないか? そんな風に考えるようになって、ものすごく滅入って、やる気も起きなくなってしまった時期があったんです。自分自身のこれからの人生だけ考えて、このまま恙なくひっそりと暮らしていけばいいか・・・なんて。だけどまた最近いろんな機会でいろんな人と話すことで自分の考えも変化してきました。確かに子供たちはそれぞれ別な地でそれぞれ新たな人生を歩むかもしれない。けれど成長の過程でいろんなことを考えて、震災原発事故のことも自分の幼少期、あるいは自分の親世代のこととして深く考えるようになると思うんです。いずれは。そしてきっと自分のルーツとか宿命としてそれを感じ、手繰り寄せようとするんだと思うんです。その時に、今の私達大人が何をしてきたのか必ず振り返ります。大人たちは子供のたちの適応能力と想像力を信じてあげること。そして今、子供たちに将来の選択肢をたくさん作っていてあげること。子供が自主的に考え、歩んでいく時まで、その材料をたくさん用意してあげること。例えば何十年か後に子供が大人になって、自分であの地に行ってみたい、もっと知りたい、研究したい、それを伝えたい。それができる環境を最低限作っておきたいと思う。それが自分たちの今やるべきことなんじゃんないかなあと最近思うようになってきてます。
2013.08.28
-

海水浴と汚染水
ぐずぐずしてると夏は終わっちまうぜ~(>_<) 今年は海水浴に一回だけ行きました。しかも太平洋じゃなくて新潟の海、日本海。太平洋も一回だけ眺めには行ったけどね、新舞子。新潟のお友達と一緒に間瀬下山海水浴場って所へ行って子供を遊ばせてきました。まさか自分の子供の初海水浴が日本海になるとは思ってもみなかった。思えば俺なんて田舎育ちだからさ、夏は海しかないのよ遊ぶ所は。夏休みは海水浴かハワイアンズ、みたいな(*^_^*) それでも従兄弟なんかと一緒に楽しい夏休みを過ごしてきた。いわきの海もたくさん行ったけど、広野の岩沢海岸はよく行ったね。広野火力発電所の下で福島第二原発を眺めながらの海水浴。何の疑問も感じなかった。まっ黒に日焼けして楽しかった。高校時代は双葉の郡山海水浴場にもよく行った。福島第一原発を眺めながらの海水浴。この時も何にも疑問を感じなかった。楽しい思い出しかない。今じゃ原発事故の影響で汚染水垂れ流し状態の海では泳ぐ気にならないけど。それでも新潟の海で子供を遊ばせながら、子供を海で遊ばせるって大事だな~ってつくずく思った。わくわくドキドキ、いろんなものを見て、触れで、いい経験になるし、子供が海に教わることは多いと思う。いつか太平洋で遊ばせたいけど、いつになるのやら。それでも来年もまたどこかの海へは行こうと思う。
2013.08.20
-
原発事故賠償と時効
いんふぉ9月号掲載の記事をそのままアップします~ 福島第一原発事故に伴う東京電力(株)への損害賠償手続きは、多くの方がその対象者となっており、現在もなお手続きは続いています。時が経つにつれ、その請求手続きは多岐に亘り、より複雑になってきています。そして請求内容は被害者ごとに異なるため、更に手続きが分かりにくい状況になっています。震災から2年半近く経ち、この賠償問題に関連して「時効」という言葉をテレビや新聞で頻繁に見聞きするようになりました。私も多くの方々から相談を受けるようになり、その関心の高さを実感しています。今回その「時効」について取り上げ、分かりやすく解説したいと思います。Q 今回の原発事故の賠償請求権は、いつ時効消滅してしまうのでしょうか? このまま何もしないでいると請求できなくなってしまうのでしょうか? A 今回の原発事故の賠償請求権について、原則どおり民法の規定が適用されるとすれば、損害及び加害者を知ったときから3年の消滅時効にかかってしまいます。平成23年3月11日に発生した損害であれば、平成26年3月11日に権利が消滅してしまうことになります。それを阻止するためには、原則裁判所への訴えなど強力な手続きが必要になります。Q 平成25年6月に施行された時効中断特例法について教えてください。この法律が出来たことで賠償請求権が時効にかかって消滅することがなくなったのですか?A この特例法では、原子力損害賠償紛争解決センターを利用して和解の仲介申立手続きをした被害者のみをその対象として、1,原子力損害賠償紛争解決センターへの申立をして、手続きが打ち切りとなった人が2,手続き打ち切り後1ヶ月以内に3,請求の全部について訴訟を提起することがその適用の要件となっています。ですから、全ての被害者の損害賠償請求権を時効による消滅から救済する法律にはなっていません。Q それではこの時効問題について、加害者である東京電力(株)はどのように考えているのでしょうか。原子力損害賠償紛争解決センターへの申立をして、手続きが打ち切りとなった人が2,手続き打ち切り後1ヶ月以内に3,請求の全部について訴訟を提起することがその適用の要件となっています。ですから、全ての被害者の損害賠償請求権を時効による消滅から救済する法律にはなっていません。Q それではこの時効問題について、加害者である東京電力(株)はどのように考えているのでしょうか。A 東京電力(株)では、東京電力(株)自身が請求書やダイレクトメールを送付した時に時効が中断するという独自の考えを示しています。また、柔軟な対応をするとして、具体的に被害者と協議している期間中は時効期間は事実上停止しているものとして扱うことや、消滅時効完成後に賠償請求をした場合にも、誠実に協議する方針だと説明しています。しかし被害者にとって、東京電力(株)がいつ消滅時効を主張してくるかもわからない不安定な立場のまま賠償の話し合いをしなければならないことに変わりがありません。これについては、新たな法的救済措置の創設を含め、その動向を注意深く見続ける必要があります。また今後被害者自らが専門家の協力を得ながら、時効消滅にかからないための策を検討していかなければならないでしょう。
2013.08.19
-
民の力を繋げよう
でもさ、被災地域では復興に向けて何ができるか、何をすべきか、知恵と力を結集しなきゃならないのに、なんでこんなに私利私欲しか考えてない連中ばっかりなのかね~ 利権と私欲ばっかり。あっちこっちで足の引っ張り合いばかりだし、うんざりする。こういう時だからこそ、権力のある者、上に立つものは、民に、平民に「俺に協力してくれ!」「頼むから俺について来てくれ!」「俺と一緒に変えてくれ!」って頭下げて、手を伸ばすべきだろ? 選挙の時ばっかで票欲しいときばっか、そんな風に装って見えて滑稽。この2年4か月それを見えないとこで民に歩み寄って、民に這いずり回って地面に頭こすりつけてでもお願いして回った権力者はいたか? 一人もいないとは言わないけど。俺だったらそうするけど。俺みたいな平民はそういう志ある権力ある者に心動かされたて見たいと常々思ってんだよ。心動かしてくれよ!手を差し出すから強く握り返して引っ張ってくれよ。 地震がグラッってきて、原発がボンッってなって、目が覚めた? 日本の歴史上最悪の事故が起こって変わろうとしたんじゃないのか? 結局何も変わってないじゃん。一時騒いでみて後は忘れんのか? 参院選が終わる来週で振り子は完全に戻る? 振れたけど戻っていくんだな。なかったことにされていくのか。 ただ幸いに思うのは、民の中に、行動力と発想力があって、人望もあって、私利私欲を顧みずに被災地被災者を思う有志が少なからずいるっていう事。頭下げて手を差し伸べて一緒にやっていこうという有志がいるって事。そういう人たちが繋がっていくことでしか打破できないんじゃないかな。俺はそういう人達に心動かされる。もっと揺さぶってくれ!やろうぜ!
2013.07.21
-
休日の朝に思う
事務所や相談会で相談を受けるとたまに相談者に泣かれることがある。今に始まったことじゃないけど、震災後原発事故後は特に多くなったような気がする。避難中のことでの相談だったりすると自分の事とオーバーラップされて熱くなる。そして脳天をぶっ叩かれたような気になる。避難中でまだまだ憤って、悩んで、抱え込んで、苦しんでいる人がたくさんいることを思い知らされる。俺がただ漫然と仕事をしててどうする。しょぼくれてメソメソしててどうする。俺にはやらなければならないことがまだまだたくさんあって、まだまだできることがたくさんある。そう思いを新たにする。 最近娘がパパパパ~って抱きついて来たりするようになって、デレデレで「もう仕事なんて行きたくな~い」って休日明けには思うんだけど、飴と鞭じゃないけど、自分に鞭打ってまだまだ諦めないで被災者のために自分自身のためにやれることをやろうと思う。
2013.07.14
-
七夕
今日は七夕。願い事はたくさんありますね。この日は祖母の命日。4年前の今朝見送りました。享年94歳。大往生だけど、俺おばあちゃんっ子だったからもっともっと長生きして欲しかったな。4年経った今日もまた亡くなった朝のことを思い出しているんだけど、4年前とは私達は環境が一変していて、その思い出の家にも住んでいないし、両親とも離れて暮らしているし、4年前に逝ってしまってて良かったと思う。あの病床にいた状況で避難を強いたり、避難生活をさせられてたりしていたら、きっとすぐに避難先で亡くなっていたと思うから。そう思うと長生きしなくて良かったなと思ってしまう。そう思う自分への嫌悪感が湧くと同時に、長生きしなくて良かったと心底思わせるこの国って何なんだよ!とまた腹立たしくなってしまう。そうやって避難させられて亡くなって高齢者はどれほど多いことか。無念だろう。まだまだ長生きできた命がたくさんあったんだもの。原発事故で亡くなった人はいないなんて口が裂けても言ってほしくない。改めて、何度でも言うよ。 来週は久しぶりに研修講師のお役目が入っています。林先生みたいにできればいいのにな(笑) 書かなければならない原稿もあるし、まだまだ頑張ります。
2013.07.07
-
飯舘村長泥地区の住民
紛争解決センターに申し立てた飯舘村の住民に対する東電の意見が明らかにされました。当時飯舘村には風向きの影響で大量の放射性物質が飛散したわけだけど、村の人々は安全だ安全だと言われてしばらく留まったんだよね。結局遅れて避難する羽目になったわけだけど、その放射線被曝への恐怖や不安は計り知れないものがあったと思う。けれど東電の意見は「低線量被ばくと健康影響に関する科学的知見と整合せず、既に公表しているとおり月額10万円の慰謝料をお支払いすることとなることも踏まえれば、かかる金額を超えて慰謝料を支払うべき具体的な権利侵害があったと認めることは困難である上、本事案にとどまらない影響があり得ることから、かかる考え方を本和解手続きにおいて受け入れることは困難」というもの。要するに低線量被ばくは影響ないし、それを認めたらみんな認めなきゃならないから認めませんということ。全国各地にホットスポットという所は点在しているし、これ以上賠償対象者を増やしたくないし増額事由にしたくない、というのが東電の本音だろう。時効の問題もそうだけどなるべく被害対象者を狭めて、なるべく被害が小さかったことにして、賠償金を抑えていこうという東電の意図を強く感じます。
2013.06.28
-
たまにはこんなブログも
なんか最近夜が無性に寂しいな。仕事に疲れて夜になると何をしていいかよくわからなくなる。酒もさ、辞めてやろうか思うくらい、別に飲みたいと思わないし。子供と遊びたいんだけどな。結局今夜もビールと読書。20代の頃を思い出す。司法書士の受験勉強をして夜疲れてビールと読書。いろんな本を毎日読んでた。孤独すぎるぐらい孤独でね。ホントに。友達いなかったもん。もてなくて女もいないしね。ずっと一人で一日中机に向かってんの。後は自転車で近所を彷徨うくらいの生活。なにくそ、なにくそって思いながら悶々としてがむしゃらだった僕の20代前半。それが下積時代で、今ではその時代が肥しになっていると思っている。最近またあの頃の感じに似て来てる。仕事に疲れて夜ビールと読書。なにくそ、なにくそ思いながら過ごす毎日。神様がまだまだ修行しろって言ってるんだろうね。うん、ブログ書くと前向きになれる。俺も絶対負けないから、頑張るからさ、そこのあんたも負けんなよ。おやすみね。
2013.06.26
-

22日原子力損害賠償紛争審査会 in福島
22日福島ビューホテルで開催された原子力損害賠償紛争審査会を傍聴してきました。今回が32回目で、福島県内で行われるのは2回目、私は県の司法書士会枠で初傍聴です。どうせ県内でやるなら、富岡町の学びの森でやればいいのに。楢葉、大熊、双葉、浪江、小高の役場か文化センターあたりでいいよ。そうしないと緊張感出ない。最低でもJビレッジ辺りに泊まってやってもらわないと思う。 それはともかく、今回は財物賠償が始まっている中その基準が低すぎるという事で、原賠審の委員が先日現地視察したんだけど、それを踏まえて、今回各自治体の長に現状と意見も聞いておこうという趣旨で会議が行われました。だから会の形式は各自治体の長が代わる代わる現状を陳情、要望するという事をやっていて、私達はただそれを一日中見ているといった格好でした。発言するメンツはやはり知る人ばかり。個人的にも双葉郡の方々は何らかの登記で関わったことのある人ばかりでしたが、それでも眠かった・・・ 何故でしょう?ホテルの会議だからかな。 共感できる所がほとんどでしたが、その自治体のトップの発言によって、その自治体の在り方とか、賠償に対する取り組みが透けて見えるもんですね。質というか。 どの自治体もそれぞれ状況が違うし立場が違うんです。福島第一原発からどのくらいの距離にあるのか、線量はどうなのか、区域指定はどうだったか、どう再編されたのか、財物賠償の対象内なのか外なのか、帰還に向けて動いているのか、手つかずのままなのか、除染を進んでいるのかないのか、住民の意向はどうなのか、住民の人数は・・・ 各自治体によって、そして同じ町内でも、特に相双地区はズタズタに分断されていて、全く状況が違ってくる。 例えば財物賠償の対象外とされて、僅かな修繕清掃費用の賠償しか受け取っていない、帰還宣言はしたものの、ほとんど住民が戻っていない広野や川内のような地域にとっては、安定した生活ができるような帰還の支援策が基本的には必要だし、財物賠償の対象区域となっている町村と同じようなダメージを受けているわけなので、同じような賠償を求めていくことがその主な主張となる。他方例えば大熊のようなほぼ帰還困難区域にあるような町は、どちらかというと新しい土地での生活再建ができる支援策が基本的に求められ、賠償の長期継続、早期の全損賠償を求めていくことになる。 そして自治体間はもちろん同じ自治体の同じ区域の住民間でさえ、家族構成によって将来の方向性によって考え方は異なってくる。同じ町内でも5人家族と2人家族ではまるで必要とされている支援策も賠償の在り方も違ってくるんです。その家族の方針によっても違ってくるように、それは家族ごとに千差万別といっていいい。何十万という家族の何十万通りの思いがある。 時が経つにつれてますますその違いは広がっているのを感じました。これからどれだけ各家族の実情に則した支援と賠償ができるかが原発被災地の復興のカギとなるんだろうと思う。
2013.06.24
-
ダウンしてしまいました。
最近いろんな事があってへこみ気味です。先月末に高熱が出て一週間下がらずダウンしてしまいました。病気で仕事を一週間も休むのは、10年の短い司法書士人生で初めての経験でした。病院へも通いました。肝臓が炎症を起こしているとかで、よく原因もわかりません。ずっと寝込んで食欲もなかったのでネガティブにもなりました。おかげで3キロ減りました(今はリバウンドしてますが)震災原発事故から2年3ヶ月、やっぱり埼玉といわきの二重生活は限界かな~とか、いわきで仕事続けるのも難しいのかな~とか、このまま熱が下がらず死んだら災害関連死になるのかな~とかね。そして、このまま死んだら自分の家族の賠償もできなくなるだろうし、他の地元の人のためにも俺がやらなきゃならないことはまだまだたくさんあるし、今死ねない、と改めて思いました。自分でも分からない疲れが溜まってんだよ~っていろんな人に言われたけど。そうかもしれない。でも、みんなそうですよ。きっとなんか晴れないんだよね、心がさ。でも死ぬまで諦めるわけにはいかないでしょ、いろんな事を。ダウンして多くの人にご心配とご迷惑をおかけしました。熱も数値も下がったし、今はシャキーン!ってなってるから大丈夫です(^^)/ これからますます愚かなほどハングリーに生きたいと思っています。そして私を含め皆さん、長丁場になります。十分な心の休息を。私もまた温泉でも行きたいな。
2013.06.18
-
原発 立地地域の苦悩
これまでいろんな震災・原発事故関連本を読んできて、最近思うことがある。震災・原発事故によって双葉郡があんな事になってしまって、かっこつけて言えば、「俺たちこれから未来の子供達が幸せになるために何ができるだろうか」なんて考えたり、「俺たち歴史を作るんだよ」なんて実際思うわけ。だけど、双葉郡に原発を誘致した当時の地元の人達も「俺たちこれから未来の子供達が幸せになるために何ができるだろうか」って考えて、これで双葉郡が豊になる、新しい歴史が始まるって思って原発を置いたんだよな。そりゃあ「無知と貧困につけ込まれた」とか「中央の発展のために地方が犠牲になった」とか今となってはいろんな言い方はできるかもしれないけど、当時の地元の人達は、決して自分たちの私利私欲のために、後先考えずに誘致したわけではないだろうってこと。もちろん、まさか50年後こんなことになるなんて夢にも思わなかっただろうしね。そこには善意しかなくて、なんとかこの地が発展すればいいと思っていたんだよね、それを思うと余計に切なくなるよ。
2013.06.13
-
いつまで「避難」?
「避難」ってやっぱり概念として一時的なものでしょ。「緊急避難」的に一般的に認識されて当然だと思う。 私なんかも避難当初は一時的なものだと思って避難したんですよね。みんなそうだと思うけど。明日には帰れるだろうと思って避難した。けれどふたを開けたら2年3ヶ月。これからどれだけ続くかわからない。ほとんどの人はまさかこんなことになるなんて思っていなかった。原発が危ないから避難したんだけど、その危うさは今も解消されていない。一時的のつもりで避難したけれど、その避難の原因が除去されていないんだからいつまでも避難のままなんだよね。世間的には風化が進み、原発事故は過去のものになりつつあるけど、私達はあの時避難したままその延長線上にまだいる。毎月10万円の精神的損害を始めとする賠償の支払いで生活を維持し、仮設と借り上げ住宅の期間が場当たり的に延長されて、なんとか生活をつないでいる状態。根本的に賠償問題が解決したわけでもなければ、生活再建の見通しが立ったわけでもない。その場しのぎで、付け焼刃場的な支援で避難者の「避難」が生殺し的に継続されている。身動きが取れないでいる。世間的にはとっくに原発は収束して警戒区域が解除されて、住民は帰還できていると思われているし、賠償だって十分支払われていると多くの人が思っている。私達は避難した日のことを昨日の事のように覚えているし、今もその延長線上にいる。「避難」を終わりにしたいと思っている人が多くいる一方、抜け出せない人がたくさんいる。全部取り上げられて1から新転地で始めるのは容易ではない。しかし周りは「もうそろそろ自立したら」「いつまで避難してるの」という風潮になっていく。世間とのギャップはますます広がるばかりだ。「避難」ではなく「長期にわたる土地利用権の強制収用」がなされたのだという学者の方がいたが、まさしく私達は「強制退去」させられたのだ。しかし世間の認識とのギャップとは裏腹に、国や東電の対応はといえば、従来型の「避難」に対する、つぎはぎ的発想でしか動いていない。
2013.06.01
-
東電賠償の今
賠償については当初から、東電という加害者側がその賠償基準を決めて、その請求内容の査定までずっとしてきてるわけじゃない? 被害者団体や各所から様々な批判を受けて、東電側は請求書を何度か改訂し軌道修正させられたとはいえ、それはごくごくごくごく一部であって、大部分は加害者である東電の思惑どおりに今も事が進められてきている。そしてこの東電の大きな波に被害者は呑み込まれるように賠償手続きに乗せられてきている。財物の賠償に至っては、紛争審を排除して、経産省の傘の下でやりたい放題という感じがさらに強くなっている。 月日が経つごとに賠償請求項目の種類も増え、回数も増えていくと、賠償手続きは客観的に見て多岐に亘っていてとても複雑にみえる。東電の請求書の種類自体ももう何百種類にもなっていると思う。細かすぎてとても当の本人じゃないとついていけなくなっている(当の本人でもついていけなくて加害者に丸投げ状態の被害者も多い)。だから被害者団体の牽制の目も細部まで行き届かせることが難しくなってきていて、東電はその姑息さを増すばかりなのだ。間口を狭め、あれは駄目、これも駄目、「基準が変わりました。」「方針が変わりました。」といって以前当然認めていたものまで間口を閉じてきている。大企業と一被害者なんてその力の差は歴然。グーの根も出ない被害者は従うしかない。反論しても東電は「国の借金が・・・」「当社も財政が・・・」とか一時のサラ金業者のような言い訳をしてきて、今じゃそれが電話対応の枕詞になっている。「今応じておかないと東電だっていつまで持つかわからないよ。早く合意した方が無難だよ。」というニュアンスで圧力をかけてくる。しまいには「うちだって被害者ですから~」と言わんばかりの開き直りまでしてくる。電話する度腹が立って仕方ない。私みたいな鼠がいくら化け猫に噛みついても化け猫はビクともしないのは百も承知だけど。噛みつかない事には始まらんので今後も噛みついていきます。
2013.05.31
-
時効 特別法案成立 どうしてそう~なるのかなっ!
「時効過ぎても東電に賠償請求可能 特例法案成立」って新聞に載ってたけど・・・頭痛いわ~なんでこんな法案になるんだか理解できない。一般世間的にはこれでめでたし!めでたし!なのかな~? 要するに、紛争解決センターに申立てをしている人が、申立て中に時効期間が過ぎても、交渉打ち切り後の1ヶ月以内なら訴訟提起できるっていう扱いにしただけでしょ!? これで多くの被害者が救済されると思ってのかな? このままでは、ほとんどの被害者の権利は時効消滅してしまう。ほとんどの人が紛争解決センターに申立てをしているわけじゃないんだから。逆に東電に「あなたは紛争解決センターに申立てをしていませんので、請求権は時効消滅しています。したがって賠償は支払えません。」って言い易くしたんじゃん!?
2013.05.31
-
区域再編後 初めての立ち入り 2
いわきから車で北上して、広野、楢葉、富岡へと向かった。広野に入ると辺りはなんだか懐かしい景色が広がっていて、学生の頃夏休みに久しぶりに田舎に帰ってきたような、そんな感覚に襲われた。 北上するにつれ次第に手持ちの線量計がうるさく鳴り、車内の音楽が耳障りになってステレオを消した。そしてエアコンをオフにしてマスクを掛けた。見る限り住人は誰もいなかった。走行している6号国道は常時車が行き交うため、原発事故前と何も変わってないじゃん、と思えた。しかし楢葉に入ると、国道脇の田畑や河川に大量の黒い袋が至る所山積みになっていて、異様な光景があちらこちら広がっていた。除染で出た放射性物質を含んだ土が黒い袋に包まれて集積されているのだろう。最終的な処分場も決まらず、いつまでこのまま放置しておくのか・・・テレビでも観たやつだ、そんなことを思いながら更に北上を続けた。楢葉と富岡の間にある私の事務所の看板が悲しい顔で出迎えてくれた。「まだ、あったんだ・・・久しぶり、ごめんね。」そんな独り言を心の中で呟いた。富岡に入り、国道から左折すると、その見慣れた街並みは明らかに国道を走っている時と雰囲気が違った。静まりかえっていた。その見慣れた街並みは確かに死の街と化していた。誰もいない、景色は変わらない、でも誰もいない・・・よく見ると震災後2年前に見た崩れかけの建物は倒壊し、道路の陥没もひどくなり、雑草が我が物顔で生い茂っている。久しぶりに見ると悲しい、とにかく、ただ悲しかった。事務所に着くと雑草は伸び放題、植木も荒れ放題になっていたが、外観はそれほど変わっていないように見えた。中に入ると、まさに3・11のまま。時が止まったまま。書類は散乱し、そこらじゅうに物が転がっている。よく見ると犬か猫か鼠か、はたまた狸か、よくわからないものの糞がいたるところに散乱している。地震で剥がれていた壁や建物の損傷部分は、2年前に立ち入った時より更に傷んでいた。やはり人が使っていないと建物はだんだん駄目になるんだね、そんなことを思った。特に持ち出す物もなく、数点のファイルを手に建物を出た。最後に事務所の周りを一周し、屋上に通じる梯子をよじ登り、街を見渡した。誰もいない街並み。動いているのは、遠くに見える川の水と顔をたたく風、そして頭上の白い雲だけだった。青空が広がる最高の天気が更に虚しさを増幅させた。つづく
2013.05.12
-
区域再編後 初めての立ち入り
先週、自身1年半ぶりに富岡町に立ち入りしてきた。私の自宅と事務所は平成25年3月25日付けの富岡町区域再編で、居住制限区域と避難指示解除準備区域にそれぞれ指定され、一応午前9時から午後3時まで立入りが自由となった。あれから多くの知人友人から富岡に行ってきたという報告を受けていたが、いざ自分が行くとなるとなぜか緊張(^_^メ) 自分の家に帰るだけなのだが。富岡は除染が完了したわけでもなく2年前と変わりはない。多少空間線量が低くなったと言われても、安全である保障はどこにもなく、自由に立ち入れるようにしていること自体おかしいいと私は思っている。震災前の基準であれば、放射線管理従事者が重装備で、被爆線量の管理が厳格に行われていたレベルをこえるような線量なのにだ。それが今では自由に無防備で線量計さえも持たずに立入れるようになっている。私達は原発事故後、急激に被曝に対する免疫でもできたというのか? ホント私達は全く愚弄されているんですよ。モルモットなんですよ。全く人の命が軽んじられている。あ、立ち入りの報告レポートするつもりが・・・その前に長くなってしまったので続きは次回に!
2013.05.11
-
避難先で亡くなるということ
先日先輩の司法書士が亡くなられたという訃報を受けた。享年95歳。私はもちろん、私の父もお世話になった大先輩だ。90歳を過ぎても現役で、絶対100まで生きられると周囲の誰もが思っていた。しかしその先輩も原発事故で避難を余儀なくされてしまっていた。 原発事故があった福島第一原子力発電所周辺地域の司法書士達は、福島県司法書士会相双支部という支部に所属していた。支部会員20名中12名が避難を余儀なくされ、その後1名が退会、そして今回1名が亡くなられた。私を含めその他の10名は今も元の事務所を追われて戻れていない。他所で仮の避難先事務所を再開しても、なかなか以前のようにはいかず不自由していることは私も身をもって感じている。残りの会員10名も元の事務所で再開できずに事務所をたたむのかな・・・なんて想像したりする。平均は65歳以上の司法書士高齢化地域だったので尚更だ。支部の存続も危うい状態だ。 水が違うと魚が弱ってしまうように、住み慣れた場所を離れて生活するというのは精神的にも肉体的にもダメージが大きい。高齢者になると以前の生活環境に執着が大きい分尚更きつい。 何より自分の自宅で自分の事務所で終期を迎えたかっただろうなと思うと悔しい。原発事故が無ければ未だ現役で事務所で仕事を続けていただろう。 心よりご冥福をお祈り致します。
2013.04.23
-
原発事故と水俣病
今朝の新聞に最高裁が初めて水俣病の患者認定をしたと言う記事が1面に載っていた。汚染した魚介類を食べた人に起きた神経性中毒症状が公式に確認されたのは1956年だという。私が生まれる遙か前だ。これまで多くの人が窮状を訴え、かなわず、亡くなっていったことだろう。多くの涙が流れ枯れ果ててきたことだろう。そして多くの支援者が関わってきたことも想像できる。 このような公害問題や公害訴訟について、正直私は今まで所詮他人事だったし、そんなに深く考えたことはなかった。けれども今、福島原発事故賠償問題に日々関わっていると、ものすごくこれらの公害問題に関心が高まっている自分がいるし、学ぶべき事が多くあることに気付く。知れば知るほど共通点が多いことを思い知らされる。学んで活かさなければと思う。国や加害者の対応もかぶる。「今も昔もずっと同じか・・・」そんなことを痛感させられる。被害の種類は違えども、国や加害者の対応はずっと変わってないんだな、今始まったことじゃないんだな、と気付かされます。私が思っていたよりずっとクソだったんだなこの国は。 この水俣訴訟も、はじめに訴訟したのは被害者の大部分の多数派ではなくて、ごく一部の人達だったと聞く。そこから広がっていった。ほとんどの被害者が声を上げることができずに苦しんでいたことを想像できる。 福島原発事故賠償問題もきっと息の長い闘いになると思う。健康問題はまだ顕在化していないし、私達が死んでも続いていくのだろう。私達が生きている間に私達ができることをしよう、そう思う。
2013.04.17
-
財物賠償 所有権の行方
今週末、13日土曜日、福島県司法書士会による財物賠償の電話相談会が開催される。先月29日から東電による財物賠償の請求書手続きが開始されたことを受けての開催となる。財物賠償についてはもちろん、賠償問題全般について相談があれば電話して欲しい。 昨日NHKでも放映されていたが、不動産賠償に関して、福島県司法書士会が現在問題視していることの一つに「所有権の帰属」の問題がある。ここで少し噛み砕いて解説しようと思う。 通常民法の原則からすれば、全損による全額賠償がされれば所有権は相手方に帰属する。(民法422条) すなわち今回の不動産賠償でいえば、不動産が全損したとしてその全額を東電が賠償すれば、その不動産の所有権は東電側に帰属するわけである。しかし東電側は今回、所有権は賠償後もなお元の所有者に残しておく取り扱いをすることにしている。全損の賠償を受けてなお、被害者に不動産の所有権を残すとしたことは、一見被害者にとって良いことじゃないかと思えるし、東電も被害者感情に配慮したとしている。しかし、これは被害者全体にとって必ずしも良い事ばかりではないのだ。 所有権が残るということは所有者の責任もずっと付きまとうという事である。家を不在にしている間も所有者として法律的に管理責任を負うことになる。家屋に火災や倒壊が生じた場合の責任を負い、これからも恒常的に管理していかなければならない。数年後には固定資産税も払わなければならなくなるだろう。特に、もう戻らないと決め、新転地で新たな生活を始めた人にとっては、近い将来残してきた住まない土地建物が悩みの種となってくるだろう。このままでは所有権は残されたものの、管理責任や建物の収去費用の負担を負わされ、将来売却したくても買い手が付かない状況が待っている。 何より、そういった状況や責任が生じることを何の説明もなしに(しゃばぐっちぇ)合意書に盛り込んで一律に取り扱おうというやり方、被害自身に選択の余地が与えられないことが問題なのだ。東電側の本音としては無駄に所有権を争いたくないし、虫食い的にそんな不動産を取得しても意味がないというところだろう。 だいたい賠償をはじめすべての被災者支援が、被災者に選択の余地が与えられずに、被災者無視で進められていることがそもそもおかしいいし、、、、ま~これを言い出すと長くなるからやめるが、、、、 被害者のためには避難指示が解除になり、将来いよいよ決断しなければならないその時まで、所有権を残すか残さないかの判断を保留できるようにしなければならない。これを機に、政府主導で何とかこの所有権の帰属を被害者主導で選択できるような道筋と、不在地の不動産の管理責任について超法規的な政策を打ち出さなければならない。 将来に所有権の選択の余地を残すべきだというのは、今すぐその判断を被害者に求めるのはあまりにも酷過ぎるからだ。本当に帰れるのか帰れるのか、帰るのか帰らないのか、今の原発の状況、除染の状況、線量、町の状況、賠償の行方をみても判断はつけられないのが当然だろう。13日 土曜日 10時~16時 電話はこちら 024-531-5233http://fk-shiho.com/consult/consult3.html
2013.04.10
-
富岡町の区域再編に物申す ビール片手に番外編
昨日富岡町が警戒区域解除されて区域再編されました。この警戒区域解除と区域再編は多くの住民の本意ではない。俺なんかさ、個人的に区域再編なんて受け入れずに、警戒区域は維持して、粛々と除染とインフラ整備をすればいいじゃないかと思っているわけ。入りたい人には許可を柔軟にしてさ。それよりも、安全じゃないのに、帰れると思ってないのに勝手に帰れることにされてしまって、無かったことにされてしまって賠償や支援が打ち切られるようなことがあってはならないと思うわけ。 けれどさ~~~ 正直みんな行きたいよね~~~富岡。 俺もだよ。当たり前だよ、だって自分の家だもの。2年以上も自分の家に帰れなかったのに今日から帰れるようになったんだよ~一応物理的にはさ。矛盾するけど、良かったような気がしてしまう、騙されてんだけどさ。両親なんかも行って掃除する気満々だもの。これから頻繁に通うらしい、やめとけっては言ったけど。でも気持ちは痛いほど分かるしね。最低5年は住めないと分かっても家をほっとけないんだよ。 昨日と今日はニュースで富岡町のあちこちが放映されているわけ。涙出るくらい懐かしいもの。全部、道分かるんだもの。2年前まで普通に毎日行き来していた場所でしょ~ そこには平凡な幸せがあったことを痛感させられるんだよ。「あ~!創夢館と井出自工の所にバリケード張られてる~」みたいなさ。テレビに登場してくる町民も皆知ってるし。 戻れるものなら皆戻りたいんだよ。3・11以前と全く同じになるならね。けれど元通りになることはない。それもみんな頭では分かっているんだけどね。それを受け入れるのはまだまだ時間がかかるんだろうね。どうなっちまうのかね・・・
2013.03.25
-
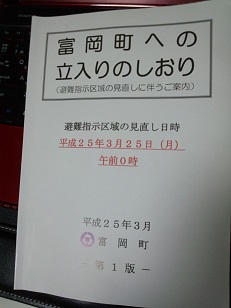
富岡町の区域再編に物申す
本日3月25日午前0時、我が富岡町が区域再編された。11市町村中8番目だそうだが今までの市町村とは規模が違う。富岡町は3分割され、町の29%が帰宅困難区域、62%が居住制限区域、残り9%が避難指示解除準備区域となった。居住制限区域だけで約4000世帯もあるという晴れて富岡町の大部分が今日から自由に出入りできるようになったわけだ。 町民には事前に町役場から「立入り証」と「立入りのしおり」が配布されている。「立入り証」は自由に入れるようになったものの、警察に職務質問された時に簡単に身分を証明するために提示するものだという。 「立入りのしおり」を読むと、一番最初のページには「立入りの際にはタイベックスーツ、マスク、手袋等の防護装備を着用してください。」と赤く大きな文字で記載されており、線量の高い所もあるとの注意書きがある。立入りには線量計を持ち歩き、ノートに被曝線量を記録し、帰る時にはスクリーニングを受けるようにとも書かれている。これを読んだだけで、決して安全になったから警戒区域が解除された訳ではないことが分かる。読み進める毎に腹立たしくなっていくのは私だけだろうか。何のために警戒区域を解除して区域再編して立入れるようにしたのか。危険だけど、自己責任でどうぞという内容に感じる。そしてそのしおりには、国の方針に町は従わざるを得なかったと町長のメッセージまでが綴られている。その他電気、ガス、水道も使えません。トイレも使えません。ゴミも出せませんと記載されている。本当何のための解除なんだろう?考える度腹立たしくなってくる。 この区域再編は政府が早く事態を収束させたい、被害の実体を早く封じ込めたいだけのような気がする。町民のための区域再編ではない。我々住民の安全や健康などは二の次なのだろう。全く愚弄されている。安全性に関する裏打ちのないまま、町民無視で警戒区域を解除して区域再編して、事故の幕引きを図ろうという風にしか感じられない。 富岡町は町の方針として5年間帰還しないことを決めているので、区域再編してどの区域になろうが5年は誰も住めないし帰れないのだ。区域再編の意味がないのだ。除染やインフラ整備なんてやる気になれば区域再編なんてしなくてもできるはずだ。そしてこの区域再編によって賠償額に大きな差が生じて住民間の分断も生じさせている。多くの町民の思いとは裏腹に、帰れることが前提なので賠償額も低く押さえ込まれている。 この区域再編は帰還するための、またその準備のための区域再編ではない。町民にとって全く前進した感はない。メリットといえば面倒な立入りのための手続きが無くなっただけ。あとは賠償額の減額、賠償打ち切りのカウントダウン、地域の分断、住民の分断、健康被害のリスク、とデメリットしか見当たらないのではないか? 私自身もう1年以上家にも実家にも行っていないので、今年は防護服を着て両親を連れて立入りしようと思っている。防護服を着て荒れた大地と朽ち果てた我が家をみて自分自身に印籠を渡すための、諦めをつけるための立ち入りになるのではないか。
2013.03.25
-
富岡町 区域再編を前に
昨夜午後7時頃、福島第一原発で停電があって共用プールの冷却機能が停止しましたね。未だ原因不明だし、また公表も遅れたし、原子炉への注水に問題は無いと言うけれどどこまで信用したらいいのかね? また爆発するのか? この2年間私達はずっと政府や東電の対応に翻弄され続けてきたからね。常に疑心暗鬼だよね。いつでも避難できるように、その備えを今後40年間続けなければならない。死ぬまで続けるって事だよね。 来週から我が富岡町でも警戒区域が解除され、区域再編がなされる。私から言わせれば全くナンセンスな話だけど、これを受け入れれば「賠償がもらえますよ」「除染が進みますよ」「家に戻れるようになりますよ」と町は国にごり押しされて受け入れてしまった。多くの住民も区域再編でようやく物事が進むって好意的に捉えている節があるんじゃないかな。 来週から富岡町は3分割されて、帰還困難区域はバリケードが張られ、居住制限区域(年50mSv以下~年20mSv超)と、解除準備区域(年20mSv以下の区域)は日中自由に立ち入りしていいという事になる。ついこの間まで完全防備で立ち入っていた地域に無防備で立ち入りしていいって事になるんですよ!? 原発事故前は放射線業務従事者でも年20mSv近い被曝はきわめて少なかったというじゃない、年50mSv以下だから自由に立ち入れるってどうなの!?もちろんそれよりも高いホットスポットも点在しているのに。今の状態で自由に立ち入れるっていうのは、私のヒューマニズムからしても受け入れがたいがたい(泣)。私達を日本国民だと思ってるんですかね(怒)愚弄されているよ。ホント腹立つね。 そこに人が帰れるのか?自分の子供を連れて来れるか? 大熊町、楢葉町には中間貯蔵施設も建設されて、高線量の放射性廃棄物を積んだトラックが生活道路を毎日往来するわけでしょ? その上不安定な福島第一原発という爆弾を抱えながらの生活なんて想像するだけで普通の神経じゃ無理だよね・・・来週以降どうなるんだろう・・・
2013.03.19
-

双葉翔陽高校 サテライト校
先週「高校生のための法律教室」で双葉翔陽高校にお邪魔した。双葉郡大熊町にあった双葉翔陽高校は、学校も生徒も原発事故によって避難を強いられ、県内各地に仮庁舎が分散して設けられていた。そして卒業式を間近に控えた先月、ようやくいわき明星大学の敷地内にあるサテライト校舎内に一つにまとめられ、生徒達もみんな一緒に授業が受けられる環境が整ったそうだ。生徒達はやっと仲間達と再会できたものの、皆仮設住宅や親元から離れて寄宿舎から学校へ通っているそうだ。 震災の数年前、私は大熊町の双葉翔陽高校に同じように「高校生のための法律教室」でお邪魔したことがある。思い返せばあの頃は平和な授業だったけれど、今は学校も生徒もそして私自身も避難生活を強いられている。今回はいわき支部の先生に頼んで双葉翔陽高校の法律教室に参加させてもらった。同じ避難中の身だからこそ生徒達に伝えられる事があると思ったからだ。生徒達は一見普通の高校生と変わらない様子に見えるけれど、その胸の奥には避難生活の苦悩を抱えていることを私は知っている。だから傲慢かも知れないけれど、私は生徒達に何か伝えたい衝動に駆られて少し話する時間を頂いたのだ。法律教室の内容とは無関係で強引感はあったけれど同じ立場の私が伝える意味があったと思う。そして生徒達に次のようなことを伝えお願いした。 まず「あなたたちは何も悪くはない。」ということ。突然の避難によって幾多の苦難に遭遇し、そしてそのことでこれからも苦難が立ちはだかるだろう。もしかしたら、いわれのない差別を受けることがあるかも知れない。けれど、あなたは決して悪くない。だから毅然と立って歩いて行って欲しいということ。 そして、これまでの困難やこれから立ちはだかる困難は必ずあなたの成長の糧になり、大きな大人にする、人に優しくなれる、それを信じること。「優しい大人になって欲しい。」ということ。 最後に泣きたいときは泣いていいし、不満でもいい、「大人を頼って欲しい。」大人に相談してぶつけて欲しいということを今回は生徒達にお願いしてきた。少し偉そうだったかもしれないけれど。 実は子供達が今回の原発事故避難で一番皺寄せをくっていると私は思う。多感な成長期、青春時代に突然学校生活が奪われてしまったのだ。学校も友達も先生も失って、親の都合で避難所を転々とし、今の仮の住まいで生活している。地元に就職や進学が決まっていた人も多くいたのに、就職先、進学先ごと無くなってしまったのだ。そしてこれから放射能の影響はないだろうか?結婚はできるのだろうか?子供はつくれるのだろうか?と子供ながらにリアルに考えている。親の苦労を横目に、悩みさえ打ち明けらえれない子供達も多いと思う。みな多くのもの背負わされて抱え込んでいるのだ。本当に子供達は何も悪くないのに。これからも機会があれば避難中の高校の法律教室を回りたいと思う。傲慢かも知れないけど私が伝えたいという気持ちが大きい。
2013.03.07
-
様式、運用変更による実質賠償の打ち切り
先日こんな話を聞いた。 Aさんの父親が病気で入院して手術を受けることになった。医師と家族の手術前面談の際に医師から「お父様の病気は原発事故による避難とは無関係ですから。」と言われたという。そして手術後、退院までの説明を受ける際にもまた「お父様の病気は原発事故による避難とは無関係ですから。」と念を押されるように言われたという。こちらから何も触れていないのに、医師の方からこういう話を切り出されたことに不快に思ったAさんは、医師に抗議したという。医師は現場の実情を話し謝ったという。 原発避難者が避難生活中医療機関にかかり、医療費等のいわゆる「生命・身体的損害」を東電に請求する場合、東電所定の医師の診断書の提出を求められる。この用紙には避難生活と病気との因果関係の有無の記載項目がある。□因果関係あり □因果関係なし □不明 に医師がチェックするようになっている。医師に厳格な因果関係の有無など判断できるわけが無いと思うのだが、県内の医療機関では事情を与んでくれて当初は割と □因果関係あり にチェックしてくれる医療機関が多かった。そしてたとえ □不明 にチェックがされていても賠償金の支払いがなされる運用がされていた。しかし最近突然 □不明 の選択肢が削除された。間口を狭められたのだ。それは、医師によるより厳格な因果関係の有無の判断を求めらたことにもなる。そして東電から医療機関に圧力がかかり、診断書を書く医師も上からの圧力がかかって、容易に診断書を書けなくなったとも聞く。上記の話は診断書を書く現場の医師が萎縮、警戒しての発言なのだろう。おまけに東電所定の医師の診断書様式はコロコロと変えられ、高齢者の多くはその複雑難解な手続きを前に、実質請求を断念させられている現状がある。 原発事故による一連の賠償は、被害者自らが分厚い請求書を解読し記入し、損害を請求しなければならない。できない者は置き去りにされ切り捨てされている。その請求書に潜む罠も、回を重ねるごと日を追うごとに多くなっている。気づかない者は気づかない。被害者の知らないうちに様式を変え、運用を変えてきている。気づいて文句を言っても埒があかずに泣き寝入りするしかないのが現状なのだ。加害者の一方的で姑息な取り扱い変更によって実質賠償の打ち切りが進んでいる。
2013.02.28
-
賠償金 課税
原発事故によって避難を余儀なくされた事業者の賠償って、逸失利益の賠償でしかないじゃない。本来事故が無ければ得られたであろう収入の賠償でしかないわけ。言い換えれば原発事故が無ければその収入はずっとずっと入ってくるはずだったわけですよ。その償いである賠償もここ数年で打ち切られてしまう。じゃ数年後に何が残るかっていうと、結局場所も顧客もその地域も将来の見込み収入もそこで生きる生き甲斐も全て奪われた現実だけなんですよね。数年で賠償金が打ち切られて身ぐるみ剥がされて放り出されるわけですよ。しかもですよ、その逸失利益の賠償金に税金がかかるんですよ~決して十分な額ではないのに。酷ですよね。給与所得者だって同じ。一時所得として課税される。そして職を失った現実だけが残る。今更この歳で再就職なんてできないという声も多く聞きます。普通に考えて30代後半や40代になれば難しいよね。そしてサラリーマンの場合ほとんど申告の経験がないだろうし、知らずに確定申告しないケースも出てくると思うから公平性としてどうなんだろうと思う。今は原発周辺地域12市町村では税金の申告、納税期限の延長措置がとられているけれど、これが終われば多くの方はものすごい税金がかかってくる。それを知らずに運転資金につぎ込んでしまった事業者も多いはず。延長措置が終わったら、ほとんどの事業者の経営が立ちいかなくなるんじゃないかな。復興は厳しい。今は延長措置で問題が顕在化してないだけであまり騒がれていない気がするけど。水俣病やオウムの問題では賠償金の非課税措置があったわけじゃない。原発事故の賠償金だって失われたものに対して決して満足のいく支払いは行われていないわけだから、絶対特別な措置が必要だと思う。 私が仕事をしていて一番つらいのは、原発事故前、地元でバリバリ仕事をしていた社長さんが、避難させられて仕事も生きがいも奪われて鋭気を失ってしまった姿を目の当たりにする時。避難前のオーラと全然ちがうの。何もなければずっと地元の優良企業でい続けられただろうに・・何の落ち度もないのに・・・そんなことを思うとやりきれない。これからもマスコミや世間は賠償金の額だけを面白おかしく話題にするんだろうけど決してお金の問題じゃない。その気持ちは今のところ奪われた当事者にしか理解されていない気がするよね。
2013.02.24
-
原発事故賠償金をめぐる親族間の争い
見ず知らずの人に突然叱責、罵倒されることって大人になってあんまり無いよね。 相続登記の依頼で、依頼者に見ず知らずの異母兄弟がいることが判明してしまったり、依頼者に長年音信不通だった親類がいて連絡もとれないというような状況に出会すことは、司法書士事務所ではよくある風景である。直接その異母兄弟や音信不通の兄弟と交渉することはできない旨を依頼者にはっきり伝えるが、どうしても手紙だけでも作ってくれないかとお願いされることもしばしばある。業としてではなく善意で丁重に丁重に文章を考えて「まずは連絡くださいませ。」という内容の手紙を依頼者自身に送ってもらうのだが、突然事務所に電話がかってきて「てめ~!!この~野郎!!ピーーーピーーー(放送禁止)」なんてこともしばしばある。正直凹む。話し合いできる余地はなさそうだということで弁護士さんを紹介するのが通常だけれど、たまに「あれから本人と話し合いができて印鑑もらえるようになりました。」ということもある。「え!?なんで!?あれだけ人を罵倒しておいて・・・」なんて理解できないこともしばしば。血のつながっている者同士にしか分からない親族の事情があるのだろう。結果オーライで凹んだ自分を慰めるのである。 さて、今日の新聞で来月末にも避難区域の財物賠償の請求受付が始まるという記事が載っていた。未登記物件や遺産分割未了で所有者が確定できない物件の賠償は後回しにされる様相だ。当然親族間で揉めていて遺産分割ができない物件の賠償の支払いは後回しになる。死亡した人の銀行口座解約手続きを想像してもらえば分かるように、親族の書類への実印押印や印鑑証明書がなければこの財物賠償手続きも進めることはできない。固定資産税の納税義務者に対しても支払うべきだとする論調もあるけれど、所有者ではない以上二重支払いの危険を冒して東電が納税義務者に支払うことはまずないだろう。つまり、仮に納税義務者に支払いをしてしまったら、後から他の相続人からの支払い請求を東電は拒むことはできなくなるのだ。原発事故の賠償金が絡んでいるせいで現場では既に親族間の紛争が表面化してきている。むしろ原発事故賠償によって親族間の争いが誘発されている嫌いもある。そしてこれからますます・・・ 原発事故によって狂わされてしまった親族関係とでも言うべきか。そして私が罵倒されることも増えていくんだろう・・・呑みにでもいくか~
2013.02.20
-
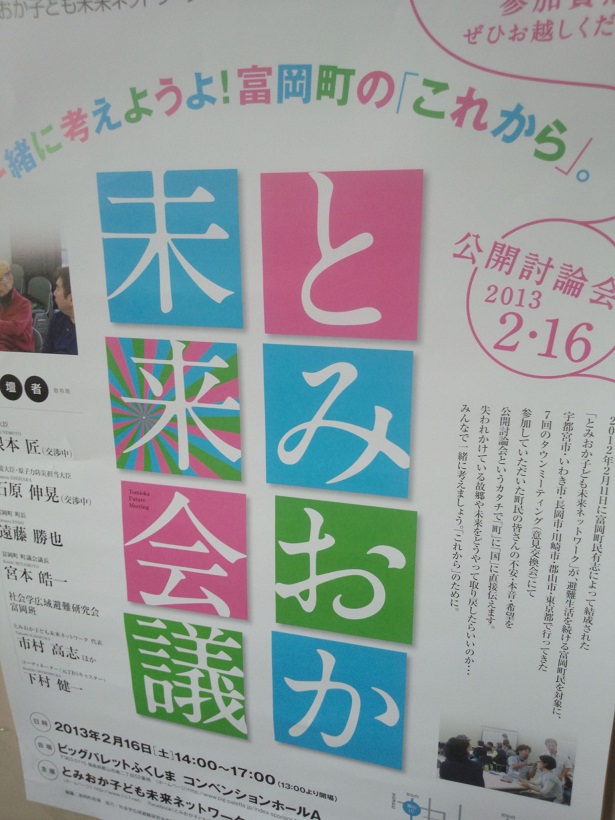
とみおか未来会議 2月16日14時~郡山ビックパレット
今週16日に郡山ビックパレットで「とみおか未来会議」が開催される。いよいよ!という感じで感慨深いものがある。平成23年の初秋、震災・原発事故から半年経った頃、発起人の4人がいわきの居酒屋で初めて顔を合わせた時の事を思い出す。「どうなってんだ!?何でこんな事態になってんだろう!?」「俺たち突然町から追い出されて、どうして誰も何も説明してくれないんだ!?」「町民無視で全ての物事が決められていく!」「どうして俺たちの声は全く聞き入れられないんだ?」 避難を強いられた身で「絶対おかしいよな」という共通の思いをぶつけ合った。「俺たちの町のこと、俺たちの将来のこと、俺たちの人生のことは俺たちが創っていかなければならない。」「突然町を追い出され、突然生活を壊され、人生を狂わされてしまった。そのうえ未来までも奪われるなんてまっぴらごめんだ。」「なかなか理解してもらえない。うちらの状況はうちらにしか分からないのかもしれない。」「だったらうちら自身が声を上げなければ。そして避難している町民の本当の声を届けよう。」そんな思いはずっと一貫して持ち続けてきた。私もここで支援者という立場で携わっているつもりはない。避難を強いられている当事者として、町民による町民のための草の根運動が大切なんだと思う。あれから1年以上、全国各地で避難している同じ富岡町民とタウンミーティングを続けてきた。たくさんの方とつながり、避難生活の苦悩を吐露しながら、一緒に町の将来、自分たちの将来を話し合ってきた。たくさんの支援者とつながり、応援、サポートをしていただきながら紆余曲折やってきた。たくさんの出会いがあった。失敗と挫折の繰り返しだった。「そんな事して何になんだい?そんな事言ったってしょうがねぇべ。変えられるわげねぇべ。」という意見と自分の弱さと葛藤しながら、それでも、「変えられないかもしれない。けれど何もしなければ絶対に変わることはない。町民一人一人の力は小さいけれど、束ねればそれは大きな力になる。勝てないまでも一矢報いたい。」と思いながらやってきた。その集大成として今週末の「とみおか未来会議」がある。タウンミーティングで出た多くの住民の声を、社会学者の協力のもとで整理、集約し、それを町や国に公開討論の場で届けるという試みだ。当日はマスコミも多数駆けつける。多くの富岡町に思いをはせる方達にぜひぜひご参集いただきたい。集まれ富岡町民!!勝てないまでも一矢報いたい。
2013.02.14
-

平成25年2月2日 富岡町住民説明会 感想文後編
後半の東電による説明会では、まず東電社員による謝罪と福島復興本社代表の挨拶から始まった。福島復興本社代表は福島第二原発の所長を務めていた経歴もあり、事故前富岡町民と深い関わりがあった方だ。冒頭その代表が、復興への意気込みと富岡町に対する深い思い入れを述べた。多くの富岡町民は彼のことを知っており、私の知る限り悪く言う人を聞いたことがない。多くの町民が彼に親近感を持っていると思う。実は何を隠そう私の結婚式にも出席いただいているのだが・・・彼が福島復興本社の代表に就任して住民の意見は通り易くなるのか、逆に住民は物を言えなくなるのか。私は物を言い続けるスタンスを崩すつもりはないし、彼が福島復興本社の所長になったことによって、住民の苦境が賠償に反映され、より建設的な話合いができるようになり、物事が進むことを期待したい。 さて東電からの説明の内容とはといえば、財物賠償についてよく知っている者にとっては注して目新しい情報もなく、理解できない町民にとっては念仏状態の説明だったのではないだろうか。驚いたのは概ね住民が納得している前半の区域再編の国や町の説明の方では質疑が荒れ気味だったのに対し、難題山積の東電賠償の質疑ではあまり荒れず、住民の威勢が感じられなかったということ。中には「あなたたちには頑張っていただきたい」と敬意を表し、奉る発言まであった。この期に及んで住民は東電崇拝しているのか。愕然とさせられた。はたまた一度崩壊した東電崇拝構造が再構築されてきているというのだろうか。理解に苦しむが、とても居心地が悪かったのは確か。無理もない。参加したほとんどの町民の親類には、東電社員や関連企業の社員がいる現状。今なお職がある町民のほとんどは福島第一、第二、火力発電所の修復作業や除染、そしてそこに深くかかわる業種の人たちばかりなのだ。 この説明会で、今回の賠償問題が加害者の一方的なスキームによって封じ込められ、被害者が懐柔させられている理由、血の巡り悪いその元凶をまざまざと見せつけられてしまった気がする。被害者は加害者に物が言えず、従わざるを得ない、むしろ心酔して従っている。それは原発事故後も東電依存から抜け出せないその構造の強固さ、根深さからきているのではないか。賠償問題の血の巡りをよくするにはやはりこの構造からの脱却がなければ無理なのではなかろうか。そうでなければ根本的に血の巡りは良くならないのではないだろうか。いくらその場しのぎで輸血をしても正常に回復しないのだろう。病原を突きとめて取り除かなければ。そんなことを思いながら家に帰った私はぶっ倒れた・・・インフルエンザじゃないといいが・・・
2013.02.07
-

平成25年2月2日 富岡町住民説明会 感想文前編
2月2日いわきの明星大で富岡町の住民説明会が開催された。富岡町民が一堂に会するこの説明会は原発事故から今回で2回目。もう原発事故から2年近くも経つけれど、町民が町や国から直接話を聞く機会は本当にこれが2回目なのだ。しかも今回は自分たちの重要な財産、特に先祖代々受け継いで守ってきた土地、家屋敷の命運にかかわる事柄、そして自分達の人生にかかわる事柄の説明なのだが、いずれも奥歯に物が挟まったような担当者の説明会でしかなかった。そして今回も一方的に決定された結果の事後報告形式でしかなく、当の住民に選択の余地は全くなかった。それは住民の意志が反映されたものではない。誰かが決めた事柄の事後報告なのだ。 さて、説明会は、前半、町と国から区域再編の説明が2時間行われ、後半は東電による賠償の説明が2時間行われるという2部構成で催された。私自身は「声を上げ続けよう」という信念を貫きたかったので、前半か後半で手を挙げて質問しようと思っていた。そして後半に僭越ながらこの位置から質問させていただいた。 前半の区域再編に対する説明に対して町民の雰囲気はというと、なぜか「もう仕方がない」という区域再編容認ムードが漂っていたように感じた。ある意味驚いた。私に言わせれば全くおかしい国の都合による区域再編なのだが、大半の町民はというと「区域再編が決まれば財物賠償が進む」「区域再編が決まれば除染が進む」「これで一歩前進だ」というような歓迎ムードなのだ。これは町長をはじめとする役場の人間も同様。本来区域再編と、賠償、除染の話は別であり、区域再編ありきで、その受け入れが前提条件で強引に進められていること自体おかしい話なのだ。国の思惑としてはこうだろう。何としてでも区域再編をしたい。すなわち区域再編=警戒区域を解除し、この問題を一刻も早く終結して対内的にも対外的にも安全をアピールしたいというのが本音なのだろうと思う。国はもうこの問題を終わりにしたい。そして町も町民も、賠償と除染の進捗は区域再編が決まれば加速度的に進むかのような国の策略にまんまとはめられてしまっているというのが私の感想である。私がここで「区域再編反対!」と言おうものなら「おまえは余計なことを言うな!」「そんなこと言ったら賠償と除染が遅れるだろ!」と罵声を浴びせられる雰囲気さえあった。そして国や東電にとっては区域再編ができれば全損賠償の範囲が狭められ、支出は少なく済ませられることになるだろう。しかし町民にとっては区域再編が受け入れられれば住民間に賠償の差が生じ、住民間の繋がりもますます薄れ格差が生じていくだろう。そして何より区域再編されれば、町にとって将来の存続自体が危うくなるという、消滅の引き金を引く結果となるだろう。 最後に用意された質問の時間には、例のごとく町民から町と国の役人がサンドバック的に責められることになる。無理もない住民の発言は本当に震災以来これで2回目なのですから。 これが前半の区域再編の説明のざっとした感想である。
2013.02.05
-
避難解除 事業再開できても
元の町に戻って事業再開できた事業者だって前途多難なんですよ。元の場所に戻ったって、町は、住民は、元どおりではないんですから。双葉郡の広野町や川内村の一部では現在警戒区域等の指定が解除されて、普通に生活できる場所になった。正確には普通に生活できることにされてしまったと言うべきか。新聞を読む限りでは住民の帰還や町の復興が進んでいるかのような錯覚に陥るんだけれど、実際に地元の生の話を聞くと必ずしもそうではない。昼間、人や車の出入りは多いものの、ほとんどが除染や原発の作業員で、夜になると人の気配がないと言う。もちろん子供の姿なんてない。先日事務所にいらした広野に戻った人の話では「約1割が戻ったと言われているけど、本当に戻って24時間広野町で生活をしている人はもっと少ないですよ。買い物できる所もないんですからあたりまえです。ほとんどの人が借上住宅や仮設住宅との行き来をしているんです。」そんなことを漏らしていた。 川内村や広野町で事業再開した事業者の話も最近よく聞くようになった。再開した当初はマスコミの報道や懐かしさから足を運んでくれる客もいたけど、それもそう長くは続かないと漏らしていた。「仮設や借り上げ住宅の近くのスーパーで買って行った方が便利ですからね。意地になって元の場所で事業再開したのが間違いだったかな・・・」と。 既に避難解除されて除染が進んでいるとされている自治体でさえそんな現状ですよ。それなのにそれよりも福島第一原発に近い、それ以北の町が避難解除されても元どおりになるなんてありうるのか? ましてや中間貯蔵施設やがれきの管理処分場が乱立する地域に人は戻るだろうか? 廃炉作業に果てしない期間を要するその傾いた原発の近くに、親は安心して子供を連れて戻って来れるだろうか? 高濃度の汚染された瓦礫を運ぶトラックが行き交うその町で、はたして安心して子育てができるだろうか? ある議員さん曰く、町が避難解除を受け入れた途端、国は全く話を聞いてもくれず見向きもされなくなったという。そんなもんだろう。
2013.01.23
-
大熊町 事業者の苦悩
昨年大熊町にあったある事業者がいわきで事業再開するということで、うちの事務所でお手伝いさせていただく機会があったんだけど、その方の事業所に先週久しぶりに顔を出してみた時の話。何気ない会話の中から事業再開の厳しさは十分窺えた。その時こんな事業者賠償への不満を漏らしていた。「今もらえている賠償の額って普通に大熊で営業していれば普通に入ってきた収入なんですよね~それだけの賠償ですもの。私たちがここまで必死で避難して避難生活を続けながら事業を何とかしなければと思ってやってきている苦労っていったい何なんでしょうね~?この先何年店をできるかわからない。絶対方向転換してやっていかなければ続けられないですよ。大熊で普通にできていれば・・・大熊で今までずっとやってきたことが全て水の泡になってしまったんですよね~何でこんなに苦労してるんだか正直分からないですよ~」そんなセリフが私の頭の中で何度も反芻されている。そう、今の事業所への賠償は逸失利益の賠償のみでしかない。震災以前の利益と現在の利益の差が補填されているにすぎない。それもきっと数年で打ち切られるだろう。損害賠償とはそういうものだということは私も頭の片隅では理解しているけど、やっぱり解せない。今まで培ってきた店の価値、顧客やマーケット、歴史、伝統、暖簾、そして懸けてきたもの、投資はもちろん愛情、思い出、そして描いていた未来。そして店を失ったことで受けた店主の精神的な苦痛。法的にも当然賠償されるべき損害が黙殺されているのが、この原発事故の損害賠償の現実。これを言ったら事業者の賠償に限ったことではないけれど。店主の痛みは痛いほどよくわかる。わかりすぎる。同じようなことを前にも書いた気がするけど何度でも書こう。
2013.01.21
-
富岡町民による富岡町民のためのタウンミーティング
今日は雪で仕事に行けなかった(^_^.) 常磐道通行止めなんだもの~ 埼玉からいわきへ通勤なのでこんな日があっても仕方ないですね。昨日は2回すっ転びましたよ(^^ゞ 雪掻きで筋肉痛だし・・・ 先週土曜日は、「とみおか子ども未来ネットワーク」主催の第6回タウンミーティングがいわきでありました。富岡町の住民が集まってこれからの生活の事やこれからの町の事を、町民自身が主役になって考えようじゃないかという試みです。震災から1年10ヶ月。この1年10ヶ月、「我慢していればいつか何とかなるんじゃないか」「いつか役場が、いつか国が、いつか議員さんが」と待ち続けていた町民が期待を裏切られ続けてきた1年10ヶ月だったとも言えます。やはり自分たちのことは自分たちが一番良く知っていて、自分たちがなんとかしなければならない。一人ひとりの力は小さいけれど、町民が一丸となれば変えられる、そう信じて私も参加しています。そして町民が結束して変えていくこの方法でしか、風穴は開けれないんじゃないかとも私は考えるようになりました。タウンミーティングでは毎回はっとさせられる発言があります。今回私が印象的だった発言は「富岡町は5年間帰還宣言しないと町長が明言したけれど、じゃ5年間町民はどうすればいいの?何も示してはくれない。一番は住まいのこと。復興住宅がいつできるのか。どこにできるのか。はたして希望者全員が入れるような所なのか。借り上げ住宅、仮設住宅はいつまで延長になるのか。そもそも5年後にちゃんと帰れるようになっているのか疑問だし。かといって、断ち切って新しい生活を踏み出そうにも不動産賠償がいつ決着するのかも分からない。何もかも分からないで、何も材料がなくて、町民はいつまでも決断ができない。いったい町民にどうしろというの!。」もっともな意見です。自分も身を持って感じていること。町民の精神状態はますます疲弊し、限界はとっくに超えているのがひしひしと伝わってきました。 タウンミーティングでは他にも印象的な発言が多くて、休みがつぶれるの嫌~って思うんだけど、毎回参加してよかったな~って思う。みんな思ってることは一緒なんだなと。だからこそ何とかしたいなと。
2013.01.15
全975件 (975件中 1-50件目)