全197件 (197件中 1-50件目)
-

【485夜】『檸檬』 梶井基次郎
【485夜】『檸檬』 梶井基次郎 1991 集英社文庫梶井基次郎は、1932年3月24日、肺結核のために亡くなりました。31歳でした。彼が結核を発病したのは20年、第三高等学校理科甲類在学中のことです。そのために生活は荒み、学業は怠りがちとなります。それでも5年がかりで高校を卒業し、24年、東京帝国大学英文科に入学。翌年、学友らと雑誌「青空」を作り、『檸檬』を発表しますが、病状が悪化し、退学して伊豆・湯ヶ島で療養生活を送ります。今でこそ、結核というと過去の病というイメージですが、それは1944年にストレプトマイシンが開発され、結核の治療の糸口が見出されて以後の話です。それまでの結核は「不治の病」として恐れられ、よく知られている歴史上、文学上の人物も若くして亡くなった人の多くが結核でした。たとえば…滝廉太郎(23歳)、樋口一葉(24歳)、立原道造(24歳)、沖田総司(25歳)、高杉晋作(27歳)、石川啄木(27歳)、八木重吉(29歳)、新美南吉(29歳)、中原中也(30歳)、佐伯祐三(30歳)、正岡子規(34歳)、国木田独歩(36歳)、長塚節(36歳)、宮沢賢治(37歳)、といった具合です。結核を題材とした文学作品も多く、自身が肺結核で長い闘病生活を送った堀辰雄の『風立ちぬ』、徳富蘆花の『不如帰』などがあり、俳人の石田波郷は数多くの闘病句を詠みました。結核は空気感染ですから、いつの間にかどこからともなく忍び寄ってくるという性格を持っています。エイズなどよりはるかに感染力が強く、予防の方法がほとんどありませんでした。このころは結核だけでなく他にも多くの感染症があり、若い人であっても「死」は決して遠い存在ではなかったのだ、とあらためて思います。つい50年ほど前まで、若くして命を失うことは常にありえることだったのです。「国民病」といわれるほどの猛威をふるった結核が完全に治る病気になったのは、最終的な特効薬であるリファンピシンが73年に使われるようになってからのことです。ただし、結核は”過去の病”とは決して言えないようです。現在も死亡順位の20位前後にあり、日本は先進国中では群を抜いて結核感染率の高い国です。咳が長引いて風邪だと思っていたら、実は結核だった、そして、知らぬ間に職場や学校、近隣の人に集団感染を引き起こしていたなどという事例が後を絶ちません。若い人は結核が猛威をふるった時代を知りませんので、免疫もなく、感染しやすいということがありますし、高齢者では、かつて感染し、免疫の力で抑え込んでいた結核が病気や老化に伴う免疫力の低下で再発することがあるようです。最先端の空気清浄・活力器【イオンシグマDR】【送料無料・消費税無料】医療のレベルをコンパクトに!結核菌やMRSAも溶かして殺菌最先端の空...
Mar 24, 2006
-

【47夜】『魯山人書論』 北大路魯山人・平野雅章編
【47夜】『魯山人書論』 北大路魯山人・平野雅章編 1980 五月書房・1996 中公文庫まだ二桁代の千夜千冊です。日付は2000年5月10日。6年前になります。1年、2年くらいだと、ついこの間という気がしますが、6年となると、ちょっと時間がたったな、という感想を持ちます。20世紀から世紀をまたいで書き継がれたことになるのですね。6年前のそのころといえば、私はマウンテンバイクで東北の桜を楽しみつつ、旅をしたというのが、思い出です。弘前城の桜は見事でしたし、国道7号の桜並木も陶然とするような美しさでした。北大路魯山人、「これは日本の数寄文化をめぐる一種の踏み絵のようなものである」と松岡正剛はいっています。私などは魯山人が漫画『美味しんぼ』の海原雄山のモデルらしいと聞いている程度で、彼については何も知りません。まあ、食べ物がおいしいかどうかは、まず食べる人の身体の状態が第一、と思っているような人間なので、美食的視点は全く持ち合わせていないのです。食べ物は基本的に身体を養うためのものであって、うまいかまずいかは、食べる人の空腹感に左右されます。おながかが一杯のとき、病気で体調が悪いとき、いくら一流料亭の料理人が包丁を握ったと言われたところで、食べられるものではありません。これまでの人生を振り返って、心の底から「うまいっ!」と感じたのは身体の状態と食べ物がぴたっと寄り添う関係になったときだけです。それはお料理をされた人の責任ではなく、純粋にそのときの「めぐり合わせ」のたまものだということです。魯山人は自分の料理を盛る食器を作るために陶芸を始めたということです。低級な食器に甘んじているものはそれだけの料理しか作れず、そんな料理で育った人間はそれだけの人間にしかなりえない、と彼は言うのですが、凄いことを言うものだなと思います。プロの料理人、陶芸家としては瞠目すべき意見なのかもしれませんが、美食と縁のない私のような人間は「そうですかねぇ」と疑問を持たざるをえません。彼が傍若無人、傲岸不遜といわれる人柄であったことは有名です。天才の中には、人格がかなりゆがんでいて、通常のつきあいがなかなか難しい人があります。彼も多分にそういう人だったのでしょう。これで何もなければただの偏屈オヤジですが、数寄文化の中に「魯山人」というブランドを残したのですから、生身の彼の姿が遠いものになるにしたがって、落ち着くところへ落ち着きそうです。「ぼくは“事実”というものを信用していない。しょせんはすべては“編集的事実”であ るとおもっているからだ」と松岡正剛は言います。歴史的事実といわれているものはすべてこういうものでしょう。それを目撃した、体験した人であっても、その人の数だけその事実の編集はあるわけで、魯山人はそういうことが起こりやすい人であったといえそうです。北大路魯山人は、1883年3月23日、京都で上加茂神社の社家に生まれます。6歳の時に竹屋町の木版師・福田武造の養子となり、尋常小学校卒業後、丁稚奉公にでます。画家を志しますがかなえられず独学を決意。ここから先の年譜を見ると、生涯に5度結婚離婚を繰り返し、それだけでも大変な人物だったんだろうな、と納得します。【北大路魯山人】 織部 紅葉文台付皿
Mar 23, 2006
-

【427夜】『民藝四十年』 柳宗悦
【427夜】『民藝四十年』 柳宗悦 1958 宝文館・1984 岩波文庫「民藝」という言葉が柳宗悦たちによって1920年代に生み出された造語だと知って、驚きました。たとえばGoogleで「民芸」を検索するとトップには「日本民藝館」、その次には劇団民藝があがり、その後は各地の民芸館と民芸店がずらっと並びます。考案者の柳は「民藝」に登録商標はつけなかったのだな、と妙なことを考えました。民芸は民衆的工芸の略語です。民衆が日常つかう実用品をさし、家具調度、衣服、食器、文房具などがふくまれます。それまでの工芸品というと、王侯貴族やお金持ちのために作られるものだった(今もそうかもしれませんが)のでしょう。また、こうした特権階級向けの工芸品は、ひとりの芸術家が自己の作品として制作しますが、民芸は無名の工人の集団分業作業によって多量に生産され廉価で売られたものです。ただ、大量生産とはいっても近現代の工業的大量生産品とは異なり、基本的には大規模な機械は使わない手づくりのものという特徴があります。柳宗悦が発見した当時の民芸は、青森県津軽の刺し子こぎん、岩手県の南部鉄瓶、栃木県益子の山水土瓶、愛知県瀬戸の馬の目皿、京都大津の大津絵、兵庫県の丹波焼、大分県小鹿田の飛びかんな模様瓶、沖縄県の紅型や壺屋の抱瓶などに代表されるものです。田舎の片隅に埋もれていたものが多く、『丹波焼の蒐集』の中で、柳は「此上ない茶器ともいえるその角鉢は、見出された時は百姓家の鶏の餌入であった」と書いています。「こんな力は雑器にこそ、残りなく示現されるのであって、茶趣味の狙いなどを、振りむきもせぬ品なのである。だからこそ本来の「茶」の面目に満ち満ちているといってよい。前にも述べたが丹波の真の茶器は雑器の中にこそ活きているのであって、狙った茶器などには住んでおらぬ」と柳は民芸の生活雑器の無造作の魅力、意図せぬ中にこそある美を書いています。それらの品はずっと前からそこにあったのですが、柳をはじめとする都会で西欧近代のエリート教育を受けた人たちの目があって初めて発見されたものです。丹波の農家のおじさんにその目はなかったし、そんなことを言い出しても誰も耳をかさなかっただろう、と思うと、異質なものの偶然の出会いというのは、驚くべき力を秘めている、と感じます。これらの工芸品が「発見」されたことにより、民芸品は今や博物館で見るもの、あるいは骨董品として購入するもの、大量のコピーがみやげ物店に並ぶものという存在になり、無名の工人集団が作った生活雑器という姿は失いました。見出された瞬間から「無名」ではなくなるわけですから、皮肉といえば、皮肉なことではあります。柳宗悦は、1889年3月21日、海軍少将で測量技術者の楢悦を父に、柔道家嘉納治五郎の姉の勝子を母に、その三男として東京で生まれました。学習院高等科在学中に志賀直哉、武者小路実篤らの同窓生と雑誌「白樺」を創刊。そのころ来日していたバーナード・リーチの影響でウィリアム・ブレークに心酔します。13年、東京帝国大学哲学科を卒業。15~16年の朝鮮旅行をきっかけに朝鮮工芸への関心を深め、これがのちの民芸運動につながっていきます。仙台箪笥(仙台民芸埋木シリーズ)部屋箪笥 UB-50S「楽天シニア市場」
Mar 21, 2006
-
【789夜】『経済学・哲学草稿』 カール・マルクス
【789夜】『経済学・哲学草稿』 Okonomisch-philosophische Manuskripte 1844 カール・マルクス Karl Heinrich Marx 城塚登・田中吉六 訳マルクス主義というのは、最後の国家レベルでの宗教だったのかもしれないな、と思います。「宗教は民衆の阿片だ」とマルクスはいいましたが、共産主義の夢がしばらくの間はそれに変わっていた、とでも言えるでしょうか。今も原理主義やカルトといった宗教的麻薬はまだ世界にあるとはいえ、単一の教義を国家が信じ、それをあからさまに人々に強制しようという世界は過去のものになりつつあります。50年代後半から60年代にかけての時代について書かれた文章を今読むと、あのころは、共産主義が光り輝いていた時代だったのだな、と感じます。789夜の中でも松岡正剛が早稲田で革マル派の“組織”に入らないかと誘われている場面が出てきますが、安保闘争などにからんで学生運動華やかなりし頃だったのです。搾取する資本家と搾取される労働者という図式、金持ちを打倒して労働者が主権を握るという考え方が説得力を持っていました。マルクスは『共産党宣言』の中で、「万国のプロレタリアート(労働者)よ団結せよ」と呼びかけました。マルクスとエンゲルスがえがいた社会主義像は、労働力が商品ではなくなり、労働者は同時に生産手段の共同所有者となり、共有する生産手段に自分たちの集団的労働を直接充用して生産を営む姿です。資本が廃絶され、資本主義のように資本を増殖するために労働するのではなく、各人は能力に応じて働くことが原則になります。剰余価値の生産を目的としておこなわれる人間による人間の搾取がなくなり、労働の成果は生産手段の共同所有者である勤労者に帰属します。生産は、資本主義社会におけるような無政府的、非組織的な生産ではなく、計画的、組織的におこなわれるようになる、というものです。マルクスの理想は素晴らしいですが、しょせんは夢物語だな、と今なら誰もが思うでしょう。「能力に応じて働く」は向上ではなく堕落をもたらし、集団にぶら下がる人間が増大して、社会主義国家の生産性や技術革新は絶望的なほど遅れました。こうした「みんなでみんなの幸せのために団結していこう」という考え方や働き方は、最終的には矛盾が噴出して空中分解してしまいます。その後、資本主義国家でも出現した小規模なコミューンでも永続しているものはまずありません。マルクス主義を取り入れたロシア革命は、マルクスが資本主義社会から共産主義社会への革命的転化過渡期として便宜上認めた「プロレタリアートの独裁」を恒常的なものとし、国家権力を肥大化させてしまいます。その結果、ソビエト型社会主義国家(20世紀の社会主義国家はみんなこの形です)では、プロレタリアートのユートピアが出現するどころか、全体主義の恐怖政治が支配するようになってしまったのです。人間は助け合うこともできますが、その前に自分で自分の希望、意志、所有、選択が認められる余地があることを納得したい生き物なのです。それが納得できれば進んでそれを誰かに譲り渡すこともあるでしょう。しかし、最初から何かを強制され、籠の中でエサをもらうような精神状態におかれたら、堕落し、窒息してしまう存在なのです。1818年5月5日、マルクスはユダヤ人弁護士の子としてドイツのトリールに生まれましたが、プロイセン政府と対立し、最終的にロンドンで亡命生活をおくります。1883年3月14日、彼がロンドンで死去したとき、原稿・手紙・ノート・蔵書などからなる膨大な草稿類がのこされ、『資本論』は未完でした。エンゲルスの手で『資本論』は刊行され、その後、第二次世界大戦、冷戦の終結など紆余曲折を経ながら、現在もマルクスとエンゲルスの著作を完全な形で刊行しようという事業は続けられているそうです。マルクス=エンゲルス全集CDーROM版
Mar 14, 2006
-

【765夜】『百年の孤独』 ガルシア・マルケス
【765夜】『百年の孤独』 Cien Anos de Soledad 1967 ガルシア・マルケス Gabriel Garcia Marquez 鼓直 訳 1972・1999 新潮社ノーベル文学賞受賞作なのですが、読んでいません。アウトラインを読んで、はぁ、読んでみるべきなのかな、と思うような作品です。フォークナーに影響を受けて作品世界が作られたようなのですが、フォークナーもなぁ…という感じでなんとも心もとないというべきか。ストーリーをそこから読み取って、その構造に沿って読んでいこうとする読み方では、恐らくフォークナーをはじめ、ジョイス、カフカといったガルシア・マルケスが影響を受けた作家たちの作品は理解できないのだろう、と思います。ストーリーにはあらかじめ決められたいくつかの型があり、その鋳型にさまざまな素材を流し込んで次のお話ができあがっていきます。多分、原型は聖書や神話、説話物語などにあるのだと思います。というよりは、人間の認知や理解、伝達、コミュニケーションといったものの背後にこうした「物語的」なものは欠かせないものとして存在し、それにフィットした形で発達したのではないでしょうか。読みやすい小説を読むとき、この型を使って読んでいることがわかります。映画やサスペンス小説の広告によく、「予想もしない展開」とか「意表をつくプロット」なんていう言葉が出てきますが、真実、予想できないような展開だったら、読者はあきれかえるか、怒りだすでしょう。ルールはきっちり決まっていて、こういう小説は、スポーツの展開に似ています。抑えのエースが出てきたら、打たれるか、抑えるか、それだけです。そこで彼がいきなりダンスを始めるなんてことにはなりません。ただ、魔術的リアリズムというのは、野球だと思っていたものがいつのまにか相撲になったり、フィギュアスケートになったりして、うねるように不思議な豊穣な世界を描き出していく手法のような気がします。その自在で荒唐無稽な世界の描き方はいわゆるストーリー・テラーの語り方とは明らかに違います。ガルシア・マルケスは17歳の頃から『百年の孤独』の構想をあたためており、その叙述方法を探しあぐねていたといいます。1965年のある日アカプルコ行きの車の中で幼い頃に耳にした祖母の語り口を思いだすことでついに突破口を見出し、18ヶ月間タイプライターを叩きつづけて完成しました。『百年の孤独』はスペイン語圏で「まるでソーセージ並によく売れた」と言われ、マルケスは貧乏生活から抜け出します。マルケスは1928年3月6日、コロンビアのカリブ海沿岸にある人口2000人ほどの寒村アラカタカで生まれ、事情により両親と離別し、祖父母の元に預けられて幼年期は三人の叔母と退役軍人の祖父ニコラス・コルテス、迷信や言い伝え、噂好きの祖母ランキリーナ・イグアラン・コルテスと過ごしました。この祖父母のもとで過ごした日々は彼の作品に大きな影響を与えています。百年の孤独
Mar 6, 2006
-

【197夜】『魔女の1ダース』 米原万里
【197夜】『魔女の1ダース』 米原万里 1996 読売新聞社・2000 新潮文庫家でとっていた新聞の日曜版に米原さんのエッセイが連載されていました。今でも記憶に残っているエッセイがいくつかあります。彼女は小学生のとき、お父さんの仕事の関係でチェコスロバキアに行き、そこで何年か過ごしています。そして、数年ぶりに帰国するのですが、当時、吉永小百合が大変人気のあった時代でした。今ならインターネットで「日本では何が流行しているか」をほぼ同時に知ることができますが、当時のチェコスロバキアでは、日本の印刷物さえまともに手に入らなかったのではないでしょうか。日本の芸能事情など全く知らぬ状況で帰国した中学生くらいの彼女が、最初に吉永小百合の顔を見て感じたのは「こんな醜女が人気女優?」ということだったそうです。彼女はチェコスロバキアで過ごすうち、チェコスロバキア人の美的感覚がすっかりしみついていたと述懐しています。西洋人がアジア系に感じる美人の基準とアジア人自身がアジア人を見て感じる基準はしばしば異なっています。このときのエッセイかどうかは忘れましたが、日本の人気女優何人かの写真をオーストラリア人に見せ、誰が一番美しいと思うか、と質問したところ、一番多く選ばれたのが「泉ピン子」だったという話を聞いたことがあります。これとは逆にアジアでの人気が本国よりも高い西洋の女優もきっといることでしょう。同じ日本人でも時代とともに美的感覚は変化し、平安時代のおたふくのような顔はとても今の感覚からは「美人」とは言えません。江戸時代以前は、既婚女性は眉を剃り、お歯黒をつけていました。時代劇でいくら時代考証を正確にしようと考えても、実際にやってみたら不気味で、現代の視聴者からは見るに耐えないものになります。米原さん自身も帰国して数ヶ月たったころには吉永小百合への違和感はなくなっていたというのですから、人の「美」の感覚がいかに文化に影響されるか、の好例としてあげられていたのだと思います。通訳という双方の文化をつなぐ仕事であるだけに日々そういう体験ばかり、といえるのでしょう。さて、ロシアの話ですが、彼女はソ連崩壊以前からロシア語通訳として、アンドロポフゴルバチョフ、エリツィンらとともに仕事をしています。彼らは肉食で、魚を食べる習慣は当時ほとんどなかったようです。日本食に関する彼らのエピソードが語られていました。アンドロポフは魚は煮たものも焼いたものもすべてダメでした。ゴルバチョフは刺身はさすがにダメでしたが、火をとおしたものは食べたということです。一方、エリツィンは煮魚、焼き魚はいうに及ばず、刺身だろうがなんだろうが、出たものはすべてぺろりとたいらげたということです。なんとなく政治姿勢にも通じるようなこの食事の内容がとても印象に残っています。すでにソビエト連邦の崩壊から15年近くがたとうとしています。ペレストロイカを進めた最後の共産党書記長にして最後の大統領ミハイル・ゴルバチョフは、1931年3月2日、ロシアのスターブロポリ地方のプリボルノエでコルホーズの農民の子として生まれています。冷戦終結の功績により90年にノーベル平和賞を受賞。ただ、ソ連解体のきっかけを作った人物、として旧ソ連邦内ではさっぱり人気がありません。岩手県北上トロイカボルシチ
Mar 2, 2006
-

【87夜】『日本の歴史をよみなおす』正続 網野善彦
【87夜】『日本の歴史をよみなおす』正続 網野善彦 1991 ちくまプリマーブックス 筑摩書房千夜千冊を読んで、その本を「読みたい!」と思うことは、私の場合残念ながらあまりありません。松岡正剛のように広範な興味のアンテナを持っていませんし、図書館で借りてきて読んでも、結局著者が何をいいたいのかよくわからず、途中で投げ出してしまうものもあります。しかし、網野善彦の本は久しぶりに「読んでみたい」と思えました。網野善彦は、従来の稲作を基盤とした島国日本の歴史像に対し、非農業民のあり方に注目して海を通じて周辺諸地域にも視点をもつ列島日本の地域性豊かな歴史観を提唱しました。「これまで中世の社会経済の構造や王権や宗教の構造に関心がなかった人々がしきりに読むようになった」と松岡は言っていますが、こういう従来の固定化したものの見方を覆すような話には誰もがわくわくするものです。中世社会の移動や流通の自由や平等を論じた最初の著作『無縁・公界・楽』を書いたきっかけは、彼が高校教師だった時代に教え子から受けた次のふたつの質問だといいます。それは、力が弱くなり滅びそうになった天皇がなぜ滅びなかったのか、ということと、なぜ平安末・鎌倉時代にのみ突出してすぐれた宗教家が輩出したのかということです。江戸時代、妻が離婚の決意を貫く手段として、縁切寺への駆込みがありました。幕府はこうした寺の機能を厳しく統制しようとしましたが、時代を遡れば縁切寺同様の「自由」な場、アジールの一形態と見なされる場が広範に存在したのです。そこは逆説的な「自由」の場であり、社会と縁を切った人々の集まる権力の隙間でした。こうした「無縁」の思想は西洋諸民族にも共通するものであり、原始・太古の本源的な「自由」に根を持ちます。世俗の権力は常にこの「無縁」をおさえこみ、囲いこもうとしてきました。「有主」「有縁」の世界は「無縁」の原理をとりこみにかかり、完全に管理された「無縁」の衰退・終末の段階に入っていきます。しかし、「無縁」の原理は強靭かつ永遠であり、日本の「無縁」「無所有」の思想は、現代の「無縁」の人々によって必ず創造されると網野善彦は述べています。87夜執筆は2000年7月7日。網野善彦はそれから3年半後の2004年2月27日に亡くなっています。〈岩波講座〉天皇と王権を考える(第1巻)
Feb 27, 2006
-

【278夜】『回想録』テネシー・ウイリアムズ
【278夜】『回想録』 Memoirs 1975 テネシー・ウイリアムズ Tennessee Williams 鳴海四郎 訳 1979 白水社テネシー・ウイリアムズは1983年2月25日ニューヨークのホテルでボトル・キャップを喉に詰まらせ窒息死しました。72歳でした。この死は、彼の兄のデーキンほか数人は殺人だと信じているそうです。不自然な死に方であるのは確かです。『回想録』ではゲイであることを告白しており、30年前という時代、その名声を考えれば衝撃的な著作といっていいでしょう。ゲイへの風当たりは今よりはるかに強かったでしょうし、実際、79年の1月にフロリダ州キーウェストで5人の十代の少年によって殴られるというゲイバッシングを受けています。そんな記憶も覚めやらぬ中での突然死だったため、「殺人」と思った人がいてもおかしくはなかったのでしょう。『ガラスの動物園』『欲望という名の電車』『熱いトタン屋根の猫』という彼の代表作は舞台、映画いずれにおいても私はまだ観たことはありません。三作とも彼が生まれ育ったアメリカ南部が舞台になっており、キャラクターのほとんどは彼自身と家族をモデルにしています。彼が育った家庭自身にさまざまな問題があり、姉のローズは精神を病んで生涯のほとんどを精神病院でおくっています。「熱いトタン屋根の猫」とは”逃げ場も無くジリジリ焼かれる苦しい状況”を意味しています。これら三作ともに、夫婦や親子、兄弟といった普遍的な人間関係の中でおこる軋轢を描いており、出口のないげんなりするような話であることは、あらすじを読むだけでもよくわかります。彼自身がバイセクシャルであり、精神病の影に常につきまとわれていたということがわかると、これらの業火にじんわりと焼かれるようなお話も彼の必然性から生み出されたものだと思いました。ある種の芸術はこういう部分から噴出するものなのだろうな、と。その人の「負」の部分から絢爛たる花が咲くとでもいいましょうか。すべてに恵まれ、満ち足りていたとしたら、何かを創作する必要なんてない、と思えますから。テネシー・ウィリアムズ フィルム・コレクション〈初回限定生産〉
Feb 25, 2006
-

【927夜】『狂雲集』一休宗純
【927夜】『狂雲集』一休宗純 1976 現代思潮社また少し間隔が開いてしまいました。日々のエクササイズと同じで、続けていないと動きだすまでに少々時間がかかります。3度目の師範代をつとめさせていただいたISIS編集学校の12破が先々週(3月12日)で終わり、「感門之盟」も先週の日曜(3月19日)に終わって、一息ついてまたこちらに帰ってきました。どうやら、ようやく「千夜千冊」本体の出版も目鼻がついてきたようで、2006年5月刊行との字が躍っています。松岡正剛自身、最後の仕上げに余念がないところなのでしょう。しばらく目を離していたら、1128夜まで進んでいました。ひぇ~。さて、一休です。風狂の禅僧といわれるだけあって、とんでもない人だったようです。927夜の文章を読んでみても、なんだかよくわかりません。抽象絵画を前にして何がいいのかよくわからずに途方にくれている感じに近いでしょうか。凄い凄いと人々が言うから、凄いのだろうが、自分にはよくわからないなぁ…、というのが正直なところ。ISIS編集学校の師範・師範代には松岡正剛校長から直接レクチャーを受ける「伝習座」という場があります。もちろん全部校長が話すというわけではなく、そのうちの一部の時間なのですが、ナマで松岡正剛ワールドから発せられる話を聞くことができます。そのときによって、話される内容はさまざまなのですが、「千夜千冊」からもうかがいしれるように、まあ、広大、膨大、甚大なバックグラウンドから湧くように出てくるお話ですから、こちらの小さな知識の器では掬い上げられる量がしれています。あるとき、校長に「すみません。半分もわからないのですが…」と正直に話したところ、「わからなくてもいいんだよ」とあっさり言われてしまいました。わからなくてもいいなりに、一休の話も読んで、なんとなく「はあ」で終わるのも今はよかろうか、と思います。カラスが「カー」と鳴いてどこで仏性に合間見えるかもしれません。まずは、水上勉の『一休』を読むことから始めなくては。一休は、室町時代の臨済宗の禅僧。一休は道号で、諱(いみな)は宗純、狂雲子、夢閨とも号しました。1394年2月1日 (旧暦:応永元年1月1日)京都で誕生。父は後小松天皇、母は天皇の側女といわれています。【一休さんの大丈夫だ石】にぎっていると不思議と落ち着く・・・疲れた心を一休さんが癒してくれます。
Feb 1, 2006
-

【363夜】『マルタの鷹』 ダシール・ハメット
【363夜】『マルタの鷹』 The Maltese Falcon 1930 ダシール・ハメット Dashiell Hammett 村上啓夫 訳 1961 創元推理文庫ハードボイルドの文体は私の好みにあっています。ダシール・ハメットは読んでいませんが、ヘミングウェイが好きでしたし、レイモンド・チャンドラーは2,3冊読んだ記憶があります。余計な飾りがないものが、道具でも文章でもなんでも好きなのです。簡潔、シンプル、機能性、それらが一番大事です。そんなことを考えながら、Googleで「ハードボイルド」を検索したら、ハードボイルド度診断なるものを見つけ、さっそくやってみました。結果:あなたのハードボイル度は 51.75% です。 リュー・アーチャー タイプ あなたは理想的なハードボイルド者です。ときに「融通が効かない」とか「偏屈だ」 と非難されることもありますが問題にはならない程度。 普段は他人と調子を合わせて如才なく振る舞う事が出来ますが、いざとなったら 頑として譲らない強さを持っています。ただし同じ人間と長く付き合うのは苦手で、 気の置けない友人は少なく結婚生活にも向きません。今のうちから貯金に励み、 老後に備えておく事をお勧めします。リュー・アーチャーはロス・マクドナルドの作り上げた探偵で『動く標的』に登場します。レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーロウ、ダシール・ハメットのサム・スペードとともにハードボイルド御三家の一角を担う探偵です。診断結果は、当たらずといえども遠からず、というところでしょうか。貯金はしておくことにします。しかし、リュー・アーチャーが貯金通帳を眺めているというのは、あまりハードボイルド的ではない、と思いますが。サム・スペードについて、ハメットは「ドリームマン」だと言っています。探偵社につとめていたハメットは多くの探偵を見ていますが、特にモデルはないそうです。しいていえば、誰もがそうなりたいと思っていた男、時にうぬぼれてそうでありえたと思いこんでいた男として、ドリームマンなのです。松岡はスペードの登場する描写をあげて、「ここには『アーキタイプ』そのものがタバコを吸っている」と書いています。ところで、「ドリームウーマン」というのは、あるのでしょうか。ダシール・ハメットは1894年1月10日、メリーランド州セント・メリーズ郡に生まれました。13歳で学校をやめ、アメリカ全土を働きながら放浪。このころの経験がハメットをのちにマルクス主義者にしたのかもしれません。肺結核を患ったのをきっかけに小説を書き始めたということです。ハンフリー・ボガード演じる私立探偵サム・スペード『マルタの鷹』
Jan 10, 2006
-

【636夜】『自然学の提唱』 今西錦司
【636夜】『自然学の提唱』 今西錦司 1984・1986 講談社学術文庫今西錦司は1902年1月6日、京都に生まれました。今西自然学に至る彼の歩みは、京都帝国大学農学部で昆虫学を修めたところから始まります。今西進化論の発端となった「すみわけ理論」が、加茂川のヒラタカゲロウを観察して得たというのは、出発点の昆虫学の知識によるものかもしれません。「今西錦司は生涯を賭けて進化の謎に挑戦しつづけた人だった。一言でいえば、ダーウィンの進化論に断固として立ち向かった人である」と、松岡正剛は述べています。進化論といっても、その中にはさまざまな考え方があります。何が進化を進める原動力になったのか、についてとらえ方に違いがあるのです。ダーウィンは自然選択(自然淘汰)説をとなえました。現代もっとも一般的とされ、ダーウィンの自然選択説を受け継いでいるものが総合説(ネオ・ダーウィニズム)です。自然選択説の場合、自然選択の単位が個体であり、生存競争を通じて適応的な個体が生きのこることによって進化がおこると考えるのに対し、総合説では、自然選択の単位は遺伝子であり、適応的な遺伝子が集団中にふえることによって進化がおこると考えるところに違いがあります。総合説としてもっともよく知られているのが、リチャード・ドーキンスがとなえた利己的遺伝子説でしょう。ドーキンスは、遺伝子こそが主役であり、生物個体は遺伝子が増殖するために利用する乗り物、すなわち生存機械にすぎないとさえ極論しています。今西進化論は、数ある進化論の中で、「自然選択ないしは生存競争を否定し、集団のすべての個体が一斉に変化するという主張」として、ネオ・ラマルキズムや定向進化説などと同じ範疇に入れられることが多いようです。今西進化論について、636夜では、「むしろ運のよいものが生き残ったと考えたほうがいい。極端にいえば、そう考えた。『運がいい』とはまことに非科学的な言葉だが、今西錦司はそれを全力をかけて解明したかった。その『運』をこそ自然界が襞の奥にひそませているのではないかと考えたのである」と松岡は言っています。進化論について説明した事典にも、科学的に検証することが困難、と記述されていました。いまの科学で「運」を証明することは困難でしょう。「運」と呼べる何かがこの世にあることは直感的にはわかるのですが、それは「証明」という論理的なまな板には、なかなかのってくれないもののように思えます。ただ、松岡が「自然は最適者だけしか生き残らせようなどとはしていないというのが、今西錦司の自然研究から生まれてきた結論だったのだ。激しくも厳しい自然のなかにひそむ『抱擁の構造』に、むしろ進化の原理の萌芽を見たのである」といっているように、自然全体を眺め渡したとき、今西進化論にはしっくりくるものを感じます。20世紀の科学はどんどん専門分化し、それぞれの科学者がその狭い専門分野の中に閉じこもって細く深い穴をどんどん掘り下げていく、という方向に進みました。しかし、今西錦司はそうした視野狭窄を戒め、もっと大きな目で自然そのものを眺めることの必要性を説いたのです。木を見て森を見ず、どころか、誰もが葉脈しか見てないような状態では、「自然」という大きな森について論じることなどできません。今西錦司
Jan 6, 2006
-

【465夜】『ライ麦畑でつかまえて』 J.D.サリンジャー
【465夜】『ライ麦畑でつかまえて』 The Catcher in the Rye 1951 J.D.サリンジャー Jerome David Salinger 野崎孝訳 1972 白水社この作品を読んではいません。おそらくこの先も読まないだろうと思う本です。だいいち、「物語や筋書は、ない、といってよい」ような小説を読むなんて考えただけで退屈してしまうからです。村上春樹はこの作品から大きな影響を受け、彼自身があらたに翻訳して『キャッチャー・イン・ザ・ライ』として出版しています。残念ながら村上春樹の作品も私は苦手ですので、それにも興味がわかないままでした。大勢の人がとてもいいと褒める作品なので、読んではみたが何がいいのかさっぱり自分には理解できないという本がときどきあります。村上春樹の小説は私にとってその一例です。いくつか読んで、「あー、これはアカン」と感じました。一番最近に読んだのは、『ねじまき鳥クロニクル』でしたが、これも長いわりに何が言いたいのかよくわからない小説という印象でした。物語や筋書きを明確にしないところがサリンジャー的なのだとしたら、やっぱりサリンジャーには食指が動かないのです。60年代のアメリカの若者の間でバイブルになりかかった本だということですが、レーガンやジョン・レノンを殺そうとした青年たちも何かひかれるものがあったようです。ホールデン・コールフィールドは、大人の世界のインチキをみぬく、反抗的で混乱した若者の原型として、60年代アメリカの若者の一種のアイドルになりました。60年代の若者といえば日本で言うならば団塊の世代、全共闘世代です。それからすでに40年、定年も間近になった団塊の世代は今、ホールデン・コールフィールドを見て、どのような感想をもつでしょうか。誰もが若いときがあり、ただ、誰もが若いままではいられない、というところに人間社会の悲喜劇があるかな、と思います。60年代はカウンターカルチャー全盛の時代でした。その一因は、各国で戦後生まれのベビーブーマー人口が増え、国全体が若かったということにもあります。サリンジャーは1965年以降は作品を発表することなく、隠遁者のような生活を送っています。彼は1919年1月1日生まれですから、『ライ麦畑でつかまえて』は彼が30歳のときの作品です。それ以後、数編の「グラース家サーガ」を書いたあと、45歳で筆を折り、作家として伝説の存在になることを選びました。彼が80歳を超えるまで書き続けていたとしたら、どんな作品が生まれていたでしょうか。サロン・ドット・コム現代英語作家ガイド
Jan 1, 2006
-

【463夜】『ディートリッヒ自伝』 マレーネ・ディートリッヒ
【463夜】『ディートリッヒ自伝』 Marlene Dietrich 1987 マレーネ・ディートリッヒ Marlene Dietrich 石井栄子・伊藤容子・中島弘子訳 1990 未来社マレーネ・ディートリッヒは1901年12月27日、ベルリンで中流貴族の家庭に生まれました。18歳で国立ベルリン音楽学校に入学し、バイオリニストを目指しますが、手首を痛めて断念。その後、演劇学校を経て21歳で初めての映画に出演し、23歳で結婚して、娘マリアを出産しています。ここまでは普通の女性のクロニクルにすぎませんが、彼女がスタンバーグ監督に見出され『嘆きの天使』のヒロインに抜擢されたところから運命が大きく展開していきます。人間の一生は面白いものだな、と思います。こういう決定的な出会いがその人を想像すらしていなかった場所へ連れて行くからです。「ディートリッヒが、世界を堪能させるマレーネ・ディートリッヒになったのは、100パーセント、スタンバーグの魔法によっている」と松岡が書いているように、無名のドイツ人女優はこれをきっかけに歴史に残る大スターへの道をかけあがっていくことになったからです。ディートリッヒを発掘し、「そのフラジャイルな腺病質と折り目正しさに賭け」ることによって、スタンバーグは彼のイメージの中にあった映像を生身の人間としてスクリーンの中で演じてくれる存在としてのマレーネ・ディートリッヒに磨きをかけていったのです。スタンバーグの眼力の勝利だといえますし、そこを信頼してついていったディートリッヒも見事といえます。何だかチャンピオンと名コーチの逸話のようでもあります。自伝には彼女の同時代の映画人たちも多数登場し、松岡は、「なるほどと思わせる寸評も少なくない。ともかく、よく人物を見抜いていた」と評しています。ヘミングウェイとのエピソードは意外ですが、文章指導まで受け、ヘミングウェイが「冷蔵庫の霜をとるように書きなさい」と言っていたというのは、いかにもと思わせます。ベルリン生まれでドイツの魂を常に背骨としてもっていたということが、ディートリッヒを逆に第二次世界大戦中の対ナチスの運動に結びつけていきます。「私は祖国ドイツを愛しいています。しかし、独裁者の支配する国は大嫌いです」、と彼女は帰国をうながすヒトラーに告げたといわれています。彼女がドイツ語で歌う『リリー・マルレーン』は、またたくまにヨーロッパ戦線で連合、枢軸国軍双方の兵士の間に広がっていきます。やはり運命の女神に選ばれた女性だったのです。モロッコ(DVD)MOROCCO(1930)
Dec 27, 2005
-

【280夜】『青春の闇・開高健』 向井敏
【280夜】『青春の闇・開高健』 向井敏 1992・1999 文芸春秋開高健が食道がんの手術後、肺炎を併発して亡くなったのは1989年12月9日でした。1930年12月30日生まれで、59歳の誕生日が目前でした。向井は大阪高校で開高と出会い、そのまま彼の死までつきあいが続いています。「本書の泡立つ哀切に惹かれて、つい書いてしまった」と松岡正剛が述べているように、本書は向井敏の開高健への鎮魂歌です。死の2年後に出版されていますから、まだその衝撃が心の内に大きな波をたてていたときに描かれたものと思われます。鎮魂歌というのは、なかなか書けそうで書けないものではないでしょうか。いや、書けるのかもしれませんが、本人たちを直接知らない人間が読んでもこちらに響いてくるものを持っている鎮魂歌は、意外に少ないような気がします。感情に溺れてしまってそれを伝えきれなくなってしまうからです。「鎮魂歌をこのように書けるのはやはり向井の独自の語り口である」と松岡が書いていることから、本書の雰囲気がうかがえます。1948年の夏、といえば、まだ戦後の混乱期です。「目の前で鉄棒の大車輪してみせ、そのくせ、はにかんで立ち去った」のが開高健でした。そのまま最後も鉄棒から降りて人生から立ち去ったように向井には思えたのかもしれません。ナイフで削いだように頬がこけた、痩せぎすの背の高い無口な少年は、その後、寿屋(現在のサントリー)に入り、コピーライターとして手腕を発揮します。そして、57年、26歳のときに『裸の王様』で芥川賞を受賞して作家活動に入るのです。後年、釣師、グルメ作家としても知られるようになり、私には丸々としたイメージしかありません。【DVD】オーパ! 開高 健
Dec 9, 2005
-

【405夜】『一年有半・続一年有半』 中江兆民
【405夜】『一年有半・続一年有半』 中江兆民 1995 岩波文庫405夜は中江兆民をとりあげつつ、三分の一ほどは鷲見房子さんへの追悼になっています。文楽のことなら何でも知っているという彼女から、「ねえ、兆民の越路太夫の聞き方はどういうものだったんでしょうね」とたずねられたところから、松岡の中江兆民像が一挙に改新されていったというのです。中江兆民は明治期の自由民権思想家、1847年12月8日(旧暦:弘化4年11月1日)土佐藩の足軽の子として高知に生まれました。本名は篤介で、兆民は号です。65年に藩の留学生として長崎へ行き外国語の習得につとめます。ここで坂本龍馬を知り、ひそかに師と仰ぎ、開明的思想を吸収しました。405夜ではこうした兆民の政治思想家としての一面よりも文楽狂の中江兆民が前面に押し出されています。『一年有半・続一年有半』という題名は、兆民が喉頭がんで余命一年有半とされたところからきているのですが、そこで彼が政治と哲学と義太夫を一緒に語るという芸当をやってのけていることに松岡は感嘆しています。ただ、兆民が越路太夫をどのように聞いたかについては、残された記録を見るしかなく、松岡は「われわれはそのことを思いつづけるしかないようなのである」と書いています。生身の人間がその場で演じるものを見るライブの芸能やスポーツでは、その感動はその場のものでしかなく、後の人間に伝えることはできません。さまざまな媒体でその記録が残されるようになった今でも、やはり、そのとき、その場で、同じ時間空間を共有しながら味わう感動とは、かなり質が変わってしまうことは仕方がないでしょう。だからこそのライブ、といえるのです。兆民の三十一人判釈(同時代偉人三十一選とでもいえばいいでしょうか)について、これを読解できる人間がいれば、明治文化がもたらした日本人が抱えた問題の本質の一端がわかってくるのだろうが、残念ながら、それはまったくいない、と松岡はいっています。無理もないだろうと思います。物真似名人、三味線名人、落語家、歌舞伎俳優、力士といった人たちの”凄さ”は録音も映像もない時代とあっては後世に伝えようもないからです。こういう人たちが残すのは名前と伝説のみです。たとえば稀代の天才ダンサーで、ことにジャンプがすばらしく、空中に止まって見えた、とさえいわれるニジンスキー、彼のジャンプを記録した映像は全く残っておらず、それがいっそう神話化に拍車をかけます。映像が残ることになってしまった現代の芸能者やスポーツ選手は、果たしてそれがよかったのかどうか、考えてみれば皮肉なことかもしれません。『江戸/東京芸能地図大鑑〈CD-ROM〉』
Dec 8, 2005
-

【20夜】『晶子曼陀羅』佐藤春夫
【20夜】『晶子曼陀羅』佐藤春夫 1955 講談社・1967 角川文庫 他松岡正剛は、与謝野晶子を高く評価しています。ISIS編集学校の師範・師範代を対象とした研修でも、何度か女性なら(女性ならずとも?)まず晶子を読みなさいと言われました。「生き方が根本からちがっている。根性があって、それが叙情の果てまでつながっている」と賛辞を惜しみません。松岡の晶子入門のお勧めは、『与謝野晶子訳・源氏物語』です。最初の現代語訳で、その後のどんな現代語訳をも凌駕している、とのこと。この作品は今、角川文庫クラシックスから全3巻で出ています。何年か前に中米のベリーズへ旅行したとき、これを持って行きました。海外旅行するときに日本の古典を携えていくようになったのはあれが最初かと記憶しています。ベリーズでは隆起珊瑚でできた沖の環礁へチャーターボートで出かけ、そこにテントを張ってキャンプしました。椰子の木と白い砂とラグーンのエメラルドの海。一日中シーカヤックに乗ったり、シュノーケリングをして遊び、その合間にあずまやの下に張ったハンモックに寝転んで、『源氏物語』を読みました。今や日本では経験できなくなった瓶入りのコカコーラを飲みながら。目の前でブラウンペリカンがダイブを繰り返し、魚をとっています。穏やかな波の音とカリブ海を吹いてくる海風…、そこで若き光源氏の王朝アバンチュールを昼寝半分に読みふけったのです。上巻は読み終わりましたが、さてその先はどうだったか。今も与謝野源氏というと、あのベリーズの珊瑚礁が目に浮かびます。もう一度読んでみるべきかな、と思い始めています。「今日の女性にとって与謝野晶子はさまざまな意味での"原点"にあたるはずである。これはまちがいがない」と松岡がいうほどの女性、この現代語訳を読めばその原点を考えるきっかけになりそうです。あのカリブの砂浜の上ではまだよくわからなかったもの、それを見つけたいと思います。与謝野晶子は1878年(明治11年)12月7日、大阪府堺市で老舗の和菓子屋「駿河屋」の三女として生まれました。堺女学校(現・大阪府立泉陽高等学校)に入学すると『源氏物語』などを読み始め古典に親しみます。20歳ごろより店番をしつつ和歌を投稿するようになり、1900年、歌人・与謝野鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表。翌年22歳で東京へ出て、処女歌集『みだれ髪』を刊行しました。与謝野寛晶子書簡集成(第4巻)
Dec 7, 2005
-

【673夜】『おとぎ話が神話になるとき』ジャック・ザイプス
【673夜】『おとぎ話が神話になるとき』 Fairy Tale as Myth,Myth as Fairy Tale 1994 ジャック・ザイプス Jack Zipes 吉田純子・阿部美春訳 1999 紀伊国屋書店673夜の中で「東京文化はディズニーランドでとっくにダメになっている。(中略)こんなことなら、みんなミッキーマウスになっちまえばいい(ぼくはミッキーマウスが大嫌いなのだ)」と、松岡正剛は書いています。ミッキーマウスについては何のうらみもありませんが、私もディズニーランドは好みにあいません。たった一度だけ、千葉に住んでいた友人に連れられていったことがあります。アトラクションのほとんどを経験しましたが、(12月の閑散としたシーズンだったため全く行列をつくる必要がなかったのです)まあ、二度来るところではないなと思いました。ジェットコースターやらウォータースライダーやら(アトラクションの正式な名前は忘れてしまいました)いろいろと乗ったのですが、結局、「遊ばせていただいている」場所にしかすぎません。自分から能動的に遊ぶ場所ではないということが、乗れば乗るほどはっきりし、ツマラナイと思ったのでした。夢や冒険や創造をディズニーランドから連想する人があるそうですが、それは言葉の意味を取り違えているとしか思えません。それらの言葉は自分自身で創意工夫し、自分の力で何かを成し遂げようとする人だけが手にするものです。アトラクションの椅子に座って与えられたお楽しみを消費するだけの人間は、決して手にすることのない幻想です。松岡は673夜の中で「ディズニーの呪い」について述べています。ペローやグリム自身がおとぎ話を”消毒”しなかったわけではないけれど、「ウォルト・ディズニーは、持ち前の正義感と右よりの思想とアメリカン・ドリーム主義をもって、まったく別の物語をつくってしまった」のであり、ディズニーのアニメ以後、『シンデレラ』や『白雪姫』はディズニーを通してしか、一般の子どもには届かなくなってしまっています。これは、物語がはらわたを抜かれ、切り身にされ、発砲スチロールのトレイにのせられてスーパーの店頭に並んだようなものです。血も匂いも何もなく、ぴかぴかときれいで美しいだけの物語です。なんとディズニーランドと似ていることでしょうか。ディズニーワールドでは人間が感じる感覚の細部までディズニー的管理が行き届いており、鳥の声さえ計算づくだといいます。あまたのテーマパークの中でディズニーランドがひとり勝ちしたのは、このあたりの周到なブランド構築にありそうです。ウォルト・ディズニーは1901年12月5日、シカゴで生まれました。22歳のとき、兄のロイといっしょにアニメーション映画の会社をつくり、28年にミッキーマウスが初登場する「蒸気船ウィリー」で大当たりをとりました。55年にカリフォルニアのアナハイムにディズニーランドをオープン。彼自身は66年になくなりますが、71年にフロリダ州オーランドにディズニーワールド、83年、東京ディズニーランド、92年、フランスにディズニーランド・パリがオープンしています。ディズニーファインアート 君も飛べるよ!(限定数:395) ピーターパン 【予約品】
Dec 5, 2005
-

【378夜】『化城の昭和史』寺内大吉
【378夜】『化城の昭和史』 寺内大吉 1988 毎日新聞社・中公文庫日本が太平洋戦争へと突き進んでいった思想的背景には田中智学がおこした日蓮主義の在家宗教教団「国柱会」の存在がありました。日蓮宗の開祖である日蓮は法華経にこそ釈迦の真実の教えが説かれ、それ以前のさまざまな経典は法華経を理解させるための方便にすぎないと主張して、法華経への絶対帰依を求めました。その日蓮の教えを国家主義とむすびつけたのが日蓮主義です。国柱会は1880年、蓮華会として始まり、立正安国会を経て、1914年、日蓮の「開目抄」にある「我日本の柱とならむ」にちなんで国柱会となりました。田中は、天皇と軍の最高幹部を法華経信者にすることによって、国家の法と仏教の法とが一致する王仏冥合を実現させようと考えていたようです。太平洋戦争に向かう歴史をそれだけで見ていると、「なぜあのように無謀なことを集団でやったのか」という気持ちをどうしても拭い去ることができません。米英の挑発があった、日本が日露戦争以来の戦勝で、足元が見えなくなっていた、など、いろいろな話をきき、どれもある程度の真実は含んでいるものと思います。この日蓮主義集団のことを読んで、脳裏をよぎったのは昨今のイスラム原理主義のテロ集団のことでした。日蓮主義には法華原理主義の性格があります。満州事変の発端となった柳条湖の鉄道爆破事件のシナリオを書いた石原莞爾、血盟団事件の首謀者井上日召ら激烈な日蓮主義者たちの姿が378夜でも描かれていますが、「団員たちは法華経を唱えてテロに向かった」の法華経の部分をコーランに変えれば、9.11の記述だとしても全く違和感がありません。原理主義とは、原典を絶対視し、それを文字どおりに信じて、原典に反する考え方を徹底して排除し、排撃しようとする宗教思想のことです。「日召はこれらのテロによって破壊が建設を生むと確信し、これを『順逆不二の法門』とよんだ」と松岡が書いているように、原理主義者は現実社会はいろいろなものが混じりあい清濁ごった煮の世界であることが許せない人たちです。しかも原典に反するものは「神仏」に反すると考えているのですから、正否の理屈ははなから受け付けません。原理主義に魅力を感じるのは、とくに経済的、社会的にめぐまれない階層の人間たちです。彼らは、経済的な苦境におちいった原因を、現行の世俗的な政治支配によるものとみなし、宗教的な原理によってつらぬかれた新しい政治体制の実現によって、社会が根本から革新されることに期待をかけるのです。宮沢賢治が日蓮主義者であったことについて、松岡は900夜の『銀河鉄道の夜』の中で、「賢治にはどこか、このような革命家に一発で染まっていく気質があったようだ。が、だからこそ、宮沢賢治なのだ」と書いています。純粋極まりないからこそ、日蓮主義に傾倒していったといえるのです。今、日本は「一億総中流」という時代が完全に終わり、階層の分化が進みつつあります。「下流社会」という言葉が流行語になるように、さらに貧富の差が開いていく可能性もあります。「それにしても日蓮をめぐる社会思想というもの、これはただならないものがある。おそらくはこれからも、現代の北一輝、平成の石原莞爾、21世紀の妹尾義郎の輩出を妨げることは、まったく不可能であるとおもわれる」と松岡がこの夜の文章を結んでいるのは何か不気味です。日蓮宗の開祖日蓮は晩年、甲斐国の身延山に隠棲し、弟子の指導にあたっていましたが、1282年、病をえて、常陸に湯治にいく途中、11月21日(旧暦:弘安5年10月13日)武蔵国池上で亡くなりました。【仏像】白檀 金泥書 日蓮上人 2.5
Nov 21, 2005
-

【935夜】『失われた時を求めて』マルセル・プルースト
【935夜】『失われた時を求めて』 A la Recherche du Temps Perdu マルセル・プルースト Marcel Proust 鈴木道彦訳 集英社 1996『失われた時を求めて』を読んだことはありません。全13巻、この先もおそらく読むことはないだろうと思います。抄訳どころか、935夜をざっと読んだだけで「こりゃ、多分無理だ」と思ったからです。この作品が文学史上画期的な作品であることはわかります。これ以後、文学は「何を物語るか」ではなく「いかに物語るか」を問い続ける作業になったといわれています。本作にはプルーストの前半生の経験と記憶がすべて投入されています。彼は裕福なユダヤ人家庭に育ち、生活のために働く必要もなく、社交界で遊び暮らすことができました。20代のころから数編の自伝的要素の濃い長編小説を書こうと試みてはいずれも途中で投げ出しています。『失われた時を求めて』を書かなければ、単なるお金持ちユダヤ人の遊蕩児で終わっていたかもしれないプルーストが、何をきっかけにこの大作の着想を得たのか、興味深いところです。「いかに物語るのか」について、紅茶に浸したプチット・マドレーヌのくだりはあまりに有名です。松岡正剛はプルーストの方法を「クオリアの文学」と呼んでいます。人間は生まれてから現在まで、五感を通して経験したことのすべてを記憶としてどこかに蓄えています。それらの記憶は普段は呼び戻すすべがありませんが、どこかに手がかりとなるタグがついています。紅茶に浸したプチット・マドレーヌはそのタグのひとつであることにプルーストは気づいたのです。「皿に匙の触れる音、ナプキンの固い手ざわり、髪から零れる香油の匂い、コンブレーの眼鏡屋‥‥。これらはすべて過去と現在をまたいで“そこ”にありうるものなのだ。そのときこそは、『われわれ』は超越的な時間の中に溶け合えるのだ。」と松岡が書いているように、プルーストは五感という経路を通して失われた記憶を探り、それを記録することによって、自己と自己の周囲の人々との時間を呼び戻し、永遠に定着させようとしたのです。匂いや手触りの記憶はなかなか具体的に表現されにくいものです。普段、意識している情報量としては、やはり視覚が圧倒的です。しかし、触覚や嗅覚は五感の中でももっとも原始的な部分に属するだけに、無意識領域での記憶としての蓄えは非常に大きなものではないか、と思います。ISIS編集学校の「破」では、「クロニクル編集術」という自分史年表を作成する稽古をやります。これは自分を振り返り、編集術以外にも得られるところの多い稽古です。ここでこうした五感の記憶を思い起こしていく年表を作ってもおもしろいな、と思いました。外見的事実よりも、もしかしたら人間にとってはこの五感の記憶の方が何倍も実感に近く、懐かしさと喜びを連れてきてくれるのではないか、と思います。マルセル・プルーストは幼少時から患っていた喘息の悪化により、1922年11月18日51歳で亡くなります。『失われた時を求めて』第5編「囚われの女」の校正段階の途中のことでした。評伝プルースト(上)
Nov 18, 2005
-
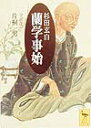
【370夜】『蘭学事始』杉田玄白
【370夜】『蘭学事始』杉田玄白 原文 1815 1978 岩波文庫1985 社会思想社 2000 講談社学術文庫蘭学というものが日本で本格的に始まった、その黎明期を伝えるのが本書です。パイオニアとなった三人の青年のひとり杉田玄白がその時代を40年後に振り返って記しています。苦闘と興奮の日々…というところでしょうか。『解体新書』が世に出たのは1774年、田沼意次が老中を勤める時代でした。同年、ヨーロッパでは、ゲーテが『若きウェルテルの悩み』を発表し、ルイ16世が即位しています。杉田玄白は1733年10月20日(旧暦:享保18年9月13日)、若狭国小浜藩の医師杉田甫仙の子として江戸に生まれました。幕府の奥医師西玄哲にオランダ流外科をまなび、53年小浜藩医となります。同僚の中川淳庵や、前野良沢らと外科医としての技術の向上に励みます。すでに日本では1754年に山脇東洋らによって、初めての遺体解剖がおこなわれていました。71年に、玄白は江戸小塚原で良沢、淳庵らとともに死刑囚の解剖にたちあい、ドイツ人クルムスが書いた『解剖図譜』のオランダ語訳本で俗称『ターヘル・アナトミア』付図の正確さに感動し、一語もわからない中で翻訳へ挑むことになります。彼らがこの翻訳へ取り組むさまを松岡正剛は編集者としての立場から読み、「ここには西洋の学問の最初の導入確立という快挙の経緯とともに、それにあたって編集的な方法がおおいに取沙汰されて、未知の構図を突破していったということが、同時に語られているということなのだ」と記しています。先日、現代日本語の成立過程について研究している大学の先生のお話をきく機会がありました。その先生は全国各地に残る古い文献をていねいに読み、そこで使われている日本語がどのような過程でどう変化していっているかを研究されているようです。かなり専門に分け入った話で、学問的なことはあまりよくわかりませんでしたが、学問というのは編集的な部分がかなりあるのだなと感じました。あるものに目をつけ、仮説をたて、それにいろいろな事実を調べだしてきて照合させていく、その繰り返しです。生活はすべてが編集である、とは松岡正剛の主張ですが、学問の世界さえかなりの部分を編集に負っているということに気づいてまた目からウロコが一枚はがれました。ウロコを落とす感覚は快感です。蘭学事始
Oct 20, 2005
-

【1030夜】『伽藍が白かったとき』ル・コルビュジエ
【1030夜】『伽藍が白かったとき』 Quand les Cathedrales etaient Blanches 1937 ル・コルビュジエ Le Corbusier 生田勉・樋口清訳 1957 岩波書店ル・コルビュジエ、本名シャルル・エドワール・ジャンヌレは、1887年10月6日、スイスのラ・ショー・ド・フォンに生まれました。ル・コルビュジエというのは母方の姓で、22年に従兄弟とともにパリで活動を開始したころからこの名前を使うようになっています。「20世紀を代表する二人の建築家」と紹介されているように、彼は歴史的様式の形態やデザインと決別して、時代が必要とする新しい20世紀様式を追求しました。鉄筋コンクリート、板ガラス、化学合成物のような近代的素材を使用し、形態の単純さと機能性に重点をおいた無装飾の建築が彼の特徴であり、国際様式として定着しました。残念ながら私は彼が設計した建物を実際に見たことはありません。建築は他の美術作品以上に実物を見ないと何もいえないものではないか、と思います。絵画や彫刻でさえ実物を見ると、そのものが持っている真の力が理屈ぬきにこちらに伝わってきます。美術の専門用語など全く知らなくても、直接こちらに響いてくるのです。ですから、図版でいくらそのものを見ていても真の力はわかりません。それは、テレビのスポーツ中継と生で見る試合との差ほど大きなものです。建築はなおさらそうでしょう。その建物の形そのもの、その建物がおかれている環境、さらには建物の中に入ってその作品に包まれるという三種類の経験が建築物を味わうには欠かせません。松岡正剛にとってル・コルビュジエは、ラ・トゥーレット修道院につきるようです。「ところがラ・トゥーレット修道院を見て、たまげてしまった。たまげるとは『魂消る』と書くけれど、まさに魂を抜かれてしまうほど驚いた」と書いています。稀代の目利きである松岡正剛を魂消させるほどのものがそこにはあったということなのですが、残念ながら写真を見ているだけではそれはさっぱりわかりません。ありふれた鉄筋コンクリートの学生寮のような建物にしか見えないからです。写真で見る限りにおいてはロンシャン礼拝堂の方がはるかにおもしろそうだと思えます。ところが、松岡正剛は「これはぼくが出る幕ではないということになる。ひたすらラ・トゥーレット修道院への巡礼を、みなさんにお勧めするだけだ」と結んでいます。ここまで言われたら、やはり生涯に一度は見ておきたい、と思わざるをえません。SALE!10%OFF!【送料無料】ル・コルビュジエ LC4 シェーズロング (PONY ポニー)
Oct 6, 2005
-

【180夜】『百科全書』ディドロ、ダランベール
【180夜】『百科全書』Encyclopedie,ou Dictionnaire raisonne des Sciences,des Arts et des Metiers 1751~1780ディドロ、ダランベール編 Diderot et d'Alembert 桑原武夫・訳 岩波文庫1971『百科全書』の編者のひとりドゥニ・ディドロは1713年10月5日、シャンパーニュ地方ラングルに生まれました。イエズス会の学校で教育を受け、20歳のときにパリへ出ます。最低限の貧乏生活を10年送り、32歳のときに最初の本格的な著作『哲学断層』を発表します。理神論を展開したため、この書物は発禁処分になりましたが、その後、彼はさらに思想を発展させ、3年後に無神論の『盲人書簡』を著して、3ヶ月間投獄されることになります。無神論が投獄されるほどの罪深い所業であるというのが現代人である私たちからはなかなか想像しにくいことなのですが、18世紀半ばにあってはそれが当然のことだったのです。無神論者にして合理主義者のディドロの最大の仕事が『百科全書』の編纂でした。モンテスキュー、ボルテール、ルソー、フリードリヒ・メルキオール・グリムなどの進歩的な学者が執筆者として参加し、彼らはのちに「百科全書派(アンシクロペディスト)」と呼ばれるようになります。ダランベールは数学分野の項目の編集をおこない、有名な序論を書きました。そこには、『百科全書』の目的として、人間の知識を体系的に示すとともに、科学技術の基本原理をふくめることが掲げられていました。ディドロは『百科全書』を聖職者の権威や固定観念、保守主義、半封建的な社会形態に対する強力な宣伝の武器として利用しました。『百科全書』はこうしたことから、後のフランス革命に思想的な影響を与えたといわれています。1751年から刊行がはじまった本書は教会とともに封建的国家権力からも敵視され、59年には既刊分は発売禁止、未完分は出版禁止となりました。しかし、ディドロはひそかに刊行をつづけました。『百科全書』はその後の百科事典の発展にも大きな影響を与えています。西洋世界の最も古い百科事典は紀元前四世紀、古代ギリシャでプラトンの弟子スペウシッポスによって編纂されたといわれています。現存する最古の百科事典はプリニウスの「博物誌」(後79頃)です。古代の地理、自然、歴史知識を集大成この百科事典は、その後1500年近くもひろく利用されました。古代からルネサンス期までの百科事典は読んで学ぶことを目的としたもので、著者個人の学問的蓄積をまとめた包括的な教科書でした。その後、近代に入って百科事典はレファレンス目的でつかわれるものとなり、アルファベット順の見出し語でテーマや情報をさすことになりました。『百科全書』のもととなった.チェンバーズの『百科事典』(1728)はクロスレファレンス(相互参照)を体系的に使用し、テーマ間の相互関連をしめしました。『百科全書』はこの形式を充実させ、さらには、大勢の専門家を編纂者や編集者として採用するという、現在の百科事典で広く用いられている形式の原型を作ったのです。【PCソフト】Microsoft エンカルタ 総合大百科 2006 CDーROM世界で最も売れているマルチメディア百科事典ソフトの決定版
Oct 5, 2005
-

【168夜】『機械と神』リン・ホワイト
【168夜】『機械と神』 Machina ex Deo 1968 リン・ホワイト Lynn White, Jr. 青木靖三訳 1972 みすず書房1968年に出版された本書でリン・ホワイトは、環境破壊によって生態系に回復しがたい不順があらわれているのは、20世紀の後半になって顕著になったことではなく、キリスト教的ヨーロッパ社会がとっくの昔におこした犯罪だということを告発し、「アッシジの聖フランチェスコに戻れ」と説いています。アッシジの聖フランチェスコ(本名・ジョバンニ・フランチェスコ・ベルナルドーネ)はアッシジの富裕な商人の家に生まれ、若いころは自由気ままな生活をおくっていました。19歳のとき、ペルージャとの戦争に出征し、1年以上捕虜生活をおくったうえに大病を患い、その後神への信仰に目覚めます。24歳でアッシジに戻り、すべてをなげうって神につかえるため父から与えられた服もすべて脱ぎ捨てて、信仰生活に入りました。歌いながら町を巡って物乞いをしたり、ハンセン病患者への奉仕活動を始めます。廃墟になっていたサン・ダミアノ修道院の聖堂の再建を志した彼は、ここで、キリストの愛をつたえ、すべての人々を回心にみちびく使命を、神からしめされたといわれています。チェラノのトマス「アシジの聖フランシスコの第二伝記」によれば-----彼は、兄弟たちに木を切る際に、まだ芽生えるチャンスを与えるために、全部を切り落とすことを禁じた。なお草の緑と花の美しさが季節ごとに、すべてのものの父であるお方の素晴らしさを告げることができるように、庭の世話をする兄弟に、庭のある部分をそのまま残すようにと命じたのである。同じく、庭に香り良い植物と綺麗な花のために、特別な場所が設けられるようにと頼んだ。それは、これらを見る人々に永遠の甘美さを思い起こさせるためであった。彼は、道で人々の足に踏まれないように、小さな虫けらを拾いあげ、冬の厳しい寒さのために飢えで死ぬことがないように、蜜蜂に蜜と良いぶどう酒をもって来させていたのである。すべての動物のうちに、柔和なものを特別に愛していたが、みな、“兄弟”の名で呼んでいた。---こうして読むと、彼の信仰は汎神論に近い印象があります。すべてのものに神が宿るとはいっていませんが、「すべてのものは神の被造物であるがゆえに尊い」ということですから、結果的にはあまり変わりないのでは、という感じを受けます。彼は教皇インノケンティウス三世の許可を得てフランチェスコ修道会を起こしていますが、解釈の仕方によっては異端とされかねない信仰ではなかったか、と思います。しかし、だからこその「アッシジの聖フランチェスコへ戻れ」なのですし、東洋の知性に学べという言葉の隣において違和感のないものとして受け止められるのでしょう。ただ、ここへのもって行き方に関して松岡正剛はホワイトの文章の安易さを次のように指摘しています。「まずは東洋思想というものがもっている『知性』のほんとうの意味と東洋思想が生態的危機に有効かどうかということを、本格的に議論しなければならなくなってくる。ついでキリスト教が現代史に突き刺さっていないにもかかわらず、何人かの聖人の思想には生態学的人間像がひそんでいたのだということを浮き彫りにしなければならなくなってくる」聖フランチェスコは司祭にならず生涯修道士の身分にとどまり、愛と祈り、福音的貧しさを実践し、托鉢をしながら福音宣教をしました。26年10月3日、弟子たちに見守られながら、フランチェスコ会誕生の小屋で息をひきとりました。1980年、教皇ヨハネ・パウロ二世によって環境問題に尽力する人たちの守護者とされています。ブラザー・サン シスター・ムーン ◆20%OFF!アッシジの聖フランチェスコの若き日を綴る、フランコ・ゼフィレッリ監督作品。
Oct 3, 2005
-

【520夜】『武家文化と同朋衆』村井康彦
【520夜】『武家文化と同朋衆』 村井康彦 1991 三一書房同朋衆という言葉を初めて知ったのはISIS編集学校でのことでした。同朋衆とは、室町時代に生まれたクリエイティブディレクター集団のことです。連歌、立花、座敷飾り、作庭にかかわる諸芸の達人であり、目利きたちです。これら同朋衆登場の背景として次の5つがあげられています。(1)「座」の社会が用意されていた。(2)座を"サロンあるいはクラブの場"にしながら、そこで「寄合の遊芸」が尊ばれた。(3)すぐれた批評、評価をする者たちが座の中から生まれていった。(4)座のなかで「趣向」を重視する傾向が強くなってきた。(数寄の心)(5)「座の文化」をまるごとプロデュースし、パトロネージュする者(バサラ大名、貴族、 室町将軍家)が登場。特に足利義満以降歴代将軍の会所重視の姿勢が同朋衆の活動を盛んにしていきました。「会所」とは、もともと特別な建物をさしたわけではなく、人々がそこで会合する「場」があり、一座建立の空間が作られたとき、そこを会所と呼んだのです。会所成立の条件として、「唐物荘厳」があり、舶来の書画・工芸品をきらびやかに並べました。会所を専用の建物として成立させたのが、三代将軍義満の「花の御所」です。会所文化は猿楽、連歌、茶湯、立花などの文芸・芸能が咲きそろいつつある中で生まれました。会所は、ジャンルの異なるこれらの芸能を取り合わせ、その面白さを語る芸談・美学論を含む多くの情報を交換するクロスオーバーのコミュニケーションスペースともなっていったのです。同朋衆的な存在が最近注目を集めていると松岡正剛は述べ、今日のグローバル社会のなかで、かえって地域的なサロンやコミュニティ型の経済文化や大衆迎合をしないクラブ財などが話題になってきたことにふれています。現在、文化の評価基準はほとんどの場合マスメディアが担っています。圧倒的な情報発信力によってそれはなされているわけですが、そのことに関して松岡正剛は「しかしながら、それで熟した経済文化が育まれているかといえば、そんなことはない。むしろたいていの文物や人物が瞬時にして流行に飲みこまれ、そのまま消えていっている」と言っています。数年前に大流行したものが、今ではどこでどうなっているかを思い出すことさえ難しいことは珍しくありません。マスメディアの嵐によってかき乱され、そのもののよさが失われてしまったというものも少なくないでしょう。マスメディアは消費するには都合がよいですが、育む力はほとんど持ち合わせていないと感じます。インターネット文化がこれからさまざまな発展を見せる中で、マスメディアの与える消費としての文化はしだいに背景に下がっていくのではないか、と思います。そこにホンモノはあまりない、それを見極める力を持った人もいない、ということに私たちはしだいに気づきつつあるからです。同朋衆発展の基礎を築いた室町幕府三代将軍足利義満は1358年9月25日、(旧暦では南朝:正平13年、北朝:延文3年8月22日)足利義詮の子として生まれました。公家文化に憧れ、和歌・連歌・蹴鞠など貴族的教養を身につけ、「文化将軍」と呼ばれます。南北朝の騒乱を収めた後、公武の権力を一手に握り、勘合貿易を始めます。明からもたらされた唐物が会所での座敷飾りに使用されるようになります。また、「乞食の所行」にすぎなかった猿楽の世阿弥を寵愛し、能楽発展のきっかけを与えました。そして、京都北山に山荘を造営し、ここに貴族・武家の一大サロンが出現します。これが「北山文化」と呼ばれるようになったのです。和太 守卑良 作 茶碗
Sep 25, 2005
-

【327夜】『吉田茂とその時代』上下 ジョン・ダワー
【327夜】『吉田茂とその時代』上下 Empire and Aftermath Yoshida Shigeru and The Japanese Experoence 1979 ジョン・ダワー John W. Dower 大窪原二訳 1981・1991 TBSブリタニカ・中公文庫太平洋戦争の終戦から今年で60年です。すでに戦争を知っているといえる人は70歳以上ですし、ある程度の分別をもってあの時代に生きていたという人は80歳以上になっています。平成の時代も始まってはや17年、昭和も遠くなりつつあります。ただ、少し遠くなってきたからこそ、あの時代のことが逆に見えてくるということもあるかもしれません。関係者が生きていては都合が悪くて明らかにできなかったことも「歴史」の中に入れば、細かな部分まで遠慮なく虫眼鏡で見たり、ひっくり返したり叩いたりすることができるからです。あの戦争に向かった時代、戦中、そして戦後処理を巡る多くの現代史には興味をかきたてられます。膨大な関連書籍がありますので、どれから手をつけていいか迷いますが、少しずつ読んでみたいと思っています。千夜千冊でもあの時代をとりあげた夜はかなりあり、ざっと拾い上げただけで11冊みつけることができました。112夜『ニッポン日記』マーク・ゲイン181夜『マリコ』柳田邦男283夜『日本の飛行機王・中島知久平』渡部一英430夜『虹色のトロツキー』安彦良和448夜『昭和精神史』桶谷秀昭568夜『大空のサムライ』坂井三郎708夜『亜細亜新幹線』前間孝則808夜『ハルビン学院と満洲国』芳地隆之832夜『国破レテ』村上兵衛960夜『野火』大岡昌平961夜『戦艦大和ノ最期』吉田満さらには、この327夜を書いたジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』も後に出版され、ピュリッツアー賞を受賞したことが997夜で紹介されています。ある一定の時間を経てその時代を見ると、近いときには頭に血が上っていてなかなか冷静に見極めることもできなかったことが違う目で見られるようになります。いろいろな立場から見れば戦争という大きな出来事にもそれぞれの顔があることがわかります。これまでは、どちらかというと”ただただ無意味に戦争の犠牲になって空襲で殺される国民”というお話を読むことが多かったのですが、そろそろもっと大きな視点、歴史的な流れや外交関係、それらのかけひき、その当事者となって歴史の大きな軸を回転させた人たち、そういう歴史を読んでみたいと思うようになりました。吉田茂は戦後の日本、大日本帝国が日本国に変わっていくときの日本側の中心人物のひとりです。彼は1878年9月22日、高知の自由民権活動家竹内綱の五男として東京で生まれています。3歳で実業家吉田健三の養子となり、9歳で養父が亡くなったために家督をついでいます。戦前は外交官として活躍し、39年にイギリス大使を最後に退官しました。戦争中も親英米派として知られ、戦争末期には和平工作を試みて陸軍刑務所に入れられています。敗戦後、鳩山一郎が公職追放された後を受けて日本自由党総裁となり、日本国憲法制定からサンフランシスコ講和条約、日米安保条約の締結までの7年間をとりしきり、彼のもとで大臣をつとめた池田勇人、佐藤栄作らが「吉田学校の生徒」として高度経済成長の日本の舵取りをしました。いわば、現代日本への方向を決めた最大の立役者といえます。もし、戦争がなかったならば、彼はこれほど大きな足跡を歴史の上に残すことはなかったでしょう。敗北を抱きしめて(上)増補版敗北を抱きしめて(下)増補版
Sep 22, 2005
-

【292夜】『夢二のアメリカ』 袖井林二郎
【292夜】『夢二のアメリカ』 袖井林二郎 1985・1994 集英社竹久夢二は1886年9月16日、岡山県邑久郡本庄村(現・岡山県瀬戸内市邑久町本庄)で代々酒造業を営む家に父菊蔵、母也須能の次男として生まれました。長男が前年に亡くなっていたため、実質的には長男として育てられました。17歳の夏、家出して東京へ出ます。その後、18歳で早稲田実業学校に入学し、雑誌や新聞にスケッチ、コマ絵などを投稿し、採用されるようになります。専攻科に進んだ20歳の夏、「中学世界」で『筒井筒』が第一賞に入選し、学校を中退して専業の絵描きになりました。このとき初めて”夢二”を名乗っています。本名は茂次郎(もじろう)ですから、このペンネームは正解だったといえるでしょう。本名のままだと、「茂次郎式美人」となって、なんとも垢抜けない感じになってしまいます。このあたりから、夢二の華麗なる女性遍歴が始まります。「だいたいモデルがないと夢二は女を描けない」と松岡正剛は292夜の中で断定していますが、女好きゆえそうだったのか、モデルを求めたためにそうなってしまったのか、そのあたりは夢二本人にきいてみないとわからないことかもしれません。まず、岸たまきの登場です。彼女は夢二が唯一戸籍上の妻とした女性ですが、夢二と出会う前に結婚歴があり、夫と死に別れ二児を抱えて生活の為に東京で開店した絵葉書店の客としてやってきた夢二と出会います。その後彼は毎日店に通いつめ、二ヵ月後の1907年1月に結婚しています。たまきをモデルに「夢二式美人」が生まれ、翌年2月には長男・虹之助が生まれます。しかし、なぜかこの二人の間はその後、ややこしいことになっていきます。09年にはいったん協議離婚、翌年、同棲してさらに11年に不二彦、16年には草一という二人の子どもをもうけています。14年、夢二は笠井彦乃に出会います(このときはまだたまきと同棲中)。彦乃は女子美大の学生でしたが、夢二のファンで彼に絵を習いたいと訪れたところから交際が始まりました。たまきとの破局はなぜか、夢二がたまきと画学生東郷鉄春との仲を疑い富山県の海岸でたまきの腕を刺す事件を起こしたことで訪れます。17年6月に京都二寧坂に転居し彦乃と同棲を始めます。18年8月から9月にかけて彦乃と九州を旅行しますが、彼女はここで結核を発病。紙問屋を営む彦乃の父は夢二が彼女と会うことを断ります。19年には次なる女性お葉と会っています。お葉は本名、佐々木カ子ヨ(カネヨ)、藤島武二らのモデルをしていました。お葉は夢二がつけた名前です。20年1月、彦乃は24歳になるのを待たずに東京お茶の水順天堂医院にて亡くなります。さすがに夢二もショックだったようですが、翌年6月にはお葉と渋谷で同棲を始めています。一児をもうけたものの夭折、25年に彼女は自殺をはかり、半年後に二人は別れています。夢二とかかわりを持った女性、どうもあまりハッピーな人はいないようです。292夜の夢二はこれら人生のさまざまなエピソードを経た後の姿です。「サンフランシスコの邦字新聞『新世界』の写真を見ると、かなり老けてみえる」と書いてありますが、無理もないことでしょう。「新たに松沢村松原の『少年山荘』で同棲していた山田順子との関係はスキャンダルにもなっていた。“第四の恋人”と夢二伝記者がよんでいる岸本雪江とも長続きしていない」と、さらなる女性遍歴は続いていたようで、その上、サンフランシスコでも小川ナジモ(18歳)に懸想した、というのですから…。結局、2年にわたるアメリカ、ヨーロッパの旅から帰国したあと、33年10月に再び台湾へ行き、そこで体調を崩して帰国。34年1月、信州富士見高原療養所に入院。9月1日「ありがとう」の言葉を残して永眠しました。辞世の歌は「日にけ日にけ かつこうの啼く音ききにけり かつこうの啼く音は おほかた哀し」でした。享年51歳。竹久夢二「黒船屋」
Sep 16, 2005
-

【913夜】『神曲』(全3冊)ダンテ・アリギエーリ
【913夜】『神曲』(全3冊)La Divina Commedia 1307~1320 ダンテ・アリギエーリ Dante Aligheri 寿岳文章訳 1976 集英社この913夜が発表されたのは2003年12月26日。もう年も押し詰まったころでした。もの凄い分量の文章にただ、仰天したのを覚えています。『神曲』を読んだことは、残念ながらありません。西洋の古典文芸にさして関心も持たなかった私のような人間にとっては、『神曲』は文芸というより、歴史の暗記項目のひとつでした。ダンテといえば『神曲』、ボッカチオといえば『デカメロン』、そんなものです。『神曲』が描かれた背景については、少しだけ聞いていました。ダンテというえらい詩人が永遠の女性ベアトリーチェへの報われぬ愛を詠った作品だということを。ダンテがベアトリーチェを見初めたのが9歳のときです。これはまあよくある話でしょう。初恋はだいたい幼稚園から小学校低学年の間に起こります。ダンテが常人と異なっているのは、それから一度もベアトリーチェに会わなかったにもかかわらず、18歳のとき、聖トリニタ橋のたもとで再会し、会釈してすれ違ったのみで、一言の会話も交さなかったのに、熱病に冒されたように彼女に恋焦がれるようになったということです。彼女の姿を見るたびに全身が震え、気絶しそうになった、というのですから、「ほんまかいな」と言いたくなります。それほど恋焦がれていたのに、なぜベアトリーチェに対して気持ちを明かさなかったのか、不思議です。ベアトリーチェはフィレンツェ有数の銀行家の娘で、ダンテは没落した下級貴族の出身であったため、結ばれる可能性はほとんどなかった、というのですが、会釈を交わすくらいですから、全くかけ離れた人というわけでもなかったでしょう。ダメでもともと、と彼女に気持ちくらいは伝えてよかったのではと思うのですが。ま、もしダンテがそうしていたら、『神曲』は生まれなかったかもしれませんが。むくわれぬ恋、片思いから生まれた文学作品は多数あります。ダンテは13世紀後半の人ですが、日本ではすでに平安時代の宮廷の和歌文化の中で数多くのむくわれない恋の歌が詠まれています。高校時代の古文の先生は「チビ太」というあだ名の小柄な方でした。授業内容はほとんど忘れてしまったのですが、午後の眠い授業の最中に突然、「みなさん、恋の醍醐味は”忍ぶ恋”にあるのですよ。みなさんのように、すぐに『あー、ええな~、好きや、好きや』とおおっぴらに言ってしまっていたのでは本当の恋の味わいを知ることはできません」とおっしゃいました。確かにこれは一理あるところだな、と妙に納得したものでした。エネルギーというものは垂れ流し状態では、何も生み出しません。それをおしどどめ、そこに生まれるえもいわれぬ感情を味わうのが、「恋の醍醐味」であるのかもしれません。実際、ベアトリーチェにしても(彼女はフィレンツェの貴婦人ビーチェ・ポルティナーリとされています)「別に聖女でもそれほどの美人というわけでもなかった」といわれ、彼女を不滅の美と愛の女性にしたてあげたのは、ひとえにダンテの一途な思い込みと想像力だったというわけです。ダンテがもし、彼女と結婚していたら、とうてい「『天国編』に登場するベアトリーチェは、天国のもっとも高いところに神といっしょに坐して、虹のような光につつまれている」などということは望むべくもなく、せいぜい煉獄の片隅か、悪くすれば地獄で幾人かの法皇とともに業火に焼かれるはめに陥っていた可能性が大です。ダンテは1265年フィレンツェに生まれていますが、晩年政争に破れ、フィレンツェを追放されます。1318年ごろよりラヴェンナの領主のもとに身を寄せ、ここで『神曲』の執筆にとりかかったのです。『神曲』完成直後、外交使節としてヴェネチアに向かう途中マラリアにかかり、1321年9月13日から14日にかけての夜中に亡くなりました。木箱入 1500ml ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ [1999] セレーゴ・アリギェーリダンテの子孫、アリギェーリ家が生産するワイン。
Sep 14, 2005
-

【209夜】『パンダの親指』スティーヴン・ジェイ・グールド
【209夜】『パンダの親指』上下 The Panda's Thumb 1980 スティーヴン・ジェイ・グールド Stephen Jay Gould 櫻町翠軒訳 1986 早川書房『パンダの親指』は私も読みました。前の職場の隣が図書館で、昼休みにそこへ出かけては、片っ端から本を借り出していました。グールドの本もこれ以外にニ三冊読んだ記憶があります。その分野の第一線の学者が一般向けに書いた啓蒙書の優れた作品というのをあのころよく読んでいて、オリバー・サックス、コンラート・ローレンツ、そして、このスティーヴン・ジェイ・グールドの著書が印象に残っています。スティーヴン・ジェイ・グールドは1941年9月10日ニューヨークで生まれています。67年にコロンビア大学で博士号を取得、73年からハーバード大学で地質学の教授となり、アメリカ自然史博物館のナイルズ・エルドリッジとともに、進化における断続平衡の理論を提唱しました。この理論は、種は、急激に変化する期間とほとんど変化しない静止(平衡)期間を持ち、”徐々に”進化するのでなく、”区切りごとに”進化していくとするものです。その根拠として、進化の中間段階にある生物の化石がほとんど見つかっていないという点をあげています。進化学説の主流である漸移説では種は長い時間をかけて連続的に進化すると考えられてきました。断続平衡説は古代生物の同時期的な大量絶滅の発生と関連しており、それをわかりやすく述べた著書が『ワンダフルライフ』です。この作品をもとに以前NHKでCGを使った番組が作られたことがあり、大変印象に残っています。そこに登場するカンブリア紀の奇想天外なデザインの生物の数々。全部化石に基づいたものだというのですから、その時代、地球上で生物デザインの大実験が行われていたということです。『利己的な遺伝子』で有名なリチャード・ドーキンスはグールドの論敵として知られており、『ドーキンスVSグールド』という二人の論争をテーマにした本さえあります。進化論の中にもさまざまな考え方があり、グールドは複雑なものは複雑なものとして説明しようとしており、すべてを遺伝子に還元したり、動物の形態や行動にはすべて適応的な意味があるといった主張には反論しています。また、進化論を否定するアメリカのキリスト教原理主義の創造論には一貫して反対の立場をとり、また、IQなどのように一見科学的に見えるさまざまな道具が白人優越主義の中で人種差別や優生思想の道具にされたことを『人間の測り間違い』で指摘しています。彼は1982年7月、40歳のときに「平均余命8ヶ月」というガンの一種である胸膜中皮腫と診断されました。しかし、そのとき視点を変えてガンと闘うことにより、その壁を乗り越えています。その時の経験を綴ったエッセイは『がんばれカミナリ竜』におさめられており、Webでも読むことができます。「平均中央値は神のお告げじゃない」 彼は2002年5月20日に60歳で亡くなりました。平均余命より19年2ヶ月長く生きることに成功したのです。世界の知性が語る21世紀
Sep 10, 2005
-

【828夜】『創造的人間』湯川秀樹
【828夜】『創造的人間』湯川秀樹 1966 筑摩叢書子どものころ、家に湯川秀樹の子供向け伝記がありました。第三高等学校の生徒だった秀樹が学校行事の山登りに行き、「ぼくはヘリコプターで一気に頂上へいくより、こうして一歩一歩登っていくのが好きだ」と友達にいう場面がありました。なぜか妙にこの本を気に入って、何度も読み直した記憶があります。ですから、湯川秀樹が具体的にはどんな業績をあげた人かは知らなくても、なにかずっと親しみをもっていました。今もノーベル賞というと大事件ですが、湯川秀樹は日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。当時、大阪帝国大学の講師であった湯川は、1934年秋、重力、電磁力とはことなる新しい「核力」を媒介するものとして、中間子の存在を予言する講演を日本数学物理学会でおこない、翌35年に「素粒子の相互作用について」と題する論文にまとめました。37年にアメリカの物理学者アンダーソンが宇宙線中に未知の粒子を発見し、湯川理論は注目を集めます。しかし、その検証と理論の発展は戦争の激化によって中断されました。戦後、47年にイギリスで2種類の中間子の存在が確認され、その1つが湯川粒子であることがわかり、湯川理論の正しさが証明されます。湯川理論は、未知の素粒子の存在を理論的に予言して成功するという、新しい素粒子論を物理学の分野で切りひらくのに大きな功績があったのです。これに対し、49年、ノーベル物理学賞が贈られました。敗戦からわずか4年、国中が戦後の混乱の中でうちひしがれていたときに、このニュースがどれほど日本人を励ましたか、今では想像もつかないことだろうと思います。学者一家に育った彼は、幼いころから漢文の素読をしており、伝記にもその場面がでてきました。828夜を読むと、彼の学者としての教養の広さ、深さがわかります。828夜で松岡正剛は「湯川秀樹の凄みは、中間子論ではわからない。むしろその後の非局所場理論から素領域仮説に転じていったところが、なんといっても凄かった」と書いています。この長い思索の過程で湯川は老荘思想を思い出します。”素粒子の奥に宿屋があった”--ノーベル賞という学者としては最高の栄誉をえながら、なお彼は”百代の過客”の列に連なる直前まで第一線の理論物理学者として精力的に思索を重ねました。『大事なことは、では、何をもって何とみなすかということなんです。このとき、「何をもって」というところにもイメージがいる。「何とみなすか」というところにもイメージがいる。(中略)この二つのイメージは別々のものでもかまへんのです。その異なるイメージをつなげ、そもそもの何を何とみなすかという「同定」をおこすことが、本当の理論物理学なんです』と湯川が松岡正剛に語った言葉が紹介されています。もちろん、これは理論物理学のお話なのですが、いろいろなものにあてはめられるのではないかと感じました。湯川は54年におこなわれた水爆実験に大きな衝撃をうけ、翌55年のラッセル=アインシュタイン宣言に署名し、パグウォッシュ会議に参加。さらに62~81年には4回にわたって科学者京都会議を主宰、川端康成らとともに世界平和アピール7人委員会を結成して、核兵器全廃と戦争の廃絶をうったえつづけ、1981年9月8日に亡くなりました。湯川秀樹の世界
Sep 8, 2005
-

【946夜】『ユダヤ人とは誰か』アーサー・ケストラー
【946夜】『ユダヤ人とは誰か』The Thirteenth Tribe 1976 アーサー・ケストラー Arthur Koestler 宇野正美 訳 1990 三交社なんだかよくわからないもの、というのはいろいろありますが、「ユダヤ人」というのも私にとってはそうでした。946夜を読んで、なるほど、そういう歴史的背景があったのか、と驚いたしだいです。この謎のカザール人については、アーサー・ケストラーをネットで調べているうちにこのようなHPに行き当たりました。ハザールとユダヤここでは最初に旧約聖書に登場する「ユダヤ人」とは誰か、から話が始まっています。イエスやモーゼ、ダビデ、ソロモンは人種的にはセム系(オリエンタル)の人々であり黒髪で黒い目を持ち肌は浅黒く、白人ではありませんでした。しかし、現代社会で一般にユダヤ人といわれている人々のほとんどの外観は白人です。人種的にイエスにつながる人たちは「スファラディ系ユダヤ人(スファラディム)」と今では呼ばれており、白人系の人たちは「アシュケナージ系ユダヤ人(アシュケナジーム)」と呼ばれています。現代、「ユダヤ人」といわれている人の90%はこのアシュケナージであるため、私たちのイメージの中に「ユダヤ人は白人」とのイメージが定着してしまったのです。アシュケナージは、西暦70年のエルサレムの「ソロモン第二神殿」破壊以後、ライン川流域に移住したという定説がありました。しかし、これは近年の遺伝学や言語学による研究で否定されつつあります。アシュケナージは7世紀に黒海沿岸に「ハザール王国」を築き、9世紀初めにユダヤ教に改宗したトルコ系人種ハザール人の子孫であるというのが有力な説になっています。それを世界に大きく知らしめたのがケストラーでしたが、彼の著作以前にもすでに100年前にはH・G・ウエルズが「ハザール人は今日ユダヤ人として偽装している」と著書の中で述べており、知る人ぞ知るお話だったのです。ハザール人はほとんど知られていませんが、6世紀中ごろヨーロッパ東部に突如出現し、7世紀から10世紀にかけてコーカサス山脈の北に現在のカザフスタン、ロシア、ウクライナの国境地帯にまたがる帝国を築き繁栄しました。ハザール王国の存在は、その後の世界に大きな影響を与えています。この時代、アラビアで起こったイスラム帝国が驚異的なスピードで勢力をのばしていました。シリア、エジプト、アフリカ、スペインを征服し、ササン朝ペルシャを滅亡させます。西ヨーロッパではトゥール・ポアティエの戦いでカール・マルテルがイスラム軍をおしとどめます。しかし、東からの進路をくいとめるのに大きな役割を果たしたのがこのハザール人だったのです。黒海をはさんで隣り合っていたビザンチン帝国はハザール王国と同盟を結び、なんとかイスラムの勢いに対抗しています。もし、ハザールがイスラムに屈していたら、東ヨーロッパへのイスラム勢力の進出は容易に達成されていたのです。イスラムへの盾になったことに加え、もう一つ彼らの行動が現代まで大きく尾をひいているのが、9世紀初頭のオバデア王の国政改革でユダヤ教に改宗してしまったことです。これによってハザール王国は世界史上、類を見ない「ユダヤ人以外のユダヤ教国家」となります。しかし、結果的にはこの改宗は国内の勢力バランスを崩すもととなり、やがて勃興してきたキエフ・ロシア公国の侵攻で10世紀半ばにはボルガ下流のハザール王国首都イティルが滅び、「ハザール」の名前は歴史の彼方に消えます。しかし、彼らは「ユダヤ人」として残り、さまざまな面で現代史にも影響を及ぼし続けているのです。イスラエル国家が建設されたパレスチナは白人系ユダヤ人の故郷であるはずがありません。彼らが宗教的なアイデンティティのよりどころとしてでパレスチナにこだわり、第二次大戦後強引に入植したために、今もなお続く流血の歴史が始まったのでした。ところでこの「ユダヤ」に関する問題をネットで追っていくと、非常に興味深いあちこちのページへいくことができます。中には”妄想”としか思えないトンデモページもありますが、歴史の真実というのはこのようにいろいろな玉石混交の中にうずもれているものなのでしょう。何が正義で何が悪かというのを単純に信じ込むことがもっとも危険で恐ろしいことか、と思いました。アーサー・ケストラーは1905年9月5日、ハンガリーに生まれています。彼の『ホロン革命』実は、読んでいるのですが随分前であるため、内容をほとんど忘れています。興味深いと感じながら読んだ記憶だけが残っています。(もう一度読んでみるかなぁ)。ユダヤ人とは誰か
Sep 5, 2005
-

【605夜】『武士道』新渡戸稲造
【605夜】『武士道』 新渡戸稲造 奈良本辰也訳 1938 岩波文庫・1997 三笠書房 他新渡戸稲造は1862年9月1日(文久2年8月8日)、盛岡藩士の三男として生まれました。新渡戸家は稲造の祖父・伝(つたう)の代から十和田地方の三本木原開拓に大きく貢献した家柄です。当時三本木原一帯は広い台地でしたが、川がなく、南部盛岡藩で勘定奉行を務めていた伝は、ここに水路(稲生川)を開くことを決意し、藩の許可を得ました。現在の十和田市中心部は稲生川ができるまではまわりにほとんど木もない草原で、わずか数軒の茶屋がある程度だったといいますから、新渡戸家の仕事が非常に大きなものであったことがわかります。稲造は幼名を稲之助といい、この地に初めて稲が実ったことを記念して名づけられました。彼は札幌農学校へ進み、その後、東京帝国大学へ進学。その試験の際に早くも面接官に「先生、私は太平洋の架け橋になりたいのです」と彼の生涯を象徴する決意を語ったといいます。のちに彼は『武士道』によって当時野蛮な未開の国と思われていた日本にも、武士道という優れた精神があることを世界に伝えようとします。「日本に対する決定的な情報欠如を、彼は大胆にも武士道には『ノーブレス・オブリージ』(身分にともなう義務)があることを朗々と説明することできりぬけた」(松岡正剛)のは、彼自身が南部盛岡藩士の子として、新渡戸家三代のノーブレス・オブリージをつぶさに見ており、血の中にそれを感じていたからではないでしょうか。605夜にも書かれているように、新渡戸の晩年は厳しいものになっていきます。軍国思想が台頭し、時代が世界大戦の嵐へと進んでいく中、彼は新聞紙上で軍閥批判を行います。そのため軍部や右翼の激しい反発を買い、幾度か命の危険にさらされます。それまで彼を賞賛していた人々の多くも彼を糾弾する側にたち、友人や弟子の多くが彼のもとを去りました。日米戦争を回避するためにアメリカに渡り、日本の立場を訴えようとしますが、「新渡戸は軍部の代弁に来たのか」と言って、アメリカの友人からも理解されませんでした。結局1933年(昭和8年)カナダで行われた太平洋会議に出席の帰途、ビクトリア市で亡くなります。正直に言ってしまうと、五千円札に肖像が採用されるまで、新渡戸稲造を知りませんでした。同時期に採用された福沢諭吉、夏目漱石の有名さと比較すると、「誰?」という感じでした。代表的な明治のキリスト者、内村鑑三、賀川豊彦に比べても彼の名前はほとんど知られていなかったのではないでしょうか。松岡正剛はそのあたりの背景についても602夜の中で少しふれています。ここの冒頭で、桑沢デザイン塾での講演で、松岡が新渡戸稲造にふれたあと、しばらくして渋谷の書店から『武士道』が消えたというエピソードが書かれています。書店ではちょっとしたミステリーだったのではないでしょうか。しかし、古典とは、良書とは、本来このようにして次の世代へと受け継がれていくものなのだと思います。対訳武士道
Sep 1, 2005
-

【012夜】『テスト氏』ポール・ヴァレリー
【012夜】『テスト氏』Monsieur Teste 1896 ポール・ヴァレリー Paul Ambroise Valery 粟津則雄訳 1934 野田書房・1939 創元社・1980 福武文庫 他おそらく二一世紀は「方法の世紀」となるだろう。---12夜の冒頭にある松岡正剛のこの言葉はこれまで何度かきいていました。そこで、ふと思いました。方法とは何だろうか、と。わからないことはアイマイにせず辞書で調べてみました。ついでにISIS編集学校「守」の稽古にもあるヴィッシュゲームも応用して、意味のシソーラスを広げてみます。これは、国語辞典から選んだひとつの同意語をさらにひいてその言葉のネットワークを拡大しようというゲームです。同じ言葉を選ぶことはできません。さて、よーいヴィッシュ!【方法】しかた。てだて。目的を達するための手段。または、そのための計画的措置。【てだて】手段。方法。すべ。策略。【策略】はかりごと。計略。【計略】はかりごと。工夫。計画。策略。【計画】物事を行うにあたって、方法、手順などを考えて企てること。またその企ての 内容。もくろみ。はかりごと。【もくろみ】もくろむこと。計画。設計。心算。【心算】心の中の計画。心づもり。胸算用。【胸算用】心の中で見積りをたてること。胸中での計算。むなづもり。【むなづもり】心中に見積ること。胸算用。【見積】あらかじめ大体の計算をすること。また、その計算。【計算】(1)はかりかぞえること。勘定。また、見積り。 (2)〔数〕演算をして結果を求め出すこと。【勘定】(1)考え定めること。かんてい。 (2)金銭出納または物の数量の計算。 (3)代金を支払うこと。またその代金。 (4)見積り。考慮。 (5)簿記の元帳に設ける特殊な計算形式。すなわち同一種類または同一名称 の資産・負債・資本・収益・費用の諸項目につき増減の記録・計算をおこな うための特殊形式。 (6)勘定衆の略。【考慮】考えをめぐらすこと。考えおもんぱかること。【考え】(1)考えること。また、考えて得た内容。 (2)勘当。【考える】(1)実情を調べただす。吟味する。 (2)糾明して罪する。勘当する。 (3)勘案して明らかにする。究明する。 (4)易などによって事を判断する。 (5)学ぶ、学習する。 (6)思考をめぐらす。あれこれと推量する。思案する。【学ぶ】(1)まねてする。ならって行う。 (2)教えを受ける。業を受ける。習う。 (3)学問をする。【習う】(1)くりかえして修め行う。稽古する。 (2)教えられて自分の身につける。まなぶ。【稽古】(1)昔の物事を考えること。古書を読んで昔の物事を参考にし理議を明らかに すること。 (2)学んだことを練習すること。学習。 (3)武術・遊芸などを習うこと。 (4)高い学識を有すること。【学習】まなびならうこと。過去の経験の上にたって、新しい知識や技術を習得するこ と。広義には精神・身体の後天的発達をいう。【習得】ならって会得すること。ならっておぼえること。【会得】意味をよく理解して、自分のものとすること。【理解】物事の道理をさとり知ること。意味をのみこむこと。物事がわかること。了解。【了解】さとること、会得すること。領解。【さとる】(1)つまびらかに知る。物事の道理を明らかに知る。 (2)推しはかって知る。察知する。 (3)〔仏〕心の迷いを去って真理を体得する。煩悩を脱して涅槃を得る。 参照:広辞苑(岩波書店)涅槃に達したところで、今日のヴィッシュゲームはひとまず終わります。進む方法によってはさまざまな展開が考えられそうです。ポール・ヴァレリーは1871年8月30日、フランスの地中海に面する町セートで生まれました。92年夏、詩作への絶望感と年上の女性への恋愛感情から、内的危機におちいり、この経験は「知的クーデター」として、その後の創作活動と思索の道筋を決定づけます。生活のために勤務を続けながら早朝の数時間を抽象的な思考にあて、その軌跡を書きとめます。この作業は約50年間つづけられ、3万ページにものぼる『カイエ』となりました。クリスチャンディオール : プワゾン EDT 100ml 【香水 フレグランス】詩人ポール・ヴァレリーの、「香りは心の毒である」という言葉から引用し「プワゾン(毒)」と名づけられました。
Aug 30, 2005
-

【781夜】『狂王ルートヴィヒ』ジャン・デ・カール
【781夜】『狂王ルートヴィヒ』Louis 2 De Baviere Ou Le Roi Foudroye 1975 ジャン・デ・カール Jean des Cars 三保元訳 1983 中央公論社とんでもない人がいたものだ、というのがルートヴィヒ2世に対する感想です。事実は小説よりも奇なり、ですが、その生まれ、美貌、男色、ワグナーの世界への熱烈な打ち込みよう、とりつかれたような築城のさま、悲劇的な謎の死…。ルートヴィヒ2世は1845年8月25日、バイエルン国王マクシミリアン2世の子としてミュンヘン近郊のニュンフェンブルク城で誕生します。父方は代々のバイエルン王家ウィッテルスバハ、母はプロイセン王家ホーエンツォレルンの出身です。中世ドイツの白鳥の騎士ローエングリンの伝説の地、ホーエンシュバンガウ城で幼児期をすごし、ゲルマンの伝説に強くひかれて育ちました。彼は多くの文学作品にとりあげられていますが、「こうしてルートヴィヒをどのように綴るかということは、まったくもってわれわれの手に負えないものとなっていく」と松岡正剛は記しています。どうやら、ルートヴィヒを充分に描けたといえる作家はいなかったようです。ヴィスコンティの映画『神々の黄昏』がまだしも、というところなのでしょうか。オーストリア皇妃エリーザベト(シシ)は女嫌いであったルートヴィヒがただひとり心を許し、交流を続けた女性でした。ルートヴィヒの死を知らされたとき、シシは「彼は狂っていたのではありません。夢を見ていたのです」といったと伝えられます。思えば、彼の生涯は、最初から最後まで、ずっと夢のような異様な物語です。16歳で『ローエングリン』を初めて見てから38歳のときにワグナーが亡くなるまで、彼の生涯はほとんどワグナーのオペラの世界のみに捧げられているといっていいありさまです。単なる趣味人というのではなく、一国の国王(しかもすでに19世紀も後半の)が国力を傾けてまでワグナーの世界にのめりこんでいるのですから、バイエルン政府が彼から権力をとりあげようとしたのも無理はなかったと思います。歴史に「もし」はありませんが、仮に、ワグナーと同時代に生きていなかったとしたら、ルートヴィヒはいったい何に情熱を傾けたでしょうか?歴史の必然というか、不思議というか、そいうものを感じないではいられません。もし、ルートヴィヒがいなければ、ワグナーの多くのオペラは完成しなかったかもしれませんし、バイロイト祝祭劇場もなかったでしょう。24歳でノイシュヴァンシュタイン城に着工したのを皮切りに、10年間でヘーレンキームゼー城、リンダーホフ城と次々に城を築いていきます。彼が即位した1864年は、ドイツ統一にむけてプロイセンとオーストリアが覇を競っていた時代でした。71年にはドイツ統一がなってヴィルヘルム1世が即位しています。統治能力のない「狂王」が国家財政を傾けてつくった三つの城と、彼の援助によってできたバイロイト祝祭劇場は、現代、世界中から人々を集める文化、観光の目玉になっています。ルートヴィヒは「私が死んだらノイシュヴァンシュタイン城を破壊せよ」と命じていたそうですが、幸いそれは実行されませんでした。ドイツ紀行 1 ロマンチック街道とバイエルンの旅
Aug 25, 2005
-

【869夜】『文化大革命と現代中国』安藤正士・太田勝洪・辻康吾
【869夜】『文化大革命と現代中国』 安藤正士・太田勝洪・辻康吾 1986 岩波新書本書の出版からすでに20年近くの歳月が流れ、文化大革命の中心人物たちも世を去りました。権力闘争を生き抜き、78-97年まで事実上の中国の最高実力者として改革開放政策をおしすすめたのは登小平でした(トウの文字は機種依存文字で使えません)。登小平は1904年8月22日、四川省広安県で生まれ、16歳でフランスに留学し、22年に社会主義青年団に入団、ついで24年に中国共産党パリ支部に入党しました。26年に帰国後、種々の活動にたずさわり、当時党内反主流だった毛沢東支持を表明。一時失脚したものの、34年からの長征に参加し、45年に党中央委員となりました。49年の中華人民共和国成立後は、副首相、財政相をつとめ、党内では56年に総書記、政治局常務委員へと昇りつめていきます。文化大革命の背景には、58年から毛沢東が進めた「大躍進」の失敗がありました。大躍進は、「衆人こぞって薪をくべれば炎も高し」を合言葉に労働力の大量投下による人海戦術で、急進的社会主義建設を目指したもので、その実行単位となったのが人民公社でした。人民公社は熱狂的な大衆の支持のもと、次々と農業生産目標を高めていきました。しかし、農民の精神力のみに依存し、科学的合理性、市場原理、機械力などの根拠を欠いたこの政策は開始1年後には早くも限界が見え始めます。生産性の客観的根拠を欠いた農業生産目標は、基本目標を大幅に修正せざるをえず農村地帯では多くの餓死者を出す事態になりました。責任をとり59年、毛沢東は国家主席を辞任します。61年に始まった経済調整で、登小平は毛沢東にかわって国家主席となった劉少奇とともに市場経済重視策をおしすすめます。これに対し、毛沢東が「資本主義の道をあゆむ一握りの実権派(登小平ら)」を打倒し、自らの復権と絶対的権威の確立をめざして開始した権力闘争が文化大革命であったといえます。文革中、中国の工業生産は20%も下落したといわれ、71年以後党の方針は、政治思想教育重視から経済建設重視への転換を余儀なくされました。いったん失脚していた登小平は、林彪事件後の73年に復活。林彪亡きあとの文革派のリーダー、江青らのイデオロギー急進派と周恩来、登小平ら実務派との主導権争いが再び激化します。76年4月には天安門事件(第一次)がおこり、この年1月の周恩来の死をいたむ群衆が、公然と文革派に反旗をひるがえすにいたって、毛沢東体制は根本から動揺。事件は登小平ら資本主義を復活させようとする「走資派」の陰謀ととしていったんは処理されます。このとき登小平はふたたび全職務を解かれています。しかし、76年9月に毛沢東が死亡して江青ら四人組が逮捕され、両派の争闘に決着がつけられました。三度の失脚からそのたびに復活した不死身の男は「中国的特色をもった社会主義の建設」を提起して、経済の改革開放路線の指導にあたりました。市場経済を社会主義の中で実現するというのが、中国的特色だということであれば、それは、確かに驚くべきことだ、とは思います。しかし、本来相容れないものである両者を並存させていくために、天安門事件(第二次)のような矛盾の噴出がこれから何度あるのか、それはまだ誰にもわかりません。中国政治経済分析
Aug 22, 2005
-

【1043夜】『生命とは何か』エルヴィン・シュレディンガー
【1043夜】『生命とは何か』 What is life? エルヴィン・シュレディンガー Erwin Schrodinger 岡小天・鎮目恭夫訳 1951・1975 岩波新書エルヴィン・シュレディンガーは1887年8月12日、ウィーンで生まれました。1043夜にはほとんど触れられていませんが、彼のもっとも重要な業績とみなされているものは波動力学の建設です。25年にハイゼンベルクによって行列形式による量子力学が提案されていましたが、26年、これと自分の波動力学が同じであることを証明。ふたつの理論は統一され、量子力学の新しい展開へとつながりました。戦時中からさらに活動領域の幅を広げ、この『生命とは何か』はその後の分子生物学発展へのきっかけになったといわれています。「そこに量子力学が介在し、そのことが生命組織に『自己』と『秩序』を形成させているという仮説については、つまりは量子生命論とでもいうべき仮説については、まだシュレディンガーから3歩も先に進めないでいるのである」と松岡正剛は記しています。つまり、60年以上前にシュレディンガーが考えたことはいまだに生命を考えるうえでの先端であり続けているということです。彼の発想の背後には、ショーペンハウアー哲学やインド哲学、とくにヴェーダンタ哲学(ウパニシャッド)がありました。シュレディンガーはヴェーダンタ哲学が提示した「梵我一如」の思想に感動します。梵我一如とは宇宙の最高原理であるブラフマン(梵)と人間の本体であるアートマン(我)とが同一であるという認識のことをさし、また、これらが同一であることを知ることにより、永遠の至福に到達しようとする思想です。この思想と量子力学のどこに接点が見出せるのか、正直にいってしまうと、私にはよくわかりません。量子力学もヴェーダンタ哲学も辞書の記述程度にしか知りませんので、それは当然だろうとは思います。ただ、それを結びつけて新たな思想を発見していったシュレディンガーは、やはり天才であるということだけはわかります。学問的業績というものは、多分、レンガを積み重ねていくような思考作業では生まれないのではないか、と思います。多くの発見や発明がひとつのひらめき、啓示から生まれています。それがどこからもたらされるのか、は誰もわかりません。真実はすでに目の前にあるにもかかわらず、そこに至る道に明かりが点っていない、そこの間に関係線がひかれていない、「わからない」とはそういうことではないか、と思います。シュレディンガーの卓見は、量子力学とヴェーダンタ哲学という常識的に考えればかけ離れたものの間に関係線を見出したことでしょう。わが世界観
Aug 12, 2005
-

【830夜】『心理学と錬金術』 I II カール・グスタフ・ユング
【830夜】『心理学と錬金術』 I II Psychologie und Alchemie 1944 カール・グスタフ・ユング Carl Gustav Jung 池田紘一・鎌田道生訳 1976 人文書院ユングを一度きちんと読みたいと思ったことは何度かあるのですが、まだきちんと読めずにいます。ユングに興味を持ったのは、心理学的なことというよりは易学からでした。易についての本をあちこち読んでいるうちにユングにたどりついたのです。ユングは彼の元型に近い考え方を持っているものとして『易経』に興味を抱きました。830夜の中に宣教師のリヒャルト・ウィルヘルムの名前が出てきますが、彼はユングから『易経』の話をきいて刺激を受け、中国に戻ったときに中国人の先生について『易経』を学び、ドイツ語に翻訳して発表しました。この本にユングは序文を載せています。この翻訳が西洋世界では易を広く知らしめるきっかけになったようです。実際のところ、私が興味をひかれるようになった易は、こうした「一度西洋世界を通過した易」でした。岩波文庫の『易経』も読みましたが、おそらくこれだけでは、易そのものに興味を抱くことはなかったと思います。ユングが易にみたものは、シンクロニシティの考え方でした。シンクロニシティとは、因果律の法則では説明できない「偶然の一致」のことです。ユングは人間の無意識はとても広い世界であり、この中心には自分自身を越えた超越的ななにか、ある種の神様の目のようなものがあると考えています。この目が動き始めると、自分の思ったことと実際に起こることが一致するといったシンクロニシティが起こってくるようです。易はそうした外の世界と自己の内側との一致をさぐり、その解釈によって占っていきます。また、運命は常に流れ、動き変転しているという考え方が基本にあります。陽が極まれば、陰に転じ、陰が極まれば陽に転じていく。ですから易は決定論的な占いとはかなり様相を異にしています。ユングはもともと神秘思想に親和性をもっていました。830夜でもポルターガイストが彼のまわりで起こったことが記されています。彼は自己の内側に二人の人格があったといっています。牧師の息子と「神」が浸透していくものすべてと近い老人です。この後者が「古い塔」であり、「オカルト」だと松岡正剛は述べています。おそらく近代以降、科学が発達し、理性でものごとをさばいていく中で、「牧師の息子」たる人格(それは合理性、意識、といったものでいいかえられるでしょう)のみが肥大し、不条理や無意識や本能、情緒といったものは抑圧されていったのです。しかし、いくら抑圧されようとも、それはさまざまな形で噴出してきます。錬金術は単に黄金を作り出そうとしただけではなく、永遠なる物、不死なるもの、完全なるものへの希求であったといわれています。金はその象徴であったのです。現代の西洋科学の発達の源はこの錬金術にあり、そこには科学から魔術や占星術まで広くさまざまなものが含まれていました。そこから合理的な要素を抽出したものが科学になっていき、いわば闇の中、裏面として現代まで流れているのが占いや魔術やオカルト、神秘思想などです。錬金術を研究することによって、ユングは「錬金術のみならずいっさいの神秘主義というものが、実は『対立しあうものの結合』をめざしていること、そこに登場する物質と物質の変化のすべてはほとんど心の変容のプロセスのアレゴリーであること、また、そこにはたいてい『アニマとアニムスの対比と統合』が暗示されているということ」に気づいていきます。ユングは人間の二面的な心理のあり方を統合する何かの象徴を「錬金術」や神秘思想に見たのです。カール・グスタフ・ユングは1876年7月26日、プロテスタントの牧師の子としてスイスで生まれています。母方に多くの霊能力者がいたらしく、彼がオカルトにひかれていく素地は充分にあったのです。元型論増補改訂版
Jul 26, 2005
-

【60夜】『陰翳礼讚』谷崎潤一郎
【60夜】『陰翳礼讚』谷崎潤一郎 1946 創元社・1975 中公文庫谷崎潤一郎、この文豪谷崎、大谷崎の作品をよく考えてみれば一作も読んだことがありません。川端康成も三島由紀夫も、一作や二作は読んでいるのに、谷崎に関しては一作もないというのはわれながら驚きでした。そのわけを考えてみますと、おそらく、倒錯的で耽美的なところがはなから読む気にさせなかったのだろう、と思います。『刺青』『春琴抄』『痴人の愛』から『鍵』『瘋癲老人日記』におよぶ耽美的系譜にはつねに異様に惹かれるものがあったので---と松岡正剛は書いていますが、私はこれらの作品のあらすじを聞いただけで「うわ、こら、あかん」と思ってしまいました。人はパンのみにて生きるにあらず、ですから、美に耽溺して生涯を暮らすというのも別にかまわないだろうとは思うのですが、どうも、うんざりしてしまうのです。自分自身の好みは乾いて明るくて簡潔なものですから、こういうねっとりと湿った隠花植物のような美は苦手です。ところで、『陰翳礼讚』ですが、今の日本家屋からは陰翳は完全に消え去っているのではないでしょうか。おそらく西洋建築や西洋の生活様式よりも日本の現代生活は異様に明るいものになっている、と思います。その主役は蛍光灯。すべての部屋に蛍光灯がつけられ、こうこうと明るい現代の日本家屋には伝統的な暗さはもはや望むべくもないでしょう。去年、台風がきて夜に数時間停電したことがありました。窓から見る暗い町に、昔はきっと夜になるとこういう風景が広がったに違いないと思いました。大都会江戸だって夜になれば濃い闇に包まれていたことでしょう。自動車の音もなかったでしょうし。学生のころ、日本最南端の波照間島へ行って、人家も街路灯もない最南端の岬に立ち星明かりの下に座って、これ以上暗くならない夜というのを初めて体験しました。聞こえてくるのは波の音だけ。完全に自然のままの闇や音を今では私たちはかなり特別なところへ行かないと体験できなくなっています。谷崎潤一郎は1886年7月24日東京日本橋に生まれています。一高入学後、校友会雑誌に小説を発表し始め、成績が下落。東京帝国大学国文科に入学しますが、中退。自然主義文学が盛んだった明治の文壇に異を唱え、倒錯的な官能美にみちた作品を発表しました。箏曲と朗読 源氏物語
Jul 24, 2005
-

【385夜】『剣禅話』山岡鉄舟
【385夜】『剣禅話』山岡鉄舟 1971 徳間書店たったひとりの人間の行動がその後の国の運命を大きく変えるということはあるものです。江戸無血開城のため、西郷隆盛と勝海舟の会談を実現させた山岡鉄舟の駿府直談判もそのひとつでしょう。怒涛の勢いで江戸へ攻め上ってくる官軍に対し、大半の幕臣は恐れをなしてなすすべを知りません。勝海舟は、江戸を離れることさえできれば、自分が行って西郷と直談判をしても…、と考えていたようです。最初、海舟は鉄舟の義弟で幕臣の高橋泥舟を使者にと考えたようですが、泥舟から鉄舟を紹介され、ふたりは初めて会います。ひとめで鉄舟の人物を見抜いた海舟は「この男でダメなら、誰がいってもダメだ」と思ったといいます。使者としてもっともふさわしいのは「誠実で機転が利き死ぬ覚悟もできている肚のすわった人間」でした。駿府で鉄舟と会談した西郷は、「金もいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらぬ人は始末に困るが、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられない」と鉄舟の人物に感銘を受け、その後の西郷・勝会談が実現します。徳川家に示された降伏条件は当初予想されたものよりはるかにゆるやかなものであり、江戸は戦火から救われたのです。これが鉄舟の社会的に見た人生のハイライトといえるのでしょうが、松岡正剛はこのことについてはさらりとふれているにすぎません。それよりも、むしろ、鉄舟が肚をつくるために、剣と禅の道をひたすら歩んだ一修行者であったことを説いています。伊藤一刀斎の剣法の達人浅利又七郎に全く勝てず、寝てもさめてもその幻影から逃れられずにもんもんとする彼の姿。それが、「ある日、豪商の商売の話をゆっくり聞いているうちに何かの気合を会得し」、卒然として何かを体得するのです。ここの描写は、禅の修行者が「悟る」ときのさまとよく似ており、興味深い出来事です。「別に何かの社会的活動に貢献するでなく、ただ自己実現をめざした。(中略)魂胆というのか、それを鍛えることのほうがよほどおもしろかったのであろう」と松岡正剛は書いていますが、そうして、ただひたすら自己の研鑽に励んだ男が結局は江戸を救ったのです。山岡鉄舟、本名・高歩(たかゆき)、通称・鉄太郎は1836年7月23日(天保7年6月10日)江戸本所に御蔵奉行の小野朝右衛門の四男として生まれました。北辰一刀流の剣法を学び、山岡静山に槍術を学んでいます。静山急逝後、請われて妹と結婚し、山岡家をつぎました。その弟が高橋泥舟です。剣禅話
Jul 23, 2005
-

【908夜】『パサージュ論』ヴァルター・ベンヤミン
【908夜】『パサージュ論』(全5巻)Das Passagen-Werk 1982 ヴァルター・ベンヤミン Walter Benjamin 今村仁司・三島憲一ほか訳 1993 岩波書店油断をしていると月日はどんどん過ぎていってしまいます。まさにパサージュ…。ベンヤミンを読んだことはないのですが、松岡正剛の文章を読んでいるだけで、この人はたぶん松岡好みに入る人だろう、と感じました。パサージュ、通過していくこと、境界線の意識。松岡は何かの中心より、ものともののアワイに興味を引かれる人です。境界そのものよりも、境界線をまたいでいくその通過の過程への興味。多分、ひとつの定まったものについて定義し、考えたほうがものごとはラクではないかと思います。明確にくぎられたあることの中心部に的を絞って考えること。しかし、そういうことでは見えなくなることもまたたくさんあり、周辺部の薄明かりやグラデーションの中にしかないもの、通過するスピードの中でしか浮かび上がってこないものがあります。後半、パサージュとは何かについての松岡はこう言います。パサージュとは通過すること、窯から茶碗をひきだすこと、書物を店頭から持ち出してページを開くこと、写真家が写真を撮ること…。それら無数の行為が配列されて布置される、それが都市というもので、社会というものだというのです。パサージュから生まれながら、パサージュではなくなっていくものを「複製」と呼んでいます。写真を例にとれば撮影者、撮影された写真をみるその瞬間にはパサージュがあります。パサージュは通過、ある意味で生き物のようなもの、ある流れ、ある動き、のようなものです。「では、これらの行為のなかでどこからが複製なのか。答えはあきらかだ。パサージュを忘れた者の意識のなかで、そのとたん、それは複製になってしまうのだ!」と松岡は述べています。「パサージュの積み重ね、それをぼくは『編集』とよんでいる」都市の中でますます深い眠りに陥ろうとする集団無意識をすくいあげる方法がベンヤミンがとったパサージュであり、彼はそれを完成させることなく亡くなります。1892年7月15日、ベルリンの裕福なユダヤ系の家庭に生まれたベンヤミンは33年、ナチスの政権奪取とともにパリに亡命。40年ナチスの侵攻でアメリカに亡命を試みますが失敗して捕らえられ、フランス国境に近いスペインの町ポル・ボウで服毒自殺しました。パサージュ論(第1巻)
Jul 15, 2005
-

【912夜】『白書』ジャン・コクトー
【912夜】『白書』Le Livre Blanc 1927 ジャン・コクトー Jean Cocteau 山上晶子訳 1994 求龍堂これは03年12月25日に発表されています。2年前のクリスマス、このころは、かなり夜も遅くなってからインターネットに登場することが多かったので、ほとんど新作は翌日、職場のパソコンで見ていました。ところが、この夜の分はフィルターがかかって見られません。いったいどういうわけだろう、と思って家に戻り、自分のパソコンで画面を見て、納得しました。こりゃ、役所のパソコンでは見られない…。それにしても、濃い恋愛関係だなぁ、と関心しながら読みました。男色者というより男に好みが勝ったバイセクシャルだったのだろうな、と。女たちだってコクトーにほれているし、彼自身女とセクシャルな関係を持つこともできたのですから。ずらーっと並んだ名前を見るだけでも壮観です。女のほうがかっこよく書かれているように見えるのは、この文章以外にその人たちを知らないからでしょうか。男はレイモン・ラディゲ、ディアギレフなど一度は名前をきいたことがある人ばかりですが、女で知っているのはコレット、ココ・シャネル、エディット・ピアフくらいです。あとは駆け出しの女優、菫色の眼をした伯爵夫人、サド侯爵の末裔、ロートレックが描いたスケーター、ロシア皇帝の姪…、なんだかとんでもない人々が並んで、こちらの想像力のあちこちがくすぐられるのです。コクトーをとりまいた男と女をスナップショットのように切り取って、コラージュした、それが912夜です。では、ぼくが一番好きなコクトーの言葉を書いておく。「私は人々がオリジナリティーにこだわることが大嫌いなだけなのである」---と松岡正剛はしめくくりました。貼り付けられた言葉の断片によって浮かび上がるのは、コクトーに影響を与えた人々、そして、コクトーが描くラフなスケッチのようなコクトー像です。コクトーは1889年7月5日パリ近郊のメゾン・ラフィットに三人姉弟の末っ子として生まれます。父親が98年に自殺。タナトスの刻印の始まりでした。Matarasso, 1957(コクトー)Mourlot Lithograph On Arches 高さ63センチ×幅48センチ
Jul 5, 2005
-

【64夜】『城』フランツ・カフカ
【64夜】『城』Das Schloss 1914 フランツ・カフカ Franz Kafka 原田義人訳 1966 角川文庫・1970 角川文庫・1981 新潮文庫 他フランツ・カフカは1883年7月3日オーストリア・ハンガリー二重帝国治下のプラハで、中産階級のユダヤ人家庭に生まれます。商人だった父は、きわめて権威主義的な人物で、この父の存在は終生カフカに閉塞感をもたらし、作品にも大きな影をなげかけたといわれています。彼はプロの作家ではなく、労働災害保険協会につとめながら、その合間に作品を書いたのでした。カフカの作品を読んだことはありません。この先もおそらく読まないでしょう。「何もおこることもなく、『城』は終わってしまう。未完とはいえ、文庫本でも552ページである。読後にはなにも残らない。」そんな本を、それでも読む人がいるんだなぁと逆に感心します。松岡正剛によれば、「そこにはただ、『届かないこと』『伝わらなかったこと』、そして『はじめからなかったかもしれなかったこと』だけが、ある。」ということなのですが、なんだか謎かけ問答のようでさっぱりわけがわかりません。カフカの作品のテーマは、理解することも抑制することもできない、なにか漠然とした力におびやかされつづける個人の孤独感であり、挫折感であり、重くるしい罪悪感だということです。読んだことがありませんので、これは辞書のからの引用ですが、こういう感じがしたので、手にとる気がしない作家だったということでもあります。カフカは、生来の不安症や憂欝症に加え、17年には結核をわずらって、7年間の闘病の末、24年にウィーン郊外キーリングのサナトリウムで息をひきとりました。あんまり幸せな人じゃなかったのだろうなと思えてきます。まあ、幸せな人は文学なんて書けないのかもしれません。幸せはとらえどころがなく、不幸よりずっと書くことが難しいものだと思います。「幸せな人」というのが本当は非常に稀だからなのかもしれません。さらに、なぜか苦悩や不安や怒り、いらだちを書くほうが文学的価値が高いことだと思われている節があります。ほんとうにそうなのでしょうか?詩と真実は、もっと安らかで穏やかで、満ち足りたものの中にあるような気がします。近代の終焉におけるフランツ・カフカと表現主義者たち
Jul 3, 2005
-

【479夜】『デミアン』 ヘルマン・ヘッセ
【479夜】『デミアン』 Demian 1919 ヘルマン・ヘッセ hermann Hesse 高橋健二訳 1951 新潮文庫ヘッセの小説で読んだといえるのは『車輪の下』『郷愁』の二作だけです。ですから、ヘッセの作品のうちでは青春文学の部分にしか触れていないことになります。読んだのは中学生のころです。母に買ってもらった100冊を越す文庫本の中にありました。旺文社の文庫本、あのころは、まだ一冊一冊が箱に入っていて、文庫本といいながら、重厚な造りでした。ヘルマン・ヘッセは1877年7月2日、ドイツのシュワーベン地方のカルプに生まれています。へッセの父親は北方ドイツ系ロシア人で、新教布教師としてインドにわたり、そこでドイツ人の牧師の娘と結婚したのです。この家庭環境では、ヘッセは当然のように父のあとをついでプロテスタントの牧師になることを期待されたでしょう。彼はマウルブロンの神学校からチュービンゲン大学に進みます。ここまでは家族の期待どおりでした。しかし、何かに彼は耐えられなくなったのでしょう。「ここでヘッセは家庭の善意が押しつけつづけた道を唾棄することにする」と松岡正剛はヘッセのドロップアウトをこう表現しています。家庭の善意が押しつけ続けた道…、『車輪の下』はヘッセの体験を反映した小説であり、ずっと、格式ばった教育に対する彼の反発が描かれていると思ってきました。しかし、彼が”車輪”として象徴させたかったものの中にはその”家庭の善意が押しつけ続けた道”というのがあったのかもしれません。親は子どものためを思っていろいろなことをします。ヘッセの両親はプロテスタントの牧師を素晴らしい仕事だと思っていたでしょう。だからこそ、ヘルマン少年に神学校を勧めたのであり、牧師への道を用意したのでした。しかし、このあたりがむずかしいところで、親子、兄弟姉妹といえど、それぞれ異なっています。親にとっていいものが必ずしも子にとっていいものかどうかは定かではないということです。それは教育や環境などによってどうこうできるようなものではなく、もっと根源的な何か、その人の魂の違いという気がします。カール・グスタフ・ユングはそのことを「ある人に合う靴も他の人には窮屈である。あらゆるケースに通用する人生の秘訣というものはない」と言っています。ヘッセはある意味で自覚的な強い枝でした。たわんだままで終わらず跳ね返し、自己の魂の導きに忠実に歩んだのです。いっそうたわめられて折れてしまうか、またはたわめられ本来とは異なる姿を耐えていくか…。メルクリンビッグトランク・テッシン(ジオラマ)[Z4321]ヘルマン・ヘッセが愛したテッシン州モンターニョーラ近辺に走る列車を、1/220スケールのジオラマとして再現。
Jul 2, 2005
-
【663夜】『孤独な散歩者の夢想』ジャン・ジャック・ルソー
【663夜】『孤独な散歩者の夢想』Les Reveries du Promeneur Solitaire 1782 ジャン・ジャック・ルソー Jean Jacques Rousseau 今野一雄訳 1960 岩波文庫ジャン・ジャック・ルソーは1712年6月28日に時計職人の子としてスイスのジュネーブに生まれました。誕生数日後に母がなくなり(産褥熱かなにかだったのでしょう)10歳のときには父親も失踪して、おじとおばに育てられます。このあたりから彼の身近な人との縁のなさは始まっていたのでしょうか。13歳で彫刻家に弟子入りしたものの3年で逃げ出し、ヴァラン男爵夫人にめぐりあってその庇護のもと、さまざまな教育を受けています。この幸せな7年間が後のルソーの基礎をかたち作ったのですが、結局10年で夫人にも嫌われてしまいます。その後、パリへ出、しばらくは不遇でしたが、50年にディジョン・アカデミーの懸賞論文に『学問芸術論』が入選し、一躍脚光を浴びます。一時はディドロ、ヴォルテール、ダランベールらと親しく交流しますが、やがてそのいずれとも絶交状態となります。思想的な対立がその一因ではあったでしょうが、こうも片っ端から嫌われたというのは、よくいえば個人を重視する、悪くいえば自己中心的なルソーの性格に原因があったようです。フランス国外への亡命を余儀なくされたときはスイス、イギリスなどを転々としました。このとき保護してくれたイギリスの哲学者ヒュームとも被害妄想から一方的に仲違いしています。『告白』は自叙伝というよりも、当時としては自己の暴露本に近い内容でした。何しろ、子どものころ手癖が悪くて盗みを働いていたことや、内縁の妻テレーズとの間にできた子ども5人を次々に捨てたことなどを赤裸々に描いているのです。『告白』を書くにいたったルソーの経緯についてに松岡正剛はこう書いています。--ルソーを迫害しつづけた者たちは、そのあまりに激しい憎悪ゆえに、たえず攻撃の手をゆるめずにルソーの苦悩をかきたてればよいものを、ついつい初めっからあらゆる手段を使い切ってしまったということだ。ルソーに何ひとつ残させまいとして、攻撃者たちは何もすることがなくなってしまったのである。ルソーはそこに一縷の残された自己探求の突破口を見出した。加えてルソーには「もはや世間に戻る気がまったくなっていること」が強みになっていた--失うものは何もない、というのが結果的に古典を生み出す力になったのですが、彼自身は最後、「世間に押しつぶされるように」死んでいます。これもまた、歴史に名を残す天才ゆえの「負の先払い」のひとつだったといえるのでしょう。孤独な散歩者の夢想晩年全くの孤独に閉ざされたルソーは、日々の散歩の途上に浮び上がる想念を、つれづれの印象を、事件を、あるいは生涯のさまざまの思い出を記し、人間と自己を見つめ続けました。
Jun 28, 2005
-

【762夜】『パンセ』上下 ブレーズ・パスカル
【762夜】『パンセ』上下 Pensees 1670 ブレーズ・パスカル Blaise Pascal 津田穣訳 1953 新潮文庫ISIS編集学校には守・破・離の三段階があります。今日からその真ん中にあたる11期・破が始まりました。私が7期・破の教室で師範代だったときの学衆のおひとりから、こんなバトンをいただきました。題して「ブックバトン」というそうです。どなたか受け取ってください。注)今日→7月25日です。<ブックバトン>1、蔵書の数 100冊そこそこというところです。本は図書館から借りるか、読み終わったら中古本として売ってしまいますので。狭いアパートに大量の本は置けない。2、今読みかけの本 or 読もうと思っている本 『ローマ帝国衰亡史(6)』エドワード・ギボン ちくま学芸文庫『物語の作り方』 G. ガルシア=マルケス 岩波書店『西行』白州正子 新潮文庫『西行巡礼』山折哲雄 新潮文庫『ビジョナリー・カンパニー(2)』ジェームズ・C・コリンズ 日経BP社あといっぱいあって書ききれず。3、最後に買った本 『日本百名道新版』須藤英一 大泉書店『建築map大阪/神戸』 TOTO出版4、特別な思い入れのある5冊 『新日本大歳時記(春)』 講談社『新日本大歳時記(夏)』 講談社『新日本大歳時記(秋)』 講談社『新日本大歳時記(冬)』 講談社『新日本大歳時記(新年)』 講談社日々使っておりますので…。あとはいろいろありすぎて5冊にはとても絞れません。5、バトンを渡す人 「千夜千冊」ファンのみなさまへと、前置きが長くなりました。ブーレーズ・パスカルは1623年6月19日、フランスオベーニュ地方のクレルモンフェランで生まれました。天才的数学者にして宗教家、哲学者、38歳で亡くなったにもかかわらず多彩な経歴です。『パンセ』にはよく知られた言葉が入っていますが、おそらく最も有名なのはこのふたつ。・クレオパトラの鼻、それがもう少し低かったら大地の全表面は変わっていたであろう。・人間は自然のうちで最も弱い一本の葦にすぎない。しかしそれは考える葦である。なぜクレオパトラなのかよく前後のことはわかりませんが、もしパスカルがこの一文を書かなかったら、クレオパトラの有名度は一段低かったであろう、といえるほどに有名な文章です。ふたつめの「考える葦」はこの夜の後半で松岡正剛が原文を引用しかなりくわしく語っています。松岡も常に「弱さ」「負」について語る人ですが、パスカルのこの「フラジリティ」に目を向ける姿勢を「パスカルはとっくに『弱さ』や『小ささ』が大きな自然や巨大な宇宙に匹敵することを知っていた。それは人間の思考を媒介するかぎり、強弱と代償が逆転するものなのである」と述べています。知恵は、われわれを幼な心に向かわせる…、「幼な心」にぐっときます。パスカル考『パンセ』を、それが本来構想されたキリスト教護教論の枠組みのもとに読み直す。
Jun 19, 2005
-
【767夜】『一茶俳句集』小林一茶
【767夜】『一茶俳句集』 小林一茶 丸山一彦校注 1990 岩波文庫7月18日からISIS編集学校の12守が始まりました。私は師範代として再度パソコンの前に座っています。この学校の教室にはそれぞれユニークな教室名がついています。教室開講前にいくつかの案を師範代が松岡校長に出しそれを校長が編集してそれぞれの教室名が決まります。オノマトペイア好きの校長のこととて、名前には「ぴんぴんもぎもぎ」などというのもあります。私が5期の守でお世話になった教室も「うふふわふわ」という早口言葉のような名前でした。今回の私の担当教室名は「ハイカイ自在」といいます。ハイカイは俳諧と徘徊をかけられたもの、と思っています。私は俳句を詠みますし、あちこちオートバイや自転車で旅してうろつくことが好きだからです。人名が登場することもあります。師範代の姓名が教室の一部に登場したり、そう、「一茶エッシャー」と人名のみでなりたっている教室もありました。一茶、松岡正剛の中では好きなリストの上位にくる俳人ではないか、と思います。松岡はこの夜の中で一茶のことをこう述べています。・一茶は決してのほほんとした俳人ではなかったのである。むしろ逆に「蝿」も 「日本」も同じサイズで観察できた俳人だった。・一茶は芭蕉を愛し、蕉風に学び、そのうえで芭蕉と拮抗したかった。そういう激し いところもあった。・いわば「負け惜しみ」の気概ももっていた。しかし、そのような「負」を「惜しむ」と いう感覚こそは、俳諧においては一茶の卓抜な透徹ともなったのである。・不耕の遊民としての自虐があって、それが感覚の律動に転位して、独自の俳諧 のリズムとなったのだ。1763年6月15日(旧暦では宝暦13年5月5日)一茶は現在の長野県柏原の農家に生まれました。3歳で生母と死別し、ここから安寧とは程遠い生涯が始まります。これは767夜の冒頭にも松岡正剛が綴っていますが、15歳で江戸に出て、51歳で故郷に戻り、継母や異母弟との遺産相続を巡る争いに勝利します。結婚もして三男一女を授かりますが、そのことごとくを幼くしてなくし、妻にも先立たれます。長女を亡くしたときに詠んだのが「露の世は露の世ながらさりながら」です。五七五の中に露の世が二度登場し、わずか十七音の中に一茶の言葉にならない深い悲嘆の思いがこめられています。もちろんこれは一茶の才能と技巧の力といえばそういえないこともありません。この夜の中で松岡正剛は一茶のさまざまな知られざる顔をスケッチして見せてくれています。ニュース好きなメモ魔の観察者という一茶の姿、とはいえ、いずれの時代においてもどのような天才も偉人も時代の子であることからは逃れられません。時代の空気を敏感に感じつつ、さらに時代を越えるものを生み出すのが天才といわれる人たちでしょう。一茶はそういう句を詠んだのです。しかしまあ、「花散りてゲツクリ長くなる日かな」には驚きました。ゲックリかぁ、やられたなぁ、という思いです。一茶事典俳人・小林一茶に関する情報を網羅的に集めています。年譜、評釈一覧、作風、参考篇、翻訳文献一覧で構成。参考篇には一茶関係の人名・地名解説、俳画一覧、研究文献目録等を収録、また翻訳文献一覧では英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語訳等の句を付載。巻末に事項索引、人名索引、地名索引。
Jun 15, 2005
-

【202夜】『ゲバラ日記』エルネスト・チェ・ゲバラ
【202夜】『ゲバラ日記』 El Diario del Che en Bolivia 1968 エルネスト・チェ・ゲバラ Ernest Che Guevara 朝日新聞外報部訳(朝日版)・高橋正訳(角川版) 1968 朝日新聞社・1974 三一書房・1990 角川文庫チェ・ゲバラ、写真で見る限り、女にもてただろうなぁと思います。危なそうな香りがいっぱいで、最後はまともな死に方をしないだろう、という雰囲気です。写真の重要な小道具は葉巻です。葉巻に成金かギャングの象徴のような印象をもつのは私だけでしょうか。葉巻は紙巻タバコと違い、高価ですし、保存にも気を使わなければいけません。ちょっと温度が高いとタバコシバシムシが孵化して穴だらけになりますし、すぐにカビが生えて味が台無しになります。ぜいたく品の極みですね。その葉巻を左翼ゲリラの指導者がずっとくゆらしていたというのですから。キューバ産の葉巻だったのでしょうか。ゲバラは完全なる共産主義の実現を目指していました。60年代というのはそういう時代だったのですね。共産主義が光り輝いていた時代、ユートピアがそこにあると信じられていた時代だったのでしょう。ソ連型の社会主義はゲバラが考えていた革命の結実とは違っていました。実際、本当の共産主義国家というのは地上に出現させることが難しいものだと思います。その後の社会主義国家の行き詰まりと冷戦の終結を時代を追ってみていくと、あの時代、誰もがひとつの夢を見ていたのだろうと思えてきます。バブルもひとつの夢なら共産主義国家もひとつの夢だった、すべて、夢は枯野をかけめぐって終わるのです。よりよきものは革命家だけでは作れないのだろうと思います。チェ・ゲバラは1928年6月14日、アルゼンチンのロサリオ市で造船業を営む比較的裕福な家庭に生まれています。本名をエルネスト・ラファエル・ゲバラ・デ・ラ・セルナといい、「チェ」はアルゼンチンのスペイン語で相手に呼びかけるときに使う言葉に由来するあだ名です。彼は革命家として日本の坂本龍馬を尊敬していたということです。アントワーヌ・プレジウソ“チェ・ゲバラ”※伝説のキューバの革命家“チェ・ゲバラ”の肖像が...
Jun 14, 2005
-

【443夜】『五輪書』宮本武蔵
【443夜】『五輪書』 宮本武蔵 1985 岩波文庫 渡辺一郎校注宮本武蔵の前半生に関してくわしいことはほとんどわかっていません。1584年ころの誕生で、『五輪書』に生国は播磨とありますので、現在の兵庫県高砂市周辺が出生地と考えられます。13歳で初めて剣の勝負に勝ち、以来、30歳までに60数度の勝負で一度も負けなかったといいます。彼の時代、勝負はすべて真剣で、負ければそのまま死につながるのですから、とても尋常の沙汰とは思えません。その超人的な強さはすでに江戸時代から歌舞伎や浄瑠璃として演じられていたといいます。現代にいたるまでも剣豪の代名詞ですし、小説やドラマ、漫画まで、今も武蔵の活躍は続いています。武芸者であると同時に、意外にも彼は優れた画家でもありました。重要文化財『枯木鳴鵙図』、『蘆葉達磨図』『布袋観闘鶏図』などが知られていますが、いずれも簡潔な墨の線で、一息に空間を切り取るように描いています。 剣の切っ先を思わせる枯れ枝の先に止まる鵙、枝の途中には這い登っている芋虫がいます。鵙の鋭い眼光、この直後、静けさが破られる瞬間…。ここにはそのまま、武蔵が命をかけた勝負の瞬間と同じものが現れてきます。この絵を描くのに時間は10分もかかっていないのではないかと思われます。しかし、この一本の線を引くことの中にどれほどの鍛錬と気力と精神の集中が凝縮されているか、を思うと、やはりものすごい絵だと思い知らされます。「線は、描いた人間の観察力はもとより、意志の強さ弱さ、決断の早さ遅さから、そのときの感情のありかたや体調までを正直にあらわします」と画家の永沢まこと氏はいいます。この絵から感じられるのは何の力みも迷いもない見事な集中と、思い切りのよさ、でしょうか。武蔵は『五輪書』で「兵法の理にまかせて諸藝諸能の道を學べば、萬事に於て我に師匠なし」と語っています。彼の二天一流という剣法は彼自身によって編み出されたあくまで実戦むきの合理的なものです。『五輪書』が読み続けられているのは、そこにいつの時代にも通じる思想が書かれているからでしょう。松岡正剛は「武蔵は人生にも『渡』があって、その『渡』が近いことを全力で知るべきだと言っている。それがまた短い試合の中にもあって、その僅かな瞬間にやってくる『渡』にむかって全力の技が集っていく。そう、言うのである」と書いています。宮本武蔵は『五輪書』をまとめたあと、1645年(正保2年)死期を悟り自戒の書「独行道」21カ条を書きのこし、6月13日(旧暦では、5月19日)に亡くなりました。枯木鳴鵙
Jun 13, 2005
-

【19夜】『マリリン・モンローの真実』上・下 アンソニー・サマーズ
【19夜】『マリリン・モンローの真実』上・下 Goddes 1985 アンソニー・サマーズ 中田耕治訳 1988 扶桑社気がついたら6月が過ぎ去り7月も上旬を終わろうとしています。月日は百代の過客にして…、と述べたのは芭蕉です。「光陰矢の如し」といったのは中唐の詩人李益です。子どものころはこんなことは考えもしませんが、20歳を過ぎたころからこれはひしひしと身に迫ってきました。これが恐ろしい真実だというのは、過ぎ去ってしまうとき、時は何の痛みも、衝撃もわたしたちに残さないからです。5月の途中まで書いてそれからなんとなく遠ざかっていたこの「伴走日記」。去年の千夜満願の7月7日も過ぎて、あの良寛の夜の衝撃がつい昨日のように思い出されます。しかし、もう1年たったのでした。楽天の日記は前月までは書き込めるのですが、それより前までさかのぼることはできず、5月の後半部分は棚上げになってしまいました。今日は6月1日生まれのマリリン・モンローを取り上げます。20世紀ハリウッドを代表するセックス・シンボル(むしろセックスシンボルという言葉が彼女のために作られたという印象さえあります)。その人生は華やかではありながら、悲惨でもあり、その死は本書でもとりあげられているように、いまだに多くの謎に包まれています。マリリン・モンロー、本名ノーマ・ジーン・ベーカーは1926年6月1日、ロサンゼルスで生まれています。母が精神を病んでいたため、孤児院、里親のもとを転々とする多難な子ども時代を送ります。16歳でこの境遇から逃れるために結婚し、20歳で離婚。軍需工場で働いていたところをスカウトされてポスターのモデルに起用され、この写真が大反響をよびます。その後、彼女は20世紀フォックスと契約を結び、50年代半ば、アメリカが最も明るく力を持っていた時代にハリウッドを代表するスター女優になっていきます。彼女の何がこれほど世界中をひきつけたのか、はわかりません。その時代の空気にあまりにもぴったりはまっていた、とでもいうべきなのでしょうか。初の主演は52年の『ノックは無用』、最後の作品が61年の『荒馬と女』ですから、活躍期間は10年に満たないのです。マリリン・モンローをめぐる本はまことに多い、と松岡正剛は欄外に記しています。華やかなカリスマ性と、悲劇、そして謎、それらが永遠のスターの条件だとしたら、彼女ほどぴったりあてはまる人は他にいないのではないか、と思えるのです。マリリンモンローサンデーBモーニング版シルクスクリーン 91cm×91cm(シートのみ)
Jun 1, 2005
-

【121夜】『サルバドール・ダリが愛した二人の女』
【121夜】『サルバドール・ダリが愛した二人の女』Persistence of Memory 1985 アマンダ・リア Amanda Lear 北川重男訳 2001 西村書店日付をもとに伴走日記を書くようになってから、「千夜千冊の小窓」をよく利用するようになりました。その日が誕生日の有名人の名前を入れてみて、ヒットすればそのページが現れます。なければ「○○にまつわる一冊を見つけられず」というあえないお言葉が提示されます。サルバドール・ダリは1904年5月11日スペインのカタルニャで裕福な家庭に生まれています。美術に全く興味がない方でも彼のどろんととろけたような時計の絵は目にされたことがあると思います。彼には全く同じ名前の兄があり、彼が生まれる9ヶ月前に亡くなっています。親は生まれ変わりと考えて、死んだ子と同じ名前をつけたのでしょうが、ダリ本人にとって、これはどんな感じがするものだったか、ちょっと気の毒な気もします。サルバドール・ダリを「小窓」に入力したところ、現れたのがこの本だったというわけです。「けれども、ここに紹介したようなアマンダ・リアのことを知っている日本人はごく少数だろう。本書もまったく話題になってはいない。アマンダ・リアは忘れられたのだ。」と松岡正剛が書いているように、私は全く知らない名前でした。日本のどこかのテレビ局が「あの人はいま」という企画でとりあげてくれないかなと思います。アマンダ・リアは1945年生まれ、30歳になったら自殺するつもりだったということですが、「亡くなった」とは書いてないので、きっとまだどこかで生きていらっしゃるのでしょう。それにしても彼女をめぐるセレブ(60年代はこうは言わなかったでしょう。きっと2020年ごろにはディスコみたいに骨董品の言葉になっているのではないかと思います。)たちの名前を見るだけでへぇ~、と感心してしまいます。こういう人たちの世界こそまさに「スモールワールド」なのね、という具合。ダリ生誕100年記念デミタスカップ&ソーサー6客セット シーズン1
May 11, 2005
-

【156夜】『本覚坊遺文』井上靖
【156夜】『本覚坊遺文』 井上靖 1981・1984 講談社文庫井上靖は私が好きな作家のひとりです。しかし、『本覚坊遺文』はまだ読んでいません。ヘミングウェイも好きな作家ですが、なぜか『老人と海』はまだ読んでいません。この二人の作家の文章の共通点は簡潔でわかりやすいということです。文章によけいな装飾がなくシンプルです。私はすべてにおいてそういうものが好みです。井上靖の作品では映画化もされた『天平の甍』や『敦煌』、ジンギスカンを扱った『蒼き狼』、ナイロンザイル切断を題材にした『氷壁』などが有名でしょう。もちろんこれらの作品もすべて読み、いずれも好きですが、ダントツに好きなのが彼の自伝的三部作『しろばんば』『夏草冬濤』『北の海』です。特に彼の旧制中学時代を扱った『夏草冬濤』は何度読んだかしれないくらい読みました。靖の分身である洪作少年は中学で一級上の自由奔放な文学少年たちと出会います。彼らと洪作の中学の日々が綴られていて、特別な大事件が起こるわけではないのですが、きらきらした明るさに満ちています。こういう自伝的作品にありがちな屈折した自意識や反抗心、鬱勃とした感情などというのがなく、まことにあっけらかんとした青春前期の少年の日常が綴られています。井上靖は過剰なものがあまり好きではないのだろう、と思います。この『本覚坊遺文』について、松岡正剛は「淡泊ではあるが、滋味深い味」と言っています。井上靖はもともと簡潔で淡白なものを尊しとした作家ではなかったか、と思うのです。同じく彼の作品である『闘牛』や『猟銃』といった作品の主人公の姿勢は「虚無的な行動主義」と評されることがあります。何かに熱中しながらもどこかいつも醒めている、ドラマに埋没し酔ってしまうということがない、そういう姿勢は井上靖自身のある一面を反映しているのだと思います。井上靖は1907年5月6日、軍医であった父の赴任先である旭川で生まれました。その後も各地を転々とし、5歳からは両親と別れて静岡県湯ヶ島で戸籍上の祖母に育てられます。このあたりの事情は『しろばんば』に描かれています。蒼き狼 成吉思汗(ジンギスカン)の生涯井上靖の小説を原作に、モンゴル帝国の創始者ジンギスカンの生涯を描く豪華Castの歴史大作。【出演】加藤剛、平幹二郎、仲代達矢、倍賞美津子、田中邦衛、泉谷しげる、神崎愛
May 6, 2005
全197件 (197件中 1-50件目)
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0942 30代を無駄に生きるな
- (2025-11-28 00:00:15)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 飛越 [ 馳星周 ]/競馬しかも障害レー…
- (2025-11-28 10:30:04)
-








