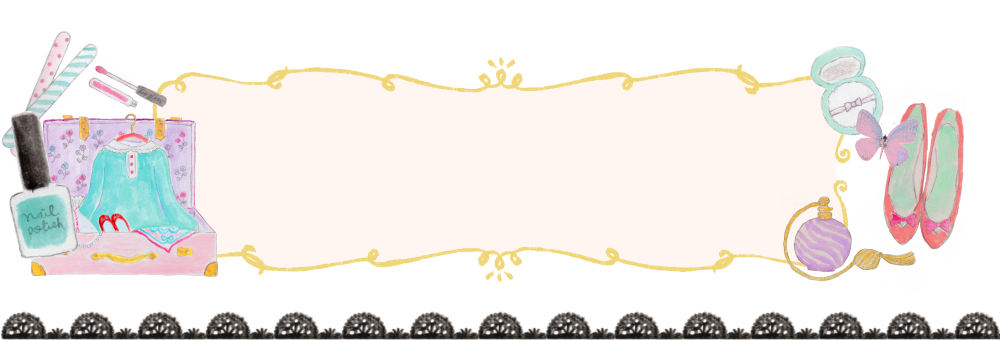テーマ: +TVで見たあの品は?+(45)
カテゴリ: 観光
先週の鉄腕DASHでは、江戸時代の双六をしながら浅草の名物を探す
という特集をやっていました。
もうなくなってしまったものも多くありましたが、歴史を学びながら
浅草名物を堪能できるなんて、面白いと思いましたね。
それでは、職人が受け継いだ技、味をお楽しみください。
長命寺 元祖桜もち

享保2年(1717年)初代山本新六が隅田川土手の桜の葉を集め、塩
漬けにして桜餅を考案、向島の名跡長命寺の門前にて売り始めてそれ
から二百八十年余、隅田堤の桜と共に名物となった。
山本山 お茶
山本山は、元禄三年(1690年)、初代山本嘉兵衛が宇治の美味しい
京都より江戸・日本橋に出てお茶の商いを行った事が始まり。
山本山と言う名前は、江戸期に発売され当社の売れ筋商品であった、
宇治煎茶の商品名「山本山」に由来し、昭和16年に法人「株式会社
山本山」の社名へ正式に採用しました。
伊勢半本店 小町紅

江戸時代より継承する匠の技で、紅花にわずか1%のみ含まれる赤い色
素が抽出され、女性の口元を彩る「小町紅」が作られます。それは、
自然の神秘が醸し出す魅惑の色彩。
根岸 笹の雪
元禄四年(約三百十五年前)上野の宮様(百十一代後西天皇の親王)の
お供をして京より江戸に移り、江戸で初めて絹ごし豆富を作り根岸に豆
富茶屋を開いたのが江戸のれんの始まりです。
豊島屋 白酒

時は江戸、慶長年間(1596~)と言えば太閤秀吉の晩年にあたり、
その城の外濠、北岸は江戸湾から隅田川、日本橋川と入って石垣の石
材などを陸揚げする鎌倉河岸(「江戸切絵図」では竜閑橋と神田橋の
間、鎌倉町。現在の千代田区内神田二丁目)で初代豊島屋十右衛門
(としまやじゅうえもん)がお城の普請で集まった多くの武士、職人、
商人達をお客様に酒屋及び飲み屋を始めたのが豊島屋のおこりです。
今戸 火鉢

下総千葉家の一族の配下の者が武蔵の浅草辺で土器や瓦を造りだした
のに始まると伝う。続いて徳川家康江戸入城に際し、三河から二人の
土風炉(茶道で湯を沸かす火鉢)師と土器師を連れて来た。
松木宗四朗と松井新左衛門で、暫く市内に住んでいた。次にまた三河
の土屋という火鉢師も市内で土器を造っていたが、明暦の大火後、瓦
焼の今津(今の今戸)に移った。
八百善 江戸料理

歴代将軍やペリーも舌鼓を打ったという高級料亭「八百善」のこと。
デパ地下のおせちコーナーで、八百善を発見。
江戸時代の料理を再現したおせちには、何度も裏ごしを重ねたきんと
ん、鯛のすり身と皮で、切り身に見立てたかまぼこなど、手間を惜し
まず作られた料理の数々。それが江戸料理たる所以。
淡島屋 かる焼き

「かる焼き本舗北島」は、大正時代創業。淡島屋はもうなく、現在こ
ちら以外かる焼のお店は残っていない。北島宏吉さんがかる焼の最後
の職人という。
かるやきとは「厄が軽くなる」とお見舞い品として重宝され、袋の金
太郎の挿絵も「病に勝つ」という意味。もち米の粉を砂糖水でのした
ものを切り分け、プレス機でつぶすと四角い種が丸いせんべいに。
それに蜜を塗ったものが江戸の名物かる焼。
おてつ 牡丹もち

麹町おてつ牡丹もちの“おてつ"とは、人の名前らしい。
今はなき“おてつ牡丹もち"を洋食レストラン「青山からす亭」
店主の古屋ご夫婦が、文献を元に復活させ、販売していた。
当時、麹町の茶屋に「お鉄」という美人の看板娘がおり、旗本弟子
が殺到したことが名前の由来。
玄米を用い、餡・ゴマ・黄粉の3色牡丹もち。
堀江 錦うちわ

堀江町は、現在の日本橋小舟町。江戸時代、団扇(うちわ)問屋が軒
を連ね、「団扇河岸」と呼ばれた。“錦団扇"は、一本の竹から作り
著名な浮世絵師の錦絵を使用。今は1590年創業の「伊場仙」が
一軒残るも、錦団扇は売られていない。
江戸紫染め

“江戸紫"とは色の名称、“染め"は呉服店で行っているとのこと。
訪れたのは、1842年創業の老舗の呉服屋「竺仙(ちくせん)」。
もともと江戸紫は、歌舞伎の演目「助六由縁江戸桜」の色男・助六
のハチマキの色から流行。それが今は、赤っぽいものから青っぽい
ものまで、江戸紫と呼ばれている。しかし、本来“江戸紫そめ"は、
紫色の根を用いた“紫根(しこん)染め"のこと。今の江戸紫色は、
化学染料で染めているものが多く、スゴロクの江戸紫そめは、ほと
んど無いという。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
なんだか日本史の授業みたいな内容ですね。でも、いまも残ってい
る文化もあるので少しほっとしました。
手間はかかるけど、職人の技は、化学製品には負けない魂がこもっ
ている・・・そう聞きました。
これからも貴重な文化・財産として伝えていきたい浅草名物でした。
という特集をやっていました。
もうなくなってしまったものも多くありましたが、歴史を学びながら
浅草名物を堪能できるなんて、面白いと思いましたね。
それでは、職人が受け継いだ技、味をお楽しみください。
長命寺 元祖桜もち

享保2年(1717年)初代山本新六が隅田川土手の桜の葉を集め、塩
漬けにして桜餅を考案、向島の名跡長命寺の門前にて売り始めてそれ
から二百八十年余、隅田堤の桜と共に名物となった。
山本山 お茶
山本山は、元禄三年(1690年)、初代山本嘉兵衛が宇治の美味しい
京都より江戸・日本橋に出てお茶の商いを行った事が始まり。
山本山と言う名前は、江戸期に発売され当社の売れ筋商品であった、
宇治煎茶の商品名「山本山」に由来し、昭和16年に法人「株式会社
山本山」の社名へ正式に採用しました。
伊勢半本店 小町紅

江戸時代より継承する匠の技で、紅花にわずか1%のみ含まれる赤い色
素が抽出され、女性の口元を彩る「小町紅」が作られます。それは、
自然の神秘が醸し出す魅惑の色彩。
根岸 笹の雪
 江戸時代からある結び方で折詰にしています。日本で最初のお土産豆腐は笹乃雪の絹ごし豆富です... 価格:2,100円(税込、送料別) |
|
元禄四年(約三百十五年前)上野の宮様(百十一代後西天皇の親王)の
お供をして京より江戸に移り、江戸で初めて絹ごし豆富を作り根岸に豆
富茶屋を開いたのが江戸のれんの始まりです。
豊島屋 白酒

時は江戸、慶長年間(1596~)と言えば太閤秀吉の晩年にあたり、
その城の外濠、北岸は江戸湾から隅田川、日本橋川と入って石垣の石
材などを陸揚げする鎌倉河岸(「江戸切絵図」では竜閑橋と神田橋の
間、鎌倉町。現在の千代田区内神田二丁目)で初代豊島屋十右衛門
(としまやじゅうえもん)がお城の普請で集まった多くの武士、職人、
商人達をお客様に酒屋及び飲み屋を始めたのが豊島屋のおこりです。
今戸 火鉢

下総千葉家の一族の配下の者が武蔵の浅草辺で土器や瓦を造りだした
のに始まると伝う。続いて徳川家康江戸入城に際し、三河から二人の
土風炉(茶道で湯を沸かす火鉢)師と土器師を連れて来た。
松木宗四朗と松井新左衛門で、暫く市内に住んでいた。次にまた三河
の土屋という火鉢師も市内で土器を造っていたが、明暦の大火後、瓦
焼の今津(今の今戸)に移った。
八百善 江戸料理

歴代将軍やペリーも舌鼓を打ったという高級料亭「八百善」のこと。
デパ地下のおせちコーナーで、八百善を発見。
江戸時代の料理を再現したおせちには、何度も裏ごしを重ねたきんと
ん、鯛のすり身と皮で、切り身に見立てたかまぼこなど、手間を惜し
まず作られた料理の数々。それが江戸料理たる所以。
淡島屋 かる焼き

「かる焼き本舗北島」は、大正時代創業。淡島屋はもうなく、現在こ
ちら以外かる焼のお店は残っていない。北島宏吉さんがかる焼の最後
の職人という。
かるやきとは「厄が軽くなる」とお見舞い品として重宝され、袋の金
太郎の挿絵も「病に勝つ」という意味。もち米の粉を砂糖水でのした
ものを切り分け、プレス機でつぶすと四角い種が丸いせんべいに。
それに蜜を塗ったものが江戸の名物かる焼。
おてつ 牡丹もち

麹町おてつ牡丹もちの“おてつ"とは、人の名前らしい。
今はなき“おてつ牡丹もち"を洋食レストラン「青山からす亭」
店主の古屋ご夫婦が、文献を元に復活させ、販売していた。
当時、麹町の茶屋に「お鉄」という美人の看板娘がおり、旗本弟子
が殺到したことが名前の由来。
玄米を用い、餡・ゴマ・黄粉の3色牡丹もち。
堀江 錦うちわ

堀江町は、現在の日本橋小舟町。江戸時代、団扇(うちわ)問屋が軒
を連ね、「団扇河岸」と呼ばれた。“錦団扇"は、一本の竹から作り
著名な浮世絵師の錦絵を使用。今は1590年創業の「伊場仙」が
一軒残るも、錦団扇は売られていない。
江戸紫染め

“江戸紫"とは色の名称、“染め"は呉服店で行っているとのこと。
訪れたのは、1842年創業の老舗の呉服屋「竺仙(ちくせん)」。
もともと江戸紫は、歌舞伎の演目「助六由縁江戸桜」の色男・助六
のハチマキの色から流行。それが今は、赤っぽいものから青っぽい
ものまで、江戸紫と呼ばれている。しかし、本来“江戸紫そめ"は、
紫色の根を用いた“紫根(しこん)染め"のこと。今の江戸紫色は、
化学染料で染めているものが多く、スゴロクの江戸紫そめは、ほと
んど無いという。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
なんだか日本史の授業みたいな内容ですね。でも、いまも残ってい
る文化もあるので少しほっとしました。
手間はかかるけど、職人の技は、化学製品には負けない魂がこもっ
ている・・・そう聞きました。
これからも貴重な文化・財産として伝えていきたい浅草名物でした。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[観光] カテゴリの最新記事
-
月曜と火曜はお花見三昧 2017.04.05 コメント(2)
-
温泉巡りにはまってます^^ 2015.09.15 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.