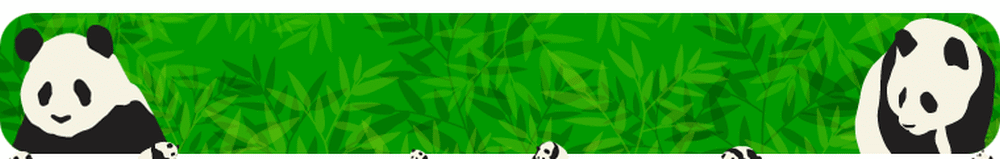黒執事小説『月の魔女』
その古城はいくつかの森を越えた湖のほとりにひっそりと
建っていた。月が満ちて森を明るく照らす夜、湖の水面に
浮かぶ満月は血塗られた。
「美しい。」
古城の主は窓からその光景を眺めてこう言った。
「我が妻は自ら贄となり、湖に住む魔女となる。湖の底に
沈んだ肉体は朽ち果てようともその魂は永遠に生き続け
るであろう。」
「お父様、何故、お母様を殺したのですか?」
「禁忌を犯したからだ。」
古城の主は鎖で繋がれている我が子の元へゆっくりと近づき
そっと足に触れた。足枷がきついのか血が滲んでいる。
「私はおまえを失いたくないのだよ。罪を犯した者はその罪
を償わなければならない。分かるね。さあ手を出しなさい。」
恐る恐る差し出した白く細い手首に手枷をはめて、古城の
主はこう言った。
「我が愛しき天使よ。きっと『月の魔女』がおまえを守って
くれる。だから今は父を信じて大人しくしていなさい。」
そして、まだ幼い我が子を抱きしめ、その唇に口づけした。
黄金色の髪を愛撫しながら別れを惜しむように唇を重ね
合わせた。一時が永遠になるかも知れない。そんな思い
が募った。長いキスの後、彼は拘束具を手にして足枷を
はめ直した。
「いや、お父様、やめて!」
泣き叫ぶ息子の口を拘束具で塞ぎ、無理やり魔法陣が
書かれた棺に閉じ込めた。彼は部屋の床に書かれた
魔法陣を消し、棺を抱えて部屋を出た。
月は美しく輝き、湖に浮かぶ死体を照らしていた。
満月の夜にふさわしい生贄だった。
森をぬけると美しい湖が広がっていた。
「綺麗ですね。」
セバスチャンは何時間も馬車に揺られてうんざりしていた
シエルに話しかけた。シエルが馬車の窓から外を眺めると
湖は太陽の光が反射してキラキラと宝石のように輝いていた。
そして、中世を想わせる小さな城が姿を現した。
「あの古城です。ようやく着きましたね。」
セバスチャンがにっこりと微笑んだ。スチュアート家の別荘
は緑豊かな森に囲まれた湖の隣にひっそりと建っている古城
だった。会社の合併話をもちかけられ、契約はぜひ接待も
兼ねてスチュアート男爵自慢の別荘でとの誘いだった。
ロンドンですれば良いものを何故とも思ったが、まるで
おとぎ話に出てくるような美しい光景を見ていると7時間も
馬車に揺られて来たことすら忘れてしまいそうだった。
古城の外門をくぐると、丸く切りそろえられた低木が連なって
城まで続いている。季節はずれのバラ園や青々とした芝生
が広がる良く手入れの行き届いた庭だった。古城の前には
赤いカーペットが敷かれていて、執事が一人立っていた。
「ようこそ。おいでくださいました。」
馬車を降りるとすぐに執事が出迎えの挨拶をした。
「長旅でお疲れになりましたでしょう。ファントムハイヴ伯爵
様。主人が客間にてお待ち申し上げております。」
黒髪に眼鏡をかけた気の弱そうな執事だった。
城の中は意外と装飾品も少なくガランとしていた。床一面
赤い絨毯で窓には深緑色のカーテンが全室つけられていた。
天井は高くシャンデリアはゴシック調だった。アンティーク
で統一された家具も趣味は悪くないのだが、部屋が広すぎて
殺風景に感じられた。エントラスルーム、リビングルーム、
長い廊下を通って、客間にたどり着いた。客間も赤い絨毯の
殺風景な部屋だった。
「ようこそ。ファントムハイヴ伯爵。遠路はるばる良く来て
くださいました。」
「お招きいただきありがとうございます。スチュアート男爵。」
「お噂はかねがね聞いておりましたが、実に可愛らしい。」
スチュアート男爵はニコニコと笑顔を浮かべており、悪気は
ない様子だったが、シエルは舐めるような視線を感じて不快
に思った。こいつも変態なのか?来るんじゃなかった。
後悔が顔に表れたのか、セバスチャンが気遣うように
「坊ちゃんは長旅で疲れております。夕食まで休ませて
いただいてもよろしいですか?」
と申し出た。スチュアート男爵は
「これは申し訳ない。さぞかしお疲れでしょう。今、執事に
部屋を案内させます。」
と言った。
「ノルマン。お客様を部屋に案内しなさい。」
コホンと咳払いするようにして執事に言いつけると、彼はまた
ニコニコと笑顔を作った。
案内された部屋は眺めの良い2階の部屋だった。窓から湖
が一望できた。シエルがバルコニーへ出て景色を眺めると、
湖の向うには山々が連なり、青い空にはぼんやりとした
白い月が浮かんでいた。今日は満月だった。森から小鳥の
声が聞こえる静かな湖だった。シエルはふと、湖の向こう側
から歩いてくる白い服の女性に気付いた。遠くてよく分から
ないが、その女性はどんどん歩いてこちらに近づいてくる。
まるで湖の中へと入って行く勢いだった。しかし、女性の
背丈はいくら歩いても同じで、白い服は濡れることなく湖の
水面から上にあった。シエルが目を凝らして見ると、白い服
の女性はシエルに気付き、にっこりと笑いかけた。
「あの女性は誰だ?」
シエルが指差してノルマンに聞いた。だが、ノルマンは
「何のことです?私には何も見えませんが・・・」
と言った。
「見えない?」
シエルがもう一度、湖を見ると女性の姿は消えていた。
その時、背後からギギーッと重い扉を開ける音がした。
シエルが振り返って見ると、ドアノブに青白い手が・・・
「エドワード坊ちゃん。立ち聞きはいけませんよ。」
ノルマンが言った。
「ごめんなさい。」
部屋の中へ入って来たのは10歳くらいの男の子だった。
金髪碧眼透き通るような白い肌の美少年は頬をほんの少し
上気させ、もじもじとノルマンの後ろに隠れた。
「坊ちゃん、お客様にちゃんとご挨拶なさいませ。」
執事に言われて、エドワードはひょっこり顔を出し
「エドワード・スチュアートです。ごきげんよう。」
そう言うとまた執事の後ろに隠れてしまった。
「申し訳ございません。坊ちゃんは人見知りが激しくて・・・
しかも、お体が弱くて学校にも行ってないものですから
お友達がおりません。歳の近いファントムハイヴ伯爵様
に仲良くして欲しいのでしょう。」
「そうですか。うちの坊ちゃんもお友達がいませんので、
ぜひ仲良くしてください。」
セバスチャンがすかさず万遍の笑みを浮かべて答えた。
子守なんかできるか!そう言いたいのをシエルは我慢した。
セバスチャンの奴、完全に面白がっているなと思った。
「エドワード坊ちゃんは喘息の持病をお持ちなので、3年前、
ロンドンからこの古城へ引っ越して来ました。森に囲まれて
空気がきれいな所で静養すれば、きっと良くなると奥様は
考えたのですが、まさかあんなことになるなんて・・・」
ノルマンは暗い顔をしてエドワードを見つめた。
「あんなことってなんですか?」
「奥様は1年前、湖で事故に遭われて水死なさったのです。」
「お食事のご用意ができました。」
メイドが部屋に知らせに来た。
「もう5時ですか。時が経つのは早いですね。今夜はシェフ
自慢の料理を取り揃えております。晩餐をお楽しみください。
ささ、どうぞ。ご案内いたします。」
ノルマンはシエル達を1階へ連れて行き、長いダイニング
テーブルのある広い部屋に案内した。20人は座れるほどの
ダイニングテーブルには4人分の豪華な食事が用意されて
いた。薄暗い部屋に灯された蝋燭の明かりが綺麗だった。
「キジはお好きですか?私が昨日、森で仕留めたやつです。」
スチュアート男爵がニコニコとキジの丸焼きを指差して言った。
「他にもフォアグラや子羊などこの古城で飼っている新鮮な
食材で作らせました。」
シエルは席に着いたとたん、食欲が失せた。
「子羊ってメイじゃないよね?」
エドワードが心配そうに聞いた。
「羊の名前なんか覚えてないが、おまえが可愛がっている
羊ではないと思うよ。」
「メイでございます。」
ノルマンが言った。
「旦那様が一番太っている美味しそうな子羊をと申されま
したので、私がシェフに伝えました。シェフは旦那様の言い
つけ通り料理したまででございます。」
エドワードの顔が見る見る蒼ざめ、エドワードはゲーっと
吐いた。汚物がテーブルの上に広がった。
「うわっ!また吐きよった。ノルマン、早く片付けろ!」
メイドが数人慌しく寄ってきて吐いたものを掃除し始めた。
「坊ちゃん、大丈夫ですか?」
ノルマンはエドワードの汚れた服や顔をハンカチで拭いた。
「もう、いい。エドワードを部屋に連れて行け。」
スチュアートが怒ったようにノルマンに言った。
「晩餐が台無しですね。」
その惨状を見ていたセバスチャンは冷ややかに言った。
エドワードと一人分の食事が速やかに片付けられた後、
晩餐は何事もなかったかのように続けられたが、ダイニング
テーブルにはわずかなシミが残っていた。シエルは子羊の
肉に口をつけなかった。キジの丸焼きは何度も勧められた
ので、仕方なく少しだけ食べたものの美味しく感じなかった。
シェフの腕が悪いとかの問題ではなくて、食事を取り替えても
おかしくないはずなのに、平然と息子が可愛がっていた羊の
肉を食べる父親を見て気分が悪くなったのだった。デザート
の後の紅茶を飲み終わるとスチュアート男爵はこう言った。
「お見苦しいところをお見せしたお詫びといっては何ですが、
我が家の家宝をプレゼントします。私は古美術や骨董を
集めるのが趣味でして、今からコレクションルームにご案内
しましょう。」
「それは楽しみです。」
黙り込んでいるシエルに代わってセバスチャンが受け答えした。
食事の後、1階の奥にあるコレクションルームと呼ばれて
いる部屋へ案内された。赤い絨毯の廊下を歩いている時、
ひぃ~、ひぃえぇ~と気味の悪い悲鳴がかすかに聞こえた。
何の音だろうとシエルが立ち止まると、スチュアート男爵は
こう言った。
「風の音です。地下に湖に通じる抜け道があって、そこの
通気口から聞こえてくるのです。」
「随分と気味の悪い風の音ですね。」
セバスチャンが眉を吊り上げて言った。だが、男爵は黙って
部屋の扉を開けた。コレクションルームとは名ばかりの
物置部屋には雑然と近世の鎧や武器が置かれていた。
そして、壁には数々の絵画が飾られていた。
「歴代の城の主とその家族の肖像画です。みな16世紀
から18世紀にかけて描かれた絵です。」
スチュアート男爵は自慢げに言った。無名の画家が描いた
にしても近世に描かれたものなら値打ちがあるということか。
それにしても、よくもまあこんなにたくさん集めたものだ。
シエルはあたりを見回した。すると、部屋の奥にもう一つ扉
があって、その横の壁にエドワードの肖像画が飾ってあった。
エドワードは何故か古めかしい貴族の格好をしていた。
「ジェームス2世の肖像画です。」
スチュアート男爵は言った。
「息子と同じ顔で驚かれたでしょう。100年前、この城に
住んでいた領主のご子息です。3年前、ここに引っ越して
来た時には私も驚きました。」
「私の祖父は代々この城を所有するスチュアート家の分家
の身でした。本家の血筋が絶えたので、この300年前に
建てられた古城を受け継いだのですが、住むには至りません
でした。私はロンドン育ちで田舎に住むのは初めてですが、
空気の良い所で育てたら息子の喘息が治るのではないかと
妻が言うので、3年前に引っ越してきました。だが、それは
間違いでした。会社を使用人に任せて私は狩りなどを楽しみ、
田舎暮らしを満喫しましたが、会社は傾き合併へと追い込ま
れました。私はファントムハイヴ社との合併がうまくいったら
会社経営から退くつもりです。私はもう45歳です。エドワード
は遅くに出来た子で、息子のことは心配ですが、ここには
私の大好きな骨董品があります。森と湖に囲まれて余生を
過ごしたいと思っています。ですから、ぜひ我が社の提示
した条件で契約をしてもらいたいのです。あ、そうそう、
先ほどの失態のお詫びに我が家の家宝をプレゼントする
お約束でしたな。」
スチュアート男爵はそう言うと、大きな木箱から小さな宝石
箱を取り出して、その中の指輪をシエルに手渡した。
「スチュアート家に代々伝わる家宝『月の魔女』です。どうか
お受け取りください。」
黄金色に輝く指輪は美しかった。
「1カラットのイエローダイヤです。リングも純金でできていま
す。ここまで球形に近くカットされたダイヤは珍しいでしょう?
満月をモチーフに造られた指輪です。満月の夜には不思議な
力がこの指輪に宿ると言われています。また、持ち主に栄光
か破滅のどちらかを与えるとも言われています。私の場合
は後者でしたが、あなたには栄光が訪れることを祈ります。」
スチュアート男爵はシエルの右手の中指に指輪をはめた。
そして、ニコッと微笑むと次の部屋の扉を開けた。
「素晴らしいコレクションですね。」
セバスチャンが感嘆した。
「これは一体・・・」
シエルは驚いて目を丸くした。
「魔女狩りの拷問道具ですよ。」
スチュアート男爵は不敵な笑みを浮かべて言った。
部屋の中央に鉄の処女が3体置かれていた。一体は聖母
マリアを模した顔の木製の人形型だった。もう一体は同じく
木製だが、高さ2メートルの樽のような形をしていた。
そして最後の一体は扉が開いていた。扉の内側には鉄製
の太くて長い針がびっしりとついており、中からも無数の
針が突き出ている。これに人を入れて扉を閉めるのかと
思ったらゾッとするとシエルは思った。鉄の処女の針には
血がこびりついていた。
「どうです?素晴らしいでしょう?」
スチュアート男爵はシエルの顔色が変わったのを見て、
ニヤッと笑って言った。
「他にも多数の拷問道具がこの部屋にはあります。審問椅子、
さらし台、鉄製の吊り籠、何でもあります。特にこの魔女の
椅子はレア物ですが、どのようにして使うかご存知ですか?
この椅子は尻を乗せる部分が周囲の枠のみで真ん中が
何も無いでしょう。下から蝋燭の火であぶるんです。尻が
こげ、排泄困難になるまであぶり続けたと言われています。」
シエルは話を聞いていて気分が悪くなった。スチュアート
男爵は魔女狩りマニアの変態だったのだ。シエルは指輪を
返して家に帰りたくなった。だが、スチュアート男爵はそんな
ことおかまいなしに喋り続けた。
「17世紀になってもこの城の主は魔女狩りをやめません
でした。むしろそれまで教会に委ねていた魔女狩りを領主
自ら行うようになり、領内の村から美しい若者を捕らえては
地下牢に閉じ込めて、拷問を繰り返していたのです。そして、
18世紀に怒った領民がこの城に押し寄せてスチュアート家
は滅亡しました。滅亡したといっても、絶対王政の時代です
から、一揆は1日で治まり、本家の代わりに分家の祖父が
家督を継ぎました。でも、祖父は血塗られた歴史に恐怖し、
この城には一度も住まなかったのです。」
「キャア~~!!」
絹を引き裂くような女性の悲鳴が聞こえた。先程とは違い、
明らかに人の叫ぶ声だった。シエルたちは悲鳴の聞こえる
2階の部屋に慌てて駆けつけた。悲鳴の主はメイドだった。
メイドは床にへたりこんで、ワナワナと恐怖に震えていた。
部屋の中には首の無い猫の死体が置いてあった。そして、
壁には猫の血で魔法陣が描かれていた。
「一体誰がこんなことを・・・」
「きっと奥様に違いないわ!月の魔女の呪いだわ!」
メイドは泣き叫んでそう言った。
「バカなことを言うものじゃない。妻は1年前に死んだんだ。
また幽霊の仕業だというのか?バカバカしい。きっとこれは
誰かの悪戯だ。お前は泣いている暇があるならさっさとこの
部屋を片付けろ!」
スチュアート男爵は怒ったようにメイドを怒鳴りつけると
立ち去って行った。
「大丈夫ですか?何か事情がおありのようですね。」
セバスチャンがメイドに聞いた。
「ええ。奥様がお亡くなりになってから気味の悪い事ばかり
起こるんです。まず、最初に魔法陣を見たのは奥様が亡く
なられた翌朝でした。湖の岸辺に大きな魔法陣が木の棒
か何かで地面に書かれていました。それからというもの
満月の日には頭のないネズミの死骸や鳥の死骸が古城の
どこかに捨ててあるんです。ダイニングテーブルに血文字で
魔法陣が書かれていたこともありました。奥様が満月の夜に
湖で入水自殺なさったから、こんなことに・・・」
「自殺?事故ではなかったのですか?」
「はい。旦那様は事故だと言い張っていますが、本当は自殺
なんです。あれは1年前の月の明るい夜でした。私は奥様
が白い寝間着のまま一人で湖へ歩いて行くのを見ました。
湖の中へどんどん歩いて入って行って、そのまま帰らぬ
人に・・・私は窓から見ていて、慌てて旦那様に知らせたの
ですが、皆が駆けつけた時にはもう手遅れでした。」
「男爵夫人は何故自殺したのですか?」
「それはきっとノルマンさんと旦那様が・・・」
「私がなんだって?」
部屋の外にノルマンが立っていた。
ノルマンは手に大きなバケツとゴミ袋を持っていた。
「無駄話はやめて早く片付けなさい。」
ノルマンはそう言うと、部屋に入って、猫の死骸をゴミ袋に
入れてメイドに手渡し、捨ててくるように命じた。メイドは
黙って受け取り、軽くお辞儀をすると部屋を出て行った。
「さっきの話はでたらめです。」
ノルマンはメイドがいなくなったのを見計らってから言った。
「奥様は夜の散歩の途中、足を滑らせて湖に落ちたのです。
彼女が見た時にはもう溺れていました。幽霊話も想像に
過ぎません。これは旦那様の言う通り悪質な悪戯です。」
「悪戯なら何故警察に届けない?」
シエルがノルマンに聞いた。
「それは・・・」
ノルマンは何か言いかけて黙り込んでしまった。
「失礼ですが、坊ちゃんの言う通り警察に届けたほうが良い
と思います。警察沙汰にできない事情があれば別ですが・・・」
セバスチャンに見透かされたと思ったのかノルマンの顔色
が変わった。
「では、質問を変えましょう。あなたは大変お若いように見え
ますが、何年くらい執事をなさっていらっしゃいますか?」
「3年です。16歳の時に父の経営する会社が倒産しまして、
縁あって旦那様が父の借金を肩代わりしてくださいました。
それ以来、こちらで執事兼家庭教師を勤めさせていただい
ております。」
「ほう、坊ちゃんの教育係も兼任なさっておいでですか?
私と同じですね。」
セバスチャンがにっこりと笑った。だが、ノルマンは暗い顔を
してこう言った。
「部屋を掃除いたしますから、出て行ってもらえませんか?」
ノルマンはバケツの雑巾で壁を拭きだした。その失礼な
態度にシエルは何か言おうとしたが、セバスチャンはシエル
を制して、大人しく部屋を出た。二人が部屋を出た後も
ノルマンは一人でゴシゴシと壁の血を落としていた。
一度描かれた魔法陣は消したくても完全には消えない。
血塗られた歴史を象徴する魔法陣は濡れて血の涙を流して
いた。やがてメイドが戻ってきて、ノルマンと代わった。
ノルマンは静かに部屋を出て、スチュアート男爵の元へと
向かった。
その夜、シエルは真夜中近くになっても寝付けなかった。
あの魔法陣は幽霊の仕業ではなく、誰か人の手によって
描かれたのだろう。ノルマンは何か隠しているとシエルは
思った。ノルマンに聞けば何か手がかりがつかめるかもしれ
ない。シエルは白い寝間着のまま部屋を出た。一人で古城
の廊下を歩いているとエドワードの部屋から物音がした。
部屋の扉の隙間からかすかに明かりが洩れている。まだ
起きていたのか。エドワードも今夜は寝付けないのかなと
思い、シエルはエドワードの部屋のドアを開けた。部屋の中
は薄暗かった。入口の横の壁の蝋燭が扉を灯していただけ
だった。エドワードは部屋の奥のベッドに横になっていた。
「なんだ、寝ていたのか。」
と、つぶやいてシエルが帰ろうとした時、
「眠れないのかい?僕もだよ。」
とエドワードは言って、体を起こした。
「体の具合、大丈夫か?」
「気分はいいよ。君と少し話がしたいけど、いいかな?」
「いいよ。」
シエルはベッドの傍らに腰掛けた。
「月の魔女は我が家の家宝なんだ。返してくれるかな?」
「えっ?でも・・・」
「本来は僕が受け継ぐはずだったんだ。返してくれ。」
いつになく真剣な眼差しでエドワードに言われてシエルは
戸惑ったが、言われるままに指輪を返した。
「ありがとう。この指輪には魔力が秘められているんだ。
栄光と破滅のどちらかをもたらすというのは作り話だよ。
月の魔女は満月の夜に願いを一つ叶えてくれる不思議な
指輪なんだ。僕はお母様に会いたくて、何度も満月の夜に
願いを叶えてもらったよ。でも、本当の望みはまだ叶えて
もらえていない。贄が小さいとダメなんだ。もっと大きな贄を
捧げないと月の魔女は僕の願いを叶えてくれない。今日
この日をどんなに待ち望んでいたことか。君に会えて良かっ
た。御礼に良いものをあげるよ。」
エドワードは枕の下に隠していた猫の首を取り出した。
エドワードは血の滴る猫の首にそっとキスをして、悪魔にも
似た微笑を浮かべながら、シエルに差し出した。
シエルは驚きのあまり声も出なかった。とっさにその場から
逃げようとしたが、エドワードに手首をしっかりと捕まえられ
てしまった。
「待って。今のは冗談だよ。」
「手を放せ!」
「君に見せたいものがあるんだ。僕の部屋の隠し扉から湖に
通じる地下道への階段がある。一緒に行こう。面白いものを
見せてあげるよ。」
「い、いやだ。」
「遠慮するなよ。君はノルマンに会いたいんだろ?彼は今、
地下牢にいるよ。」
「えっ?」
何故と聞く暇もなくシエルはエドワードに腕を引っ張られて
地下道へと続く階段を下りていた。階段を下りた先に小さな
レンガ一個分の窓があった。そこから中を覗くとノルマンが
裸で縛られていた。ノルマンは地下牢の天井から後ろ手に
縛られて吊るされていた。シエルが思わず息を呑むと、
エドワードはシーっと人差し指を唇にあてた。
「黙って見ててごらん。面白いから。」
エドワードはクスクスと声を殺して笑っている。シエルは
異常な光景に眩暈を感じたが、壁の小窓から中をもう一度
よく見てみた。ノルマンは蝋燭を体中に垂らされていた。
そして、その蝋燭を垂らしているのはスチュアート男爵
だった。彼は欲望に捕らわれた目をして、赤い蝋燭の蝋を
ノルマンの胸や腹に垂らしていた。熱くそりかえった下腹部
に蝋を垂らすとノルマンは悲鳴をあげた。ノルマンの尻には
太い蝋燭がすでに埋め込まれており、体を揺らす度に炎が
揺れていた。尻から滴り落ちる蝋が太ももを伝い赤く染めて
いた。背中にはムチの痕がノルマンの白い肌を彩っていた。
「気持ち良いかい?舌を出しなさい。」
スチュアート男爵の命令にノルマンは従順だった。おずおず
と舌を出すと、スチュアート男爵は蝋燭の蝋を垂らした。ポタ
ポタと垂らされる蝋を舌で受けとめるノルマンは苦しそうだっ
た。スチュアート男爵は更に蝋燭を顔に近づけて、炎が顔を
かすめそうになる度に恐怖に怯えるノルマンにこう言った。
「蝋燭の炎で舌をあぶってやろうか?何秒耐えられるかな?」
「お許しください。そればかりはご勘弁を・・・」
ノルマンは恐怖のあまり失禁してしまった。
「仕方のない奴だな。」
スチュアート男爵はノルマンのロープをほどき床に転がした。
そして木桶に汲んであった水をザバーッとノルマンにかけた。
「旦那様、どうかお許しください。」
震えるノルマンの足を開かせて、尻にささっている蝋燭を抜き
取ると、スチュアート男爵はノルマンに自らを挿入した。
「ああああ~」
ノルマンは歓喜の声をあげた。先ほどまでと違ってノルマンは
恍惚とした表情を浮かべて自ら腰を動かしている。支配される
喜びを感じているかのようだった。
「あいつら、いつもここであんなことをして遊んでいるんだ。」
エドワードが地下道の小窓から覗き見ているシエルに言った。
「湖で君に会わせたい人がいるんだ。行こう。」
エドワードはシエルの手首を掴んで、グイグイと引っ張った。
地下道を走るとすぐに湖に出た。真夜中の湖は静かだった。
満月が美しく夜空に浮かんでいた。エドワードはシエルから
もらった指輪を満月に掲げて、こう言った。
「月の魔女よ。我が願いを叶えたまえ。」
すると湖がさざめき湖の中から白いドレスの女が姿を現した。
「お母様!」
エドワードは湖から現れた女性の傍へ駆け寄った。
「我が愛しき天使よ。そこにいる人間は何者です?」
「贄でございます。今宵の為に連れて参りました。」
エドワードはシエルを指差した。だが、彼女は
「その者は汚れておる。贄にはならない。不浄の者は贄に
はできないのです。」
と言った。
「君が不浄だったなんて残念だよ。」
エドワードはがっかりしたようにシエルに言った。シエルは
言いがかりのような侮辱に唖然とした。
「代わりの贄が必要です。この体を湖に捧げましょう。」
「では、そうしましょう。」
母親はにっこりと微笑んだ。エドワードが湖に入ろうとした時
「お待ちなさい!」
セバスチャンが突然現れて、エドワードの腕を掴んで引き
止めた。
「人を殺した者は天国へは行けませんよ。」
「手を放しなさい。悪魔め。」
「ほう、私の正体が見えるんですか?でも、自縛霊にそんな
言い方されたくありませんね。」
「お母様は自縛霊なんかじゃない。この湖の守り神なんだよ。」
「守り神?笑わせないでください。誰が決めたんですか?」
「月の魔女にお父様がお願いしたんだ。」
「お願いね。あなたはその指輪が何でも願いを叶えてくれる
と本気で思っているのですか?答えはノーです。月の魔女
は単なる呪術の道具に過ぎません。あなたも本当はうすうす
気付いていたはずです。ジェームス様。」
「何故、知っている?」
「悪魔で執事ですから。血塗られた古城の歴史を調べて参り
ました。そして、棺のありかも・・・」
「何だって?僕の棺が何処に隠されているか知っているのか?」
「やはり、ご自分の帰るべき体を見失っていたのですね。」
セバスチャンはため息をついた。ジェームスの母親は静かに
語り出した。
「あれは1年前の満月の夜でした。湖に月の魔女の指輪を
した女性が身を投げたのです。私は月の魔女の力を借りて
ジェームスの魂を呼び起こしました。湖の岸辺に魔法陣を
書いたのですが、翌朝、城の者に見つかり、消されてしまい
ました。それで、ジェームスは眠っていた場所が分からなく
なってしまったのです。ジェームスが母親を亡くして悲しみ
に暮れているエドワードにとり憑くのは容易でしたが、霊力
が弱いため完全に体を乗っ取れるのは満月の夜だけでした。
しかも、肝心の指輪は何処かへ隠されてしまい、月の魔女
の力を借りる事もできず、ただ、毎月、魔法陣を描き、湖
から出る事のできない私と二人で祈りを奉げていました。
いつの日か天国へ行ける日が来るのをずっと祈っていたの
です。あの時、私が禁忌を犯さなければこのような目に遭わ
されなかったであろうに・・・。」
「お母様、100年前に僕が死んだのがいけなかったのです。
病弱な僕をお許しください。」
「ジェームス。全ては母が悪いのです。浅はかな母を許して
おくれ。」
二人は泣き出した。セバスチャンは二人に言った。
「城へ戻りましょう。」
「あなた方だけでお行きなさい。私は湖から出られないのです。」
「死体が湖の底に沈んでいるからですか?100年前、貴女は
月の魔女の指輪を用いて禁断の黒魔術を行った咎で、この
湖で処刑された。満月の夜、指輪と魔法陣と生贄と復活の
呪文さえあれば、死体を一時的に蘇らせることができます。
ですが、その死体は魔法陣の中でしか生きられない。一歩
でも外に出ると灰になってしまいます。貴女は100年前、
城の床に大きな魔法陣を描いて病死した我が子を生き返ら
せた。最初は一目会ったら魔法陣を消して灰にするつもり
だった。でも、愛する我が子をどうしても灰にできなかった。
何日も魔法陣から出ないように鎖で繋いで生かせておいた。
領民は貴女を魔女と思い込み、暴動を起こした。城の主は
禁忌を犯した罪で貴女を処刑し、貴女の死体を湖に投げ込み
贄として捧げた。そして、貴女の血で魔法陣を描いた棺に
息子を閉じ込め、暴徒から我が子を守ったのです。城の主は
棺を隠した後、城に押し寄せた領民たちによって殺されて
しまいました。領民たちは何の罪もない領主を殺すことで
17世紀に魔女狩りにあった復讐を遂げたのです。」
「もう一度言います。貴女は自縛霊なのです。死んだ場所
から離れられないと思い込んでいるだけで、貴女は何処に
でも行けます。そもそも呪術の力で人間は魔女や守り神に
はなれないんです。さあ、私の言葉を信じて、湖から一歩
踏み出してみてください。」
セバスチャンは手を差し伸べた。彼女は決意したように
セバスチャンの手を取り、歩みだした。湖から岸辺へと容易
に移動できた。セバスチャンはにっこり微笑んでこう言った。
「ジェームス様の棺にご案内いたします。」
セバスチャンが案内したのは魔女狩りの拷問道具が置いて
ある部屋だった。3体の鉄の処女のうち聖母マリアを模した
顔のふたを開けた。その人形型の鉄の処女は頭部に長い針
がびっしりとついているが、胴体部分には針がなかった。
子供用の小さな棺は胴体部分にすっぽりと収まっていた。
セバスチャンは鉄の処女の中から棺を取り出すとこう言った。
「月の魔女の指輪をこの棺の鍵穴に差し込んでください。」
ジェームスが指輪を棺に差し込み、180度回すとカチッと
音がして棺が開いた。棺の中には手枷足枷をした少年が
100年前の姿のまま眠っていた。100年経っていたら白骨化
しているはずなのに、少年は生きたまま眠っているかのよう
だった。少年は御伽噺のお姫様のように雪のような白い肌
と薔薇の花びらのような赤い唇をしていた。
「やっと見つけた。僕の体。」
ジェームスはそうつぶやくように言うと幽体離脱をするように
エドワードの体から離れて自分の体へと入っていった。すると
棺の中のジェームスが目を開けた。
「お母様、僕は100年もの長い間、この棺に閉じ込められて
いても、お父様を恨んだことなど一度もありません。全ては
僕を助ける為にしたことですから。お母様もそれは同じはず、
一緒にお父様の所へ参りましょう。」
「おお、ジェームス。」
二人は抱き合った。ジェームスの母が体を抱き上げ、棺から
出すと、ジェームスの体はサラサラと舞い散る灰になった。
半透明の幽体となったジェームスは母に抱きかかえられた
まま幼子のように笑った。やがて、美しい光が二人を包み
天国へと導いていった。
「ありがとう。シエル。」
「ありがとう。望みを叶えてくれて。礼を言います。」
二人は口々に御礼を言って光の中へ消えて行った。
「坊ちゃん、この指輪はどうなさいますか?」
セバスチャンが棺の鍵穴から月の魔女を取り出して
聞いてきた。
「湖に返そう。」
シエルは指輪を受け取ると、窓を開けて、湖に投げ捨てた。
月の魔女は湖に沈んでいった。
「棺も後で湖に沈めてくれ。」
シエルは母親の血で描かれた魔法陣の棺を指差して言った。
「イエス・マイ・ロード。では、エドワード様をベッドへお連れ
してから、そう致します。」
セバスチャンは気を失って倒れているエドワードを抱き
かかえて微笑んだ。
翌朝、シエルたちは古城の住人たちに別れを告げて旅立っ
た。エドワードは相変わらず、モジモジとノルマンの後ろに
隠れていたが、馬車が出発する前に
「さようなら。」
と、笑顔で手を振った。その天使のような穢れのない笑顔
は無垢そのもので、憑依されていた時の記憶もなければ、
兄のように慕っているノルマンと父親の関係も知らないのだ
とシエルは思った。スチュアート男爵が魔法陣を悪戯だと
決めつけているにもかかわらず、警察に届けなかったのは
我が子が描いている姿を見たのかもしれない。おそらく、
ノルマンも母親が死んだショックでエドワードがおかしくなっ
たと思っていたのだろう。事実は誰も知らないままに次の
満月の夜を迎えるだろう。皆の安堵する顔が目に浮かぶ。
シエルは馬車の中からエドワードとジェームスに心の中で
さよならを言った。
「坊ちゃん、せっかくお友達ができたのに残念でしたね。」
セバスチャンがニヤッと笑って言った。
「何の話だ?」
シエルが睨んだ。
「エドワード様とジェームス様は同じ顔をしていても性格は
正反対でしたね。純粋で内気なエドワード様と聡明で勝気な
ジェームス様。まるで私と出会う前の坊ちゃんと現在の
坊ちゃんみたいです。」
「過去の話はするな。」
「照れてらっしゃるんですか?」
「なんでそうなるんだ?」
「坊ちゃん。」
向かい側に座っていたセバスチャンが隣に移動してきた。
「そういえば、昨晩は忙しくて、してなかったですね。
坊ちゃんは寂しがり屋さんですから毎日しないとお寂しい
んじゃありませんか?」
「なっ、なわけない、あっ。」
セバスチャンがシエルの服の中に手を滑り込ませた。
「よ、よせ。」
「馬車は今、森の中です。誰にも見られませんよ。」
セバスチャンはシエルのボタンを外していった。椅子に押し
倒して覆いかぶさるように手足を押さえつけた。シエルは
身動きが取れなくて
「放せ。」
と言ったが、セバスチャンの唇に遮られて、何も言えなく
なった。やがて、全ての衣服を脱がされたシエルは体中を
弄るセバスチャンの手に翻弄された。
「あっ。」
敏感な先端を指で弄られてシエルは声をあげてしまった。
セバスチャンは更に舌先でチロチロと舐め始めた。
「あっ、ああ~」
指が2本シエルの中に入って来る。
「坊ちゃん、指と舌とどちらが気持ち良いですか?」
先端を舐められたまま、体の奥の最も感じる部分を指で
弄られてシエルは大きく仰け反った。
「もっと気持ち良くしてさしあげますよ。」
セバスチャンがシエルに入ってきた。
「ああああ~」
足を肩に抱え上げられて、深く繋がると、シエルは嬌声を
あげてセバスチャンにしがみついた。セバスチャンはシエル
を抱きしめるとグイッと持ち上げて座位の格好をさせた。
「坊ちゃん、自分で動いてみてください。」
「嫌だ。」
「嫌なら、抜きますよ。」
セバスチャンはそう言って、本当に抜いてしまった。
「やぁ~。」
シエルは急に抜かれて泣きそうになった。
「坊ちゃんのご命令とあれば、また抱いて差し上げても
よろしいですよ。」
「意地悪するな。僕を抱け。命令だ。」
「御意。」
セバスチャンはシエルをひょいっと膝の上に乗せて後ろから
抱きしめた。激しく何度も突かれてシエルは絶頂を迎えた。
セバスチャンはぐったりしたシエルの耳元で囁いた。
「お屋敷に着くまでまだまだ時間があります。たっぷりと
可愛がって差し上げますよ。坊ちゃん。」
屋敷に着くまでの道のりはおよそ7時間。
幾度となく果てても続く行為に命令するんじゃなかったと
シエルは後悔した。
(完)

ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 野口光の、ダーニングでリペアメイク…
- (2025-11-28 08:42:38)
-
-
-

- お勧めの本
- 首都圏は米軍の「訓練場」 [ 毎日新…
- (2025-11-27 07:40:04)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- ケシカラン こともおもしろがれる じ…
- (2025-11-27 10:58:21)
-
© Rakuten Group, Inc.