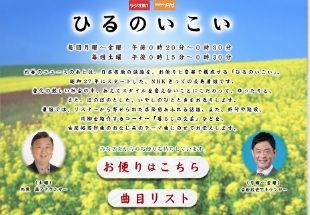PR
X
Free Space
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(0)映画 Cinema
(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube
(268)TVラジオ番組 television & radio programs
(375)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad
(148)外国語学習 Studying Foreign Language
(67)花 Flowers
(329)グルメ Gourmet
(204)介護 Nursery Care
(20)中高年の資格取得Qualification for middle
(15)散歩 Taking a walk
(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life
(121)フィットネスクラブ Fitness Club
(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath
(10)旅行 Travel
(88)読書 Reading
(54)健康 Health
(44)絵画 Picture
(25)Japanese TV Drama with English
(2)季節
(32)災害
(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス
(88)リンク修正、内容追加
(180)政治
(156)宗教
(121)写真
(27)グリーティング
(45)人生
(19)科学
(17)ダイエット
(7)少子・高齢化社会
(11)生き物 creatures
(5)月と星空
(26)不動産
(2)演劇
(1)Comments
Freepage List
テーマ: 魚料理(26)
カテゴリ: グルメ Gourmet
秋田県の佐竹知事のじゃこ天に関する発言がニュースになっていましたが、良い方向に展開して安心しました。じゃこ天を調べてみると、さつま揚げによく似ていますが、「小魚を骨ごと、皮付きのまますりつぶしている」ため、食感がしゃきしゃきしているのが、違うそうです。
また、さつま揚げは全国的にさつま揚げと呼ばれているのかと思っていたら、各地で呼び名が違うのに驚きました。鹿児島県でもさつま揚げとは呼ばれていないそうです。ネットを検索しても、全国の「魚のすり身を揚げたもの」の名称一覧はまだありません。これを作った人は日本初の快挙になると思います。
ところで、5月に長崎旅行で凛々丸で食べた、揚げたてのすりみあげは、月並みな表現で言うと、ほっぺたが落ちるくらい、とてつもなくおいしかったです。今までほとんど冷蔵庫から出した冷たいものしか食べたことがありませんでしたが、これを食べてさつま揚げに関するイメージが一新しました。今回の件で思いだしたついでに、機会があれば東京で長崎料理店を見つけてまた食べたいです。
■参考リンク
「じゃこ天は貧乏くさい」発言で炎上・謝罪の佐竹知事は「憎めない失言キャラ」? 秋田県民は呆れながらもどこか慣れた様子でフォローABEMA的ニュースショー千原ジュニア,田中萌

殿様も愛したじゃこ天おすすめアレンジ5選2016/11/29(提供元:株式会社ZUU)伊予銀行
抜粋
さつま揚げとは違う「じゃこ天」の個性とは?
じゃこ天とは、小魚のすり身を小判型にして油で揚げた、練り物の一種だ。
練り物の代表格としてさつま揚げが挙げられるが、食感に大きな違いがある。さつま揚げがフワフワとしているのに対し、じゃこ天はキシキシとした食感で、歯ごたえがある。歯ごたえの理由は、小魚を骨ごと、皮付きのまますりつぶしているからだ。魚をまるごと使っていることで、カルシウムやDHA・EPAが豊富で、噛めば噛むほど風味が増す。
宇和島市では、魚のすり身の揚げ物の事を「天ぷら」と呼んでおり、「じゃこ天」の名は主な原料のハランボ(ホタルジャコ)に、由来しているといわれている。ほかにも、小魚(雑魚)から作られるため「雑魚天(ざこてん)」と名付けられ、のちに「じゃこ天」に変化したなど諸説存在する。この名前からも分かるように、特別な魚を使っているわけではないのだ。
植物油から生まれた海の恵み─「さつま揚げ」:日本植物油協会
練り製品で、最初に誕生したのは、「蒲鉾」です。平安時代に、魚のすり身を竹に塗りつけて焼いたものが、スダレの材料にする植物の蒲(かま)の穂に似ていたところから、「蒲鉾」と称するようになりました。「蒲鉾」の元祖は、今の竹輪のようなものだったわけですね。練り物は「あぶり焼き」からはじまり、時代が下るにつれて、「茹でる」、「蒸す」、「油で揚げる」と加熱方法が加わっていきました。
「さつま揚げ」が一般に広まるのは、「蒲鉾」誕生から数百年のちの、菜種油が普及する江戸時代後期以降と考えられています。
そのルーツについては、江戸時代に、琉球と呼ばれた沖縄に中国・福建省の揚げ物料理の一つとして伝わり、これを「チキアギ」と呼び、やがて薩摩に渡って、「つけ揚げ」になったという説があります。
また、島津藩主・斉彬公が藩の産業発展策として、大量に獲れる小魚の加工を奨励したという説もあります。
日本の南の先端で生まれた「薩摩のつけ揚げ」は、北上して江戸へ至り、略して「さつま揚げ」と呼ばれるようになりました。今でこそ「さつま揚げ」という名称は全国ブランドとなりましたが、少し前までは関東の限られた地域でしか使われていませんでした。
その他の呼称としては、「てんぷら」が関西をはじめ広範囲に使用されていますが、「揚げ蒲鉾」(東北)、「はんぺん」(関西以西の一部)、さらに魚の種類や部位により「ジャコ天」「皮てんぷら」「身天(みてん)」「骨天(ほねてん)」など、地域によりさまざまな名称があります。
「さつま揚げ」の不思議
名前の由来や薩摩藩の江戸屋敷付近から広まったという話からも、関東地方の「さつま揚げ」は、薩摩の「つけ揚げ」直系と見られます。
しかし、全国のすべての「さつま揚げ」のルーツが、琉球や薩摩かというと、異説があります。
例えば、宇和島の「ジャコ天」の場合、1614年に宇和島藩主となった伊達の殿様が、仙台から蒲鉾職人を連れてきて作らせたのが発端とする説があります。たしかに、宇和島名物となる「蒲鉾」生産の基礎を築いたのは間違いないでしょう。その時期には、すでに中国や南蛮から揚げ物の類の料理が国内に入ってきているので、可能性としてはあるかもしれません。しかし、植物油の供給が十分に行われる体制が整っていないこと、仙台にも宇和島にも「揚げ蒲鉾」の記録は残っていないことから、「ジャコ天」が普及していたとする説には無理があるように考えられます。また、鹿児島、大分、長崎、京阪などから伝えられたという説もありますが、ルーツを確定することはできないようです。
鹿児島の「つけ揚げ」も宇和島の「ジャコ天」も、かつては家々でつくられていた料理でした。利用価値の少ない小魚を用い、骨ごと無駄なく潰すので栄養たっぷり、見た目の黒っぽさは揚げ色でカバーして、おいしく仕上げる「さつま揚げ」は、庶民の「もったいない精神」が育んだエコ製品ともいえそうです。
5/27、28長崎旅行:JR長崎駅前 凛々丸で人生初のカラスミ・すりみあげ・フカ湯引、炉談のちゃんぽんに挑戦!と、グレープ:朝刊(1975)

長崎馳走・バル ボンボヤージ:すり身揚げ680円(税抜)
「揚げかまぼこ」の呼び名で全国めぐり2015年8月13日
あなたの地元では「魚のすり身を揚げたもの」を何と呼ぶ?2013年3月13日 16時20分 マイナビニュース(ライブドアニュース)
また、さつま揚げは全国的にさつま揚げと呼ばれているのかと思っていたら、各地で呼び名が違うのに驚きました。鹿児島県でもさつま揚げとは呼ばれていないそうです。ネットを検索しても、全国の「魚のすり身を揚げたもの」の名称一覧はまだありません。これを作った人は日本初の快挙になると思います。
ところで、5月に長崎旅行で凛々丸で食べた、揚げたてのすりみあげは、月並みな表現で言うと、ほっぺたが落ちるくらい、とてつもなくおいしかったです。今までほとんど冷蔵庫から出した冷たいものしか食べたことがありませんでしたが、これを食べてさつま揚げに関するイメージが一新しました。今回の件で思いだしたついでに、機会があれば東京で長崎料理店を見つけてまた食べたいです。
■参考リンク
「じゃこ天は貧乏くさい」発言で炎上・謝罪の佐竹知事は「憎めない失言キャラ」? 秋田県民は呆れながらもどこか慣れた様子でフォローABEMA的ニュースショー千原ジュニア,田中萌

殿様も愛したじゃこ天おすすめアレンジ5選2016/11/29(提供元:株式会社ZUU)伊予銀行
抜粋
さつま揚げとは違う「じゃこ天」の個性とは?
じゃこ天とは、小魚のすり身を小判型にして油で揚げた、練り物の一種だ。
練り物の代表格としてさつま揚げが挙げられるが、食感に大きな違いがある。さつま揚げがフワフワとしているのに対し、じゃこ天はキシキシとした食感で、歯ごたえがある。歯ごたえの理由は、小魚を骨ごと、皮付きのまますりつぶしているからだ。魚をまるごと使っていることで、カルシウムやDHA・EPAが豊富で、噛めば噛むほど風味が増す。
宇和島市では、魚のすり身の揚げ物の事を「天ぷら」と呼んでおり、「じゃこ天」の名は主な原料のハランボ(ホタルジャコ)に、由来しているといわれている。ほかにも、小魚(雑魚)から作られるため「雑魚天(ざこてん)」と名付けられ、のちに「じゃこ天」に変化したなど諸説存在する。この名前からも分かるように、特別な魚を使っているわけではないのだ。
植物油から生まれた海の恵み─「さつま揚げ」:日本植物油協会
練り製品で、最初に誕生したのは、「蒲鉾」です。平安時代に、魚のすり身を竹に塗りつけて焼いたものが、スダレの材料にする植物の蒲(かま)の穂に似ていたところから、「蒲鉾」と称するようになりました。「蒲鉾」の元祖は、今の竹輪のようなものだったわけですね。練り物は「あぶり焼き」からはじまり、時代が下るにつれて、「茹でる」、「蒸す」、「油で揚げる」と加熱方法が加わっていきました。
「さつま揚げ」が一般に広まるのは、「蒲鉾」誕生から数百年のちの、菜種油が普及する江戸時代後期以降と考えられています。
そのルーツについては、江戸時代に、琉球と呼ばれた沖縄に中国・福建省の揚げ物料理の一つとして伝わり、これを「チキアギ」と呼び、やがて薩摩に渡って、「つけ揚げ」になったという説があります。
また、島津藩主・斉彬公が藩の産業発展策として、大量に獲れる小魚の加工を奨励したという説もあります。
日本の南の先端で生まれた「薩摩のつけ揚げ」は、北上して江戸へ至り、略して「さつま揚げ」と呼ばれるようになりました。今でこそ「さつま揚げ」という名称は全国ブランドとなりましたが、少し前までは関東の限られた地域でしか使われていませんでした。
その他の呼称としては、「てんぷら」が関西をはじめ広範囲に使用されていますが、「揚げ蒲鉾」(東北)、「はんぺん」(関西以西の一部)、さらに魚の種類や部位により「ジャコ天」「皮てんぷら」「身天(みてん)」「骨天(ほねてん)」など、地域によりさまざまな名称があります。
「さつま揚げ」の不思議
名前の由来や薩摩藩の江戸屋敷付近から広まったという話からも、関東地方の「さつま揚げ」は、薩摩の「つけ揚げ」直系と見られます。
しかし、全国のすべての「さつま揚げ」のルーツが、琉球や薩摩かというと、異説があります。
例えば、宇和島の「ジャコ天」の場合、1614年に宇和島藩主となった伊達の殿様が、仙台から蒲鉾職人を連れてきて作らせたのが発端とする説があります。たしかに、宇和島名物となる「蒲鉾」生産の基礎を築いたのは間違いないでしょう。その時期には、すでに中国や南蛮から揚げ物の類の料理が国内に入ってきているので、可能性としてはあるかもしれません。しかし、植物油の供給が十分に行われる体制が整っていないこと、仙台にも宇和島にも「揚げ蒲鉾」の記録は残っていないことから、「ジャコ天」が普及していたとする説には無理があるように考えられます。また、鹿児島、大分、長崎、京阪などから伝えられたという説もありますが、ルーツを確定することはできないようです。
鹿児島の「つけ揚げ」も宇和島の「ジャコ天」も、かつては家々でつくられていた料理でした。利用価値の少ない小魚を用い、骨ごと無駄なく潰すので栄養たっぷり、見た目の黒っぽさは揚げ色でカバーして、おいしく仕上げる「さつま揚げ」は、庶民の「もったいない精神」が育んだエコ製品ともいえそうです。
5/27、28長崎旅行:JR長崎駅前 凛々丸で人生初のカラスミ・すりみあげ・フカ湯引、炉談のちゃんぽんに挑戦!と、グレープ:朝刊(1975)

長崎馳走・バル ボンボヤージ:すり身揚げ680円(税抜)
「揚げかまぼこ」の呼び名で全国めぐり2015年8月13日
あなたの地元では「魚のすり身を揚げたもの」を何と呼ぶ?2013年3月13日 16時20分 マイナビニュース(ライブドアニュース)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2023.11.12 00:25:42
[グルメ Gourmet] カテゴリの最新記事
-
孤独にぐるぐるグルメ:6/16 長命寺桜もち… 2024.06.14
-
孤独にぐるぐるグルメ:太田ベーカリー(… 2024.05.16
-
孤独にぐるぐるグルメ:たつ屋の牛丼(新… 2024.05.14
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.