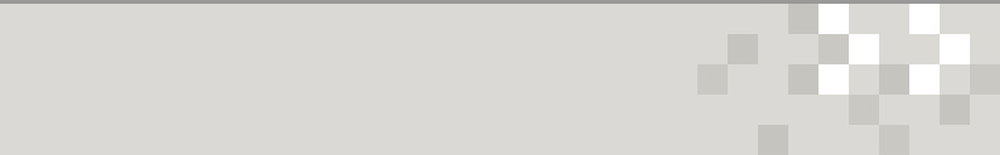全35件 (35件中 1-35件目)
1
-
「NHK"約束"評価委員会」なんてものがあるらしい。
「過半数が支払い督促支持 NHKの視聴者調査」こんな記事があって。何だかあまりにも好意的な結果に見えたので、ちょっと違和感もあり、元ネタにあたってみました。「NHK"約束"評価委員会」なるサイトがそれ。調査結果は、「平成17年度NHK“約束”評価報告書」にあるようです。ざっと見ていたら、種明かしが見えて来ました。要するに、回答者が偏っているんじゃないのかなあ、と。まず、やたら60歳以上が多い。回答数が2,018で、そのうち60歳以上が811人だから、4割以上が60歳以上。一方で、20代以下は228人で11.3%。NHKへの接触が多い高齢者では、若年層より好意的な回答になる可能性は高いのではないかと思われます。受信料支払者も多く、回答者の85.7%が支払っています。ちなみに2005年度末の受信契約率は78.5%。さらに、契約をしていている人の中にも支払拒否・保留している人がいるため、実際の支払率はもっと低いだろうと。支払拒否・保留の人の方がより厳しい意見を持っていると考える方が自然でしょうから、今回の回答者はやや甘めの方、ということになります。そもそも、回答率が6割を切っています。NHKにそもそも価値を見いだしていない人は回答すらしなかった可能性もあり、結果として好意的な結果になったとも考えられます。このあたり、アンケート調査の限界みたいなものもあるので、回答者が偏っていること自体をあげつらうつもりはないのです。でも、こうした偏りが結果にどのような影響を与えているかの分析もろくにしないで、「NHKの取り組みが視聴者のみなさまから一定の評価をいただいたものと考えています。(17年度“約束”の評価を受けて)」なんていう自己満足なコメントを出してしまうあたり、報道機関としていかがなものかな、と思ってしまうのも確か。個人的に、税金(官)でも広告料(民)でもない受信料に支えられるメディアが存在することは、本来であれば大きな意義があるものだとは思っていて、だから、自分自身は親元を離れて以来、受信料はちゃんと払ってはいるのですが。ああいうコメントを見ると、やっぱりどうしようかなあ、と思ってしまうのも本音です。
2006/06/27
コメント(76)
-
米国産牛肉の輸入再開
<米産牛肉輸入再開>日米政府が合意 7月下旬にも店頭に (毎日新聞)米国産牛肉の安全性について論評する能力はない。日本がやっている全頭検査が安全を保証しないのも知っている。でも、1つだけ思うこととして。「どんなに良いものだとしても、押し売りからモノを買ってはいけない」何の資金になるか分かったもんじゃない。
2006/06/22
コメント(1)
-
チョッキを着た犬
もう目にした方も多いと思いますが、電車で見た週刊文春の吊り広告に「天下の暴論/犬にチョッキを着せるバカ」なんてものがありました。いや、私も最近まで似たようなことを思ってたんです。さすがにバカとまではいいませんが、毛皮のある動物に服を着せるのはどんなもんだろう、と。ところが。1月6日付けの日経MJ(日経流通新聞)の記事『愛犬消費が止まらない』によれば、「空調管理された室内に慣れて、衣服を着用しないと風邪をひいてしまう犬もいる」のだとか。それは犬としてどうよ、と思う気持ちはやまやまなのですが、ともかく、服を着ている犬がいたとしても、一概に、飼い主の自己満足とかバカとかは言えないもののようです。以上、先入観を持たずに物事を考えるのは難しいなあ、というお話でした。
2006/01/12
コメント(0)
-
Restart.
長いお休みから密かに復活。今度は、短めでもいいのでマメに書こうと。それはそうと、長男が今日で無事4ヶ月になりました。なぜか早くも下の歯が生えはじめて、どうなる母乳育児?でも、父親にはあんまり打つ手がないので。まずは静観。
2006/01/11
コメント(0)
-

迷惑メールに本当に効いた!~Shuriken Pro4 /R.2
迷惑メール、どのぐらい来ますか?私が会社で使っているメールアドレスは、その昔問い合わせ先として公開してあった後遺症で、今でも月に1,000件前後の迷惑メールが届きます。以前は土日に集中していたのですが、最近は平日の昼間にも来るので、鬱陶しいことこの上なし。そんなわけで、「迷惑メールのメールヘッダや本文から特長を抽出して学習」するという「学習型迷惑メールフィルタ」なる新機能を搭載したShuriken Pro4 /R.2は、発表当初からとても期待していたメールソフトです。ちなみにShuriken Proそのものは、私が数年前から使っていたソフトなのですが、迷惑メール対策は、正直イマイチでした。アドレスやタイトルの全部・一部を指定して振り分ける機能はあるのですが、迷惑メールの差し出しに使うメールアドレスなんて使い捨てのようなものですし。タイトルも、当たり障りのないものが増えた最近では判別が難しい。これならThunderbirdの方が良いかな、などと思い始めていた矢先の発表だったのです。バージョンアップは、11/10からできるようになったので、早速試してみました。バージョンアップすると、迷惑メールフィルタとして「学習型迷惑メールフィルタ」が選択できるようになるので、これを選択し、この数ヶ月間にたまった迷惑メールを全て「迷惑メールとして認識」させてみました。ここまで数分程度の作業です。ちなみに、「迷惑メール」フォルダ内にあるメールを迷惑メールとして認識させることはできません。いったん他のフォルダに移す必要があります。それからほぼ1週間が経って。「迷惑メール」フォルダのメール総数は350通ほど増えました。でも、そのほとんどは私の目に触れず、自動的に迷惑メールと判定されたものです。私が自分で移動させたメールは、たった3件でした。数ヶ月にわたって執念深く保存した大量の迷惑メールをまとめて覚えさせた効果、ということもあるのでしょうけど、学習型迷惑メールフィルタ、期待以上に活躍してくれているようです。もう一つちなみに。本文の中身を読むような機能は、POP3で受信したメールにしか使えないこともあるのですが、IMAP4でもきちんと使えています。いちいち本文を受信するのは善し悪しではあるのですが。もちろん。期待以上でこそあれ、完璧ということはありません。某市の広報メールマガジンや、ウィークリーまぐまぐ!は、見事に迷惑メールに振り分けられてしまいました。また、なぜか、上長からのメールもいくつか迷惑メールに入っていました。いや、私が入れたんじゃありませんってば。まあ、このあたりは、差出人のアドレスを「ホワイトリスト」に登録することで防げるようになるので、迷惑メールを削除する前の点検を怠らなければ、じきに解決することでしょう。さて。ここまで上手くいくと欲も出てきます。学習させたデータを、自宅のパソコンと会社のパソコンで共有するとか、他のユーザと共有するとか、できないですかね? かなり最強のフィルタに成長すると思うのですが。学習結果はファイルに保存されているようなので、一応できるのではないかとは思うのですが。今度試してみることにします。今後、学習型迷惑メールフィルタをくぐり抜けるような迷惑メールが出てきたら話は変わってくるのでしょうけど。少なくともそれまでは、迷惑メールに悩まされる時間、相当減らしてもらえそうです。
2005/11/16
コメント(2)
-
言葉は正しく使ってほしい。
久々の書き込みがこんなので申し訳ないけど、やっぱり気になってしまう。渡辺会長「ハゲタカ」VS村上「亡者だ」のバ倒激化。おふたりの口げんかの行方に口を挟むのは無粋なので、内容ははしょりますが。破綻した会社に投資するから「ハゲタカ」というのであって、まだ一応元気な阪神電鉄とかTBSとかに投資した人を「ハゲタカ」呼ばわりするのは阪神電鉄とかTBSにかえって失礼だってことを誰かナベツネおじさんに教えてやってくれませんかね。仮にも新聞社主なんだから。以上。
2005/11/15
コメント(0)
-
アカペラ公園2005
立川で行われた「アカペラ公園2005」なるアカペライベントに、私の入っている弱小グループも参加してきました。本当は相方もメンバーの一員なのですが、立川はさすがに子どもを連れて行くには遠すぎる、ということで、今日は家で待機してもらいました。申し訳ないことですが、友だちが来てくれていたようなので、大目に見てもらいましょう。「アカペラ公園」は1997年から続いている老舗イベントで、私が初めて参加した頃の参加は20~30組でしたが、今では110組も出演するという巨大イベントになりました。1グループあたりの持ち時間は4分、1曲歌っておしまいぐらいの時間ではあるのですが、その分敷居が低いので、日頃からメンバーを固定して活動しているグループのほかに、イベント向けに結成したグループもたくさん出ているようです。レベルとしてはまあ、玉石混淆というのは否めませんが(自分のグループは置いておいて、、、)、選曲や演出、アレンジなど含めて、まだまだいろいろな発見があるイベントだったかな、と思います。個人的には、コーラスの巧さを感じるグループがちょっと増えたような気がするのは良い傾向かな、と。あと、初期から出ているようなグループ(人)には、やはり何かしらの技を感じさせてくれる人が多いなあ、とも。結成して間もないグループが今回もたくさん出ていましたが、是非是非長く続けて欲しいです。最後にいちおう自分のグループにも触れておくと。結成x年という割にお耳汚しな演奏ではあったと思うのですが。それでも毎年少しずつは進歩していると思いますので、気長に、大目に見ておいてもらえると、良いなあ、、、
2005/10/23
コメント(1)
-
ベビーカーデビュー
1ヶ月検診や初宮参りのときは、スリング(万能だっこひも、というのですかね。)に入れてお出かけしていたのですが。2ヶ月過ぎたら使おうと思って用意していたベビーカー(ココットコンパクトW EG BU-570)が実は1ヶ月児からOKだったことが判明。急遽、近所のショッピングモールへ、ベビーカーでお出かけすることになりました(別に無理矢理使わなくても良いでしょ、という話もあり)。1ヶ月児から使えるというだけあって、子どもは寝かせたまま、対面でのせることができます。シートベルトが少し窮屈そうにも見えますが、手足は十分動かせるので、嫌がりもせずに収まってくれました(あ、写真とっておけば良かったな)。スリングもそうなんですが、狭いところは別にいやじゃないんですね。猫みたい。ただ、困ったのが道路。さすがに舗装されているのはされているのですが、簡易舗装なのか予想以上にガタガタします。工事の名残なのかつぎはぎも多く。気持ちよく押していける道路ではあんまりなかったかと。でも当人の方は、不審そうな表情をすることはありましたが、特に泣きもせず騒ぎもせず。帰り道では寝入っていたので、親が気にするほど道の凹凸は気にならないものなのかも知れません。まだしょっちゅうお出かけするには早いのでしょうけど、すこし行動半径が広がりそうです。
2005/10/22
コメント(2)
-

チーズの話じゃなくて猫の話。
今日は和めるマンガの紹介、と。チーズスイートホーム(第1巻)。チーという猫が主人公のマンガです。会社から帰る電車の中で、隣に立っているおじさんが読んでいる雑誌に、何か猫のマンガがある! とばし読みされてしまったのでどうしても気になり、うろ覚えのタイトルを手がかりに、改札最寄りの本屋で速攻で買いまいした、、、、いいのか3x歳。あらすじ。主人公チーは、母猫との散歩の途中に迷子になってしまい、山田家に拾われてきたのですが。母猫の元に帰ろう帰ろうと思いながら、子猫ゆえに手段もなく。一方の山田さんの方ももらい手を探すのにかなわず。お風呂に入れられて大変な目にあったり、勘違いをしながらトイレトレーニングをしたり、猫用おもちゃが入っていたレジ袋にじゃれたり、子どもが持っていたスーパーボールにじゃれたり、ソファーより高いビンテージもののジーンズをひっかいたり、病院に検診に行って怖い目に遭ったり、というああ、猫だなあ、という話が全20話あります。山田さんのマンションはペット禁止、しかも1階の部屋なので、大家さんや近所の人に見つからないようにしないと!、というハラハラ感がちょっとしたスパイスになっています。個人的には、出窓に上がって見つかりそうになるチーを、ぬいぐるみをたくさん置いてカモフラージュするエピソードがちょっと楽しいかと。いや、だってマンガじゃなきゃ絶対あり得ない話じゃないですか。あとは、じゃれてるところや眠ってるところなど、猫好き向けカットも満載。日をおかず2巻目も買ってしまいましたとも、ええ。週刊モーニングで今も連載中。世間ではとうの昔に人気のようで、カレンダーやらストラップやらも売っているんですね。しかし週刊モーニングってことは、ジパングとか島耕作とかに並んでるのね。おそるべし、猫。
2005/10/21
コメント(4)
-
おつうじ。
2日ほど固めの話が続いたので、今日は気楽なお話、と思ったら。子どもが、60時間に近づきつつある便秘のためなのか、泣いたりうなったりしてなかなか寝つかない状況、、、今夜は長期戦になりそうなので、今日考えていたネタは明日に延ばし、これから相方と共同作戦で、寝付かせるのに集中することにします。間隔が1日2日空くのはいつものことなのですが、その度に何とかしてやれないかな、と思うのだけど。育児本にはたいてい、5日ぐらい空いた時の対処法しか書いていないので。どうやったらスムーズになるのかなあ。大人と違って繊維質をとらせるわけにもいかないし。お食事中の方、失礼しました。ではまた。
2005/10/20
コメント(0)
-
少子化対策:「両立支援より経済的支援」? それって誰が言っているんだろう?
ずっと気になっていたのですが、もう10日も前に、こんなニュースが出ていたの、記憶にありますか?「少子化対策、母親の7割「経済支援を」…内閣府調査」内閣府は8日、少子化対策に関する母親の意識調査の結果を発表した。少子化対策で重要な政策(複数回答)としては、「経済的支援措置」が69.9%で最も多く、「保育所など子供を預かる事業の拡充」が39.1%、「出産や育児のための休業・短時間勤務」が37.9%で続いた。経済支援を挙げた人に、具体的に望ましい対策(同)を質問すると、「保育料・幼稚園費の軽減」が67.7%に上り、「乳幼児の医療費の無料化」は45.8%、「児童手当の引き上げ」は44.7%だった。(中略)調査は、今年2~3月に子供を持つ全国の20~49歳の女性4000人を対象に実施し、2260人が回答した。ちなみに、調査の元ネタはこちらです。これにひとこと付け加えて記事にしているのが朝日新聞です。「子育て支援は「お金」が重要 内閣府の意識調査」なる記事中で、「1999年に総理府(当時)が行った意識調査で、必要な支援を聞いた際には「子育て中の夫婦が共に働けるような環境整備」が、税負担の軽減や現金給付の充実といった経済的支援を上回っていた。」ことを指摘し、「母親が重要と考える少子化対策は、仕事と子育ての両立支援から、保育料の軽減など「経済的支援」に変わってきている」とまとめています(実際はリード文)。背景としては、国民生活白書(2005年版)で、子育て世代の実質可処分所得が1990年以降ほとんど伸びていない一方で、世代内の所得格差が1997年から広がっていることを挙げています。記者発表だけに頼らず、自分でもいろいろ調べたことは評価しましょう。でも、問題はその内容。比較対象となっている総理府の調査というのは「少子化に関する世論調査」のことだと思いますが、質問票を見ると、今回の調査とは次のような違いがあります。内閣府調査は複数回答ですが、総理府調査は単一回答です。総理府調査では、内閣府調査で「経済的支援」とひとくくりにしている内容を「現金給付」と「税負担」に分けて質問しています総理府調査で「大いに働けるような環境の整備」とひとくくりにされていた内容が「子どもを預かる事業の拡充」「休業・短時間勤務」「再就職支援」「両立の推進に取り組む事業所への支援」といった具合に細分化されています要するに今回の調査は、最初から「経済的支援」と回答する比率が高くなるような調査設計になっているわけで、両者を単純に比較するのは意味のないことなのです。なのにここから無理矢理結論をひねり出して(ある意味ねつ造とも言う)世論や政策をミスリードしかねない記事を出したりするのは、報道機関としてどうなのかなあ、と思ってしまいます。あと、そういう調査設計のアンケートをした内閣府にどういう意図があったのかも、非常に気になるところです。子育て世代で世代内の所得格差が増えているのはそうなのでしょうし、そもそもお金はあって困るものではないので、経済的支援が充実されることは良いことなのですが。でも、それ以外の政策の重要度が低いというわけでは、恐らくないはずです。内閣府アンケートでも、フルタイム勤務者に限れば「子どもを預かる事業の拡充」「休業・短時間勤務」への支持は4割台(経済的支援は6割台)と全体より高いわけですし、実際、待機児童数だけを見ても、2001年には21,031人だったのが2004年には24,245人と大幅に増えているわけで(厚生労働省「保育所入所待機児童数調査」。実は2003年から2004年は、2000人ほど減っています。)、両立支援へのニーズが下がったなんて、まだまだ言える状況ではないと思うんですけどね。あと、たった1ヶ月子どもを育てた経験からすると(偉そうに。。。)、祖父母などの支援がほとんど得られない環境で、言葉の通じない子どもと24時間向き合うのは、(特に母親にとっては)精神的にも肉体的にも想像以上にきついものがあると感じています。私は幸いにも、自己判断で休みをまとめてとったり残業を短めにしたりすることができる会社にいるので少なくとも猫の手にはなったはず、、、、と信じてますが、世の中そうもいかない仕事の方が多いわけで。大きくなったら大きくなったで、必要なタイミングで保育園に入れる保証もなく、小学校に入れば学童保育も全然足りない、長期休暇にはどうするんだ、という話も待っていて、、、経済的支援を増やしてもらっても、ちょっと解決し難い問題がたくさん思い浮かびます。あ、でももしかして、経済的支援を増やして代わりに共働きを減らそう、という意図があるのか? それとも両立支援なんていらない人が本当に増えているのか? 実際のところは、どうなっているんでしょう?
2005/10/19
コメント(2)
-
靖国参拝:強気に出るだけでは知恵がないよね、お互いに。
賊軍の本拠地である福島県出身の私としては、薩長の戦死者を祀る目的でできた靖国神社の肩を持つ筋合いがそもそもなかったりするのですが。加えて、靖国神社は現在でも、「日本の独立をしっかりと守り、平和な国として、まわりのアジアの国々と共に栄えていくためには、戦わなければならなかったのです(やすくにQ&A)」っていう、そういう側面もあるけどそれはさすがに言い過ぎでしょ、という主張をしているところなので、政教分離とかA級戦犯合祀の話を別にしたとしても、一国の首相が定期的に訪問するべき場所としてどうなのかなあ、と思う気持ちがあるのも確かです。国としてそういう主張を肯定しているというメッセージとして受け取られるのは全くもって不本意ですから。でも、「人類の良識と国際正義への挑戦(人民日報)」とか「日中関係を破壊した歴史的責任(在日中国大使)」とか「大きな負の遺産が残された(朝日新聞)」なんて事大的な話を判で押したように繰り返されると、参拝されたら無視するわけにはいかないお家の事情があるのは理解できるにせよ、正直言って辟易してくるのも本当のところです。歴史に対する責任のとり方(そもそもこういったケースで責任をとるというのが世界史的に当然のことなのか、という話もありますが)が様々あり、いくつかが実行されている中で、参拝などという言ってしまえば形式的な意味しかもたない部分を「歴史問題の核心(韓国大統領)」に位置づけることに何の意味があるのかがよく分かりませんし、参拝と反省を結びつけることもナンセンスかと思います。論理的には、長期間参拝しなかったとしても、いつか「する」可能性があるとして、「別の形での反省」を示すことが要求されると考えるのが自然ですし、それなら最初から別の形で双方納得する方がよっぽど建設的です。また、仮に代替施設を作って、靖国神社へは一切参拝しないという話を信用してもらえたとしても、すでに「日中関係特別調査、日本から「軍国主義」連想8割」なんていう調査結果があるぐらい(回答サンプルはおそらく統計的に偏ってますが)、あることないこと徹底的に刷り込まれているわけなので、きっと他の何かしらを探し出してでも批判してくるのだろうなあ、とも思ってしまうわけで、、、、、負の遺産を残したり、関係が破壊されたりするのは、日本側が参拝しなければどうにかなることとはもはや思われません。ただそうも思う一方で。昨日の朝は、「中国、対日現実路線へ転換か 胡体制安定 常任理入り理解」なんてニュースも流れていて。数年前に「対日新思考」をめぐって論争が起こったことも思い起こすと、中国政府内でさえも、必ずしも反日一色ではないと考える方が適切なのだろうと思います。そうすると、意地で参拝して、中国政府内で、日本の(どちらかといえば)味方になってくれそうな人の立場を悪くするのは、あんまり得なことではない可能性もあるのかな、と。日米関係を例に出すとよく分かると思いますが、自国にメリットがある政治家の発言力が強まるよう側面支援するのは、外交上よくあるテクニックでもあるわけですし。「国のために殉じた方に尊崇の念を表するのはリーダーとして当然(安倍晋三)」「外国政府が、日本人が日本人の戦没者に、あるいは世界の戦没者に哀悼の誠をささげるのを、いけないとか言う問題じゃない(小泉純一郎)」というのはそれはそれで正論だと思うのだけど。「尊崇の念を表する」「哀悼の誠をささげる」というのは、果たして正論を振りかざして、意地になって肩肘を張ってするものなのかどうか。とにかく、正面からの強行突破だけでは同じことの繰り返しになるのはもう分かっているのだから、相手国政府内での味方の立場を強くすることにもちゃんとつながるやり方、何か、ないのかねえ?
2005/10/18
コメント(6)
-
読むのも書くのもすっかりご無沙汰でした。
相方と子どもが退院して以来、仕事からはできるだけ早く帰って、家にいる間はできるだけ自分で子どもの面倒を見て、相方が多少なりとも息を抜けるようにする、というまるで教科書のような方針で暮らそうとしていて。でも、新生児は眠っている時間も長いはずだから、結構自分の時間もとれるのではないかと目論んでいたのですが。子どもがそんなに思い通りに生活してくれるはず、ないのです。いや、分かっていたつもりなのですが。予想以上に、よく起きている子どもであることが判明。機嫌が良い日はそれも良いのだけど、抱いても泣き寝かせても泣き、寝かしつけたと思っても数分後には泣き、、、、、これにできるだけ真面目につきあっていたら結局のところ、1ヶ月近いご無沙汰になってしまいました。ま、多少は苦労した甲斐があって、先週末には1ヶ月検診、初宮参りと一応の区切りもついて。生活リズムの方も少しは安定してきたので、そろそろまじめに書き込みを再開しようかと思います。ま、今日のところは宣言だけだったりするのですけど。
2005/10/17
コメント(4)
-

せっかく沐浴させるのなら。
プチ育休2日目。ようやっと出生届を出しに行くことができました。しかし出生届の審査に15分って、いったい何を審査していたのだろう? 純粋に、興味津々。さて。昨日宣言した目標「プチ育休の間に沐浴も手慣れておく」を達成すべく、今日は沐浴に挑戦してみることにしました。でも1つだけ目論見があって。以前、「一緒にお風呂に入れるようになってから楽しそう」と相方が言うので購入したタミータブなるものを使ってみることにしました。タミータブ、テレビでも紹介されていたことがあるそうなので知っている人も多いでしょうが、左側の写真を見て分かるとおり、要するにとっても気の利いたバケツです。売りとしては、「胎児期と同じ姿勢なので安心し、赤ちゃんのストレスを取り除くことができる」こと、そして「少ないお湯で肩までスッポリ入るので体全体が温まる」ことなのだとか。前者は「そうなんですか」としか言いようがないですが、後者は、なんか聞くからに気持ちよさそうですよね。普通のベビーバスだと、全身お湯につかっていることってあまりないですし。あと、ちょっと不穏な発言をするとすれば、新生児は浮かす状態で入れるそうなので、これもちょっと見てみたい。そんなこんなで、実際使ってみたのですが。やっぱり難しい、、、もちろん最初は浮いてくれるのです。ちょっと楽しい。入れられる方も落ち着いたもの。でも手足が動くとバランスが崩れてしまって。結構支えるのに努力がいります。いやでも、毎日使っていると慣れるのかなあ。結局今日は、途中で普通のベビーバスに入れ替えてしまいました。でもちょっと長湯になったからなのか、今日は昨日よりぐっすり眠っているようです。で、我が家のタミータブですが。このままだと首がすわるまで、お預け?になってしまいそうです。新生児を上手に入れるノウハウ、もしご存じの方がいらっしゃれば教えて頂けるとうれしいです。
2005/09/22
コメント(2)
-
親業、今日から本番。
今日午前に、相方と子どもが退院してきました。周囲の人からは「退院に備えて今のうちに寝だめしておけ」というありがたいアドバイスを頂いていたのですが、前日夜になってから(仕事がらみで)いろいろあり、、、結局寝不足で退院を迎えることに。でも24時現在、大泣きするでもなく、比較的平穏な夜が過ごせています。まあ、これから朝まで6時間ありますので、さてこのまま無事に済むかどうか。先週末の連休中は、結構長い時間病院に滞在していたので、おむつ替えやら授乳はそこそこ慣れてきてはいて、今日も多少は手出しができたのですが。沐浴は6月の両親学級の記憶がだいぶ薄れてしまい、、、、、相方に完全にお任せになってしまいました、、、、、ともかく今日から来週水曜までは、「プチ育休」とか銘打って有給休暇をいただくことができたので。その間に沐浴も手慣れておくことを目標にしましょう。
2005/09/21
コメント(2)
-

実験:中国語はパソコンで勉強できる?
実は1年ほど前から中国語を習いに通っているのですが。あんまり考えないで、通いやすい場所というだけで選んだら、発音はあんまり気にしないでとにかく「いっぱいしゃべれる」という方針らしい、ということに最近ようやく気がつきました。いや、いくら何でもさすがにそれは違うだろ、という発音をする人がいても、ほとんど注意がなく、、、これで説的很好(よくできました)、って言われても、ねえ。ただ、時々ネイティブ並(に聞こえる)発音の人がいて、ああ、自分でがんばってるんだろうな、と。自分も何とかしないとなあ、ということで、出来心で試しにこんなものを買ってみました。学研の「パーフェクトマスター中国語」。要するに、画面に出た文を発音すると、音声認識エンジンを使って採点してくれる、というパソコンソフトです。音声認識エンジンというと、10年近く前に、日本語の音声認識ソフトを使って議事録をとろうとして、かえって大変な思いをしたことを思い出しますが、早速、どのぐらい使い物になるか、試してみました。*****とはいえ。あんまり面倒なフレーズだと、ヘボな私はそもそも正しい発音ができないかも知れない。そこで、「こんにちは」「ありがとう」ぐらいのおなじみのフレーズで、次の方法で試してみました。 (i)四声を間違えてみる …中国語は音節ごとにイントネーション(のようなもの)があるのですが、これを間違えてみます。 なおここでは、一声を(1)のように書きます。 (ii)母音を間違えてみる (iii)有気音と無気音を間違えてみる …kとgのように、息の音が伴う子音とない子音があるのですが、これを間違えてみます。 (iv)紛らわしい子音を間違えてみる …cとshとsとか、個人的に紛らわしいと思っている子音があるので、これを間違えてみます。 (v)正しいつもりでやってみる …実はこれが一番難しかったり。*****まず、「こんにちは」。(i)で、Ni(1)haoとやってみる。なぜか合格。(ii)で、Nahaoとやってみる。なんだか合格。(iii)(iv)はできないので、(v)でNi(3)haoとやってみる。さすがに合格。早速不安になってきましたが、次に、「ありがとう」。(i)で、Xie(1)xieとやってみる。とりあえず合格。(ii)で、Xiaxiaとやってみる。今度は不合格。(iii)はちょっと難しいので、(iv)で、Siesieとやってみる。再び合格。もうひとつ(iv)で、Shieshieともやってみる。それでも合格。最後に(v)で、Xie(4)xieとやってみる。もちろん合格。コメントは省略して、最後に、「かまいません」。(i)で、Mei(1) guanxiとやってみる。なぜか合格。(ii)で、Mai guanxiとやってみる。これも合格。(iii)で、Mei kuanxiとやってみる。やっぱり合格。(iv)で、Mei kuanshiとやってみる。でも合格。(v)で、Mei(2) guanxiとやってみる。一応合格。*****で、この結果から導きうる結論は、次の3つ。結論1「発音って、そんなに神経質にならないでいいのかも、、、」結論2「このソフト、あんまり使い物にならないかも、、、」結論3「自分では発音変えたつもりが、全然変わってないのかも、、、、、、(自爆)」*****結局のところ、どうも私レベルの発音では白黒つけがたいので、どなたか追試していただけると、嬉しいです。それでもって結果を教えてくれると、もっと嬉しいです。ちなみに詳しい商品紹介はこちら(学研のサイト)です。#なんてオチだ、、、、
2005/09/15
コメント(0)
-
ぐずる理由?
会社帰りに病院に顔を出して。相方はまだ子どもと同室ではないのですが、看護婦さん(助産婦さん?)が気を利かせたのか、子どもを連れてきてくれました。途中まではずっと寝入っていて、それでも百面相をしていて、気楽に見ていたのですがぐずりだしてからは、抱き上げたりおむつを替えたりなでたりさすったり。でも結局、決定打はなし。今日は面会時間終了で、看護婦さんがそのまま新生児室に連れて行ってしまいましたが。退院したら、2人でどうにかしないといけないわけで、どうなることか、今から楽しみではあります。どうしてぐずってたのかは、今のところ謎。首のあたりを払いのけるようにして動いていたので、生まれてくる時の夢でも見ているのかとも思いましたが、さすがにそれはないのだろうなあ。
2005/09/14
コメント(2)
-
総選挙の感想を少し。
投票(期日前投票)してからだいぶたつので、もう昔の話のような気がしてきてしまっていますが、お約束ですので。国民新党とかそれに近い方々がキャスティングボードを握れないという意味では非常に良い結果だと思うのですが、それにしても自民党、ちょっと多すぎるかなあ、と。公約には、正直、、、な政策もあるので、あまり国会運営が楽になってしまうのは考えもの。まあ、今回は民主党が戦略でも政策でも激しく自滅してたから、惨敗したのは仕方がないとは思います。そういえば、運動期間中に立ち寄ったある駅前で、民主党候補が「政党の命である政権公約を自民党が官僚に書かせたのは許せない、我々は徹夜で書いた」というようなことを叫んでましたが、どちらもあんまり自慢にならないような。あと、これまではイメージや期待が先行して成長してきた面が強くて、必ずしも政策が理解されて支持を広げてきた訳ではない、という自己認識が不足しているのではないかなあ。だからあんなにあっさり主役を奪われるのではないかな、と。まあいい機会なので、党内での政策的な対立の論点整理をして、突っ込まれると弱い部分を1つ1つつぶしていくのが良いのではないかと。あと、民主党の代わりに共産党や社民党ががんばってくれていれば、もう少し緊張感がある国会になるのでしょうけど、こちらも今ひとつだったかなあ。これまで通りに護憲と増税反対を言えば、必ず票を入れてくれる層がいるのは確かなのだと思いますが。護憲(とりあえず9条限定の話)なら、憲法を守りつつ国民の安全を守る方法・筋道を、増税反対なら、後の世代へのつけを減らしていく方法・筋道を、支援者以外にも伝わる、できれば検証可能な形で伝えていかないと、現在以上の勢力は望めないのではないですかね? 特に、大規模公共事業と防衛費の削減、大企業と高所得者への負担増だけで本当にどうにかなる、と思っている人、そんなに多くはないのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。いずれにしても。今後数年間はこの構成が続くわけですから。総選挙の時だけではなくて、その後の政策の展開についても、有権者としてきちんとフォローしていかないといけないなあ、と思っています。そのようなわけで、政治ネタの割合はこの数週間より減るとは思いますが。マニフェスト紹介でチェックしていただいた方(え、いる?)、これからも時折覗いていただければ幸いです。
2005/09/13
コメント(2)
-
誕生
###今日はいつも以上に、ただのひとりごとです。###今日午前、相方が第一子を出産しました。陣痛が始まってからおよそ60時間で、自然分娩から帝王切開に切り替え、母子ともに経過は順調そうです。よくあるケースですが、へその緒が首に巻き付いていて、出ようとしても出られない状態だったようで。お産がなかなか進行しない中、状況もわからないで「そろそろ出てこようね」とか言っていたのはとっても酷なことをしたなあ、と。反省。物心がつく前に、あやまっておかないと。あと、足かけ3日の先が見えない陣痛に耐えた相方にも。おつかれさま。どうもありがとう。まだ別室なこともあって、どうも実感に乏しいのですが。これからちゃんと、父親になっていきたいと。思います。#選挙以外の話題、すごく久しぶり、、、、、
2005/09/11
コメント(6)
-
選挙に行く前にこの1曲:「お願い!プライムミニスター」
実は昨日、一昨日と出張に出ていたのですが。出張先の駅のおみやげ売り場で、妙な曲を耳にしました。 ♪お小遣いアップ!お小遣いアップ! ♪お願いプライムミニスター、助けてプライムミニスター ♪今すぐに私と政権交代 ♪造反解散公認公示投票。。。 ※どうもこう続けて書くと意味深だなあ。でも実際の歌詞とは多少違って覚えているかも。どうしても気になって、うろ覚えの歌詞を手がかりに調べてみたら。分かりました。toutouなる2人組が歌っている、「お願い!プライムミニスター」。toutouっていうのは初めて聞きましたが。フジテレビ「ガチャガチャポン!」のエンディング「星占いの歌」で、今年7月にデビューした15歳と14歳、片方は1991年生まれ(、、、、、)の姉妹デュオだそうです。ホームページには、「平成のピンクレディ誕生!?」なんて紹介もされてますが、ピンクレディは姉妹じゃなかった気がするぞ。という話は置いておいて。何にせよ、残念なのは、CD発売が11月ってことです。試聴はホームページでできるのですが、ソニーミュージックさんがケチなので、ワンコーラスもかけてくれません。こういう曲こそ音楽配信で先行販売するものでしょうに。ちなみに着うたもありますが、お金を取るにもかかわらず、試聴と同じ長さです(って買ってしまった人)。だから、欲しくなった人はこちらでご予約を。あ、「お願い!プライムミニスター」は実質B面(今はカップリング曲というのだっけ?)なので、リンク先で引かないように。ご注意下さい。さて。選挙はあさってだねえ。相方の出産予定日が11日なので、私はもう投票してしまいましたが。 ♪投票率アップ!
2005/09/09
コメント(2)
-
自由民主党~自立と蜜月
各党の政策/マニフェストを読んでみる企画、第7回(いちおう最終回)は、自由民主党です。自民党からは、120の約束と題された公約のほかに、もう少し具体的に書かれた重点施策2006が発表されています。○郵政民営化 自民党が今回の選挙で一番、もしくは唯一力を入れている政策が郵政民営化です。ですが、「120の約束」には「参議院において否決された民営化関連6法案を次期国会で成立させる」という1行が記されているのみです。提案理由や法案についての説明は一切ありません。まあ、法案の内容はもう十分浸透しているはず、という認識なのかも知れませんが、これで賛否を問おうというのは、確かに「変人以上」です。別にほめようとは思いませんが。 もちろん「重点施策2006」にはもう少し詳しい説明があり、国債の購入や特殊法人向けの資金購入といった「官」の世界でのみ使われていた340兆円もの資産を、民間向け資金として活用する道を開く、という説明が筆頭にあります。小泉首相が1994年に出版した「郵政省解体論」でも、郵貯・簡保資金(を原資とする財政投融資が特殊法人に流れること)について共通した問題意識が示されており、そもそもの原点はこの巨大な資金にあると言えそうです。 実は340兆円を民間に回す、という目的自体は、民主党のマニフェストにも共通しています。ただし民主党は、新会社が「自主的に」国債など購入する可能性がある政府案では民間に回る保証がないことを批判し、当面は預入上限をコントロールして徐々に民間に回す方法を提案しているわけです。とはいえ、民主党案にしても、預入上限を減らしても現実には家族名義の預金に移動させる人が多くなると考えられ、預金量が減少する保証がないこと、個人が上限を超えた分で個人向け国債など購入する可能性があることを考えると、民間に回る保証という点では民主党案も自民党案も五十歩百歩といえます。また、そもそも、郵便貯金や簡易保険の残高は、実質的にほとんどが国債で運用されているため、国債価格の暴落なしで民間に資金を回すのはもはや不可能に近い、という指摘もあります。その意味で「340兆円もの資産を民間向け資金として活用する」方法として民営化が最適と断言することは、現時点ではちょっと難しいのではないかと思います。 また、郵便会社と競争することになる民間企業との競争条件については、全国にポスト10万本などという、高すぎる参入規制については手がつけられておらず、規定が不十分な面もあります。銀行・保険については預金限度額が設けられ、当面は新規事業や企業買収に政府の認可が必要という制限はありますが、公営企業から引き継いだ信頼感や店舗ネットワーク(例えば信用金庫は今年3月末現在、全国で7,879店舗と郵便局の半分以下)が大きなアドバンテージとなり、法案に規定された規制だけでは公正な競争が成り立たない可能性も否定できません。電電公社から民営化したNTTと新電電(KDDIとか日本テレコムとか)の固定電話シェアの差は、やっぱり技術力やサービス内容では説明しきれないと思いますし。 このように、次期国会で成立を目指すという民営化関連6法案は、どうもまだ未完成といった方が良いのではないか、という印象を受けます。ただその一方で、やはり郵政事業を民営化することが望ましいのだとしたら、これが下手をすると最後の機会だという意見も、それはそれで分からないではありません。○年金制度 年金制度については、昨年6月に成立した年金改革法によって、一通りの対応が済んだという認識であるようで、「将来にわたって国民の信頼に応えられる持続可能で安心な年金制度を構築しました」と自己評価されています。復習しておくと、厚生年金の保険料率を2004年以降順次引き上げて18.3%にする、国民年金の保険料を2005年から順次引き上げて月額16,900円にする一方で、給付水準を現役世代の50.2%にまで順次引き下げる、国庫負担割合を2分の1まで増加させる、というものです。この制度、成立時点はもしかすると持続可能だったのかも知れませんが、その後出生率が想定以上に下がったため、早くも見直しの必要があるのではないか、と言われているのはご案内の通りです。 今後の検討課題としては、公務員向けの共済年金と会社員向けの厚生年金の一元化や、非正規労働者の厚生年金加入が挙げられていますが、国民年金は一元化の対象外となっています。また、未納者の増加によるいわゆる「空洞化」や、無年金者・低年金者への対策については、特に記述がありません。○財政再建 財政再建に資する政策としては、中央官庁と地方自治体の組織・人員の業務やスリム化が中心となっています。とはいえ、削減の数値目標は特に示されておらず、国家公務員の定員については「思い切った純減」、地方公務員の定員についても「過去5年間の実績を大きく上回る純減」という、今ひとつ想像がつきにくい表現になっています。ちなみに、総務省「平成16年地方公共団体定員管理調査結果」によれば、過去5年間の職員数は、特別行政(教育、警察、消防)および福祉関係を除いた一般管理だけでは5.8%の減少、両方をあわせると5.4%の減少とのことです。 一方で公共事業については、2007年度までに15%程度のコスト削減を行うことや、「防災、地域再生、国際競争力強化などに厳しく重点化」といった文言はあるのですが、それでも「重点施策2006」で例示された公共事業のラインナップは非常に気合いが入ったものです。目立つものを抜粋すると、北海道新幹線、東北新幹線(八戸新青森間)、北陸新幹線、九州新幹線、大都市圏の環状道路、高規格幹線道路及び地域高規格道路などの自動車専用道路等のネットワークの整備、東京国際(羽田)空港の再拡張、成田国際空港の平行滑走路の2,500m化、関西国際空港の二期事業、既存空港の質的充実、等々。まあ、これもきっと厳しく重点化した結果なのでしょう。私も含め、全然そうは見えない人の方が多いと思いますが。 ただ、予算編成プロセス等の改革に言及していることは高く評価できます。決算結果や政策評価を予算編成に生かすことや、「国家財政ナビゲーション」の整備などが具体的な内容です。このうち「国家財政ナビゲーション」は、現在世代の負担だけではなく将来世代の負担を事業単位でシミュレーションしながら予算編成できるというもので、詳しくは講談社現代新書の「公会計革命」で紹介されています。個人的には、本気でこれを活用するつもりがあるなら、政策決定や予算編成のあり方は相当良い方向に変化するのではないか、と思っています。 ○地方分権、地域産業振興 地方自治体のスリム化に重点がおかれる一方で、税源移譲については民主党案に比べて大きく見劣りするものになっています。中核となっているのは、所得税から個人住民税への税源移譲で、規模は概ね3兆円とされています。なお、昨年の参院選では2006年までに4兆円を以上と公約、すでに実現したのが4,200億円ですので、これでほぼ打ち止めということになります。また、国から地方への補助金や地方交付税のあり方については「重要施策2006」でも、「地方六団体案を尊重しつつ税源移譲に結びつく改革を実現します。」と表現されているのみで、方向性は定かではありません。 地域産業のうち農業については、農林水産省が今年3月に策定した新たな食料・農業・農村基本計画に沿った政策を推進する方向性が示されています。計画の主な内容としては、中核的な農家あるいはその集団に対する直接支払による所得保障や新規就農の支援、環境や農地・農業用水等の保全といった項目が挙げられます。総論としては、それほど他党の政策と変わらない印象を受けますが、違うとすれば、農業関係補助金の扱いでしょうか。他党は削減を明記していますが、自民党の政策にはそうした方針は見あたりません。 また、中小企業振興については、「約束」では融資だけでなく経営相談機能も含めた地域金融機関の役割強化が挙げられている程度であり、あまり重きをおかれていない印象を受けます。ただ、「重要施策2006」では、どの程度の経費をつぎ込むかは定かではありませんが、公設試験場による技術力の客観的な評価や、中小企業への研究開発支援の抜本的な強化といった方針が打ち出されています。基本的に、成長力が高いところに絞り込んで支援をするという考え方がとられているようです。むろん、同じ与党の公明党と同様、必要以上の企業を切り捨ててしまう懸念も感じないではありません。 ○まとめ 「自民党は変わった」のか、それとも変わっていないのか。公約を見る限り、変わったように見える部分もある一方で、イメージそのまんまの部分もあります。 郵政民営化が典型ではあるのですが、従来の支持母体の利益にならない政策を打ち出すようになったのは、確かに変わった点でしょう。中小企業や商工業者の支援策でも、最近では酒販店の逆特区に見られたような、ちょっとやり過ぎともいえる保護策は、少なくとも今回公表された政策文書からは姿を消しています。さらに、予算編成プロセスの改善といった話が公約に出てくる、というのも(もしかしたら昔からそうだったのかも知れませんが)自民党のイメージとは異なる部分です。 その一方、公共事業のラインナップはこれぞ自民党、というべき豪華さ(?)ですし、先に挙げた「新たな食料・農業・農村基本計画(農林水産省)」「健康フロンティア戦略(厚生労働省)」「女性の再チャレンジ応援プラン(内閣府)」「u-Japan政策(総務省)」など、この数年の中央省庁の重点施策や2006年度予算の概算要求と一致する、良くも悪くも中央省庁との強い一体感を感じる政策も数多くあります。もちろん、政府与党がこれまでの政策を否定するような公約を出したらおかしいわけで、一概に悪いと言えないのは確かです。でも、中央省庁に対して、不要な事業を中止したり、やりたがらないが不可欠な事業を実施させたり、といったリーダーシップをどの程度発揮できるのか、言葉を変えればどのぐらい中央省庁から自立しているのか、公約からはちょっと計りかねる、というのが正直な感想です。
2005/09/08
コメント(0)
-
民主党~明瞭さと曖昧さと
各党の政策/マニフェストを読んでみる企画、第6回は、政権交代を目指す野党第一党、民主党です。 民主党のマニフェストについては、広告もばんばん打ってますし(映画の予告編前に2本連続で流れてた)、メディアでも取り上げられているので、ざっとした内容はご存じの方が多いでしょう。ので、内容そのものの紹介よりも、「立候補者の支持・反対の表明」になってしまわない範囲で突っ込みを多くしてみようかと。できるかなあ?○年金制度 民主党が今回の選挙で一番売りにしているのは、ご案内の通り年金制度です。大まかな枠組みとしては他党と同様、全額を税金でまかなう「最低保障年金(民主党案では月額7万円)」と、厚生年金や国民年金などを一元化し、掛け金に応じて支払われる「所得比例年金」の2階建てとなっています。最低保障年金の財源の一部として年金目的消費税の創設が提案されています。また、所得比例年金の料率は15%が上限とされています(現在は13.9%)。 最低保障年金部分については、他党案と同様、将来的に確実な給付を保障している点は評価できます。ただ、想定される支給総額が明示されていないため、3%の年金目的消費税(4.7兆円程度)と2分の1の国庫負担(それ以外の税金)でいつまで賄えるかには疑問も残ります。月額5万円の共産党案(7.7兆円)を基に推計すると年間10.8兆円必要になりますが、年金目的消費税の税収はその半分に足りません。もちろん、最低保障年金は高所得者に給付しない方針であり、167万人(年金受給者の3%程度)を給付対象外にすれば当面はつじつまが合います。ただ、年金受給者は今後数十年にわたって増加するので、近い将来に何らかの対策は不可避になるのではないかと思われます。 また、所得比例部分の給付水準が維持できるかどうかにも不安が残ります。民主党が2004年に国会に提出した「高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するための公的年金制度の抜本的改革を推進する法律案」には、「所得等比例年金の支給は、当該年度に納付された保険料の総額で」という文言があるのですが、保険料を上げず、保険料の支払者が減少する一方で受給者が増えれば、普通に考えて支給額を下げざるを得ません。共産党案や社民党案では(適否はともかく)積み立ての取り崩しで給付水準を維持するという案がありましたが、民主党案にはそうした提案がないのが残念なところです。 もちろんこれは、公約に示されているのがまだ未完成に見えるというだけであり、現行制度を当面維持しようという案に比べれば、大きな改善であることは間違いありません。ただ、年金なら、、、というキャッチフレーズはいまのところ、「民主党なら確実に年金改革に手をつけます」というメッセージだと理解しておくのが良いようです。 ○雇用、労働 雇用については、共産党や社民党と同様、正規職員と非正規職員(パート、派遣、請負等)の均等待遇を目指した「パート労働法の改正」が、実質的な筆頭課題となっています。また、職業能力開発としては、失業給付期間が終わっても就職できない人や、自営業を廃業した人などを対象に、月額10万円の手当を最大2年間支給して能力開発訓練を支援することや、結婚や出産を契機に離職した女性が再就職・起業するための教育訓練制度の創設が提案されています。 一方で、雇用の拡大や創出については、目標としては示されていますが、具体的な方策は示されていないようです。まあ、他の分野で育成方針が示されている、特定非営利活動法人(NPO)や、生命科学、情報通信、ナノテク、環境エネルギーいった成長分野で新規雇用が生まれることを期待しているものと考えることもできます。○地方分権 地方分権に関する政策は、年金と並んで力が入っている領域の1つのようです。柱としては、現在地方に交付されている補助金20兆円のうち18兆円を、地方の裁量で利用できる財源として再配分することが提案されています。 18兆円のうち5.5兆円は税源移譲(国税から地方税への切り替え)によるものですが、残りは新たに設ける「一括交付金」によるものです。一括交付金は「教育」「社会保障」「農業・環境」「地域経済」などの大くくりで交付するもので、具体的な使い道についてはそれぞれの地方が自由に考えることができます。補助金をつけてもらうために、有力政治家の力を借りたり、中央省庁に陳情したりすることも不要になります。誰とは申しませんが、「利益誘導が政治家の仕事だ」などと大見得を切っていらっしゃる方々には大打撃になろうか、と。その意味でも非常に良い提案です。 ただ、一括交付金の算定方法について示されていないのは不満の残るところです。民主党は4年ほど前に、「公共事業一括交付金法案」を作成していたようですが、そこでは直近5年間の補助金総額から算定していました。もちろんそれはそれで1つの考え方なのですが、様々な理由でそれまでの補助金額が必ずしも適切でない場合もあるわけで、本当にそれで良いのかな、と思ってしまう部分もあるのは確かです。○地域産業振興 地域産業のうち農業については、他党とも類似した、農家への直接支払による所得保障制度が提案されています。財源も他党案と同様で、従来の補助金などの廃止です。その上で民主党案の特徴としては、米・麦・大豆・雑穀・菜種・飼料作物などの主要品目のみを対象としていることと、総額の半分(5,000億円)は地方が独自の基準で配分できるようにしたことを指摘できます。前者については、野菜やら畜産やらは入れなくて良いのかなあ、などと思ったりもしますが、後者については、棚田や有機農法など地域の事情に応じた支援を行える点で評価することができます。また、新規就農希望者に対する農地取得の下限面積条件の緩和も、担い手確保方策として評価できるかと思います。 一方、中小企業の振興については、やや質量的に乏しい印象を受けます。メニューとしては、「中小企業向け助成と商店街活性化のための予算を倍増」「エンジェル税制の拡充で起業を促進」「金融マニュアルの買い手により貸し渋り・貸しはがし解消」といった基本的な項目は揃っているのですが、中小企業の競争力を高めていくための独自の、具体的な政策としては十分に語られていないように思えます。もっとも、地方自治体の財源・権限が強化されることで、より地域に即した効果的な方策が実行されることが期待されているのかも知れませんが。 ○まとめ 全体として、年金や地方への税源移譲といった、国の骨格にあたる政策だけではなく、「著作物の公正使用(フェアユース)の確立」「インターネット選挙運動の解禁」「成人年齢の18歳への引き下げ」といったような細々とした政策もあり、よく目配りがきいていると感じます。定量的な表現も多く、各政党の中ではかなり明瞭なメッセージを出している部類に入るかと思います。 ただその一方で、重点政策の中でも、思いつきレベルとしかいえない政策が混在しているのも確かです。個人的には、「子ども家庭省」構想や「国際平和協力隊」構想あたりがその代表ではないかと思います。有事法制との関連がよく分からない「緊急事態基本法」、言葉だけが上滑りしている「介護保険のエイジフリー化」なんていう提案もそうかも知れません。 このうち、「子ども家庭省」は、現在文科省、厚労省、法務省、警察庁などに分かれている子ども関連の施策を一つの省庁にまとめて縦割り行政をなくそう、というアイディアなのですが、一つの省庁にまとめても縦割りがなくならないのは、総務省(自治省+郵政省)や厚生労働省(厚生省+労働省)という実例がある通りです。また、子ども関連がまとまる一方で、例えば医療関連などは分断されてしまうわけで、結局は別の縦割りが生まれるだけとも言えます。所管省庁が多くにまたがることを大前提にして方向付けをし、メリハリをつけるのが政治の役割だと思うのですが、一つの省にまとめてしまおうというのはある意味「霞ヶ関丸投げ」の発想ではないかとも思ってしまいます。 また、「国際平和協力隊」は、もともと小沢一郎氏のアイディアだったと記憶しています。ここ数年は民主党内でもろくな議論をされていないようで、サイト内で検索しても関連文書が見あたりませんが、小沢氏の案では、防衛庁のもとに、国連の指揮を受けて(武力行使を含む)PKFに参加するための常設組織を置くとされています。自衛隊との二重投資だとか隊員が集まるのかとかいう現実的な話はとりあえず置いておくとしても、国連の指揮に従って武力行使できる組織を作る、ということは、国民の統制がきかない「軍隊」を国内に作るということでもあり、非常に危険な面があります。在日米軍もそうだ、という意見もあるかも知れませんが、いずれにせよ、こういった微妙な部分がある案をろくな党内論議もせずに公約に載せてしまう脇の甘さはどんなものでしょう? さらに言えば、本来であれば党として立場を明確にすべき憲法や税制について、非常に曖昧な記述しかされていないのも、政権を目指す党としてはどんなものか、と思います。特に憲法については、「自らの『憲法提言』を国民に示すと同時に、その提言を基として、国民との対話を精力的に推し進めていきます」と書きつつ、どういった問題意識があるのかについては全く示していないという意味不明なものです。提言しなければいけない理由すら分かりません。護憲改憲どちらを打ち出すにせよ、マニフェストに掲げた改革を進める際に直面するであろう抵抗に比べれば、所詮党内なのですから、ずっと合意しやすい話だと思うんですけどね。
2005/09/05
コメント(0)
-
公明党~中堅政党の生きる道?
各党の政策/マニフェストを読んでみる企画、第5回は、与党の一角、公明党です。公明党は自党の公明党マニフェスト2005とは別に、自民党と「第44回衆議院総選挙 連立与党重点政策」を出しているのですが、ここでは基本的にマニフェストの内容、それも、重点政策には取り上げられなかった公明党独自の政策についてみていこうと思います。なお、公明党を含む各党の教育政策については、あーさんままさんのサイトで紹介されています。公明党の教育政策は大受けになっていましたので、どうぞご覧になってください。○財政再建 歳出削減策としては「事業仕分け作戦」を挙げ、2010年にプライマリーバランス(国債の発行や償還を除いた単年度の収支がトントンになること)を達成することを目標としています。「事業仕分け作戦」は、省庁の部・課ごとに民間の専門家や自治体の担当者を交えて議論し、業務を「不要あるいは民間で可能」「他の行政機関の仕事」などに分類させよう、というものです。 中央省庁の課室数は997(平成12年の省庁再編時点)らしいので、膨大な数の会議が動き、収拾がつくのかどうか心配ですが、検討参加者が積極的に考えてくれればある程度の成果があがるかも知れません。経費を削る話だけだと元気が落ちてくるものですが、削った額の70%を新規事業に使えるという配慮がされているのも評価できます。 ただ一方、省庁どうしが縄張り争いをしているような領域(たとえばIT政策での総務省と経済産業省)で、自分から予算を削ろうなんて言う話が本当に出てくるのかどうかは疑問も残りますし、内部で調整して横並びの削減率になってしまう可能性もあります。結局、ある程度の案は現場に出させるとしても、やはり政治のリーダーシップは必要になるのではないか、と思いますが、その点については「行政効率化対策本部」ぐらいしか記述がなく、「霞ヶ関丸投げ」になってしまう危険性もあるのは否定できないかな、と。○雇用 雇用については、新産業の育成や規制改革によって生み出すという方針が中心となっており、失業手当など失業者に対する直接的な支援策は特に提示されていないようです。 ただし、若年失業者に対する政策は少子化対策という意味合いもあって、比較的手厚くなっています。目立ったところでは、ある意味社民党の能力開発マイレージと似た発想なのではないかと思いますが、就業経歴を書き込める「キャリアパスポート」制度、社会が必要とする職業能力を身に付けた若者に国が「証明書」を発行する「YES―プログラム(若年者就職基礎能力支援事業)」が挙げられています。 また、パソコンなど活用して職業教育を受講できる「日本版ラーンダイレクト(草の根e―ラーニング)」なんてものも提案されています。「ラーンダイレクト」はもともとイギリスの制度ですが、彼の地では識字率向上や電子機器の使い方あたりから資格取得支援までメニューがあるとのことです。もっとも、経済産業省が数年前に研究会をしていたようで、独自の政策といえる段階ではなくなっているかも知れません。 なお、社民党や共産党が重視している、パート・派遣などの非正規労働者対策については、簡単にしか触れられていません。2003年にパートタイム労働指針が改定されているため、この浸透・定着を図れば十分であるという認識であると考えられます。が、指針を出しただけで守られるはずもなく、浸透のための具体的な方策があっても良いのではないか、と思ったりはします。○地域振興・まちづくり 中小企業対策は、社民党や共産党などとはかなり色合いが違っています。成長分野(環境、バイオ、情報通信、ナノテクなど)の企業や意欲が高い企業、あるいは起業を希望する女性を中心的な対象として 研究開発支援や創業支援を行うというもので、逆に、貸し渋り・貸しはがし対策に使えそうな政策は、「金融機能の多様化」ぐらいしかないようです。パラサイト企業は無視、というような基本線は理解できるのですが、現在の政策だけだと、支援対象がそうとう限られてしまい、必要以上の企業を切り捨ててしまうのではないか、という印象も受けます。 まちづくりの関連では、歩いて暮らせる範囲内に日常生活の諸機能を集約する「歩いて暮らせるまちづくり事業」が目を引きます。勝手に読み込むとすれば、地域コミュニティの再定義という部分もあり、脱クルマという意味で環境対策という部分もあり、あるいは子どもや高齢者を地域でケアすることにもつながるのではないかと思います。ちょっと私の妄想が入ってますが。ただ、個々の生活圏内を結びつける公共交通体系とあわせて検討した方が、地域間交流とかいう視点も入ってきて良いのかも知れません。○まとめ 個別のサービスや事業としてみれば、全体として充実したメニューになっているのではないかと思います。ただ、真面目にやったら非常にお金がかかりそうなものがとても多いのも事実です。所々思い出したように数値目標があるのですが、「全中学校区域に総合型地域スポーツクラブを設置」「小学校1年生から毎日英会話を、民間の英会話学校に委託して実施」など、どこまで本気なのか疑ってしまうものがあるのも確かです。 一方で、税制とか地方制度とか外交とか憲法とか、そういった国の枠組みに関する政策については、記述されていないか、あるいは非常に曖昧な、どうにでも解釈できるものが多いのも事実です。もっとも、そうした政策にはこだわらないで他の政党と協力関係を築き、自党の得意分野の政策を実現しやすくするという戦略もありうる訳で、単独政権を目指さない中小政党としては筋が通っているのかも知れません。 ただ、それなら余計に、政策の効果と負担の両方を個別に示しておくのが責任ではないか、とも思います。しかも連立与党としての政策で「サラリーマン増税はしない」と言い切ってるのだから、なおさらそうする責任は重いのではないかなあ、と。
2005/09/03
コメント(2)
-
日本共産党~甘い水と「たしかな野党」
各党の政策/マニフェストを読んでみる企画、第4回です。はじめにちょっと脱線。「選挙運動の期間中に立候補者の氏名や政党の名称を記載して、これらを推薦したり支持・反対を表明するような行為は公職選挙法に抵触する可能性がございます」などという話もあります。実際、国会答弁にもあるように「違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきもの」と、グレーゾーンです。この企画の中では特定政党に対する支持も反対もせず、良いところはほめるし、悪いところはけなして、あとは読んだ人に勝手に考えてもらう方針ですが(ほめようがない場合はあり得ます)、それでも違反だ、摘発するというなら相手はします。まあ、そう粋がって言うほど読んでる人多くないんだけどね(^^;)さて、本題。今回は「たしかな野党」を目指す日本共産党です。政権をねらえる数の候補者を出しておきながら、最初から野党を目指すというのはいったい何なんだ、という突っ込みは置いておくとして。共産党についても社民党と同様、「大増税反対」「開発優先から暮らし優先」「護憲」「イラク撤退」「米軍基地縮小」などの主張は耳に(目に)したことがある方も多いと思われます。ので、それ以外のところで特に特徴的な主張を中心に紹介しようと思います。それでもかなり長文です。すみません。○年金 年金については、他党がほぼ共通して掲げている「一元化」に反対していることが特徴といえます。理由としては、給付は低い方に、負担は高い方に統合される危険性があることを挙げています。 代案としては、すべての年金の土台となる「最低保障年金」制度を創設を提案しています。この制度の概要は、以下のようなものです。 ・最低年金額の上に、支払った掛け金に応じた額を上乗せして給付 ・支給額は当面月額5万円だが、安定的な財源を確保して引き上げ ・財源は、全額国庫負担(掛け金や目的税はつくらない) 現在の基礎年金と一見似ていますが、全額を国庫負担にしたため、これまでの掛け金支払い有無にかかわらず最低額が保障されることが大きな違いです。つまりは確信犯的に掛け金を払わなかった人でも年金を受け取れてしまう、ということでもありますが、特に対策は提案されていません。 なお、これまでの厚生年金や国民年金などは上乗せ分としてそのまま維持されるのですが、この財源は掛け金に加えて、年金積立金の取り崩しによってまかなうとされます。現在は5.2年分にあたる164兆円が積み立てられていますが、これが諸外国に比べて過大なので活用しよう、という考えです。社民党も同じようなことを言っていたような気がします。5.2年が多いのか少ないのかは私にはちょっと判断がつきません。○中小企業支援 中小企業支援策としては、金融機関によるいわゆる「貸しはがし・貸し渋り」対策が筆頭です。手段としては、国による信用保証の活用や、中小企業金融公庫などの公的金融の活用など、要するに中小企業に融資する際のリスクを国が肩代わりする構図です。また、大企業に対する下請け中小企業の地位向上のための方策も提案されています。これらの政策は、とりあえず当面の倒産防止には一通り有効ではないかと評価できます。 一方、中小企業にとっての需要創出策としては、社会民主党にも同様の政策がありましたが、住宅・福祉・防災・環境・交通安全など、暮らしに密着した公共事業の拡充を通じて、中小企業の仕事を確保することが挙げられています。具体的な事業分野としては、堤防改修防災対策、歩道や自転車道の整備、開かずの踏切の解消、福祉施設の増設、バリアフリー化などが挙げられています。これらの財源としては、公共事業補助金の、地方の自由裁量を強化することで実現するとされています。実際、車があんまり通らない高速道路や、一日何便しか飛ばなくて結局利用されない空港を造るよりも、歩道と車道をきちんと分けて交通事故を減らす、線路を地中化して空き地を有効利用するとかの方が税金の使い方として納得がいくのは確かでです。ただ心配があるとすれば、地方の自由裁量は増えるとしても、補助金の交付先についての裁量が中央官庁や政治家に残ってしまうことでしょうか。○農業政策 農業政策としては、主要農産物に対する価格保障・価格支持制度を中心に、食料自給率を50%まで上げることを主張し、輸入自由化策を強く批判しています。価格保障・支持のための財源としては、公共事業からの転換を挙げています。 価格保障制度については、最近まで数十年続けてきた価格支持政策(生産者米価、とか。)で結局農業は強くなったのか? とか、輸入自由化の前から弱かったのでは? という疑問もあり、それに答えていない不満はあるのですが、農業分野の予算でありながらなぜか土木・建設業界に流れてしまっていたお金が、本筋の農業支援に回るようになること自体は評価してよいかと思います。とはいえ、農業機械とか農薬とかが押し上げている農産物の生産コストをどう引き下げていくか、については、目立った政策がないようです。 また、農業のある意味根本問題ともいえる、担い手の確保方策については、あまり重点が置かれていないようです。株式会社の参入には反対していますが、一般の就農希望者を支援したり、就農しやすくしたり、といった策は皆無です。○地方自治 地方自治関連では、税源移譲以外、あまり建設的・具体的な施策はありません。地方交付税と国庫補助負担金の制度改悪や、市町村合併の押しつけ、道州制導入、自治体リストラの強要などへの反対が主な内容です。基本的に、中央からの押しつけに反対する、という筋書きになっているようです。まあ、うがった見方をすれば、自党の地方議員が減りそうなものには反対している面もあるのかも知れませんが。 自治体が行う住民サービスの民間企業移管(アウトソース)へも反対しているのですが、これがもっとも理解に苦しむところです。共産党ではこれを「財界への奉仕」と位置づけて反対しているのですが、実際には、地域住民の自主的な取り組みとして設立された会社(コミュニティビジネス)や、あるいはNPOに移管されるケースも多いのではないかと思われますし、また、政策にも保健・医療・福祉など担うNPOへの支援が挙げられています。こうした団体がサービスを担うのは、それこそ絵に描いたような「住民本位」だと思うのですが。○まとめ 共産党というと、政策的にはどうしても「リアリティがない人たち」という印象を持っている人が多いのではないかと思います。 でも、実際の政策には、農業の所得支持政策や、公共事業の内容の転換など、同じ省庁の枠内でちょっと発想を切り替えればできる「はずの」ものも多いような印象を受けました。とはいえ省庁は同じでも局単位の争いもあるわけで、、、業界にも政界にも利害関係者が多いので、、、、、実現しようとしたときの抵抗は、恐らく郵政民営化の比ではないでしょうけどね。 一方、全体として、いろいろな給付に重点が置かれていますが、お金をつけて終わり、という分野が目立つともいえます。失業対策は、職業能力育成より失業手当の充実に重点が置かれているように感じますし、中小企業についても積極的に競争力を高める策は手薄です。農業の担い手育成についても、少なくとも選挙向けには具体策は示されていません。 加えて、公務員を増やさないと回らないような規制の強化も多く挙げられています。給付の増加とあわせ、歳入の半分近く(2005年度予算で44.6%)を国債でまかなっている現状で、果たしてどうやって実現するのかは、どうしても無視できないところです。 もちろん、軍事費や大型公共事業の削減、大企業や高額所得者の「応分の負担」という一応の説明はあります。 しかし、よく知られているように、防衛費約5兆円のうち44%は人件・糧食費、37%は歳出化経費(要するに以前買った兵器のローン返済)なので、すぐに減らせるのは最大1兆円程度にとどまります。他でもない共産党が、自衛隊員の即時解雇を言うわけにはいかないでしょう。 公共事業関係費は、災害復旧を除いて約7.5億円(他に地方が負担する分もあるのですが)。大規模事業は中止しても「暮らし密着型」に回る部分もあるので、やはり全額を削れるわけではありません。でもまあ、半分弱ということで、3兆円カットぐらいは見積もっておきましょう。 法人税はどうでしょうか。2004年度の法人税収は約6兆円。税率を30%から50%に引き上げたとして単純に考えると、税収の増加は4兆円程度です。 また、高額所得者(とりあえず年収2,000万円以上)からの所得税収入は、税収約9兆円の13.4%にあたります。この層の税率を70%に引き上げたとして、やはり単純に考えると、税収が増えるのは2兆円程度。 合計すると、新しくできる財源は約10兆円。もちろん、少ない金額ではありません。また、もっと細々としたところを切っていけば、もうちょっとは上乗せできるだろうとも思います。なお、共産党自身では10兆円(国・地方あわせて)分のむだ遣いを削減することを公約としています。 この金額は、2005年度予算での国債発行額34兆円の3分の1にも満たない金額ですし、償還と利払に充てる18兆円にも及びません。「最低保障年金」には7.7兆円を見積もっているので当面は十分ですが、高齢化が進めばすぐに怪しくなります。国債発行を減らす前提で考えれば、新規事業に充てる財源は相当厳しいことになります。 つまり、共産党の言うとおり高額所得者や大企業への課税を強化し、軍事費や大規模公共事業を削る、それはそれで有意義だとしても、新しい政策を実現するにはかなり財源不足で、もっと高齢化が進めば本気で別の財源が必要、ということは否定できないのではないかな、と。これについても高額所得者や大企業にかかってくるのだと思いますが、果たしてどこまでの負担に耐えられるのか。 本当に「庶民」や中小企業の税負担を増やさないで済むのか。疑問が残るところではあります。 もちろん、最初から野党を目指しているということなので、そこまで考える必要はないのかも知れません。が、自分だけ安全地帯にいておきながら、自民党・民主党の増税志向を批判するのは、ちょっとフェアじゃあないのではないでしょうか。無駄遣いを減らすのは当然なのですが、政策を実現するために新たな負担が発生する可能性があるなら、そのことを誠実に示した上で競うのが、本当に「たしかな野党」なのではないかな、と思ったりします。良い政策もあるんですから。 なお、共産党の「「最低保障年金制度」を実現し、いまも将来も安心できる年金制度をつくる」の中では、日本の国民所得に占める企業の税負担・社会保険負担の比率が12.3%と、ヨーロッパ諸国(イギリスでも16%、フランスは23.6%)に比べて低いとして、まだ企業に負担余地があると主張しています。でも、ヨーロッパは国民負担率(国民所得に占める税負担と社会保障負担の割合)そのものが日本に比べて高いので、先の数字だけを根拠にして、企業が楽をしていると主張するのは、数字の使い方として失当かと思います。P.S.ようやくこれで、過半数を超えました、、、、、あと3つ。がんばります。
2005/09/02
コメント(6)
-
社会民主党~「"五"十年一日」と新しいアイディアと
各党の政策/マニフェストを読んでみる企画、第3回は社会民主党(社民党)です。 社民党は、「社民党総選挙政策2005」「社民党総合政策ガイド2005」なる文書を公表しています。「社民党総合政策ガイド2005」は全部で82ページ。けっこうがんばっています。でも、これを何回かに分けて全部紹介しようとすると、最後の自民党までたどり着きませんので、さわりだけ紹介しようかと思います。○基本方針 「社民党総選挙政策2005」では、小泉政権が進めてきた政策を、「大企業のための、強い者のための、アメリカのための、弱肉強食の「競争社会」を目指す」ものと批判した上で、「平和憲法の理念を大切にした、誰もが安心して暮らせる「共生社会」」を、目指すべき社会像として提示しています。 誰もが安心して暮らせる「共生社会」の核として、「政策ガイド」でも大きな紙幅が咲かれているのが、年金(社会保障)と雇用、地域再生です。ここではこの3つを中心に紹介したいと思います。他には、「護憲」「消費税率据え置き」など、耳慣れた主張もありますが、これはここで紹介するまでもなく、ご存じの方が多いでしょうから、省略します。○年金 社民党が提案する年金制度のおおざっぱな内容は、以下の通りです。 ・月8万円の「基礎的暮らし年金」と「所得比例年金」で構成する ・「基礎的暮らし年金」の財源は、防衛費や公共事業などの歳出削減と、 所得税の累進の強化、および法人税の課税強化などによってまかなう ・所得比例年金は、職域(自営、会社員、公務員)にかかわらず共通料率とする。 ただし、企業が賃金総額に応じて負担する保険料率は、大企業と中小企業で差をつける 一元化への方向性は、民主党などと共通するものですが、一元化までの期間(5年間)や移行措置を(不十分ではあるものの)明示している点は、評価してよいかと思います。ただ、財源の確保方策については、そもそもそれでまかなえるのか、という話は別としても、いかにもお約束通りの発想という感じがするのは否めません。○雇用・労働政策 さすがに元々が労働者の党だけあって、雇用・労働政策には力が入っており、かなり細かいトピックまで書き込まれています。 解雇制限ルールの厳格化や、労働基準監督の強化といった、ある意味伝統的な政策はもちろんあります。が、雇用のセーフティーネットとして、失業手当よりも職業能力の開発支援が中心に位置づけられているのは、正直少々意外ではありましたが、評価できることではないかと思います。また、研修・教育訓練などの成果をポイント化し、企業を移動しても客観的なスキルを示すことが可能になる「能力開発マイレージ制度」は、実際の制度化は簡単なものではないとしても、ユニークなアイディアかと思います。 ただ、男女雇用機会の実質的な均等化をはじめとして、女性の労働に対する施策も充実しており、それは良いのですが、女性の社会進出の障害ともいわれ、以前は田嶋陽子氏(当時は社民党の参議院議員)も国会質問で廃止を要求していた配偶者控除や配偶者特別控除にについては全く触れていません。おそらくは「大増税」と批判している政府税調の案を、たとえ一部であっても肯定したくないということなのでしょうが、これはちょっと姑息なやり方ではないのかなあ、と。○地域振興 地域振興に関しては、金融機関に対して、中低所得者や女性、中小・ベンチャー企業に対する一定割合の融資を義務づける「地域再投資法」の制定・活用を中核に据えています。この法律を活用して、地域に「職・食・住・遊・学」といった場所をつくり、そこに関わる人材を育成し、雇用につなげていくというシナリオが想定されているようです。金融機関にそんなことを義務づけて採算が合うのか、という話もありますが、先に導入したアメリカでは地域コミュニティと共生するビジネスモデルを確立し、一定の収益をあげているとのことです。 地域の住民が中心となって地域のニーズを充足する「コミュニティビジネス」の育成を通じて雇用を創出するという発想は、どの程度の成果が期待できるかは未知数であるにせよ、企業誘致や国の補助金に頼らない地域振興の方向性として、心意気は評価できるのではないか、と考えます。○まとめ さすがに歴史のある党だけあって、エキスパートもいらっしゃるのでしょう。雇用や地域振興については、意外に新鮮な(と少なくとも私は感じる)提案もあります。ただその一方で、「"五"十年一日」とでも言いたくなるような発想も根強いようです。福島党首の最近の演説からは、「金持ち」や「大企業」に対する敵意をあおって庶民の味方を印象づけようとする意図を強く感じてしまいますが、これこそ「"五"十年一日」の代表か思います。 「社民党総選挙政策2005」では、資産と所得の格差拡大を問題にしており、おそらくはそれを反映して、所得税の累進強化が提示されています。でも個人的には、世代の中での、ある意味一時的な格差が広がることよりも、現在すでに存在してしまっている格差が次の世代にも受け継がれ、格差が固定化してしまうことの方がよっぽど問題なのではないかと思っています。しかし、社会民主党の政策にはそうした問題意識は感じられませんし、実際、固定化を防ぐために効果的と考えられる施策も、奨学金・育英制度の拡充や、何を意味しているかあいまいな「『社会的引き継ぎ』が可能な資産課税の適正化」ぐらいしかありません。 そもそも、フェアに働いて「金持ち」になった人、人々の役に立ちながら「大企業」になった会社を敵視する社会が、果たして「一人一人が輝くやさしい社会」といえるのかどうか? 庶民対金持ち、中小企業対大企業などというわかりやすい図式に単純化して、後者が前者から搾取している、という扇動をするのは、もうそろそろ終わりにしても良いような気がします(これは社会民主党だけではなく、国民新党にも、おそらくは共産党にもいえることです)。庶民がフェアな手段で金持ちになれること、中小企業がフェアな手段で大企業になれること。もちろんそれが全てだとは思いませんが、金持ちや大企業を目指す機会が誰にも開かれていて、成功したら素直に祝福できる社会が本当の「共生社会」だと思うのですが、大甘ですかね?
2005/08/31
コメント(1)
-
やっぱりばらまき?それとも~国民新党
くまさんのブログで「マニフェストを読む(憲法編)」を書かれているので、読みにいってみました。自分のと違って勉強になるなあ、と。こちらも多少気合いを入れ直して、精進したいと思います。 今回は、「新党」ラッシュのさきがけ(そういえば昔そんな党もあった、、、)、国民新党です。 国民新党のホームページ は、chilimeさんのブログで衝撃の4コマ漫画が紹介されているのでもう見られた方もいらっしゃると思いますが、まあ、政策云々よりも随所に「小泉憎し」が徹底していて、政党というよりどこぞの電波系サイトを見ているような気分になるのが正直なところです、、、、、が、それでも気を取り直して、基本政策・方針やら公約やら、何人かの所属議員の方のホームページからその内容を紹介してみることにします。 さて、国民新党の「公約」は11項目ありますが、大きくまとめると、「経済政策」「防災」「外交」「教育」に関心があるようです。意外なことに郵政民営化については公約にはなく、基本方針で「わが党は利用者の声を聞き、利用者の「郵政改善」を実現します」と謳っているのみです。 民営化に反対している理由は新党日本と似たようなものなので、省略しますが、一言だけ言っておくと、民間企業の活動を非常に平板に見ているのが気になります。不採算部門を切り捨てるのも民間企業ですが、不採算部門から利益が出るような仕組みをつくるために知恵を絞るのもやはり民間企業なのですけどね。このあたりは今勉強中なのですが、特定局から簡易局に切り替えれば存続できる郵便局も多いのではないのかなあ、と思うのですが、甘いでしょうか?○経済政策 経済政策としては、「弱者を切り捨てる名ばかりの改革でなく、年金・福祉政策を確立し、すべての国民を幸せにする真の改革を行います。」「経済合理性のみに基づいた弱肉強食の競争原理主義を排除し、勝ち組み・負け組みをつくらず、すべての国民の生活の安心と安全を守る経済政策を展開します。」とあります。 亀井久興氏は、政治レポート「どういう社会を目指すのか」で、「小さな政府」やアメリカ型資本主義社会に対する違和感を吐露しており、郵政だけが新党の理由ではないと述べています。これが、失敗してもやり直しができる社会を目指しているのか、それとも失敗する前に丸抱えで面倒を見る(そして抜け駆けは許さない)社会を目指しているのかは分かりません。ただ、思いっきり好意的に見れば、いわゆるヨーロッパ型の資本主義をモデルとして、自民党とも民主党とも異なる存在価値を出せる可能性もないではない、といってあげても良いかも知れません。 ただ、「弱者」というのは難しい概念で、機会も能力もある(あった)はずなのに税金にパラサイトしている自称「弱者」の面倒はどこまで見たもんなのかなあ、本当にそこまで面倒見る気があるのかなあ、というのも正直なところです。その意味では、弱者を切り捨てないというのは単なるスローガンにすぎないかも知れません。 なお、新党日本とは兄弟党などと言っているようですが、その割に、新党日本の代表が最重視しているとみられる財政赤字の問題については、基本政策・方針にも公約にもほとんど触れられていません。逆に、財政赤字ごときを気にしてどうする、とでもいうような、一種の開き直り(?)すら見受けられます。 まず、実質的な看板ともいえる亀井静香氏。自身のホームページでは、「民間に元気がない時には政府が思い切った財政出動をする。真水で10兆円、事業規模で50兆円、国債を発行し内需を拡大する。」と言い切っています。使い道としては「生活を豊かで便利なものにし、環境を守る公共事業」として、拠点空港とか高規格道路(要するに高速道路です)の整備とか電車の地下化とか電線の地中化とかを例示しています。他には、「農漁村の水洗トイレの普及」とか「高速道路の無料化」なんてものも挙げています。 で、返すあてですが、「当面借金は増えるが、それによって景気が良くなり、国民所得も上がり、税収が増える」と。現在の所得税率・法人税率を前提にして、税収を60兆円分増やすには、どのぐらい国民所得を上げたらよいのか非常に気になるところです。ちなみに日本の国民所得は、2003年で510兆円でした。 また、結党後に副代表に就任したエコノミストの紺谷典子(こんやふみこ)さんは、ちょっと古い話ですが、2002年に日本医師会での講演で、さらに踏み込んだ主張を述べています。曰く、・財務省が言うほどの財政危機はなく、借金を財政赤字と国民に思い込ませている。・政府が財政出動で歯止めをかけなければデフレ・スパイラルは止まらない。 無駄でない必要な公共事業をやればよい。・社会資本整備を税金でなく借金で行うと、5.5%の財投金利で3年間で倍になる。 公的資金のほうが結果的に国民のコストは非常に少なくて済む。 財政危機とはいえない根拠としては、国債残高に見合った資産や、「巨大な黒字がある」社会保障勘定の存在を挙げています。そのあたりについては機会があったら検証してみたいとは思いますが、定義上、建設国債ならともかく、赤字国債に見合う資産っていうのはやっぱりないと思うんですよね。国債を返すためのお金が毎年の予算の結構な割合を占めているのも事実ではありますし。 ○防災政策 防災については、「かけがえのない自然環境を守り、治山・治水を怠らず、災害の防止に努めます」とあり、都市型災害に対する防災対策には、あまり興味がないようです。 「約束」では、「学校や公共施設の耐震化事業を強力に推進」とあります。それはそれとして重要なのですが、建物が崩れなければそれで十分、という訳なのですかね? ○教育政策 教育については、「資源の少ない日本の未来を拓くため、教育を重視します」「知識のみならず心の教育にも力を入れます」とあります。具体論までは展開されていませんが、例えば亀井静香氏のホームページでは、・教育基本法を改正し、知識の詰め込みが主体の教育を改める・日本人が本来備えていた誇りや魂を蘇らせる人間教育に重点 ・公立校の全寮制教育を導入する・6・3・3制から6・6制への移行といった提案が出されています。「日本人の自国の歴史に対しての誇りと自信を失った結果、精神的荒廃が進」んだという問題意識のようなので、一番やりたいのは「人間教育」とやらなのでしょう。また、教育基本法と詰め込み教育にどのような関係があるのかは不明ですが、一定水準の知識が詰め込まれてさえいないのも、それはそれで問題なのかなあ、と、個人的には思います。○外交・防衛政策 外交・防衛政策については、「友好関係の構築に勝る安全保障はないとの観点に立ち、自主独立の外交を展開します。」「自分の国は自分で守るとの気概を持ち、平和を守り戦争に反対します。」とあります。 「約束」では、拉致問題の早期解決を、自立した外交・防衛の具体的な内容として想定しているようです。 参考までに、亀井静香氏のホームページでは、米国頼りの安全保障を批判した上で、ミサイル防衛システムの全国配備を提案したり、「相手に言うべきことを言わない、譲歩するだけの妥協外交」を批判し、「国益を思い切って主張する」ことを提案しています。そういう2元論で外交ができたら楽ですよね、きっと。ちなみに首相・公職者の靖国参拝が、「国益を思い切って主張する」ことにあたるのかどうかについては、興味深いところではあるのですが、何も触れていません。
2005/08/29
コメント(4)
-
代表はしゃげど所属議員は?~新党日本(2)
新党日本の2回目です。今日は、所属議員の考えや政策について見てみます。ただし、代表代行の小林興起氏のホームページがここ数日つながらないので、その分は含んでいません。まず、新党日本の最大の共通項である郵政民営化について。言うまでもなく、新党日本に所属している方は皆先の郵政民営化法案に反対しているのですが、反対した理由を最大公約数としてまとめると、・郵便局の数が減ったり値上げされたりして、国民に不利益になる恐れがある・米国資本に狙われやすくなる。外国銀行になると預金保険がきかないので国民の資産を守れない・諸外国で民営化して失敗している・現在は黒字であって急いで民営化する必要はない。また、急を要する課題が他にあるあたりでしょうか。それぞれの意見の当否についてはあらためて考えたいと思うのですが、少なくとも郵政民営化に対する考えとしては、所属議員の考えは一致しているようです。ただし、田中代表のホームページに、郵政に関する意見が一切載っていないのが気にかかるところです。他の課題についてはどうでしょう。例えば民主党が最大の課題と位置づけているのは年金ですが、年金について一応の主張を述べているのは副代表の滝実(まこと)氏です。昨年度に行った年金制度改定については「一連の年金改革が具体化」したことで将来の年金への不安を解消する道筋がつけられた」と評価しています。まあ、与党にいたのだから当たり前のことですかね。あとは、同じく副代表の青山丘(たかし)氏は、郵政より国民が望んでいる年金制度の確立に取り組むべき、と述べています。さらに幹事長の荒井弘幸氏は、「税金・年金のムダやめる!」を宣言していますが、今のところ中身には踏み込んでいません。全体的にいえば、問題意識はあるものの、昨年の制度改正で一息ついている状況の方が多いのではないか、と思います。一方、田中代表が一番強い問題意識を持っているのは、この数日中に掲載されたメッセージを見る限り財政再建のようですが、これについてはどうでしょう。各人のホームページをざっとみたところ、これに該当するのは先に挙げた荒井弘幸氏の「税金・年金のムダやめる!」ぐらいしか見あたりませんでした。敢えて書かずとも当然のことだと認識していらっしゃるとは信じたいのですが、ことによると現在の自民党における郵政民営化のように、代表だけは関心を持っているけど所属議員は関心がない政策になってしまう懸念もないではありません。こうして見てくると、「寄り合い所帯」だとは言われますが、ある意味所属議員どうしの共通点は多いのかも知れず、むしろ、代表と所属議員の間に一番溝があるのが気になるところです。田中代表が議員にならない以上、代表の言っていることを責任を持って実行してくれる人がいない可能性もあるわけで、候補者個人の主張に惹かれて選挙区で、というならともかく、比例代表でこの党に投票するのは、ちょっとリスキーかなー、とも思います。次回は国民新党、の予定。結構疲れるね、このテーマ。
2005/08/28
コメント(1)
-
政策はなくても壁紙ダウンロード~新党日本
開設1週間ですでに軌道から外れかかっていますが、いろんなモノを自分でお試ししてご紹介、というのがこのブログの基本スタンスでした。でも早くもネタ切れ。。。。?そこで、選挙も近いので、各党のマニフェストなるものを一通り読んで、自分の勉強がてら紹介してみようかと。各党の政策については新聞でもある程度紹介しているのですが、何かしら新聞では採り上げない、面白いことを紹介できればいいなあ、と思います。とりあえずは、二大政党中心の新聞やテレビの逆をいって、小さいところ=議員数が少ないところから紹介してみましょう。さて、1回目は、一番新しい「新党日本」、にしようかと思ったら。サイトを見ると、党首の手による檄文のようなものはあるんだけど、公約とか政策の類ってどこにも書いていない。一応「このサイトは準備中です」ということなので、また何日かしたら覗いてみることにしましょう。でも。公示後はホームページの更新できなくなるので、ロゴの説明とかポスターのダウンロードとか壁紙のダウンロードとか待ち受け画面のダウンロードとかのメニューを作って盛り上がっている暇があったら、早く選挙公約を出した方が良いと思うけど? それとも、無党派層の取り込みには政策よりもその方が、という判断なのかな?(ちなみに、リンク先のロゴの綴り、間違ってんぞ。)ちなみに、新党日本のページからは、「チーム・ニッポン」なるサイトにリンクされています。新党日本とチーム・ニッポンとの関係はどこにも説明がないのですが、田中康夫代表が2004年ぐらいから呼びかけている「新政策機構」のようで。会員区分に「SPA会員」なんてものがあるところからすると、例の雑誌の連載から始まった企画かも知れない。誰か知っている人いますか?「チーム・ニッポン」の設立趣旨にはこうあります。日本の崩壊がもたらす現況は、政・官・業がつくる既得利権のもたれ合い構造です。「チーム ニッポン」は、この悪のトライアングルを破壊します。古い土台に根を生やした人や組織には一斉退場を願い、「真の改革の獅子たち」によって「日本」を甦らす国民参加型の新政策機構です。個人的にはこれはこれで、至極まっとうな考えだと思いますし、田中康夫氏が長野県知事として行ってきたことと通じる部分もあります。その上で、今回集まった方々が果たして「真の改革の獅子」なのか、次回は立候補者のページを覗いてみることにします。
2005/08/26
コメント(0)
-
台風以外は平穏な日
昼食は、出先の職員食堂でした。ゴムのように歯ごたえがある豚肉と、とっても刺激的なタマネギでできた肉じゃがの定食。肉じゃがをがんばって食べたのは初めてだな。貴重な経験。それにしても、最近の台風は来る来るといってなかなか来ないねえ。午前中あたりは雨が激しかったりもしたけど、蝉が鳴いている時間帯もあって、あんまり傘を使わず歩けたり。でも自宅あたりでは、22時過ぎからちょっと風の音が強くなってはきて、23時過ぎからBS/CSの映りが相当悪くなってきました。仕方ないので今日は早めに。
2005/08/25
コメント(0)
-
うなぎのじゅもん
おさかな天国とかしゃぶしゃぶレンジャーの歌とか焼き肉マンボとか、食べ物のイメージソングのようなものがたくさんありますが。どうやらそれの、浜名湖名産「うなぎパイ」版のようです。どうやら某友人のツボにはまってしまったようで、強くプッシュされてしまいました。歌っているのは小椋佳&アルザ。アルザというのは愛知周辺では有名な中学生姉妹のタレントのようです。東海地区ではCMを流しまくっているので結構有名らしく、検索するといろんなところで紹介されています。小椋佳さんの曲というだけあって、基本線は真面目。しゃぶしゃぶや焼き肉とは明らかに一線を画しているような。「うさぎのうなじ/うわぎのうらじ/うなぎのうまみ/うなぎの元気勇気本気」なんていう、落ち着いた言葉遊びが大人の雰囲気ってところでしょうかね。公式サイトでは、振り付けビデオも見れます。ラジオ体操の代わりに、とかいって気合いが入ってますが、踊れるようになるにはちょっと鍛錬がいりそうだぞ。試聴して買いたくなった人は、ここからどうぞ。
2005/08/24
コメント(0)
-

分煙社会を目指す会「空気のおいしい禁煙レストラン&カフェガイド」
こんな本があるんですね。「首都圏のお薦め飲食店のなかでも、完全禁煙、あるいはきちんと分煙されている店」を約230店紹介した本です。お店の名前と所在地、電話番号、営業時間の他、席数や予算まで紹介してあります。首都圏とは言っても東京都内、さらにいえば山手線内あるいはその西側が中心ではありますが、まあ、お薦め飲食店というものが多くあるのがそういった地域だと思うので。名前ぐらいは聞いたことがある有名店もけっこう入っているので、相方の身動きがとれるようになったら行ってみたいかな。こちらから購入できます。1,470円(税込み)。
2005/08/23
コメント(0)
-
あじさい茶屋「冷やっこうどん」
仕事の日。中央線での移動中に、中野駅ホームのあじさい茶屋で「冷やっこうどん」なるものを発見。昼時だったので、早速食べてみました。値段は480円。名前に違わず、冷やしかけうどんの上に、豆腐が一丁まるごとのっているというもの。揚げ玉、ねぎ、わかめという基本トッピング(っていうのかな?)に加えて、豆腐向けトッピングとして削り節と海苔が。冷や奴ということで醤油とおろし生姜も一緒に出てきましたが、うどんの出汁があるので醤油はかけなくても良いような。味は、豆腐好きの私としては、まあいいかな、と。なお、あじさい茶屋の分煙状況ですが。さすがに立ち食いそばで煙草吸う人もいないだろう、ということで、ノーチェックです。
2005/08/22
コメント(0)
-
今日は一日家に。
梅がようやく干しあがりました。漬けるのは今年で2回目ですが、去年に比べるとけっこう自信作かな、と。早く食べたいところですが、食べ頃はまだ先だということなので。
2005/08/21
コメント(0)
-
草五庵「胡麻辛味肉つけ汁饂飩」
今日行ったのは、亀戸の駅ビルの6階にある「草五庵」です。某分譲マンションの眺望観望会なるものを見に行った帰りに立ち寄りました。食べたのは、「胡麻辛味肉つけ汁饂飩」。大盛りで値段は880円。担々麺風のつけ汁にうどんをつけていただきます。つけ汁、うどんそれぞれ、温かい/冷たいを選べるのですが、なぜか血迷って両方「温かい」にしました。つけ汁には豚肉。薬味としてはネギとショウガ。大汗かきますが、暑い日にはいいかもなあ、と。全体の席数は40ぐらい。料理と一緒に配られたアンケートによれば禁煙席もあるらしいのですが、入ったときには気づきませんでした。入って右側あたりがそうだったのかな? だとすれば10席ぐらいでしょう。禁煙席とは離れているので、煙はあまり気にならないのではないかと期待。機会があったらまた行ってみます。
2005/08/20
コメント(0)
-
口上
特にどうして、という理由もきっかけもなく始めてしまったのですが、基本的に、日頃であった珍しいもの、面白いもの、変なものを、興味に従って紹介していこうと思っています。興味の方向からすると、特に、ジャンクフードやデジタルもの、トマトものあたりに注力していくことになろうかと思いますが、さあ、どうなることか。あと、もともとタバコの煙が苦手なこと、相方の出産が近いこともあって、外食やお茶をするときには、できるだけ禁煙席があるところを選ぶようにしています。ただ、禁煙席にもいろいろあって、、、、、禁煙喫煙のどちらかが別室になっていたり、して完全に分煙されている禁煙席もあれば、喫煙席の一角にあって煙がノーガードで流れてくる禁煙席もあります。でも、なかなかそこまで書いてあるサイトや本は少ないですよね?そんなわけで、お店について書くときには、料理だけではなくて禁煙席の状況についても書いておくようにしたいと思います。ま、のっけから何日分もまとめて投稿していたりする人ですので。気が向いたときに見に来ていただければうれしいです。よろしくお願いします。
2005/08/19
コメント(0)
全35件 (35件中 1-35件目)
1