御香宮神社(厄払い)

神功皇后(日本第一安産守護神)を主祭神として仲哀天皇応神天皇他六柱の神を祭っている御香宮神社は最初、『御諸神社』と称していましたが、平安時代貞観四年(八六二)九月九日、この境内から「香」の良い水が涌き出たので、清和天皇より『御香宮』の名を賜りました。
表門(伏見城大手門)

豊臣秀吉は願文と太刀(重要文化財)を献じてその成功を祈り、伏見桃山城築城の際は城内に鬼門除けの神として勧請し社領三百石を献じました。その後徳川家康も元の地に本殿を造営し社領三百石を献じました。鳥羽伏見の戦の際は官軍(薩摩藩)の屯所となリましたが幸いにして戦火は免れました。十月の神幸祭は、伏見九郷の総鎮守の祭礼とされ、古来『伏見祭』と称せられ今も洛南随一の大祭として有名です。
参道

寛永二年(一六二五)、徳川頼宣(紀州徳川家初代)から寄進されました。桁行七間(けたゆき七げん)、梁行三間(りょうゆき三げん)、入母屋造(いりもやづくり)、本瓦葺の割拝殿(わりはいでん)。正面軒唐破風(のきからはふ)は、手の込んだ彫刻によって埋められています。特に五三桐の蟇股や大瓶束(たいへいづか)によって左右区切られている彫刻は、向かって右は『鯉の瀧のぼり』、すなわち龍神伝説の光景を彫刻し、左はこれに応ずる如く、琴高仙人(きんこうせんにん)が鯉に跨って瀧の中ほどまで昇っている光景を写しています。この拝殿は伏見城御車寄(くるまよせ)の拝領と一部誤り伝えられる程の豪壮華麗な建物です。
拝殿

御香宮の名の由来となった清泉で「石井の御香水」として、伏見の七名水の一つで、徳川頼宣、頼房、義直の各公は、この水を産湯として使われました。絵馬堂には御香水の霊験説話を画題にした『社頭申曳之図』が懸っています。明治以降、涸れていたのを昭和五十七年復元、昭和六十年一月、環境庁より京の名水の代表として『名水百選』に認定されました。
御香水

「御香水」に代表される伏見の名水によって、日本でも有数の酒どころとして全国に名をとどろかせています。
伏見には日本を代表するような蔵元が多数存在します。
伏見には日本を代表するような蔵元が多数存在します。
伏見の銘酒
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- ブラックフライデー2h全品 半額〜…
- (2025-11-19 18:48:00)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-
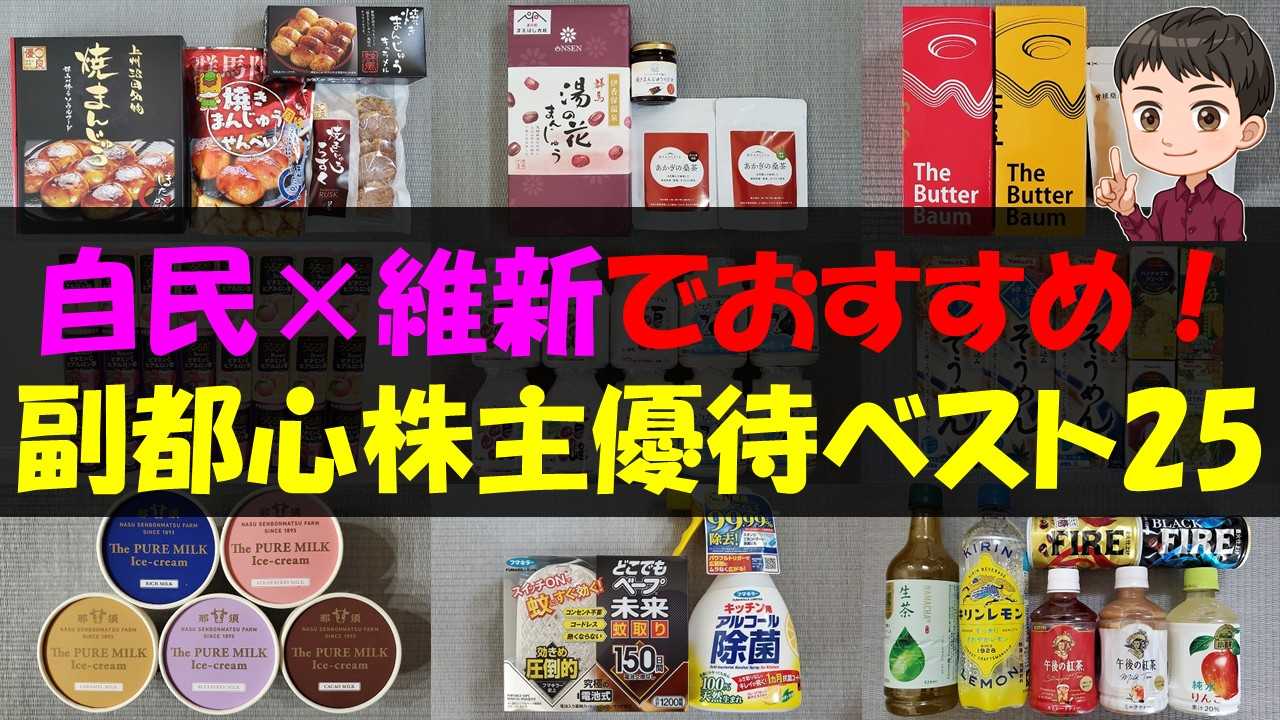
- 株主優待コレクション
- 【大阪】自民×維新でおすすめ!副都…
- (2025-11-19 18:00:06)
-
© Rakuten Group, Inc.



