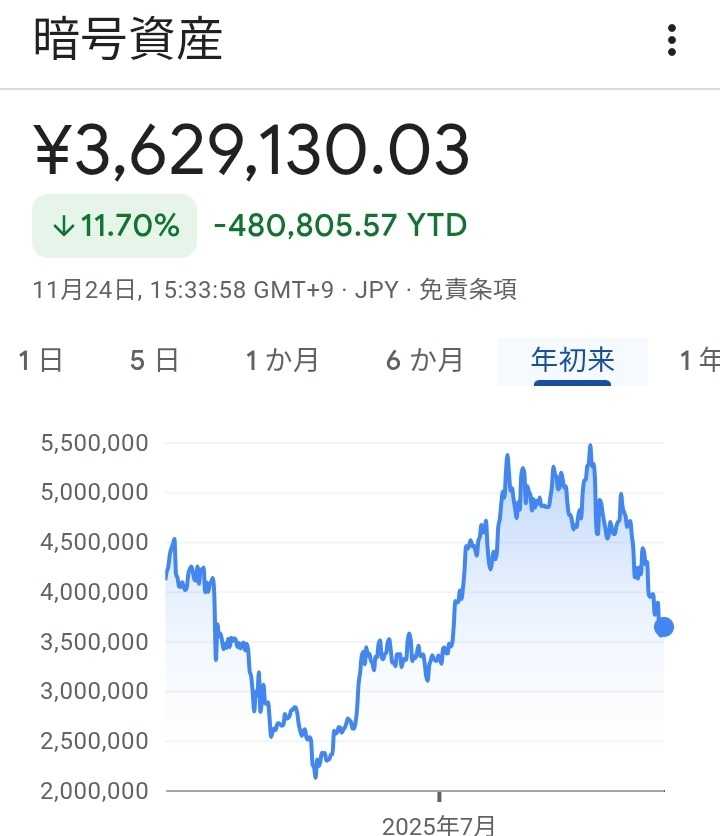多元的幸福
風のない静かな冬の日。
空には雲がほとんど無く、快晴に近い。
ベランダに出ると、排気ガス混じりの都会の空気も、妙に新鮮で、おいしく感じる。
そう言えば、このところ、週末以外はずっと部屋に閉じこもって隠者のような生活をしていた。
無意識に外出のきっかけを探していると、ちょうど住民票が必要だったことに気づき、昼食の
ついでに区役所まで30分程度、散歩することにした。
途中、行きつけの定食屋に寄る。
ランチ定食を注文。
この定食屋のメニューは、いくつかの小品を少しずつ組み合わせているところがいい。
必要な栄養素がバランスよく取れて、しかも非常においしい。
それに、自分にとっては腹六分の量になっているのが、ありがたい。
料理を待つ間、浅田次郎の「三人の悪党」を読む。
彼の作品は、笑う場面でも、泣かされる場面でも、戦慄を感じる場面でも、深く感動させられる
場面でも、読む者の心の琴線を弾くバランス感覚が、天才的に巧みだ。
ふと目を上げると、テレビで司馬遼太郎の生涯を紹介していた。
今日が、彼の命日だそうだ。
「竜馬がゆく」「坂の上の雲」「項羽と劉邦」「燃えよ剣」、、、、
僕という人間が、司馬遼太郎の小説から人生的に得たものは、計り知れない。
自分の人間観・世界観のあらゆる場面に、彼の小説に登場する人物の生き方が反映されていると思う。
ところで、あれだけ大量のすばらしい長編小説を生み出しているのだから、文章を書く時には
次から次へと的確で鋭い言葉が自然に溢れ出てくる人なのだろう、と、思っていた。
ところが、その生原稿の映像を見て、驚いた。
何度も、何度も、何度も、校正を繰り返したらしい原稿用紙は、赤と黒と緑の線や括弧や細かい字で
グチャグチャに埋め尽くされていたのだ。
司馬遼太郎ほどの文章の達人でも、1枚の原稿用紙のために、あんなにも何度も手間をかけて文章を
練り直していたという事実に、すっかり感動してしまった。
いや、逆に、手間と時間をかけて苦しみながら生み出した文章だからこそ、あれだけの名作として
完成できたのだろう。
何か書こうとするときはいつも超遅筆で、何度も文章校正をしなければ気が済まない自分自身の
文才の乏しさを今までは恥じていたが、、、、、そんなふうに、恥じていた自分こそ、今は恥ずかしい。
定食屋を出て、区役所までの散歩を楽しむ。
春のように暖かな陽気も手伝って、交通の激しい通りの歩道を歩きながらも、心の中がすっかり
洗われていくような気分になった。
帰りに、レンタルビデオ店で、「マトリックス・リローデッド」と「バッファロー ’66」を借りる。
財布の中に「レンタル1本無料券」があったのを思い出して、使おうとすると、
「これは、 当店のものではない ようですが・・・・」
と、言われた。
それも、そのはず。
よく確かめると、僕が差し出したのは クリーニング店の 20%割引券だった。
ちらと視線を上げると、店員が笑いをこらえている。
「あ、そのようですね」と、冷静に割引券を財布に戻して、通常の料金を払い、逃げるように
店を出たのだった。
気を取り直して、セブン・イレブンに立ち寄り、「週刊少年マガジン」を購入した。
落合信彦が「狼たちへの伝言」の中で、電車の中で漫画を読んでニヤニヤしている大人は
平和ボケした豚だ。狼として生きたいなら、漫画を読んでる暇があれば新聞や情報誌を読め、
というような趣旨のことを書いていたのを思い出した。
かつて、「小説など、人を堕落させるだけのもの」と言われていた時代があったように、現在は
「漫画を読むとバカになる」などとも言われるが、いやいや、漫画の中にも、すぐれた芸術作品
以上の感動を与えてくれるものがある。
人生を楽しむために、文化が高級である必要は必ずしもないと思う。
サブ・カルチャやB級グルメの醍醐味は、自ら味わってみないと決してわからないものだ。
無意識の深層が豊かになる。
心の地下風景が広がる。
上品に気取った文芸作品や、高価な食材を使ったアラカルトでなくても、十分に心は潤うものだ。
ただ、落合氏のエッセイを読んで以来、電車の中では学術書や文芸書や「TIME」などを読むことにした。
電車で「週刊少年マガジン」を読んで、家で「TIME」を読んでも、その逆でも、得られる情報量は
変わらないのだが、、、、、まあ、外ではそれなりにオシャレをしようかな、と。(爆)
“最も賢い処世術は、社会的因襲を軽蔑しながら、
しかも社会的因襲と矛盾せぬ生活をすることである。”
―― 芥川龍之介
家に戻り、例によって鉄アレイを振り回し、サンドバッグを殴り蹴り、腹筋を鍛え、拳立てをした。
基礎代謝量が十分に上がったところで、コーヒーを淹れる。
ブルーマウンテンを思いっきりアメリカンにして、乾いた喉を潤す。
至福の瞬間。
“「感じる人」にとっては、この世界は悲劇である。
「考える人」にとっては、この世界は喜劇である。”
―― ホレス・ウォルポール
幸福の“実感”を求めて、日々、汲々としている人にとって、人生は悲劇以外の何物でもないだろう。
理屈で全てを説明しようとする冷笑家にとっては、人生は滑稽なコメディでしかないだろう。
喜劇と悲劇の交錯する人生を「よりよく」生きるには、少しばかりの才能が必要だ。
心の表と裏(理性と感性)が、風通しのいい関係を保っていることが必要だ。
イギリス初代首相の息子であり、自身も政治家であった H. ウォルポールは、晩年になって、
怪奇・推理小説の元祖と言われる「オトラント城奇譚」を書き、当時のイギリスで爆発的な人気を博した。
彼は、“怪奇”と“恐怖”さえ、読者の中に一種の美意識や快楽を呼び起こしうることを、小説を
通して鮮やかに証明してみせたのだった。
"serendipity"(思いがけない幸運を見つける能力)という言葉の生みの親でもあるウォルポールは、
彼自身、人間の心の裏側に巣食う真実を発見する天才であった。
心の底に存在する理屈では説明できない不合理な何かこそが、人生を美しく輝かせる源なのだ
ということを、彼はよく知っていたのだ。
悲劇も、喜劇も、怪奇譚も、、、、政治も、文学も、すべて人間が幸福を追求するための1つの手段に
過ぎないのだということを、彼はよく知っていたのだ。
© Rakuten Group, Inc.