柳田國男あれこれ
<柳田國男あれこれ>驕る中華に反撥するかのように、ナショナリズムが盛り上がる昨今である。
そういう時代の雰囲気に触発されたのかもしれないが、柳田國男に関心が向かう大使である。
というわけで、柳田國男についてあれこれ集めてみます。
・柳田国男の故郷七十年
・勝手に関西遺産より
・これを語りて日本人を戦慄せしめよ
・民俗と民芸
・播磨気質
・白峰の出作り
・定本柳田國男集
 生家
生家柳田国男を旅する) が、ええでぇ♪
<柳田国男の故郷七十年>
図書館で『柳田国男の故郷七十年』という本を手にしたが・・・・
この本は柳田国男入門には最適とのこと。
兵庫県民なら、なおさらやで・・・ということで借りたわけです。
【柳田国男の故郷七十年】

石井正己編、PHP研究所、2014年刊
<「BOOK」データベース>より
小林秀雄も絶賛の隠れた名著・柳田国男の口承自伝を読みやすく最編集して復刊。
【目次】
故郷を離れたころ/私の生家/布川時代/辻川の話/文学の思い出・交遊録/私の学問
<読む前の大使寸評>
この本は柳田国男入門には最適とのこと。
兵庫県民なら、なおさらやで・・・ということで借りたわけです。
rakuten 柳田国男の故郷七十年
まず、大使のツボともいえる木地屋のあたりを見てみます。
p118~120
<木地屋のこと>
ふるくから山奥の原始林地帯に入って、木地の材料を求め、これを加工していろいろの木器を造って里に出していた木地屋の生活には、われわれとして研究すべきものがたくさん含まれている。
小倉とか小椋、大蔵など、オグラという言葉は、私は山上の「小暗き所」という意味だろうと思うが、こういう苗字や地名は、大体において、この木地屋に由縁があると見られる。
近江の君ヶ畑や蛭谷などを心の故郷としたこれら同業の人々は、近江、伊賀、伊勢はもちろん、北陸にも東海にも東北にも、また中国から西国の果ての九州の島々にも、いたるところその足跡を残している。
田中長嶺の書いたものとして世に知られる「小野宮御偉績考」なども、木地屋についての問題を扱い、遠く南北朝の時代にも遡ろうとする面白い試みであるが、何分にもその基になるものが全部近江蛭谷に伝わる作りごとから出発しているので、信用いたしかねるのである。
本の出来た年代にしても、私がこの事柄をいい出したときよりは、やっと十年ぐらいしかさかのぼれないのである。収録されている古文書の写しなども、太閤時代の長束正家という人に関するものなどは、本物らしいが、他はどうも疑わしいものが多い。
しかし木地屋そのものは、なかなか興味のある問題をもっている。播州西部の谷間でも話にきくし、但馬、丹波、越前あたりにかけても、その拡がりが認められる。
全国の木地屋の総元締と伝えられてきた近江の木地屋も、愛知郡の蛭谷や君ヶ畑、犬上郡の大君ヶ畑など、それぞれの系統があったらしい。しかもここでは寛政、享和のころにはすでに木地の材料がなくなって、ただ諸国に散らばっている木地屋を糾合するだけであった。木地屋の系統といえば、私は面白いことから近江と地方とのつながりを知ったことがある。
明治40年前後私が内閣の役人をしていたころ、賞勲局に横田香苗という人がいた。彦根藩士で、名家の出で、学者でもあった。もと警視庁の捜査係をしていたこともある。他のことではあまり冗談も言わない人だったが、この人の話に、維新前、今の日比谷に彦根藩の邸があって、そこに一人、近江犬上郡大君ヶ畑の木地屋に関係のある者がいた。いつも道楽をして金が足りなくなると、箱根の木地屋に行って僅かだけれど借りて来たというのである。つまり箱根の木地屋が大君ヶ畑の系統であったからという話であった。
箱根の木地屋は一時寄木細工などをしていたが、やがてこれでは手数がかかるので、それも廃れてしまった。明治になって、山林を自由に伐ることができなくなった木地屋は、大体二つに分かれてしまったようである。
まず少し有能の士は里に降りて来て木地の卸し売りをし、方々と連絡をとって大規模な生産や供給をした。次に能力の乏しい方は、コケシなどを造るようになったのではなかろうかと考えている。
私は近ごろまた木地屋のことに興味をもち出したのは、民族の国内移動ということを調べるのに、この山間を漂泊した木地屋などは最もよい例だと思うからである。
<木地屋のこと>
ふるくから山奥の原始林地帯に入って、木地の材料を求め、これを加工していろいろの木器を造って里に出していた木地屋の生活には、われわれとして研究すべきものがたくさん含まれている。
小倉とか小椋、大蔵など、オグラという言葉は、私は山上の「小暗き所」という意味だろうと思うが、こういう苗字や地名は、大体において、この木地屋に由縁があると見られる。
近江の君ヶ畑や蛭谷などを心の故郷としたこれら同業の人々は、近江、伊賀、伊勢はもちろん、北陸にも東海にも東北にも、また中国から西国の果ての九州の島々にも、いたるところその足跡を残している。
田中長嶺の書いたものとして世に知られる「小野宮御偉績考」なども、木地屋についての問題を扱い、遠く南北朝の時代にも遡ろうとする面白い試みであるが、何分にもその基になるものが全部近江蛭谷に伝わる作りごとから出発しているので、信用いたしかねるのである。
本の出来た年代にしても、私がこの事柄をいい出したときよりは、やっと十年ぐらいしかさかのぼれないのである。収録されている古文書の写しなども、太閤時代の長束正家という人に関するものなどは、本物らしいが、他はどうも疑わしいものが多い。
しかし木地屋そのものは、なかなか興味のある問題をもっている。播州西部の谷間でも話にきくし、但馬、丹波、越前あたりにかけても、その拡がりが認められる。
全国の木地屋の総元締と伝えられてきた近江の木地屋も、愛知郡の蛭谷や君ヶ畑、犬上郡の大君ヶ畑など、それぞれの系統があったらしい。しかもここでは寛政、享和のころにはすでに木地の材料がなくなって、ただ諸国に散らばっている木地屋を糾合するだけであった。木地屋の系統といえば、私は面白いことから近江と地方とのつながりを知ったことがある。
明治40年前後私が内閣の役人をしていたころ、賞勲局に横田香苗という人がいた。彦根藩士で、名家の出で、学者でもあった。もと警視庁の捜査係をしていたこともある。他のことではあまり冗談も言わない人だったが、この人の話に、維新前、今の日比谷に彦根藩の邸があって、そこに一人、近江犬上郡大君ヶ畑の木地屋に関係のある者がいた。いつも道楽をして金が足りなくなると、箱根の木地屋に行って僅かだけれど借りて来たというのである。つまり箱根の木地屋が大君ヶ畑の系統であったからという話であった。
箱根の木地屋は一時寄木細工などをしていたが、やがてこれでは手数がかかるので、それも廃れてしまった。明治になって、山林を自由に伐ることができなくなった木地屋は、大体二つに分かれてしまったようである。
まず少し有能の士は里に降りて来て木地の卸し売りをし、方々と連絡をとって大規模な生産や供給をした。次に能力の乏しい方は、コケシなどを造るようになったのではなかろうかと考えている。
私は近ごろまた木地屋のことに興味をもち出したのは、民族の国内移動ということを調べるのに、この山間を漂泊した木地屋などは最もよい例だと思うからである。
先日、竹中大工道具館の企画展「木地屋 小椋榮一の仕事」で「木地屋集落と移住ルート」を観たのだが・・・・
営々と移動した庶民の活力または悲哀に感じいったのです。
 木地屋集落と移住ルート
木地屋集落と移住ルート<勝手に関西遺産関西遺産より>
朝日に「勝手に関西遺産」というシリーズが10年以上続いていて大使も時々、気に入ったものをスクラップして保存しているのです。
そのうちの「播州弁」という記事が、柳田国男にふれていたので紹介します。
2012.10.4 【播州弁】わがイチ推し 押しの強さ より

播州弁は、そのアクセントからか「日本一押しが強い方言」と言われる。
私の祖母は兵庫県太子町出身で、時々、播州弁をしゃべった。「まだ寝とみないのか(寝たくないのか)」「おやつし(おしゃれ)」など。ふざけて「なんどい(何ですか)」と言われた時は、「オッサンか」と思わずツッコミたくなった。
福崎町出身の同僚(38)によると、高校時代、女子も「ごうわく(腹立つ)」と言っていた。男子は「おんどれ(おまえ)」と呼ぶことも。母親に「使わないで」とクギを刺され、大学進学後はあまり播州弁を使わなくなった。
「ざ行」の音が「だ行」に聞こえるのも、播州弁の特徴だ。あぜ道は「あで道」。ぞうきんは「どうきん」。質問の語尾に「こ」がつくこともある。「もう昼こ? 飯食うんこ?(もう昼? ご飯食べる?)」を「お昼を食べたら、すぐうんこ?」と勘違いしたという話も聞く。
そんな播州弁に復権の動きがある。市民がつくる「播州弁研究会」が、昔ながらの播州弁を人気順に番付表にしたり、かるたを作ったりして話題になっているのだ。
かるたの絵を描いた姫路市の漫画家、前田賢一さん(36)は「多くの関西弁と違い、播州弁は『はる』を使わない。それで荒っぽく聞こえるのかも」と言う。「先生いてはる?」は「先生おってか?」など。「でも尊敬する気持ちはちゃんとあるんですよ」
研究会の井上四郎会長(86)は「一口に播州弁といっても、姫路城下、海辺、農村地帯など、地域によって様々。京言葉や古語に近い言葉もあります」。米作りが盛んで都に献上していたことから、京都とのつながりも強い。「おてし(小皿)」「ずつない(苦しい)」といった播州弁は古い京言葉がルーツという。
意外にやわらかくもある播州弁。日本民俗学の創始者、柳田国男は福崎町出身。「故郷七十年」で、故郷では「クニョハン(国男さん)」と呼ばれていたのに、13歳で長兄が住む茨城県に移り住むと、子どもたちが互いの名を呼び捨てにしていて驚いたと回想している。
姫路市出身のエッセイスト、池内紀さん(71)は「柳田さんの本には『わが播州では』という言葉がよく出てきます。播州の体験は、柳田民俗学を完成させる礎になったはず」と言う。播州弁を聞くと、故郷に戻って来たことを実感するという池内さん。街がどこも同じ表情になってしまった今、ぜっぺ(是非)残したい言葉である。(田中京子)
◇
メモ:代表的な播州弁○べっちょない(大丈夫)▽せんどぶり(久しぶり)▽だてこく(いい格好をする)▽たいていやない(簡単ではない)▽さんこ(散らかす)▽らっきゃ(いいですよ)▽めげる(壊れる)▽なんじゃかんじゃ(いろいろ)
<これを語りて日本人を戦慄せしめよ>
この本のタイトルは『遠野物語』の冒頭にある「これを語りて平地人を戦慄せしめよ」から来ているそうである。
柳田國男は山人の立場で、かなり挑発的な言葉を発しているわけだが・・・・
山人とか、木地師とか、ウッディジョブは、このところ大使のツボであり、まさに柳田國男に戦慄するわけです♪
これを語りて日本人を戦慄せしめよ より

<人間苦追う「経世済民」の人:赤坂真理(作家)>
経済効率が至上となったこの国で、忘れられたのは、「経済」というまさにその語が、「経世済民(世を経〈おさ〉め民を済〈すく〉う)」の略だったことではないだろうか? 法制局参事官として「経世済民」を考え挫折した柳田国男は、未だ近代化の及ばざる山と山里に出かけ、まったく新しい学問を日本に拓いた―民俗学。
本書の衝撃的なタイトルは、『遠野物語』の冒頭にある「これを語りて平地人を戦慄せしめよ」から来ている。一体、山に何を見たのか? 人里から追われ、飢餓線上をさまよう山人たち。彼らの生きる様を「偉大なる人間苦」と柳田は呼んだ。著者は「人類の生存に課せられた業のような重荷」ではないかと言う。そこにあるのは仏陀のような視点でありはしないか。
「経世済民」を離れて「経済(エコノミー)」となった活動は、獰猛で、私たちを呑み込み、その内にいるも苦、外れるは、さらに苦。今こそ柳田国男を読み、戦慄しつつ、未来を紡ぎなおす時ではないか。そう思う。
◇
山折哲雄著、新潮社、2014年刊
<「BOOK」データベース>より
山に埋もれた人生を描いた代表作『遠野物語』が出されたのは明治末期。さらに『山の人生』では、山間部の壮絶な人間苦が描かれていた。小説という娯楽も広がり近代国家を謳歌する時代、柳田は文明から遠く離れた過酷な人生に目を向けていた。その半生を俯瞰し、民俗学という新しい学問を通して訴えたかったメッセージを探る今までにない柳田論。【目次】
第1章 普遍化志向/第2章 平地人を戦慄せしめよ/第3章 偉大なる人間苦/第4章 折口信夫/第5章 二宮尊徳の思想/第6章 ジャーナリストの眼/第7章 「翁さび」の世界/終章 日本文化の源流
<読む前の大使寸評>
梅棹忠夫さんの著書を読んだりして民俗学に関心があるわけだが、柳田国男については、まだ手付かずです(梅棹忠夫は民族学だったか―笑)
自宅には父が残した定本柳田国男集(全39巻)が飾ってあり、読書環境は申し分ないんですけどね。
山折哲雄も『遠野物語』や山人たちに注目しているので、まずこのあたりから手をつけようと思うわけです。
rakuten これを語りて日本人を戦慄せしめよ
<民俗と民芸>
『民俗と民芸』と言う本を図書館で借りて読んだのだが・・・
「一国民俗学」、「日本の眼」など柳田や柳のナショナルな視点を「あとがき」から紹介します。
<あとがき> p240~244より
柳田が唱えた「一国民俗学」は、彼が南方熊楠への手紙(大正5年)に書いていたように、近代日本語で創り出されるべき「ナショナルな学問」だったが、このことは、たとえばナショナリズムと呼ばれるような愚昧な主張とは関係ない。柳田が追求したものは<原理としての日本>だった。
この<原理>は、大陸の南の端から東の島々にわたるアジアの文明を貫いて働き、絶えず生成され、結果として<日本>と呼ばれることになるひとつの場所を造った。「米の信仰的用途」と彼が呼んだものが、疑いなくこの<原理>の中心を流れ続けている。あたかも、血液が心臓を循環し続けるように、である。
(中略)
<原理としての日本>は、柳宗悦の民藝運動のなかにもはっきりと働いていた。李朝陶磁や沖縄の紅型、あるいは木喰仏の内に、彼が突如として発見したものは、実はこの潜在的原理であったと言ってもよい。たくさんの器、着物、木彫は、この原理を通して、これを具現して余すところのない事物として、驚くべき言葉の力で創造され直した。こうした創造を前にして、多くの人々は「芸術」「作家」「個性」「独創」といった観念が、みるみる色褪せ、無内容となっていくところを見たのである。
もちろん、柳は、こうした<原理>が民藝のはっきりとした推進力として在ることを、理論的に書いたわけではない。けれども、この原理の存在は、彼の文章のいたるところで示唆され、時には見事に説き尽されている。最晩年の柳が、心臓の不調で病床にあった時に書いた「日本の眼」(昭和32年)という文章は前にも引いた。その冒頭で、彼は次のように言っている。
東京の国立近代美術館が「現代の眼」と題する月刊誌を発刊し、同じ題名の展覧会を開く。が、そこにあるのは、みな「西洋の眼」でしかない。「現代」とは「西洋」のことにほかならない。そういう仕儀となっている。なぜ、日本の美術館が、現代に光る「日本の眼」を標榜しないのか。「進んでは『日本の眼』をこそ輝かせて『西洋の眼』の足りぬ所を補足し、また補導しないのか」。西洋の流行りが、そのまま「現代」であると、なぜ早合点に思い込んでいるのか。そのことに「大いに反撥を感じる」と。
高麗や李朝の器に至上の価値を見出したのは「日本の眼」であった。作ることより以上に「見る」ことに、日本の文明は優れた能力を持っている。私たちの眼の能力には、おそらく気の遠くなるような過去から、本能に似た深い記憶から蘇ってくる働きがある。これは、個人の、一代限りの天分や修練で身につく能力ではない。日本の臨済宗や茶は、このような能力と密接に結びつくことによって発達している。が、それらは、時代が生んだ現実の結果に過ぎまい。柳の言う「日本の眼」は、それらのものを、また他の無数の作物を、現実の歴史に生み出してきたひとつの潜在的な原理である。柳の民藝運動が掴んでいたものは、この原理にほかならない。
柳は「無事の美」ということを、しきりに言った。「日本の眼」が見つめ通してきたものは、どこまでも「無事の美」であったと。平穏無事の暮らしの連続のなかでこそ、ほんとうの「美」が生きられている。いや、「美」などと言うこともない。物とじかに触れ合って生きる心の限りない充足、と言っても少しも差し支えはない。天才も、事件も、動乱も、挫折もここにはない。あるのは、あくまで平坦な暮らしの道である。
「無事の美」が基礎としているのは、やはり農の暮らしであろう。あるいは、農の暮らしが極まるところで磨かれる植物的な生の循環である。狩猟、牧畜に基礎を置く文明は、闘争や競合から離れることができない。事件や動乱に主眼を置いた歴史の俯瞰図は、このような文明のなかで描かれる。平穏無事の暮らしなどは、語るに値しない例外的状態ということにされる。
(中略)
柳宗悦の語る「日本の眼」は、柳田國男が説いた「米の信仰的用途」」に深く繋がっている。あえて言うなら、これら二つを生み出してきたのは<原理としての日本>であり、この原理は、現実の国家にも領土にも捉え込まれない潜在性の領域でのみ働いている。日々の暮らしが、そのまま信仰となり、美しい衣、食、住の聖なる生産と消費になり、そこでの幸福が、すでにそれだけで語る要もない道徳となる。そのように純粋な原理の領域が在った。いや、今も在ることができる、できるのでなくてはならない。柳田の民俗学と柳の民藝運動とは、それぞれの異様な努力を通して、私たちが生きる日々の潜在的な原理を、それが送り込む希望と喜びとを、示した。示したとは、一から創り直したという意味である。
柳田國男の民俗学と柳宗悦の民藝運動を並立して語るという着想もいいけど・・・
それをなぜ書きたいかと説明する「まえがき」がええでぇ♪
著者自ら「学術研究ではないし、一般読者向けの紹介とかいったものではない」と断ったうえで、この本の生い立ちを述べています。
<まえがき> より
柳田國男の民俗学と柳宗悦の民藝運動とは、二人の天分に従って大変異なる方法、手段、言葉遣いで展開されたのだが、それらを生み出し、成長させた土壌は同じひとつのものだ。二人は、そのことを充分に知っていながら、まるで疎遠な兄弟のように、互いにほとんど通い合うところがなかった。
論争も称賛も交し合うことがなかった。それほどに、二人の仕事は、歴史中の大きな困難を、それぞれの仕方で突き抜けたところにあって、説きがたい孤独な普遍性を帯びていたと思う。これまで彼らに向けられてきた崇拝、懐疑、揶揄、罵倒は、みなそのことを裏から示している。
私もこの本は、彼ら二人の仕事をして輪唱のように歌わせたい、という願望から書かれている。声質も音域も異なり、伴奏法もまったく異なる二人に、同じただひとつの曲を交互に歌わしてみたい、という願望である。
(中略)
そういうわけだから、これから私が書くことは、もとより学術研究ではないし、一般読者向けの紹介とかいったものではない。私は柳田と柳と、さらにこの二人をめぐる幾人かの人々の歌から注意深く採譜して、それらを繋ぎ合わせ、できれば自分なりの演奏をつくり出してみたいのである。そういうことが、できるかどうかはわからないが、この試みは、少なくとも私にとっては無上の喜びだ。それでよい。書く喜びが、最も深い動機でないような本を、私は結局のところ信用することができない。
【民俗と民芸】
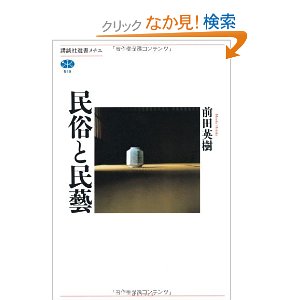
前田英樹著、講談社、2013年刊
<内容紹介>より
柳田國男の民俗学と柳宗悦の民藝運動―。異なる方法、言葉遣いで展開されたそれらを、成長させた土壌は同じひとつのものだ。それを本書で著者は“原理としての日本”とよぶ。時期を同じくしながら、交わることの少なかった二人の仕事によりそい、二人の輪唱に誘う力作。
<大使寸評>
柳田國男の民俗学と柳宗悦の民藝運動を並立して語るという着想もいいけど・・・
それをなぜ書きたいかと説明する「まえがき」がええでぇ♪
著者自ら「学術研究ではないし、一般読者向けの紹介とかいったものではない」と断ったうえで、この本の生い立ちを述べています。
amazon 民俗と民芸
民俗と民芸 byドングリ
<播磨気質>
「なんどい ダボ!」
神戸や摂津の住人にとって播州弁ですごまれたら・・・怖いでぇ。
でも播州弁や河内弁は、けんかの時は断然優位に立つわけで・・・
その口調を覚えておくべきかと思ったりする(笑)
冗談はさておいて・・・
図書館で「播磨気質」という本を借りたのだが、柳田国男の生誕地である市川筋のあたりを見てみましょう。
<純農村>p135~138より
学者の宝庫といえばよいだろうか。市川流域から維新後、日本を代表する大学者や文人がわくように群がり出た。
日本民俗学の父・柳田国男を筆頭に、国男の次兄で国文学者の井上通泰(神崎郡福崎町)、「古寺巡礼」や「桂離宮」を著した和辻哲郎(姫路市仁豊野)など、人材の豊富さは全国でも例がないほどだ。市川筋には学者や文人をはぐくむ土壌があるのだろうか。
「この地方はもともと、儒学が盛んな土地柄。あちこちに藩校や私塾があって、教育レベルはかなり高かったようです」と柳田国男記念館の永井早苗館長は指摘する。
(中略)
姫路藩の学問奨励策は、豊かな経済力を誇るこの川筋の地下人、百姓身分にまで向学心を植え付けた。その代表が大庄屋「三木家」(福崎町)。当主は代々学問好きで、蔵書は実に4万冊にも及んだ。柳田は三木家の書庫に自由に出入りを許され、すさまじいまでの読書が向学心を生み、学者への道に踏み込ませたようだ。
同時に市川筋は、生野の銀の運び道として、早くから交通が開けた流域。生野が天領だった関係から、江戸、大坂と直結、風通しの良さは抜群。柳田国男の育った福崎町辻川はまさにその典型といえよう。
辻川は飾磨から生野を経て但馬にいたる南北の道と、播州中央部を東西に横切る道路との交差点にあたる。高い文化や新鮮な情報が黙っていても入ってきた。「辻川という旧い道路の十文字になった所に育ったことが、幼い私にいろいろの知識を与えてくれたように思う。外部のものの一つずつに対して関心を寄せながら成長するようになった」と柳田が「故郷70年」で述懐している通りだ。
豊かな経済力と姫路藩が打ち出した学問への前向きな姿勢。この川筋特有の自然、文化風土が、柳田以下の学者群を生み出したといえないだろうか。
柳田がなぜ、当時全く未開拓の民俗学を志したのか。このあたりの事情も市川筋の自然環境が大きくかかわっているようだ。「この川筋は江戸時代300年が築き上げた純農村の姿を最もよく残しているところ。風俗、習慣、生活など学問的に採り上げるテーマがどこにでもころがっていた」と姫路学院女子短大の打浪教授は分析する。さらに人間の往来に伴う情報の多さが、一つの研究テーマを幅広く派生させる自由な姿勢を生んだのでは―という。
民俗学の原郷ともいえるこの川筋に私設の「香寺民俗資料館」と「日本玩具博物館」が誕生、大きく育ちつつあるのも当然だろう。
<白峰の出作り>
「ブナ・ナラ・クリ(木の文化5)」という本のなかに、本多さんの説く“白峰の出作り”という話があったので紹介します。
柳田國男が言うところの山人なんでしょうね。
<白峰の出作り> p114~116
「元禄時代から明治初年までは、全国的には新田開発が一段落して人口があまり増えなかった時代ですが、この白峰ではその間も人口が増えたのです。そのころ、この地が非常に豊だったということですね」白山ろく民俗資料館の山口一男館長はこう語る。
今では山間の僻地というイメージが強いが、白山を背後に「出作り」と呼ばれる生活と、さらには木を上手に使う技術がこの土地に豊な生活をもたらしたという。出作りをはじめとした白山麓の民族文化に詳しい山口館長の話をもとに、往時の白山麓の暮らしを探ってみたい。
<土地をもとめて出作り>
白峰(現在は石川県白山市)では500年ほど前から「出作り」という形態がはじまった。白峰の集落は、標高500mくらいの標高だが、さらに標高1000mくらいまでの山にでかけて農業をおこなう。春5月に一家をあげて標高の高い出作り小屋へ行き、夏の間はそこで耕作と養蚕をおこない、11月の初旬から中旬に降りてくる。中には出作りといっても冬も山で越す永久出作りもあった。
白峰の集落周辺では耕地も限られていて、人口が増えるに従って食糧を確保するために、より高いところに耕地を求めた。白山麓でも白峰側は比較的山がなだらかで豊かだったからできたこと。狭い谷間の集落には住める人の数は限られており、300戸を超えることは難しかった。その許容量を超えて人が住もうとすれば、別の土地を求めざるを得ない。
<焼畑と養蚕>
出作りでの耕作は、山林を伐採しての焼畑。1年目にはヒエ、2年目にはアワ、3年目には大豆という具合に土地が痩せないように作物を変えてつくっていく。このような雑穀は、気候変動などによる収穫の増減が少なくて安定していた。通常一軒で0.2~0.3ha程度の焼畑をしていた。ひとつの焼畑を5年ほど使うと、その後20~30年は放棄し、地力が回復して草木が生育するとまた火入れをして利用する。
この地域の焼畑の単位面積あたりの収量は、他の地域の焼畑に比べ高かったということだ。20~30年の周期で伐採する木材もさまざまに利用された。また、放置された焼畑ではフキ、ヨモギ、ウド、ワラビなどの山菜も収穫できた。出作りは自給自足の生活で支出もないけれど、収入もなかった。しかし、現金収入を得るために養蚕がさかんになってくる。
「出作りのための大きな要因は養蚕だった」と山口館長は指摘する。桑を植える土地を求めて山に登っていった。養蚕にかかる年貢は米などに比べて低く、生糸は軽いため運搬にも便利。現金収入を得る手段として、養蚕が出作りを推進したとも言える。
白峰からは加越国境をこえて、福井県側まで出作りに行った記録がある。福井県側では水田耕作ができるところまでしか農耕が行われなかったが、国境をこえて白峰の人々は山中に出作りをした。「他の地方の人々は奥山で養蚕や農耕をするという発想がなかったけれど、白峰の人々はそれが出来る技術もあり収量も高かったのです」と山口館長は教えてくれた。
<木の使い方を熟知>
当然、木を利用する技術にも長けていた。
さまざまな道具に使われている樹種を見ると適材適所で、現代のさまざまな木材実験のデータとも一致するという。大きな木槌の柄にはミズナラを使い、頭にはどんな衝撃でも割れないナツツバキやミズメを使う。標高が高くなるとブナの原生林に自然と遷移していく地域だ。鍬の柄にはブナが使われている。ツルハシの柄には強度が大きくて折れにくいミズナラ。建物の中では敷居には硬いナシを使っている例がある。
<宵越しの金は持たない>
白山という信仰の山をもち、白山山頂の堂社の造営や維持管理・登山者の世話等の仕事があるという地の利もあったが、養蚕と紬や麻などの織物生産がこの地域に豊かな経済をもたらしてくれた。この土地でも「」という風潮があったというが、それは持っていなくても将来に養蚕などで必ず収入が得られるという裏づけがあったから。雑穀しか収穫がまくとも、他の地域から米を買うのには十分な経済力があった。
近代的な視点からすると、白峰は山間僻地としてのマイナスイメージが先行するが、山の恵みを十分に利用して経済的に豊かな時代があったことを忘れてはならないだろう。それは循環型社会の構築を求められている現代に、ヒントを提供することができるかもしれない。
<日本がモデルを示すべき:オークビレッジ稲本正さんに聞く> p128
日本は世界でもまれに見る木とのつきあいの長い国なのです。歴史的に見て日本が木から離れたのは、古墳時代と現代だけといっていいでしょう。縄文時代は「第一次期の文明」、飛鳥時代からほんの数10年前までは「第二次期の文明」の時代。戦後しばらくの頃までは、住宅も9割が木造住宅でした。木についてトータルに見ても、デザイン・使い方などで一番発達しているのは日本です。世界にこうしたモデルを示すことができるのは、ドイツと日本だと思っていますが、ドイツはすでに成功のパターンに入りつつあると思っています。
今の世界ではアメリカがひとつのモデルになっていますが、環境問題からいうと、アメリカ型は失敗モデルです。近い将来、中国・インドもアメリカ型になる可能性があります。
木の文化・文明に長い間親しんできた日本こそ、木という再生可能資源を中心とした循環型システムの成功モデルをつくって世界に示すべきでしょう。「第三次期の文明」の実現に向けたイメージをつくりあげていく必要があります。
【ブナ・ナラ・クリ(木の文化5)】
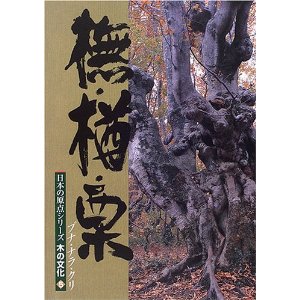
ムック、新建新聞社出版部、2006年刊
<「MARC」データベースより>
ブナ・ナラ・クリを中心に、広葉樹の建築と職人、広葉樹の歴史、山林に学ぶ、山麓の暮らし・里山の自然など、幅広い観点から広葉樹にまつわる日本の文化を紹介する。全国の巨木や、ブナ・ナラ・クリの基礎知識なども収録。
<大使寸評>
ブナ・ナラ・クリといえば・・・
日本ではありふれたというか、代表的な落葉広葉樹であり、大使のツボをつくわけです。
とくに“山林との共生”というコンセプトがいいですね。
Amazon ブナ・ナラ・クリ(木の文化5)
<定本柳田國男集>
父から引き継いだ定本柳田國男集なんですが…
【定本 柳田國男集】

柳田國男著、筑摩書房、1968年刊
<「BOOK」データベース>より
古書につき、「BOOK」データ無し。
目次はtoranokobunkoデータ参照
<大使寸評>
初版本全36巻(全31巻+別巻5巻)を父の蔵書から受け継ぐものだが・・・
旧仮名遣いと旧漢字にたじろいでいます(笑)
toranokobunko 定本 柳田國男集
© Rakuten Group, Inc.







