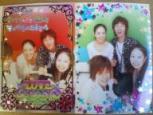全2534件 (2534件中 1-50件目)
-

移転/素晴らしい日/皆様ありがとうございました/
素晴らしい日。今日、僕らはとても多くを学ぶことができました。(僕ら、とはここでは僕と何かしらの時間を共に過ごしていただいたすべての方々を指しています。)1週間で7日ほどの日が僕にとって素晴らしい日。それ以上の日々はどこにもない・・・。すべての方に感謝を。ありがとうございます。また楽天ではこのように多くの方と様々なお話しをさせてもらう事ができました。実際にブログをきっかけに多くの方とお会いする事もでき、僕にとってはすべての瞬間がとても貴重な学びのときとなりました。今日この日をもちまして楽天を引っ越します。移転先はこちら。↓http://mrhonda.jugem.jp/すべての皆様に感謝をこめて。今後はこちらで・・・宜しくお願いいたします。m(__)m。
March 14, 2007
-
中3生へ
塾に来てくれた受験生すべてのみんなへ。本当によくがんばってくれました。みんなの努力はさらに次なる舞台で大きく花開くはずです。僕はひとりひとりが今できる最善を尽くせたとそう信じている。今出来る最善の最大量は、これからもっともっと伸びていくだろうし、伸ばしていって欲しい。そのようにこれからも困難や壁がやってくるたびに多くを学んで欲しいと思う。出た結果が今のすべて。それ以上もそれ以下もない。今のすべてではあるのだけれど、君と君の人生のすべてではない。これからも自分の道で各々の最善を尽くしていって欲しいと思う。中3のみんなよくがんばりました、お疲れ様、そしてありがとう。
March 14, 2007
-
僕から僕へ/決意
(くれぐれも特定の方や塾に向けて書いておりません、ご理解下さいませ。批判や悪口ではなく自分の意思表明の文です。)ふと思った。うちの生徒が○○中学校の1番です、なんて触込みを絶対に使わない塾にしよう。1番のその子だけがそんなに偉いのか?・・・ちょっと違う。・・・ぜんぜん違う。そんなのは僕の流儀に完全に反する。塾の手法として学校で上位の子が来ていますよ、とか平均点付近の子を対象にした塾です、学校授業についていくのが難しい子をお助けします、・・・という顧客にターゲットを知らせる手法というのはサービスを提供する側、受ける側、両者にとって非常に有益な手法だろうと思う。だが、個人名を張り出したり、特定の子だけをチョイスするのは僕の流儀に完全に反する。僕は300人の生徒みんなを愛している。実名をあげて自慢するなんてまっぴらだ。実名をあげるときは300人みんなの名を上げる。僕にとってがんばるみんな、ダイヤモンドの個性を輝かせるみんな、一人一人が何よりの宝物だよ。絶対にそういう塾であり続ける。絶対に。何でこれまでの塾ってそんなにみんな成績を威張り散らすんだろう?僕はそういうありきたりの既存の”塾”という名のスタイルが大嫌いだ。よくあるじゃん?ガラス面一面に実名入り成績張り出すの?それをやるのが塾だというのならね、いいからさ、僕は”塾”という名前を使わないから。それより「みかみ塾は、子ども達みんながとても愛されていて、とても勉強を頑張れる空間で、でも優しくて温かくてそれでも賢くなれるんだって。」と言われる塾を作るよ、絶対に。そして塾という名をいつか飛び越えるんだ。僕から僕へ。「おいっ、ミスターホンダ、お前がやれ」「あぁ、やってみせる。」
March 14, 2007
-
ここはそのような場所
悪口を言わない大人になろう。愚痴を言わない大人になろう。批判をしない大人になろう。人の不幸を3時のおやつにするのはやめよう。陰湿で暗い気持ちで生活するのをやめよう。横柄でない大人でいよう。人を疑わない大人になろう。人のせいにしない人でいよう。笑顔を絶やさない大人でいよう。”人の良いところを見つけて褒める選手権”のランカーとして生きよう。思いやりを持った大人になろう。願望を持って生きる大人になろう。夢を語れる大人になろう。美しいものに涙できる大人でいよう。今年こそひさしぶりにクラシックのコンサートに行きたいなあ・・・。無理?忍耐力を持った大人になろう。言葉を大切にできる大人でいよう。信じる事ができる大人になろう。ユーモアで人を笑わすことのできる大人でいよう。ときどき吉本新喜劇を見よう。love。行動できる大人になろう。人を許せる人間でいよう。自分を大事に出来る大人でいよう。自分を許そう。愛情に溢れた大人になろう。・・・・・・ちょっとだけ書いたつもりだけれど大人ができることなんて本当にたくさんあるんだ。これらが当たり前である空間、それが僕らの塾のあり方。それが当たり前であるチームでありファミリーでいよう。塾という名を使わないときが来るかもしれない、塾という呼び名にこだわりはない、そのときはhomeだったりfamilyだったり・・・名前はどうあれ、そのような場所であり続けたい。
March 14, 2007
-
寒さ
ひとまず帰宅。さすがに夜中は少し寒い。最近はまたちょっとだけ寒さが戻った感がある。そういえばまた学校でも風邪やインフルエンザでお休みの子もいるようだ。みんな気をつけてね。
March 14, 2007
-
明日
いよいよ明日が公立高校の合格発表。すべての子の最高の結果を祈っておこう。もう僕が緊張してきた・・・。==========塾が近いみんな、先生たちは周陽にいるから来れる人は顔を見せにおいでね?来れない子は連絡待っているよ?
March 13, 2007
-
残っています
MUSTの予定時間を終え、数人で残って勉強しています。早く来て自習をしてくれた子、残って頑張ってくる子、絶対に意義ある時間だ、君たちはすごいと思う、がんばろうね。
March 13, 2007
-
子ども達の側に
体験授業が進んでいる。自習部の子も勉強に励んでくれている。目を輝かせている子どもたち、僕らはいつもその輝きを失わせないでいられるようなそのような接し方、励まし方、支え方を常に学び意識し行動や言葉に繋げたい。
March 13, 2007
-
変則
ミーティングを終え、移動し原稿書き中。まもなく完成。今日も体験と変則日程授業。塾内テストも近い。テストに関してもしっかり意義のあるものにするという大人の意識付けが大事だ。テストという目標を立てることで学習の習熟度合いを高めたい。
March 13, 2007
-
信頼はどこから来るのか?
”信頼はどこから来るのか?”(特に誰かに向かって書いていたり、誰かを責めていたり、このことを討論したいと思って書いていたりしないことをどうぞご理解の上お読みください。)子ども達が学校の先生の悪口を言う時代になった。いや正確には、信頼しない時代になったという言い方が正しだろう。一昔前だって○○先生は嫌いだ!なんて言っていたがそれとはずいぶん違う。学校の先生がそもそもおかしくて間違っていて信用できない、という風潮が強まっている。嫌いなのと信頼できないのとでは根本が違う。ときどき子ども達がそうした内容を話しているのを聞くと、僕は授業する気を失う。(少し前、新人王もそのようなことにショックを受けていて肩を落としていた。もっともなことだと思う。)どの子も人を信じられない人間になんて育って欲しくない。そもそも人は、誰かに不信を抱く前に自分を振り返ることが先であるはずだからだ。この発端は単純に親であると認識している。子は親の鏡、家庭を映し出す鏡といってもいい。子どもはまだまだ自我、自己の判断、を養っている最中である。他者に対する不信感を子が勝手に持ち出した!なんてことは起きない。子の価値観は親が与えたものに他ならない。他人に対する信頼感、それを与えるのも親だ。親が他者を信じないのなら子はそのように思うだろうし、親が他人を信頼するなら子もまたそのようであるだろう。家庭で学校の先生の信頼を失うような発言をしていないか?振り返ってもらいたいと思う。不信感を仮に持ったとしても、それはきちんとした場で、つまり両者できちんとした話し合いを持つことを考えるべきだろう。それで理解し合えないのであればまた然るべき方法を取るべきだと思う。そういったことをせずに、ただ聞くままに子どもの話が100%だと信じ、安易に不信感をあらわにすべきではない。子に限らず、2者のうちの1者からの話はどのような場合も主観という偏りがあることを理解せねばならない。それは”子を疑う・信じる”の話ではない。人が2人いれば2通りの、10人いれば10通りの言い分があって然りなのだから。不信感がどこから来るのか?まずはその自覚をすべての親御さんに持っていただきたい。子どもが何かしらの話をした際、”どうして相手がそのような行動を取り発言をしたのだろう?”と考える時間を与えて欲しいと思う。また、それを一緒に考えるようにして欲しい。先にすべきは相手を理解しようとする姿勢であって、不信感をあらわにすることではない。それでも相手の言動の理由が理解に苦しむものであるなら、その上で然るべき対処をすべきだろう。結局すべては人が行う行為である。100の理解というのは到底不可能なのだから、それよりも相手を少しでも理解しようとする心を育てる方が大事ではないか?そんなに誰も彼も信じることの出来ない子に育って欲しいのだろうか?本来子ども発信の事柄は、ものすごく前向きでクリエイティブな事象ばかりなのではないのかと思う。逆にネガティブなものこそ、大人が影響したがための憂いではないかと疑って欲しい。人を信じられる世の中であって欲しいと願いこの記事を書いている。また、学校不信の核は家庭であることも避けては通れない事実であり、信じないという意思表明の前に、社会の一員である皆で理解し信じあえる社会を築くことが出来ればと願って止まない。すべての親御さんの子どもに対する何にも代えることのできない愛情に敬意を表して。どうかすべての人が幸せでありますように。
March 12, 2007
-

ただいま
今日も変則日程でみんなで復習に取り組んでいる。結果を出すための努力。特に新3年生達は受験生としてさらなる頑張り、そしてさらなる壁に立ち向かわねばならない。毎回の積み重ねを大事にしながらがんばろう。
March 12, 2007
-
淘汰は進むという考察
いよいよ淘汰の時代に入った。これから塾の勢力図は大きく変化するはずだ。塾外で話をすると、”教育産業はずっと需要が続くし、安泰ですね”といった内容を耳にすることがある。確かに教育産業自体がなくなることは考えにくいが、それでも安泰の塾はおそらく一つもないだろう。なぜなら、塾業界は完全に選別の時代、淘汰の時代に突入したからだ。その理由のひとつに、一時代を築いた(主に)家塾の先生方がおおよそ年齢的に引退を考えられる時期となっていることがある。いわゆる世代交代の波である。また、業界全体が次の曲線(新しいスタイルのサービス)作りにシフトしていることからも既存のサービス商品は衰退期に入ったといえる。もうひとつは、塾のスタイルの変容である。少子化と個を重んじる時代に入り40~50人という大人数での授業スタイルはもはやマイノリティー、現在は10~20程度の少人数制集団もしくは個別のスタイルに移行している。既存のやり方に固執しすぎる塾ではこの波を超えることは難しいだろう。時代の流れは速い。この1・2年で大きく既存の塾が淘汰されていくのではないかと感じている。世代交代(つまり新規参入)と業界のスタイル転換が一気に進めば、消費者の選択がこれまでと大きく変わってくる。大手だったら安心だろうという選択はもはやない。そうすると、大手にしろ小さな塾にしろ、これまでの”付き合い、昔からの馴染み”のような古くからある”塾に対する人の感覚”が薄れて来て、淘汰の流れは加速するだろうと思う。より良いものを求めるという人間の欲求がある以上”好ましくないもの””求められていないもの”は当たり前だが淘汰されるべきだと思う。それが自然の摂理だろう。ニーズもウォンツもないものがどうして生き残れよう?消費者にとってより良いものが残るというのが市場の原理ではないかと思う。選択と淘汰。消費者の選択の変化と淘汰が進めば一気にそのエリアの様相が変わってくるだろう。
March 12, 2007
-
視野を広げて
視野を広く持ちたい。狭い世界に閉じこもってしまってはならない、いつもそう思う。今日も多くの方と話をすることができた。大局でものを見る、ということに繋がること”視野を広く”。近い将来、日本中そして世界中で活躍する子ども達を預かっているのだ、単に塾という小さな空間に閉じこもっていてはいけない。僕らは塾という社会の一員ではなく、あくまでも世界という社会の一員である。チームの先生方にもさらに見識を広めていただきたい。そのように僕も仲間達も向上していければと思う。
March 12, 2007
-
誰もがその努力を
予定通りいくつかの仕事が終了。少しずつ新年度の足音が聞こえ始め、学年末を終え塾を移ってきてくれる子達が多く入塾してくれている。みなが良い結果が出せるよう、僕の役割を果たしたい。もちろんそのためには先生方や保護者の方の協力、本人のがんばりが必要不可欠だ。どれが欠けても思うような結果は出ないだろう。先生のスキルや頑張りが欠けても駄目、保護者の方々の深い理解がなければ駄目、子ども達の成長を促せなければやはり駄目、そしてそのどれもに愛情が欠けていてはいけない。そのすべてを引き出すのが僕の役割だ。大局で物事を見定め、広い心と深い愛情を持って新年度も努力し、また学び続けたい。
March 11, 2007
-
意識を高めるのは一部の人間だけではない
新年度さらなる取り組みも待っている。準備もどんどん進めている。また勉学に対する啓発も今後の取り組みのひとつと考えている。まずは大人が勉強に対する重要性を認識すること、これが大事にしたい意識付けのひとつだ。自分にとって都合の良い取り組みだけをして、都合よく成績があがるという安易な方法論から脱したい。つまり成績アップのために必要な”種まき”を大事にする、種をまくことなしに収穫を期待しない、という意識を高めるところからのスタートだと思う。大人も子どもも塾も学校もすべてが向上できるよう取り組んでいくつもりだ。
March 11, 2007
-
本を
読書。車での移動中や1・2分の空き時間を見つけては読書をする。また同時に数冊を読むように心がけているので、いつもカバンが膨れ上がる。そんな日々の読書。で、最近1冊本を失くしてしまってちょっとショック。あぁ・・出てこないかなー・・・。
March 10, 2007
-
スタート
スペシャル週間初日。新3年生たち、みんなよくがんばってくれた。当たり前だが、力はまだまだまだまだのレベルだ。受験の意識もしっかり高めていきたい。最後まで残ってくれたみんな、よくがんばったね。みんながやらないときにだけ人との差が生まれる。これを続けていけるようにがんばろうね。
March 10, 2007
-
シャレ
お洒落に生きよう。新年度からもますますいわゆる塾の先生のイメージを完全に壊して生きたい。(*^。^*)。まずは買い物・・・と。(この時間を作るのが手ごわい)
March 10, 2007
-
体験・変則日程スタート
授業が続いている。新一年生の体験授業が今日から始まったところだ。なるべく各教室に顔を出せればと思う。さらに今日から3月の変則日程がスタートする。会場を外に移して塾内テストもある。これでまた子ども達の勉強する瞬間を増やしたい。それを応援したい。積み重ねた者が求める結果を手に入れることができるはずだ。ともかく今日から変則日程、みんな間違えずに来てね。
March 10, 2007
-
じむ
新年度の入塾・問い合わせも順調に推移している。この時期はやはり事務系の仕事が最も大変になる。特にテストなども含め、3月中は変則日程になっているので連絡ひとつとってもなかなか大変だ。チームの皆様宜しくお願いします。みんなが支えてくれる中、僕もしっかり仕事を進めておきたい。==========塾に通っていただいている皆様へ塾お知らせ掲示板を移転しました。(ここでおおよそのお知らせは分かるようになっています。時々チェックされてくださいね。携帯からも可です。)今後とも宜しくお願いします。
March 10, 2007
-
準備も
明日からの授業準備中。ようやく終わりそう。新2・3年生、みんなに頑張ってほしい。テストにしろ自習部にしろ授業にしろ、新3年生はいよいよ受験生。毎回毎回の結果を大事にしたい。
March 10, 2007
-
ニード
学ぶ必要があるときに人は学ぶようにできている。素晴らしいことだと思う。逆に言えば自分が相手にこうして欲しいと望んでも、相手が学ぶべきときが来なければ学んではくれない。誰にとってもそれは同じ。そこにイライラを募らせても仕方ない。だって相手は相手、自分は自分の人生を生きているのだから。人の道とはそのようにあってとても素晴らしい。
March 10, 2007
-
受験勉強の嘘たちへ告ぐ
受験勉強の嘘たちへ告ぐ君たちは勝手な想像によって作られた都合のいい製造年月日シールのようなものだ。何の根拠もなく嘘で貼り付けようとするならば、確かにそれはいくらでもごまかせるだろう。だが、僕の目はごまかせない。だから目の前から消えて欲しい。なぜって?・・本当はそうじゃないからだ。だって僕の目の前の子達がそう教えてくるのだから・・・・。○受験勉強で個性が埋没する → そんなことが起きたらもう僕は塾をやっていない。僕の目の前の子達は僕の知る大人以上に無限の色に輝くダイヤモンドだ。怠惰につまらない日々を送っている大人達の何倍も素晴らしい個性を持っているではないか。○受験勉強で優しい心が育たない→ 僕の子達は受験勉強をしてないのだろうか?と思えるほど思いやりのある優しい子達ばかりだ。○受験勉強で自分勝手な子が育つ→ 先生の授業もろくに聞かず、宿題や課題も出さない、そんな子より自分勝手に振舞うことの方が難しいのではないか。少なくとも僕は、競争心や仲間意識をしっかり持った”周りの子を思いやれる子”達ばかりに囲まれている。○受験勉強が過度のストレスを生む→ 受験勉強をしていない大人に鬱が多いのはなぜだろう?心とはその持ち方次第である。むしろ多少のストレスの中でこそ自分を成長させることができる子になって欲しい。○受験勉強が創造性を阻害してしまう→ 正しい知識、よりよい心構えを学ぶことこそが本当の創造性を生むのだ。無から生まれるものが創造ではなく、知識と心の集大成こそが創造である。例えば、モーツァルトがクラシック音楽を創造したわけではない。クラシックにおける先人たちの知識と彼の心が、彼の素晴らしい曲を創造させたのだ。○受験勉強=詰め込み勉強が心の成長を阻害する→ 日本国民のほとんどは心が育ってないことになりますね?それって本当ですか?僕の子ども達はみんな優しい心を育ててくれてありがとう。日本からいつか飛び出そうね?○受験勉強はすべてではない。→ はい。正解。そう、正解。もしそう思っていたら合格した後もみんな変わらず何十年も受験勉強をしているでしょう?僕はそんな人にあったことありませんが・・・。受験勉強の嘘たちへ。さようなら。君たちの賞味期限はもうすでに来ているんだよ・・・。
March 9, 2007
-
僕へ
僕から僕へ感謝のない人と付き合うのはやめましょうね?自分がどのように相手に与え、また相手をどのように理解しようと努めるか?それができる大人でいましょう、なりましょう。だからそれができない人と付き合うのはやめましょうね?人は自分が出している波動に吸い寄せられるように集まってくるものです。だから感謝できる自分をしっかり持って相手と接しましょう。それで相互理解できる者同士で付き合えばいいわけです。僕らの波動に合わない人は去っていくだけになるかもしれません。それも学びのひとつです。相手を大事に、自分を大事に。僕へ。
March 9, 2007
-
みんなの頑張りを”本当”にするために
みんなはとても大事なことを学んでいる最中だ。そこには何の疑いもなければ何の迷いもいらない。これはとても大事なものだと自分に言いきかせながらしっかり学び続けて欲しい。「受験勉強なんて・・・学校の勉強なんて・・・勉強だけできても仕方ない・・・・」なんてことは一切ない。他の大人達が少しだけ勉強が出来ないことの言い訳をしても、僕はしないよ。だからみんなも、”勉強をしなくていい理由”を探さなくていい。今やっている勉強は最高に意義あるものだ。自分の目標を高く掲げて前進しよう。
March 9, 2007
-
努力3乗
学年末の結果がおおよそ返ってきた。前回に比べるとさすがに学年末、どの学校でもほとんどの教科で学校平均点が下がっている。基本的な評価はテストの難易度に左右されてしまうので順位と平均点との差でみるのがベストだろう。(もちろん平均・難易度に左右されて欲しくはないが)(平均80点のテストで85点・・平均50点のテストで85点・・・・単純に点数だけで見るとおかしなロジックに陥るだけだ・・・これで一喜一憂しても仕方ない。)僕の全クラスは目標を95点に据えているが、今回は達成出来ずじまいで終わりそうだ。これまで95点を超えていたクラスもあったが、どうやらおよそ90点付近に落ち着きそう。学年順位はまだ出揃っていないが、大きくジャンプアップした子もいる。各学校で一桁の子も多く出るだろう。逆に思うとおりにいかなかった子もいるはず。問題は満足できない点を取ったときに、このままでは駄目だ、と思えるかどうか。勉強時間にしろ勉強スタイルにしろ、多くを見直し次の糧にできるか否かが勝負の分かれ目だ。皆に奮起してもらいたい。努力した分が結果に返ってくる、そういう結果をたくさん目にしてきている。努力の先にまた努力。努力を2乗、3乗と累積していきたい。がんばろう。
March 9, 2007
-
卒業式
今日はS中卒業式に出席。今年は親御さんに同行させていただき入れてもらう事ができた。(昨年はS中に断られてK中に出席。)素晴らしい卒業式だったと思う。やはり卒業生たちの表情と言葉が胸をうつ。心がこもっているとはなんと素晴らしいことか。(ただ形式のみで綴られたあいさつ文の5億倍感動的だ。)たぶん子ども達は僕とあきこ先生が来ていることには気づいていなかったと思うけど、”みんな卒業おめでとう。”
March 9, 2007
-
明日は
仕事を続けている。もう少し進めておこう。明日は卒業式なので学校に入らせてもらえれば子ども達の中学生活最後の姿を目にすることができる。もちろんすべての学校に行けるわけではないのが残念だけれど。どの子にとっても思い出深く素敵な卒業式になって欲しい。
March 9, 2007
-
入試 山口県
山口県公立高校入試2007。英語。例年に比べるとやや難。解答を作りにくい単語なり英作文になっている。確かに教科書の範囲内だろうが英作なんかは微妙なところをついてきた、という感じで答えにくさがある。教科書の範囲内でテストをつくり難易度を上げるとしたら、当然といえるつくりといえるだろう。数学が少し楽になった分、こっちにしわ寄せがきたというべきか・・。5教科の中では平均点が最も低くなるかも?数学は基本問題がかなりイージーな感がある。昨年に比べるとかなり点数が取れるつくりになった。平均もそれなりに上昇するだろう。予想通りといったところ。但し、難易度の高い問題のいくつかと時間と費やしてしまいそうな規則性の問題が高得点は阻む感じか。上位校を狙うみんなは難易度の高い問題がどれくらい解けたか?の勝負。理科は毎年あまり難しくないので少し難化するのかな?と想像していたがかなり取りやすいテストだったといえる。なにより山口県特有の問題のややこしさが緩和されている。しっかりした入試勉強をしていれば対応できただろう。逆に塾などでしっかり受験用に学習していないと苦しいかも。塾のみんなはしっかり出来た!と信じたい内容。(不安な子ども達が参考にできるように”読み”を書いています。あくまでも読み、もう少しみんなの自己採点を待ちたい。)僕以外に、県内でテストの難易度・点数読みを書かれている先生がいたら教えてください。
March 8, 2007
-
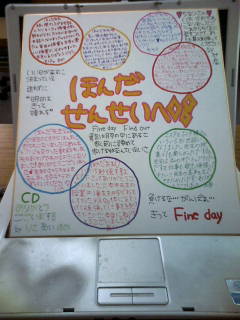
もらったもの
卒塾する何人かの子達からこれをもらった。↓感激!!学校まで違う子たちがこうして書いてくれるのは本当に嬉しい。大事にします。
March 8, 2007
-
パソコンが
今日も移動に移動を重ねて授業へ。パソコンがなかなか機能しないのでブログやメールに苦労をしています。なんとかしないと。
March 8, 2007
-
次から次へと
さらに次の仕事に取り掛かっている。まだまだ計画が盛りだくさんだ。心構えと同様しっかりした準備が欠かせない。がんばろう。
March 8, 2007
-
何が本当に必要なのか
本当に人が手に入れるのはいつも”学び”だと思う。例えば試験で、あなたは合格、あなたは駄目・・・・・判定がどのように下ってもそれは学びのひとつだと思う。頑張りを認められるならそれはそれで良い学びであるしそうでない結果であってもそこには何かしら学びがある。というより出された判定から学びを得なければならない。そういう意味ではもはや肩書き的な学校名は意味を成さない。大事なのはどのような肩書きを与えられたか?ではなくその肩書きを得る際に、どのような学びを手に入れたか?だろう。だから本来、人にとって肩書きはほとんど意味を成さないのだ。誰かが何かを判断する目安にはなっても目安以上にはなり得ない。成功にしろ失敗にしろ出た結果から学びを得た人が最も強いはずだ。そこにあるのが自分の成長なのだから。そのように学びから自分の力を高めることこそが大事だと思う。そこには肩書き以上の何かが必ずや存在するからだ。要は、”君がどのように成長し向上するか?”だ。そうすればどのような肩書きにも、君は勝てる奴になっているはずだ。
March 8, 2007
-
今日という日
授業が終了した。夕食を食べる合間もなくようやく今日を終えた。メールをくれた3年生のみんなありがとう。
March 7, 2007
-
入試を終えたみんなへ
今日試験を終えたみんな、お疲れ様。よくがんばったね。今日自己採点を終えたらゆっくり休むんだよ。みんなきっと不安で心配で落ち着かないと思うんだけどね?しっかりがんばったのを先生は知っているから、大丈夫だよ。落ち着いたら先生に顔を見せにおいでね?他の仲間たちの顔も見においで、待っているよ。よくがんばりました。
March 7, 2007
-
自己採点を
山口県公立高校入試。みんなの自己採点はどうだっただろう。授業の合間に入試問題を解いている。数学は基本問題がかなりイージーな感がある。昨年に比べるとかなり点数が取れるつくりになった。平均もそれなりに上昇するだろう。予想通りといったところ。上位校を狙うみんなは難易度の高い問題がどれくらい解けたか?の勝負。理科は毎年あまり難しくないので少し難化するのかな?と想像していたがかなり取りやすいテストだったといえる。山口県特有の問題のややこしさが緩和されている。塾のみんなはしっかり出来た!と信じたい内容。=========みんな自己採点の結果を教えてね。
March 7, 2007
-
入試
公立高校入試日。先ほど応援にみんなの顔を見に行ってきたところだ。少し声をかけることもできた。各々が試験を頑張ってくれるはずだ。みんなの良い結果を祈っておきたい。
March 7, 2007
-
できること
もう僕らに出来ることはせいぜい祈ることくらいになっただろうか。明日は受験する子が多い高校に(もちろん全部は行けないのだけれど)顔を見に行こう。僕もいつもと変わらずこのあともしっかり仕事をしておこう。みんなも普段どおりでいい。もうあとは落ち着いて答えを書いてくるだけだ。努力した分が返って来る日。応援しているよ、がんばろうね。
March 7, 2007
-
あすは
今日も移動に移動を繰り返し、授業を終えた。先ほど周陽に戻ってきたところだ。いよいよ明日、入試。しっかり最後の力を振り絞るのみ。みんなの全力が発揮できることを祈っています。
March 6, 2007
-
どんとふりーず
パソコンがまともに動かなくなってきている。今日も先ほどになってようやくアウトルックとエクスプローラーが反応し始めた。あまりに危険なので先ほどからバックアップの作業に入っている。============今日も軽い打ち合わせを終えた。3月こそしっかり動いておきたい。問い合わせも順調にいただいている。(お電話では連絡ごとが多く、問い合わせの際、”通話中”の状態が長く続く事が多いのですが、通話中でもこりずに時間をおいて再度お電話いただければと思います。)しっかり準備していこう。
March 6, 2007
-
明日
いよいよ明日、みんなの本番がやってくる。公立高校入試、これまでの自分の努力をしっかり解答に記してきて欲しい。すべての子がしっかり力を発揮できますように。
March 6, 2007
-
何よりも澄んだ水
なかなか水が湧いてこない・・・・掘っても掘っても・・・水の湧かない井戸・・・けれど深ければ深いほどそこからはいつか清らかに澄んだ誰も見たことのない水が湧く。
March 6, 2007
-
落ち着きと勢いの調合
落ち着きのある勢い。これが成績のアップしていく子の姿勢。単にドタバタ騒いだり、落ち着きがなく授業を受けてしまっている子。楽しいかもしれないが成績は上がらない。本当は、勉強しに来て勉強で成果が出ないのは楽しいことじゃない。僕も含め塾の講師は、プロフェッショナルなのだから楽しくすることも厳しくすることも比較的容易にできるものだ。あとはどのラインを基準ラインに置くか?どのラインで成績アップを目指すか?そのラインの据え方こそが講師の持つべき空気作りのスキルだ。講師はその教室の雰囲気を作り出す、ある意味で魔法使いなのだ。そしてほとんどの権限を持ってしまっている頑固親父・星一徹のような存在なのだ。広告にも書いたが楽しいだけでは成績は上がらない。逆に、厳しさのあまりいやいや勉強しなければならない、というのでは最高に脳を使う際の効率が悪い。さらに悪いことには、継続することのハードルが高くなってしまう。単なる勢い作りでもなく単なるスキル作りでもない奇跡の調合を生み出したい。これが常日頃からの願いだ。落ち着きのある勢い、そういう芯の強い姿勢を作る環境を与えていきたい。
March 5, 2007
-
苦しいことから逃れること
苦しいことから逃れることを教えるのが人生論ではない。誰もみな苦しいことから逃れようとする。当たり前だ、だって・・・苦しいんだもの。でもよく考えて欲しい。その苦しいことを乗り越えた先に何を得る事ができるのか?なんのために君の前に苦しみが現われ横たわっているのか?何かその先のものが欲しいのじゃあないのか?その先に到達したくてウズウズしているんじゃないのか?その先を目指して努力しているんじゃないのか?斉藤一人氏が本当に困ったことは起きない、と書いているがそれは苦しみから逃げなさい、なんていうことではない。その弟子たちを見てみればいい、むしろ一生懸命取り組むべきところでは寝る間を惜しんで努力しているじゃあないか。さらに氏は”困ってしまうときは人が学んでいるときだ”と説いている。困っているのではなくて学んでいるのだ、と。それこそ人が苦しいと思うまさにそのときかもしれない。だがこれも前向きに考えればそのことも苦しいことじゃないのだとすら思える。だって学んでいるんでしょう?ラッキー。それで学んでまた新しい何かを手にできるんでしょう?目指しているところに近づける、もしくはそれが手に入るんでしょう?なぜだか楽をして成功しよう儲けよう、努力なんて要らない、といった趣旨の本が出回り始めあたかも素晴らしい人生論を展開しているようにも見えるが僕は本を売るための戦略、ぐらいにしか捉えていない。そりゃ誰だって楽したいから・・・。本当の学びは楽をしようではなくて、困ったことは起きないよね?だから学ぼうね?なんだと思う。だってしっかり学んでいる人は実は何が起きても楽に物事を捉えることができる人なんだから。そう、苦しいことから逃れることを教える事が人生論ではない。
March 5, 2007
-
現在
問い合わせが続いている。最近は途切れることなく毎日新入塾のお問い合わせをいただいている。新一年生だけでなく他学年の問い合わせもある。3教室分の問い合わせをいっきに1箇所でもらっているがこうして支持していただけることはとてもありがたいことだ。さらにステップアップした勉強空間を目指したい。==========単語テスト中、がんばれ!
March 5, 2007
-
積み重ね・継続
積み重ねの力はいつも偉大だ。人が都合よく大勝利できないのは、そのことに対しての積み重ねがないせいだといっていいだろう。一日一歩、一年で365歩、10年で3650歩・・・その力を知ってこそ成果は上がるはずだ。勉強ひとつとっても同じ。積み重ねを大切に。更に言及するなら積み重ねには継続の力が必要だ。継続の力こそが人の本領を発揮させる。そしていつも忘れてはならないのは大人がその大切さを伝える努力をするということ。夢を描くそしてそれを実現させるための努力をする・・・そこに継続の力は欠かせない。
March 5, 2007
-
関係
”関係より状況に重きを置かないこと”僕の好きな本の中の一節。とても大事なことだと思う。何かしら自分の周りの人とのやり取りの中で思い通りにいかないことがあるだろう。そんなとき、単なる「正しいことの主張」は相手に金槌を落とすだけに過ぎない。相手をこてんぱにする事がそんなに嬉しいことなのか?・・否。正しいことも大事なのだがそれより大事なのは相手との関係のはずだ。その人がどのように自分の人生に関わり、また大事な存在であるかを知ること、それをいつも忘れないでいたい。そのときの状況よりも、その人との関係を大切に。感情に任せても正しさを主張しても大事なものはいつも変わらないのだと思う。これからも心にしっかりとどめておきたい。
March 5, 2007
-
だからこそ自分がやれることをやる
(すごくざっくりとした話だが、すごくざっくりとしたイメージで捉えてほしい話)言うだけなら簡単である。ねぎらうことも確かに大事だ。(小阪氏の著書にも”ねぎらい”を大事にしたチーム作りに触れてあるのを思いだす。)これはこれで非常に大事だし、むしろ当たり前の行為だろう。だがそれだけで「アー残念、出来ませんでした。」で済ませてはいけない。「大変だから、苦労が絶えないから、やっぱり無理ですよね、仕方ない。」だけでは世界はよくなりようがない。どのようなねぎらいの言葉もそれを変えるだけの力はない。どんなことでも同じだが、今、やるべきはずのことがきちんとなされていない、そんな現実があったとする。(これがここでのテーマ。問題はなんであってもよい。)公のものでもそう、民間のことでもそう、些細な事だって構わない・・・。何かがきちんと遂行されていないとき僕達は社会の一員としてしっかりその問題に目を向けなければならない。怒りを持つことは向上への第一歩でもある。よりよい世界を創ろうと思うならどんなときも「だからこそやり遂げるにはどうすべきか、何が今出来るか」を考えなければならない。そしてそれを実際にやる。このような多くを踏まえ僕は今自分が出来ることを精一杯やっている。今の立場から訴えられる、または実践できることを最大限にやっていきたい。形になったものもずいぶんとある。まだまだ出来る事がこれからも増えていくだろう。これまで同様、出来ないと思われていることもどんどんやっていくつもりだ。
March 5, 2007
-
たどり着くためにある場所
今日も自習や授業でがんばる子ども達を目にすることができてよかった。苦しい中、勉強の意義だってよくわからないままひたすら勉強に向かう姿は誇るべき姿だと思う。大人だって苦しいことからは逃げてしまいがちになる。さらには「俺にだってやればそのくらいはできる。」「私だって○○の仕事について、□□くらいの収入なんて簡単に手に入れられるのに。」なんて・・・やらずして負け惜しみを言っている大人がなんと多いことか。やらなければ結局意味がないのだ。○達成するためにどのように考えるか?○達成するまでの距離はどのくらいあるのか?○達成するためにどのような行動をするか?○達成するために代償として支払うものは何か?○達成したら何をしたいか?これらがきちんと噛み合って、その人の成功があるといえる。それを闇雲に「ただなんとなくやっている」ではたどり着けない場所がある。これからもしっかり結果を出し続けたいと思う。子ども達のがんばりに大人が負けていてはいけない。みんなが憧れてくれるだけの大人になりたい、またそのようでありつづけたい。ずいぶんと授業週7が続いていて休みはもちろんない。休み休みで達成できるような目標を抱いてはいない。むしろしっかりフォーカスしてこの道を行かなければならない。その覚悟をして臨んでいる。さらなる向上を。
March 4, 2007
-
今の
今日の授業が始まっている。自習部も集まってきた。今の頑張りが実を結ぶ。逆に今の頑張り以外で未来を創るものはないといえる。1・2年生も入試になって「あのときがんばっていれば・・。」だけはないように今できる勉強を大事にして欲しい。・・・行きたい高校をちゃんと選べるように。
March 4, 2007
全2534件 (2534件中 1-50件目)
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …
- まんだらけの優待のまんだらけZEM…
- (2023-06-24 23:18:46)
-
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪『久保史緒里*卒業コンサ…
- (2025-11-26 23:11:00)
-